
図の説明を特にしてこなかったが、川崎巨泉の瓢箪の図柄のおもちゃ絵は、「瓢箪山の辻占」である。河内の瓢箪山稲荷は、全国に行き渡った辻占の元祖だという。添えられた文字は、「大正甲子寿日 於人魚洞写 巨泉」と読める。大正甲子は13年。辻占は「百番 目出たし目出たし」と、この「おもちゃ箱」最後の頁であることを祝っている。巨泉には「瓢箪山稲荷の辻占」という文章もある(「上方」1938.2.)。昭和13年当時の地名だと、大阪府中河内郡枚岡南村大字四條にある名高い稲荷が、瓢筆山稲荷である。現在の神社のおみ籤と異なり、その作法は、先ず神社に祈願して社務所で籤を引く。籤には番号が書いてあるので、占場(鳥居の石橋)に身を潜め、往来の通行人の風体言葉に注意する。籤が一番ならば、最初の通行人、三番ならば三人目をよく観察する。しかも時刻は、夕方か深夜が適しているというから、人通りが少なければなかなかの忍耐が必要だ。その通行人の言動を社務所に伝え、占を頼む。これだけのことをして得られた答えは、桶を持った人が通れば風呂屋を開業するとか、馬の話をしていたので競馬が良いとかの、たわいもないものらしい。古代からの辻占が昭和前期まで残っていたようだ。
巨泉は絵師だが、新聞の美術記者をしていた金井紫雲が人魚について書いている。題して「人魚考」。雑誌「動物文学」1942年3月号。戦争中でも人魚の考証をしていたのである。pp.42〜48。「動物文学」のこの号は、特集「動物考證集」で、「人魚考」を含め五論文が巻頭を飾る。他の四論文は、中島利三郎「禽獣虫魚語源考」、沖野岩三郎「日本神代史動物考」、蘆谷蘆村「鼠崇拝と鼠の説話」、伊豆山善太郎「禅に現われた動物」である。何となく時局を感じさせる内容であるが、巻末には仏英米人作家の翻訳も載っている。
「動物文学」は、編輯兼発行人が平岩米吉(1898-1986)、1934年創刊である。平岩は川端玉章に日本画を学んだ動物学者。1937年に平岩犬科生態研究所を創立、その狼、犬に関する著作は、1990年代になって築地書館から復刊されている。
紫雲「人魚考」の書き出しはこうだ。
人魚というものに凡そ三種ある、第一は最も普通に知られている人魚で、上半身人体、下半身魚体の想像的動物、第二は海中に棲息する鯨に似ている哺乳動物『ざんのいを』即ち儒艮のこと、第三は山間の渓流などに棲息する『さんしょうのうを』のことである。
この定義は大槻文彦『大言海』に一致している。本草書では人魚を鯢魚(オオサンショウウオ)、テイ(魚偏に帝)魚(サンショウウオ)と説くことが一般的であった。大槻はリョウ(魚偏に陵の旁部分)鯉を「イシゴイ」と読ませ、儒艮の文字は使わないが、「南洋ノ海中ニ棲ム。鯨ノ類ニ等シク、前脚ハ鰭ノ如ク、海産ノ哺乳獣ナリト云ウ。印度ノ安貝那島ニテ捕ウト」と説明している。安貝那はアンボイナと読む。文彦の祖父、大槻玄沢(1757-1827)の著『六物新志』に同字が使われているが、インドネシア、モルッカ諸島の一島である。
金井紫雲は、本名は泰三郎。1888年高崎生れ。学歴は小学校中退。1902年上京、坪内逍遥の薫陶をうけ、独学、雑誌編集の経歴により、1910年6月、中央新聞に入社。社会部外交から始めて、1919年社会部長になり、1922年4月退社。同年5月、都新聞に移り、美術趣味担当となり、学芸部長に進む。1935年、都新聞退社。1954年1月死去。
独学の紫雲は、美術と動植物に詳しく、京都芸艸堂発行の芸術叢書といわれる『〜と芸術』の題名を持つ書物で有名である。『花と芸術』(1929)、『樹木と芸術』(1930)、『草と芸術』(1931)、『動物と芸術』(1932)、『魚介と芸術』(1933)、『蔬果と芸術』(1933)、『虫と芸術』(1934)、『鳥と芸術』(1936)、『天象と芸術』(1938)、『山水と芸術』(1940)の10冊。中には戦後の改訂版もある。
都新聞は現在の東京新聞の前身であるが、中央新聞は馴染みのない方がほとんどであろう。前身は1883年発刊の絵入朝野新聞、1892年改題。政友会系の新聞。講談掲載の嚆矢として知られる。1904年の発行部数は4万。(同年、大阪毎日、大阪朝日ともに20万、読売1.5万、報知14万、都6万、万朝報16万など)。明治40年代の中央新聞には、後に文学者となる若山牧水(1885−1928)、永代静雄(1886−1944)、光用穆(1887−1943)、山田邦子(1890−1948)、若杉鳥子(1892−1937)らが在席していたが、新聞自体は政友会機関紙という以外、これという特色もない新聞であった。
牧水らが1、2年の在席で辞めていった中、紫雲は外回りから、編集へと経歴を重ね、1914年『盆栽の研究』、1917年には『趣味の園芸』『新趣向の盆栽』の著を持つこととなった。その間、自学奨励会から家庭自学文庫の一冊『百花倶楽部』という本も出した。都新聞に移ってからも、新聞の出版部から『花と鳥 趣味と栽培飼育』(1925)を出し、昭和になってからの美術研究家への基礎を固めている。紫雲の主著は、『芸術資料』48冊(芸艸堂、1936-1941)、『東洋画題綜覧』18冊(芸艸堂、1941-1943。1997年、国書刊行会から復刻)であろう。昭和期の刊行はほとんど芸艸堂からのもので、戦後も『茶道精観』を出しているが、1943年、大雅堂から『東洋花鳥図攷』という書が発行された。戦局も厳しさを加えて行く時期の出版であった。その、pp.56〜69が「動物文学」所載の「人魚考」である。
紫雲が人魚に興味を感じ始めたのは、「恩師蒲原有明氏の長詩『人魚の海』を読んだ時に初まる」。有明の「人魚の海」は第四詩集『有明集』(易風社、1908)の巻末に収録された、井原西鶴「命とらるゝ人魚の海」(『武道伝来記』巻二)に題材を取ったバラッドである。西鶴の同作品からは、太宰治「人魚の海」(『新釈諸国噺』)も生まれている。「人魚考」には文中に小見出しがあるが、順を追って紹介すると、「西鶴の『人魚の海』」「日本書紀の人魚」「人魚を見た話」「支那の人魚」「人魚の性別」「人魚の肉味」「人魚は明神の使」「山椒魚と人魚」となっている。日本、中国の資料はやはり『広文庫』からのものが多い。『広文庫』以外の引用で注目されるのは、「人魚の肉味」の部分の石橋臥波によるものである。
一つは隠岐の八百比丘尼伝説であるから良いとして、もう一つが出自の分からない豊後佐伯の「人魚は嘘つき」という伝説である。紫雲の参照した臥波の記述は、『日本百科大辞典』第8巻の「人魚」の項であろう。
佐伯の百貫五兵衛は浜から人魚を引いてきたが、人魚の哀れな話(病母と幼い娘がいる)に同情して放してやる。海に没する直前、人魚は「五兵衛は馬鹿ぞ、小指一本が千両々々」と叫ぶ。それ以後、豊後では人魚は嘘つきということになっている。という内容なのだが、臥波の記述以外に原典が見付けられない。浜に取り残された人魚をめぐるフォークロアは英国のものに多いが、日本では珍しい。明治以降の移入も考慮すべきであろうが、一方、先に紹介した「大分県宇佐市、四日市郷土人形」や、福岡県博多の冷泉浜の人魚伝説などを思えば、出自が明らかな典拠がある可能性は捨て切れない。この「人魚の嘘つき」は、霧月研究所のサイトでも紹介されていたので、四日市人形同様、お知恵を拝借したい。
『東洋花鳥図攷』所収のテキストと「動物文学」掲載分との唯一の相違は、雑誌では最後の見出し「山椒魚と人魚」が、単行本では、「山椒魚と人魚」と「人魚の絵画」に分かれ、文章の増補があることである。
「動物文学」p.48
絵画に現われた人魚は、昔からよく散見する所で、近くは文展十二回に鏑木清方氏 が『妖魚』と題して之を描き、その門下で蠱惑的な作も多く遺して死んだ増原咲二 郎も人魚をよく画いた。
『東洋花鳥図攷』pp.68-69
絵画にも人魚はよく現われる、近くは文展の第十二回に鏑木清方氏が、六曲屏風に 『妖魚』と題して、これを描き、故落合朗風氏も、同じく六曲にこれを描いているし、清方氏の門人で蠱惑的な作を多く遺して死んだ増原咲二郎にも、これを描いた作があり、

『東洋花鳥図攷』の口絵には、清方「妖魚」がある。以上の文章の後、『里見八犬伝』の挿絵とベックリン「波の戯れ」をあげていることは同じであるが、雑誌では最後に、「が、いまはしばらく日本のものゝみにとゞめて置く」の一文が加わっている。
テキストの異同はここまでであるが、雑誌には、文末に編輯部の附記がある。いわく、「第二輯、須川邦彦氏「舟と動物」人魚の項、参照。」
「動物文学」第2輯(1934)pp.19−28「船と動物」は、「船と関係のある動物は、荷物として積込むもの、食料に又は乗員の慰みに飼って置くもの、航海中に接触する各種のもの等で、数え上げると実に夥しい。」という前置きで、犬、猫、鼠、豚、龍、蛇、人魚、海象(セイウチ)が語られる。
人魚の項では、東西の伝説として、隠岐の八百比丘尼伝説(紫雲と同様)と、6世紀にアイルランドの海岸で捕らえられた人魚が洗礼を受けたことを述べている。そして、人魚の正体としてジュゴンを挙げ、沖縄でザンノイオ、日本統治下のパラオではマヌキューと呼ぶと伝えている。パラオでは、第一頚椎骨を酋長の腕にはめて尊んでいると言う。最後はミイラに言及、猿の上半身に鮭などの下半身を接合したもので、だまされてはいけないと喚起している。
東西の伝説、正体としてのジュゴンの生態と文化誌的記述、剥製人魚の実体。人魚をめぐる言説は固定化している。明治以来の、西洋知識の精髄である百科事典的記述、日本の資料の集積である『故事類苑』(1910)、『広文庫』(1916)の整備が関連している。特に物集高見博士の家の事業である『広文庫』の影響は深いものがある。便利な物だから、利用者が『広文庫』以外に資料の探求を求めず、安易に引用するだけでは、人魚記述に面白味がなくなる。人魚言説のマニエリズム、その徹底した究明と解剖が、コラムニストの希望するところで、主旋律として提示して置く。
紫雲は美術と人魚の関連に触れている。鏑木清方、落合朗風、増原咲二郎、ベックリーン。アルノルト・ベックリーン(1827−1901)の展覧会は、バブル経済が始まろうとする1987年に開催されている。ベックリーンの日本への紹介は明治期に始まり、未明の「赤い蝋燭と人魚」にはベックリーンの「波の戯れ」の影響があると上笙一郎が指摘したのは1966年のことであった。バブルが弾けた1992年には、日本放送出版協会から「魂の叫び 落合朗風」(NHK日曜美術館/幻の画家 回想の画家3)が出版されている。ただし、人魚を描いた屏風絵は収録されていない。朗風(1896−1937)は最初、文展、帝展に出品していたが、1934年、明朗美術連盟を創設した。その第一回明朗展に「人魚」「東京風景三題」を出品している。1936年には文展招待者、37年にはオリンピック芸術評議委員に任命されるも、この年、湿性肋膜炎にて死去する。帝展の日本画部審査委員であった鏑木清方(1878−1972)が第二回帝展(1920)に出品したのが「妖魚」である。緑の岩に休らっている人魚の魚体は金泥で表現されている。構図がベックリーンの人魚を描いた「凪」(1887)に似ていたため、賛否両論の問題作となった。清方自身は、
二回には人魚を扱った失敗作を出している。人魚の伝説には格別の知識はないが、黒い髪に白い膚。下半身が魚体になって、海中に尾鰭を動かす。鏡花文学を愛好する一画家が、これを選ぶに不思議はない。そうでなくてもいつ頃からかこうした幻想は多くの人の心を捉えた。寛政の昔に山東京伝は黄表紙「面屋人形箱入娘」の戯作もある。(中略)実は「黒髪」もルノアールに示唆を受けている。だがベックリンの人魚は耳には聞いているがまだどんな複製も見ていない。
『続 こしかたの記』
と回想している。戯作者条野採菊の子である清方が京伝の「箱入娘面屋人魚」を思うあたりは興味深い。現在は福富太郎のコレクションに帰している「妖魚」のカラー版は、『芸術新潮』1999年4月号(特集 鏑木清方が描き、語る 私の東京ものがたり)でも見ることができる。私は「妖魚」が好きである。大正が人魚マニエリスムの時代だとすれば、その一翼を担う作となっている。
最後に「さ」は山東京伝(さんとうきょうでん 1761−1816)の「さ」でもあるので、少し触れておく。「面屋人形」は昨年、小学館から復刻されたので容易に見ることができる。浦島太郎と鯉との間に生まれた人魚を品川沖で吊り上げた平次は、人魚を女房にする。人魚をなめると若くなることに気付いた平次は「人魚御なめ所」を商売にして金を儲ける。ところが、平次自身も女房を嘗め過ぎて、子供になってしまった。そこへ浦島太郎がやってきて、玉手箱を開けてくれたので、平次はちょうどよい若者になり、人魚もあまりに人に嘗められたので鱗が剥げ、手足も生えて本当の人間になった。二人は仲睦まじく、人魚町訛って現在の人形町に居を構えた。これらの話は7900年前のことだが、不老不死の二人は、今はわたくし京伝の隣に住まっている、と結ぶ。
京伝には他にも人魚が出てくる黄表紙がある。最近出た『山東京伝全集』第3巻(黄表紙3)に収録されている「浦島太郎 龍宮羶鉢木」(たつのみやこなまぐさはちのき)である。龍宮城の主八代龍王は娘乙姫に婿をとって九代目を継がせようとするが、乙姫は人間の浦島太郎を見初め出奔する。龍王の地位を簒奪しようとした蝶鮫は成敗されるものの、その魂は虎鰒に乗り移り、玉璽に等しい玉手箱を盗み、悪計をめぐらす。そうとは知らない龍王は、人間界と縁を結んだ乙姫の首を取れと、守役の蓑亀に言い渡す。乙姫の身代わりを探していた亀のもとに、人魚が現われる。この人魚は、龍王と鯉との娘で、面立ちは乙姫に似ている。乙姫の身代わりになった人魚が太刀魚で首を落とされたところに、虎鰒が現われ、亀と勝負になる。鯛、海老の助けを得て、河豚は討ち取られる。亀の忠心、人魚の犠牲に感じた龍王は、乙姫を許し、玉手箱を伝えた浦島太郎を九代龍王とした。
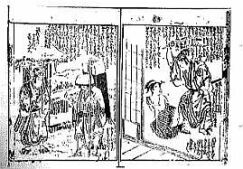

生ぐさ、魚類にまつわる洒落をふんだんに散りばめたこの作でも、人魚の魚部分は鯉である。「胸から上は乙姫様の面影あり。胸から下は母の形の鯉に似て、本草に人魚と呼ばれ、異物志にも載せられて」と説明されている。人との恋によって交わるからには、コイ(鯉)が良いらしい。もっとも、『和漢三才図会』でも「あらい鱗は浅黒色で鯉に似ており」としているので、当時の一般知識でもあろう。文章は曲亭馬琴の代筆ないし協力が指摘されている。『らくだこぶ書房21世紀古書目録』によれば、2040年頃には黄表紙が復活するようなので、京伝を今から読んでみるのも一興であろう。雑誌関連の人魚はまだまだあるが、「春は曙。紫だちたる雲の」の紫雲の「し」に移り、季節も初夏を迎えるので、次回は新聞の「し」ということにしよう。
(by 八谷鏡人)

 図の説明を特にしてこなかったが、川崎巨泉の瓢箪の図柄のおもちゃ絵は、「瓢箪山の辻占」である。河内の瓢箪山稲荷は、全国に行き渡った辻占の元祖だという。添えられた文字は、「大正甲子寿日 於人魚洞写 巨泉」と読める。大正甲子は13年。辻占は「百番 目出たし目出たし」と、この「おもちゃ箱」最後の頁であることを祝っている。巨泉には「瓢箪山稲荷の辻占」という文章もある(「上方」1938.2.)。昭和13年当時の地名だと、大阪府中河内郡枚岡南村大字四條にある名高い稲荷が、瓢筆山稲荷である。現在の神社のおみ籤と異なり、その作法は、先ず神社に祈願して社務所で籤を引く。籤には番号が書いてあるので、占場(鳥居の石橋)に身を潜め、往来の通行人の風体言葉に注意する。籤が一番ならば、最初の通行人、三番ならば三人目をよく観察する。しかも時刻は、夕方か深夜が適しているというから、人通りが少なければなかなかの忍耐が必要だ。その通行人の言動を社務所に伝え、占を頼む。これだけのことをして得られた答えは、桶を持った人が通れば風呂屋を開業するとか、馬の話をしていたので競馬が良いとかの、たわいもないものらしい。古代からの辻占が昭和前期まで残っていたようだ。
図の説明を特にしてこなかったが、川崎巨泉の瓢箪の図柄のおもちゃ絵は、「瓢箪山の辻占」である。河内の瓢箪山稲荷は、全国に行き渡った辻占の元祖だという。添えられた文字は、「大正甲子寿日 於人魚洞写 巨泉」と読める。大正甲子は13年。辻占は「百番 目出たし目出たし」と、この「おもちゃ箱」最後の頁であることを祝っている。巨泉には「瓢箪山稲荷の辻占」という文章もある(「上方」1938.2.)。昭和13年当時の地名だと、大阪府中河内郡枚岡南村大字四條にある名高い稲荷が、瓢筆山稲荷である。現在の神社のおみ籤と異なり、その作法は、先ず神社に祈願して社務所で籤を引く。籤には番号が書いてあるので、占場(鳥居の石橋)に身を潜め、往来の通行人の風体言葉に注意する。籤が一番ならば、最初の通行人、三番ならば三人目をよく観察する。しかも時刻は、夕方か深夜が適しているというから、人通りが少なければなかなかの忍耐が必要だ。その通行人の言動を社務所に伝え、占を頼む。これだけのことをして得られた答えは、桶を持った人が通れば風呂屋を開業するとか、馬の話をしていたので競馬が良いとかの、たわいもないものらしい。古代からの辻占が昭和前期まで残っていたようだ。 『東洋花鳥図攷』の口絵には、清方「妖魚」がある。以上の文章の後、『里見八犬伝』の挿絵とベックリン「波の戯れ」をあげていることは同じであるが、雑誌では最後に、「が、いまはしばらく日本のものゝみにとゞめて置く」の一文が加わっている。
『東洋花鳥図攷』の口絵には、清方「妖魚」がある。以上の文章の後、『里見八犬伝』の挿絵とベックリン「波の戯れ」をあげていることは同じであるが、雑誌では最後に、「が、いまはしばらく日本のものゝみにとゞめて置く」の一文が加わっている。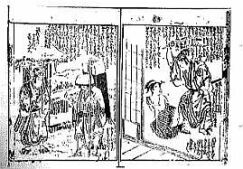
 生ぐさ、魚類にまつわる洒落をふんだんに散りばめたこの作でも、人魚の魚部分は鯉である。「胸から上は乙姫様の面影あり。胸から下は母の形の鯉に似て、本草に人魚と呼ばれ、異物志にも載せられて」と説明されている。人との恋によって交わるからには、コイ(鯉)が良いらしい。もっとも、『和漢三才図会』でも「あらい鱗は浅黒色で鯉に似ており」としているので、当時の一般知識でもあろう。文章は曲亭馬琴の代筆ないし協力が指摘されている。『らくだこぶ書房21世紀古書目録』によれば、2040年頃には黄表紙が復活するようなので、京伝を今から読んでみるのも一興であろう。雑誌関連の人魚はまだまだあるが、「春は曙。紫だちたる雲の」の紫雲の「し」に移り、季節も初夏を迎えるので、次回は新聞の「し」ということにしよう。
生ぐさ、魚類にまつわる洒落をふんだんに散りばめたこの作でも、人魚の魚部分は鯉である。「胸から上は乙姫様の面影あり。胸から下は母の形の鯉に似て、本草に人魚と呼ばれ、異物志にも載せられて」と説明されている。人との恋によって交わるからには、コイ(鯉)が良いらしい。もっとも、『和漢三才図会』でも「あらい鱗は浅黒色で鯉に似ており」としているので、当時の一般知識でもあろう。文章は曲亭馬琴の代筆ないし協力が指摘されている。『らくだこぶ書房21世紀古書目録』によれば、2040年頃には黄表紙が復活するようなので、京伝を今から読んでみるのも一興であろう。雑誌関連の人魚はまだまだあるが、「春は曙。紫だちたる雲の」の紫雲の「し」に移り、季節も初夏を迎えるので、次回は新聞の「し」ということにしよう。