東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>4P
やっと、ビロクシーの人々の人魚が語れる。ビロクシーはルイジアナとミシシッピを分けるパスカグーラ川に沿ったメキシコ湾岸に住んでいた人々である。彼らは、人魚型の女神を崇拝し、その像を祭っていた。川からは人魚の歌声が聞こえ、それに合わせて女たちが楽器を奏で、戦士らは女神像の周りで踊る。そんな日々を送っていたビロクシーの集団に、1539年頃、一人のカトリックの宣教師がやって来た。布教はかなりの成功を収め、人魚像は川に投げ捨てられてしまう。すると、まもなく川より水柱が上がり、出現した人魚が、「お出で、私の元へ、海の子供らよ、教会の鐘や聖書、十字架が何するものぞ、私が女王」と歌うと、人々は、焚き火を囲んで、踊り、飲み、口々に女神の名を叫びながら、川に飛び込み、翌朝には、一人のビロクシーもいなくなった。
宗教上の集団自殺か、敵対するチョクトーの人々に虐殺されたのか、定説をみないが、伝えられている逸話では、人魚女神が川に呼び込んだと、言われている。
アメリカ原住民と人魚との関係では、アジアから新しい大地に渡るときに、人魚神に導かれたとか、海神に誘惑された乙女が一族に富をもたらしたとか、海獣の女神セドナのことなどを思い浮かべるが、キリスト教との関係が絡むビロクシーの伝説は興味深い。アフリカ奴隷がもたらした女神とマリア信仰が混合した、メキシコ以南に見られる、豊穣の人魚像も視野に入る。
ポカホンタスの伝説で有名な最初期の移民の一人、ジョン・スミスも1614年に人魚を目撃し、「大きな丸目、可愛らしい鼻、長めの耳、ながい緑色の髪は、不細工ではなかった」と伝えている。一方、ヴァージニア植民地のラパハノック川での目撃状況を英国学士院に報告したのは、トマス・グローバーであった。「皮膚は褐色、頭部は毛がなく、黒目は大きく、黒筋が入った上唇は端が捲れ、表情は陰鬱で恐ろしげ、私をじっと見つめた後に潜水した。」(1676年報告)
記載され、研究の対象となる人魚は、南にいるらしい。そんな知識人の共通した思いは、16世紀以降、ヨーロッパで盛んになり、日本へも伝えられたかもしれない。宣教師が編んだ『日葡辞書』には、「Ninguio その歌で、聞く人人を眠らせると言う人魚」とあるが、安土の信長の元で、人魚談義はなかったのだろうか。先の『家忠日記』の他にも、信長に纏わる人魚記述はある。『當代記』巻二、天正7年春のこと、「この春、信長公在京の砌、若狭の国丹波五郎左衛門人魚を献る。両手足人に違わず、長さ五尺ばかりこれ在り、かの魚岩の上へ登り寝ることしばし、その所を見つけこれを取る云々」とある。丹波五郎左衛門は長秀(1535−85)、信長家臣の武将。海獣と思える内容であるが、主人の若さ、長久を念じた献上品だったのだろうか。『當代記』の編者は姫路城主、松平忠明とも伝えられるが、徳川家の重臣らには、信長晩年と人魚をめぐる噂でもあったものか。
家康の開いた江戸時代、日本の人魚知識は、オランダ経由の書物を含め、充実してくる。それらを含め、以降の人魚話は進む。
(by 八谷鏡人)

そこで海中の動物の中で、何が一番伝説の人魚に近い特徴をもっているかと云いますれば、先ず儒艮でありましょう。それから海牛、海豹、膃肭獣、臘虎、海象、鮫というようなものなども、人魚伝説を生んだ嫌疑者であると思います。と述べている。人魚とジュゴンの関連は当時としても耳新しい知識ではなかったが、『科学知識』の本論の方は、啓蒙記事としてはかなり充実したものになっている。
『科学知識』のエッセイは、「人魚の傳説とその正體 能澤鱗」というものである。全体を、「一、日本と支那における伝説」、「二、西洋における伝説」、「三、人魚の正体」の三つに分けて述べている。日本・中国の部では、谷崎潤一郎『人魚の嘆き』から説き始めていることが注目されるが、その後の例は、『広文庫』の引用である。西洋の例は、英語文献からの抽出であるが、今のところ原文が何であるか特定するまでは至っていない。人魚の話は東洋に限らず、「ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、グリーンランド、オランダ、デンマーク、英国、アメリカ、アフリカ」にもあると言う。ロシアのルサールカを「川の仙女」と紹介している。その後、目撃談に進み、コロンブス、ジョン・スミス、1670年のデンマーク(人魚が禁酒演説をした)、キアスコ湾、センテン湾、1403年のエダムの人魚と続く。ギリシヤ神話ではグラウコスを、中世の英雄伝説からは、ジークフリートを、フォークロアからは「キューリーのお爺さんの話」を引く。最後に人魚の見世物について語り、
西洋には昔から人魚の見世物があって西暦1755年にも1822年にもロンドンで開かれたそうです。小説家アレキサンダー、ジュマーもオランダのハーグで見物したといっています。西暦1825年に我邦へ渡来したオランダの船が人魚の見世物を持ってきたそうですが、拵物で、大概支那あたりの細工物らしいということでした。そしてその人魚の見世物は身体は乾魚で、頭は人の子供か猿若しくは石膏細工だそうで、中々巧妙には出来ているそうであります。と述べている。
 (1)の前半部分が『変態心理』に転載された。ジュゴンが沖縄の言葉で、「ざんのいを」(ザンヌイユ、ザン、ザノ、アカンガイユ)と呼ばれていたことは明治以来、共通の認識になりつつあったが、能澤は「琉球では三四月頃乳呑児を伴れて泳いでいます。」といって、授乳の様が海上に出た女人に見紛うという説(今日では否定されている)を引く。水産物としてのジュゴンの利用は、肉、脂、皮、骨に及ぶことを述べ、「わが国へは昔人魚の骨は解毒に神効ありといってオランダ人が輸入したものだそうです。しかし贋物が多かったようです。」と伝えている。この部分では、「ルイツベルの話に、聖書に所謂、ユダヤ人が幕屋を飾る蓋は、紅海に棲む儒艮の皮を以てしたもので、」が注目されよう。儒艮の頸椎骨の腕輪が紹介されているのも、早いほうではないだろうか。ここでは、沖縄のジュゴンが触れられているだけであるが、明治以降統治に加えられた台湾、南洋諸島にもジュゴンの生息地があり、台北帝大の動物学者たちが研究を進めるのは、これ以降のことであった。江戸時代の薩摩藩の琉球支配、台湾、南洋、第二次大戦のフィリピン・マレー・インドネシア、さらにはオーストラリアと日本の南進の経路はジュゴンの道であった。そのジュゴンが今、沖縄本島では、アメリカ軍基地反対のシンボルとなっているのも興味深い。アメリカの太平洋への進出は鯨であったが、捕鯨禁止の急先鋒と化したアメリカに対するに、ジュゴンの保護は有効か。水産は、かつて帝国主義推進の力となっていたが、今日では抑止力となっている。
(1)の前半部分が『変態心理』に転載された。ジュゴンが沖縄の言葉で、「ざんのいを」(ザンヌイユ、ザン、ザノ、アカンガイユ)と呼ばれていたことは明治以来、共通の認識になりつつあったが、能澤は「琉球では三四月頃乳呑児を伴れて泳いでいます。」といって、授乳の様が海上に出た女人に見紛うという説(今日では否定されている)を引く。水産物としてのジュゴンの利用は、肉、脂、皮、骨に及ぶことを述べ、「わが国へは昔人魚の骨は解毒に神効ありといってオランダ人が輸入したものだそうです。しかし贋物が多かったようです。」と伝えている。この部分では、「ルイツベルの話に、聖書に所謂、ユダヤ人が幕屋を飾る蓋は、紅海に棲む儒艮の皮を以てしたもので、」が注目されよう。儒艮の頸椎骨の腕輪が紹介されているのも、早いほうではないだろうか。ここでは、沖縄のジュゴンが触れられているだけであるが、明治以降統治に加えられた台湾、南洋諸島にもジュゴンの生息地があり、台北帝大の動物学者たちが研究を進めるのは、これ以降のことであった。江戸時代の薩摩藩の琉球支配、台湾、南洋、第二次大戦のフィリピン・マレー・インドネシア、さらにはオーストラリアと日本の南進の経路はジュゴンの道であった。そのジュゴンが今、沖縄本島では、アメリカ軍基地反対のシンボルとなっているのも興味深い。アメリカの太平洋への進出は鯨であったが、捕鯨禁止の急先鋒と化したアメリカに対するに、ジュゴンの保護は有効か。水産は、かつて帝国主義推進の力となっていたが、今日では抑止力となっている。海を神として怖れていた未開の時代において、ヒョッコリ儒艮のような海獣が海上に現れたとしたならば、これを認めた浦人―殊に迷信の多かった当時の航海者には、どうしても単純な動物とは考えられないで、これを神若しくは人間化した人面魚身の人魚と信じてしまったのも無理からぬことと思うのです。と、合理的に解釈している。これこそが近代の神話というものであろう。その形成を跡付けることに興味を引かれるが、それには雑誌の探索が不可欠となる。
(by 八谷鏡人)
 1914年6月、山村暮鳥、室生犀星、萩原朔太郎らは人魚誌社を結成し、翌3月には雑誌「卓上噴水」を創刊した。1912年3月には大阪で宇野浩二が関係している「シレエネ」という雑誌も出ている。ただし、雑誌の内容と人魚は直接の関係はない。同時期、東雲堂が出版元となっていた「番紅花(さふらん)」(1914)という雑誌の表紙は、富本憲吉による「人魚の喜びと花をまつ蒲英の葉」と題された版画である。
1914年6月、山村暮鳥、室生犀星、萩原朔太郎らは人魚誌社を結成し、翌3月には雑誌「卓上噴水」を創刊した。1912年3月には大阪で宇野浩二が関係している「シレエネ」という雑誌も出ている。ただし、雑誌の内容と人魚は直接の関係はない。同時期、東雲堂が出版元となっていた「番紅花(さふらん)」(1914)という雑誌の表紙は、富本憲吉による「人魚の喜びと花をまつ蒲英の葉」と題された版画である。★人魚 四号、川崎巨泉氏が蒐集の人形をもじった人魚なる小冊を出されて三年になる 二月末其四号が生まれた、口絵は氏の自彫になった鴻之巣雛三度刷が、非常に面白く出来ている、全誌三十四頁、始めから終りまでおもちゃ話で埋まり多くの挿絵もお手のものと云い乍ら面白い「見当たらぬ玩具」は氏の考案になったものだがこうしたものの出現を期待する 非売品。

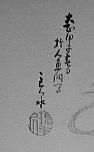 これで判断すると、雑誌「人魚」はこれまた人魚と直接関係はないようである。山東京伝の黄表紙「箱入娘面屋人魚」が「はこいりむすめめんやにんぎょう」と読ませるように、人魚と人形は同じ音で通じる。『隠語大事典』には「にんぎょう/にんぎょ」、「にんぎょうくい/にんぎょくい」、「にんぎょうやのむすめ/にんぎょやのむすめ」が立項されている。人形屋の娘とは、内気な娘のことであり、その他は直接辞書で確認されたい。
これで判断すると、雑誌「人魚」はこれまた人魚と直接関係はないようである。山東京伝の黄表紙「箱入娘面屋人魚」が「はこいりむすめめんやにんぎょう」と読ませるように、人魚と人形は同じ音で通じる。『隠語大事典』には「にんぎょう/にんぎょ」、「にんぎょうくい/にんぎょくい」、「にんぎょうやのむすめ/にんぎょやのむすめ」が立項されている。人形屋の娘とは、内気な娘のことであり、その他は直接辞書で確認されたい。私も人魚を蒐めだして時々奇妙なものを見せられたり贈られたり困った事もある 友人から聞いたのであるが伊予のあるところでは瓦焼きの人魚 を棟に上げた事もあるというので友人の細君の生家が瓦師であるので作ると云う、最近或家で見た人魚其れが棟瓦の人魚であったが後に色彩を施し ていた。
 愛媛県には鯱に似た人魚があったらしい。この一文が巨泉から得られた人魚情報の全てである。雑誌「人魚」に何が載っていて、何号まで続き、今どこに収納されているのか、皆目わからない。最後に郷土人形の人魚について、一つだけ報告しておこう。大分県宇佐市に四日市(地名)郷土人形があったが、手に玉をもつ人魚の形をしている。これについても何ら知ることがない。同好の士で、御存知の方、お教えいただきたい。今回、川崎巨泉に関しては、坂井絵里さんの協力があった、感謝。
愛媛県には鯱に似た人魚があったらしい。この一文が巨泉から得られた人魚情報の全てである。雑誌「人魚」に何が載っていて、何号まで続き、今どこに収納されているのか、皆目わからない。最後に郷土人形の人魚について、一つだけ報告しておこう。大分県宇佐市に四日市(地名)郷土人形があったが、手に玉をもつ人魚の形をしている。これについても何ら知ることがない。同好の士で、御存知の方、お教えいただきたい。今回、川崎巨泉に関しては、坂井絵里さんの協力があった、感謝。 『番紅花』について少し説明する。顧問は森鴎外。後に富本憲吉と結婚する尾竹一枝(紅吉、1893−1966)が中心となって創刊。尾竹一枝は元青鞜社社員の日本画家、文筆家。一枝については、折井美耶子が『薊の花』(1985)で研究の先鞭をつけ、最近、渡邊澄子も『青鞜の女・尾竹紅吉伝』を出版した。近代に活躍した女性たちを簡単に調べるには、今まで『日本女性人名辞典』があったが、対象が物故者のみで、記述に精疎が感じられた。今回、折井らが中心となって、『近現代日本女性人名事典』(ドメス出版、2001年3月。3300円)が紆余曲折の末、完成した。1309人の中には、花園歌子、内藤千代子、本荘幽蘭、渡辺幽香など興味深い人物が立項され、編集委員の一人鈴木裕子の専門とする、運動家、今井歌子、堀保子らの記述も研究の進化が感じられる。また、田沢稲舟の部分でも、「最初の新しい女」と表現するあたり、清新な内容となっている。女性漫画家では、大島弓子、里中満智子、萩尾望都が、それぞれ一歳違いであるのが分かるなど、興味深く活用できる。参考文献も各項に付与されている。富本一枝を参照したが、以後、利用する機会が増えそうである。ご紹介しておく。
『番紅花』について少し説明する。顧問は森鴎外。後に富本憲吉と結婚する尾竹一枝(紅吉、1893−1966)が中心となって創刊。尾竹一枝は元青鞜社社員の日本画家、文筆家。一枝については、折井美耶子が『薊の花』(1985)で研究の先鞭をつけ、最近、渡邊澄子も『青鞜の女・尾竹紅吉伝』を出版した。近代に活躍した女性たちを簡単に調べるには、今まで『日本女性人名辞典』があったが、対象が物故者のみで、記述に精疎が感じられた。今回、折井らが中心となって、『近現代日本女性人名事典』(ドメス出版、2001年3月。3300円)が紆余曲折の末、完成した。1309人の中には、花園歌子、内藤千代子、本荘幽蘭、渡辺幽香など興味深い人物が立項され、編集委員の一人鈴木裕子の専門とする、運動家、今井歌子、堀保子らの記述も研究の進化が感じられる。また、田沢稲舟の部分でも、「最初の新しい女」と表現するあたり、清新な内容となっている。女性漫画家では、大島弓子、里中満智子、萩尾望都が、それぞれ一歳違いであるのが分かるなど、興味深く活用できる。参考文献も各項に付与されている。富本一枝を参照したが、以後、利用する機会が増えそうである。ご紹介しておく。(by 八谷鏡人)