�����l�`��y�����������Ȗ��M

INDEX��38P
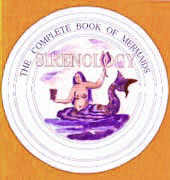
���ތ��ҁw�}�_�K�X�J���̖��b�x(�_�n�ЁA2007.1.30)�̓}�_�K�X�J���̖��b10�҂ƃR���������̖��b�T�҂����߂邪�A�}�_�K�X�J���̕��Ɂu�l����ނ����j�v(pp.47�`63)������B�n�������t�̃u�g�D�́A��ɋ��ɏo�邽�ѐ_�ɍȂ����Ă�悤�F���Ă����B�s���̌�Ɋ|�������̂͐l���ŁA���̂𑼐l�ɖ������Ȃ��Ƃ��������ňꏏ�ɕ�炷���ƂɂȂ����B�l���͎w��炷�ƁA���̂���l�Ԃɕς�邱�Ƃ��ł����B�����͊y�ɂȂ������A���l�����̓u�g�D�̉ł̂��Ƃ�m�肽����A�������܂��āA���ɐl�����ƕ����o���Ă��܂����B�Ƃ͌��̂悤�ɕn�����Ȃ�A�Ȃ̎p�͏����Ă����B��ōŌ�Ɍ����l���́A�u�g�D�̕s�����w�E���A�i���ɐ��ɋA���čs�����B
�@���[���b�p�ɂ����{�ɂ��ޘb������A������l�����[杂ł���B���s���A�����j�I�����ݏZ�̐��́A�}�_�K�X�J���k���̑��A���c�H�q�q�o�g�̏�������}�_�K�X�J����ƃt�����X��Ő̘b�����{�ɏЉ���B�R�����̘b�͕����̘V�w�l���畷���A�F�l���t�����X��ɖ����̂����߂Ă���B�}�_�K�X�J���̓A�t���J�嗤�Ƃ̓��U���r�[�N�C�����u�Ă邾���ł��邪�A�Z���̓C���h�l�V�A�E�}���[�V�A�Ƌ߉��Ō���(�}���K�V��)�̓A�E�X�g���l�V�A�ꑰ�ɕ��ނ����B�R������̓A�t���J�̃o���g�D�[��n�ł���B
�@�}�_�K�X�J���́u�l����ނ����j�v�̗ޘb�Ƃ��āA�K�u���G���E�t�F����(1864�`1935)�w�}�_�K�X�J�����b�x(1893�N)p.91�`92�u�I���f�B�[�k�v�������邱�Ƃ��ł���B�}�_�K�X�J���łQ�Ԗڂɐl���̑��������x�c�B�~�T���J�i���C�݂ɋ��Z�j�̘b�Ƃ��ăt�F�����͓`���Ă���B�j����Œނ�����Ă���ƁA���������̐������������B���������A���������̔��l�́A���̐��Ƃ������̂𑼐l�ɖ������Ȃ��Ə����ōȂƂȂ�A�j�ƈꏏ�ɕ�炷�悤�ɂȂ�A���q��l�A����l�����܂ꂽ�B������A�j�͎��ɐ����čȂ̐��̂𖾂����Ă��܂��B�Ȃ͖���l��A��Đ�̐����ɖ߂�A���q�����͕��̌��ɂƂǂ܂�A�u���̑��q�v�Ƃ����Ӗ��̃U�t�B�}���m(Zafimarano)�Ƃ����Ɩ��𖼂̂�悤�ɂȂ�A�^�}�^���ɍ������̎q�����Z��ł���B�t�F�����̓^�}�^��(���g�D�A�}�V�i�B�}�_�K�X�J�������݂̍`�p�s�s)�̃U�t�B�}���m�Ƃ̕w�l���炱�̘b���Ă���B�t�F�����͐�s����ޘb�Ƃ��ă��\�A�����@���H��(Rasoalavavolo)�Ƃ������̐��̘b�𒍂Ŏ��グ�Ă���B�鋳�t�Ƃ���1870�N����1887�N�܂Ń}�_�K�X�J���ɑ؍݂����m���E�F�[�l���[�X�E�_�[��Lars Dahle(1843�`1925)�̒��w�}�_�K�X�J�����b�I�x(1877�N)�Ɏ��߂�ꂽ���̂ł���B������(lavavolo)�̃��\�A(Rasoa)�����ɏZ��ł����B����l�X�̓��\�A�����@���H�����}�_�K�X�J���̑z����̐�Z�����@�W���o���ƌ����A���̐l�X�͉����̈�l���Ƃ������Ă���B�q���̗~�������������\�A�����@���H���ɋ�̎w�֓�Ɠ�̊ې������ƁA�͓�l�̒j�̎q�ɂȂ����B�j�̎q�����̓}�_�K�X�J���̐l�X�̐�c�ɂȂ����B
�@�}�_�K�X�J���̐��̐��Ƃ��Ắu���̖��v�U�U���@���B���mzazavavindrano��u�ҏ��v
�A���y���}�i�j�Tampelamananisa�Ȃǂ��m���Ă���B�A���y���}�i�j�T�͎�����̉����҂�����B�����̐��̐������͐l�Ԃƌ���āA����ƌn�̐�c���Y��ł���B�܂��A�Y�k��K�v�Ƃ����U�U���@���B���m���V�k��A�ꋎ��A����ɓ̋���^�����Ƃ������Ƃ�1948�N�ɋN�������ƌ��ꂽ�肷��B��������ɂ�����A�v�ɉ��̎g�p�≖�ւ̌��y���֎~�������m��(Ronoro)�́A���j����ƁA���ɔ�э��ݓ�x�ƌ���Ȃ������B���̉����Ƃ����Ӗ��̃A���h���A���o���B���mandriambavirano�͓V��̑��݂ł��������A�l�ԊE�ɋ����������̗t�ɕϐg���Čɗ����Ă����B���q�����̖̗t��������Ə��_�̎p�ɖ߂�A��l�̊Ԃ̎q�������͂��ꂼ�ꕨ��̎�l���ƂȂ��Ă������B�n�������t�R�g�����̖��ƌĂȂ��ŃA���h���A�����@���B���m�ƌ������T���ɂȂ����B�₪�đ��q��l�Ɠ�l�̖������܂ꂽ���A�����Ė�j��A���q�̂ݎc���Đ��E�ɋA���čs���Ƃ����b������B
�@���E�̏������l�Ԃɉł��b�́A�x���E�F���^�E�H�[�w�C�̖����x�ł̓K�[�i�암�̃g�E�B��(Tshi�ATwi)��b���l�X�̂��̂����^���Ă���B���̂𑼂ɖ������Ȃ��Ƃ����ŋ��ƌ��������j�́A���E�Ɉꎞ�߂肽���Ƃ����Ȃ̋��߂ňꏏ�ɐ����ɂ������A���t����œ˂���Ă��܂����B�j�̏���������ƕv�w�Œn��̉Ƃɖ߂�A��������ɉB���Ă������B�������������������̋��t�ɒj�͑S�Ă�b���Ă��܂��B���̎��͉����N����Ȃ��������A�j����l�ڂ̍Ȃ��}����ƁA��l�ڂ̍Ȃ͍ŏ��̍Ȃ������ƚ}�����B���̍Ȃ͖��̎q��A��ĉi���ɐ��E�ɖ߂�A�n��Ɏc���Ă������N��̓�l�̎q�������̎q���͕�ł��鋛�̖��𖼏��A�����Ă��̋������ɂ��Ȃ��Ȃ����B
�@���̂𑼎҂ɂ͘b���Ȃ��ƌ����ŁA������{�̂Ƃ��鏗���ƌ�������b�́A�w���E�̖��b(7)�A�t���J�x(���R���q��A���傤�����A1977.2.10)�Ɂu�����������[�v(pp.317�`312)�Ƃ��Ď��^����Ă���B�_�z���i���x�i���j�̃t�H�������̘b�ł���B�J���V�J���є��E���ŎႢ���ƂȂ����̂�������l�́A�є���B���Ă��܂��A�^���𖾂����Ȃ��Ƃ����ōȂɌ}�����B��l�ɂ͐�ɑ��v�l���������A�V�����Ȃ��J���V�J�ł���ƌ����Ă��܂����B��l�̍Ȃ͌��܂ɂȂ�A�O�x�ڂ̌��܂���J���V�J�̖є�������A�V�����Ȃ͉Ƃ��o�čs���Ă��܂����B���̓r���ŁA���ɏo�Ă����v�ɉ�A��l�͘b�����������A���܂������Ȃ��B����Ŗ����̌��t�ŁA�b��l�Ԃɕς����@��m�����v�́A�J���V�J���Ăѐl�Ԃɕς��ƂɘA��߂����B���v�l�ɂ͌��܂��ւ����B���P�́u�����珗�[�����ɂ͂ق�Ƃ��̂��Ƃ��������Ⴂ���Ȃ��̂��v�B�t�H���̘b�ł́A�v�w�̓^�u�[�N�Ƃ̌���A���̏�Ɏ��܂����B
�@�x���E�F���^�E�H�[�̓g�E�B�̘b���W�����E�A�[�m�b�g�E�}�J���b�N�w����̗c�N���F���b�Ɩ��J�v�z�̌����x(1905�N)������p���Ă���B�}�J���b�N(1868�`1950)�́w���E�̖����̐_�b�x�S13���̕Ғ��҂ŁA�w��r�_�b�w�x(1902)�w�P���g�_�b�w�x�Ȃǂ̒���������B�w����̗c�N���x��12�͂͑O�͂Ɉ�����������ɕ\��ꂽ�^�u�[�ɂ��ċL�q���Ă���B�^�u�[�N�Ƃɂ��Ȃ�v����������́A�܂��́u�v�i�ȁj�����邱�ƂȂ���v�Ƃ����^�u�[���M���V�A�_�b�́u�G���X�ƃv�V���P�i���[�}�̃N�s�h�ƃT�C�L�j�v�ő�\����ďq�ׂ��Ă���B���Łu�v(��)�̔閧�𑼐l�Ɍ�邱�ƂȂ���v�Ƃ����Ⴊ�S�b�Љ��Ă���B
�@��P�b�͐�قǂ̃}�_�K�X�J���̘b�ŁA�Q�ƕ����̓t�F�����̂��́B��Q�b�͋��t�����X�̃R���S��Fjort�̖��b�B�}�����K������̗t����������ƒj�⏗�ɕς��A���̏��̈�l�ƌ������A�T���ɂȂ����B�s�v�c�Ɏv�����e�ނ̓}�����K�������Đ^�����o���B�^��������Ă䂭���Ƃɐg�ɕt���Ă������������̂������ĂȂ��Ȃ�A�Ƃɖ߂����Ƃ��ɂ͍Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�}�����K�̘b�̓��`���[�h�E�G�h���[�h�E�f�l�b�g(1857�`1921)���w�t�����X�̃R���S�̃t�W�����g�l�̖��b�T���x(1898�N)���Q�Ƃ������ł���B�f�l�b�g�͗ޘb�Ƃ��ČZ��ɗ₽�����ꂽ�u�C�e�����Ō����ʂ�̔��������ɏo��T���ƂȂ邪�A���œ������͕K������藎�Ƃ��Ď����A��Ƃ�����j��S�Ă������Ƃ����b���Љ�Ă���B��R�b�̐��A�t���J�̘b�������悤�����A�d��(awiri)�̃C�����x�͊l���ł���m�l�Y�~�̒��ɉB��āA���̑��q�ł��邪�n�����j�̉Ƃɍs���A�j�̗��璆�ɐH���̎x�x�����Ă����B��p�t�̏����ŃC�����ׂ��������j�́A�l�Y�~�̒�����o�Ă����Ƃ����ڂ������܂���C�����x���g�Ɍ���Ȃ��Ƃ����Ō��������B�j�͂�͂�x�T�ɂȂ������A���̐����Ń^�u�[�����ɂ��Ă��܂����B��̓�l�̎q���ƕx�͒j�Ɏc���ꂽ���A�ȂƑ��̎q�������͋����Ă������B����̓��o�[�g�E�n�~���E�i�b�\�[(1835�`1921)���w���A�t���J�̎������q�x(1904�N)��������Ă������̂ł���B�d���̍Ȃ͖��@�̗͂������p�����q���e�̂��ƂɎc���������łȂ��A���̎q�����������͂�K�v�Ƃ���Ƃ��ɂ͂��ł�����ė���Ɩ��Ă���B�����đ�S�b���g�E�B�̋����[�̘b�ł���B�x���E�F���^�E�H�[�́A�قڒ���I�Ɉ��p���Ă��邪�A�}�J���b�N���g�̓A���t���b�h�E�o�[�h���E�G���X(1852�`1894)�̒��w���A�t���J�����C�݂̃g�E�B�ꖯ���x(1887�N)���Q�Ƃ��Ă���B
�@�G���X���`���鋛���[�̘b�͑�14�́u�x�������Ɠ������q�v�Ō���Ă���B�G���X�̂��A�g�E�B�����͖{��12�̎x���ɕ������Ƃ����B�q���E�ꑰ�A���}�l�R�ꑰ�A�X�C�M���E�ꑰ�A�C�k�ꑰ�̂S�x�����ł��Â��A�ȉ��A�C���R�A�����E���o�V���E�A�g�E�����R�V�A���g���A�ԓy�A���V�����Ȃǂ������B12�ȊO�ɂ��ו�������A�����[�̓T���t�E�l���i���i�T���t���}�O���̓���H�ׂȂ��j�ꑰ�̋N���Ƃ��Č���Ă���B���̈ꑰ�̓v����͌���Chama�Ƃ������ɏZ��ł���B�G���X�̘b�̓x���E�F���^�E�H�[��}�J���b�N���܂Ƃ߂����̂��������B
�@Chama�̒j�͍ŋߍȂ�S�������̂ŁA���_���Ȃ���C�݂�����Ă����B���̎��A�Ⴂ�����Əo��A�������邱�ƂƂȂ����B��������A�Ȃ͗��������Ȃ��Ȃ�A�e�ʂɉ�ɍs���˂Ȃ�Ȃ��ƍ��������B�Ȃ͈�l�ōs���ƌ��������A�j�͈ꏏ�ɍs�����Ƃ������������B�Ȃ̉Ƃ͊C���ɂ���A�e�ނ��ޏ����g�������Ɩ������A�v���Ȍ㌈���ĊC�̉Ƃ�Ƒ��̂��Ƃ����ɂ��Ȃ����Ƃ�������B�C�̉Ƒ��ɒg�����}�����A�O�ɏo�Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ��ӂ���ē����߂����Ă����B�������ƁA�j�͋��̂悤�ɂȂ��Ă������B��A�C��ɓ��肪�Ƃ���ƁA���ɂ���Ƃ������������̈�ł������B���ɗU��ꂽ�j���ӂ�ӂ�Ɛ��ʋ߂��ɏオ���čs���ƁA��œ˂���Ă��܂����B�C�̉Ƒ��͒j�������߂����Ƃ��邪�A�ނ�l�̗͂����������グ���悤�Ƃ��Ă����B�C�̉Ƒ��͎L�ɗ���ŁA��ɕ������Ă���j�����ݐ��Ă��炢�A�悤�₭�C�̉Ƃɒj��߂����Ƃ��ł����B�����肾���A���̎蓖������ƒj�͌��C�ɂȂ������A�e�������͍Ăѓ����悤�Ȃ��Ƃ��N���邱�Ƃ�S�z���čȂƋ��ɗ��ɖ߂�悤�Ɍ������B���̎��A�y�Y�Ƃ������n���A�ۊǂɒ��ӂ���悤�����Y�����B�j�����ŏZ�މƂ͒�������L���Ē����`�Ɉ͂����̈�ł��������A���̑������̒������E�����B���N��ɁA�����S�̂̏��L�҂͉������ւ��邱�Ƃɂ����B�����ŗ�������������Ƃ́A���ꂪ���Ď�������������ł��邱�ƂɋC�t�����B������������悤����ꂽ�j�͌�������Ă������A���݂̋^����������ꂻ���ɂȂ�A���ɐS�Ȃ炸���^����b���Ă��܂����B��j�����͂����ɂ͋N����Ȃ��������A��l�ڂ̍Ȃ��}�������ƂŎ����͐������B�ȓ��m�����_�ɂȂ�A��Ԗڂ̍Ȃ̂��Ƃ������ƂȂ����Ă��܂����B�v�̐����ɂ�������炸�A���̍Ȃ͈�ԉ��̎q��������āA�{���̎p�ɖ߂��ĊC�ɋA���Ă������B��l�̔N��̎q�������͕��̂��ƂɎc����A���̎q�������̓T���t�E�l���i���ꑰ�ƂȂ��āA�T���t�i�}�O���j�͐H�ׂȂ��B
�@�G���X�̓A�y�C�Ƃ�������Ԃŕ߂炦���C���T�i�Ƃ����j�̘b��ޘb�Ƃ��ďЉ�Ă���B�C���T�i�������E�����Ƃ���Ɩ��������̂ŁA���̂܂܉ƂɎ����A�����B���̌㋙�ɏo�����Ė߂��Ă���ƁA�Ƃł͔������Ⴂ�����Ǝ������Ă����B���̓C���T�i�̖S���Ȃ������e����ȂɂȂ�悤�ɗ��܂ꂽ�����Ɩ������A�Ȍ�A�y�C��H�ׂȂ��悤�ɂƌ������B�C���T�i�͈ꑰ�̍Ō�̈�l�ł��������A���̍Ȃ��}���Ă���ꑰ�͔ɉh���A�A�y�C���A��ɃA�p���Ɩ��̂�悤�ɂȂ����l�X�̖��͒��̖��̂ɂ��Ȃ��Ă���B���̂悤�ɓ���̓����A���A���̓��◑�A�A��������邱�Ƃ͐�̑����ł���ꍇ�̂ق��ɁA�T��x�A���ɉΗj���Ɏ��Ƃ������K�ɂȂ��Ă���l�X������A�ƃG���X�͓`���Ă���B�x�����V�����������Ƃ��́A���������x���͓�̋֎~���ł͂Ȃ��A�ŏ��̕��͎̂Ă��āA�V�������ݕ����̗p���邱�Ƃ����ʂł���B
�@�w���A�t���J�����C�݂̃g�E�B�ꖯ���x�ł͍L���n��ŐM����Ă���^���h(Tando�A�k���A�A�V�����e�B�l�̎�_)��{�{�E�B�V(Bobowissi�A�암�̎�_)�Ȃǂ̑��ɁA�n��M�̐_�X���L�q����Ă���B�^���h�͓����̐�̐_�ŁA�Ȃ̓J�^���E�B��Katarwiri��̏��_�ł���B�J�^���E�B���͍����̂悤�Ȕ������Ă��āA����ő����Ă���B�����̐����т�v�����A���j�����b�ł���B�{�{�E�B�V�̍ȂƂ��Ă̓A�u�E���X��̏��_�A�|���j�AAppollonia��������l�X������B
�@�P�[�v�R�[�X�g�n��̎�_�͏��_�t�H�[�X(Fohsu)�ŁA���ΐ����̖��ɏZ��ł��Đl�X�ɉ�����Ă����ƍl�����Ă���B���̉��̓��̒[�ɂ̓A�W�E�A�j��(Adzi-anim)�Ƃ����j�_�����Ĉ�������l�X�Ɍb�ށB���̓�_�͕v�w�ł���B�`�̐_�W�E�B�E�W���k(Djwi-j'hnu)��1824�N�V��11���ɖk���̃A�V�����e�B�l���P�[�v�R�[�X�g���U�߂Ă������ɁA���ނ����y�n�Ō��������ꂽ�_�i�ł���B�R�b�g�[�E�N���o(Kottor-krabah)�͓����̈�˂ɏZ�ސ_�ŁA���I�̌`�����Ă��āA�����`���ɂ��ƁA����������P�[�v�R�[�X�g�ɍŏ��ɂ���Ă����l�X�Ƌ��ɓy���̚�ɓ����ē��s���ė����_�i�ŁA�����Ɉ�˂��@������悢�������Ă��ꂽ�_�ł���B�P�[�v�R�[�g�̏㗤�n�����_�̓~�E�C���p�t�I(Mi-impahuo)�ł��邪�A�C�̗̈�̐_�͑����������������Ƃ��ł���B
�@�P�[�v�R�[�X�g��̊�̉��ɂ���̂��^�[�r(Tahbi)�A�������l�`�ł��邪�A����̓T���̕h�̂悤�ɂȂ��Ă���B�l�X�̖���D���A���̎��͖̂ő��Ȃ��Ƃł͌�����Ȃ��ƍl�����Ă���B���̐��̊��ɏZ��ł���^�[�r�̍ȃ^�[�r�E�C��(Tahbi-yiri)�͔������ŏk�ꔯ�������l���`�̏��_�ł���B����ɂ͕Z�\�������A���Ă͒������������Ă������A���ł͐��ꉺ�����Ă���ƍl�����Ă���B�l�̖���D���A���ɑ��̓y�n�o�g�̎҂ɂ͗e�͂��Ȃ��B�P�[�v�R�[�X�g��K�ꂽ�ŏ��̃��[���b�p�l�ł���|���g�K���l�̎���ɁA�^�[�r�E�C�����C���j���Ŋ��ŏ������l�q��ڌ��������t�������Ɠ`�����Ă���B�j�_�N�[�W��(Cudjo)�͓G���C�������ė���Ƃ��ɖh���ł����̐_�B�A�[�g�E�G���e�t�B(Ahtoh-enteffi)�̓o�[�t(Burf)�Ƃ����n�_�̐_�ŁA���͔������k�ꔯ�A���l�`�Ől�Ԃɂ͍D�ӓI�łȂ��B���Ƃ����Ӗ��̃A�u���E�N(Abroh-ku)�͒�̔g�̐_�B�͂͂���قNj����Ȃ��A�D��]�������Ă����܂ł͒D��Ȃ��B���͊D�F�ŁA�����ő����Ă���B�C�J�[�E�`�����[(Ichar-tsirew)�͊C�݂̑傫�Ȋۂ���ɏZ��ł��鏗�_�A���ʂ̐l�Ԃ̑傫���ō����������Ă���B���̊�ɂ͒j���͋߂Â��Ȃ��B�����̐����ł���A�j�����킸�V�����͂����Ŗ��t�����A�������鏗���͂��̊₩�獥�Ƃ֘A����Ă����B���̍ہA��̌��Ƀ�������������A���z�������ɕ~�����B�Ɠ��̈��S�ƁA�D�w����邱�Ƃ��ł���ƍl�����Ă���B���_�̉E��ɂ́A�N������j����ǂ������ڂ������Ă���B�ȏ�̂U�_�͊C�ݐ������_�i�ł���B
�@�A�N���E�u���t�H(Akum-brohfo)�͔��l�̎E����Ƃ����Ӗ��̊C�_�ł���B�D�����v����ƁA��D���Ă���y�n�̍��l�͉j�����I�݂œM�����邱�Ƃ͂Ȃ����A���l�͂悭���𗎂Ƃ��̂ōl����ꂽ�V�����_�i�ł���B�C�݂̏㗤�n�ɂ͂��ꂼ��̃A�N���E�u���t�H�����āA�p�`�����ꂼ��قȂ��Ă���B���܂Ŗ��O�̕t���Ă��Ȃ�������ʂł��A�j�D���Ĕ��l���M������ƃA�N���E�u���t�H���h���ƂȂ�B�y�n�̐l�X�Ɉ��ӂ������Ȃ��A�N���E�u���t�H�������āA��L�̐_�i�ɂ͗r�A�{�A�������A���V���ȂǓK���ƍl�����Ă�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�G���~�i�n��̒n���_�Ƃ��Ă̓V���~��E�J�N����̐_�ł���C�`�C��(Ihtiiri)������B�������Œ����ȋ��l�͐��̒������𒅂Ă��āA�E��ɂ��ڂ�U��グ�Ă���B�l�ԂɈ��ӂ������Ă��邪�A�G���~�i�̐l�X�ƃA�V�����e�B�l�ɂ͍D�ӂ�����Ă���B�ꌎ�̓���̓��ɂ͉͌��̑��ɐl�X�͏W�܂�A�C�`�C���ɋ]���������B���Ă͐��l�j�����]���ɋ������B�C�`�C���̑��ƍՒd���݂���ꂽ�ƂŎ藎�Ƃ��ꌌ�������������ꂽ�B���̌�h�����̗x��┭�C�A�����Ƒ����B�R�g�[���E�r�E�V��(Kottor b'iusin)�͍����̎��_�ł��鏗�_�B���̕v�̓R�R�E�C�r(Koko-ibi)�B���̓�_�͔������̕��ʂ̐l�Ԃ̌`�����Ă���B�{���X�A�k(Bons'ahnu)�͔g���������ӂ���C�̊�ɂ���_�B�������������l�̎p�����Ă���B�l�ԂɈ��ӂ�����A�l�Ԃ̋]�����ŋ߂܂ŕ�����ꂽ�B�x�[�j��(Behnya)�͓����̐�̒j�_�B�E��ɂނ��A����ɓ��������l�ŁA�R�_�ł�����B�x�[�j���̍Ȃ��i�i�E�G�i(Nana enna)�ŁA�j�B����ɏo���������ɁA�c��������������삷��V�k�p�̏��_�ł���B
�@���ꂼ���ɂ͐_���h��A�A���R�u����̒j�_���\�EWassau(�������A�l�ԂƓ����̎p)�A�A�n��̃A�n���^Ahanta�i���b�̓��j�j�A�X���E�E�B�X��̒j�_�k�N�����E�t�H�XNkwam-fohsu(���F�̔��A�l�ԂƓ����̎p)�A�A�~�T�E�g�E�B��̒j�_�A�~�TAmissa�i�܂��̓I�LOki�B�������A���l�j�Ȃǂ�����B���̐F�A�傫������߂��Ă��āA�����͐l�Ԃ̋]�������߂鈫�ӂ����_�X�ł���B�n��̐�̐_�X�͌�ɐ����s�v�̋��ʂ̔F�������L���鏗�_�}�~�E���^�̖��̂ŌĂ��悤�ɂȂ�A�M�̓�����}���邪�A���̉��ʂ̈ӎ��ł͖{���̐���̐_�X�������Ă���B
�@�}�J���b�N�̒���ɖ߂�ƁA��R�̃^�u�[�N�Ƃ́u�Ȃ̖��i����̌��t�j�����ɂ��邱�ƂȂ���v�ŁA�����ɑO�X��Љ���G�X�g�j�A�̐l��杂��o�ꂵ�Ă���B�l���ƌĂ�ł͂Ȃ�Ȃ��ƌ����ĊC��ɏZ��ł����_�v�͖�j��A�n��ɖ߂��ꂽ�Ƃ��ɂ͘V�l�ɂȂ��Ă��āA�Ԃ��Ȃ�����ł��܂����B���Łu���v�Ƃ������t���g��Ȃ��ŗd���ƌ��������A���O�[�W����̋R�m�̘b�A�A�����J���Z���ł���V���[�j�[�̐l�X�̐_�b�ŁA�Ȃ̖����������r�[�ɗY���ɕϐg���Ă��܂����j�̘b���Љ���B
�@��S�̐N�Ƃ́u�������ƉƂɂ��邱�ƂȂ���v�B����ꏊ�ɒ����Ƃǂ܂邱�ƂŁA����܂ł̐�����Y��Ă��܂����Ƃ͑����̖��b�Ō�����B��T�́u�v�͍Ȃ�{�点�邱�ƂȂ���v�ł���B�Î��L�̃A���m�q�{�R�ƃA�J���q���̐��b���܂��Љ��A�����Ń{���l�I�̃_���N�̐l�X�̋������̘b���Љ���B�����ϐg�������ƌ��������j�͍Ȃ��Ȃ����Ă��܂��A�Ȃ͐��E�֖߂�Ƃ����b�ł��邪�A�ٌ`�̍Ȃ�{�点�Ď����Ƃ����p�^�[���͑����̖����Ɍ�����B�G���X�̓^�u�[�N�Ƃ̐��b�E���b���Љ����ŁA���̈Ӗ�������̂𐢊E�̖����̊֘A����K�����猩�o���Ƃ�����r�����w�I�L�q���s���Ă���B
 �@���āA�G���X�w���A�t���J�����C�݂̃g�E�B�ꖯ���x�ɓ��݂Ƃǂ܂肷�������A�A�t���J�̐l���֘A�Ńx���E�F���^�E�H�[���w�E����`���͂��������B�x�j���̉��I�w��(�x���E�F���^�E�H�[��Ohen�łȂ�King
Chen�ƕ\�L���Ă���)��\�����u�����Y�̃����[�t�Ɋւ���b�ł���B�����̖�Ⴢɖ`���ꂽ���́A����̒n�ʂ�ۂ��߂ɁA���E�̐_�I���N���̉��g�ƂȂ����̂ő������ɂȂ����Ɛl�X����������߂��B���̂��߁A�u�����Y�̎p�͗����������āA���̐�[�������ƂȂ������ʌ����̉��ƂȂ��Ă���B����͂����郁�����W�[�k�^�̓l���̌`�Ԃ��v���N��������B�������[���b�p�Ɛ��A�t���J�̉����œ����Ɍ����铯�`�̃f�U�C���͐l�X�̋����Ƒz�����h�����Ă����B�_�O���X�E�t���C�U�[�Ɂu�x�j������у����o�|�p�̋������v�Ƃ����_��������B
�@���āA�G���X�w���A�t���J�����C�݂̃g�E�B�ꖯ���x�ɓ��݂Ƃǂ܂肷�������A�A�t���J�̐l���֘A�Ńx���E�F���^�E�H�[���w�E����`���͂��������B�x�j���̉��I�w��(�x���E�F���^�E�H�[��Ohen�łȂ�King
Chen�ƕ\�L���Ă���)��\�����u�����Y�̃����[�t�Ɋւ���b�ł���B�����̖�Ⴢɖ`���ꂽ���́A����̒n�ʂ�ۂ��߂ɁA���E�̐_�I���N���̉��g�ƂȂ����̂ő������ɂȂ����Ɛl�X����������߂��B���̂��߁A�u�����Y�̎p�͗����������āA���̐�[�������ƂȂ������ʌ����̉��ƂȂ��Ă���B����͂����郁�����W�[�k�^�̓l���̌`�Ԃ��v���N��������B�������[���b�p�Ɛ��A�t���J�̉����œ����Ɍ����铯�`�̃f�U�C���͐l�X�̋����Ƒz�����h�����Ă����B�_�O���X�E�t���C�U�[�Ɂu�x�j������у����o�|�p�̋������v�Ƃ����_��������B
�@�x�j���̃u�����Y�͗L���ł��邪�A���̋N���͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�u�x�j���̐����𒆐S�ɂ����|�p�́A�A�t���J���p�̒��ł��ł��D�ꂽ���̂��Ƃ����]�����^�����Ă���B(����)�x�j���̐����p�͎ʎ��I�ȗl��������Ƃ��Ă���A�\������������Ă���B�������A�����̌����҂͂��̗l�������āu�A�t���J�炵���Ȃ��v�ȂǂƑ����A���̍�҂��O���̎҂ƍl�����肵���v(�ԍ㌫�u�X�ђn�т̓s�s�ƍ��Ɓv�A�w�V���A�t���J�j�x�A�u�k�Ќ���V���A1997.7.20�Ap.146)�B�x�j�������̓i�C�W�F���A�암��13���I����1897�N�܂ő��݂��A���݂��x�j���E�V�e�B�[�ɉ������鉤���ł���B�I�w���͂��̏����̉��i��W��j�ŁA�݈ʂ�14���I����(1334?�`1370?)�ł������B�݈�25�N�̂���A������Ⴢ��Ă��܂����B�����͉��̌��N������s�g�Ƃ��đ������A���ʂƂ��ĉ����E���Ă��܂��̂ŁA�I�w���͏Ǐ���B�����Ƃɂ����B��c�ɐ旧���ĕ����ɓ���A�F���ސȂ�����ɏo��A�Ƃ������Ƃɂ��Ă������A�̃��[�_�[�͐g���B���ĉ��̔閧��m���Ă��܂����B���̓��[�_�[���E���Ă��܂������A���̌�̉����ǂ��Ȃ������ɂ��Ă͐���������Ă���B�����̐S�͉����痣��A�Αłŏ��Y���ꂽ�A�܂��͎��E�����Ƃ������B����̓x���E�F���^�E�H�[���`���Ă���悤�ɃI���N���̉��g�Ƃ��Đ����Ȃ��炦���Ƃ������B���̌��ʂƂ��đ��悪�D���ŕ\�����ꂽ���̎p�̃u�����Y������Ƃ����̂͂ǂ����j���ł͂Ȃ��悤���B
�@�x�j���̉��Ɛ��E�̐_�I���N���͌��т��Č���邱�Ƃ��悭����B�I�w���̑��q�ŌZ�킽���̍Ō�ɉ��ƂȂ����G�E�A���i��12��A15���I���A1440?�`1473?�j�͑剤�ƌĂ�A���Ƒ̐��������͂��g�債�����A�`���ł̓I���N���̋{�a��K��A�_�̗�͂��߂��X��̈ߏւ𖧂��Ɏ����o�����ƌ����Ă���B�I���N���͕x�������炷�_�Ƃ��M�����A���傤�ǂ��̂��됼�A�t���J�Ɍ��ꂽ�|���g�K���l���V��ȕx�������炷�I���N���ƌ��т��čl����ꂽ�悤���B���Ɨ����ړ����A�X���e�Ί�������炷�|���g�K���l�̓I���N���Əd�Ȃ�B���Ɨ��ɂ܂������Đ������郏�j�A�ցA�D��(mudfifh)���܂��I���N���ƌ��т��B���i���邢�̓I���N���j�Ƃ����̐������Ƃ̍��̑����t���C�U�[�����グ���u�������v�ł���B�t���C�U�[�̓C�t�F�A�����o���܂߂��x�j�����Ӓn��ɂ���u�������v�i���ʌ����̉����A�����́u��v�̂悤�ɗ������L���ď���ɂ����A���������ɕό`�������B�X�^�[�o�b�N�X�̃��S���A�`����Ă��Ȃ��������܂߂Ďv���`���߂��`�ɂȂ�j���O�̃^�C�v�ɕ����Ă���B1)�����̂悤�ȁA�オ�������������Ă��鑜�A2)���̕t�����ɋ�(����)�̓��������āA�������̑S�̂��`�Â����Ă��鑜�A3)�オ�����������j��g�J�Q�̂悤�ɂȂ�A����̕����������ɂȂ��Ă��鑜�A�̂R�^�C�v�ł���B���ʌ����̐l���̓����́A���Ō����������͗l�A�܂��͎���A�[��̃X�J�[�g�̂悤�Ȗ͗l�A�ڗ����`�A�����̊��A�Ȃǂ��t�^����Ă���B
 |
 |
 |
�@���́u�������v�͈�ڌ���A���}�l�X�N���z������l���Ɨގ����Ă���̂ɋC�t���B���[���b�p�l�̓����ȑO�ɑ��̓`��������ƍl�����A���}�l�X�N�̐l���ɐ旧�����`�̐}�����G�g�����A�A�X�Ƀ��[�}�鍑�����n��ɐڂ���C�����A�C���h�A�A�t�K�j�X�^���ɂ����`��������̂ŁA�t���[�U�[�̓��[�}�����悩��̉e�����������Ă���i�C���h�𒆐S�ɂ������b���ƃM���V�A�E���[�}�̊W�ɂ��ẮA���앐���E�呺�����w���Ȃ錶�b�x�A�W�p�АV���A2009.12.21���Q�Ƃł���j�B�������A���̌o�H�A����͓���ł��Ȃ��̂ŁA�C�t�F�i�����o�ŏ��̉����j�ɉe�����Ă���ƍl������m�N����������ɓ���Đ������Ă��邪�A�`���A�Ǝ��Ƃ�����I�Ȃ��Ƃ͕������Ă��Ȃ��B
 �@���}�l�X�N�̓l���ɂ��ẮA�����͔��`��a�q(�u�C�̖L�`�@�̐l�������߂����āv�A�w�C���[�W�̉�ǁ@�����x�A�͏o���[�V�ЁA1991.1.16�App.51�`69)�A�ŋ߂ł͋���S�}(�u�l���̂��ߑ��ƃP���^�E���X�̊��Ⴂ�@���}�l�X�N���p�̖����݂Q�v�A�uUP�v��36����W���A�ʊ�418���A������w�o�ʼn�A2007.8.5�App.45�`50)�̘_�l������B���`�A��������y���Ă��郆���M�X�E�o���g���V���C�e�B�X�ɂ��A�V�����|�o��(�n���@�v��A�w�ٌ`�̃��}�l�X�N�@�ɍ��܂ꂽ�����̗���z�x�A�u�k�ЁA2009.3.12)�B
�@���}�l�X�N�̓l���ɂ��ẮA�����͔��`��a�q(�u�C�̖L�`�@�̐l�������߂����āv�A�w�C���[�W�̉�ǁ@�����x�A�͏o���[�V�ЁA1991.1.16�App.51�`69)�A�ŋ߂ł͋���S�}(�u�l���̂��ߑ��ƃP���^�E���X�̊��Ⴂ�@���}�l�X�N���p�̖����݂Q�v�A�uUP�v��36����W���A�ʊ�418���A������w�o�ʼn�A2007.8.5�App.45�`50)�̘_�l������B���`�A��������y���Ă��郆���M�X�E�o���g���V���C�e�B�X�ɂ��A�V�����|�o��(�n���@�v��A�w�ٌ`�̃��}�l�X�N�@�ɍ��܂ꂽ�����̗���z�x�A�u�k�ЁA2009.3.12)�B
�@���}�l�X�N�̐l���͂Ȃ��Ȃ̂��ɂ��āA����͐�s�������R�ɕ����ďЉ�Ă���B�u���́A��{���ł͂���肪�����̂ŁA��{�ɕ������v�A�u���ɁA�����X�L�����̖͕���v�A�u��O�ɁA�L�`�F����v�B��O�̖L�`���͔��`�̘_�l�܂������̂ł���B�܂��L���X�g�������ɐl�������闝�R�Ƃ��āA����̓��N�����N���}���N�X�́u�A�C�������h��k���̓`���̉e���ň�I�̐��l�`�╶�w�ɂ́A�C��҂�������ǂ��l���������Ε\�킳���v�Ƃ����w�E���Љ�Ă���B���N�����N���}���N�X�̌�������1997�N�o�łł��邩��A���`�͓��R�Q�Ƃ��Ă��Ȃ��B
�@���`�́u�l�����ł���Ƃ����L�q�����Ă��镶���͂ǂ��ɂ��Ȃ��v�Ƃ��A�}���\���ɕ\��闝�R�Ƃ��āA�u�V�����g���[�̒Nj��v(�A�����E�t�H�V����)�A�u�A�W�A�N���̐}���v(�����M�X�E�o���g���V���C�e�B�X)�Ƃ��������I���R�B�u�ً��I�Ȃ��̂Ƃ��Ă̈Ӗ��Â��v(�}���A�Z���[�i�E�`�F�b���B�u�P���^�E���X����{�̔��������̂Ƃ��ē�ʐ������ً��̃V���{���ƌ�����Ƃ��납��A�T�C�����ɂ��ً��̃V���{���Ƃ��Ă̐�����тт����邽�߂ɔ����ɕ������v)�A�u�G���e�B�b�N�ȈӖ��̊ܒ~�v�A�u�Ӌ����v�i�L�A���E�t���S�[�j�j�A�u�������E�L�`�̃V���{���v�i�����s�O��j�A�u�L���P�[�E�V�r�b���Ƃ̌��т��v(�G���~�[���E�]�b��)���Љ�A�u���}�l�X�N���ɂ͓�������������͂܂���d���������݂ł������B�����炱������͐l�����L�`�Ƃ����Ñォ��̃V���{���̈Ӗ����c�����܂܃L���X�g���̃R���e�L�X�g�̒��ɂ��܂܂ꂤ��Ō�̎��エ��яꏊ��������������Ȃ��̂ł���v�Ƙ_�l����߂������Ă���B���̃W�F���_�[�_�i�t�F�~�j�Y����]�j�I�����ɂ��ċ���́A�u�ŋ߂̌����ł́A�u������N���������v�Ɂu���悯�v��u���Y�F��v�ȂǁA���ԐM�̖��c���������́A�ے肳�ꂩ���Ă���B�قƂ�ǂ���I�ȍ~�̍��Ɩ��炩�ɂȂ������Ƃ���A�߂̏�i�̂ЂƂƂ��āA�L���X�g���̕����ŗ�������̂��Ó��̂悤���v�ƌ����Ă���B����E����̕��͂Ƃ���s�������Љ�̏��_�ł���A���}�l�X�N���Ɍ��肳��Ă���̂ŁA�_�O���X�E�t���C�U�[�ɂ��x�j���̃u�����Y���͎���ɓ����Ă��Ȃ��B
 �@���āu�̐l���v(���`��a�q�E����S�})�Ƃ�����}���ɂ��ẮA���{�ł́u����l���v�u�o���l���v�u�������W�[�k�v�ȂǂƂ��Ă�ł��邪�A�_�O���X�E�t���C�U�[�͘_���̃^�C�g���ł́uTHE
FISH-LEGGED FIGURE�v���g���Ă���B�_�����ł́uYoruba self-domping
figures�v�ua figure grasping foliate, curling tails�v�uthe
fish-tail-holding figure�v�ȂǂƂ������Ă���B����ɓ����i���j�������������L���Ă���}�����uAnimal
Master�v�܂��́udompteur�v(�t�����X��B�����t�E�ҏb�g��)�ƃt���C�U�[�͌ĂсA����̏ے��ł�����q���E�𗼎�Ɉ����Ă��郈���o�̉��̐}�����Љ�Ă���B�l��������ɋ��������Ă���}���悭�m����Ƃ���ł���B�uself-domping�v�Ƃ͉p����̑g�ݍ��킹�̑���ł��낤�B�}�~�E���^�̑�ւ�g�ɂ܂Ƃ��Ă���G�}���uself-domping�v�̈�ƍl���邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B���āA�t���C�U�[�ȊO�́u�l���v��\���p������Ă݂�ƁA�ua
mermaid with two tails�v�ua two-tailed mermaid�v�ua twin-tailed mermaid�v�ua
doublu-tailed mermaid�v�ua bifid mermaid�v�ua bifurcated mermaid�v�Ȃǂ��ڂɕt�����B�܂��A�O�m�[�V�X�֘A�̐}���u�A�u���N�T�XAbraxas�v�Ȃǂ�����ɓ����Ă���B
�@���āu�̐l���v(���`��a�q�E����S�})�Ƃ�����}���ɂ��ẮA���{�ł́u����l���v�u�o���l���v�u�������W�[�k�v�ȂǂƂ��Ă�ł��邪�A�_�O���X�E�t���C�U�[�͘_���̃^�C�g���ł́uTHE
FISH-LEGGED FIGURE�v���g���Ă���B�_�����ł́uYoruba self-domping
figures�v�ua figure grasping foliate, curling tails�v�uthe
fish-tail-holding figure�v�ȂǂƂ������Ă���B����ɓ����i���j�������������L���Ă���}�����uAnimal
Master�v�܂��́udompteur�v(�t�����X��B�����t�E�ҏb�g��)�ƃt���C�U�[�͌ĂсA����̏ے��ł�����q���E�𗼎�Ɉ����Ă��郈���o�̉��̐}�����Љ�Ă���B�l��������ɋ��������Ă���}���悭�m����Ƃ���ł���B�uself-domping�v�Ƃ͉p����̑g�ݍ��킹�̑���ł��낤�B�}�~�E���^�̑�ւ�g�ɂ܂Ƃ��Ă���G�}���uself-domping�v�̈�ƍl���邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B���āA�t���C�U�[�ȊO�́u�l���v��\���p������Ă݂�ƁA�ua
mermaid with two tails�v�ua two-tailed mermaid�v�ua twin-tailed mermaid�v�ua
doublu-tailed mermaid�v�ua bifid mermaid�v�ua bifurcated mermaid�v�Ȃǂ��ڂɕt�����B�܂��A�O�m�[�V�X�֘A�̐}���u�A�u���N�T�XAbraxas�v�Ȃǂ�����ɓ����Ă���B
�@
�@�G�h�l�̃x�j�������̒��S�s�s�̓x�j���s(�l���S���l�ȏ�)�ŁA�����͕������Œ��q�����̓`���Љ�ł���B�y���e�R�X�^���h�Ȃǂ̃L���X�g���ƁA�߈˂��_���q�𒆐S�Ƃ���`���M�����݂��邪�A��s�s�ł�����B�ߑ�Ɠ`���̒��ŁA1980�N��ȗ��A����1990�N��ɓ����Ă���}�~�E���^�𐒔q�_�ɉ�����Վi�iOhen�j���ڗ��悤�ɂȂ����B�����̗����E�����A�o�ϓI�i�o���Љ�I�w�i�ɂ���A�}�~�E���^�ɑ����A�߈˂����o����M�A���y�A�|�p�ŕ\������l�X�������悤�ɂȂ����B�}�~�E���^�Ƃ����ތ^�I�}����m���͂���ȑO���炠�������A���g�߂ɂȂ����̂͂����Â����Ƃł͂Ȃ��B�}�~�E���^�ɂ̓X�B�[�c�≻�ϕi�A���v�ȂNjߑ�I���i���������A�n�[���j�J��M�^�[�Ȃǂőt�ł��鉹�y���Ղ�ɂ͌������Ȃ��B�G���E�V���A���W�I�����A���y�Ƃ��������s�����Ɠ`���M���b�������ɂȂ����`�Ń}�~�E���^�M�͍L�܂��čs���B�x�j���s�̃}�~�E���^�ɂ��ẮA�`���[���Y�E�S�A�u�}�~�E���^�@�i�C�W�F���A�A�x�j���s�ɂ�����s�s�I���݁A�`���`���ɂ��āv���Q�Ƃł���B�����ł͐l�ފw�҃��n�l�X�E�t�@�r�A��(1937�`)�̊w����M�^���X�g�A���B�N�^�[�E�E���C�t�H(1941�`)�̉��y���Љ��Ă���B
�@�G�h�̋ߗז��������o�̘̐b�u���������Ƌ��v(�w���E�̖��b(7)�A�t���J�x�A���R�~�q��A���傤�����A1977.2.10�App.267�`271)�ɂ͐��̐��I�j�W�F�M(onijegi)�A�͂̏��_�I���E�F��(Oluweri)������Ă���B���������ׂĒf���āA�����ň�Ԕ������j�ƌ������悤�ƐS�Ɍ��߂Ă������������́A�����ϐg������҂Ɩ��@�̉̂����}�ɂ��ĉ���Ă����B��l�̔閧��m�����킪���e�ɘb�����̂ŁA���e�́A���̗���ɋ����E���A�������ɂ��A�A���Ă������ɐH�ׂ����Ă��܂����B�^����m�������͉͂̏��_�ɕv������ł���Ȃ�A�͂̐���Ԃ����߂�悤�Ɋ肢�A�͂ɔ�э��݁A���̐��I�j�W�F�M�ɂȂ����B���ł��A�I�j�W�F�M�̉̂���������Ƃ����B
�@���l�̘b�͑吼�m��n���āA�o�[�W�������ɓ`����Ă���B�u���Ƃ��̗��l�v(�w���E�̖��b(31)�J���u�C�x�A���傤�����A1985.10.10�App.65�`69)�ł́A���l�̋���H�ׂ�����ꂽ���͓����悤�ɐ�̐[�݂ɓ����Ă������A���̐��ɂ͂Ȃ�Ȃ������B���e������̋����ȍs�ׂ�����݁A�Q���߂��ނ��ƂŏI����Ă���B����ɁA�T�E�X�E�J�����C�i�̃V�[�����ɂ̓V���f�����^�̗ޘb���`����Ă���B�ȑO�Љ�����Ƃ̂��郍�o�[�g�E�c�E�T�����X�[�V�w�X�[�L�[�Ɛl���x�̌��b�ɓ�������̂ł���B�G���V�[�E�N���[�Y�E�p�[�\���Y(1875�`1971)���w�T�E�X�E�J�����C�i�B�V�[�����̖����x(1923�N)����x���E�F���^�E�H�[�������Ă���(pp,209�`210)�B�p��Ǝo���ɂ����߂��ĉ쎀���O�܂łɂ����������l�̖���l�����C���ɘA��čs���Ă��ĂȂ��B�ӂ����Ɏv�����o���ƕ��e��������čs���A�l�����Ăяo�����}��m���Ă��܂��B�l�����Ăяo�������e�́A�e�Ől���������E���Ă��܂����B�l��������Ȃ��Ȃ����̂ŁA���͒Q���̂��܂�A�C�ɐg�𓊂��Ă��܂��B
�@�i�C�W�F���A�̐��̐��̘b�Ƃ��Ă͑��ɁA�k�i�C�W�F���A�A�t����(�t���j�H)�����̘b�u���Ɛ�̉����܁v(�w��Ǝq�̐��E�ނ����b�V���[�Y�@��11���@�A�t���J�̂ނ����b�x�A�ؕ鐳�v�^���A��茹��Y�^����A1968.5.10�App.19�`33)���Љ��Ă���B��l�̂��܂̓��A��l�ɐՌp���̉��q���Y�܂��B�q�̂Ȃ��܂́A���q���E���悤�ɖ�Ԃɖ����邪�A��Ԃ͎E�����Ƃ��ł����A���q��X�ɒu������ɂ���B���Ő�̐����Ăяo�����Ƃ�������ꂽ���q�́A��̕P�Əo���������B���̍���Y����Ȃ����q�́A���@�̔n�ɏ��ȂƋ��Ɍ̍���K��A���҂�Ǖ�����B�����S���Ȃ�����́A��Ɨ��A��̍��̉��ƂȂ��āA���@�̔n�ɂ܂�����A�s�������Ȃ���K���ɕ�炵���B���̘b�̌Ăяo���̌��t�́A��̖��̖��O�ł������B
�@�w�l���̂������@�R���S�̖��b�x(�A���W�F���E�J�f�B�}�|�k�W���W�E�J�u���T�^���A�W�F�C���E�v�e�B�W�����^�G�A2007�N)�Ƃ����y�[�p�[�o�b�N�G�{������B�R���S���勤�a���o�g�̏������q���̍����������b���A���ݍݏZ�̃A�����J�ŏo�ł������̂ł���B�������͌����K����ɂȂ�ƁA���𔒂��A�����Đ�点�邽�߂Ɏ��̎���K�˂ɏW�c�ŏo������B����n�_�܂ŗ���ƁA���ꂼ��L�\�Ȏ��ɏ�����悤�A�v���v���̕��p�ɐi�ށB���̖̎��k�S���͉��炵���V�l�ɏo��A�����Ă�������B�S�Ă̍�Ƃ��I���܂łV�������������A���̍Ō�̓��ɁA�V�l�͉Ƃɒ����܂Ō����ɐ��܂�ŁA���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɩ������B�������̏W���ꏊ�ɒ����Ă�����b�����Ȃ��k�S�����A���̖������͋����āA���ɘb�������邱�Ƃɐ��������B�k�S���̎��͂��炵����������Ă����̂ŁA�������͎�����̋����҂����Ȃ��Ȃ�ƐS�z���āA�k�S����ł��t���Ēr�Ɏ̂ĂĂ��܂��B���ɋA�����������́A���ꂼ��K���Ȍ��������ɂ͂��������A�X�̒r�ɐl�����o�����ĉ̂��̂��Ƃ����b���L�܂�B�E�C�̂����҃J���o�����S�ƂȂ��āA�j�B���ԂŐl����߂炦�邱�Ƃɂ����B�l���ɕς���Ă����̂̓k�S���ŁA���������̗͂Ō��̎p�ɖ߂�A�J���o�ƌ��ꂽ�B�k�S����r�Ɏ̂Ă��������͕����B
�@���̘b���G�{�̍�҂ɘb���Ă��ꂽ�̂͗��e�̔_��̐��b�����Ă����b�̖���̒j�ł������B���̂悤�Ȍ�����A���E�F�i�E�J�T��(mwena kasala)�Ƃ����ƍ�҂͓`���Ă���B�}�_�K�X�J���A���[���V���X�A�Z�C�V�F���A�����j�I���A�R�����̌��肽���̘b��121�b�W�߂��A���[�E�w�A�����O���w���ƌ��@�C���h�m�n��̖��b�ƃN���I�[�����x(2007�N)�ɂ́u�T�C�����E�K�[���v(The Siren-Girl�App.178�`199)�Ƃ��������b�����߂��Ă���B�b�҂̓��[���V���X�̃V�h�j�[�E�W���[�t�ŁA1990�N�S��18���ɕ��������̂ł���B�b����y�ł����邱���̒n��ł́A�I�݂Ȍ��肪�A�Œ肵���̘b�łȂ��A�Ǝ��ɘb��l�X�ɕ�������̂ł���B�W���[�t�̘b���A���낢��Șb�̗v�f���q�����킹�Č���Ă���B�ŏ��́u�������Ȃ�{���j�v�r���Łu�����̏��́v�Ō�́u���ɉB�����S���v�Ƒ傫���R�̃^�C�v�̘b�����Ȃ����Ă���B
�@�S�͎̂�҂��T�C�����̖���{���o����������Ƃ����b�ł��邪�A���[�͕s���̋��t�����q�������o�������ɊC�̐�����L��������Ƃ������̂ł���B���q�͊C�̏�ʼn��s���Ȃ���炵�Ă������A��Ȗ�ȒN�����ɐQ�Ă��Ęr���ɂ��Ȃ�B�ꎞ�n��ɋA���ăi�C�t�ƃ}�b�`���ꔠ��ɓ����B�C�ɖ߂�����҂́A�����A�Q�Ȃ��ňÍ��̒��ɉ�������Ă��āA���ɉ��҂�������ė������Ƀ}�b�`���C��B�T�C�����̖��Ɗm�F�����r�[�A��͏�������A��҂͒n��Ɉ�l�߂����B�����čs���r���ŁA�l�����ǂ���������悢���l�������˂Ă��郉�C�I���A���V�A�A���ɏo��B��҂��i�C�t�Ő蕪�����̂����ӂ����R�C�́A���ꂼ��̓����̎p�ɕϐg�ł���H��q�Q��^����B��҂͕��������A�R�r�̐��b�𐳂����ł�����A���������ƕP�����Ƃ����G���ڂɂ���B���܂ŁA�R�r�͐X�̃��C�I���ɐH�ׂ��Ă����̂ł���B�R�r�̐��b�W�ɂȂ�����҂́A���C�I���ɕϐg����͂��g�������ɋ߂����Ȃ��A�Ō�ɕP�̐ڕ��̗͂ŐX�̃��C�I�������ނ���B�̗��s�����炭�P�\���Ă��炢�A��҂̓T�C�����̖���T��������B�K�˂��Ă����́A���e�̃��C�I���Ɏ��ꂽ��ɏZ��ł����B�A���ɕϐg���Đ������A���e�̃��C�I�����S�����B���Ă���閧���o���A�R�r��H�ׂĂ����X�̃��C�I���̑̂ɐ��ރ��V�̒��ɉB���������A���̃��C�I���̊z�Ŋ���A����D�����Ƃ��ł��邱�Ƃ��o���B���@�̗͂œ����ʂ�������҂ɑ��A�����E���ꂽ�T�C�����̖��͓{��A�܂������Ƌ��ɏ���������B�����Ƃ̌�������߁A�����g�Ȃ�Ŏ�҂̓T�C�����̖���{�����𑱂���B�����s��Ŗ�ǂ��o�c���Ă��邱�Ƃ�m��A�݂��ڂ炵����҂͖K�˂čs���B��҂̈�r����m�������́A�T�C�����ł��邱�Ƃ�邵�Ă��ꂽ��Ƃ��������Ō����ɓ��ӂ���B�V�h�j�[�E�W���Z�t�͍H��̒��x�݂ɓ����ɘb�������肷����肾���A���̃T�C�����̖��̘b�͂������ɒ����̂ŁA����̍Ղ�Ȃǂɐ����ɕ����Ęb�����肷�郌�p�[�g���[�ł���B�T�C�������������t�̓n�C�`�Ɠ��l�N���I�[����Lasiren�ł���B
�@�n�����j���C�̏���(The Queen of the Sea)��Ԃŕ߂炦�A�������銷���Ɋ肢���������@�̕i����ɓ����Ƃ����b���A���[�E�w�A�����O�́w���ƌ��x�Ɏ��^����Ă���B�Z�C�V�F���ō̏W�����b�ŁA���������͂��̓x�ɖ��̖��t���e�̏������x�������̂����A�O�x�ړ������Ƃ��N���悤�Ƃ������́A�{���̏��L�҂ɗL���ɓ����A�R�̕�����߂��K���ɂȂ�B
�@�A�t���J�e�n�̐��̐���͐��������݂��A���ꂼ���c�����邱�Ƃ͍���ł��邪�A�t�����N�E�E�B���b�g���w�A�t���J���p�@�����Łx(1993�N)�ɂ��I�g�{(Otobo)�Ƃ������삪�Љ��Ă����B�j�W�F�[���E�f���^�̃J���o���l�̐���I�g�{�̓J�o�Ɛl�Ԃ̗v�f�������A�U���I�Ȑ��i�Œm����B�J���o���̐l�X�́A�傫�ȖڂⒷ���@�ŕ\�����ꂽ����̉��ʂ�D�w���������邱�Ƃ�����ł���B�Y�܂��q���̎p�ɉe�����邱�Ƃ�����Ă̂��Ƃł���B����̑��͈Â���_�Ɏ��߁A���i�͌����Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�x��̎����A�I�g�{�͓���ɍڂ����A���V�≎�̓��W���ň͂܂�Ă��āA��������Ɍ������Đ������A�l�̖ڂɐG��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�����x���͖\�͓I�ɂȂ�A�ϋq�⎩�g�����������邱�Ƃ�����B�I�g�{�͒j���I�Ȑ��̐���ł��邪�A���̃}�~�E���^�ƌĂ�鏗���̐��̐��Ɋ֘A����e�n�̖��̂������t���邱�Ƃ́A�܂�����ɂ��悤�B
�����@�G
�@ �@
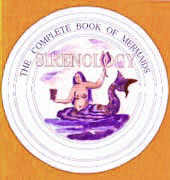
�@�����E�O�E�m�c�J�C�Y���E�ߊl�̕ŋߎl���������B2009�N11��20���A���������]�s���ۊ֒���4.3m�̌́A12��15���ɂ�3.96m�̃����E�O�E�m�c�J�C���x�R�������s�̊C�݂ɕY�����Ă���i�Ƃ���YOMIURI ONLINE�j�B2010�N�ƂȂ��āA�P���X���A���茧���ˎs��v�ے��K�m�Y��3.8m�̗Y�̂���u�ԂɊ|����A��\�㓇�����ق̑吅����34���Ԑ������p�����J���ꂽ(����V��)�B�P��10���ɂ͕��䌧���l����K�̊C�݂ɖ�4m�̃����E�O�E�m�c�J�C���Y�����A�Ԃ��Ȃ����S����(����V��)�B2008�N�̕�ꂩ��V�N�ɂ����Ă��A12��10��(���茧�Δn�C���A4.1m�A�C�ʕY���A���C�p�[���V�[���]�[�g)�A12��24��(�X���O���l�A���`�A1.5m�A�Y��)�A1��8��(�������o�_�s��В��n�z�k�A��̕l�A3.5m,���[�Y��)�A1��20���i���䌧�։�s�������A�����C������A3.63m�A�Y���A���䌧���Y�������j1��22��(�X�s�A�����p�A3.94m�A�i�}�R���̃_�C�o�[�����̂��A��œ˂��ĕߊl�A������)�A2��8��(��錧�g�c���A��|�C�݁A2.81m�A�Y���A���������)�ƁA�e�n�Ń����E�O�E�m�c�J�C�ߊl�̃j���[�X����ꂽ�B
�@�l�b�g�̕��y�Œn���̃j���[�X���e�ՂɌ����ł���̂ŁA�����E�O�E�m�c�J�C�Ɋւ��Ă������������邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����E�O�E�m�c�J�C���A�t�N�W�{�Ƃ��Đ����قȂǂɓW�����A�W�q��}�鎎�݂��e�n�ōs���Ă���B�ŐV�̕x�R���̏ꍇ�ł��A���Ð����ق��u�P�[�X��p�ӂ��ĕW�{�W���������v�i�ǔ��V���j�A�u�M�d�ȕW�{�Ƃ��ēW������\��v�i�k���{�V���j�A�u�W���ɂ��č���A�����v�iNHK�x�R�̃j���[�X�j�Ƃ��Ă���B���]�s�ł��s���u�W�{�ɂł��邩�����������v�i�ǔ��V���j�A�u�͂������́A10�N�x�����\�Z�Ŗ�450���~��g�݁A��t���s��s�̐��Ǝ҂ɔ�������B10�J�����x������Ƃ���A�W�������̂�11�N2���ɂȂ肻���v�i�����V���j�Ƃ̕�����B��\�㓇�����ٓ�����ɂ́A2002�N�ɕ��ˎs�x���ŕߊl���ꂽ4m�̃����E�O�E�m�c�J�C�������W������Ă���B
�@���{�̐l���������E�O�E�m�c�J�C���҂̈�l�ɐV����w���_�����{�ԋ`��(1930�`)�����邱�Ƃ͊��ɕ��B�u���{�C�����v��11��(2005.10.1)�ɖ{�Ԃ̌����u���{�×��̐l���A�����E�O�E�m�c�J�C�̐����w�v���ڂ��Ă���(pp.126�`127)�B�{�Ԃ́u�����E�O�E�m�c�J�C�����l���ɂȂ���ꂽ�����ł��邱�Ƃ��A�ŏ��Ɏw�E�����̂́A��喼�_�����ł��������c�b���Y�ł���v�Əq�ׁA�����E�O�E�m�c�J�C�̒n�於�Ƃ��āu�{�������v�E�u�c�ы��v�i��p�E�����j�A�u�T���J���`�[�v(���N)�A�u�Ԋ@�v(�x�R�p)�A�u�V���^�L�v�i����j�Aoarfish�Eribbonfish(�p��)�ARiemenfisch(�h�C�c��)�������Ă���B���ފw�Җ{�Ԃ́u���҂́A������ɕY��������ߊl���ꂽ�肵�������E�O�E�m�c�J�C��ߎ���̃T�P�K�V���A�A�J�i�}�_(�n�`�X��������)�Ȃǂ̐��B�B�⑼�̊튯�g�D���A�������ɂ���Ċ@�𑱂��Ă����̂ŁA�����̌��ʂ��{��̐������l���������v�ƕ��͂�����ł���B�{�Ԃ͎t���⋱��(1887�`1965)�̌��Ƃ��āu��p�≫��ł́A�W���S����l��������`���͑��݂��Ȃ������v�Ɠ`���Ă��邪�A�ǂ��ł��낤���B�m���ɁA�����w�ҁA�x�c�g�Y(1899�`2001)�����p�����ɏ�i�W����(1885�`1972)�̌��ɂ́u�l���͎ł͂Ȃ��v�Ƃ��邪�A����₻��ȓ�̒n��̐l��杂̓W���S���������W���Ă��Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��ł��낤�B�����āA�l�����W���S�����͂��̓��ۂ͖��ł��邪�A�l�������j�ɂ����Č��y����Ă������Ƃ͎����ł���A�����j����鎞�ɂ͔������Ȃ��̈�ł���B
�@�����ɂ�����l�̃W���S�����l�����̈�w�E���w���m������B���s��w�Ŕ������w���u������������(1875�`1932)�ł���B������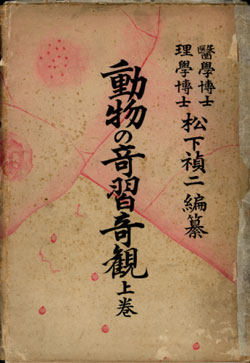 �[�̒��w�����̊�K��ρx�㊪(�ۊw����ЁA1913.11.1)pp.94�`101�u�攪�́@�l���v�����Ă݂悤�B�����o���́u�×����Ԃɐl���Ɩ��Â��锼�l�����̓�������ƌ��B�ӂ���ܘ_���m�̖ϑz�ɉ߂��Ȃ��̂Ŏz���̔@���z������ꂽ�����͎A�C��(�}�i�c�X)
�A�C�^�̗ނł���v�ƂȂ��Ă���B�����āu���@�C�̂���(����)����v�B��A�t���J�A�P�[�v�^�E���ߊC�ŕߊl���ꂽ���̊炪�u����l�̊�ɗގ��v���Ă���̂ŁA�p���l�́u�I�[���h�}���@�I�t�@�[�[�@�V�[(�C�̉�)�v�Ɩ������A�藎�Ƃ������̓��ɃV���N�n�b�g��킹�A�a�m�̕������������Ƃ����z�������B�l�Ɏ������Ƃ������ƂŁA����(1912�N)�b��ɂȂ������̋��́A�����(1898�`1985)�w�����d��杁x�i�{�����ŁA1926�N�B�L�����[�ŁA1979�N�B�������ɔŁA2006�N�j�́u�l���v�̍��ł����グ���A����́u���ނ̌�F���l���`���̋N���ƂȂ����낤�v�Əq�ׂĂ���B
�[�̒��w�����̊�K��ρx�㊪(�ۊw����ЁA1913.11.1)pp.94�`101�u�攪�́@�l���v�����Ă݂悤�B�����o���́u�×����Ԃɐl���Ɩ��Â��锼�l�����̓�������ƌ��B�ӂ���ܘ_���m�̖ϑz�ɉ߂��Ȃ��̂Ŏz���̔@���z������ꂽ�����͎A�C��(�}�i�c�X)
�A�C�^�̗ނł���v�ƂȂ��Ă���B�����āu���@�C�̂���(����)����v�B��A�t���J�A�P�[�v�^�E���ߊC�ŕߊl���ꂽ���̊炪�u����l�̊�ɗގ��v���Ă���̂ŁA�p���l�́u�I�[���h�}���@�I�t�@�[�[�@�V�[(�C�̉�)�v�Ɩ������A�藎�Ƃ������̓��ɃV���N�n�b�g��킹�A�a�m�̕������������Ƃ����z�������B�l�Ɏ������Ƃ������ƂŁA����(1912�N)�b��ɂȂ������̋��́A�����(1898�`1985)�w�����d��杁x�i�{�����ŁA1926�N�B�L�����[�ŁA1979�N�B�������ɔŁA2006�N�j�́u�l���v�̍��ł����グ���A����́u���ނ̌�F���l���`���̋N���ƂȂ����낤�v�Əq�ׂĂ���B
�@�����̑���u�@Halicore dugong�v(pp.95�`96)�ł���B���̕����͍���}���فA�ߑ�f�W�^�����C�u�����[�ł͌��łɂȂ��Ă���̂ŁA�u�v���S�������p���悤�B
�@�͗����ߊC��ɔ��d�R�Q�����߂ɑ����������邪�g�C�A��x�m�A���������̉��݂ɂ����ċ��问���̕����ɂăU���m�C���Ɖ]�ӌ`��͊C��(������)�Ɏ���铒����ڈȏ�ɒB�����͚����@�E�͏��������E�����тē����̑O�[�ɋ߂��ʂ��O���Ɍ��ĊJ�����O�����ċ�����͏�������粂ɂ͏_��Ȃ�т��O�����ڂ͍ł����������k�͂Ȃ��畆�͋ɂ߂Ċ����ŒZ�т�a�����Ă���w�ʂ͊D�F�ŕ����ʂ͔��F�ł��錨�͍��E�ɒ���
�Ă͋����ɚ����c�ꂽ���̓��[��L�������ɂĂ͎O�l�����t���ЂėV�j���邪���ɚM������ۂɂ͑O���ɂĎ���������̓��Ǝ��Ȃ̓��Ƃ����ɐ���ɏo���Ȃ�����̂ɉ����V��]�߂Β��x�l�Ԃ��V�j���ċ���l�Ɍ����@��{�ɂ͒���Ȃ�厕�����đ����E�����ɂ͉P�����O��������O���͕h����Ȃ��ǂ��㎈�Ȃ����h�͐����ɝ����ċ����ɌQ�����ĊC���y�уA�}���ނ̔@���C����H�ӎ̓��͔����ň���l�͋����Ɏ��ċ���Ɖ]�Б��̐l�͓ؓ��ɋ߂���������Ɖ]�ӎ��b�����������ŋv�����ۑ����邱�Ƃ��o����є�͎�X�̗p�ɋ������̎��������獟�����̔�y�����v���Ƃ��Ďx�߂֑����Ɖ]��
�u��O�@�C�� �@Manatus�v(pp.96�`97)�̍ŏ��̂Q�s���������Ă���̂ŁA���p����B
�@�ɍ��������M�������ł��ċ��������Ȃ��铋�͎�����債�����͎����c�L���ɂ��Ĕ��h�͚��邢铒����ʔ��ڈʂ��Ĕ畆�͈Ê��F��悵�C�����̑��̊C����H���ċ���h����Ȃ���O�����Ȃėc����������̂ݐ��ʏ�ɘI�o����l�͐���w�l�̏�Ɏ��ċ��鐫�������ŖԂɂĕ߂֖��͐ɒǂ����݂Ėo�E����̂ł��鎞�Ƃ��Ă͑����Q���Ȃ��ĉ͂�k�鍟�ۂɂ͘V���擪�ƂȂ葽���̖ĎҔV�ɏ]�Зc���͑��̒��Ԃɕی삹���R�̂ł��鉢�B�ɂĂ��C��Women of the Sea�ƈٖ������ċ��郁�L�V�R�p�y��ē����̐�C���ɃA�t���J�̐����C�݂ɎY���V��ߊl����ɂ͑������ċz��ਂ߂ɊC�ʂɕ����オ���҂��Ėo�E����̂Ő�Î����E���ΗY�y�c���͔V��q�˂ċ��炴��ɂ��F�E�C�����R�̂ł���
�@����厖�ɂ���K���𗘗p���ČQ��S�̂�ߊl����Ƃ����L�q�́A����i(1973�`)���X�e���[�J�C�M���E�ɂ��ď����Ă���R�����ɂ�����ꂽ�B�u�X�e���[�_�C�J�C�M���E�ɂ́A���Ԃ������Ă���Ə����悤�Ƃ��āA��������̒��Ԃ��W�܂��Ă���Ƃ����K�����������B�Ƃ��ɏ��������̂����X�̏ꍇ�́A���̏K���������������v�i�w��ł�����ȓ����x�A�u�b�N�}���ЁA2009.12.10�Ap.163�A�u�x�[�����O�C�̔ߌ��v�j�B
�@�����́u��l�@�C�^�@Phoca vitulina�v�A�u��܁@�C�ہ@Trichechus rosmarus�v�Ɓu�l���v�̑���̉��ɋL�q���Ă���B�C�ۂ̓Z�C�E�`�̂��Ƃł���B�����́w�����̊�K��ρx�͎�ɁuMarvels of the Univers�v�Ɉˋ����ċ��������������ȓ����̘b���I�сA�ێ���Ђ̎Ј��ɑ�w�̌������Ō��q�M�L�����Ă܂Ƃ߂����̂ł���B�㊪�ɂ͌Ð����̋L�q������A��́u���̈̊ρv�ɂ͑z�������ł��间�̂��Ƃł͂Ȃ��A�ڈ旴(Atlantosaur)�A�间(Allosaur)�A�p��(Ceratosaur)�A���{��(Duck-Billed-Dinasaur)�A�a�v���h�N�X(Diplodocus)�A�X�e�S�]�[��(Stegosaur)�A�i�I�]�[��(Naosaur)�A�G���I�v(Eryops)�A����ь����̃g�J�Q�ނ̐����Ɛ}������B��\�͎͂n�c���B�����ɂ��ۂ̑c��A�҂̑c��A�����A����(Plesiosaur)�A�����Ղ�����Ă���B
�@��������͎F���̐��܂�A�h�C�c�Ɏ���w���A��w�A�ۊw�A���A���w�A�����w�A�N�w���w�сA��w���m�A�N�w���m�̊w�ʂċA���B����36�N�A���s�鍑��w��ȑ�w�����ƂȂ�q���w���u���A�吳5�N�ȍ~�͔������w��S�������B�吳9�N�A��w�����������Ď��������I�o�̑�c�m�ƂȂ�A���a7�N�v�����B�w�Ɖu�w�u�`�x�w���f�f�w�x�w�`���a�e�_�x�w�V����q���x�Ȃǂ̒�������B�܂��w�����̊�K��ρx�̔��s���A�ۊw����Ђ͖���37�N�T���ȍ~�A�G���u�q���w�y�ۊw����v�s���A�����́u���{�������w��G���v�u���{�������w�a���w�G���v���o�āA����28�N12���n���́u�ۊw�G���v�ȂǂƏ��a19�N�V����������A���s�́u���{�ۊw�G���v�ƂȂ��Ă���B�ۊw����Ђ̒P�s�{�͎�ɏ����̂��̂ł������B
�@
�@�܂���l�A�W���S�����l�������Љ��Ȋw�҂�����B�_�ސ쎕�ȑ�w�����߂��A���w�E��w���m�A�L�c���C(�Ƃ悾����̂ԁA1909�`1999)�ł���B�n�X�̌����Œm����i�w�n�X�̎��̌����x1967�N�A�w�n�X�̌����x1981�N�A�w�n�X�_���W�x1987�N�j�L�c�́A���̒��w�����w�G�b�x(�������A1984.5.10)�Ɂu�l���̓`���Ƃ��̐��́vpp.117�`126�����߂Ă���B���ˉw�O�̐l��������n�܂镶�͂ɂ́u�l���̓`���v�u���m�̐l���v�u�l���̐��́v�u�W���S���v�u����̐l���v�u��̓��̐l���v�u���H�����قŎ��Y�̌�ځv�̌��o��������B�L�c�͐l���`���̂��ƂƂȂ��Ă�����̂ɋ��`�̐���̐l�i���A�C�������̔����������A�C�������Ƃ��Ă̓W���S�����ł��L�͎�����Ă���Ƃ���B�u���̊�͂�����Ƃ݂�ƃu�^���T���A���邢�͐l�Ԃɂ��������Ă���悤�����A��e�W���S���͑O���Ŏq��������ē������܂��邱�Ƃ�����B���̐���������ƃu�^�̂悤�ȁA���邢�͐l�Ԃ̗c���̂悤�Ȑ�������悤�ł���B��������l���Ƃ������t�����܂ꂽ���̂Ǝv����v�Əq�ׁA���̑��̉\���Ƃ��āA�A�U���V�A�I�b�g�Z�C�A�A�V�J�̕h�r�ށA���ނƂ��ăT���������A�u�T���V���E�E�I���܂��l���ٖ̈��ƌ����邱�Ƃ�����v�Ƃ��q�ׁA�u���ɃT���V���E�E�I��l���Ƃ�Ԃ��Ƃ́A���̖��������̂��Ƃ��Ȃ���t��������̂ł��낤�v�Ƃ��Ă���B���_�I�ɂ́u�l���̐��̂Ƃ��čl������̂́A��͂�W���S�����ł��L�͂ŁA�I�b�g�Z�C�A�A�U���V�Ȃǂ��A�Ƃ��ɂ͌�F����邱�Ƃ����낤�v�Əq�ׂĂ���B�L�c�̒Z���͏펯�I�ȕ��������邪�A���p����Ă��鎑���ɂ͋����[���_������B
�@�p���I�A�R���[�����̐l���ɂȂ������A�L�㍲���̕S�ьܕ��q���ߊl�����u�������l���v�A���S��u��Ɋւ��Ă��ዷ��łȂ��A�B�l�̘b���Љ�Ă���B���m�̓`���Ƃ��Ă̓_�S���A�I�A���l�X�A�T�C�����A���[�����C�ƕ��ʂɐi�݂Ȃ���A�G�X�g�j�A�̓`���������Ă���B���d�R�ߊC�ł̂��ẴW���S�����A�X���o���ݏZ�̉���o�g�҂̃W���S�������L�A�g���X�C���ł̃W���S�����ƁA�Z���L���̒��ɖL�c�̐l�������T���̐Ղ��M����B
�@�L�c�����Ă��鍲���̕S�ьܕ��q�Ɛl���̘b�͓��قȎ����Ƃ��āA�����̐l�������ɓo�ꂵ�Ă���b�ł���B����ӎ��́u���z�I�f���Q�v�ɐV���@�����Ƃ��ĉ|�c���l�u�S�ьܕ��q�v(�u���y�����v��1����10���A�吳2�N12��)����Ă���(2000�N02��12��)�B�c�ӌ�́u�o�T�s���ň��p����邱�Ƃ������b�v(���̂Ɛl�Ԃ̕����j143�w�l���x�Ap.105)�Ƃ��Ă��邪�A�|�c���l���ł��Â��Љ�҂ł���Ǝv����B�����Ő���g�A���䎇�_(1888�`1954)�Ȃǂ���O�ɏ����c���Ă���B�|�c�̘b�́A�S�ьܕ��q���ԂŐl����߂炦�����A�l���͕ꂪ�a�C�ł���Ƃ������ŋ����Ă���Ƃ��������̂ŁA����ĕ����Ă�������A�l���͐U��Ԃ肴�܂Ɂu�ܕ��q�͔n�������A���w��{���痼�X�X�v�ƌ����Ē��̂ŁA�����ł͌��i�N�_���A���g�̗\���b�j�͐^�����A�l���͉R�������Ɠ`���Ă���A�Ƃ������̂ł���B
�@�b���Z���̂Łu���w��{���痼�v�ƌ������Ӗ����킩��ɂ����B���ʂ́A�l���Ƃ������݂��M�d�ŁA���w�ł������痼�ɒl����Ɖ��߂��邪�A���w�̎�����͌ܕ��q�ŁA�痼�ɒl����l�����w�ʼng�����Ă��̂ɁA�����ɂ���Ă݂��݂��������Ƃ��l������B���̒Z���b���킩��₷�����F�����̂���������ł���B���́u�����̐l���v�ɂ́A�l�����v�͔��őł��ŁA�ܕ��q�̉Ƃɍs���A�V��Ɩ����삦�ɋꂵ�ނƑi����B�ܕ��q�͏t�H����������ĊC���q�˂�悤�ɂ�����Ɛ�������B�l���́A����ł͉Ƒ��ɕʂ�������Ă���ƌ������̂ŁA�ܕ��q�͎莝���̏��K���������Ă�����B�l���́u�ܕ��q�̃o�J�ҁA���͖̑̂��痼�A���w��{�ł��痼���v�ƚ}�����B�w��������̗d�����T�x(�������o�ŁA1981.8.30�App.20�`21)�ɂ���b�ł���B�Y�����Ă���F�ʉ�̓x�b�N�����́u�g�̋Y��v���A�����W�����A���ŌQ��Ă���j���A�y�юq���̐l�������ł���B�Ȃ����̓����ɂ́u�ዷ�̐l���v(pp.68�`69)�A�u�����̐l���v(pp.70�`71)������A�X�Ɂw��������̑��d�����T�x(���������X�A1984.7.15)�ɂ́u�C���m�v(pp.190�`191)�A�u�U��(�l��)�v(pp.192�`193)���ڂ��Ă���B
�@���̘b���قڂ��̂܂Љ�Ă���̂�����@�ł���i�w�`���ƌ����߂��l���x�A1983.8.31�Ap.133�A�u�����̐l���Ƌ��t�v�j�B�o�T�̖��L�͂Ȃ����A�����̓`���Ƃ��ďЉ�Ă���͍̂��ԗǕF(�w�l���̌n���@�������C�̏Z�l�����x�A�܌����[�A1999.1.28�Ap.138)�B�Q�ƕ����͋��䎇�_�ł��낤���B�����u�ܕ��q�v�Ƃ��������Ă����l�����u�S�ьܕ��q�v�Ɩ��L����A�l�������Ԃ����C����u���̖��v(���͒P�Ɂu���̕��v�Ƃ��Ă���)�Ɠ`���Ă���B�|�c�A����́u���菼�̍�v�ƌ����Ă���B�c�ӌ�́u�S�ьܕ��q�v�Ɩ��L���Ă��邪�A�u���̔g�ԁv�u�킽���̑̂͐疜���A�w��{�ł��痼�͂����v�Ɛ��̘b�Ɉˋ������悤�ȕ���������B
�@�x�c�g�Y�͍����̘b�͒m��Ȃ������悤�ł��邪�A��c���ꂪ���䏬�E�q�傩�畷�����b�Ƃ��āu�́A���O�Y�Ƃ����n�R�ȋ��t���g�ɏZ��ł������A�邵�ɍ����Đl�̂��܂�s���ʓ�֒ނ�ɍs������A��ȋ���ނ�グ���B���ꂪ�l�Ԃ̖���������B�}�炵���̂ŕ����Ă������A�i�A�����̒��O�Y�A�w��{�Ő�іځj�ƈ����������Ȃ��瓦���Ă������v�Ƃ������̂������ň��p���Ă���(�w�C�̐_�M�̌����x���A�����[�A1979.6.25�Ap.345)�B��c�́w���H�u���̖����@�u���l�̐������T�x(���H�u������������A1970)�ɂ́u���O�Y������������ނ�グ��ƁA�l�Ԃ̐��������āA������ɒ��O�Y�̈����������̂ŁA�����Ă�鎞�A�n�R�����Ȃǂ���̂���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA���O�Y���������������A���̋��͏����Ă������Ƃ������v�Ƃ����b������B�x�c�́u�ǂ��������т����b�Ƃ͍l���ɂ����v�Ƃ��āA�S�̂�l�����[杂Ƃ��ĂƂ炦�A���������l���������������[�Ƃ��Ă���ė��āA���O�Y�̃^�u�[�N�Ƃɂ���ĊC�ɖ߂镔���������Ă��܂����ƍl�����B�u�w��{�Ő�іڂ̋��𐅗g���o�����Z��^�����v�Ƃ������t�ŁA�����ł͂Ȃ��Ɩx�c�͌����Ă���B�x�c�������̘b���Q�Ƃ�����A�����ȕ����Ɖ��߂͂��Ȃ������Ǝv���B�u���̘b�����p���Ă���̂��A���ɂ͈��m��ȑ�w�����ł�������U�w�ҋg����v(1932�`)�ł���(�w�l���̓����������x�A�V���فA1998.10.5�Ap.68) �B�c�ӂ͎u���̘b���u�l���̘b(�O�d)�v�Ƃ��āu�����̋��t�Ɛl��(�啪)�v�̒��O�Ɍf���Ă���B
�@�w���{�̘b�ʊρx��15��(�O�d�E����E���E�ޗǁE�a�̎R)p.185�ɂ͎u���̏�����������u�l���̈����v�Ƃ����b�����^����Ă���B���O�Y���ߍ]�֖̌Ԃ��g���ɍs�������̂��ƂƂ��Č���Ă���B���x���Ԃɓ����Ďז������l�����A���̓x�ɕ����Ă������A���܂肽�т��тȂ̂Ŏ����ċA�낤�Ƃ�����A�l�������Ԃ����B�����i���`�t�X�j�ɜ�点��A�n�R�ɂ���A�Ɖ��~��b�����ɂ���A�Ȃǂ��܂�̂��ƂȂ̂ŁA�����̂Ă���A�l���́u�ƂĂ��n�R�Ȓ��O�Y�A���w��{���痼�痼�v�ƁA���w���o���Ȃ��璾��ł������B
�@�l���̌��t�́A�����̉��l�����w��{�ł��痼���ƁA�͂����茾���Ă���B�܂��A�l���̌��t���a�C��n�R�Ƃ��������ꂩ�����ė���Г�ŁA�A�}�r�G�I�ɂ����߂ł��A���w��{���������ʼn���ł���Ƃ������Ă���悤�ɂ��v���Ă��܂��B���t��������̗\���ƕx�A�ߊl�i�ގ��j����j���̑��݂����邪���ǐl���͊C�ɋA��A�ȂǗ\���Ɛ}���̃A�}�r�G(�A�}�r�R)�����ƂƂ����l�X���A�]�ˌ�����疾�������ɂ����Ċ����������Ƃ̔����Ȏc�����A���̎u���ƍ����ɌǗ������b�ɂ���̂ł��낤���B���ꂾ���̎����ł͉��������Ȃ����A����Ȃ��̂����ׂ��ԓx�Ȃ̂ł��낤�B�x�c���l�����[���杂ɓ���݂����邠�܂�A�u���̘b�ɑz���������������悤�ɁA�A�}�r�G�E�_�ЕP�Ɉ�����邠�܂�A���e�𓊉e���������̂�������Ȃ��B���S��u��Ɛl�����[�ȊO�́A���܂�ɐl���̘b�E�`�����_�Ƃ��ČǗ����Ă�����{�̌���ł͗��_�͓W�J���ɂ����B
�@�x�c�̐l���_�͎�ɉ���̎�������グ�Ă���̂ŁA��ɏ�̌������邪�A��͂�W���S���i�W�����A�C�n�j�Ɗ֘A�����b�����グ���Ă���B�W���S���̘̐b��������X�ɓ�ɒH���Ă݂悤�B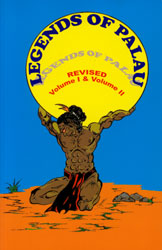
�@�W���[���E�G�Z�x�C�E�e�����M���w�p���I�̓`���x(2004�N)pp.50�`51�u�p���I���̐l���`���v�́A�v���������ɔD�P���������l�����W���S���ɂȂ����Ƃ����b���Љ�Ă���B�N�������ƁA���̕�ɉ�����ꂽ�����R���[�����̃k�Q���G���u���ŕn������炵�Ă����B�������������ɔD�P���Ă��邱�Ƃ�m������́A����ȏ�̕s���_������邽�߂ɔD�w�ɉȂ���ꂽ�H�ו��̃^�u�[�����悤���������n�����B���̐Ԃ������Y��͂܂��ʂ̐H���^�u�[�����������A���̈�P�A���̎��͖��̍D���ł������̂ŁA�ꂪ�O�o���Ă���ԂɗU�f�ɕ����ĐH�ׂĂ��܂����B��Ƀ^�u�[�N�Ƃ��C�t���ꂽ���́A���낵���ŊC�ɔ�э��݁A���ւƉj���i�߂��B��͖߂��Ă���悤���肵�����A���͎���Ƀ��Z�L���E(�W���S��)�Ɏp��ς��Ă������B����������������Ȃ����ɂ������ޕ�e�����Z�L���E�͌ċz�̓x�Ɍ��Ԃ��Ă������A���Ɏp�������Ȃ��قlj��ɉj�������Ă��܂����B��e�͏����Ă��������Ɍ������A�ς��ʈ���ƁA���̎v���o�ɃN���N(�ݕ��ƂȂ�r�[�Y�̈��)����邱�Ƃ�`�����B���̃N���N�͌������閺�ɁA���e�ɏ]�����Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂƍ����Ƃ��ēn�����̂ƂȂ����B�e�����M���͕��͂̍Ō�Ƀp���I�̃W���S���̐�������200�ȉ��ŁA�V�����͑̒�100cm�A�̏d25kg(���b��3m�^500kg)�ŁA�V�N�ԕ�e�Ƌ��ɍs�����A15�N�Ő��n����ƋL���Ă���B�W���S���͕ߊl�����ƁA�܂𗬂��Ƃ��`���Ă���(Legends of Palau�AJeRome EseBei Temengil�AMoonShadow Publications�A2004�App.50�`51�APalau island's fable mermaid)�B
�@�������V���S���ɂȂ����Ƃ����b�̓p�v�A�E�j���[�M�j�A�A�~�����p�n���ł�����Ă���(�w���E�̖��b�x��23���A�p�v�A�E�j���[�M�j�A�A���쒴��A���傤�����A1978.12.10�App.110�`114�A�u�C���W���S���v)�B�̎ւ��l�Ԃ̖����Y�݁A�����������͎�҂ƌ��������B���͕�e���ւł��邱�Ƃ�v�ɉB���Ă������A�₪�Ēj�̎q�����܂ꂽ�B���͕�e�̎ւɐH�����^�сA�q���̐��b�𗊂B������A�v�͎ւ��q���̑��ɂ���̂������A���Ŏւ̑̂��o���o���ɐ��Ă��܂����B�ώ����N�������Ƃ�m�����Ȃ́A���ɕ�ւ̖S�[���W�߁A���q�Ƌ��ɊC�ӂɍs���A�u��̂��߂Ɏ��̂��v�Ɖ̂��Ȃ��琅�ɒ���ł������B���̓W���S���ɂȂ�A�j�̎q�́u��F�̒W�����v�ɂȂ�A�l�Ԃ͂��̓�𒇊ԂƎv���A�����ĐH�ׂ��肵�Ȃ��B�̎ւ́u�h�{�i�v(���������)�ƌĂꐒ�߂��A�V���S���́u�߂��݂ɒ���ł���̂ŁA�[�C�ɂ����Z�܂Ȃ��v�ŁA�u�l�Ԃ̊�����A���̂悤�ȓ��[�����v�Ƃ�����B����̓��`���G���E�^�����g�B
�@ �}���A�E�c�E�R���l���ҁw�t�B���s���̖��b�x(�y�ЁA1997.7.25)pp.148�`151�u�l���̓`���v�̓W���S���̘b�ł͂Ȃ��B���_����������邩���ɁA���܂�Ă���q��������N��ɂȂ�����v������Ƃ������[���b�p�̘̐b�̗ޘb�Ǝv����B�D�P�����Ȃ��T�o�q�[(����A�W�A�C��Y�̐H�p���A�~���N�t�B�b�V��)��������H�ׂ�����̂ɍ������v�́A�T�o�q�[�̉��ɁA�q�����V�ɂȂ�����T�o�q�[�̍��ɘA��čs���Ƃ��������ŁA��������͂��Ă��炤�����Ă��܂��B���܂�Ă����q�͏��̎q�ł��������A����͖̂ɂ��悤�Ƃ��Ė���l�ӂɋ߂Â��Ȃ��悤�ɂ����B������A�l�ӂɒ��i���^��ł����D������ė��āA�D��S�ɂ���ꂽ���̎q�͈�l�őD�ɋ߂Â��A��g�ɂ�����Ďp�������Ă��܂����B�Ό�������A�����̔ӂɁA�N�V�������e�̖ڂ̑O���A�����̐l�����������j���ōs�����B(���C�e�B�A�q�����S�X�s)
�}���A�E�c�E�R���l���ҁw�t�B���s���̖��b�x(�y�ЁA1997.7.25)pp.148�`151�u�l���̓`���v�̓W���S���̘b�ł͂Ȃ��B���_����������邩���ɁA���܂�Ă���q��������N��ɂȂ�����v������Ƃ������[���b�p�̘̐b�̗ޘb�Ǝv����B�D�P�����Ȃ��T�o�q�[(����A�W�A�C��Y�̐H�p���A�~���N�t�B�b�V��)��������H�ׂ�����̂ɍ������v�́A�T�o�q�[�̉��ɁA�q�����V�ɂȂ�����T�o�q�[�̍��ɘA��čs���Ƃ��������ŁA��������͂��Ă��炤�����Ă��܂��B���܂�Ă����q�͏��̎q�ł��������A����͖̂ɂ��悤�Ƃ��Ė���l�ӂɋ߂Â��Ȃ��悤�ɂ����B������A�l�ӂɒ��i���^��ł����D������ė��āA�D��S�ɂ���ꂽ���̎q�͈�l�őD�ɋ߂Â��A��g�ɂ�����Ďp�������Ă��܂����B�Ό�������A�����̔ӂɁA�N�V�������e�̖ڂ̑O���A�����̐l�����������j���ōs�����B(���C�e�B�A�q�����S�X�s)
�@�t�B���s���̊C�̏��_�A�}���V�i��(Amansinaya)���l�Ԃ̖��ł������B�C���D���ł������A�i���V�i���͊C����̌Ăт����Ő��ɓ��菗�_(�l��)�ƂȂ����B�C�ӂ̐l�X���܂����Ƃ�m��Ȃ��������A�삦�ƍb��B��ɋꂵ�ސl�X�Ɏ�p�t(catalonan)��ʂ��āA������蔲���ďM�邱�ƂƁA�ӂŖԂ����邱�Ƃ��������̂̓A�}���V�i���ł������B�^�K���O��Ɖp��\�L�̊G�{�A���E�W�j�E�G���@�X�R�^���A�z�Z�E�~�Q���E�e�q�h�^�G�A�w�A�}���V�i���@�C�̏��_�x(2007�N)�ɂ��B
�@�W���S���ɂ��Ă̐V���L���������E���Ă݂悤�B
����40�N�X��19���u�ǔ��V���v��R�ʁA�u�l���̓����@���\�ܓ��������E�ɂā@�o����l���͗��������d�R���̕��߂ɕ߂ւ��锍�����Ĉ���ڑ�̔n�ɋ߂��傢���ɂĊ�炵������Ȃ���[��L�����H�̏㉺�ɊJ��������̂Ȃ�Ƃ��Ӂv�B
�@���a16�N�P���W���u�ǔ��V���v������V�ʁA�u��m���燀�l�����@�_�o�I�ŕ߂炦���s�V�����̒��i�v�B�O�N12��13���A�t�B���s���A�~���_�i�I���_�o�I�̃_�^�A�I���C�݂œ��{�l���߂炦���V���S�����u�X�L�Ăɂ��ĉ������v�Ƒ�㏤�D�В��Ɉ��Ăɔ��l�߂ɂ��đ����Ă����Ƃ������e�B�߂炦�����{�l���ŏ��͋C�������������A�m�l�������ăX�L�Ă��ɂ��Ă݂��Ƃ���A�u���͖쒖�Ɏ��ĂȂ��Ȃ����������v�̂ŁA�c��̓���X�l�߂ɂ��đ������B
�@���̋L���̓W���S���łȂ��A�N�W���E�C���J�ނƎv����B
���a19�N�T���S���u�{���l�I�V���v��Q�ʁu�l�̂�����̓�C�̉����@�ߊl�́u�l���v����U�v�B�S��24���A�o���g�͂ŁA�����Qm�A�̏d60kg�A�Î��F�A�����^�́u�l���v��ߊl�����̂ŁA�������̎R�{���m����U�����B�O���Ɂu�w�A���A���h�v�������u�~�̔@�����𐁂��������[�v�ɂ���u���͐l�Ԃ̎��ɗގ��v���Ă���Ƃ���̂ŃW���S���ł͂Ȃ��B
�@�{���l�I(�J���}���^��)���̒W����ɂ̓J���S���h�E(�C�����W�C���J)���������Ă��邪�A����̓��R���쐅��ł������A�u�l���v�`���ƌ��т����Ƃ�����B�����P�V�u�l���`���ƃS�[���h�E���b�V���v(�w���I�X�_�R���n�挤���x�A���R�q�E�������ҁA�߂���A2008.3.21�App.121�`130)�́A���I�X�A�T���@���i�P�[�g�����B���u���[�S�Ői�߂��Ă�����E���z�R�J���ƁA�v�����g�߂��Ɏc���ꂽ�����ȐX�Ɉ͂܂ꂽ���n�ɂ��Ă̏��_�ł���B���n�́u�l�����c�v�ƌĂ��ۑS�������ł���B�����̓��A�����A�����̌ØV���畷�����u�l���`���v���Љ�Ă���B��g�̐l���v�w���A�x�z�҂̑��q��A�ꋎ�����̂ŁA��p�҂��l����߂炦�A�R�[�q�A���i���V�ȃr���E���j�̖Ɍ��т����B��p�҂��Y�̐l����荏�݁A�����ɂ܂��U�炵���̂ŁA�u����Ƃ���ɐl���̗삪�h��v���ƂƂȂ����B�Ȃ̐l���́A�K���ɂ��������̂ŁA�@�������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂������A�����������邱�Ƃ��ł����B����ȗ��A��ɓ��鎞�͑傫�Ȑ����o���Ă͂����Ȃ��ƌ�����悤�ɂȂ����B�l�Ԃ��A�����ĂȂ��Ȃ����@�̂��Ƃ����Ă���Ǝv���A���l�������̐l��A�ꋎ���Ă��܂�����ł���B�l�������{�����Ɠ`�����Ă���ꏊ�ɂ́A�����ߍ��܂ꂽ�~�����c����Ă���B�J���S���h�E�͎��b�g�D�������̂��傫�ȁA�ۂ������������I�ȃC���J�Ȃ̂ŁA�u�@���������v�Ƃ����l���ɏd�Ȃ�Ǝv����B
�@���X�x�X�E�X���C�^�[(Liesbeth Sluiter�A1951�`)���A���R���E�E�H�b�`��A�w��Ȃ郁�R���A���̖L������I�ފJ���x(�߂���A199.5.17)�ɂ́A�u�C�����W�C���J�́u�l�ԋ��v�ƌĂ�A���[�Ə���������Ɛl�͌����v(p.65)�Ƃ���A�n�[�g�j���C���i���I�X�j�̑���(���n���X�[����)��������u�l�ԋ��v�̕�����Љ�Ă���B�́X�A�����ƃx�g�i���͗��A���A�n�k�Ɍ������A�l�X�͎��ɐ₦�A�����l�̓C���J�A�x�g�i���l�̓A�W�T�V�ɐ��܂�ς�����B�A�W�T�V�ƃC���J�͂悭��������ɂ��āA�l�Ԃɂ͊�Q���������A�����邽�߂ɐ����Ă���(p.76)�B�J���{�W�A�E���I�X�̍����n�т̋��t���A���E�V�[�z�[�C���܂��C���J�ƃA�W�T�V�̓`��������Ă���B�v�w�����Ń��R����������Ă��āA��ɒĂ��A�v�̓A�W�T�V�A�Ȃ̓C���J�ɐ��܂�ς�����Ƃ������̂ł���(p.86)�B���A���̓C���J�̎��͈��삩��q������閂�����ƂȂ�̂ŁA�u�P��3000�L�[�v(��S�h��)�v�Ŕ���邱�Ƃ�����ƌ����Ă���B
�@�A�t���J�嗤���C�݂̓W���S��������̐��[�ł���B�^���U�j�A�̃W���S�������閯������Ă���̂��A�C���[���E���C���[(�A���X�e���_����w�A��Ðl�ފw)�A�u�l���̎��ƃC���h�m�̐����I�A�d�v�ł���B�}�~�E���^�����̈�Ƃ��ăX���q���ꌗ�̐l���֘A�̐l�ފw������1999�N����2000�N�Ƀ^���U�j�A�ōs�����B�^���U�j�A�̃C�X�������k��nguva(�W���S���A�l��)�ɂ��Ă̘b�ɂ͈�ʓI�Șb�Ə@���I�ɔF�߂�ꂽ���P�b�̓������A�������}�^���U�j�A�v���}(CCM)�̊Ǘ��̉��ŕ�����蒲�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�l�����Ӗ����錾�t�ɂ�nguva�̑���samaki(��)-mtu(�l)������B�A�t���J���C�݂̃C���h�m�ɐ�������W���S���͐������炵�Ă��āA�^���U�j�A�ł͌��ݕS���ȉ��Ɛ�������Ă���B���C���[���ŏ��ɘb�����̂́A����A�W�A�o�g�҂̎q��(Muhindi)�Ń_���G�X�T���[���ɂ��ޔ�r�I�L���ȋ����o�o�E�t�@�q������ł������B20�N�O�A�o�o�E�t�@�q�������D���Ƃ��ă\���S�E�\���S���߂��ŋ������Ă��鎞�A�l����߂܂����B�㔼�g�͏����ŁA�����g�͋��A�����ÐF�̔��ŁA���̓A���u��C���h�l�̂悤�ɔ������F�����Ă��āA��������オ���Ă����B�l���̓X���q����Ŕ������̂��̂��Ƃ���Ă������A���̐l���̓R�[���������p���Ȃ���A�����ƎE�l�̍߂�Ƃ��ʂ悤�D���B�ɑi�����B�D�������͋c�_���d�˂����A���ǁA�l���͐l�ԂłȂ��̂�����E���Ă��߂ɂȂ炸�A�s��ō��������ƌ��܂����B�\���S�E�\���S���Ɋ�e����ƁA�����̐l�X���D���B�̍s������A�����ɂȂ����B�D���̂���҂͍��Ɍq����A����҂͓����瓦���o�����B�����C���[�̓o�o�E�t�@�q���ƐڐG�������A���̓x�Ƀ\���S�E�\���S���֍s�����Ƃ����߂�ꂽ�B�����ŁACCM�̋��̉��R�l�̔N�z�҂Ƀ\���S�E�\���S���Řb���@����B
�@�\���S�E�\���S���ł̍ŏ��̘b�́A�l�����@���ɂ��Đ��܂ꂽ���Ƃ������̂ł������B�Ȃ��l�����t�������B�Ⴂ���̍Ȃ͔D�P�������A������l�̍Ȃɏ�Ɏ��i�S������A�v�ɂ˂��蕨��v�����Ă����B�v�͉䖝�ł��Ȃ��Ȃ�A�v�w���܂��n�܂�A�Ⴂ�Ȃ͓{��ɂ܂����A�C�̕��֑����čs���A��э������Ƃ����B�v�͍Ȃ��j���Ȃ��̂�m���Ă����̂ŁA�~�߂悤�ƌ��ǂ������A�Ԃɍ���Ȃ������B�܂��A����b�ł́A�T���Ȗf�Տ����D�P�����Ȃ��D�ɏ���Ė{�y�ɂ���Ȃ̎��Ƃ�K��悤�Ƃ������̎��Ƃ��Ă���B�Ȃ͔�������ۂ��߂ɏ\���ȕ���v������Ȃ��ƕs���������n�߁A�v�͍Ȃ̘b�������Ă������A�{�����Ȃ͑D����C�ɐg�𓊂��Ă��܂����B�Ȃ͕v�������Ă������̂Ǝv���Ă������Ԃɍ���Ȃ������B���i�S�⏬���Ȏ����S�̂��߂ɁA����̖���e���ɂ������Ƃɓ{�����_�́A�����̏�����l���ɕς��Ă��܂����B���ꂪ�l���̋N���ł���B��̘b�̔D�w�͒j�̎q��s��ł��āA�l���ɕϐg���Ă��琔������ɒj�̐l�������܂ꂽ�B���l�ɂȂ����j�l���͕�ƌ�����āA�l���푰�̐��������Ă������B�ߐ[���l�Ԃ������Ɏp��ς�����Ƃ����b�͑�������A�R�[�����ɂ����ɕς���ꂽ��a���҂̘b������ƁA�\���S�E�\���S�̘V�l���͘b�����B
�@�����ŃW���S�����ɘb�͐i�ށB�W���S���̐��͌����������A�|���O�E�F����W���W�����A�\�}���K�̉��ł͖ڌ����邱�Ƃ��o����B�W���S���̓����͑S�g�ɖт������A�l�Ԃ̏����̂悤�ȋ������Ă��āA�C����g������ƁA�X���q����́u�����v���Ӗ�����wapi�ƌ����悤�Ȑ������Ă�B���t�����́A�W���S���𐅂���g����ƁA�w�����ɂ����A�������琅��S�ēf������B�������Ȃ��ƁA��C���ł����܂ł�����������ƐM���Ă���B���̃W���S���͐l�Ԃ̂悤�ȏ�����������A���t����l�ŕߊl�����ꍇ�͕s���ȊW���������˂Ȃ��̂ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������Ɛ�������łȂ��ƁA�W���S���̓��͐���Ȃ��̂Ƃ��Ďs��ł͗��ʂł��Ȃ��B���U�̐����������ꍇ�A���̋��t�̓W���S���̓������Ɍ��ɂ����玀��ł��܂��ƐM�����Ă���B�܂��A�U�f�ɕ������肵����A�_�̓{��ɐG��A�W���S���Ɏp��ς����Ă��܂��Ƃ��l�����Ă���B����ɁA�W���S�����ɂ����������ł́A��ダ�K���K�ɂ����ʂ̐��߂̋V�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\���S�E�\���S�ɂ̓o���g�D�[�n�̏����̎{�p�t�������Ȃ��̂ŁA�C�X�����̏p���s�����K���K�̓L�����E�L���B���W����ĂъȂ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɃW���S�����͔��ɖʓ|�Ȃ��̂ł��邪�A�K���ɏ��������A���̓��̖��͓��ʂȂ̂ŋ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A�ƘV�l�����͌�����B�W���S������H�ׂ邱�Ƃ��^�u�[�Ƃ��ă��K���K����ւ����Ă���ƌn�̐l�X������B�^���U�j�A�ł̓W���S�����𑱂��Ă���l�X�����邪�A�قƂ�ǂ͕ی쓮���ł��邱�Ƃ�m�炸�ɋ����s���Ă���B
�@�U���W�o���̏�����������l���̘b�͎��̂悤�ł������B�Ƃ�g�̋��t�͍Ȃ������Ƃ�����Ă������A���D�ŋ��ɏo�����ɁA�������l�����D�ɏオ���Ă��ăX���q����̔������̂��̂����B�l���ɖ�����ꂽ���t�́A�ԂŐl����߂܂��悤�Ƃ����B�Ԃɂ��������l���͍ŏ��͒�R���Ă������A���t�̌���������ɉ����čȂƂȂ�A�����̔N�����������B�l���̍Ȃ͉Ǝ������ɂ��Ȃ��A�v��������A���Ă���Ɣ��������ʼn̂��̂��Ă��ꂽ�B������A���t�̓_���G�X�T���[���ɑ�ȗp���ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�Ȃ��c���čs�������Ȃ������̂ŁA�l���Ȃɔ������悻�s���̃u�C�u�C�𒅂��A�n���D�ɏ�����B�Ȃ͒��炭�C�����Ă��Ȃ������̂ŁA�ŏ��͌˘f���Ă������A����ɊC�ʼnj�������Ƃ����C������}�����Ȃ��Ȃ�A���������ŗ��ɒ������Ƃ��鎞�A���ɊC�ɔ�э���ł��܂����B����̗܂��ׁA�l���͐U��������ƂȂ��j�������čs���B�v�͂��̌��ǂ����Ƃ������������Ă��܂����B�Ȃ���߂��Ȃ��V���t�́A�����A�l���̎p�����߂ċ��ɏo�邪�A�Ȃƍĉ�邱�Ƃ͊���Ȃ������B
�@���R�����߂āA���邢�͌����}�����ꂸ��ނȂ��A�܂��͕s�{�ӂɊC�ɋA���Ă��������������̘b�Ƃ��Đl���a��杂��Ƃ炦��A�U���W�o���ɍŏ��ɗ��ꒅ�������{�l������������m�̐l���������̂����m��Ȃ��B����A�W�A����C���h�m���z���ăU���W�o���ɂ���ė������������́A�����u����䂫����v�ł������B���Ό���w�U���W�o���̖��q�R�x(�Љ�v�z�ЁA���㋳�{����1533�A1995.3.30)�ɏڂ����B�܂��A�X���q���̌������w�ɂ��ẮA�{�{�����w�X���q�����w�̕��y�@���A�t���J�C�ݒn���̌��ꕶ�����x(��O���فA2009.12.25)������B
�@�W���S���̃A�t���J���ݐ�����́A�^���U�j�A�̓�k�Ɋg����A��̓��U���r�[�N�E�}�_�K�X�J�����݁A�k�͍g�C�܂ŐL�тĂ���B�����ɕs�v�c�ȋL�^������B�|���g�K���̐鋳�t�t�����V�X�R�E�A�����@���X�̒��w�G�`�I�s�A�������x(1540�N�����A�r�㛨�v��A��q�C����p����2����4���A��g���X�A1980.1.7)�ł���B��136�͂Ɂu���̉����k�S�C�A��[�S�W����])�ɂ͑傫�Ȍ�(�^�i�B�_���r���Ƃ��Ăꂽ�l������A�j���̐l�����Z��ł���ƌ����Ă���A���ۂɖڌ������Ƃ����l������v(p.504)�Ƃ���B�܂��A��134�͂ɂ���u�A�}�]�i�k�A�}�]���l�̉����v�ɂ��Ă̒��ɂ́u���͂��̍��𗬂���͂�ʂ��Đ��A�t���J���痈���B�R���B��������������Ƃ���ɂ��ƁA���̑�͂ɂ͒j�̐l�����Z��ł���A���Ĉ�l�̐l�����v���X�e�̋{�a�ɘA��Ă���ꂽ���Ƃ�����A�g�ߒc��s���G�`�I�s�A�ɂ���Ƃ��ɂ��ʂ̈�l���A��Ă����A�|���g�K���l����������������A���̐l���͘b�����Ƃ��ł����A����H�ׁA�Ȃɂ����܂��A�e���v�̂悤�Ȕ畆�ɕ����A�l�Ԃ����傫���葫�������A�є��͍r���Z���A�����ĖڊW��������Ƃ̂Ȃ��ڂ͎˂�悤�Ȍ�������Ă����B���͂��̐l�����A���悤�ɖ������B�v(p.502)�Ə�����Ă���B�^�i�̓G�`�I�s�A�ő�̌ŁA�i�C��������o���Ă���B�C���̃W���S���̐����͂Ȃ��B�܂��A���A�t���J�̉͐�ɐ�������A�t���J�}�i�e�B�[���G�`�I�s�A�ɂ͂��Ȃ��B�A�����@���X�̓�����l(15���I�㔼����16���I�O��)�y���E�_�E�R���B���������`���Ă���l���͋��̎Y�n���A�t���J�ƒʂ��Ă����͂̑��݂�A���̐H���E�l�Ԃ��C���ނ��v�킹��̂ŁA�A�t���J�}�i�e�B�[�̉\�������邪�A�f���͏o���Ȃ��B
�@�g�C�ɂ̓W���S������������B�X�[�_�������A�g�C���݂ɏZ�ރx�W�������̃t�B�[���h���[�N�����Ă��钹���w�̓�c�_�u(1968�`)�́A�e�B�O����ŃW���S���̂��Ƃ����b�g�E�o�t���ƕ�����ŕ\������ƕ��Ă���B���ޖ��̂قƂ�ǂ��P��b�f����Ȃ�̂ɑ��A�C���M���ނ̓C���J���i�A�b�g�E�o�t���ƂȂ�悤�ɕ����̌�b�f�ŕ\�������B�C���J�ƃW���S���ɋ��ʂ́u�o�t���v�́u�C�́v���Ӗ�����C����A���b�g�́u���n�����ċ��v�A�i�A�b�g�́u���n�������p�k�v�ł���B���l�́u���������W���S���Ɏq�W���S�������Y�����܂��A���܂ꂽ�q�E�V����E�V�̂��𗣂ꂸ�e�q���J���������ƂƎ��Ă���v�u���҂̓������������v�Ɨގ����̐��������Ă���(��c�_�u�u�Q�̃G�R�g�[���̌����n�Ƃ��ẴX�[�_�������E�g�C���݈�F�x�W�����̓K���̋@�\��T��v[�u�n�����v��10����1���A2005.8�Ap.25])�B
�@�A�t���J�}�i�e�B�[�̐����͈͂́A�u�k�̓��[���^�j�A�A��̓A���S���A���̓`���h��22�J���v(���l�Y�u�l���̐��ފC�@10�@�A�t���J�̐l���v[�uTOBA SUPER AQUARIUM�v��55���A2009.7�Ap.19])�ɋy��(���[���^�j�A�A�Z�l�K���A�K���r�A�A�M�j�A�E�r�T�E�A�M�j�A�A�V�F�����I�l�A���x���A�A�R�[�g�W�{�A�[���A�}���A�j�W�F�[���A�u���L�i�t�@�\�A�K�[�i�A�g�[�S�A�x�j��(�x�i��)�A�i�C�W�F���A�A�`���h�A�J�����[���A�ԓ��M�j�A�A�K�{���A�R���S�A�U�C�[���A�A���S��)�B���͂܂��A�u�A�t���J�}�i�e�B�[�͊C�ɉ��邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����w�҂����邪�A�u�A�t���J�}�i�e�B�[�͊C�̊��ł͒����ԑς����Ȃ��悤�ł����A�W���邱�Ƃ��ł���Ή����̓��ɐ���������A�삩���ւ̈ړ����ɊC�ł��������Ƃ�����悤�ł��v(�uTOBA SUPER AQUARIUM�v��56���A2009.12�Ap.19) �Əq�ׂĂ���B
�@�}�i�e�B�[����������j�W�F�[���삪�����i�C�W�F���A�ɏZ�ރI�N�y��(Okpella)�̐l�X�́A���ɕ�Ȃǂ̕�������ɏZ�ތ��b�A�`�R�{(achikobo)�̑��݂�M���Ă���B���̌`�̓}�i�e�B�[�^�A���j�^�A�J���^�Ƃ��낢��ɑz������Ă��邪�A�������ɕ�������Ă��邱�Ƃ����ʂ��Ă���B�I�N�y���̐l�X��18���I�����Ƀx�j������ڏZ���Ă��������ŁA�G�h��ɋ߂������b���A�l���͂R���T��قǂł���B�A�`�R�{�Ɋւ���b�Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����B��l�ƌ��������Ⴂ�����ɁA�v�͊l���邽�тɔ�������^���Ă����B���̓l�Y�~�����̓]�E�܂ŁA���������^�����邽�тɍȂ͕�Ɍ���ꂽ�ʂ��ɂ���ĕۊǂ��Ă������B������A�v�͕�̓����A�`�R�{���l���Ƃ��Ď����A�����B�v�̐e���͊�ѕ����ꂽ�B�������l�̂Ȃ�������Ȃɗ^���Ă����̂ɁA����̓A�`�R�{�̔����Ȃɗ^���邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ȃ͔��͎����̂��̂ł���Ǝ咣���A���̂��Ƃɑi�����B�Ȃ͔��͎����̂��̂ƁA���܂ł̌o�܂��̂��A�؋��̕i�Ƃ��ĕۊǂ��Ă�������������̂ŁA�A�`�R�{�̔��ƁA����ɒ����Ă����݂͂ȍȂ̂��̂ł���Ɖ��ٌ͍������B�ȏ�́A�W�[���E�l�E�{�[�K�b�e�B�̘_���u�A�`�R�{�̘b�F���͎��̂��́v�ɂ��B���_���̒��ɁA���A�t���J�ł̓}�i�e�B�[�͗�(��)�̑Ώۂł��葱���A1990�N���̈Ŏs��̎������͂P��800�h���O��ŁA���͖ܘ_�A���b�w�͕a�C��\�h�����莡�Â����肷��Ƃ���A�܂����W�⍜�͓��ʂ̗͂�����ƒ��d�����A�ƋL���Ă���B
�@�吼�m�̐��݂ɂ̓A�����J�}�i�e�B�[�ƃA�}�]���}�i�e�B�[����������B���̃A�����J�}�i�e�B�[�̐�����ł���J���u�C�ɖʂ���j�J���O�A�̉f��u�l���Ɛ����v�v(La Sirena y el Buzo�A�����Z�f�X�E�����J�[�_�E���h���Q�X�ē�)��2009�N�H�A��22�����ۉf���natural TIFF����ŏ�f���ꂽ�B�j�J���O�A�E�z���W�����X�̃J���u�C���ݕ��ɏZ�ރ~�X�L�[�g�����̐��̏��_�`����w�i�ɂ����A�����v�̃h�L�������^���[���̕���ł���B�~�X�L�[�g�̐l�X�͒����A�����J�̌��Z���ł��邪�A���l�Ƃ̍����T���{�Ƃ��Ēm���(1641�N�A�K�C�A�i����u���W���ɑ����鍕�l�z�ꂪ�������N�����A���X�L�g�C�݂ɗ��ꒅ���A��������)�A�C�M���X�̕ی�̂ł���������������17���I������19���I���܂ʼnp���̉e�����ɒu����A�Ǝ��̉�����������Ă����B�~�X�L�[�g��͒��ăC���f�B�A������̃~�X�}���p�ꑰ�̈�ł��邪�A�p��n�̃N���I�[�����b�����B�V���̃������@�A����̉e�����傫���̂��A�j�J���O�A�̑��n��ƈقȂ��Ă���B�����̂��`�����Ă��邪�A2009�N�ɂ͓Ɨ��錾���\�����Ă���B�l���̓z���W�����X�̂ɂS���A�j�J���O�A��10���قǂł���B
�@�~�X�L�[�g�̓J���u�C�ŊC�T�����Ă������A�ߔN�̓��u�X�^�[���̐����ɏ]������l�X�������B�ߍ��ȏ���(�n��͑����ŁA43���̐��[�܂Ő���)�ł̐����ŁA�����߂������Q���Ă���Ƃ�������������B���Q�͊C�̃^�u�[��j�������߂ƍl����~�X�L�[�g������B�C�ɂ̓����E�}�C����(liwa mairin)�Ƃ����l���̏��_(�j�̐l���̓����E���C�N�iliwa waikna)�����āA�C�̎�����ی삵�Ă���B�ߓx�Ɏ��D��������v�͐l���̎̔�������A���D���]���������M����������B�N��50�l�̐����v���������A�z���W�����X�̂�9000�l�̐����v�̓�4200�l�����Q���Ă���Ƃ���������B�~�X�L�[�g�̎q�������͂�����g�ɕt���āA���Ɉ������܂��̂�h���B��p�t(sukya)�����t�Ƃ��̉Ƒ������V�����s���B�����E�}�C���������Ɍ��ꂽ��A�a�C�ɂȂ��Ă��܂��̂Ŏ�p�t�ɗ��邱�ƂɂȂ�B�܂��A�����a���l�����N�������̂ƍl����ꂽ�̂ŁA��p�t�̗̈�ł���B�l���͂܂��镪�ɑD���ʂ鉹�𗧂ĂĐl�X����������B���͂��邪�D�̎p�͌����Ȃ��B�l���̑��ɐl�X�ɕa�������炷�҂Ɏ��҂̍�������B���҂ɕ����킳��A���̏d�݂Ō����ɂށB��p�t�͎��҂̍������炩�ɂ��邽�߂ɋV�����s���B�Î��Ɍu�������ƁA�߂܂��č��̑i�����A�ǂ������獰�����S�ł��邩�Ƒ��ɓ`����B�������҂̍��ɖ߂��x��Ƌ����̋V�����s�����Ƃ�����B�z���W�����X�̓��k���ɏZ�ޏ��������p���̐l�X�͋��ނ̕�ł���l���͂X�̖ڂ������A�͐얈�ɐl�������āA���̑O�ɂ͋V�����s���A����߂鋖�����Ƃ����B�J�J�I�Ǝ��������Z�����_�ɕ������B�~�X�L�[�g�̋ߗו����K���t�i�l�������C��͌��ɐ��̐�(�l��)���Z�ނƂ����M�����L���Ă���B�ȏ�̋L�q�̓E�F���f�B�E�O���t�B���Ɋ�Â����̂ł���B
�@���E�̖��b��31���u�J���u�C�v(���˕��F�E�ɓ��x�Y�E�����L���A���傤�����A1985.10.10)�ɂ̓j�J���O�A�̘̐b���Q���^����Ă��邪�A���̈�u���҂̍��֍s�����j�v(pp.254�`259)�́A���Ȃ�Y����Ȃ��j���u�܂��Ȃ��t�v�ɗ���Ŏ��҂̍�����Ȃ�A��߂����Ƃ��邪����ꂸ���s����Ƃ����b�ł���B���҂̍��͌̓��̓�������~��čs�����ƂɂȂ��Ă���B�܂��Ȃ��t�́u�������Œn�ʂɊ�d�ɂ��~��`���āA���̂������ɁA�D���g���ėl���܂Ȃ��邵��A������A�����������ꂽ�v�B���ɂ����j�̊z�E���E�w�ɂ��u�Y�łӂ����ȕ����������t�����v�B���̕������������ď����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƌ������B�j���~�̒��S�ɗ�������ƁA�܂��Ȃ��t�́u�J�𐁂��Ȃ���A�j�̎����x��n�߂��v�B�j�͑̂��y���Ȃ����悤�ɂȂ�A������ꂽ����i�ݎ��҂̍��ɓ�������B���҂̍��ɂR���؍݂�����ɒj�̑̂̕����͏����Ă��܂��B�j�͂���ł������������Ȃ�A��Ė߂��Ă������A�܂��Ȃ��t�ɗ��邱�Ƃ���߂āA���܂ŋA��A�Ō�Ɏc�����u���邵�v���ȂɌ����Đ���Ă��܂����B�U��Ԃ�ƍȂ̎p�͂Ȃ��������A��ɖ߂������̂Ǝv�����ɓ����Ă������B�����͎����̒m�����Ă������Ƃ͗l�q���ς��A�]�Z��͂Ƃ����Ɏ��ɁA�����̎p�͘V�l�ɕς���Ă��܂����B�����āA�j�̎p������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�C�U�i�M�̉���̍��K��ƉY��杂����킳�������e�ɂȂ��Ă���B�Ȃ��A�u�J���u�C�v�҂ɂ́u���@�ŋ��ɕς���ꂽ��ҁv(�W���}�C�J�App.27�`32)�A�u���Ƃ��̗��l�v(�o�[�W�������App.64�`69)�A�u���̕�v(�R�����r�A�App.220�`221)�����߂��Ă���B
�@��Ă̐���̏��_�Œ��ڂ��ׂ����݂ɃC�G�}���W���[(Iemanja)�����邱�Ƃ͊���̒ʂ�ł���B�u���W���̃J���h���u���A�E���o���_�ȂǂŐM�����C�̏��_�ɂ��āA�r��F�A�́u�u���W���̖����w�҂ɂ���āA�A�t���J�̃����o���ɋN�������_�i�ł��邱�Ƃ��A�����炩�ɂ���Ă����v�u�C�G�}���W���[�́A�����C���x�z����_�i�ł͂Ȃ��A�i�C�W�F���A�ɂ���I�O����̗d���ŁA�����������݂���A���Ȃ��悤�Ȑ��i�����d���̂ЂƂɂ����Ȃ������v(�����܍����^�ʐ^�E�r��F�A�^���A�u�C�G�}���W���[�@���̏��_�̍Ղ�v�A�u�G�������w�v��S����R���A�ʊ�13���A1980�App.30�`35)�Əq�ׂĂ���B�C�G�}���W���[�̓I���V���ƌĂ��A�t���J�N���̐_�i�̈�l�ł���B�u�C�G�}���W���`���ɂ͊��x�ƂȂ����ς��������ē��e�͖L�ɂȂ�܂������A�{���ł͌��̓`���ɋ߂����̂��̗p���Ă��܂��v�Ɩ������Ă���̂��w�C�̏��_�A�C�G�}���W���x(�}�����l�E�y�������W�F�C����A���������܂肱��A�V�����A2002.10.30)�ł���B
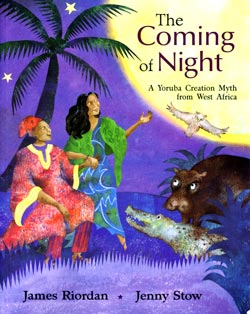 �@�y�������W�F�C��(Marlene
Perlingeiro)�̓`����C�G�}���W���͎��̒ʂ�ł���B�C�G�}���W���́u���ׂĂ̊C�̐������������ǂ�v�I���N���̖��ŁA�C�t�F�̉��I���t�B���ƌ��������B�q���ɂ��b�܂ꂽ���A�C�G�}���W���͑ދ��ŏ���o���A�ꂩ��^����ꂽ���@�̐��Ŗ������ꂽ����������B���̓C�G�}���W�����̌��ɉ^��ōs���A�C�G�}���W���́u����C�����߂�v���_�ƂȂ����B�l�X������т₩�ȕ�����������ƁA�C�G�}���W���͐l�X�����K�������B���̑受�_�̖����n��̉��ƌ�������Ƃ����b�́A�W�F�C���Y�E���I�[�_�����E�W�F�j�[�E�X�g�E�G�w��̒a���@���A�t���J�A�����o�̑n���_�b�_�b�x(1999�N)�ł������B���̐������܂ꂽ��̂ɂ͖�Ƃ������̂��Ȃ��������������Ă����B��̑受�_�C�F����(Yemoya)�͖��A�W�F(Aje)��n��̉��I�h�D�h�D��(Oduduwa)�ƌ����������B�C�F�����͐��̔��Â����E���瑾�z�����X�ƋP�����E�։ł����̂ł���B���炭�K���ɕ�炵�Ă������A�₪�đ��z���I���������E�����������ł̐��E��������v���悤�ɂȂ����B���͖�𑗂�悤�ɃC�F�����ɓ`����悤�J�o�ƃ��j�ɓ`����������B�C�F�����́A�r���ŊJ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����܂߁A�܂ɋl�߂����Ɏ��������B���ɏオ�����͑܂��畷�����Ă����̉��ɋ����A�܂��قǂ��Ă��܂����B�܂���͖�̈łƋ��ɖ�̐�������������т����Ă����B�݂ő҂��Ă����C�F�����͖�̎҂����𐧌䂵�A�����̖������A�V�������̎n�܂�ɒ�߂��B
�@�y�������W�F�C��(Marlene
Perlingeiro)�̓`����C�G�}���W���͎��̒ʂ�ł���B�C�G�}���W���́u���ׂĂ̊C�̐������������ǂ�v�I���N���̖��ŁA�C�t�F�̉��I���t�B���ƌ��������B�q���ɂ��b�܂ꂽ���A�C�G�}���W���͑ދ��ŏ���o���A�ꂩ��^����ꂽ���@�̐��Ŗ������ꂽ����������B���̓C�G�}���W�����̌��ɉ^��ōs���A�C�G�}���W���́u����C�����߂�v���_�ƂȂ����B�l�X������т₩�ȕ�����������ƁA�C�G�}���W���͐l�X�����K�������B���̑受�_�̖����n��̉��ƌ�������Ƃ����b�́A�W�F�C���Y�E���I�[�_�����E�W�F�j�[�E�X�g�E�G�w��̒a���@���A�t���J�A�����o�̑n���_�b�_�b�x(1999�N)�ł������B���̐������܂ꂽ��̂ɂ͖�Ƃ������̂��Ȃ��������������Ă����B��̑受�_�C�F����(Yemoya)�͖��A�W�F(Aje)��n��̉��I�h�D�h�D��(Oduduwa)�ƌ����������B�C�F�����͐��̔��Â����E���瑾�z�����X�ƋP�����E�։ł����̂ł���B���炭�K���ɕ�炵�Ă������A�₪�đ��z���I���������E�����������ł̐��E��������v���悤�ɂȂ����B���͖�𑗂�悤�ɃC�F�����ɓ`����悤�J�o�ƃ��j�ɓ`����������B�C�F�����́A�r���ŊJ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����܂߁A�܂ɋl�߂����Ɏ��������B���ɏオ�����͑܂��畷�����Ă����̉��ɋ����A�܂��قǂ��Ă��܂����B�܂���͖�̈łƋ��ɖ�̐�������������т����Ă����B�݂ő҂��Ă����C�F�����͖�̎҂����𐧌䂵�A�����̖������A�V�������̎n�܂�ɒ�߂��B
�@�C�G�}���W���[�����̐�̐�����D�ʂȒn�ʂɗ��������Ƃɑ��čr��F�A�́u�u���W���̃����o�n�̃Z�N�g�ł́A�����_�I�������Ɛl�ԂƂ̂������̃R�~���j�P�[�V�������Ƃ���A����ғI���݂ł���I���V�������̕�Ƃ��āA�L���X�g���̐���}���A�ƏK�����āA���ƍq�C���i�ǂ�A�L���X�g�ƏK������I�V�����ɂ��_�i�ƂȂ����v�Əq�ׂĂ���B�u���W���ɂ̓A�t���J�n�̐��̐_�̑��ɁA���Z���C���f�B�I�̐�̏��_�C�A�[��������B�A�}�]���여��ɏZ�ރg�D�s�[�����̖��C�A�[���͂ƂĂ��������������A�����j���������W������ɓ����̂Ă�ꂽ�B���̐���̓C�A�[���̎p��l���ɕς��A�i���ɐ��̒��ŕ�炷���ƂƂȂ����B�u�l���C�A�[���̐������j�͂��̉̐��ɖ������āA�����͂ň�������B�����Ă��̔������p��ڂɂ����҂́A�̂���邱�Ƃ��ł����A�C�A�[���ɂ�����Đ��̒�ɘA�ꋎ��ꂽ����A�������Ă��ǂ��Ă͂��Ȃ��v(�w���E�����������{�̖@�u���W���E�C���f�B�I�̐_�b�Ɠ`���x�A���@���f���}�[���^�Ęb�E�G�A�i�c��q��A�����ُ��X�A1996.10.25�App.48�`49)�B
�@�E���o���_�ɂ��Ď��H�I�������܂Ƃ߂��̂��e�L�T�X��w�̎Љ�l�ފw�҃����[�C�E�w�C���ł���B���̒��̑薼�́w�l���̉̂��Ȃ���@���I�E�f�E�W���l�C���̃E���o���_�x(2009�N)�ł���B�u���̕�͐l���@�����������@�l���̉̂��̂��Ȃ���@��͐l�X�̂��߂ɒn��ɂ���ė����v�B�w�C����22�N�O�ɕ������̂̈�߂ł���B�w�C���̓E���o���_�̋q�ϓI�A�����I������ڎw�����킯�ł͂Ȃ��A���g���W�����ɂR�̃E���o���_������Љ�Ă���B�E���o���_�̓J�g���b�N�̐��l�ƏK�������A�t���J�o�R�̐_�X�I���V��(Orixas)�_�ɂ����A�C���f�B�I(Caboclos)�A���l(Pretos Velhos)�A�q��(Criancas)�Ȃǂ̗삪�A�g�����X��Ԃ̗�}��ʂ��Č�肩����V�������S�ƂȂ�B���[���b�p�̐S��p�̉e�����ɐ������A���l�A���l�A�C���f�B�I�A���m�l�Ƒ����̐l�킪�Q�����Ă���B�I���V�����J���h���u���ƈႢ�A�X�_�i���m�F����邾���ł���B�I�V����(Oxla)�A�i�i��(Nana)�A�I����(Omolu)�A�C�G�}���W���[(Iemaja)�A�I�O��(Ogum)�A�V�����S(Xango)�A�I�V����(Oxum)�A�C�A���T��(Iansa)�A�I�V���V(Oxossi)�B�����Ƃ����l�n�̃E���o���_�ł͂��̑��̃I���V��(�I�V���}���A�I�T�C���A�e���|)���d�v������Ă���B�C�̏��_�C�G�}���W���[�̓I���V�������̕�Ƃ������A����G��ł́A�Ɣ��̃h���X�𒅂āA���̓������t���C����o�����銯�\�I�ȍ����̔����ɕ\�������B�ꐫ�I�Ŏq���������邠�܂�q���������C��̋{�a�ɂ�����Ă��܂����Ƃ�����B�}���A�ƏK�����邪�A�V�N�̋V���Ƃ��ă��I�E�f�E�W���l�C���̊C�݂ł̓C�G�}���W���[�̍Ղ肪�j����B���F�A���A�s���N���C�G�}���W���[�̐F�Ƃ���A�y�j�����C�G�}���W���[�ɕ������Ă���B�w�C��������E���o���_�̋V���ł̓J�{�N��(cabocla)�ł���W�����}(Jurema)���C�G�}���W���[�̎g���̐l���Ƃ��ēo�ꂷ��B��̉̂̈�߂��l���W�����}���̂������̂ł���B�W�����}�Ƃ͓��Ȃ̐A����~���U�̈Ӗ������B
�@���A�t���J�𒆐S�Ƃ���l���`�̏��_�}�~�E���^�ɏے�����鐅�̏��_�M�́A�A�t���J�̐l�X���z��Ƃ��ĐV�嗤�ɘA��Ă���ꂽ���߁A�J���u�C��A�u���W���A�A�����J���O���̍��l�n�����ɑ��Ղ�H�邱�Ƃ��ł���B�s��Ȑl�����߂���f�B�A�X�|���̕����͋ߔN���ڂ̗̈�ł��邪�A�Ȃ��Ȃ���������Ȃ��B����̓W�J���������Ƃɂ���B
�����@�G�@