東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>37P
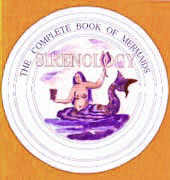
資料と本、提供いただいた情報とグッズは溜まるばかり、はき出す力は衰え、棚というより床に山状態となって久しい。気の付いたことを少しばかり書いておこう。
2008年は田辺悟著『人魚』で暮れてしまったが、その後、東京子ども図書館発行、季刊「こどもとしょかん」第119号(2008.10.20)「資料室の本」に田辺『人魚』が紹介されていることを知った。研究書15点の1冊。「海の民俗学者が国内外の現地調査や取材を基にした人魚研究の集大成。伝承、文学、歴史、美術、工芸等様々な角度から人が抱いてきた人魚像に迫る。人魚のミイラ他、写真多数。」とある。
人魚のミイラは今年も博物館展示で見ることができた。兵庫県立歴史博物館(2009.4.25〜6.14)・京都国際マンガミュージアム(7.11〜8.31)「妖怪天国ニッポン−絵画からマンガまで−」展。京都会場について報じる「山陽新聞」7月30日号(17)面には「「見世物文化の中の妖怪」として人魚のミイラや半人半牛の姿をした怪物件のはく製も展示する」とある。人魚ミイラは原野農芸博物館蔵のもので、2006年に国立科学博物館「化け物の文化誌」展で公開されたものと同じある。
化け物文化誌展のもう一つの人魚、八戸市博物館蔵、双頭の人魚ミイラは青森県立郷土館「妖怪展 神・もののけ・祈 り」(2009.8.28〜10.12)に登場した。郷土館学芸員、太田原慶子氏は!0月3日「描かれた人魚−妖怪展資料から」と題して講演を行っている。「妖怪展」図録を見ると、ミイラのほかに3点の人魚が掲載されている。宝暦7(1757)年3月下旬、外ヶ浜石崎村で網にかっかた異魚(顔は人で、角が二つあり、髪をかぶり、胸に輪袈裟にようなものをかけ、全身がうす黒い)。展示の資料は弘前市立弘前図書館蔵「三橋日記」であるが、同様の記述は、笹間良彦『ロマンの怪談ー海と山の裸女ー』(雄山閣出版、1995.11.20)p.81に引く「津軽旧記」にある。笹間著『人魚の系譜』(五月書房、1999.1.28)p.137
でも触れられている。袈裟をかけた様な姿から、百年ほど前に松前に渡る途中で海へ墜ちた「藤光寺弟子坊主」ではないかと噂された異魚である。宝暦8(1758)年3月下旬のこととしている。この人魚は松井魁『伝説と幻を秘めた人魚』(1983.9.31)p.41、p.52にも指摘されている。宝暦年間(1751〜1764)に津軽で人魚が出現したことは大槻玄沢も「六物新志」に記述しているが、その人魚は女性であった。松井魁は江戸時代に津軽で目撃された人魚の例として他に、元禄元年(1688)7月「津軽野内浦(津軽一統志)」、文政年間(1818〜1830)「津軽夏泊半島田沢村野田沖(平内志)」をあげている。
り」(2009.8.28〜10.12)に登場した。郷土館学芸員、太田原慶子氏は!0月3日「描かれた人魚−妖怪展資料から」と題して講演を行っている。「妖怪展」図録を見ると、ミイラのほかに3点の人魚が掲載されている。宝暦7(1757)年3月下旬、外ヶ浜石崎村で網にかっかた異魚(顔は人で、角が二つあり、髪をかぶり、胸に輪袈裟にようなものをかけ、全身がうす黒い)。展示の資料は弘前市立弘前図書館蔵「三橋日記」であるが、同様の記述は、笹間良彦『ロマンの怪談ー海と山の裸女ー』(雄山閣出版、1995.11.20)p.81に引く「津軽旧記」にある。笹間著『人魚の系譜』(五月書房、1999.1.28)p.137
でも触れられている。袈裟をかけた様な姿から、百年ほど前に松前に渡る途中で海へ墜ちた「藤光寺弟子坊主」ではないかと噂された異魚である。宝暦8(1758)年3月下旬のこととしている。この人魚は松井魁『伝説と幻を秘めた人魚』(1983.9.31)p.41、p.52にも指摘されている。宝暦年間(1751〜1764)に津軽で人魚が出現したことは大槻玄沢も「六物新志」に記述しているが、その人魚は女性であった。松井魁は江戸時代に津軽で目撃された人魚の例として他に、元禄元年(1688)7月「津軽野内浦(津軽一統志)」、文政年間(1818〜1830)「津軽夏泊半島田沢村野田沖(平内志)」をあげている。
青森県立郷土館所蔵「横山家文書」にある「男人魚」は「この魚を見る者は長寿になるといい、弘前藩の若殿が「母親に見せよ」と筆写しれくれたもの」と説明されている。横山家は弘前藩の兵学者であった。同形の人魚は、平尾魯仙(1808〜1880)筆「異物図会」にもある。安政4(1857)年、原田宇吉が魯仙に示して写させたものだと記されている。但し、大きさが違う。魯仙のものは3尺6、7寸、横山家の図には1尺2寸となっている。この二つの人魚は大きな胸鰭が目立つことが特徴となっている。
人魚に関連したしたものとしては、越後国福島名田吉に現れた光り物も展示されていた。これは以前報告した「藤岡屋日記」にある童子形の光り物と同じである。女の声で5年間の豊年と、あく風による多数の死者を予言し、姿絵を朝夕見れば難を逃れることが出来ることを伝えるために現れたと、柴田忠兵衛という武士に語った。色摺物で、金色の雲に正座した胸に鱗状の模様がある人物が海上に浮かんでいる。また、宝暦9年(1759)年春、加賀国に現れた角の生えた女面の魚が載る「姫國山海録」も展示された。この異魚はすでに報告した神社姫(文政2(1819)年)と有名な瓦版の文化2(1805)年、越中国に現れた巨大な人魚に似ている。絵姿は神社姫、記述の「首より尾まで3丈8尺、火炎を吹いて民家千軒を焼いたので、銃で殺した」という点は瓦版人魚に類似する。
人魚ミイラは、 新宿区歴史博物館「名宝展」(2009.3.14〜5.10)でも見ることが出来た。菓子商「荒井谷」野口家に伝わってきた、長寿と繁栄を祈願した人魚である。頭はネズミと言われる変わった形の人魚である。
人魚ミイラを博物館で展示することついては、かつて兵庫県立歴史博物館学芸員であった近藤雅樹(国立民族学博物館教授1951〜)が「人魚のミイラと博物館」(「淡交」第58巻第8号、2004.8.1、pp.38〜41)
で、「私がこの特別展示を企画し、実現させる以前には、人魚のミイラを陳列した国公立博物館など、まだどこにもなかった。こうした造形物は贋物だと認識されていたからである。」と述べている。
「この特別展示」とは、1987年7月11日から8月30日まで、兵庫県立歴史博 物館で開催された特別展「お化け・妖怪・幽霊・・・」のことである。この妖怪展のため、近藤は学文路の仁徳寺から「蒲生川で捕獲された」という伝来を持つ謡曲「苅萱」ゆかりの人魚ミイラを借り出した。画布に描かれた妖怪・幽霊だけでなく立体造形物も「妖怪文化」を形成してきた「作品」と考えたのである。同展には河童のミイラも展示されたが、近藤らは「全国各地に残る立体的な造形物の所在調査」を行い、その結果「その多くが往年の縁日で見世物にされていたものではなく、寺社に奉納され、祀られている信仰対象であることも判明した」としている。同展図録p.40には苅萱堂・人魚ミイラが載り、見開きのp.41には近藤のコラム「明石浦と人魚」が黒地に白抜き文字で綴られている。14世紀後半に成立した「峯相記」に載る明石浦の人魚を巡るコラムである。その後、近藤は最古の奉納記録を持つ大阪瑞龍寺の人魚ミイラ、ヨーロッパ各地の博物館に所蔵されている人魚ミイラに対面している。博物誌資料として堂々と常設展示しているヨーロッパの博物館に比べ、「かつて人魚のミイラの輸出大国であったニッポン」を示す博物館の出現を希求する文章で全体をまとめる近藤であったが、最近では毎年妖怪展が開かれ、国立科学博物館でも展示されたり、学文路の人魚が和歌山県有形民俗文化財に指定(2009年3月17日)されるなど、人魚ミイラを巡る環境は随分と変わった。
物館で開催された特別展「お化け・妖怪・幽霊・・・」のことである。この妖怪展のため、近藤は学文路の仁徳寺から「蒲生川で捕獲された」という伝来を持つ謡曲「苅萱」ゆかりの人魚ミイラを借り出した。画布に描かれた妖怪・幽霊だけでなく立体造形物も「妖怪文化」を形成してきた「作品」と考えたのである。同展には河童のミイラも展示されたが、近藤らは「全国各地に残る立体的な造形物の所在調査」を行い、その結果「その多くが往年の縁日で見世物にされていたものではなく、寺社に奉納され、祀られている信仰対象であることも判明した」としている。同展図録p.40には苅萱堂・人魚ミイラが載り、見開きのp.41には近藤のコラム「明石浦と人魚」が黒地に白抜き文字で綴られている。14世紀後半に成立した「峯相記」に載る明石浦の人魚を巡るコラムである。その後、近藤は最古の奉納記録を持つ大阪瑞龍寺の人魚ミイラ、ヨーロッパ各地の博物館に所蔵されている人魚ミイラに対面している。博物誌資料として堂々と常設展示しているヨーロッパの博物館に比べ、「かつて人魚のミイラの輸出大国であったニッポン」を示す博物館の出現を希求する文章で全体をまとめる近藤であったが、最近では毎年妖怪展が開かれ、国立科学博物館でも展示されたり、学文路の人魚が和歌山県有形民俗文化財に指定(2009年3月17日)されるなど、人魚ミイラを巡る環境は随分と変わった。
荒俣宏が近藤を招いて対談しているのが「荒俣宏の万物に叡智あり 出島から西欧へ輸出 シーボルトも調査した「人魚のミイラ」とは何だ」(Foleフォーレ、第76号、2009.1.1、みずほ総合研究所)である。荒俣は近藤企画の「お化け・妖・幽・・・」展から話を切り出している。また荒俣は人魚のミイラはサルを魚類と繋いだ物が多く、その技法を「袋剥ぎ」と言っている。一方近藤は胴体を木で造り、張り込んだ和紙の襞が皮膚のように見えると応じている。荒俣がシーボルトやオランダ商館長のことを持ち出すと、近藤は長崎周辺の漁民が外国船に売る密貿易品の中に人魚ミイラが含まれていた可能性を示唆している。話はヨーロッパの博物館に移り、ライプチヒ民族博物館蔵の「メザシに小人の胴体がついたような」極小サイズ人魚からライデン民族学博物館の2メートル近い大型人魚へと進む。近藤はライデンの大型人魚の胴体のほころびから藍染め木綿布がはみ出しているところから日本製であろうと推測している。但し、両人とも人魚ミイラの製作地を特定することは難しいとしている。この対談の場に近藤はヘルシンキの文化博物館にあった子ども向けの塗り絵を持参し、その中の人魚数種を紹介している。荒俣が「ムンク型人魚」と呼ぶ「頬に両手をあてて、口を開いた姿」のミイラ、人面魚型、ヨーロッパの二又人魚、ヒンドゥー教のヴィシュヌ神の化身の1形態などである。近藤はまた、人魚のミイラを「民具の一つ」として見て(近藤の専門は民具である)、日本の人魚については次のように言っている。「人魚は明らかに、古くから日本の漁民の間に伝わる水神信仰とかかわってきた。そこからさらに竜宮伝説や、八百比丘尼の不老不死の話へとつながっていく。こう考えると、非常に豊かな広がりをもった表象だといえますね。」一方荒俣は、対談タイトルのすぐ後に「幕末の日本でつくられ、世界へ持ち出された「人魚のミイラ」をご存知だろうか。「人間のつくったものではないか」などと侮ることなかれ。出島にやってきたシーボルトやオランダ商館長の心をとらえた不可思議な魅力には、人間精神のなんたるかが表れているのである」との一文を添えている。
富山市八尾町にある海韻館で企画展「人魚伝説 海牛と海の仲間たち」(7月25日〜9月28日)が開催された。副題にある通り、2006年10月に高岡市五十辺で発見された約300万年前の海牛の化石とその周辺に埋まっていた化石、ヤマガタカイギュウなど日本各地で発見された化石海牛の展示である(2006年12月には新潟県高岡市妙見町の200万〜250万年前の地層からカイギュウの肋骨が発見された)。初日には長澤一雄氏による「富山の人魚はどこから来たか?」と題した講演があった。なお、2009年8月には長野県中条村の450万〜500万年前の地層から海牛の肋骨化石が発見されている。長野県では2例目(1965年、戸隠村)の海牛化石である。
2009年11月13日には、高松市の新屋島水族館のアメリカマナティーのつがい(父ベルグ、母ニール)に雄の赤ちゃんが生まれた。15年間の飼育で、初めての出産である。夫婦共にドイツ、ニュルンベルグ動物園生まれのマナティーで、母親は授乳がうまくできない。
ヘルシンキ市美術館では去年(2008年)、「ハーヴィス・アマンダ百年記念」展が開催された。ハーヴィス・アマンダとはヘルシンキ市場広場に1908年9月20日に噴水の像として設置されたバルト海を擬人化した乙女像である。設立時、フィンランドはロシア支配下にあったがロシア革命の年、1917年12月に独立を達成した。像の製作はヴィッレ・ヴァルグレン(Ville Vallgren、1855〜1940)、パリで勉強した彫刻家で、ハーヴィス・アマンダ像も1906年にパリで製作された。ヴァルグレン自身は人魚像(Merenneito)と呼んでいたが、海藻にのって海から立ち上がろうとする乙女像を、スウェーデン系の新聞はHavis Amandaと言っていた。設置当時は裸像に反対する人々もいたが、やがてヘルシンキの象徴として受け入れられるようになり、毎年大学生の祭り(vappu、5月1日)の前夜には、巨大な学生帽を被せ、像を花で飾ることとなる。独立後のフィンランドにおける多数派フィンランド語住民と少数派スウェーデン語住民の軋轢をスウェーデン語風刺誌「ガルム」の画家ヤンソン母娘に焦点を当てて述べている冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界 ムーミントロールの誕生』(青土社、2009.5.20)には、ヴァップについての次のように記述がある。「学生帽と酒の組み合わせは、フィンランドで盛大に祝われる祭日のひとつヴァップ(聖ヴァルプルギスの祝日前夜)を思わせる。四月最後のこの日、学生が街角やカフェにくりだし、酒を飲んで大騒ぎをする。ドイツの学制に範をとったフィンランドでは、学生は新生国家をになうエリートだ。よって、白地に黒いベルトが巻かれた学生帽は、男女学生に共通のステイタス・シンボルである」(p.61)。
フィンランド国民の中、スウェーデン語を主要言語とする人々は少数派で、30万人ほど(『現代ヨーロッパの言語』、田中克彦・H.ハールマン、岩波新書、1985.2.20)である。多数派フィンランド語住民は440万人である。ムーミンの作者トーヴェ・ヤンソンは少数派であるスウェーデン語住民であり、母親シグネ・ハンマルステン・ヤンソン(1882〜1970)はスウェーデン生まれの画家、トーヴェの父ヴィクトル(1886〜1958)はヘルシンキ生まれの彫刻家である。トーヴェの原画展の巡回展が日本で開かれた2009年には、トーヴェ関連の出版物がいくつか出版された。先に述べた冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界』もそうであるが、そのほか「月刊モエ」特集「ムーミン谷のあそびかた」(第31巻第5号、2009.5.1、白泉社)、「芸術新潮」特集「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソンのすべて」(第60巻第5号、2009.5.1)などである。「芸術新潮」P.73にはヴィクトル作の足先が魚尾になっているブロンズ「人魚」像(高さ110cm、1941年作)、p.64には人魚や海馬が描かれたシグネ画「クルーヴ島の地図」が載っている。
トーヴェのムーミンシリーズにも第一作『小さなトロールと大きな洪水』(冨原眞弓訳、講談社、1992.6.20)から人魚は登場している。「波間をおどりながらボートとすれちがう人魚。小さな海のトロールの群れが、ちらりと姿を見せたりもします。」(p.48)。p.47には挿絵があり、人魚と海のトロールのイメージが確認できる。講談社『ムーミン童話の百科事典』(1996.5.30)の「人魚」項(p.165)には「ムーミン谷近くの海にはおひめさまの人魚や男の人魚(正しくは、海の乙女Sjofroknarや海のトロールsjotroll)が住んでいる。彼らはとても友好的で、ムーミンたちが船で海にでると、よく船のそばにあらわれる。」と説明されている。登場作品は「たのしいムーミン一家」(講談社『ムーミン童話全集』第2巻、p.98「へさきのまわりでは、おひめさまの人魚や男の人魚がダンスをし、空では白い大きな海鳥が、輪をかいてとびちがいました」)と「ムーミンパパの思い出」(講談社『ムーミン童話全集』第3巻、pp.127〜128「人魚たちが尾をふっていたので、わたしたちは、オートミールをなげてやりました」)である。童話版の他にコミック版のムーミンにも人魚は登場する。「わがままな人魚Mumin och Sjojungfrun」(筑摩書房、『ムーミン・コミックス』第7巻「まいごの火星人」、冨原眞弓訳、2001.1.20)である。こちらは訳題が示している通り「友好的」とは言えない自分勝手な人魚がムーミンを振り回す。人魚のパートナーとして、海藻に覆われたガラモン(ピグモン)のような「海男」も登場する。
北欧神話の冥府の番犬「ガルム」を誌名とするカリカチュア雑誌の主任画家であったヤンソン母娘について詳細に論じる冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界』には人魚のモチーフについて触れる部分がある(pp.360〜364)。「ガルム」を読んで大笑いする人魚の表紙は1946年7月号。翌年の7月号の表紙も黒犬ガルムとムーミントロールを囲む7人の人魚が描かれている。1946年の人魚は父ヴィクトルの彫刻のように二本の足を持ち、先端が魚尾になっている。一方1947年ではお尻の部分は人間であるが、その先は一本の魚尾となっている。トーヴェのムーミントロールは童話以前に「ガルム」誌上に画家の感情を表現する署名としては1943年に登場した。但し名前はスノーク。更に全身「黒いムーミントロール」は1934年に既に描かれている。
足の二本ある人魚像はコペンハーゲンの人魚像が有名であるが、その像が上海万博で公開されることを報じつつ、もう一つの人魚姫像がコペンハーゲンに設置されたことを伝える記事が朝日新聞に載っていた(長島要一、2009年7月18日、9面)。王立図書館前にあるアンネ・マリー・カール−ニールセン(Anne Marie Carl-Nielsen、1863〜1945。デンマークの著名な作曲家カール・ニールセン[1865〜1931]の妻)作の複製像がそれである。1921年製作のブロンズ像は国立美術館に収められているが(オリジナル石膏像はフュン島美術館蔵)、港の人魚姫の留守を埋めるためなのであろうか、コピー像が図書館前に出現した(2009年5月5日)。うねった一本の魚尾は力強く表現されている。
図書館前の人魚で、思い出されることは、アメリカ東海岸の軍港都市ノーフォーク(ヴァージニア州)である。市のシンボルとしての人魚が公共施設、ホテル、銀行、商店などの建物に、左手を前に、右手を後ろに突きだした横向きの形で置かれている。形は同一(クリス・アレクサンダーのデザイン。原型はノーフォークのブロンズ彫刻家ケヴィン・ギャラップによる)だが、色彩やアトリビュートがそれぞれ異なっている(それぞれの人魚には固有名が付けられている)。図書館の人魚は魚尾の背に本をのせて、識字能力向上運動に貢献している。300以上ある人魚の歴史はそれほど古いものではない。1999年 市の司法長官であるピーター・デッカーが市のイメージ向上にと提案したのがその始まりである。ピーターは妻のベスから人魚のアイデアを貰ったと言っている。その当時、シカゴで牛のアートが町中に置かれ、夏の観光の目玉になったことから思い付いた振興策であった。公共と芸術家、商業の協力で町のイメージを高める同様の運動は、牛、人魚の他に、ノース・キャロライナ海岸部のペガサス、リッチモンドの魚などと広がりを見せている。
ノーフォークの人魚についてはリサ・スーヘイ『あ、人魚だ!』という冊子がある。スーヘイは『人魚と黄熱病』という19世紀にノーフォークで黄熱病が流行したときにフランスから大西洋を越えて人魚たちがやって来て、病人を救ったという創作民話まで作った。ノーフォークでは屋内外、町中に人魚があふれかえっている。10フィートの人魚は一体5000ドル、5インチのオーナメントが10ドル。これらを商売にしているのがクリス・アレクサンダーのコースタル・アートという会社である。年間、大小1万体以上の人魚を作っている。
話をデンマークに戻し、Mosekonen(沼女)という沼地の霧や靄に関連する存在についてお知らせしたい。霧が立ちこめると人々は沼女が酒や魔法の薬を醸していると噂する。イブ・スパング・オルセン『ぬまばばさまのさけづくり』(福音館書店、1980.7.25、きむらゆりこ訳)では、「ぬまばばさま」(かみのけが うすくて はなが とてもおおきく、はだしのあしは ごつごつで どろだらけです)の家族に、「ぬまじじさま」(おおおとこ。カワヤナギに変身)、「ぬまむすめ」(かわいいかお。ふさふさの かみのけは、いちども くしで とかしたことが ありません。草むらに変身)、「ぬまこぞう」(かわいくない、いたずらっこ。枯れ枝に変身)がいて、全員太陽光が大嫌い。真夏に酒造りをして、たちこめた湯気は靄となり、人々は「ごらん、ぬまばばさまが おさけを つくってる!」と言うでのである。樽に入れた酒を秘密の場所に隠して、一家は土に潜って冬ごもり。春になったお祝いに、一家は酒を飲み干し、それからは太陽に当たっても平気で、息を吹きかけたり、地面を踏みならして辺りを春景色にする。ヨーロッパの春を迎える祭りは先にハーヴィス・アマンダのところで紹介したヴァップ、聖ヴァルプルギスの祝日=五月祭(メイ・デイ)である。
スカンジナビアの人魚の俗信、昔話をもう一度みておこう。参照するのはベンウェル/ウォー著『海の魔女 人魚と水の精の物語』である。『海の魔女』全15章の中、民俗・民話関連は地域ごとに4章が宛われている。第9章「英国諸島:イングランド・ウェールズ・アイルランド」、第10章「英国諸島:スコットランド」、第11章「外国:旧世界」、第12章「外國:新世界」。それぞれ20ページほどである。スカンジナビアは第11章の最初に充てられていて7ページ分、続いてドイツ3ページ、フランス5ページ、その他のヨーロッパ諸国(イタリア・スペイン・ロシアとエストニア)3ページ、アフリカ1ページ、中国・日本半ページとなっている。スカンジナビアの事例は、トマス・カイトリー(1789〜1872)『妖精神話学』(1850年、教養文庫『妖精の誕生:フェアリー神話学』、市場泰男訳、1989.9)、ウィリアム・クレーギー(1867〜1957)『スカンジナビアの民俗』(1896)、ベンジャミン・ソープ(1782〜1870)「北方の神々」(1851)を主たる引用先としている。これらの引用文献は現在ではグーグルによるインターネット・アーカイブで直接見ることが出来るようになっている。なお、クレーギーの著書は東浦義雄(1914〜)による抄訳『トロルの森の物語』(東洋書林、2004.11.10)があり、第5章「人魚と水馬」(pp.197〜232)には15話が収められている。「女性の人魚と男性の人魚」「すると人魚が笑った」「人魚の魔力に負けない工夫」「人魚との遭遇は不吉」「海に住む妖精」などである。東浦には『人魚と結婚した男−オークニー諸島民話集』(トム・ミュア著、あるば書房、2004.2.12、全63話中、人魚・ひれ人間・アザラシ人間関係の話は22話)という三村美智子との共訳書もある。
ベンウェルらはスカンジナビアではマーマンもマーメイドに劣らず語られることが多いと注意を促し、ドイツのニクセにあたるネックについて、音楽との関連事象を述べている。次いで、国別の事象にうつり、ノルウェーでは人魚はhavfrueで、嵐や不漁の前兆とみなされ、運悪く人魚を見てしまったら、仲間に話さず、火打ち石で火花を立てることで悪い結果を回避することが出来るとしている。また、人魚には予言能力があると信じられ、子どもの人魚(marmaeller)を捕まえた漁師は、予言を聞き出すために家に連れ帰る。男の人魚はhavmandで、緑か黒の髪と鬚で、人間に友好的だとされている。ネックに対してはお守りとして金属、特に鋼を用意する。
スウェーデンの伝説としては「グンナー騎士と人魚」がまず紹介される。西ゴットランドのアンテン湖中にあるロホルム城の城主グンナーは湖で溺れそうになったところを、人魚に助けられた。人魚はお礼として、同じ場所である日時に再会することを騎士に約束させたが、騎士は忘れて、現れなかった。怒った人魚は湖の水位を上げて城を水没させようとした。騎士は小船で脱出したが、船は沈没してしまい、その近くには大きな石があり、後に「グンナー騎士の石」と呼ばれるようになった。グンナーは湖の底で人魚と共に暮らしているという。スウェーデン王グスタフ1世(1495〜1560、在位1523〜1560)の義父エリック・アブラハムソン(?〜1520。娘マルガレータ[1516〜1551]がグスタフ1世の2番目の妻となる。)はグンナーの子孫であった。
スウェーデン女王マルガレータが生んだ10人の子どもの一人マグヌス公爵も人魚と深い関係のある人物である。イーヴァル・ハルストレム(1826〜1901)作曲の歌劇「マグヌス公爵と人魚」の主人公であるが、同名のバラッドが知られいる。人魚が提示する船、金・真珠・宝石を拒んだ公爵は人魚によって精神を狂わされてしまう。マグヌス公爵(1542〜1595)はグスタフ1世の成人した4人の息子の中で唯一スウェーデン国王とならなかった人物である。最初の結婚(カタリーナ・フォン・ザクセン=ラウエンブルク)の長男はエリク14世(国王在位1560〜1568、精神を病む)、マルガレータの息子はヨハン3世(在位1568〜1592)、次がマグヌス、末弟はカール9世(在位1604〜1611)。グスタフ1世が創始したヴァーサ王朝は7代のスウェーデン王と3代のポーランド王(始祖はヨハン3世の息子、スウェーデン王を兼ねたジグムント3世)を輩出した。マグヌス公爵と人魚については『海の魔女』に言及はない。
ドアから現れた女性の手をつかんだら、引きずられて海の底の家に連れ去られてしまった若い漁師の話が「海の魔女」スウェーデンの部分で次に語られる。手の主は人魚で、陸に残した漁師の妻が再婚することになり、漁師は家に入らないという条件で花嫁姿の妻を一目見ることを人魚から許された。堪えられなくなって家に入ってしまった漁師は屋根に潰され、3日後に亡くなってしまう。ウィリアム・ジョーンズ『古今本当のような話』からの引用である。
少年にネックには救済はないと言われたので、傷つき水の底で泣いていたネックだったが、少年の父親である牧師は救済はあると伝えるよう命じる。それを聞いて喜んだネックはハープを陽気に奏でるのであった。カイトリーからの引用である。
僧から土に突き刺した杖に花が咲けばネックも救済されると言われたが、奇跡が起こりついに花開き、ネックは喜びの余り夜中ハープを弾いたという同様の話もカイトリーのものである。
次いでデンマークの人魚maremindに移る。ベンジャミン・ソープは老漁師が実際母と子どもの人魚を見たことを伝えている。また、人魚は海の牛を飼っていて、陸の草を食べさせる。それを怒った人間が人魚と海牛を囲って、人魚の持つ宝石付の帯を渡さなければ自由にしてやらないと要求した。渋々交渉に応じた人魚であったが、その後に村を砂で埋めてしまった。陸に上げられたマーマンを教会墓地に埋めたところ、砂が噴き出し、その地が気に入らないことを示した。砂丘に埋め直すことで、不思議な災害は止んだ。ウィリアム・クレーギーからの引用である。
フィンランドについては魚を人々にもたらす海の神格アハト(アハティ、アハヴォ)から始まり、アハトの娘になったアイノが語られるカラワラの紹介へと続く。ワイナモイネンに求愛されたアイノは溺れて人魚になった。ワイナモイネンが釣り上げたアイノはサケに変身していて、釣り針から逃れた後は、ヴァラニオの人魚として海深く大理石の部屋で暮らすこととなった。(「カラワラ」第4と5章)
フィンランドの人魚も海で家畜を飼っているが、家畜たちは時に魚尾を持つ。また、水の精は前面は美しい乙女だが、背は鱗に覆われ鰭があると言われている。
ラップの人々の人魚様の海の女神はAkkrivaで、水面に浮かび髪を梳る姿が目撃され、時として海から川を遡上するが、その時は人々に大漁を恵むとされる。人魚たちは人間になったり魚になったりと、姿を変えて現れる。
アイスランドの人魚はmarmennillとして知られる。また、水馬はニクル、ニニルと呼ばれるが、蹄が逆方向に付いているのですぐわかる。アイスランドの北にあるグリムセイ島ではニクルは海に住み、人々が家畜をアイスランド本島に運ぶ時に現れ、水馬のいななきを聞いた家畜たちは海に飛び込んでしまうと信じられていた。アザラシが紅海で溺れたファラオとその軍隊が変身したものであるという俗信はアイスランド、フェロー諸島、シェトランド諸島で共通に伝えられている。フェロー諸島では20世紀に入っても、トロルや人魚を信じているとはネルソン・アナンデールが述べているところである。フェロー諸島に人魚がいることはLuke Debesが証言しているが、アザラシ乙女の方がより知られた存在である。アザラシ乙女は漁民の釣り糸を絡ませたり、釣り針を取ったりと、悪戯をする。人魚の髪は金か黒で、船に近づいて来るようであれば嵐になり、マーマンと一緒に泳いでいれば好天に恵まれる。人魚の歌は人々を狂わせるので、手袋の親指で耳を塞ぎ、難を逃れる。マーマンを捕まえて、逃げないようにして漁に出ると漁場の目安になるという。マーマンが船上で浮かれ出したり、指を海に浸したりすると大漁が期待できる。フェロー諸島の水馬ニクルは、その名ニクルを人間に呼ばれると魔力を失う。同様のことはスコットランド水馬ケルピーでも起こる。水馬は扱い方を心得ている人間にはおとなしく仕える一面もある。
以上が『海の魔女』スカンジナビア項記述のあらましであるが、ロシアの部分に併録されているエストニアの人魚についても見ておこう。エストニアの川の神Wokhandaは青と黄色の長靴下をはいた小男の姿をしている。またメリュジーヌと浦島の要素を持つ話が知られている。人魚と結婚した農民の末息子は海の底に住んでいたが、妻から人魚と呼ばないよう、また毎週木曜日には一人にして欲しいと要求された。その約束を破って木曜日に妻の姿を除いてしまった男に、人魚は別れを告げ、瞬時に陸に立った男は老人になっていて、死んでしまう。
異界・妖精の国の時間が人間世界の時間と異なっていることは多くの民間伝承で語られるが、北アメリカの人魚についてのレポートにも浦島型の物語があった。チャールズ・スキナー『アメリカの神話と伝説』(1902年)からの引用である。カヌーが沈み、湖の底で水の精と住むこととなったカンダワゴノシュは、陸の生活が忘れがたく、年老いた両親に一日だけ会うことを妻である水の精に願った。水の精は樺の箱を渡し、ベルトに付けて開けてはならないと言って夫を陸に送った。自分の村はなく、茂みの中に見つけた墓は自分自身のものであった。無意識に箱を開けると、煙がでて妻である人魚の形になり、悲しげな表情を見せたと思うと瞬時に消えてしまった。両親が墓を作ったときに愛犬を生きたまま埋めたのであるが、その犬が墓から現れ、カンダゴワノシュを墓の中に引き入れてしまった。地上の時間が一時に襲いかかり、老人となったカンダゴワノシュは生きていられなかったのである。ミシガン、グロス・カープ近郊の話である。
「合衆国の人魚、あるいは海の女性の研究」(1968年)は、インディアナ大学に学んでいた日本女性がウォレン・E・ロバーツ博士(1924〜1999)に提出した20ページの英文リポートである。1965年にアメリカ版が出版されたベンウェル/ウォー『海の魔女』も参照されている。このレポートは著者ご自身から最近ご恵贈を受けた。著者の日本の大学での卒業論文は「浦島説話」であった。「合衆国の人魚研究」の内容報告は他日を期したい。
エストニアの海の民話としては『うみの女王とまほうのスカーフ』(M.ザドウナァイスカ再話、B.シャトゥーノフ絵、宮川やすえ訳、岩崎書店、1991.4.25)が知られている。不漁に悩むエストニアの漁師たちが、海の女王と仲良しだったカーレルじいさんに相談する。カーレルは魔法のスカーフを渡し、一つ目の角を結ぶと船を進め、二つ目を結ぶと魚が集まるが、三つ目の角は結んではならないと教える。欲を出した漁師の頭が三つ目を結ぶと、巨大はカマスが一頭掛かり引き上げると、船は動かなくなる。海からは「しっぽなし山羊」が帰ってこないと声があがる。カマスを海に戻すと風が吹き荒れ、ある島に船は打ち上げられる。島の小さな老人の助力で自分たちの村に帰った漁師たちは約束を固く守るようになった。カマスを帰ってこない「しっぽなし山羊」 を呼ぶ所など、海の女神(人魚) は海で家畜を飼い、陸で放牧するというスカンジナビアの俗信に通じる要素がある。同様の話は「ほどいていけない結び目」(田辺佐保子訳、ヤン・タムサール絵、『バルト海地方の民話』ソビエトの民話集(1)、R.バブロヤン/M.シュームスカヤ/伊集院俊隆編、新読者社/ラードガ出版所、1985.12.20、pp.72〜94)という題になっている。カーレルじいさんがくれたスカーフは結び目が三つあり、一つ目をほどくと順風を運び、二つ目をほどくと魚を誘うが、三つ目はほどいてはならないというものであった。カマスが「しっぽのないやぎ」と呼ばれるなど、他の部分は全く同じである
『バルト海地方の民話』にはラトビアの「海の国のおよめさん」(富田知佐子訳、pp.26〜46)という話も収録されている。不漁の原因は九つ頭の怪物男であった。餓えを避けるために、総領息子を怪物のもとで働かせる約束をしてしまった。怪物は海の王を殺し、王国は魔法にかけられ、王女は怪物の虜となっていた。王女の助力で怪物を倒し、王女と結婚式を挙げることとなった若者は自分の親類に知らせに帰る。その時、王女から願いが叶う指輪を貰うが、王女のことを自慢すると良くないことが起こると忠告された。王女を自慢したために指輪をなくした若者であったが、ライメーがくれた魔法の靴により、めでたく王女と再会することが出来た。ここでも、約束を守らなかったことで、不測の事態に陥ることが語られる。
「海の国のおよめさん」ではライメーは薪の束を背負った老婆の姿で現れる。若者が気の毒に思い、背負うのを替わろうと申し出たので、魔法の靴と助言を授けた。「親せつな人をしあわせにしてくれる」のがライメーだと説明されている。G・アデグザンスキー、F
・ギラン『ロシアの神話 スラヴ・リトワニア・フィンランド』(小海永二訳、みずず書房、1960.12.15)p.99には次のような説明がある。「ライメーまたはラウメー、その名はリトワニアの民間歌謡になかに残っているが、これは運命と幸福の神である。特に若い娘や子供たちの運命と幸福についての。山々の上に現われて、人間たちに彼らを待つ不幸を予言するこの神について、いくつかの歌謡が歌っている。(中略)いくつかの歌謡や伝説のなかで、ライメーは《「太陽」にさらにいっそう明るさを与えている》。このことは、著述家たちに、ライメーがまた「月」の女神でもあったと想像させる根拠となる」。「海の国のおよめさん」のライメーの助言は「月」のところへ行って、魔法をかけられた国への道をたずねる、というものであった。
『バルト海地方の民話』には他に海から三つ頭、七つ頭、九つ頭のへびが現れて退治される「白いしか」(ラトビア)、小人姿のきのこの王様が、四つ足の竜、六つ頭の竜、十二頭の竜を退治する王子を助力する「きのこの王さま」(エストニア)、おばあさんからもらった、進む道を教える糸玉といくら食べても減らないパンのみみや、義兄弟の鷹・熊・カマスがくれたショール・壺の中の粥・金の箱の力を使って王子が太陽の女王と結婚し、更なる試練を経て幸福になり、月という子供を得る「太陽をすくいだした王子」(リトワニア)という話が収められている。「太陽をすくいだした王子」には、ババ・ヤガーのような「年よりの魔女ラウメ」が登場する。また、太陽の女王をさらった大男の力の源は鴨の卵にあるところはコシチェイ的要素も感じられる魔法昔話となっている。
ヴィクトル・ガツァーク編『ロシアの民話1』(渡辺節子訳、恒文社、1978.12.20)にも「バルト海沿岸とカレリア地方」の昔話が10編収められている。その一つ「川の母のおくりもの」(エストニア、pp.186〜188)は、孤児の貧しい娘が湖に住む「川の母」から小石をもらい幸福な結婚を得るという話である。他にリトアニアの「九つの頭の龍と九人の兄の妹」いう、複数頭をもつ怪物の話もある。バルト三国のメルヘン集には世界の民話(33)「リトアニア」(虎頭恵美子訳、ぎょうせい、1986.2.10、全77話)もあり、「十二頭の竜と王子」(pp.90〜100)という話も収録されている。
リトアニアの伝説・昔話で有名なものに「ユラテとカスティティス」がある。19世紀半ばに記録されて以来、多くのバージョンが存在するが、その内容は以下のようである。人魚とも考えられている女神ユラテはバルト海中の琥珀の城に住んでいた。漁師のカスティティスが配下の魚たちを沢山獲ることを怒ったユラテはカスティティスを懲らしめようとしたが、恋するようになり、琥珀城で幸せに暮らしていた(嵐から救ったカスティティスを恋するようになる、という話もある)。不死の女神が人間と恋仲になったことを知った雷神ペルクナスは雷を放ち琥珀城を粉々にしてしまい、ユラテを海底に鎖で繋いだ。バルト海から打ち上がる琥珀は、破壊された琥珀城の破片であるという(ペルクナスに殺されたカスティティスをユラテが悲しみ、その涙が琥珀になるともいう)。
アレグザンスキー/ギラン『ロシアの神話』pp.88〜94「リトワニアの主要な神々」では、特に崇拝されていた三神として、「海と水の神」パトリムパス(アオリムパス)、「悪と憎しみと死との神」ピクラス、「神々の王、天と地の王、自然の支配者」雷神ペルクナスをあげている。もっとも、同書では「A・ミエルジンスキー氏は、ペルクナスが他の神格たちより一段高い位置にいたということを否定する」とも述べている。
リトアニアには「ユラテとカスティティス」の銅像や首都ヴィリニュスの幸福をもたらす人魚像があるが、エストニアの首都タリンにもEdgar Viies(1931〜2006)の人魚像(Merineitsi)がある。自由と希望のシンボルとして親しまれている。1893年、タリンからヘルシンキへ向かう途中、嵐で沈没したロシアの戦艦「ルサルカ号」の祈念碑はカドリオルグの海岸に立っている。エストニア彫刻界の第一人者Amandus Adamson(1855〜1929)の作で、金の正教会十字架を持つ黒い天使が海を見つめている。
この様に人魚関連の昔話・伝説を拾って行くときに常に思うことは、各国はに人魚に興味を持つ人々がいて、しかも本にまとめているのではないか、それを知らず、また読めないのは、いわゆる識字能力がないのと同じで悲しいことだ、という素朴な感慨である。きょうせい『世界の民話』(全37巻)のような「世界の人魚」各国編(数十巻)が欲しいものである。
安諸 宏
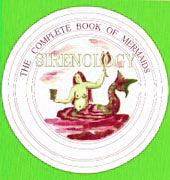
世の中にあるすべての本は人魚本である、という考えを持っている。本を読む、そこに人魚、およびそれに関連する語(水の精、メリュジーヌ、トリトン、セイレーン等々)が書いてあれば、それは人魚についての本である。また、何ら人魚に関連していなければ、人魚が出てこなかった本となる。「人魚が出てこない」ということが確認できれば、人魚文化を考える際に、空白、または負の要素として考慮できるので、これらは人魚本となる。そんなことを常に意識していると、不思議と多くの本に「人魚」の語を見つける。たとえば、ジョン・バース『ストーリを続けよう』(志村正雄訳、みすず書房、2003.4.21)p.271〜272「珊瑚礁の深さ五メートルのところにあった全く申し分のない女性用サングラスがのろい海流によって近くまで寄ってくる。誰かの小説か短篇の少し字の消えた一ページ(水に浸かっていたにもかかわらず、意味明瞭とは言えないまでも、少なくとも前後関係なしで判読できる)、まるでどこかの人魚が読書中に妨害されたような。」a perfectly satisfactory pair of women's sunglasses five meters deep on a coral reef and, lolling near it in the lazy current, a palimpsestic page from some novel or short story(more legible than intelligible, at least out of context, despite its immersion), as if some mermaid had been interrupted in mid-read(John Barth、“On with the Story”、Back Bay Books、1997、p.247)。川本三郎『荷風と東京 『斷腸亭日乘』私註』(都市出版、1996.9.5)p.413「それは花柳小説よりもむしろ泉鏡花の「高野聖」のような夢物語に近い。お雪は現実の女というより、雨と雪とともに忽然とあらわれた夢の女、水の精であり、「墨東綺譚」の言葉を借りれば、「お雪は倦みつかれたわたくしの心に、偶然過去の世のなつかしい幻影を彷彿たらしめたミューズである」。」。バースと人魚、荷風と人魚。なんでもありで文章が書けるが、今回は、ど真ん中の直球、田辺悟『人魚』(ものと人間の文化史143、法政大学出版局、2008.7.15)をめぐる話をしよう。
2008年7月7日(月)朝日新聞朝刊1面のサンヤツ(新聞広告用語。15段組み紙面の下部3段を横に8分割したもの。朝刊一面の下部に並ぶ書籍広告のこと。)、法政大学出版局の第1本目が「田辺 悟著 人魚(にんぎょ)」。「10日発売 フィールド調査と資料をもとに、各地に伝承される人魚の実像を追ったマーメイド百科。〈ものと人間の文化史143〉」とあった。田辺氏は「ものと人間の文化史」シリーズでは「海女」「網」の著がある民俗・民具学者。「フィールド調査と資料」と謳っているので、すごい内容になるのだろうと、10日(木)を楽しみに待つ。新宿、神田の大書店をまわるも、10日には入手できなかった。結局は、12日(土)、地元の書店で購入することとなった。そこでの入荷は3冊。しばらくしてから見てみると、他に一冊購入した人がいたことがわかる。
ブログではなく、既成メディアによる紹介・書評は、「出版ニュース」(出版ニュース社)が一番早かったと思われる。発行一ヶ月後の8月11日、通巻第2149号、p.22、「ブックガイド」の一番始めに紹介された(他には寺田道雄「知の前衛たち」、津野海太郎「ジェローム・ロビンスが死んだ」などで、全部で9冊の紹介がある)。「文献はもとよりヨーロッパやトルコなど人魚伝説の地のフィールドワークによる紀行文的記述も加え、この〈異形のもの〉の文化をうきぼりにする」と総括し、最古の人魚像が、アッシリアの男の人魚であることに紹介者(無署名)は興味を示している。次いでこの週の週末(8月17日、日曜)、神奈川新聞が読書欄で「人魚を知りたければ、この一冊で足りる。間口が広い。奥行きも深い」と最大級の賛辞で紹介した。人魚にまつわる話を「細大漏らさず集めて」くるが、「フリーク」ではなく「本来の研究の延長線上に」あり、人魚のミイラに対しても「学者の良心」「信仰一般への謙虚さ」で接していると紹介者(無署名)は伝えている。ミイラの他に紹介者が伝えているのは、日本の人魚伝説は、9割は八百比丘尼系統で、その他は人魚の報恩譚があるということである。著者田辺悟を「元横須賀市自然博物館・人文博物館館長。文学博士」と報じている(第16面)。
全国紙で紹介したのは読売新聞。9月7日(日)の読書欄で田中純が「人魚伝説や人魚をかたどった美術・工芸品などを幅広く渉猟した「人魚の百科全書」」とまとめている。田中は短い紹介文の中で人魚ミイラが明治まで日本の輸出品であったこと、人魚に入れ込むのは男性が多いことなどを伝えている。その田中は同じ頃、東京大学出版局のPR誌「UP」(第37巻第9号、431号、2008.9.5)pp.63〜67に「『リヴァイアサン』から『崖の上のポニョ』へ−ある象徴の系譜」(イメージの記憶13) を発表している。ホッブス『リヴァイアサン』の扉絵、人間の集合からなる巨人で表されたリヴァイアサンが伝統的な解釈、海の巨大生物とは異なっていることをカール・シュミットの解釈から始めて、扉絵では描かれていない海から現れたと思われる巨人の下半身が魚形で、この巨人は人魚かも知れないと提起する。そこで参照されるのが田辺悟の『人魚』である。文中には読売新聞での紹介文と同様の部分も見られ、全5ページの文章中、田辺『人魚』に話題が集中するのはおよそ2ページ分。その後、男性が人魚に強く入れ込む理由を説明するのにシャーンドル・フェレンツィの論文「性器論の試み」中の「タラッサ的退行」(ペニスは象徴思考としては魚であり、膣への挿入による母体内の海に回帰する。タラッサは「海」の意)、更に脊椎動物の進化史上の水中から陸上への生活圏移行に進み、人魚イメージの「想像力の論理」を解き明かし、『崖の上のポニョ』に及ぶ。「「降海の見果てぬ夢」と母胎回帰を同時に実現した男の娘が人魚となり、今度は逆に、系統発生的な「上陸誌」を再現しようとするのである」とポニョを紹介している。人魚は様々なことを考えさせる「観念連合」の場だとし、田中自身も「その虜になってゆくようである」を最後を結んでいる。
出版から一ヶ月ほどの間の田辺『人魚』の宣伝例を二つ見ておこう。平凡社PR誌『月刊百科』(550号、2008.8.1)表紙裏の4社の広告の中の一つには、「ロマンとファンタジーに彩られた世界各地に伝承される人魚の実像をもとめて東西の人魚誌を渉猟し、フィールド調査と膨大な資料をもとに集成したマーメイド百科」とある。また、春秋社PR誌『春秋』(501号、2008.8.25)巻末広告では「世界各地に伝承されるロマンとファンタジーに彩られた人魚の実像を求め、東西の人魚誌を渉猟し、膨大な資料をもとに集成したマーメイド百科。写真・図版200余点を収める」と謳っている。
人魚に引かれるのは男性に限るものでないことは明らかなことで、ことさら強調することはむしろ慎まなければならないはずであると思っている。『読売ウィークリー』(第67巻第40号、通巻3147号、2008.9.14)では片岡直子が「妄想をかきたてるマーメイド」の見出しで田辺『人魚』を紹介している(p.68。「この3冊にサプライズ」の1冊)。人魚に人は何故入れ込むかという田辺の問いに、片岡が注目するところは「子育てする人魚、櫛や鏡などの人魚の持ち物、妖しさを伴った挿絵」、山東京傳「箱入娘面屋人魚」から片岡が得る感想は「鯉との不倫の子が人魚だとか、人魚を嘗めて若返り乳が欲しい、だとか、日本人の先輩の発想の可愛らしさに、心がとろとろしてきた」である。自身では入手しなかったかも知れない「さりげない装丁」の本は、「カタログ的な面白さにおいても、あきさせ」ず、「愛らしさが定着している現在の人魚像を、ぐらぐら豊かにし、妖しく、揺らす」とまとめている。片岡直子は「詩人、エッセイスト」、『産後思春期症候群』で第46回H氏賞受賞。
次いで『人魚』が取り上げられたのは、日本経済新聞2008年10月15日(水)夕刊、「目利きが選ぶ今週の3冊」(7面)。井上章一が選んだ3冊の1冊(他は、大阪府立文化情報センター編『「プガジャ」の時代』、三橋順子『女装と日本人』)。短文での紹介は「人魚の記録は、古くアッシリア時代からある。日本でも、『日本書紀』に記録されていた。古今東西のさまざまな人魚伝説を、網羅的にしめしてくれる」というもの。星は3つ(読みごたえあり)。なお他の「目利き」、サイエンスライター竹内薫が選んだ1冊にニール・シュービン『ヒトのなかの魚、魚のなかのヒト』があったことを申し添えておこう。
「歴史研究」第50巻第11号(2008.11.10、歴研)p.73「私が推薦する本」として小川博が田辺『人魚』を紹介している。「人魚の百科辞典的な著作」で、「数多くの挿絵や写真も多く、楽しく読ませて頂ける」と述べ、特に「能登の舳倉島」の「人魚のハエ」に注目し、田辺の本来の研究領域、海女の研究との関連を示唆し、「歴史研究」という掲載紙と、日本史研究論文目録作成に長年従事してきた紹介者小川の立場を際だたせている。
田辺悟著『人魚』についての書評・紹介文はこれら以外にもあっただろうが、管見に入ってきたものだけをたどってみた。「この一冊で足りる」「百科全書」「カタログ的」「網羅的」「百科辞典的」と全ての紹介者が認める本書は、今後人魚について知りたく思う人々がまず手に取る書物であろうと思われる。その利用についての注意点と言うと大げさに過ぎるが、気になった点を少し述べてみよう。
田辺『人魚』p.54に以下のような文章がある。
まず、古文献とはいえないが、一般に『人魚の研究』と訳されている著作を紹介しよう。表題は「海の娘」だが、本の原題は、
Benwell(G) & Waugh(A): Tochter des Meere von Nixen. Nereiden, Siren ind Tritonen. 276p.1962
この本は、ベンウェルとワウスの共著で、一九六二年にドイツのハンブルクで刊行されたもので、刊行後すでに半世紀を経ているが、人魚の研究で質量共に本書を凌駕しているものは他にない。内容面でも日本の人魚の「根付」などにもふれており、幅が広い。
この他、図録としての『人魚』の本も出版されている。原著は、
Beatrice Phillipotto Mermaids text, Printed by Dai Nippon Printing Co.Ltd., Japan Russel Ash/ windward,1980
この書物も図録とはいえ、「最初の人魚」にはじまる史的背景が記述されており、ヨーロッパにおける人魚の足どりを知るために欠かせないテキストである。(第一部 ヒトと人魚−文学・歴史・民俗 第二章 古文献の中の人魚たち 西洋の古文献の中の人魚)
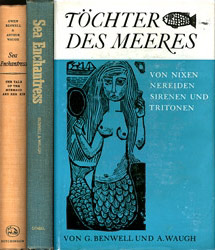 先に何点かの書評・紹介文をたどってきたが、この文章に気をとめた評者はいなかった。p.55に書影まで載せている『人魚の研究』(?)のオリジナルはドイツ語ではない。人魚に興味を持つ人なら誰でもが知っていようが、
先に何点かの書評・紹介文をたどってきたが、この文章に気をとめた評者はいなかった。p.55に書影まで載せている『人魚の研究』(?)のオリジナルはドイツ語ではない。人魚に興味を持つ人なら誰でもが知っていようが、
Gwen Benwell & Arthur Waugh、“Sea Enchantress : The Tale of the Mermaid
and her Kin”、Hutchinson、London、1961
が原著である。総頁数287である。1962年、ハンブルグのMarion
von Schroder VerlagからKlaus Birkenhauerによるドイツ語訳が出版された。田辺が紹介したドイツ語版の扉裏に、Aus
dem Englischen ubertragen von Klaus Birkenhauer・Die Originalausgage erschien
untrt dem Titel 《Sea Enchantress》Bei Hutchinson & Co., London 1961 by
Gwen Benwell and Arthur Waughと明記されている。アメリカ版はThe
Citadel Press(New York)、1965年刊である。総頁數は変わらないが、イギリス版で随所に収められていたモノクロ図版頁がp160とp.161の間に8葉まとめて収録されている。田辺が言及している根付けの写真は2つ。
15a Mermaid on a clam : netuke, early nineteenth century, signed Hideharu.
Courtesy of the Victoria and Albert Museum (15a Seejungfrau auf einer Muschel ;
Netsuke, Fruhes 19. Jahrhundert)
15b Octopus making love to a mermaida : netsuke. Courtesy of G.Bell & sons
Ltd(15b Tintenfisch bei der Werbung um eine Seejunfrau ; Netsuke)
本文では、英語版p.199、第11章「In Folklore Overseas:In the Old World」[China and Japan]で根付けへの言及がある。中国・日本合わせて21行、根付けの他の記事は、日本のマーメイドには前足があり、毛に覆われたマーメイドは「mu jima」といい、「ニンギョ」はTaiyan諸島海域に生息し、魅力的な人間の胸と魚尾を持つもので、貝に耳をあてて海の秘密を知る、などとある。ムジマとはなんであろう。まさかムジナのことではないだろう。Taiyan諸島とは、これまた聞き慣れないが、台湾のことであろうか。根付けという現物以外は、よくわからない情報が語られている。
著者グウェン・ベンウェル、アーサー・ウォーについて知る所はほとんどない。ともにフォークロアに興味を持ち、サー・アーサー・アレン・ウォー(Sir Arthur Allen Waugh、1891〜1968)はインド植民地行政に携わり、フォークロア協会の会長も務めたことぐらい(それも正確かどうか分からないのであるが)しかわからない。ただ彼等の著書は人魚研究の基本書であることは、キャサリン・ブリッグズ『妖精事典』(冨山房、1992.9.28)「マーメイド」項で触れられている通りである。「この長い時代にわたる複雑なテーマを研究したいと思うならば、グウェン・ベンウェルとアーサー・ウォーによる『海の魔女−人魚とその一族の話』(1961)を読むことから始めるとよい。この書物は、魚の尾をした神々から始まり、古典時代の神話および初期の動物学を扱ったあと、マーメイドやそのほかの海の生き物にまつわるほとんど世界各国の最近の信仰にまで言及している」(p.369、井村君江訳)。
アーサー・ウォーは小説家イーヴリン・ウォー(Evelyn Waugh、1903〜1966)の父(1866〜1943)と同名であるが、別人である(イーヴリンらのウォー家については、2004年にイーヴリンの孫アレクサンダー・ウォーが『Fathers and Sons』という本を書いている)。アヴラム・デイヴィッドス(Avram Davidson、1923〜1993)も人魚についてのエッセイの中で次のように述べている。
When I say “major mermaid sightings,”I mean, those which were for one thing written down,and for another, were reported in the very good book, Sea Enchantress: The Tale of the Mermaid and Her Kin, by Mr.Owen(ママ)Benwell and Sir Arther Waugh, and published by The Citadal Press, N.Y., in 1965. (The authers are described as “both prominant members of the Btitrish Folk-Lore Society −Sir Arther has been its Presidennt − and have devoted several years to collected mer-legends of all times and places.” I don't know if Sir Arther is any relation to Evelyn Waugh, whose father was also named Arther, but who was not a sir and died many years ago. )
[Avram Davidson、“Adventures in Unhistory”、Tor、2006、pp.286〜287]
デイヴィッドスンはグウェンをオーウェンと間違って記憶しているので、ミスターを付けているが、グウェンは女性だろう。なお、デイヴィッドスンのエッセイはジャック・ダン、ガードナー・ドゾワ編のアンソロジー『マーメイド!』の巻頭に置かれた(Jack Dann & Gardner Dozois、“Mermaids!”、Ace Fantasy Books、1986、‘The Prevalence of Mermaids’)。
なお、ウォーらの著書が『人魚の研究』と一般に訳されていることは寡聞にして今まで知らなかったし、「人魚の研究で質量共に本書を凌駕しているものは他にない」と断言しきって良いのかもわからない。例えば、2007年にアメリカ版2版が“Seduction and the Secret Power of Women :The Lure of Sirens and Mermaids”という題で出版されたメリ・ラーオの著(初版はイタリア語。1985年出版)や、日本語訳もあるド・ドンデの『人魚伝説』、田辺があとがきでも触れている松井魁著『伝説と幻を秘めた人魚』(1983年)なども日本で人魚について調べる際にはおろそかに出来ない著書であると思う。
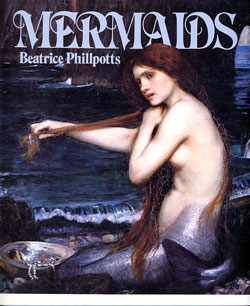 田辺が触れている2番目の文献は、巻末「引用文献」の書影では「ベアトリーチェ・ヒルポッツ『マーメイド』ルーシェル・アッシュ・ウインドワード、1980年」と説明されている(p.332)。著者Beatrice
Phillpottsは普通ビアトリス・フィルポッツであり、日本語では『妖精たちの物語』(原書房、2000.7)、『魔法使いになるための魔法の呪文教室』(東洋書林、2004.9)の2点が出版されている。フィルポッツはイギリスの編集者で、妖精画についてなど10数点の著書がある。手許にあるフィルポッツ『Mermaids』はアメリカBallantine
Booksのペーパーバック版(初版はイギリス、ラッセル・アッシュ、1980年)であるが、全96頁、カラー図版は口絵も含め33点、モノクロ図版69点、巻末Further
Reading13点にはベンウェル/ウォーの著作も当然含まれている。なお、『Sea
Enchantress』のSelect Bibliography(pp.279〜280)には34冊が挙げられているが、古いものは1625年刊、新しいもので1953刊である。ドイツ語版ではこの参考文献は省略されているが、各章ごとの引用文献がまとめられている。原著では脚注として印刷されていたものをまとめたものである。原著にある索引もドイツ語版では省略されている。
田辺が触れている2番目の文献は、巻末「引用文献」の書影では「ベアトリーチェ・ヒルポッツ『マーメイド』ルーシェル・アッシュ・ウインドワード、1980年」と説明されている(p.332)。著者Beatrice
Phillpottsは普通ビアトリス・フィルポッツであり、日本語では『妖精たちの物語』(原書房、2000.7)、『魔法使いになるための魔法の呪文教室』(東洋書林、2004.9)の2点が出版されている。フィルポッツはイギリスの編集者で、妖精画についてなど10数点の著書がある。手許にあるフィルポッツ『Mermaids』はアメリカBallantine
Booksのペーパーバック版(初版はイギリス、ラッセル・アッシュ、1980年)であるが、全96頁、カラー図版は口絵も含め33点、モノクロ図版69点、巻末Further
Reading13点にはベンウェル/ウォーの著作も当然含まれている。なお、『Sea
Enchantress』のSelect Bibliography(pp.279〜280)には34冊が挙げられているが、古いものは1625年刊、新しいもので1953刊である。ドイツ語版ではこの参考文献は省略されているが、各章ごとの引用文献がまとめられている。原著では脚注として印刷されていたものをまとめたものである。原著にある索引もドイツ語版では省略されている。
江戸時代の人魚については花咲一男『江戸の人魚たち』が最重要な著作であることは衆人の一致するところであり、田辺も江戸時代に関しては多くを同著によっており、「同氏(花咲)は同書(江戸の人魚たち)の中で、謙遜されて、管見であるがなどと記されているが、実に博識多才である」(p.221)と賛辞を呈しているが、どうも先行研究である松井魁の業績は参照するだけで、正当に評価していないような気がしてならない。それは、人魚に興味を持ち始めた初期に松井氏の著から多くのことを学んだ私自身の個人的感想かも知れないが、「松井魁氏の同著書を拝読し、類書が多いことを知ったが、あわせて、これまでの「人魚の本」は、人魚のことが「あの本にでてくる」、この「資(史)料にのっている」といった程度の紹介にとどまっていることがわかった。そこで著者は具体的に、時間をかけてでもできるだけ現地調査・取材を重視した内容の「人魚の本」をまとめたいものだと考えるようになった。」(p.336)との「あとがき」には強い違和感がある。文献・資料は調査の結果・業績であり、その尊重なしに研究を進めてはならない。文献調査をもう少し丁寧に行えば、もう少し広がりのある「人魚の本」ができあがったのではなかろうか。例えば、イギリスの妖精研究の井村君江やブリッグズの業績は参照されていない。荒俣宏の引用文献が『セクシーガールの起源』だけであるのも寂しすぎる。また、博物学関連の磯野直秀、本間義治、妖怪研究の湯本豪一(文中で言及されているが)、アダム・カバット、イギリス文学の松浦暢(水の精の系譜研究)あるいは高宮利行、仏蘭西文学篠田知和基、ドイツ文学者九頭見和夫、ロシアフォークロアの塚崎今日子、山海経研究の伊藤清司、浦島研究の林晃平、ピアニスト青柳いづみこ、植物学者日野巌など、多くの先行研究者がいるが、巻末参考・引用文献には見られない。
また、あらゆる書物は人魚本である。白川静『中国の神話』は中公文庫で容易に手にすることが出来る本である。読み始めてすぐに、「禹もまた、人面魚身の神であったと思われる。黄河中流の最古の土器文化である彩陶に、人面魚身の図が多く描かれているが、それが禹の神像であったと、私は考えている」(p.20)の記述に出会う。白川の解釈はともかく、中国の彩陶にある人面魚身の図は、田辺の「今日までのところ、世界で最も古いとされる、アッシリアのコルサバート宮殿址から発掘された紀元前八世紀の人魚像(オアンネス)は、その浮き彫りに、はっきりとした長い髭をはやしている男の人魚であることがわかる」と矛盾しないだろうか。この部分を田中純は肯定的に言及している。だが、フェミニズムの研究家なら、こうも言うであろう、「the Babylonian fish goddess Tiamat」(Jane Caputi、“Goddesses and Monsters:Women, Myth, Power, and Popular Culture”、Popular Press、2004、p.25)。人魚に引かれるのは、田辺が言うような男性が多いわけではない。男性に取って代わられた強さを示す原初の女性人魚を強調する立場も多い。その強さが残っている、または復活したのが、アフリカ、オセアニア、中南米、北極圏の人魚たちであろう。
田辺は博物館関係者(元横須賀市自然博物館・人文博物館両館長)である。その田辺が、2008年からの巡回展「Mami Wata:Arts for Water Spitits in Africa and Its Diaspora」のことは無理でも、2007年5月から2008年1月までアメリカ自然史博物館で開催された「Mythic Creatures:Dragons、Unicorns & Mermaids」や1987年の巡回展「The Tale of the Mermaid」、ヴィック・ド・ドンデも関係したCGER画廊(ブリュッセル)での展示「Sirenes」(1992年11月〜93年2月)、1995年ディエップ、城の美術館での「Avez-Vous Vu les Sirenes? 」展(6月から9月)、国内各地での妖怪展、2004年川崎市市民ミュージアム「日本の幻獣」展(7月〜9月)、国立科学博物館「化け物の文化誌」展(2006年10月から11月)に言及しないのは寂しい。第二部第九章「美術館の人魚」(pp.183〜193)で国内、世界各地の美術館の人魚を紹介しているのだから、人魚をテーマにした展示へも踏み込んでもらいたかった。少なくとも直近のアメリカ自然史博物館でのユニークな展示は現在の人魚研究の方向性を窺うにも好都合な企画であり、紹介されるべきだと私には思われた。「Mythic Creatures」では、最近の子供用人魚概説書でも触れられているマミ・ワタ及びカリブ海諸国のアフリカ系住民が信仰する人魚形の精霊、イヌイットのセドナ、Taleelajuq、アボリジニーのYawkyawk、バニップ、ネイティブ・アメリカンのMishepishu、そして日本の河童、アステカのAhuizotlなど、ヨーロッパのマーメイド主体の概説より、現在進行形の信仰、または美術・工芸品として制作されている形象、今まで研究が手薄であった文化圏での検証が行われている。その意味では、多くのブログが追跡している日本のマンガ作品での人魚像などは最適のテーマかもしれない。また、児童文学、絵本の人魚に関する総合的な研究、または紹介さえまだまだ少ない。アンデルセン人魚姫、小川未明「赤い蝋燭と人魚」に集中しすぎている。
今後の方向性として田辺は「人魚辞典(事典)」の完成、文献目録のデータベース化、「人魚国の知的共有財産」化を「人魚ファン」に呼びかけている。「人魚ファン」という言葉を田辺は何度か使っているが、私には奇異に聞こえる。人魚に関心のある人、人魚に興味を覚え何らかの探求をしている人、その多くの人がネット上に情報を載せている。それらを検索すれば「辞典(事典)」程度の内容は既に手に入れられるだろう。文献もある程度ネット上で追跡することが現在でも可能であろう。それで十分ではなかろうか。それ以上は、個々の楽しみの領域であって、学問化や権威のために人魚を使うことには些かためらいを覚える。いや、私自身はそうしたくない。人魚に興味を覚え追跡した古人の足跡、進行中の研究、それらを個人として辿り、楽しむ、そして時に報告し、必要な人だけに届くだろうと思いを馳せる、それだけである。完成や総合化は私には無用である。辿った結果が、そのように見えれば、それはそれで良いのだが。田辺氏もコレクションを語り、人魚ミイラ、伝説の地を訪ねる文章は生き生きとしている。少しだけ視線、姿勢が私と異なっているだけである。新しい知見も教えていただいた。多くの人がまずは手にしやすく、長く在庫できるシリーズの一冊が出版されたことは楽しみがまた加わった。素直に歓迎しよう。
なお、ベンウェル/ウォーの『Sea Enchantress』、松井魁『伝説と幻を秘めた人魚』、アヴラム・デイヴィッドスンのエッセイについては他の機会に述べることとする。
安諸 宏