�����l�`��y�����������Ȗ��M

INDEX��36P
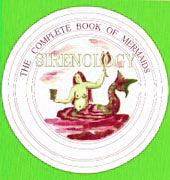
�@�P��̏H�̉����A����͉��l�B�u���x�c�ē�i�u��̉ԁv����ɁA���łɐl������q���Ƃ������Ƃŏo���������A�����͑䕗���a�B�A�_���Y�E�t�@�~���[�Ȃ�A�ō��̓V�C�Ƃ������ƂɂȂ邪�A������͖}�l�A��ςȂ��ƂɂȂ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�܂��́A�݂ȂƂ݂炢�����{��ʂ�w���ԁA�o���R����J�̒����V���u���֕����A���l�J�`�����ّO�̖k���������X�g�����u�X�J���f�B�A�v�ցB�X�܂̊p������āA�R�y���n�[�Q���̐l�������̃��v���J���u���Ă���B���s�̂l����́A�l���̑��ɕs�v�c���邱�Ƃ�����B��{�̑���ƒ������ɕh������A�d�Ȃ��Ă���l�q�������[���B���Edvard Eriksen(1876�`1959)�̃T�C�����������ꂽ�A��⏬�U��̃��v���J�ł���B
�@�R�y���n�[�Q���̐l���P���́A�J�[���Y�o�[�O�E�r�[���̂Q��ڎВ��J�[���E���R�u�Z��(1842�`1914)�������ƃG�Y���@�[�h�E�G���N�Z��(1876�`1959)�ɐ�����˗����A1913�N�Ɋ��ꂽ���̂ł���B���R�u�Z���̓n���X�E�x�b�N�̃o���G�u�l���P�v(1909�N12������)�Ɋ������A�v���}�h���i�A�G�����E�v���[�X(Ellen Price�A1878�`1968)�̖ʉe�𑜂Ɏc�����Ƃ���]�����B�G���������̃��f���ɂȂ邱�Ƃ����̂ŁA�痧���̓G�����A�̂͒����Ƃ̍ȃG���[�l�E�G���N�Z�������f���Ƃ����ƌ����Ă���B�R���T�v�́u�G�����E�v���[�Y�̋r�����܂�ɔ����������̂ŁA�G���N�Z�����l���P���̔��h�𑫐悾���ɂ����A�Ƃ����b�����邪�{�����ǂ����͂킩��Ȃ��v(�u�l���P���̒a���v�B�u�A���f���Z�������v��17���A1996.6�App.46�`51)�Əq�ׂĂ���B
�@�G���N�Z�������S�ȃ��v���J����邱�Ƃ��ւ������߁A���E���ɂ���͑���80%�ɏk������Ă���B�J���t�H���j�A�̏��f���}�[�N�A�\�����@���O(Solvang)�ɂ���l���P��������ȏk�����v���J�̈�ł���A���{�e�n�ɂ����̂����݂���B���`�A�V�ێR�}�[���C�h�L��ɂ��鑜�́A1995�N�A�R�y���n�[�Q���`�Ƒ��`�̗F�D�L�O�ɃJ�[���X�o�[�O�Ђ��瑡��ꂽ���̂ł���B�q�~�s�A�q�~�`�{������(1997�N�V��18���J��)���`�{���ΐl���̓��A����s�A�f���p�[�N(����s�Y�ƕ��������A1997�N�S��29���J��)�������ɂ��A�l���P���v���J�͂���B�o�ʃ}�����p�[�N�j�N�X�̃j�N�X����A�D�y�w�R���R�[�X�Ȃǂɂ�����B80%���v���J�̓l�b�g��500���~�قǂŔ̔�����Ă���̂ŁA�܂��܂����ɂ����邾�낤�B
�@�l���P���͐ؒf���ꂽ��A�y���L��������ꂽ�萔�X�̎����Ă������A2005�N�Ɏp���������l�������j���[�W�[�����h�ɂ���B�k�����������C�݁A���C���ŗL���ȃz�[�N�X�x�C�n���̃l�C�s�A�s�ɂ���Ïʂ̉����p�j�A��������ł���B�C�̉����p�j�A�͓��v�ƂƂ��ɗ��ɏオ��A���̏o�O�ɊC�̐l�X�̌��A���Ă������B����ł́A�C�߂��̃t�J�����f�R�̉��ɂ������͂ɐ����鈟���̖݂ɂ����g���B���Ă����B�����A�̂ǂ̊������o�����j���p�j�A�������v�w�ƂȂ����B�p�j�A�͍��܂łƓ����悤�ɒ��ɂȂ�ƊC�ɋA���čs���A�[�ɂ͕v�̌��֖߂��Ă���̂ł������B��l�̊Ԃɂ̓}���}���Ɩ��t����ꂽ���q�����܂ꂽ�B�v�͑��q���C�̐l�X�Ɏ����̂ł͂ƐS�z�����p�t�ɑ��k�����B���p�t�͍ȂƑ��q�ɗ��Œ������ꂽ�H�ו����A��l���Q�Ă���ԂɌ��ɓ����ΊC�ɖ߂�Ȃ��Ȃ�Ƌ������B�������A�\���ɉ������Ă��Ȃ������̂��A�v��͂��܂��������A�p�j�A�͂���ȗ���x�Ɨ��ɏオ���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ������B���q�̃}���}���͑S�g�т̂Ȃ��҂Ƃ����Ӗ��̖��������Ă������A�t�J�������̈ÏʂɏZ�ގL�ɂȂ����B���t�������p�j�A�̓`�������ƁA�������̎��͈Ïʂ̊��Ƀp�j�A�̎p�����邱�Ƃ�����Ƃ����B���邢�̓p�j�A�͊�ʂɎp��ς��ėl�X�ȋ������ɏZ������Ă���Ƃ����B�g�̂̊e�����ɂ���ĈقȂ�����ނ̋��ނ��ߊl�ł���Ɠ`�����Ă���B
�@�p�j�A�̑����������ꂽ�̂�1954�N�U��10���ŁA�}�I���̖����ߑ��ɐg�����w�������f���ɂ��ăC�^���A�Ő��삳�ꂽ�B���̑���2005�N10��27�� �A���܂�Ă��܂����B�K��11���S���Ɍ������A16���ɂ͌��̏ꏊ�}���[���E�p���C�h�ɐ����邱�Ƃ��o�����B���̓l�C�s�A�̊ό������ŁA���̑��ł�Ɨ������A����ƌ����Ă���B
�@�Ȃ��A�l�C�s�A�̓l�s�A�E�e�B�b�V���̌̋��ł���B���q�����̊֘A���Pan Pac Forest Products Limited�̓l�C�s�A�s�̖k���ɂ���A�p���v�`�b�v���l�C�s�A�`����k�C���֗A�o���Ă���B
�@�X�J���f�B�A�ő��߂̒��H���ς܂��A�������̉��l�J�`�����قŎ��Ԃ��߂����B���̌�A��J�̒����C�ݒʂ��`�F�R�f��Ղ̉��A���l���p�ق��������A�J�r�͌������𑝂�����ł������B�����Ƀ^�N�V�[���E���A���p�قɓ����B�ړI�̉f��u��̉ԁv�͂R��������Ȃ̂ŁA�u�V�������A���X���Ɣ��p�v�������ƌ����B�W���A���E�~���u�l�Ӂv�ɐl������������Ă����B�V�C�������A�Ղ��肳�̐l�������{�����Ă��������������A�܂��̋@��ɂ��āA���N�`���[�z�[���։���čs���B
�@�f��u��̉ԁv�͌���J�����E�����~�[���E�G���x��(1811�`1870)�A�ē�F�DA�D�u���x�c�A2000�N���J�̃I���j�o�X��i�ł���B���̓`�F�R�͓̉��̉f�悾�Ǝv���Č��ɍs�����̂ł��邪�A���ꂾ���łȂ��A���b��f�ނɂ����V��i���A���{�̕S����̂悤�ɘX�C�������Ȃ��瑱���A�Ō�͕S�S��s�G�����J���悤�ɍ��܂œo�ꂵ�����b�`���̏Z�l�����������ɗ��������ʂ��W�J���Ė������߂�Ƃ����悤�Ȏ�̍�i�ł������B���̂悤�Ɍ��āA�\���m�����Ȃ������̂ŁA�{���͐������o���Ȃ��̂ł��邪�A��ɒm�������Ƃ�t�������Ă������B
�@����҃G���x��Karel Jaromir Erben�́u�`�F�R�̎��l�ŗ��j�Ɓv�u�v���n�s�̏���Õ����ۑ����v�B�u�`�F�R�̖��w�v(1841�A43�A45�N)�A�u�`�F�R���O�̉̂Ǝ��v(1864)�A�u�X�����������̘̐b�Ɠ`���v(1865)�Ȃǂ̃t�H�[�N���A����������B���̌����̉ߒ��ŁA���b����������W�u�ԑ��vKytice(1853)�\���Ă���B���}����`���w�̉^������19���I���������ł̓t�H�[�N���A���̖��b�W�A���W�����s�ƂȂ�A�X���u�����ł����l�̌��ۂ��N�������B���w��i�̓I�y���A�������Ƃ������y�A�܂��G��ƘA�����A���̗d�����l�������u�[���ƂȂ������Ƃ͐����Â݂��w���̉��y�|�I���f�B�[�k�ƃ����U���h�x(�݂������[�A2001.9.)�ɏڂ����B
�@�f��̌���ƂȂ����u�ԑ��v��13�҂̎��ō\������Ă��邪�A�u���x�c�͂�������A�u�ԑ��vKytice�A�u���̐�(�͓�)�vVodnik�A�u�ԉňߑ��vSvatebni kosile�A�u�^���̖����vPolednice�A�u���̎��ԁvZlaty kolovrat�A�u���̎vDcerina kletba�A�u�N���X�}�X�E�C���vStedry den�̂V�̃G�s�\�[�h��I�B�f��ȑO�Ɂu�ԑ��v����z����i�ɉ��y���������B�h���H���U�[�N��Ȍ������u���̐��v�u�^���̖����v�u���̖a���ԁv�u��Ɓv�A�����I�J���^�[�^�u�H��̉ԉŁv�A�t�B�r�t��ȁu���̐��v�A�}���e�B�k�[��ȃo���G�E�J���^�[�^�u�H��̉ԉŁv�Ȃǂ��m���Ă���B
�@���āu���̐�(�͓�)�v�͎��̂悤�ȕ���ł���B�Ώ��Ȃɕ�ƏZ��ł���������������悤�Ƃ��Đ��ɗ����A���̐����H�h�j�[�N�̍ȂƂȂ�B���H�h�j�[�N�ɂ͐�Ȃ������悤�ł��邪�A��l�̊Ԃɂ͒j�̎q�����܂ꂽ�B��ɂ�����x������Ƃ̎v�����̂�A���͈�������̋A������H�h�j�[�N���狖�����B��͖����ƂɂƂǂ܂点�悤�Ƃ���B�}���ɗ������H�h�j�[�N�ɉƂ̌˂��J����邱�Ƃ͂Ȃ��A�˂��ĂъJ����ꂽ�Ƃ��́A���̐��Ƃ̎q�͎��̂ƂȂ�A����o�������ΐ��ƍ������Ă����B
�@�����V�[���͎��ʂ̂悤�ŁA���H�h�j�[�N�A�����A�j�̎q�͐��̒��ʼn����Ă���悤�������B�b�̗����ǂ����Ƃ݂̂ŁA�ו��ɒ��ӂ��s���͂��Ȃ��������A�����A���Ă����ƂɐԂ��ь炪���������Ƃ͊o���Ă���B��̈��͉f��u��̉ԁv�ł̊�ƂȂ�e�[�}�ł��邪�A�يE�֍s�����҂����߂��Ƃ����v�����܂����̈�ł���B�`�F�R�̃��H�h�j�[�N�͋ߔN�z�C�ȃL�����N�^�[�Ƃ��ĕ`����邱�Ƃ����邪�A�{�����̐��͎��������炷�댯�ȑ��݂ł������B�G���x���̎���i�u���̐��v�͂ǂ��ł����������Ă݂悤�B�K���T�C�����E���g���w���A�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c���t�u�h���H���W���[�N�������W�vCD(TOCE-55738�E39)���C�i�[�m�[�c�ɂ͊֍����o�j(1929�`�A��w���m�A�`�F�R���������ƁA���i�[�`�F�N�E���_�����)��u���̐�(���H�h�j�[�N)�v���ڂ��Ă���B����ɂ��Ɓu���̐��v��60�A�̃o���[�h�œ��e����S�̕����ɕ�������B��1�����͌ΔȂ̃|�v���̎���Ń��H�h�j�[�N�����g�̌����ߑ�����������̉��D���Ă���B�����̋��j���ɂ͐l�Ԃ̉ԉł��}���悤�ƐS�Ɍ��߂Ă���B��Q���A���j���̑����A�ꂪ�~�߂�̂��������A���̓X�J�[�t���ɐɍs���B���������ꖺ�͐����ɒ��ށB�|�v���̎���ł̓��H�h�j�[�N�����@���B��R���͂��̃o���[�h�̒��S�����ň�Ԓ����A31�A���₵�āA�����Ŕ߂��݂̐����𑗂閺�̐S��`���Ă���B��e�͖��̉ł��p���v���`���Ă������A���̖��͐��̐��̐��E�Ɉ���������A�y���݂�D��ꂽ���X�𔖈Â����E�ʼn߂����Ă���B���܂ꂽ�q�����B��̊�т����A�߂��݂̉̂��̂�����B���H�h�j�[�N�͂��ɒn��ł͒N���������A�閾������[���܂ŁA���̊Ԃ͎q�ǂ��͐��̐��E�ɒu���Ă����Ƃ��������ŕ�e��K�₷�邱�Ƃ��������B��S���ł͕�e����i�����킵�Ă��܂����Ȃ̌������H�h�j�[�N�͂R�x�K�˂邪�A��e�͖����A�点�邱�Ƃ͂Ȃ������B��e���u�E�l�S��A�ɋ���I�����̖��͂ǂ��ւ����ʁG�Ԏq�������Ă���Ȃ�A�����֘A��Ă��邪�����v�ƌ����ƁA�͗��ƂȂ�A�Ԏq�̋��������~�݁A���̉��ɉ����������鉹�������B�u��̕��̂����C�̒��Ɂ@���낵���őS�g�Ɉ���������G���̂̂Ȃ��Ԏq�̓��Ɓ@���̂Ȃ������ȑ́B�v���ꂪ�ŏI�A�̌��t�ł���B
�@�`�F�R��́u���̐��v�N�ǂ́A�t�B�r�t��Ȃ̃����h���}CD�ŕ������Ƃ��o����(Supraphone Records�ASU 1922-2 911)�B���B�[�`�F�X���t�E�m���@�[�N(1870�`1949)��Ȃ̌������u�^�g���R�ɂāvOp.26�u�i���̓���vOp.33�ƃY�f�j�F�N�E�t�B�r�t(�t�B�r�q�A1850�`1900)�̃����h���}�u���̐�Vodnik�vOp.15�u�N���X�}�X�̓�Stedry Den�vOp.9�����^����Ă���B���t�̓J�����E�V�F�C�i(Karel Sejna�A1896�`1982)�w���`�F�R�E�t�B���B�u���̐��v�̘N�ǂ̓��@�[�c���t�E���H�X�J(Vaclav Voska�A1918�`1982)�ŁA�G���x���̎��̔w�i�Ƀt�B�r�t���Ȃ�t���Ă���(1883�N)�BVodnik�̉p����The Water Goblin�B�u���̐��v��1959�N6��15���A�v���n�ł̘^���ł���BStedry den���G���x���́u�ԑ��v����̎��ŁA�f��u��̉ԁv�ʼnf�������ꂽ�B
�@�}�V���[�E�A�[�m���h�́u���ނ��ꂽ��Y�̐l���v(Matthew Arnold�AThe Forsaken Merman�B�X����B�u�R�M�g�v��87���A1939.8.1�App.45�`53)�̐l�Ԃ̍Ȃ́A����̏��̒��ׂ��āA�����ĊC�ւ͖߂�ʊo��ŁA�����Ղ̎����ɐl�Ԑ��E�֖߂��Ă������A�`�F�R�ł͕�e�̋����ӎu������n��ɗ��܂点�邱�ƂɂȂ����B���̌��ʃ��H�h�j�[�N�Ƃ̊Ԃ̎q�̖��������悤�Ƃ��B�A�[�m���h���ł͕��e�l���͎q�ǂ��ƂƂ��ɒ��߂ĊC�ɋA���čs�����̂ł��邪�B�u�������Ɉ��������Z�܂ӁA���͂ꂻ�͂�Ȃ��āA�i�ւɉ��u������ʁ@�킾�C�̉����̂����v�ƃA�[�m���h�͎������B
�@�G���x���̎��A��24�A�́u�����ĕv�́c�������ƁI��n�̏�����ԔG��ł������A�̒��ŏ����Ț�Ɂ@���߂���ł�͐l�̍��B�v�Ƃ��邪�A�����ɓ���ĉB���Ă��鐅�̐��ɖ���������������鏗���̕��ꂪ�V���e�p���E�c�@�t����(1932�`1999)�̊G�{�w�ʂ܂̂����Ԃ@�{�h�j�b�N�x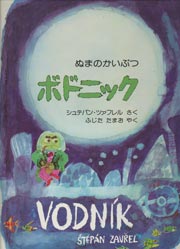 �ł���(Stepan
Zavrel�AVodnik�A1970�B���c�\�Y��A�ق�Տo�ŁA1978.7.10)�B
�ł���(Stepan
Zavrel�AVodnik�A1970�B���c�\�Y��A�ق�Տo�ŁA1978.7.10)�B
�@�X�̉��ɑ傫�ȏ�������A�����ɂ̓{�h�j�b�N���Z��ł����B���݂̊ɂ��鐅�ԏ����ɂ̓}�����Ƃ���������l�Z��ł��āA�N�z���c�@��������\�����B�{�h�j�b�N�̓}�������q���̂��납��˂���Ă��āA��l�ɂȂ�����ȂɌ}���悤�ƓƂ茈�߂��Ă����̂ŁA���̋���Ō������������悤�ƃ{�[�g�ŏ���n��}�����ƃz���c�@���P�����B����͓y�j���̂��Ƃł������B�{�h�j�b�N�̓z���c�@��o���̏X�����ɕς��A�}�������Ȃɂ��Ă��܂����B�}�����Ƃ̌������ɂ́A�{�h�j�b�N�͂��˂ėp�ӂ��Ă����V�����Ԃ��C�𗚂��ďo�Ȃ����B���ɕς���ꂽ�z���c�@�̍��͊W��������ɓ����ꂽ�B�{�h�j�b�N�̓}�����ɑ����̎d�������������B��������Ȃ��Œ��ɑo���̋��ɏo�����A���̎p�ɖ߂����ƁA���g�����������Ă����R�̖��@�̕���g�����Ƃɂ����B�����̕�́A�ȑO�Ƃɔ��߂Ă��������k�����������̂ŁA���A��A�D�̎O�ł������B�������āA�����{�h�j�b�N�Ɋ����t����ƁA�����͂����ɖ����Ă��܂��A����₩��������ƁA�z���c�@�͐l�Ԃɖ߂����B�Ɨ��̐��������������������̂ŁA�C���t�����{�h�j�b�N�̓E�i�M��h�����ăz���c�@��߂܂��悤�Ƃ����B�D��U�肩�����ꂽ��l���A�傫�ȊI�������ǂ������Ă����B����ǂ̓�V���Ő蔲������l��ǂ��āA�{�h�j�b�N�͐��ʂ����яオ��n��ɏオ���Ă��܂����B�{�h�j�b�N�ɂ͑��z�̌����V�G�ł���B�n���ď����Ȑ����܂�ƂȂ����{�h�j�b�N�́A���̐��������ĉi�v�ɏ����Ă��܂����B�����̂��Ȃ��Ȃ������ԏ����Ńz���c�@�ƃ}�����͕�炷�̂ł���B
�@�c�@�t�����̕`���{�h�j�b�N�͒����̔������āA�畆���B�ΐF�̏㒅�ƁA�Ԃ��V���c�A�Ԃ��ȃY�{���𗚂��A���~���̒�������Ƀp�C�v�������A���������~���̂��鑫�ɂ͐Ԃ��C�𗚂����p�����Ă���B�G���x���̎���S�A�ɂ́u�̏�߂ɁA�Ԃ��C�v�Ƃ���A��35�A�́u���Ȃ����������ɕ����Ȃ��@���ɂ�������Ȃ�I�@�������ɕς��āA�L���������Ȃ��Ɂv�ł���B���̐��ɂ͎p��ς��Ă��܂��͂�����炵���B����ɃG���x���̐��̐�������ɒn��ɏオ���ė���悤�ŁA�Âɑ��z�Ƒ������ǂ��Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@�w�ʂ܂̂����Ԃ@�{�h�j�b�N�x�̖�ғ��c�\�Y(�ӂ����E���܂��A1905�`1999)�̓`�F�R�o�g�̊G�{���Stepan Zavrel���V���e�p���E�c�@�t�����Ɠǂ�ł��邪�A���̖M�ł̓V���`�p�[���E�U���W�F���A�X�e�t�@���E�U�u�����A�V���`�F�p���E�U�u�[���A�V���^�p���E�W�����F�����A�X�e�p���E�U���B�[���ȂǂƂ��Ă���B12���قǂ̖�����B
�@���̐��ɕ߂���ĈيE�ɍs���t�H�[�N���A�ɂ́A�����̃p�^�[�������邪�A������v�f�𒆐S�ɍl����ƁA�ǂ̂悤�ɕ��ނł���ł��낤�B
�`�D���̐��͂܂��j���Ƃ������ʂŕ�������B
1�D���̐��j(�j�̐l���A�����E�A���@�b�T�[�}���A���H�h�j�[�N�A���@�W���m�[�C�A�͓��Ȃǂ̐��E�e�n�̐��̐��B�C�̐_�B�~�A�L�A�C�b�A�T�A�����Ȃǂ̐�������)�B
2�D���̐���(�l���A�j�b�N�X�A���T�[���J�Ȃǂ̐��E�e�n�̐��̐��B���P�ȂNJC�̐_�B��������)�B
�a�D�����ƊW�����l�Ԃ̐��ʁB
1�D��(���l�E�q��)
2�D�j(���l�E�q��)
�b�D�ǂ���̐��E�ɗ��ߒu����邩�B�@
1�D���E(�يE)
2�D�l�ԊE
�c�D���̐��E�ɍs�����ӂ̗L���B
1�D���ӗL
2�D���ӂȂ�(�f�v)
�d�D���̐��E�ł̐����̗l�q�B
1�D�K��
2�D�s�K(��s)
�e�D�ِ��Ԃ̌��ѕt���ɂ��q���̒a���̗L���B
1�D�L
2�D�Ȃ�
�f�D�q���̌`��
0�D�q���Ȃ�
1�D���̐�
2�D�l��
3�D�n�C�u���b�h
�g�D���̐��E�ւ̋A��
1�D�L(�K���ȋA�ҁA�s�K�ȋA��)
2�D�Ȃ�(�K���ȑ؍݁A�s�K�ȑؗ�)
3�D�ꎞ�I�ȋA��(�K���A�s�K)
�h�D�A�҂̉����
1�D�e��(���A��A�z��ҁA�Z��o���A�����E���A�Ȃ�)
2�D��O��(���@�g���A�_�A�يE�̏Z�l�A�ق�)
3�D����
4�D�Ȃ�
�i�D�A�҂����������
1�D�L
2�D�Ȃ�
�@�G���x���u���H�h�j�[�N�v�͂`1�A�a1�A�b1�A�c2�A�d2�A�e1�A�f1�A�g1�A�h1�A�i2�ƂȂ�A�u�ʂ܂̂����Ԃ{�h�j�b�N�v�͂`1�A�a1�A�b1�A�c2�A�d2�A�e2�A�f0�A�g1�A�h4�A�i1 �ƂȂ�B
�@�A���f���Z���u�l���P�v�͂`2�A�a2�A�b2�A�c1�A�d1�̂�2�A�e2�A�f0�A�g2?�A�h1�����2�A�i2?�ƂȂ邩������Ȃ��B���w��i�Ȃ̂ŒP���Ɋ���邱�Ƃ̏o���Ȃ��v�f������B�O�������b79�u���̐�Die Wassernixe�v(�쑺�Ђ낵��w����O�������b�W�x��4���A�����ܕ��ɁA2006.3.10�App.45�`47)�͒Z���b�ł��邪�A�`2�A�a1��2�A�b1�A�c2�A�d2�A�e2�AG0�A�g1�A�h4�A�i1�ƂȂ�(�Z�Ɩ�����̐��̐��ɕ߂܂�A�e���ȐH���ŏd�J������������B�Z���̓u���V�A���A�������ɓ����Ȃ��瓦�����A�����̂т�)�B
�@�������ȏ�̗v�f���ނ͑e�G�̂��̂ŁA�a�������q���ɂ��Ă݂Ă��A�����A�\�́A�l�ԎЉ�ւ̎���Ȃǂ̉������ޗv�f���l���邱�Ƃ��o����B�ٗލ���杂Ƃ����Ő��܂ꂽ�q���ɂ��Ă͏����a�F�̘_�l������̂ŁA�ȉ��̘_�����݂Ă������������B
�����a�F�u�ٗލ����̉F���|�u�S�̎q�v�Ɓu�Б��l�ԁv�v�A�u�ւ�߂��v��10���A1987.3.5�App.125�`136
���u�ٗލ����̉F���|�u�Б��l�ԁv�Ɓu���q�v�v�A�u�ւ�߂��v��14���A1988.3.3�App.186�`195
�l���֘A�ł́A�Z���L�[�Ƃ̎q�������͎w�ɐ��~�����������l�ԂƂ��ĎЉ�Ɏ�����ĉƌn���q���ł������Ƃ�A�̘b�Ől���Ƃ̑��q�����e�̌���K�˕��͂��ꂽ�\�͂����邪�A�₪�ĊC�ɋA��Ƃ����b��A�l���ƌ��������ꂪ���q�ɐl�Ԃ̋|���Ƃ���������܂ŏЉ�Ă����B�������̎҂ł���ꍇ�ł��A�G���x���̎q���̎��A�A�[�m���h�̕��̌��ň�A�������w�ł̏o����m�炳�ꂸ�ɐl�Ԃ̕�ƕ�炷�A�Ƃ����悤�ɗl�X�ɓW�J���邱�Ƃ��ł���B
�@�ߔN�h�C�c�̐��̐��ɂ��Đ��͓I�Ș_�l�\���Ă���̂���R��w�O����w���������c�E�ł���B�u���̐��̃o���[�h�v(�u�A�J�f�~�A�@���w�E��w�ҁv��67���A1999.9.30�App.559�`585)�A�u���̐��̃o���[�h�|�w���_�[�A�n�C�l�A�~�[�Q���Ȃǁ|�v(�u�A�J�f�~�A�@���w�E��w�ҁv��68��,2000.3.31�App.177�`206)�A�u���̐��̕��w�|�n�E�v�g�}���́w�����x���߂����ā|�v(�u�A�J�f�~�A�@���w�E��w�ҁv��72���A2002.6.30�App.69�`96)�A�u���̐��̕��w�|������u���C���̉ԉŁv�o���[�h�ɂ��ā|�v(�u�A�J�f�~�A�@���w�E��w�ҁv��73���A2003.1.31)�A�u�h�C�c�`�����w�Ɛ��̐��v�|�u�}���X�t�F���g�̌̃j�N�Z�v�ɂ��ā|�v(�u����(CORONA)�|��R�Q���}�j�X�e�B�b�N�|�v��17���A2006.3.31�App.1�`13)�A�u�h�C�c�`���Ɛ��̐��|�e���[�����Q���n���̃j�N�Z�`���v(�u�A�J�f�~�A�@���w�E��w�ҁv��83���A2008.1.�App.193�`209)�Ȃǂ\���Ă���B
�@�o���[�h�u���C���̉ԉŁv�͈قȂ�o�[�W�����̑��̂ł��邪�A�u���̐��̉ŒD���ƌ��������v�̕��ꎍ�ł���A�G���x���u���̐��v�����ɎQ�l�ƂȂ��i�ł���B�u���C���̉ԉŁv�ł͐��̐��ɋ������ꂽ���l�̖��̓��C����̋���n���Ă��鎞�ɐ����ɗ����Đ��̐��̍ȂƂȂ�B�G���x���̎��ł�����ɏo�������u�����ŏ��̃X�J�[�t�𐅂ɐZ���Ɓ^����Ă��������ӂ��ɕ���^�Ⴂ���̎p�����������ƂɁA�^�[�݂Ő����Q���܂��Ă����B�v�Ƃ���A�����n��Ɛ��̐��E�̋��E�Ƃ��ďd�v�Ȉʒu�ɂ���B
�@�G���x���̎��ł͉̂��Ă��Ȃ��������A�f���ł͕�e�̉Ƃɂ����������S����ۓI�ł���A�����Ӗ�����̂ł��邩�C�ɂȂ��Ă����B�����S�̈Ӗ��������Ă��ꂽ�̂�����E�ł���B�u�킵�̃n���i���v�Ƒ肷��o���[�h���A���̐��̍ȂƂȂ��������̕���ł���B���Ƃ̌��̖��n���i�������̐��̑������u�������̋��v���琅�ɒ��݁A���̐��E�̂V�N�ԂɂV�l�̑��q���Y�ނ��A����̏��Œn��ւ̎v�������ꎞ�n��ɋA�҂���B���̐��̓����S�ɕϐg���ăn���l���̗l�q���M���A���ɖ߂肽���Ȃ��n���l���͎q�����S�l�ƂR�l�ŕ����悤�ƒ�Ă��邪�A���̐��͕����ɂR�R�ƁA�c��̈�l�͔������ɂ��悤�Ǝc���Ȏ��������B�n���l���́A�u���̎q���蕪�����邭�炢�Ȃ�A�^���̒��Ɏc����������Ƃ܂��A�^�����ȃn���l���́B�v�Ɛ��̐��E�ɖ߂��čs���B
�@�����S�͐��̐��̕ϐg�A�n����݂�ځi���̐��̖ڂ͐Ԃ��j�ł������B�n��Ɏc�肽�����߂ɁA���q�̕��������ꂽ�̂��u�}���X�t�F���g�̌̃j�N�Z�v�ł���B�����ł̐��̐��͏����ł���B�����̐��̐��Ɉ�����āA�R�̓����������A�͂�Č��ꂽ�r�����̒j���̋��̑��Ɉꎞ�߂�ƁA�n��ɗ��܂邱�Ƃ�I�ԁB�Ȃ͈�l���q������ƌ����A�r�����͉����g��Ⴂ���B�Ȃ�������㔼�g���ɓ��������Ɓu���C�ȋ��v�ƂȂ�A�n��̉����g���ݕӂɖ��߂�ƕS����������B�n��Ɏc�邱�Ƃ�I������ƁA�q�͊��S�Ȏp�ł͂����Ȃ��Ȃ�B���ƕ�ŕ����ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B���̌���l�́A���̐��̎q�E���Ƃ��������Ȃ����́A�������ꂽ�q�̂��ꂼ��̕����̕ϐg�ȂǁA�F�X�ɍl���邱�Ƃ��ł���B
�@�h�C�c�̐��̐��ɂ��ẮA���c�E�̑��ɁA��������(�u�w���̐��x���_�|�h�C�c���ꎍ�|)�v�A���{���w������52���A1976.6.20�App.39�`56)�A�������q(�u������̐��̐��|���ԓ`���ƕ��w��i�ɂ�����Wassermann�|�v�A�h�C�c�ꕶ����������2���A2004.7.15�App.24�`38)�̘_�l������B���������グ���i�́A���N�������ɔŁw�h�C�c���ꎍ�x����u���̐��v�u�����������t�F�[�v�A�A�O�l�X�E�~�[�Q���w�������A�O�l�[�e�x�ł���B�܂������́A�����̐��̐�Wasserfrau�ɑ��A�j�̐��̐�Wassermann�͒m���x�A���w��i�ł̈����ŁA�����y�Ȃ����R��T���Ă���B���͂ň��������́A���ԓ`���ł́A�O�����Z��w�h�C�c�`���W�x�A�x�q�V���^�C���w�h�C�c�`���{�x�A�G���N�^�ׁ[���w�h�C�c�̉̂̕�x�A�y�b�c�I���g�w�h�C�c���ԓ`���x��45�b�A���w��i�́A�t�P�[�w�E���f�B�[�l�x�A���[���P�w���������E�̕���x�A�n�E�v�g�}���w�����x�A�~�[�Q���w�������A�O�l�[�e�x�A�n�E�X�}���u�����t�F�[�v�̂T��i�ł���B�����͒j���̐��̐��͉Ƃ̎�l�Ƃ������i�������Ƃœ��퐫���ێ����Ă���̂ŁA�َ��A�����Ƃ����l�Ԃ���v�����镨�ꐫ�Ɍ����邱�Ƃ��A���������킹�闝�R���ƌ��_�t���Ă���B�j�̐��̐��ŗB��A�l�Ԃ��狻���������̂́A�u�j���v�������������N�̐��̐��̕��ꂾ�Ƃ��A���̗�Ƃ��ăv���C�X���[�w�����Ȑ��̐��x�������Ă���B�����A�����̐��̐��̗U�f�҂Ƃ�������Ȗ��͂ɂ́A�ǂ����Ă����Ȃ�Ȃ��B

 �@�I�g�t���[�g�E�v���C�X���[(Otfried Preussler�A1923�`)�́w���������̐��x�͑�˗E�O(1921�`)��(�w�K�����ЁA1966.7.1�A�V�������E�̓��b�V�[���[�Y13)�ƁA�͂�����䂤��(���V�T�q�A1960�`)��(���ԏ��X�A2003.3.31)�̓�̖�{������B�����G�͋��ɃE�B�j�[�E�K�C���[(Winnie
Gayler�A1929�`)�̂��̂ł���B���̐��̕��ꂩ��Y�܂ꂽ�j�̎q�͐Ԃ��X�q����A�̓��E���ŁA�ΐF�̏㒅�A�Y�{���A�C��g�ɕt���Ă���B�j�̐��̐�����l���Ƃ���ƁA�l�ԂƓ����悤�ȓ��킪�����Ɩ������q���w�E���Ă��邪�A�����Ȑ��̐��̒j�̎q���l�ԂƓ����ōD��S�Ɩ`���S�ɖ��������X�𑗂��Ă���B���N�ł���̂œ��X(����)���P���Ă���̂ł���B�v���C�X���[�̓h�C�c�̎������w�҂ł��邪�A���܂�̓`�F�R�X�����@�L�A�̃��x���c(Liberec�A�h�C�c�E�|�[�����h�����܂�20km�ŁA�h�C�c�l�Z������������)�A�w���u�V�������E�̓��b�v�V���[�Y�ɂ́w�����������x(��˗E�O��A1967.6.20)�A�w�����������x(��˗E�O��A1965.7.20)�Ƃ����u������Kleine�v��薼�Ɏ���i�����߂��Ă����B�ߔN�A���X����u�v���V�X���[�̘̐b�v�R�������s����Ă���B�V���w���������̐��x�ɂ��Ă͍]�X���q���u�q�ǂ��ƓǏ��v��341��(2003.8.20)pp.28�`30�ŏЉ�Ă���B�\���A��b���A��̃`�v���k�X�̈����ɐV���ňႢ������Ǝw�E���Ă���B
�@�I�g�t���[�g�E�v���C�X���[(Otfried Preussler�A1923�`)�́w���������̐��x�͑�˗E�O(1921�`)��(�w�K�����ЁA1966.7.1�A�V�������E�̓��b�V�[���[�Y13)�ƁA�͂�����䂤��(���V�T�q�A1960�`)��(���ԏ��X�A2003.3.31)�̓�̖�{������B�����G�͋��ɃE�B�j�[�E�K�C���[(Winnie
Gayler�A1929�`)�̂��̂ł���B���̐��̕��ꂩ��Y�܂ꂽ�j�̎q�͐Ԃ��X�q����A�̓��E���ŁA�ΐF�̏㒅�A�Y�{���A�C��g�ɕt���Ă���B�j�̐��̐�����l���Ƃ���ƁA�l�ԂƓ����悤�ȓ��킪�����Ɩ������q���w�E���Ă��邪�A�����Ȑ��̐��̒j�̎q���l�ԂƓ����ōD��S�Ɩ`���S�ɖ��������X�𑗂��Ă���B���N�ł���̂œ��X(����)���P���Ă���̂ł���B�v���C�X���[�̓h�C�c�̎������w�҂ł��邪�A���܂�̓`�F�R�X�����@�L�A�̃��x���c(Liberec�A�h�C�c�E�|�[�����h�����܂�20km�ŁA�h�C�c�l�Z������������)�A�w���u�V�������E�̓��b�v�V���[�Y�ɂ́w�����������x(��˗E�O��A1967.6.20)�A�w�����������x(��˗E�O��A1965.7.20)�Ƃ����u������Kleine�v��薼�Ɏ���i�����߂��Ă����B�ߔN�A���X����u�v���V�X���[�̘̐b�v�R�������s����Ă���B�V���w���������̐��x�ɂ��Ă͍]�X���q���u�q�ǂ��ƓǏ��v��341��(2003.8.20)pp.28�`30�ŏЉ�Ă���B�\���A��b���A��̃`�v���k�X�̈����ɐV���ňႢ������Ǝw�E���Ă���B
�@�h�C�c�ꌗ���������̖|�Ő��̐����W������̂ɂ́A���ɃO�[�h�����E�p�E�[�o���NGudrun Pausewang(1928�`)�w�����̐��̐�nterm Haus der Wassermann�x(���R���q��A�������X�A1991.2.15)�A���[�E�y�X�g�D��Jo Pestum(1936�`)�w���̐��r�n�r����Ein Wassermann funkt SOS�x(���싨�q��A�����o�ŁA1995.6.15)������B�p�E�[�o���N�̍�i�ɂ͈�˂ɏZ�ޗΐF�̐��̐�Wassermann���o�ꂷ��B�쒆�ʼn���H�ׂĂ��邩�����ꂽ���̐��́A�u����������ł��������v�Ɠ����Ă���B�܂��A���̐��͏Z��ł����˂𗣂�Ă͍s���Ȃ��ƁA�u�݂����݂̉����܁v�����߂Ă��āA�ւ�Ƃ������̐��́u�݂����݂̒�ɂ����߂��āv�u�Q�ǂƏ�ɏオ���Ă���Ȃ��Ȃ�v�Ƃ���Ă���B��{pp.128�`129�ɂ̓C���Q�E�V���^�C�l�b�P(Inge Steineke�A1942�`)�ɂ��u�݂����݂̉����܁v�̎p���`����Ă���B���̗l�q�́A�u���̐��̊�Ƃ悭�ɂĂ��܂��B�̂��݂ɗ̂͂��A�̖ځB�ł��A���̐��Ƃ́A����ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��傫���ł����v�Ƃ���B��l���̉����l�́A�ɒ��߂�ꂽ���̐��������邽�߂ɁA���̐��ƌ�������B�y�X�g�D���̍�i�ɂ́A�{���̐��̐��͓o�ꂵ�Ȃ��B����オ���Ă���̂̓A�N�A�����O��t�����l�Ԃł���B
�@���F���j�Q���[�f���N���������c�u�h�C�c���w�W�R�@�����v(TKCC-15123�A�h�C�c�V�����v���b�e�����R�[�h�^���ԃW���p���R�~���j�P�[�V�����Y�A�S23��)�̑�X�ԖڂɁA�u�̐���Es
freit' ein wilder Wassermann�v(�����ҋȁF�t���b�c�E���C�^�[�A�\�v���m�F�A���h���A�E�C�[��)�����߂��Ă���B�����������u�����������t�F�[Die
schone Lilofee�v
�Ƃ��ďЉ�����̂Ɠ����̎��ł���B���̐��ɋ������ꂽ���������t�F�[�́A�Ώ�̏�Ɉꎞ�߂������A������߂ċ����Ă���q�������Ɉ�����āA�̒��ɖ߂��čs���B�����́u���̃o���[�f�͑f�p�ȃ����f�B�[�Ŏq��̂Ƃ��ĉ̂��Ă�����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B�܂��b�c�̃��C�i�[�m�[�c(�F�쓹�`)�ɂ́A�u�̎��A�����Ƃ��h�C�c�̊e�n�ɂ��܂��܂Ȍ`�ŎU�݂��Ă��邪�A���̔��˂͖��炩�łȂ��v�Ƃ���B�܂��A���c�E�́A���̉̂��u�킵�̃n�i���v�̒Z�k�����ꂽ���̂Łu�����ł��u��Ȑ��̐������������v(Es
freit ein wilder Wassermann)�̃t���[�Y�Ŏn�܂�Z�k�����ꂽ�̂͂����Ă��̖��w�W�Ɋ܂܂�Ă���v�Ƃ��Ă���B
�@�V���[�}��(Robert Schumann�A1810�`1856)��ȏ��������ȁu���̐�Der Wassermann�v(�u���}���c�GRomanzen��Q�W�vOp.91(1849�N)�̑�R�ȁANaxos8.570456�u�V���[�}���@���}���X�ƃo���[�h�W�v�A�}�[�N�E�~�q���G���E�f�E�X���g�w���A�A�N�A���E�X)�́A���X�e�B�k�X�E�P���i�[(Justinus Kerner�A1786�`1862)�̎��ɂ����̂ł���B�����̎���łT���̗x���x���Ă���`���[�r���Q���̉��������̂��Ƃɗ��h�Ȏ�҂Ƃ��Đ��̐�������A��Ԕ����������l�b�J�[��ɘA�ꋎ��Ƃ������e�ł���B����悤�Ƃ������A���͐����̐����̍L�ԂɘA��čs����Ă��܂��B�P���i�[�̎��͂����܂łŁA�Ăђn��ɖ߂鎞�̂��Ƃ͌���Ă��Ȃ��B
�@���̐��ɘA�ꋎ����̂͏����Ƃ͌���Ȃ��B�m���E�F�[�̍�ȉƃg���F�C�g(Geirr
Tveitt�A1908�`1981)�̌����G��u���̐�Nykken�v(BIS-CD-1207�u�n���_���Q���E�t�B�h�����t�ȑ�P�ԁA��Q�ԁA���̐��v)�ł́A�Ă̐Â��ȔӂɐX�̒r���甒�n�̎p�ƂȂ��Đ��̐��������B���l�ɉ���Ă�����҂��A�ƂɘA��ċA�낤�Ɣ��n�Ɍׂ�B���߂͂��ƂȂ����������n�ł��������A����ɋr�𑁂ߍr��Ă����B��҂͔n�����э~��悤�Ƃ��邪����Ȃ������B�X�����H���āA���n�͎�҂��悹�Ēr�ɔ�э��ށB���ɂȂ�ƁA�������Ȃ��������̂悤�ɐÂ܂肩����BCD������̕\���ɂ́A�r�ɂ܂��ɔ�э������Ƃ��锒�n�ƁA�����݂���҂̊G���`����Ă���B���n�Ƃ��Ă̐��̐��ɂ��ẮA�u���b�O�X�w�d�����T�x(�y�R�[�A1992.9.28)���Q�Ƃ��ꂽ��(�A�b�n�E�C�[�V���J�A�G�b�w�E�E�[�V���J�A�J�[���@���E�E�V���^�A�P���s�[�A�V���[�s���e�B�[�A�����n�A�m�b�O��)�B
�܂��A�����n�Ƃ͌����Ȃ����낤���A�w����̂Ȃ��̂͂�˂��݁x(���[���[�E�m���V���e�C���^�Z���Q�C�E�R�Y���t��A�t�����`�F�X�J�E�����u�[�\���@�G�A�����G�q��A�����ُ��X�A2000.10.25)�ɂ́A���̒����猻��锒�n���`����Ă���B�_��I�͔n�͉��x���o�ꂷ��d�v�ȃC���[�W�ł���B���ɂ́A��ɗ������n���l�Y�~�������Ă����i�}�Y�̂悤�ȑ��݂�����Ă��邪�A���V�A�̐��̐����@�W���m�[�C���i�}�Y�Ɛe�����W�ɂ���̂ŁA�������Ɗ֘A����_��I���݁����̐��Ƃ�����z�ɓ�������i�ł���B
�@�V�x���E�X(Jean Sibelius�A1865�`1957)�̉̋ȁu���̐�Nacken�v(Op.57-8)�́A�G�����X�g�E���[�Z�t�\��(Ernst Josephson�A1865�`1957�A�X�E�F�[�f���̉�ƁA���l)�̎��ɍ�Ȃ������̂ł���(Finlandia�AWPCS-10618�A�u�V�x���E�X�F�̋ȏW�v�A�g���E�N���E�Z�^�o���g���A�O�X�^���E���[�v�V���[�o�b�J�^�s�A�m)�B�呩�ȎO�̖ł͋}�������ꗎ����̏�Łu���������т̏��N���H��̂悤�ɐ��߂ā^�|�Ō����܂������Ă���v�B���@�C�I������t�ł邻�̏��N�͐��̐������A�p�������Ǝv�����͎̂��l�̌��z�ŁA�����Ԃ��������Ă��邾���ł������A�Ƃ����Z���ł���B���̎��ł̐��̐���Nacken(a�̓E�����E�g)�ł��邪�A�����Ӗ���Stromkarlen(o�̓E�����E�g)�Ƒ肷��̏�ɍ��|���A�|�Ń��@�C�I������t�ł闇�̂̏��N�p�̐��̐����A���[�Z�t�\���͖��G�ɕ`���Ă���(1884�N)�B���Ƃ͈قȂ萅�̐��̔��͒��F�������������ł��邪�A���̏�i�͎��Ɠ������̂ł���B
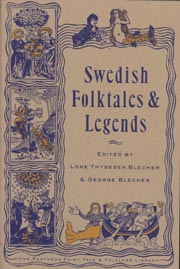 �@���̃X�E�F�[�f���̐��̐��ɂ��ẮA���[���E�V�O�Z���E�u���b�`���[�A�W���[�W�E�u���b�`���[�ҁw�X�E�F�[�f���̖��b�x(�Č��܂�q��A�y�ЁA1996.12.10)pp.76�`79�u�x�b�J�w�X�g�v���Q�Ƃ��ꂽ���B�x�b�J�w�X�gBackahast(a�̓E�����E�g)�̓X�E�F�[�f���̒W���ɏZ�ސ����n�ŁA�l�b�N(Nacken���̐�)���ϐg�������n�ł���B�l�Ԃ𐅂Ɉ������ނ��A���Ӑ[���l�Ԃ����̔�����т������������@�C�I�����̋|�ɒ���ƁA�f���炵�����y�ƂɂȂ��ƌ����Ă���B�X�ɖ���ɂȂ�ɂ́A�l�b�N�����L���郔�@�C�I�������̂��̂���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m���r�I�[�X�S�̘V���@�C�I�����e���̓x�b�J�w�X�g�̔w���烔�@�C�I�������A������т���邱�Ƃɐ������A�X�E�F�[�f���P�̖���ɂȂ����B�����A���̂��̉��t�̓X�g�����J�[��(���j���x�b�J�w�X�g�A�l�b�N)�����ڂ�A�����������łȂ��֎q��e�[�u���ȂǕ������̂��̂��x��o�����̗x���t�ł邱�Ƃ�����B���n�x�b�J�w�X�g�͎��ɐ��̕����Ԋۑ���A�]�������{�[�g�Ɏp��ς��邱�Ƃ�����B���̕����Ԗɕϐg����̂̓��V�A�̐��j���@�W���m�[�C�ɂ�������B�Ȃ��A�w�X�E�F�[�f���̖��b�xp.77�ɂ͔w���Ƀ��@�C�I�������悹���x�b�J�w�X�g�ƃ��@�C�I�����e�����i���̂��鏬���ȗ��������őގ����Ă���}�G���f�����Ă���BBertil
Bull Hedlund(1893�`1950)�̍�i�ł���B�Ȃ��A�����ɂ̓w�h�����h�ɂ��}�G��10�_�A����13���̉�Ƃ�57�_�̃C���X�g���ڂ��Ă���B�ł������̑}�G���ڂ��Ă���̂�Einar
Norelius(1900�`1985)�ł���B
�@���̃X�E�F�[�f���̐��̐��ɂ��ẮA���[���E�V�O�Z���E�u���b�`���[�A�W���[�W�E�u���b�`���[�ҁw�X�E�F�[�f���̖��b�x(�Č��܂�q��A�y�ЁA1996.12.10)pp.76�`79�u�x�b�J�w�X�g�v���Q�Ƃ��ꂽ���B�x�b�J�w�X�gBackahast(a�̓E�����E�g)�̓X�E�F�[�f���̒W���ɏZ�ސ����n�ŁA�l�b�N(Nacken���̐�)���ϐg�������n�ł���B�l�Ԃ𐅂Ɉ������ނ��A���Ӑ[���l�Ԃ����̔�����т������������@�C�I�����̋|�ɒ���ƁA�f���炵�����y�ƂɂȂ��ƌ����Ă���B�X�ɖ���ɂȂ�ɂ́A�l�b�N�����L���郔�@�C�I�������̂��̂���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m���r�I�[�X�S�̘V���@�C�I�����e���̓x�b�J�w�X�g�̔w���烔�@�C�I�������A������т���邱�Ƃɐ������A�X�E�F�[�f���P�̖���ɂȂ����B�����A���̂��̉��t�̓X�g�����J�[��(���j���x�b�J�w�X�g�A�l�b�N)�����ڂ�A�����������łȂ��֎q��e�[�u���ȂǕ������̂��̂��x��o�����̗x���t�ł邱�Ƃ�����B���n�x�b�J�w�X�g�͎��ɐ��̕����Ԋۑ���A�]�������{�[�g�Ɏp��ς��邱�Ƃ�����B���̕����Ԗɕϐg����̂̓��V�A�̐��j���@�W���m�[�C�ɂ�������B�Ȃ��A�w�X�E�F�[�f���̖��b�xp.77�ɂ͔w���Ƀ��@�C�I�������悹���x�b�J�w�X�g�ƃ��@�C�I�����e�����i���̂��鏬���ȗ��������őގ����Ă���}�G���f�����Ă���BBertil
Bull Hedlund(1893�`1950)�̍�i�ł���B�Ȃ��A�����ɂ̓w�h�����h�ɂ��}�G��10�_�A����13���̉�Ƃ�57�_�̃C���X�g���ڂ��Ă���B�ł������̑}�G���ڂ��Ă���̂�Einar
Norelius(1900�`1985)�ł���B
�@�X�E�F�[�f���̎������w�҃A�X�g���b�h�E�����h�O���[��(1907�`2002)�̒��w�₩�܂����̏t�E�āE�H�E�~�x(��˗E�O��A��g���N���ɁA2005.12.16)�̑�10�͂́u���̐������ɂ����܂����v(pp.117�`133)�ɂ́A���ԏ����̕��������[�n���̌��t�Ƃ��āA�u���̐��͂ˁA���ԏ����̉��́A��������ɂ���A���̂Ȃ��̊�ɂ�����ĂȁA���ɂ��ꂢ�ȉ��������āA���@�C�I�������Ђ��Ă��̂��B���̉�������܂肫�ꂢ�Ȃ���ŁA�킵�́A�����킸�Ȃ��Ă��܂�����v�u����Ȃɏt�߂��Ă���ƁA���̐��́A�����ނ��イ�ɂȂ��āA�܂���A���̊�ɂ��āA���@�C�I�������Ђ��̂��v�Ƃ���B�����ł��A��ɂ�����āA���@�C�I�������Ђ����̐��̎p���`�����Ă���B
�@���X���u�ɑ�����`�F�R�̐��̐����H�h�j�[�N�ɂ��āA�G���x�������W�����t�H�[�N���A���݂Ă݂悤�B��|���O(1941�`)��ҁw�`�F�R�X���o�L�A�̖��b�x(�P���ЁA1980.7.20)pp.74�`78�u�͓��v(Vodnik)�ł́A���{���ƃ��H�h�j�[�N�̊W������Ă���B�u���ԁA�͓��͐��̏�ɐԂ����{�����������A�q�����������{���ɐG���ƁA�����܂����̒������Ă��܂��v�B�͓��̕����ɂ͑�R�̃��{�������т����Ă��邪�A���̃��{���ɂ͓M���l�̍��������Ă���Ƃ����B�܂��A���{���͍��̂͂��������������Ă���Ƃ��`���Ă���B���{���Ɛ��̐��̌��т��̓J�����E�`���y�b�N(1890�`1938)���G��Ă���B��g���N���Ɂw������������҂���̘b�x(����D�v��A1986.3.12�A���ő�35��)�ɂ͓�́u�J�b�p�v�b���ڂ����Ă��邪�A�P�Ƃ̍�i�u�J�b�p�̘b�v�ɂ́u�ڂ�{���̂˂��܂������������A����͂ǂ������������vp.118�Ƃ������t������B������̃J�b�p�b�́u������������҂���̘b�v�̂P�G�s�\�[�h�u�n�������B�c�F�̃J�b�p�̕a�C�v(pp.43�`49)�ł���B���̓�̘b���܂Ƃ߂��A�j���[�V�������G�{���������̂��A�u�`���y�b�N�̃t�B�����G�{�V���[�Y�@�R�v�w�J�b�p�̂��b�xVodnicka Pohadka(�S�}�u�b�N�X�A2007.9.10)�ł���B�A�j���̊G���́w������������҂���̘b�x�̑}�G���Z�t�E�`���y�b�N(�J�����̌Z�A1887�`1945)���Č��������̂ł���B�J�b�p�̓J�G���̂悤�Ɍ�����B�J�b�p����c���J���Ă��鏊�ɗ����������l�Ԃ̌��t�Ƃ��ăJ�����́u���傤�́A�����Ԃ�ƃJ�G���ǂ��������Ă邶��Ȃ����v�ƋL���Ă���B
�@���̐����M���l�̍��𐅂̒�̚�ɉB���Ƃ����`���́A�A�C�������h�A�h�C�c�Ȃǂɂ�����B�ЎR�L�q(1878�`1957)���u�J�b�p�̃N�[�v�Ƃ��Ė��A�C�������h�̘b�́A��(�x����{�u�����ς́@�N�[�v�A�w�x����{�S�W�x��W���A���V���X�A1986.3.20�App.77�`81)��G�{�ł����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�C�F�[�c�ҁw�A�C�������h�̐_�b�A�`���A�̘b�x(�����ܕ��Ɂw�P���g�d������x�w�P���g���z����x�A�䑺�N�]���)���̃����E�̘bThe Soul Cages(T.Crofton Croker�ɂ��)�Ƃ��Ă悭�m���Ă���B�����ECoomara(����Coo)�ƗF�����ɂȂ����l��Jack Dogherty���Ă̕����߂�ꂽ�M���l�̍���������镨��ł���B����ׂ��`�����g�b�p���̂��͂Ȃ����ق�R�w�J�b�p�̃N�[�x(�{��͓�^���A�t���[�x���فA1969)�Ō���ƁA�����E�̃N�[�}���͊{�E���L���A�Ԃ��X�q����A����ȑ��ŁA�r�ɂ̗͗�����A���{�̃J�b�p�̉e�����Ó��A�{�̂悤�ȐO�������p�����Ă���B�h�C�c�̗ޘb�́w�O�����@�h�C�c�`���W(��)�x(�����E�b��N�Y��A�l�����@�A1987.4.30)pp.58�`59�u52 ���̐��Ɣ_�v�v�ł���B�ɏZ�ސ��̐��Ƌߏ��Â����������Ă����_�v����̒��̐����l�̍����������Ƃ������̂ł���B�����ł̐��̐�Der Wassermann�́u�O���͕��ʂ̐l�ƕς��Ȃ��B���������o���ƁA�ΐF�̎���������Ƃ��낪����Ă���B���������Δ���Ă���X�q���ΐF�ł���B�r�̂����Ⴂ���������Ă���ƁA���̐��͐�����o�Ė��̃��{���̒������v��A���̒����ɐ����V�������{���𖺂ɓ�������v�Ƃ���B�h�C�c�̗��ł���`�F�R�A�|�[�����h�ł����l�̘b������B
�@�`�F�R�̐��̐��ɂ��ẮA��������}���ٍ��ێq�ǂ��}���قR�K�A�{�̃~���[�W�A���ŊJ�Â���Ă���u�`�F�R�ւ̔��|�q�ǂ��̖{�̐��E�|�v�W(2007.1.26�`2007.9.7)�ł��Љ��Ă���(���W����}�^�͍�������}���ٍ��ێq�ǂ��}���ٕҏW�E���s�A2008.1.22)�B�W���̍Ō�̕����A�ǍۂɁu�J�b�p�H�|�`�F�R�̐��̐��v�̃R�[�i�[������A�W���̖{�����邱�Ƃ��ł���B����͎��̂悤�ł������B
�@Vodnik�Ƃ́A����Ƈ����j���Ő��̐��Ƃ���Ă���B���H�h�j�[�N�́A���A���̕��҂������̂��̐���ɏZ��ł���A���ӂɋ߂Â����l�Ԃ𐅒��Ɉ������݁A�M��������B���̒��ł͗͂����邪�A���ɏオ��Ɨ͎͂ア�B���Ă��镞�́A�����G��Ă��Ċ����Ǝ���ł��܂��B���~����������Ƒ��������A����̂͗ΐF�B�����܂ł���Ɠ��{�̃J�b�p�Ɏ��Ă���ƍl����l�͑����悤�ŁA���H�h�j�[�N���u�J�b�p�v�Ɩ��Ƃ͑����B
�@�`�F�R�̇��J�b�p���͌���̔ӂɖ��̎}�ɍ��|���ČC���B���̏�ʂ����_��Y�}�h�[�R���@�[�炪�G�ɂ��Ă���A�Ԃ��X�q�A�Ԃ��C�ŁA���ɂ̓p�C�v������炵�Ă���B�G���x���̘̐b�ł́A�M���҂̍����ɓ���ďW�߁A����������čȂɂ���Ƃ����`��������B���̖������炤�g�J�b�p�h�̘b�́A�G���x���́w�ԑ��x(No.18)�̒��ɂ�����A���ꂪ�h���H���W���[�N�̌������u���̐��v�̑f�ނɂ��Ȃ��Ă���B���낵�����݂ł������ŁA�n�쓶�b�̐��E�ł͐e���܂ꈤ���ׂ��o��l���Ƃ��Ȃ��Ă���A�����̎������w�ɓo�ꂷ��B
�@�W�����ꂽ�W���̖{�́A�G���x���w�`�G�R�̘̐b�Ƌ��b�x(������ꂽ����A����`���̐l�Ԃ̏������J���Ă��܂�)�A�����E�h���_��^���[�t�E���_�G�w�`�F�R�̘̐b�x(1968�N�B�r�[���𐅒�ł̂ށg�J�b�p�h)�A���[�t�E���_�^����T�E���c�䳎q��w�����Ƃ����ρx(�����ُ��X�A1979.11.20)�A�`���y�b�N��^�����|�F��^���R���Y�G�w�J�b�p�̂͂Ȃ��x(�����[�A1958�B�}�G�̐��̐��͓��{�̃J�b�p�̎p�����Ă���)�A�J�����E�|���[�`�F�N��^����c���q��^���[�b�t�E�`���y�b�N�G�w�����̂ނ��������x(��g���X�A1969.6.16)�A�{�t�~���E�W�[�n��^�����E�N�h���[�`�F�N�G�w�J�b�p�����͂ǂ�����ăi�}�Y�������Ȃ��߂����x(1974)�A�V���e�p���E�c�@�t������^�ӂ������܂���w�{�h�j�b�N�|�ʂ܂̂����Ԃx(�ق�Տo�ŁA1979.6.15)�A�H�열�V��u�͓��v�̃X�����@�L�A���gVodnici�h(1958�B�C�����t�E�U�[���v�X�L�[�G)�A�ł���B�`���y�b�N�u�J�b�p�̘b�v�A�c�@�t�����w�{�h�j�b�N�x�ɂ��Ă͏Љ�ςł���B
�@�|���[�`�F�N�w�����̂ނ��������x��150���z�������ƌ��F�����C�X�^���E�o�[�o��
�̓�l�̑��q68�̑������G�h�_���g��66�̑������t�����`���������w�������Ɩ`�����镨��ŁA����gEdudant
a Francimor�h(1963)�ł���B�`���̓r���ŁA�u�݂ǂ�̂�������v�̃J�b�p�u�t�S�E�J�p�X�L�[�v�ƒm�荇���A�r�̉��ɂ���J�p�X�L�[�̉�����K�˂Ă���B�J�p�X�L�[�͎��l�̍����ŋ߂͑��₷���Ƃ��ł����A�T�L�\�t�H���𐁂����E�����Ă���(�M��p.64�ɂ͌���ɐ�ӂ̖ɍ��|���T�L�\�t�H���𐁂��J�p�X�L�[�̎p���`����Ă���)�B�J�p�X�L�[�͐���Ō��������Ă��邪�A���̌��́u�݂ǂ�F�̖сv�ŁA�ڂ́u�����邢���F�v�A�u�w�Ǝw�̊Ԃɐ������v�����Ă����B���_���l�J�����E�|���[�`�F�N(1892�`1944)�́A�`���y�b�N�Z��̗F�l�ŁA�A�E�V�����B�b�c���e���֑���ꂽ�B�M�ɂ͊�g���N���Ɂw�ڂ���͂��ς��T�l�g�x(����c���q��A1990.11.19)�Ȃǂ�����B
 �@�w�J�b�p�����͂ǂ�����ăi�}�Y�������Ȃ��߂����x�̃W�[�n�^�N�h���[�`�F�N�ɂ́w�������Ȍ������x(��o�O�q��A���S�ЁA1986.8.20)�Ƃ����A��͂萅�̐����o�ꂷ��M������B�r�ɏZ�ށu�����ς̂���Ԃ�v�X�^�[���N��������ɂ́A��q�̂����ς�����Ɨ��̃i�}�Y������B�����ς͖X�q����A�J��o�C�I�����Ȃǂ̊y���e���A���Ƀp�C�v���ӂ����Ă���B�u�������Ђ��A���ӂԂ����ڂɁA�͂����̑��v�A���ꂪ�u�����Ƃ��������ρv���g�ɂ��Ȃ��Ă�����̂��B�q�ǂ��܂łȂ��Ȃ���A�������������Ă��Ȃ���ׁ̂[�i�A�X�^�[���N�͈ȑO�Q����ԉł��}���邽�߂̃x�[���������A���n���J�Ǝ��������邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɁA�ׁ[�i�͌�Ȃ̂ɁA�����ςƓ����������X�q����A���ɂ̓p�C�v�����킦�Ă���B�C�̐i�܂Ȃ��ׁ[�i�v�Ȃ̌��������ǂ��Ȃ邩���w�������Ȍ������xSVATBA
V RYBNICE(1982)�̘b�ł���B��҃{�t�~���E�W�[�n(1907�`1987)�ɂ̓A�h���t�E�{����(�G)�Ƃ́u�r�[�e�N�v�V���[�Y�Ȃ�10���قǂ̖M������B��ƃ����E�N�h�D���[�`�F�N(1928�`)�͓샂���r�A�o�g�ŁA���̐������x���`���A�u�`���E����Ȃ�v�u�y�g���[�V���J�v�Ȃ�10���ȏ�̖����s����Ă���B�ڂ��傫���A�J�G���̂悤�Ȏp�̐��̐������F�ƂȂ��Ă���B���ɐl�C��ƂȂ̂Ń`�F�R�̖{�������Ă���T�C�g�ŏ��e�A���e�Ȃǂ��m�F���邱�Ƃ��ł���B
�@�w�J�b�p�����͂ǂ�����ăi�}�Y�������Ȃ��߂����x�̃W�[�n�^�N�h���[�`�F�N�ɂ́w�������Ȍ������x(��o�O�q��A���S�ЁA1986.8.20)�Ƃ����A��͂萅�̐����o�ꂷ��M������B�r�ɏZ�ށu�����ς̂���Ԃ�v�X�^�[���N��������ɂ́A��q�̂����ς�����Ɨ��̃i�}�Y������B�����ς͖X�q����A�J��o�C�I�����Ȃǂ̊y���e���A���Ƀp�C�v���ӂ����Ă���B�u�������Ђ��A���ӂԂ����ڂɁA�͂����̑��v�A���ꂪ�u�����Ƃ��������ρv���g�ɂ��Ȃ��Ă�����̂��B�q�ǂ��܂łȂ��Ȃ���A�������������Ă��Ȃ���ׁ̂[�i�A�X�^�[���N�͈ȑO�Q����ԉł��}���邽�߂̃x�[���������A���n���J�Ǝ��������邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɁA�ׁ[�i�͌�Ȃ̂ɁA�����ςƓ����������X�q����A���ɂ̓p�C�v�����킦�Ă���B�C�̐i�܂Ȃ��ׁ[�i�v�Ȃ̌��������ǂ��Ȃ邩���w�������Ȍ������xSVATBA
V RYBNICE(1982)�̘b�ł���B��҃{�t�~���E�W�[�n(1907�`1987)�ɂ̓A�h���t�E�{����(�G)�Ƃ́u�r�[�e�N�v�V���[�Y�Ȃ�10���قǂ̖M������B��ƃ����E�N�h�D���[�`�F�N(1928�`)�͓샂���r�A�o�g�ŁA���̐������x���`���A�u�`���E����Ȃ�v�u�y�g���[�V���J�v�Ȃ�10���ȏ�̖����s����Ă���B�ڂ��傫���A�J�G���̂悤�Ȏp�̐��̐������F�ƂȂ��Ă���B���ɐl�C��ƂȂ̂Ń`�F�R�̖{�������Ă���T�C�g�ŏ��e�A���e�Ȃǂ��m�F���邱�Ƃ��ł���B
�@�Ȃ��A���[���b�p�̃i�}�Y�͐��̐��̏�蕨�ƂȂ邾�������āA���ɑ�^�ł���B���[���b�p�̃i�}�Y���͂Q��ŁA�M���V�A�ɕ��z����A���X�g�e���X�i�}�Y(Silurus aristotelis)�Ɠ����E���V�A�ɐ������郈�[���b�p�i�}�Y(Silurus glanis)������B�`�F�R�̃i�}�Y�̓��[���b�p�i�}�Y�ŁA�`�͓��{�̃i�}�Y(Silurus asotus)�Ɏ��Ă��邪�A�̒���5m�ɂ��B����Ƃ����B��i�}�Y�Ƃ��Ēm���郁�R���I�I�i�}�Y(Pangasianodon gigas�A�v���[�E�u�b�N)�ł�3m�ł��邩��A���̋��傳���z������悤�B���{�̃r���R�I�I�i�}�Y(Silurus biwaensis)��1m�����A����ł���r�ɂȂ�Ȃ����ł���B���E�ő�̒W�����Ƃ��ėL���ȃs�����N��3�`5m�Ȃ̂ŁA���[���b�p�i�}�Y�͂���ɕC�G����傫���Ȃ̂ł���B�C���ɂ��������邪�`���E�U���������x�̑傫���ɂȂ邱�Ƃ��m���Ă���B���[���b�p�i�}�Y�͂܂��u�i�}�Y���ڂ̂Ȃ��ł͂����Ƃ��k���ɐi�o������̂ЂƂł���v(�ȏ�̋L�q�́A������݂ǂ�u�i�}�Y�̐��E�v[�w�|�C���[�W�Ƃ��̑f��x�A��ߕ��_�Ɓ^�ďC�A�O�����P�E�{�{�^��^�ҁA���⏑�[�A2008.2.25�App.142�`160]���Q�Ƃ���)�B
�@�w�������Ȍ������x�̖�҈�o�O�q�́A�������Ƃ����ŁA�`�F�R�̐��̐��ɂ��Ď��̂悤�ɓ`���Ă���B
�@���r�̒��ɁA�l�ԂɎ������̂��Z��ł���Ƃ����A�̂���̂��������ł́A���{�̂����ςƓ����Ȃ̂ŁA�����ςƋL���Ă��܂����A���̘b��A�h�{���U�[�N�̃I�y���u���T���J�v�ŏo�Ă���A���̐��E���i���Ă�����́A���̎�Ƃ����̐��Ƃ��������́A�܂��A�Ƃ��ǂ����������������̂Ƃ��A���̒��ɎႢ�����Ђ����肱��ōȂɂ���Ƃ��A�l��������Ă��̍�����̂ڂ̒��ɂƂ����߂Ă��܂����̂Ƃ��A���낢��̊T�O������܂��B�݂ǂ�F�̕��𒅂āA���̍����Ƃɍ������A�p�C�v���ӂ����A�㒅���琅���������肨����p�́u�����Ƃ����ρv(���c�䳎q��^�����ُ��X��)�̃��[�t�E���_�̊G�ŁA���{�ł��e���܂�Ă��܂��B
�@�w�������Ȍ������x�ɉƗ��̃i�}�Y�A���̓����҂ł���R�C�̑��ɁA�J���J�}�X�A�J���X�Y�L�A�J�W�J�A�^�i�S�A�j�S�C�A�Ƃ������������L����Ă��邪�A�C�������Ȃ��`�F�R�̋��̑�\�Ƃ����A��͂�R�C�炵��(�������A�������邪)�B�����E�v���n�Y�J��A�t�����X�E�n�[�P���G�A�g�����u��w���悰�A�ڂ��̃R�C�x(���ԏ��X�A1995.19.30)�̓h�C�c��ł���̖|��ł��邪�A�����E�v���n�Y�J(1929�`1971)�̓`�F�R�̍�Ƃł���B�N���X�}�X�ɐH�ׂ�R�C���C�ɓ��������N���K���ɋ��̖�����낤�Ƃ��镨��ł���B�쒆�ł͑傫�ȃR�C�͍쒆�ł͕S�R���i�̒l�ł������B�|���n�Y(�X)�J�ɂ͑��ɁA�����ˏ��[���w���������J�x(�R���l�Y��A1976.2)�Ƃ���������B
�@�F���G�o�͎G���u�{���v(��104����S���A2007.12.5)�Ɂu�`�F�R�̌���v�Ƒ肷��G�b�Z�C���Ă���(pp.14�`17)�B�F���ɂ��ƁA��ʓI�ɂ��܂苛��H�ׂȂ��`�F�R�ł��A�W�����͎��ɐH��֏�邱�Ƃ�����Ƃ����B�����^���@(�����_�E)���k�サ���`�F�R�암�ɂ͑����̗{���ꂪ����A�������܂ܑ�s�s�ɉ^��A�N���X�}�X�̓��ʗ����ɂȂ�B�����@�̓t���C���O�����ł���B�F���͋ߐ��j�ƃ��H�����̋L�����Љ�āA16���I�ɍŐ������}�����`�F�R�̒W�����{�B�̗��j���q�ׂĂ���B�{�B�̐��i�҂͋M���ŁA�̎�̉��ɂ͐��̗{�B��l�����āA�u�����{�݂̌v��ƍH���A���H�̉��̊Ǘ��ƕۑS�A�����Ă�����̗{�B�Ƌ��l�A�̔��Ǝ��v�̊Ǘ��v�ɋy�сA�V���`�F�p�[�l�N�E�l�g���c�L�[�A���N�v�E�N���`�[���Ƃ������{�B���Ƃ̃v���̖��܂ŋ����Ă���B(�r�̊Ǘ��A�����H���̐ӔC�҂Ƃ��������́A���Ƃ����ɏZ�ސ������̎x�z�҂Ƃ��Ă̐��̐����H�h�j�[�N�ɋɂ߂ėގ����Ă���B���j�Ɩ��������т��ړ_���u��(��)��s�v���{�B��l�ɂ��邩������Ȃ��B)�����͒Z���A16���I���ɂ̓r�[�������Ɏ�͈͂ڂ�A�헐�ŗ��ʂ��@�\�s�S�Ɋׂ�A�{����͕��u���ꂽ��A���ߖ߂��ꂽ�肵���B���u���ꂽ���ʂ͎��R�̒r�A�ƕς��Ȃ��Ȃ��A���W���[�ɗ��p����Ă���Ƃ����B
�@��̎�Ɨ{�����Ƃɂ��Ă̓`�F�R�̗��j�ł͏펯�炵���A���ɃN�Z�W���w�`�F�R�X�����@�L�A�j�x(�s�G�[���E�{�k�[���A�R�{�r�N��A�����ЁA1969.4.5)�ɂ͎��̂悤�ȋL�q������B
��w�M���̂ق��́A�����̏㏸�ɑς��Ă����邾���̎��͂������Ă����B�����͔_�z����̕��ۑd���������ɂ���邱�Ƃ���߁A�ē�������傫���Ȃ����̒n�̒��ڌo�c���l����悤�ɂȂ����B���Y�A�̔��A�A�o�������ė��v��������ׂ���Ƃ����������Ƃ����킯�ł���B���Y���Ƃ��Ă͏���������A�܂��A�Ƃ��ɓ�{�w�~�A�ł͋���Ȑl�H�r�̂������ŋ�(��)���Ƃꂽ�B(p.41�A�����n�v�X�u���N�Ə���(��ܓ�Z�`��Z�ꔪ))
�@����ɁA�F���̒����V���ł̒��w����@�`�F�R�̗��j�|�X�ƍ����ƌÏ�̍��x(�������_�V�ЁA2006.3.25)�ɂ́A�y�����V���e�C���ƃ��B���[���Q��(1438?�`1521)�ɂ��Ă̕����ŁA�u���B���[���̎���ɍł��������v���������͉̂��Ƃ����Ă����Ƃł���B�C�̂Ȃ��`�F�R�ł́A�Â�����r�Ō��{�B���ċM�d�ȉh�{���ɂ��Ă����̂ł��邪�A�y�����V���e�C���Ƃ̂悤�ȍL��ȏ��̂����M���������ƁA�^�͂��@���ĉ͐삩�琅�������A��K�͂ȗ{���r�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B���݂ł̓`�F�R�암�̗{��Ƃ��L�������A��Z���I�ɂ͓����̃p���h�D�r�c�F���ӂ����Ƃ̈�咆�S�n�ł������B���̋Z�p�҂������ă��B���[�������点���r�̂����A�傫�����͖̂ʐς���Z�Z�Z�w�N�^�[�����A�����C�̌�{�B����Ă����Ƃ����B�v(p.119)�A�Əq�ׂĂ���B�����������B�A�̃y�����V���e�C���ƁA�{�փ~�A�암�̃��W�F���x���N�ƂƂ������L�͋M�����{��ŕx��~�ς����B
�@�Ȃ��A�N�Z�W���w�`�F�R�X�����@�L�A�j�xp.83�ɂ́A�u���}����`�̐���́A�p�������܂��ɓ�̌���𐢂ɑ������B�ЂƂ͉C���ŁAK=J�E�G���x���ɂ���ĕҏW���ꂽ(�ꔪ�O)�Z�����w�W�w�ԑ��x�ł���A�����ЂƂ͎U���ŁA�����ƃ{�W�F�i�E�j�F���c�H���@�[�̎�ɂȂ�w��������x�ł���v�Ƃ����G���x���w�ԑ��x�ɐG�ꂽ�L�q������B
 �@�`�G�R�́u�J�b�p�v�̑����K�̓��[�t�E���_(1887�`1957)�w�����Ƃ����ρx(����T�E���c�䳎q��A�����ُ��X�A1979.11.20)�ōς܂����B���e�ɓ���O�Ɂw�����Ƃ����ρx�̌�������Ă݂悤�B�gBubaci
a Hastrmani�h�Ƃ���B���܂܂Ń`�F�R�̐��̐��̓��H�h�j�[�NVodnik�Ɠ`���Ă������A�Ⴄ�P�ꂪ�g���Ă���B�薼�̉p����T���ƁA����gGhosts
and Water Sprites�h�Ƃ�����A�gBogeymen and Water Sprites�h�A�gSpooks
and Goblins�h���������B�I�ɂ��邪��x�����������Ƃ��Ȃ�����Ivan
Poldauf�ҁw�`�F�R�|�p�ꎫ�T�x��4��(1965)�����Ă݂�B
�@�`�G�R�́u�J�b�p�v�̑����K�̓��[�t�E���_(1887�`1957)�w�����Ƃ����ρx(����T�E���c�䳎q��A�����ُ��X�A1979.11.20)�ōς܂����B���e�ɓ���O�Ɂw�����Ƃ����ρx�̌�������Ă݂悤�B�gBubaci
a Hastrmani�h�Ƃ���B���܂܂Ń`�F�R�̐��̐��̓��H�h�j�[�NVodnik�Ɠ`���Ă������A�Ⴄ�P�ꂪ�g���Ă���B�薼�̉p����T���ƁA����gGhosts
and Water Sprites�h�Ƃ�����A�gBogeymen and Water Sprites�h�A�gSpooks
and Goblins�h���������B�I�ɂ��邪��x�����������Ƃ��Ȃ�����Ivan
Poldauf�ҁw�`�F�R�|�p�ꎫ�T�x��4��(1965)�����Ă݂�B
bubak�́A�ubugbear�Abugaboo�Abogle�Abogy�v�܂�́u�����v�Ƃ������B
hastrman�̕��́A�uwater sprite�v���u���̐��v�ł���B
���Ȃ݂�voda�́uwater�@���v�A�`�e����vodka��watery�Aaqueous�ŁA�`�e���̔h����Ƃ���vodnik��water
sprite(or elf)�Anix���ڂ��Ă����B
�@���Ȃ݂Ɏo���ł�Jan Caha�^Jiri Kramsky�ҁw�p��|�`�F�R�ꎫ�T�x��4��(1964)�ŁA�l��mermaid�������ƁA�umorska
panna�v�Ƃ������Bmorsky�́usea�@�C�v�Apnnna�́ugirl�Alass�Amaiden�@�����A���v�ł��邩��Amermaid�̖{�`���`�F�R��Ɉڂ��������̌�Ǝv����B
�W���̐��̐��ɑ��Ă͖����I�Ȍꂪ���邪�A�C�̃}�[���C�h�͌�`���ړ����������Ȃ̂��낤���B�܂��A�u���̐��v���H�[�h�j�N�ƃn�X�g���}���̈Ⴂ�ɂ��ẮA�܂������킩��Ȃ��B�|�[�����h�암(�܂�A�`�F�R�����n��)�V�����X�N(�V���W�A)�́u�͓��v�̌Ăі��̈��hasterman�����邱�Ƃ��I�����Y���Ă���(�u�|�[�����h�͓̉��`���vp.187)�B�I�����`����V�����N�X�́u�͓��v���ɂ́A���ɁAutopiec�Autopnik�Autopek�Autoplec�Autoplaszek�Autopluszek�Arokita�Ararek�Ajaroszek�AIwan�AFranc�A
Jedra�Awasermun�Awasermon�A��Hasterman���܂�15�ٖ̈�������B���ӂ̑���������܂ޑ��ʂȐ��̐��̖����������Ă��邪�A�`�F�R�ł����l�Ȏ��Ԃł��낤�Ɛ��������B���܂̓��H�[�h�j�N�A�n�X�g���}���̂Q���m��݂̂ł���B���Y�t�H���s�̎G���u�^�C�g���v2003�N�R����(��4
����3��)�u�v���n���U������vp.85�ɂ́u�������D�Ƃ������Ƃ�A�`�F�R�̃u�b�N�f�U�C���v�Ƃ��ă~���V���E�E���o���w�͓��x(�A���S��)�Ƃ��������̕\���ʐ^�����邪�A�͓��Ƃ�Hastrman�̂��Ƃł������B�Ⴂ��������������ł���A�X�q�������ΐF�̔畆�A�Ԃ����̊����Hastrman���\���ɕ`����Ă���{�ł���B
�@���[�t�E���_(Josef Lada)�́A�v���n��x�̃t���V�c�F�ɌC���̑��q�Ƃ���1987�N�ɐ��܂ꂽ�B��2007�N�Ő��a120�N�ł������B�`�F�R�̍����I���w�n�V�F�b�N�w���m�V�����F�C�N�̖`���x�̑}�G(�����p��A��g���ɔłł����_�̑}�G���g���Ă���)���L���ł��邪�A���悩��n�܂�A�̘b�E���b�̑}�G�A�₪�Ă͕��͂����Ȃ��悤�ɂȂ����B���{���ɂ́A�w�����Ƃ����ρx�̂ق��w���˂��~�P�V���̂ڂ�����x(����c���q��A��g���X�A1967.7.7)�A�w���˂��̂�����x(���c�䳎q��A�����ُ��X�A1966.6.1)�Ȃǂ�����A2005�N�ɂ͕��}�Ђ���w�ǂ��Ԃ@���������x(�C�W�[�E�W���[�`�F�N���A�ѓ�����A2005.3.9)���o�ł���Ă���B�w�ǂ��Ԃ@���������x�̓��_�̐��a�S�N�L�O�Ƃ��ă`�F�R�Ŋ��s���ꂽ�{(1987�N)�̖|��ł���B
 �@�w�����Ƃ����ρx�́A�ߑ㉻�̒��ł��̂Ȃ���̐��������V�X���t���ɏZ�ސ��̐��u���`���[���Ƒ��q�v���c�A�u���`���[���̗F�l�Ƃ��Ă��̑��ɉz���Ă����������̃����T�[�N�Ƒ��q�u�o�[�`�F�N�̓�g�̐e�q�Ɛl�Ԃ����̌𗬂�`��������ł���B���R�A�ߑ㉻�ւ̕��h�����߂��Ă���B���_�̐�������u�����ρv�̗l�q�����Ă݂悤�B
�@�w�����Ƃ����ρx�́A�ߑ㉻�̒��ł��̂Ȃ���̐��������V�X���t���ɏZ�ސ��̐��u���`���[���Ƒ��q�v���c�A�u���`���[���̗F�l�Ƃ��Ă��̑��ɉz���Ă����������̃����T�[�N�Ƒ��q�u�o�[�`�F�N�̓�g�̐e�q�Ɛl�Ԃ����̌𗬂�`��������ł���B���R�A�ߑ㉻�ւ̕��h�����߂��Ă���B���_�̐�������u�����ρv�̗l�q�����Ă݂悤�B
�@�u���`���[���e�q�́u���͂���̌Âт����ԏ����̏��̒r�v�ɏZ��ł��āA�u��ɂȂ�ƁA�Âт����ԏ����ɂ悭�o�����Ă����āA�Ƃ��ɂ́A���̐l�����ɂނ����b������������v�����B���ԏ�����K�˂�Ƃ��̎�݂₰�́A�Ҋ��A�H�Ƃ������ł���B���Ԃɂ��ẮA���̉J�͂��ł���Ƃ��A�r�̐��̊Ǘ��Ƃ������ʓ|���悭�݂�B�D���͏Ă��ь�ƏĂ������A�����ăp�C�v�ŋz�������B�u���`���[���̏�蕨�́A�S�C�̑�l�R�Ɉ��������˂���(�ԗւ̏������ɂ̓R�E�����̎���p����)�ł���B���[����ɏ��̂ŁA��ɖڂ������l�R�łȂ��ƎԂ͈����Ȃ��̂ł���(�����ς͖�ɍs�����A���Ԃ͒r�ŐQ�ĉ߂���)�B���Ȃ݂ɁA�����̏�蕨��ⴂ̔�s�@(�����̐��E�ł�����x��)�Ƌ��Ԏ����Ԃł���B�����ς̐����́A�u����葐�ł��V�����ڂ��������Ԃ��āA�悻�䂫�݂̂ǂ�̊O���𒅂āA���̂܂��̏\�ܖ�̔ӂɖ��̘V�̏�ł�����������̐Ԃ����v�ł���B�����ς͐����ŗ���ł��g����C�����삷��B���邢�����̔ӂɁA�̂��̂��Ȃ���A����A���A�|�v���Ȃǂɍ��|���ČC��D���B���_���`����̂́A�u�Ђ��肩���₯�A�������܁A���悩�����A��������Ɓv�Ƃ������̂ł���B���q�̃v���c���C�����ɍ���悤�ɂƁA�u���`���[���̓v���c��l�Ԃ̌C���Ɍ��K����ɏo�����Ƃ܂ł���B�C���ɂȂ��Ȃ��g������Ȃ��v���c�́A�ϐg�̌m�Â����܂��s���Ȃ��B���_�ɂ��ƁA�u�����ς͔��������̂��̂Ȃ�A����ɔn�ɂ��A�ɂ�Ƃ�ɂ��A�Ԃ��ɂ��A�Ȃ�ł��Ȃ肽�����̂ɂ����v��B�������Ƃ�����m�Â�ς܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m�Â����܂��i�܂Ȃ��v���c�́A�V����̂����ςƂ��āA�w�Z�ɍs���ė{���p���w�сA���ݕv�l�̗{�����̎x�z�l�ƂȂ����B��́A16���I�̗{����l�����̐����v���o������悤�ȓW�J�ł���B���_�͂�����̐��̖{���̎d����Y��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ς̂��Ƃ��Ƃ̎d���́A�u���̒��ɐl�������ς肱�v�݁A��̒��ɍ���~���邱�ƂȂ̂ł���B�Â�������������͖������������֒ė�����B�G���x���̐��E���u���`���[���͂Ȃ��������Ă���B�������A�����ς����������q�͂��邪�A�Ȃɂ��Ă͐G����Ă��Ȃ��B
�@�����ς͘b�̓r����Ō�Ɂu�u���P�P�P�N�X�I�v�Ƃ����^�̖��������邱�Ƃ������ƂȂ��Ă���B�n�E�v�g�}���w�����x�̃j�c�P���}��(���̐�)���u�u���P�P�P�c�N�X�v(��g���ɔŁA�����Z�Y��)��A������B�Ԃ��˒��|���Ƌ��ɖ��w�����x(����40�N�T��)�ł��u����b�A����b�v�̑��Ɂu�Ԃꂯ���������v�ƖĂ���B���{�ł��͓��̖����̓`���͂��邪�A�h�C�c�A�`�F�R�o���ŁA�gWrekekex koax koax�h�Ƃ����^�̖����Ȃ̂ł��낤���B�`���y�b�N�u�J�b�p�̘b�v�ɂ́u�O���O���O���b�N�X�v�Ɓu�N���N���N���J�P�v�Ƃ����J�b�p�̃J�b�v�����o�ꂵ�A�u�����킹�Ȑ������������āA���킢���I�^�}�W���N�V���A�������܂ꂽ�v�Ƃ���B���������A���_�́w�����Ƃ����ρx�̑}�G�ł͑��q�̂����σv���c�ɂ͕��e�ɂ͂Ȃ��I�^�}�W���N�V�̔��̂悤�Ȃ��̂�������ɐ����Ă���B��͂�A���̐��Ɗ^�͏d�Ȃ鑶�݂Ȃ̂ł��낤���B�畆����������Ǝ��̂��^�Ɠ����ŁA���Y���������q�Ƀu���`���[���͈�T�Ԃ��炾�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������Ȃ����B���̐����ɁA�u�����ς��Ă����̂́A�����イ���炾�𐅂ł݂�߂Ă��Ȃ���Ȃ��̂ł��B�����A���܂ł�����킸�ɂ��Ă݂Ȃ���B�Ђӂ��₯�ǂ����݂����ɁA�Ђ�Ђ肵�Ă����v�ƃu���`���[���͌����Ă���B�Ȃ��A���_�̂����͐l�����������Ƃ��d���ŁA�R�[�q�[�E�~���̂悤�Ȍ`�̓���������A���̈����o������A�u���A�����A���Ȃ蕗�A�J�A�����A���݂Ȃ�A���Ȃт���v���N�����B���ɏq�ׂ�|�[�����h�̕��������Y�B�[�i�╗�����^���B�F�c�ɒʂ��鐫�i�������Ă���悤���B
�@�C�W�[�E�W���[�`�F�N�́w�ǂ��Ԃ@���������x�̊����u���[�t�E���_�̂����v�ŁA�u�����������[�t�����v�ɂ��āu����˂��~�P�V�����@�Ƃ������Ł@�����ς�@�悤�����Ɓ@���肠���Łv�Əq�ׂĂ���B�܂��A�J�����E�|���[�`�F�N�����w�ڂ���͂��ς��T�l�g�x(����c���q��A��g���N���ɁA1990.11.19)�ŁA���N����̎v���o�̂悤�ɂ��āA�����܂�ʼnj���ł��ĉ����ɑ�����������ꂽ���̂��Ƃ��A�u�ڂ����J�b�p����Ȃ����Ǝv���Ă���B�����ĂЂ��ς������̎肪�₽���Ăʂ�ʂ邵�Ă�������ˁv�Əq�ׂĂ���B
�`�F�R�̐l�X�ɂ͐��̐��͓��{�͓̉��̂悤�ɐg�߂ȑ��݂̂悤�ł���B
�@�|�[�����h�ɂ��Ă͌I�����Y�u�|�[�����h�͓̉��`�� Utopiec�v(�u�|���j�J�v��Q���A1991.12.15�A�P����)pp.181�`199�ɏڂ����B���y�ʐς�30�����Ώ�����߂�|�[�����h�ɂ͐��̐��̓`���������A�u���̋S�_�����́A�ꕔ�͎��R�̐��̗͂̉��g�ł��邪�A�ꕔ�͐l�ԂɋN���������A�Ƃ��ɐ����l�̍����琶�����d���ƐM����ꂽ�v�B���̐����Ӗ�����W���I��b��topielec�g�s�F���c�A�����`topielica�g�s�F���c�@�ł��邪�A�u���̂Ɠ`���͒n���ɂ���Ă��܂��܈قȂ�v�ƌI���͕Ă���B�암�V�����X�N�ł͕���utopiec�E�g�s�F�c�ƌĂ�A���̐��̋{�a�̐����I�ɂ́u���Ԃ��ɂ�����ƚ�̉��ɂ͓M�������l�X�̍����v�����Ă����B���̉����֘A��čs���ꂽ���N�́A���̒I�������Ă��܂��A�E�g�s�F�c�ɍ�������������A���Ԃ�����̉��ɒu���ꂽ�B�E�g�s�F�c�ɂ͍ȂƓ�l�̖����������A���N�����킢�����Ɏv���������炩�班�N�̍�����肾���A���̒��ɓ������B���N�͐����Ԃ邱�Ƃ��ł����B�E�g�s�F�c�͗ΐF�̏��j�ł��邪�A���̖������͔������ƍl�����Ă����B�܂��E�g�s�F�c�����H�h�j�[�N���l�A���̌��̉��ōȂ̂��߂̒��C��D���B�E�g�s�F�c�̓��{���łȂ��A�u�Ԃ��X�g�b�L���O�v(�V�����X�N�̏����̖����ߑ��̗v�f)�ŏ��������т���B
�@�g�㏺�O�E�O��ցE������r�E���J����Y�E�X���B�狤��ҁw�|�[�����h�̖��b�x(�P���ЁA1980.7.20)�ɂ��g�s�F���c�̘b�����^����Ă���B�J�W�~�F�V���E���C�`�c�L(1807�`1879�B�u�|�[�����h�̖��b��`�����܂Ƃ߂čŏ��ɏo�ł����v)�A������r��u�����l�̗d���vpp.141�`148�ł���B�`�F�R�ƈ���āA�|�[�����h�ɂ͊C������̂ŁA�o���g�C�ɂ��u�����l�̗d���v�͂��āA�̐��Ŗ�������U���A�C��Ɉ������荞�ށB�ΐF�̊{�E�A�������Ă���B����ɂ́u�l�Ԃ̎p�������A�w�̍����A��̂悤�ɔ������`�v�̂��̂����āA�Q��ʼnj���ł����肷��B���̂悤�ȗd����������ʂȔ\�͂����܂���������u�l�v���X�`�v�ƌĂ��l�X�������B�h��������(�z���S)�ɑR���锒���r�������Đ��܂ꂽ�l�X(�N���[�X�j�b�N�A���B�G�h�S�j���A�Y�h�D�n�`)�A�z���S�Ɛl�ԂƂ̊Ԃ̎q�ǂ�(���@���s�[�����B�b�`)�ɕC�G�������\�͎҂ł���B�u�����l�̗d���v�Ƒ肳��邭�炢������A���̂��邢�͎���M�ꎀ�҂��A�����̗͂��S��A�����Z���Ƃ��Đ��҂𐅂Ɉ��������A�Ƃ����̂������̓`���ł���B�g�Ă����������̓M���l���琶�܂ꂽ�d���Ƃ��l����ꂽ��A���悾���łȂ����X���������āA�`�F���W�����O��l����������Ƃ��M�����Ă����B���B�X�����u�N��ɂ͓��ʂȏ��̐��̐������ꂽ�B�u�X��̎����v�����Ă�����A�u�ΐF�̊��v��t���Ă����肵���B
�@���̐��������W�[�k�̓t�����X�̓`���ł��邪�A�h�C�c���o�R���A�|�[�����h�ɂ��`����Ă���B�m�[�x�����w�܂���͂������l�`�F�X���t�E�~�E�H�V��(1911�`2004)�́w�|�[�����h���w�j�x(�������E�����F�E����[�`�E���J����Y�E�X���B���A���m�J�A2006.5.10)�ɂ̓������W�[�k�ɂ��Ď��̂悤�ȋL�q������B
�R�m������̏���l���������W�[�k�́A�|�[�����h�̓ǎ҂̂������ł��傢�ɐl�C�����B���̕���͒����t�����X�Ő��܂�A�����̌���ɖ|��|�Ă��ꂽ�B�������W�[�k�Ȃ�l���͂����炭�u���[���E�����W�k�v�ɗR�����Ă���A�����W�k�͋M���̉ƌn�h�E�����W�j�A���Ƃ̐�c�̏����Ɗm�肳���B�������W�[�k�́A���Ƃ��b�̏���l���̑����Ɠ��������l���b�ł������B�T�Ɉ�x�A�y�j���ɂ��̔����������̓��T�E�J�k���̐��̈��Ŕ��������֏�l�ɕϐg���āA��ň�����߂����̂������B�ޏ��͌������đ����̎q�������������B�v�ɂ͓y�j���ɂ͎����̎p�����Ȃ��悤�ɁA�Ɨ��ށB�ޏ����v�𗠐��Ă���ƈӒn���������҂ɍ�����ꂽ�v�́A�s�K�ɂ��ޏ��𓐂��邱�ƂɂȂ邪�A�v�̌��ӂ͂��܂��̕s�K���������B���̕���ɂ́A���l�◳�ȂǂƂ̌������ӂ�ɕ`����Ă���B����͑����̔ł��d�ˁA��\���I�ɂȂ��Ă��c�ɂ̎s��Ō���ꂽ�B�܂�����̓|�[�����h���烍�V�A�ɓ`������B
�@�������W�[�k(�|�[�����h�ꃁ���Y�B�[�i)�̖��́A�V��Ɏ������V�����f���A�Ől���̌`�̑����̂��̂��w�����ƂɂȂ����B�܂����������Ђǂ����łł͂Ȃ������̂��Ƃ��A�|�[�����h��ł̓����Y�B�[�i�ƌĂ�ł���B(p.100�A��O�́@�l����`�Ə@�����v�|�\�Z���I�Ə\�����I�����A�X���B���)
�u���������Ђǂ����łł͂Ȃ��v�Ƃ́ABuautiful, not overly strict girls were also called �gmelusines�hin Polish. (Czeslaw Milosz �A�gThe History of Polish Literature�h�A1983�A p.53)�̖�ł���B�܂��A�M��{�Łu�T�Ɉ�x�A�y�j���ɂ��̔����������̓��T�E�J�ɕϐg���āA��ň�����߂����̂������v�Ƃ��������͉p��łł́AOnce a week (on Saturday) this beutiful maiden was transformed into a mermaid and would spend the whole day in a spring. �ƁA�l���ɕϐg����Ɛ������Ă���B
�@�I�����Y�̓������W�[�k�ɂ��āA�ʂ̕��ʂ���Љ�Ă���B�u�|�[�����h�͓̉��`���v�ɑ����q�|�[�����h����杁r�̂R��ځu�������^���B�F�c�A���������Y�B�[�i�v(�u�|���j�J�v��R���A1992.11.20�App.192�`209)�ł���B���^���B�F�cLatawiec�́u�ނ������N������C�̐���v�ŁA�����C���N�u�X(�C���L���o�X)�Ƃ����ꎋ���ꂽ�B�����̃��^���B�F�c�̓��^���B�c�@Latawica�ŁA�X�N�u�X(�X�L���o�X)�ɓ���A�u���Y���̗삩�琶�������̂ŁA�������ۂƓ��ꎋ�����v�B�X���u���E�ł́A����A��������Ɏ����҂͗d���A�S�_�̗ނɂȂ�ƐM�����Ă������A���^���B�F�c�����l�̑��݂ŁA�j���j�N���������ƂȂ�A��������߂�ꂽ���́A�u���l���j������������Ȃ����߂ɃA�_�����G���@�̖���^���āA���ƌ��t�������Đ���������邱�Ƃ͑�ςȎ蕿�v���ƍl�����Ă����B
�@�V�����N�X(�V���W�A)�ł́A���̋S�_�̓����Y�B�[�iMeluzyna�ƌĂ��B�l�X�Ȍ����`�������邪�A�l���u�X�B���[�iSyrena�v�ƌ��т����A�l�Ԃƌ������q�������܂ꂽ���A�v����j��A�q�������̂��Ƃ��v���ċ����Ă���(���̉�)�ƐM����ꂽ�B�t�����X�̃������W�[�k�͖��T�y�j���Ɋ���Ȏp(�l���E�֏�)�ɖ߂邪�A�|�[�����h�̕����́u��N�Ɉ�������A�N���X�}�X�E�C���̓��ɂȂ�ƁA�̂̔����͐l�Ԃ̖��̎p�A�����͋��̎p�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̎p����l��v�ɔ`�������āA�ނ����Ƌ��ɉ��˂����ы������Ɠ`�����Ă���B���̌����`����P���Ɏ~�߂�A�ǂ����Ă����w��i�����ꂽ�t�����X�̃������W�[�k�`���̉e�����w�E�������Ȃ邪�A�w���M�ɂ��ė킵�������Y�[�B�i�̕���x(1847�N)�̖|��҃��[�t�E�����pJosuf Lompa�́A�����w�҂ł����������A���w��i�Ɩ��ԓ`���̉e���W�ɂ��Ă͔ے�I���ƌI���͓`���Ă���B�Ȃ��A�|�[�����h��ւ̍ŏ��̖|��́A1569�N�A�}���`���E�V�F���j�NMarcin Siennik�ɂ��h�C�c��łɂ����̂ł���B
�@���_�����Y�B�[�i�̓`���̓|�[�����h�̗אڒn��A���|�[�����h�̂̃`�F�R�A�E�N���C�i�ɂ������A�`�F�R�ł̓��B�F�g���j�c�Fvetrnice�A�����Y�B�[�imeluzina�ƌĂ�A�u�����߂��܂Ƃ����A�������ꔯ�̏����ŁA���˂̒��A�ˊO�ł͖݂̒�����ł��߂�����������v�Ƃ����B�E�N���C�i�ł͕��̉����́A�u���C���̉Ԃ̍炭����A�����������قǂ����p�Ō���v�A�u���ɂ���ė���ƁA���̔N�͖L��ɂȂ�v�Ɠ`����ꂽ�B���C���∟���̖L�������I���݂Ƃ��ẮA���X�����̃��T�[���J�A���̗d��������B����ɂ́A�앨����މJ�����Ɋ֘A�����`���Ƃ������B
�@�ȏ�|�[�����h�̕��������Y�B�[�i�ɂ��Ă͑S�ʓI�ɌI�����Y�̋L�q�Ɉˋ����Ă���B�I���́q�|�[�����h����杁r�͋g�㏺�O(1928�`1996�A������w�����A���V�A�E�|�[�����h���w�B�Ȃ͓��c�䳎q)�̎G���u�|���j�J�v�ɖ����A�ڂ��ꂽ�B
��P��A�u�|�[�����h�̃o�W���X�N�`���v�A�u�|���j�J�v��P���A1990.8.30�App.145�`154
��Q��A�u�|�[�����h�͓̉��`���v�A�u�|���j�J�v��Q���A1991.12.15�App.181�`1999
��R��A�u�������^���B�F�c�A���������Y�B�[�i�v�A�u�|���j�J�v��R���A1992.11.20�App.192�`209
��S��A�u�^���̐��ƎR�W�v�A�u�|���j�J�v��S���A1994.2.20�App.178�`191
��T��A�u�z���S�v�A�u�|���j�J�v��T���A1995.6.30�App.198�`209
�@�������A����A�`���E���b�̖|��A�Q�l�����A�}�G�ƁA�����[�������Љ�s���Ă���B�Ȍ���Q�Ƃ��邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@���Ƃ�����I���ɂ́u�X�����̐_�b�`���ɂ�����u���v�v(�w�_�b�E�ے��E�����@�R(�R�̓��[�}����)�x�A�y�发�@�A2007.5.10�App.11�`22)�����邱�Ƃ�t�������Ă������B�u�����ăX�����l�̖��ԐM�ɂ����Ă͋�����˕��͈����̏o���ƌ��т���ꂽ�v�u�u�������v�͗l�X�ȕa�C�̍����ł���A�ƍl����ꂽ�B�ł�����ׂ����͐l�X�ɉu�a���邢�͐��_�a�������炷���ł���v�Ƃ̋L�q������B
�@�u�|�[�����h�̘̐b���v�Ƃ��ďЉ��Ă���u�X�U���J�Ɛ��̐������v�Ƃ����b���w�����h�����łЂ�������x(���鐴���^�e�G�A���R�����q�^���b�A�邵�̎蒟�ЁA1989.8.1[��4��]�App.26�`33)�Ɏ��^����Ă���B����ŐQ�߂��������̐��̉����������A���~�ŐS�D�������X�U���J���ʕ���A�X�U���J�̌ق���ł��������~�ȕS���͌�H�ƂȂ��čs���m�炸�ɂȂ�Ƃ�������ł���B���̐������ɂ��āA�u���̐������̓J�G���ɂ悭�ɂĂ��܂��B�傫�����J�G�����炢�A��ɂ͐�����������܂��B�ۂ��傫�ȖڂƑ傫�Ȍ��A�Z���㒅�𒅂āA�悭�ӂƂ��Ă��܂����B�v�u��ӂŃJ�G�����L�C�L�C���킢�ł���̂́A���̐��̂��ǂ��������͂��Ⴂ�ł��邩��ł��v�Ƃ���B
�@�u�X�U���J�Ɛ��̐������v�͏���r�v�ҁw���E�̖��b�@��T���@�����Q�x(���傤�����A1977.8.10)�����u�����ɂ��ăX�U���J�͐��̐��̖��t���e�ɂȂ������v(pp.114�`128)�Ɠ����b�ł���B�|�[�����h�E�h�C�c�E�`�F�R�̍����n��V���W�A�̃|�[�����h��Z���̘b�����ƂȂ��Ă���B�n���Ƃ��Ă̓_���J�E(�_���R�t)�A�I���T��Ȃǂ��o�Ă���B���̐��ɂ��ẮA�u���̐��̗Y�͂��������Ђ������邭�炢�̑傫���ŁA���Ɗ�͏�����Ɏ��Ă���B�@�͂��@�ŁA�w�Ǝw�̂������ɂ́A���Ђ�̂悤�Ȑ�����������B���Ă�����̂͒Z����߁A�܂��͏���ς�A�����o���ς��Ă��āA�݂ȉh�{���悢�v�Ƃ���B���̉��l���������X�U���J�́A�����Ȃ����f���āA���������̍����������ƌ����A������܂ꂽ����̉��q�̖��t���e�ɂȂ�B���̉���͍��ȑ���ŁA�u����A���o�X�^�[��A�嗝�A�_�C���A��A�܂��͕ǂ����v�ŏ����A�ʍ��͋��ƃ_�C�����ł������B�u�܂��ԂȂ��ނv�ɂ���܂������q�́A�u���������������Ƃł́A���̂��ׂĂ̐��̐��ƕς��v�Ȃ��������A�X�U���J�������グ�āA�O��z�ɃL�X���āA���ɉ������Ă�ƁA���q�́u�����܂����ڂ������������l�Ԃ̎q�v�ƂȂ����B���̐��Ƃ킩��̂́A�w�̊Ԃɐ��~�������邱�Ƃ����ł������B���q���������Ȃ������Ƃɖ����������̐��̉��́A�X�U���J�̊肢�u�I���T�삪�×����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ɓv�������A����ɐQ�m�����ׂ̍��_�ɕς��ĕ��B�X�U���J�̉\�����������̉��̓X�U���J�����q�̍Ȃɋ��߂��B����A�X�U���J�̌ق���́A���̉��������邱�Ƃŋ��邱�Ƃ��o�����A�t�ɒ~�������܂ł����m�ɂȂ��Ă��܂����B�e�ؐS�������b�ł��邪�A���̐��͐l�Ԃ̐^�S�ɐG��邱�ƂŁA�����ς��邱�Ƃ��o����(���̐��̉��q���������Ȃ����悤��)�Ƃ������Ƃ́A�E���f�B�[�l�A�l���P�ɒʂ���A���[���b�p�̐��̐��ς̌���ł��낤�B
�@�|�[�����h�Ɛl���ƌ����A��s�����V�����̖�͂Ɍ��Ə|�����l�����g���A�s���̕����̒n�_�ɐl�����������邱�Ƃ́A�����̐l�����Ă���ʂ�ł���B���̈����Ƃ����`���͗l�X�ŁA�ǂꂪ�Ñ̂�`���Ă���̂����f�ɋ�����B
�@�����V������13���I���Ƀ}�]�t�V�F�������B�X���쒆���̉͊ݒi�u��Ɍ��݂������Ƃ���n�܂�B���ꂪ���s�ŁA���ꂩ��1���I�قnj�ɖk�ׂɐV�s�����݂���A���݂̃����V�����s����\�����Ă���B1413�N�ɂ̓}�]�t�V�F�����̎�s�ƂȂ����B�|�[�����h�����̗��j��10���I���Ɏn�܂�A�s�A�X�g�����̃J�W�[�~�F�V��1��(1038�`1058)�͎�s���N���N�t�ɒ�߂����A13���I���ɂ͑召24�A5�̌��������݂����B14���I�㔼����̓��M�F�E�H�����̎���ƂȂ胊�g�A�j�A�E�E�N���C�i���܂ލL��ȃ|�[�����h�E���g�A�j�A�A������(1569�N)���������A�����Ɉʒu���郏���V�����̏d�v�������܂�A�N���R�t�̉��{�̉Ύ�����A�W�O�����g3��(1587�`1632)�̓����V�����Ɏ�s�@�\���ڂ��A1611�N�A�����ɉ����̎�s�ƂȂ����B�����V�����̖�͂̋N���ɂ��Ă����������邪�A
14���I���ɂ͌��Ə|�����������~�����̉H����t�����h���S����̉����g�Ə㔼�͊��������l�Ԓj�����`���ꂽ�ӏ����m�F�ł���悤�ł���B16���I���ɒj���͏����ɁA���͂Ȃ��Ȃ�A17���I����18���I�ɂ����āA�h���S����̉����g�͋��`�Z�C���[���ɂȂ����B�ȏ�̖�͂͋��s�̂��̂ŁA�V�s�ł͉����ƃ��j�R�[��������͂��p�����Ă����B�|�[�����h�̓v���V�A�A�I�[�X�g���A�A���V�A�ɂ���ĕ�������A���V�A�̎x�z���ɓ����������V�����ł́A�l���̖�͂�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�A�Ăюg����悤�ɂȂ����̂�1918�N�A�Ɨ��A�|�[�����h���a���ɂȂ��Ă���ł���B1938�N�ɃV���`�F�X�j�[�E�N�����^(Szczesny
Kwarta�A1894�`1980)�f�U�C���̖�͂��̗p����A1967�N�ύX���ꂽ���A1990�N����Ăюg�p�����悤�ɂȂ����B���Ə|�Ŏs�����ӏ��͍ŏ�����ŁA�h���S����l���ɑւ��͂������A�s�̖�͂̓����V�����̐l�X�̋��菊�A��R�̃V���{���Ƃ��ďd�v�ȈӖ���S���Ă����B�l���Ƃ̌��т��͓r������̂��̂ŁA���̈������͂����肵�Ă��Ȃ����A���ꂾ���炱���F�X�ȓ`����l�X�͕t�����A�V���ȓ`�������܂�Ă��Ă���B
�@Artur Oppman�̓`������͎̂��̂悤�Șb�ł���B���s�̃��B�X����ɂ͔������̂��̂��l�������āA�Ԃɂ�����������������A���̎ז������Ă����B���t�����͈�x�͖ԂŐl����߂܂������A���̉̐��ɖ������ĕ����Ă�����B�����ɐl����߂炦�Č������ɂ��悤�Ƃ������l������ė��āA�l���������ɉ������߂Ă��܂����B�ߖ������_�v�炪�l����������A���̂���ɐl���̓����V�����̐l�X�����������ɂ͏����������ׂ̂邱�Ƃ����B���̂��ߐl���͌��Ə|�ŕ������Ă���̂ł���B
�@Maria Kruger�́u���M�ȃO���t�B���Ɣ������l���v�͈�����b�ƂȂ��Ă���B�����̃����V�����̖h�q�̓O���t�B�����S���Ă����B��������ăo���g�C�ɏo���O���t�B���͔������l���ɋ������ɂ������B�O���t�B���ɂ��ă����V�����ɂ���Ă����l���́A����Ȍ��l�Œ�������Ă����B������A�G���x�������ɎO���t�B���͓|��A�����Đl�������Ə|�ŗ����������������ʂ����B�l�X�͂���Ȍ�s�̖�͂ɐl���̎p�����ނ悤�ɂȂ����B
�@�܂����̓`���ł́A�}�]�t�V�F�̌��q�����ɏo�����A��Ől���Əo������Ƃ���B�l�������������ǂ������q�́A���鋙�t�̏����ɍs�������B�����ɂ͑o�q�̐Ԃ�V����ĂĂ����e�����Č��q�ɐH�ו����^�����B���q�͒j�̎q�ɂ̓����XWars�A���̎q�ɂ̓T��Sawa�Ɩ��t����悤�Ɍ����A�����̎���̓y�n��^�����B���q�����̘b�����Ă��鎞�ɁA�삩��l�����p�������A���̓y�n���������s�s�ɂȂ邱�Ƃ�\�������Ƃ����B
�@���������̂̓}�]�t�V�F���łȂ��A�|�[�����h���J�W�[�~�F�V���剤(1333�`1370)�ŁA�N���N�t����O�j�F�Y�m�������r���A���B�X���쒆���̒n�ŁA���t�̃s���[�g���ɐV�N�ȋ���H���ɏo���ꂽ�B���t�ɂ͑o�q�����܂ꂽ����ł��邪�A���̒n�ɂ͋���Ȃ�������������Ȃ��ł����B���͋A��ɍĂї�����邱�Ƃ�ė��������B����A���͎i�Ղ��ăs���[�g���̌���K��A���t���e�ɂȂ����B���q�̓����X�A���̓T���̖��A�s���[�g���͉����̋��t�ƂȂ�A��т̐X�т̏��L�҂ƂȂ����B���̒n�����W���ă����V�����ƂȂ�B���̘b�ɂ͐l���͓o�ꂵ�Ȃ��B
�@�Ⴂ���t�̖��������X�������A�Ƃ���b������B�����X�͐�Ő����т����Ă������������U��Zawa���D���ɂȂ�A������\�����ށB����ƃU���͋�������A�������l���Ől�ԂƂ͌���Ȃ��g�ł��邱�Ƃ������A���ɉ���ɂ͑��蕨�������Ă���Ɩ���B���̑��蕨�Ƃ͌��Ə|�ł������B�U���͍Ăщ���Ƃ͊���Ȃ����A�킢�ł��̌��Ə|��p����Ό����Ĕj��邱�Ƃ͂Ȃ��ƍ����A�����X���p�Y�ƂȂ��āA�f���炵���s�s�̌��ݎ҂ƂȂ邱�Ƃ�\������B��l�̗����L�O���āA�����X�̌��Ă��s�s�̓����V�����ƌĂ��悤�ɂȂ����B
�@�g�㏺�O�́u�|�[�����h�e�n�̒n���I���̂̋N���⒬�̖�͂ɂ܂��`���͖����Ɂv����Ƃ��A�ŌÂ̓`���̈�Ƃ��āA�u�O�j�F�Y�m�̒���z�������t�ƁA���̌Z��`�F�t�A���X�̓`���v���Љ�Ă���B���t�̓|�[�����h�����̑c�A�`�F�t�̓`�F�R�A���X�̓��V�A�l�̑c�ł���B�O�l�Z��͂��ꂼ�ꍑ����̂��߂ɎO���ɕ�����ė��������B�k�Ɍ����������t�̖��Łu���т̎��X����|����A���z�����Ƃ����Ƃ��A�������V�̑傫�ȑ�(�O�j���Y�h)������B���t�͂�����g���Ƃ݂Ȃ��A�������V������̐킢�̈�Ƃ��A�����ɒz��������O�j�F�Y�m�Ɩ��Â����v(�w�|�[�����h�̖��b�x�A�P���ЁA�g�㏺�O�u����v)�B
�@�܂��A�吼�m�����l�̐l���̎o�����o���g�C�Ɍ������A�����Ȗ����R�y���n�[�Q���`�ɗ��܂�A�͂̋����o�̓O�_�j�X�N���烔�B�X�����k�サ�����V�������s�X�ɒH�蒅�����Ƃ����V�����`�������܂�Ă���B
�@���݃��B�X����̋��̂����Ƃɂ��V���[�i��(Pomnik
Syreny)��1939�N�A����������Loise (Ludwika Krasowska-)Nitschowa(1889�`1989)�����삵�����̂ŁA���f���͏������lKrystyna
Krahelska(1914�`1944)�ł���Ƃ���(�ޏ���1944�N�W���P���Ɏn�܂��������V�����I�N���ɖS���Ȃ����B�I�N��63���ԑ��������A�h�C�c�R�ɒ�������A�����V�����̑啔���͔j��A���҂�65���l�ɋy��)�B���s�X�ɂ��鏬�U��Ȑl�����V�����J(��������Ȑl���@Pomnik
Syrenki)�͈������ŁA1855�NKonstanty Hegel�ɂ���Đ��삳�ꂽ�B�L��̒��S�Ɉڂ��ꂽ�B���̑��ɂ��l�����͂���A��͎͂s�̎{�݁A�o�X�A�H�ʓd�ԁA�^�N�V�[�Ȃnj�ʋ@�ւƂ����悤�ɖڂɂ���@������B
(�ȏハ���V�����̐l���ɂ��ẮA�A���u�����[�Y�E�W���x�[���w�|�[�����h�j�x[�����Е��ɃN�Z�W���A1971.1.5]�A�����V�����s�����E�F�u�T�C�g�A���Q��)
�@�w�����h�����łЂ�������x�ɂ͂���������̐��̐��̘b�����^����Ă���B�u�n���K���[�̘̐b���v�Ƃ���u�݂����݂̏��v(pp.88�`93)�ł���B����̏��̉������������̗d���̉����A�������̒j�������̂����ď����ɓ������ꂳ����B�V�������͉������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��B�d�������͈ȑO�̂悤�Ɍ݂̊ɏo�ėւɂȂ��ėx��A���l�͖̓��Œ��Q���y���ށB�ɏ�������ł���̂��������̂ŁA���̎�҂����͎��X�Ɉ����グ�ɍs�����N���A���Ă͗��Ȃ������B��l�̎�҂��d���̉����̏����āA�Β�̐����{�̃G�������h�̕����ɉB���Ă�����������o���ē˂��ƁA�d���̏�͕���A�d���▂���͍��ɖ�����Ă��܂����B���͍Ăї�q���ɒ݂���A�l�ԂƂȂ����d���̉����͎�҂ƍK���ɕ�炵���B�ɒ����u�����v�̓n�E�v�g�}��(1862�`1946)�̕��w��i�ł��邪�A���́u�n���K���[�̘̐b�v�Ƃ͈قȂ镨��ł���B
�@�n���K���[�ɂ͒����ő�̌o���g����(�ʐς͔��i���ЂƂ܂�菬����)�����邪�A���̌̓`����`���Ă���̂́w�\�A�E�����̖��b�x(���E���b�̗��S�A���E���E�珑�[�A1970.2)pp.176�`185�ł���B�����ł�����䂪�Ԃȏ����̎��߂�������J�Ԃ��A�����̎��i�S�ɂ�鐅�ɂ̂܂�đ傫�ȌɂȂ�Ƃ����b�ł���B���i�̑���͗d���̖��o���g���ŁA�l�X�̓o���g���̐��炩�ȓ����v���o���A�ɂ��̖���t�����B���ɒ��މ䂪�Ԃȏ����̍��Ƃ́A�u���^�[�j���̃C�X�̓`�����v���o������(�V�������E�M���A�L�c���Y��w���߂�s�@�C�X�̒��`���x�A�z���ЁA1990.9.10)�B�C�X�̉��_���͐l���ɂȂ����Ƃ��`�����Ă��邪�A�o���g���ɒ������̂��̌�͌���Ă��Ȃ��B
�@�X�C�X�̃c�[�N�̐��̐��j�N�V�[�́A�n���W�Ƃ����������̎�҂̃��[�f���ɖ������āA�ނ��̂����ɗU���B�n���X�͐��̐��ɗU��ꂽ�҂͓�x�Ɩ߂�Ȃ��ƕ����Ă������A�j�N�V�[�����̒ꂪ���ɂȂ����炢�ł��n��ɖ߂��Ɩ����̂ł��čs�����B���������x�ɁA�n���W�̖]�ޕ����玝���Ă����j�N�V�[�́A���ɑ����̂��̂��Β�Ɏ����Ă��Ă��܂����B�n���W�͗����镨���Ȃ��Ȃ�A����Ȍ�c�[�N�̒����݂͌Β�ɒ���ł���Ƃ����B���̐����U���Ă����l�Ԃ�n��ɖ߂��̂ł͂Ȃ��A�n�セ�̂��̂𐅂̐��E�ɍČ����Ă��܂����Ƃ����b�ɂȂ��Ă���B�V���[���[�E�N�������w�l�����b�W�|���E�̐l���b�|�x(1997)�̑�S�b�u�n���W�Ɛ��̐��v���`����b�ł���B��������ɂ��ƁA1435�N�̈��A�c�[�N�̑��̈ꕔ���ˑR�A�ɒ��Ƃ����B���̐Z�H��p�ɂ����̂Ȃ̂��낤���A���̐��̎d�Ƃ��ƍl�����l�������̂ł���B�c�[�N�̐��̐��̘b�́AFritz Muller-Guggenbuhl���AKatharin Potts�p��A�gSwiss-Alpine Folk-Tales�h(Oxford University Press�A1958)�App.93�`96�A�u�c�[�N�̐l��The Mermaid of Zug�v�ł�����Ă���B
�@�u�c�[�N�̐l���v�ł̎�҂͒��̏��L���̑��q�ŁA�̐l���͖����Ɏv�����Ă����B��҂��{�[�g�ŌΖʂɏo�ė����܂ɁA�l���͂��̎v���������A��҂��l���̔������Ɉ�����A���̌㉽�x����@���������B�l���̕��A�̉��́A�����l�ԂƉ�̂��D�܂��A��҂����̐��E�ւ���ė��Ȃ�����A����ȏ����Ƃ��ւ����B��҂́A���̐��E�ł������čs�����Ƃ��ł��鐅���l��������炢�A�Β�̐����{�Ŋy������炵�Ă����B����܂�̒ʂ�A�n�オ���������Ȃ����v�����āA�l���͎�҂��Z��ł������͂̂Q�X��̉ƁX�̈��ݐ��ɖ��@�̖�����A�l�X���������Ƃ��Ɉ�������āA�n��̐��������Β��Ɉڂ��Ă��܂����B���ł��A�Õ��Ȑg�Ȃ�̐l�X��A����̏���I���K���̉����������畷�����A����ȏ�ʂɏo������l�X�͋F��������Ƃ����B
�@���̐��͔ă��[���b�p�I�`���ł���A�A�C�������h�E�A�C�X�����h���烍�V�A�܂ŁA���ʂ��镔���A���فA�`�d�ȂǑ����̂��Ƃ��l�����邪�A�S�ʂɐG��āA�����������Ȃ�łȂ����e�̒��q�����邱�Ƃ�m��Ȃ��B�L�����̐��̋L�q��������̂����߂邱�ƂɂȂ�B�ʌꂲ�Ƃɂ͖��m�Ȃ̂ŁA���ꂼ��̐��ƂɈˋ����鎟��ł���B�V�����m���������邱�Ƃ́A�����ł��ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�����䂢���Ƃ����v�����Ȃ��B�Ȍ���A�I�ɂ��鏑���̐��b�ɂȂ�Ȃ���A�X�������E�𒆐S�Ƃ������̐���q�˂邱�ƂɂȂ낤�B
�����@�G