東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>33P
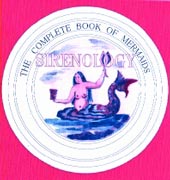
人魚の歌や声が気になっていた時に出会った本から紹介してみよう。
「ホーイ ホーイ ホーイ」これが『アザラシの少女セリナ』(レーシー・ヘルプス作、河毛二郎・福島栗雄訳、セーラー出版、1987.11.12。原題Selina, the Circus Seal、1967)で語られる人魚の歌である。サーカスから逃げ出したいと思っているアザラシをアナグマが手助けをするという絵本であるが、その逃げる先がコーンウォールのセント・アイブス、人魚の歌が聞こえる所であった。その地が選ばれたわけは、「人魚の歌をいちどでもきいたものは、よその土地でしあわせにくらすことはできない」という言い伝えであった。アザラシの少女はかつて人魚の歌を聞いたのであろうか。その歌は「かつてきいたことのない、不思議な音」であり、「悲しい歌」のようでもあり、「歌声についていくと、そのまま海の中につれていかれる」というものであった。アナグマが見たのは、「海から黒っぽいものが浮かびあがり、平たい岩の上によこになる」姿でした。それは人魚なのか、アザラシなのか、アザラシの少女セリナは人魚の仲間なのか、判然としないが、アナグマがお礼にもらった白い貝からは波の音、そして、人魚たちの歌声も聞こえてくるようだった。
レーシー・ヘルプス(Racey Helps)は1913年2月2日、ブリストル生まれ。母からスコットランドの血を受け継いでいる。美術学校中退の後、古書籍商となるが、娘のために書いた絵本がウィリアム・コリンズの目にとまり、初期の作品のほとんどはコリンズから出版されている。邦訳は、河毛・福島訳の4冊のみで、セリナの他は、『はりねずみパイ』(Prickly Pie、1957)、『ティーポットのひみつ』(Two from a Teapot、1954)、『ふたりはなかよし』(Two's Company、1955)で、すべてセーラー出版、1987年11月12日発行である。ティーポットはネコと二匹のネズミ、パイはハリネズミ、ウサギ、キツネ、モグラ、なかよしは野ネズミ、ハリネズミ、カエルというように小動物が擬人化されて語られる世界はビアトリクス・ポター(Beatrix Potter、1866〜1943)やジル・バークレム(Jill Barklem、1951〜、のばらの村のものがたり)、シンシア/ブライアン・パターソン(Cyntia、Brian Paterson、B1949〜、フォックスウッドものがたり)、スーザン・バーレイ(Susan Varley、1961~)に通じる世界である。40作以上の作品があり、ヨーロッパ諸国で翻訳され、主人公の動物はカードや絵葉書になっている。
訳者河毛二郎(かわけじろう)は、1987年当時王子製紙社長、福島栗雄は王子製紙参事という異色のコンビである。河毛の著『逆風順風』(日本経営者連盟広報部、1994.5.20)から出版の謂われを拾ってみよう。仕事上の縁があったセーラー出版社長、小川悦子から翻訳の打診があり、河毛は一人では心許なく思い、社内の英語専門家福島の共訳ということで承諾したという。福島栗雄は1919年、米国オークランド生まれで、14歳まで同地で過ごし、東北大学英文科卒後、海軍兵学校外国語教官で終戦を迎え、1948年王子製紙入社という経歴の持ち主である。河毛は旧制高校文科時代から英語原書に親しみ(中にはロレンス『チャタレイ夫人の恋人』もあった)、戦時中も英語に親しみ、晩年はタイム、エコノミストの他、シェルダン、フォーサイス、アーチャー、グリシャムなどの小説を原語で楽しんでいた。翻訳書はヘルプスの絵本が初めてであったが、その時の心境を、「この年になって多少でも「英語を読む」という道楽から脱皮して、幼いこれからの日本を背負う子供たちの夢を、情操をはぐくむ一助にでもなったかと、近来ないすがすがしい気持ちになった」と記している。もっとも、翻訳はこの時限りで、「私は二度とやる気はない。理由は極めて簡単、翻訳ほどむずかしいものはないからだ。これはやった者でないとわからない」との他の所では書いている。
河毛二郎の経歴を、これまた『逆風順風』を中心に素描してみると、1918(大正7)年8月2日男子の双子として生まれる。双子の兄一郎は東大法科卒業後、運輸官僚となり、第13代海上保安庁長官(1968〜1970)を務め、退官後日本海員掖済会会長となり、1988年6月20日に亡くなっている。一郎、二郎には姉、妹(五人兄弟姉妹)がいるが、父は幼いときになくなり、祖父の元で母(母の実家は滋賀県旧丸屋町の書店、五車堂)と共に生活していた。
祖父河毛三郎は金沢出身の官僚で、若い時分は滋賀県庁に勤務していた(その頃の三郎の著書に『衆議院議員選挙法実用』[明治23年3月]がある)。明治の終わりから大正にかけて北海道渡島支庁長を務め、大沼公園に桜を植えたということもあった。官を退いてからは金沢に住み、水力発電の会社を経営し、65歳で引退した後は、「謡曲と囲碁に明け暮れ、また官吏として北海道で過ごしたときからの趣味であったアイヌ語と日本の地名との関係について研究をこつこつと続けていた」。
一郎、二郎は金沢一中、四高をを経て、共に東大に進学した。二郎は昭和13年東大経済学部に入学。日本経済史の土屋ゼミに籍を置き、論文が入選し、その賞金で岩波「日本資本主義講座」を手に入れ読書会を始めるが、マルキシズム理論研究の嫌疑で元富士署に連行された(昭和15年9月)。起訴にならなかったが、留置は二ヶ月以上に及んだ。昭和16年、王子製紙に入社。当時の王子製紙は藤原銀次郎(1869〜1960、1920〜1938年まで王子製紙社長)の後を継いだ高島菊次郎(1875〜1969)、足立正(1883〜1973、1942〜1946年社長)の社長時代で、国内洋紙生産80%のシェアを誇る企業であった。王子製紙は当時の南樺太に9工場を持ち、パルプ45万トン、紙20万トンを生産していた(王子の全工場数36、洋紙生産量は70万トン)。河毛は樺太恵須取(ウゴレゴルスク、西海岸)工場で敗戦を迎え、昭和23年8月までソ連の下で同工場に勤務し、真岡(ホルムスク)港から函館へ引き上げてきた。戦後の王子(昭和24年、過度経済力集中排除法のより、苫小牧製紙[のち王子製紙]、十条製紙[のち日本製紙]、本州製紙[1996年、王子と合併])での仕事は企画、人事に関わり、1982年から1989年まで社長を務め、以後会長、相談役、名誉顧問となる。その間、1990年から1995年には日経連副会長と務め、1994年には経団連日本ロシア経済委員会委員長に就いている。業界団体の製紙連合会会長も1990〜94年務めた。
10歳年下の由已子夫人は羽仁進と小学校のクラスメイト、武満徹夫人浅香とは恵泉女学園の同級生で、二郎共々のつき合いが続いた(第二随筆集『私のカウントダウン』には「武満徹さんと私」という章があり、「弔辞」も収録されている)。子息河毛俊作(フジテレビ、ドラマディレクター、1952〜)も谷川俊太郎と武満との思い出を語っている(『谷川俊太郎が聞く 武満徹の素顔』、小学館、2006.11.20、pp.130〜161、「第5章 徹さんは、ロックスター−河毛俊作」)。
河毛二郎にはペルプスの翻訳4冊、『逆風順風』の著作の他に、『私のカウントダウン』(日経連出版部、2000.7.10)、『紙は生きている』(トランスアート、2003.11.12)の2著がある。その文章は自己の経験を語るとき、心に伝わるものがあり、コモンセンスに満ちた紳士の文である。2004年5月24日、肺ガンのため85歳で死去された。
人魚と人間とのコミュニケーションは、人間が普通に考えるような言語によるものではないというのが、ジェイン・ヨーレン(Jane Yolen、1939〜)の立場のようだ。ヨーレンはたびたび人魚に関する著作を刊行しているが、まずは1997年の絵本『男の人魚』(The Sea Man、クリストファー・デニーズChristopher Denise 絵)を見てみよう。1663年に、オランダ軍艦に救助された人魚の話である。漁網に絡まった人魚を救助した軍艦内では、不吉な者なので殺して売ってしまおうとする船員等と人魚に同情心を持つ副船長(船長は上陸中で不在)とが緊張関係にあった。人魚の様子は、指の間に灰色の膜があって水掻きのようで、口は魚のように丸く、目は水色、髪は灰緑色、首には赤い鰓があり、尾はマグロのよう、鱗は銀青色というものであった。魚のような口には歯はあるが、舌がなかった。副船長は人魚に話しかけるが、舌がないので言語によるコミュニケーションは無理だと判断し、困惑する。人魚は悲しい歌のような音を発し、知性、感情、人間とは形式の異なる言語を持ち、物語の最後には副館長と手話による交流が見られる。人魚は嵐がやって来ることを教えてくれるのである。鰓と水掻きがあり、舌を欠くので言語でなく手話や口から発する水中の気泡で交流するという人魚の設定はヨーレンのヤングアダルト小説『水晶の涙』(村上博基訳、ハヤカワ文庫、1987.10.31)[The Mermaid's Three Wisdoms、1978]でも同様である。短篇「人魚に恋した乙女」(ハヤカワ文庫『夢織り女』所収)でも、人魚は海中では手振りとつぶやきで話しを伝えると述べている。
絵本の最後に「著者の覚え書き」があり、この物語がヨーレンの「マーマン」調査中にであった資料に触発されたことを記している。ヨーレンには既に『ネプチューン・ライジング:海に住む人々の歌と物語』(Neptune Rising、1982)という19編の詩と物語による水の神・精の著書があるが、「男の人魚・水の精」に特化した昔話再話集を2001年にシュラミス・オッペンハイム(Shulamith Oppenheim 、1930〜。オッペンハイムには『セルチーの種』The Selchie's Seedという人魚関連の著がある)との共著でまとめた(ヨーレンとオッペンハイムの共著には『海の王』The Sea Kingという絵本もある)。『魚の王子ほかの物語:マーマンの民話集』(The Fish Prince and Other Stories:Mermen Folk Tales)である。そのp.4に「ネッカムは12世紀に男人魚を見たことを記述している。1554年にはロンデレティウスの記述もある。1663年には宣誓付きで、水兵が男人魚を捕獲したと証言している。その人魚はオランダの沿岸を泳いでいて、海軍大尉に捕獲された。また、1726年には、オランダの植民地の船長が「アンボイナ自然誌」を著し、魚譜の部分で男人魚Zee Menschenと人魚Zee Wyvenを事実として引用した」と書いている。これは絵本の覚え書きと重なっている。
絵本の基となった1663年のマーマンについてはこれ以上知るところはないが、オランダでは1660年にスワルトワーレの教会に乾燥人魚が吊されていたことが知られている。また、1554年の人魚とはいわゆる「海の修道士」のことである。海の怪物として諸書に引かれているので、大方はご存じであろう。手近な例としては、小学館文庫『アラマタ図像官1「怪物」』(荒俣宏、1999.6.1)p.51にゲスナー『怪物誌』からの「海坊主」として図が確認できる。同書p.54には「海の大主教」も見え、荒俣は「修道士が身にまとう衣服に似た頭部を持つ巨大なダイオウイカが正体といわれている。この種の怪物がカトリック腐敗を断罪するシンボルとしてマルティン・ルターらに利用された経緯については、総解説で述べた」「一説に、海坊主や海の大主教の正体を海産哺乳類とするが、やはりダイオウイカが原形になっているものとみなしたい」と説明している。同書p.129、p.132にはパレ『怪物について』から「僧服を着た海の怪物」「僧正魚」が転載されている。パレは「修道士の頭をして鱗に覆われた腕とからだを持つ海の怪物」についてロンドレの魚譜を引き、ノルウェー海域で見られ、その姿から「修道士」と命名されたと記している。また「司教の服装をした海の怪物」についてもロンドレから、1531年にポーランドで目撃されたことを伝えている。
「海の修道士」Sea monkについては水谷仁氏からステーンストルプ関連の論文をご教示いただいた。パックストンとホランドが「ステーンストルピア」(コペンハーゲン大学動物学博物館紀要)誌に発表した「ステーンストルプは正しかったのか?−16世紀エーレスンド海峡の海の修道士について新解釈」(Charles G. M. Paxton & R. Holland. 2005. Was Steenstrup Right? A New Interpretation of the 16th Century Sea Monk of the Oresund−Steensttrupia29(1):39-47)である。
ステーンストルプ(Japetus Steenstrup、1813〜1897)は、デンマーク、コペンハーゲン大学教授の動物学者で、1854年に「海の修道士」の正体はダイオウイカであるとの説を発表した。そもそも16世紀の「海の修道士」とはどのようなものであったかというと、デンマークのシェラン島とスウェーデン南部間の海峡エーレスンド(英名サウンド海峡、独名ズンド海峡、バルト海と北海を結ぶ。島田荘司「人魚兵器」には「オーレスンド大橋」と「オーレスンド地方」の描写がある[島田荘司『溺れる人魚』、原書房、2006.7.3、pp.113〜183])で、1546年に捕獲され、デンマーク王クリスチャン3世(1503〜1559)から神聖ローマ皇帝カール5世(1500〜1558)に図が送られた奇妙な生き物のことである。その特徴は、全体に人間のような形態で、頭部は修道士のように頭頂が剃られていて黒く、からだ全体は僧衣をまとっているように見え、赤や黒の斑点がある有鱗の海の生物、大きさは4エル、言葉を話すことはなくため息だけを発し、陸上で3日間生存した後、埋められたという(乾燥標本になったという伝承もある)。ゲスナー(Historiae Animalium動物誌、1558)の他に、同時代の博物学者としてはピエール・ブロン(Pierre Belon、1517〜1564)『水生生物について』(De Aquatilibus、1553)、ギョーム・ロンドレ(Guillaume Rondele、1507〜1566、ヨーレンが引く「ロンデレリウス」はそのラテン名)『海産魚譜』(Libri de Piscibus Marinis、1554)が報告している。ブロンはpiscis monachus(修道士魚)、ロンドレはpiscis monachi habitu(修道士のような服装の魚)と呼んでいる。ステーンストルプはブロン、ロンドレ、ゲスナーを含む8つの最初期の「海の修道士」に関する記述を検討している。パックストン/ホランドは更に3例を加え、ダイオウイカより可能性が高い生物を提示している。「海の修道士」はカスザメであったというのが彼らの結論である。大きさ、鱗の有無、頭部の色、口の位置、胸鰭(腕)の有無、腹鰭、体色、尾鰭、バルト海での生息、北海での生息という10項目について、海の修道士、ダイオウイカ、カスザメ、ジェニー・ハニヴァー、アンコウ、ハイイロアザラシ、ゼニガタアザラシ、モンクアザラシ、ズキンアザラシ、セイウチを検討し表化している。パックストンらは4エルを62cm×4で約2.5mとして大きさを比較している。カズザメは中世からSquatinusとして知られていて、当然ブロン、ロンドレ、ゲスナーにも既知の魚類であるという点を認めつつ、海の修道士はカスザメだろうとパックストンらは推定している。monk fishは現代英語でカズザメ、アンコウを指すので、真っ当さに拍子抜けするが、巨大イカ説が常識化しているので異説として注目してよいのかもしれない。
ジェニー・ハニヴァー(jenny haniver)は荒俣宏の読者などには既知の怪物であろう。エイなどの乾燥体を加工して頭部、翼、尾を形成され、初期にはドラゴン、バジリスク、後には人魚に類したものとして博物誌に記載された生き物である。Anversアントワープに起源を持つという説もある。片瀬の土産物屋の店頭で見かけたこともあり、現在でも作られている息の長い幻獣である。ジョアン・フォンクベルタ、ペレ・フォルミゲーラ『秘密の動物誌』(菅啓次郎訳、筑摩書房、1991.12.5)pp.137〜140には「スカティナ・スカティナ」ニンギョモドキとして登場している。
ヨーレンが伝える1726年「アンボイナ自然誌」の人魚は、日本では六物新志が引くファレンティン「東インド誌」(Francois Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indien, 1724-6)の人魚として有名である。
花連的印(ハレンテイン)東海諸島産物志安具那(アンボイナ)部に曰く、和蘭(オランダ)開国一千七百十有二年、熱伊物以弗(ゼイウエイフ)−此に海女と翻す、を東海武魯(ブーロ)(亜細亜洲小島の名、東の方爪哇、安具那等の島と隣す)の海に捕へ獲たり。輙ち(竹+御)を構へて之を潮汐通ずる所の池沼に養ふ。然ども之と言ふに對ること莫く且つ絶へて其の聲音を發せず。之に食を與ふるに甞めず。又た人未だ其の嗜好を知らず。百計を以て之を押しまんと欲すれども終に其の情を得ること能はず。四昼夜三時半にして而して竟に斃ると云ふ。其の物長さ五十九拇指横径又た禮印狼度(レインランド)−國名の度を以て之を度るに凡そ五脚因て其の之を得るの之由る所を聞くに、則ち安具那島主の臣沙米烏児花児烏爾(サミウルハルウル)なる者之を武魯島の海に獲たり。其の生けるや之れが真を寫し其の死するや之を薬汁の内に貯ふ。其の形日を歴して稍短縮す。已にして而して之を其の主般垤児私的爾(ハンデルスアル)に献ず。般垤児私的爾、一覧して而して之を還す。蓋し此の物往往之有て、而して敢て珍奇とせざるか。故に又、沙米烏児花児烏爾、寫す所の之圖を觀る。則其の頭面眼耳鼻口胸腹乳房臑臂腕一つに婦人と相同じ。唯其の色白ふして而して淺蘭色を帯ぶるの意有り。其の眼球淡青色をなす者の此を異とするのみ。其の髪は則干項後に垂れ、灰白にして淺蘭色を帯ぶ。凡そ上體臍より顎下に至るまで之を度るに、長さ十四拇指横径にして、下體臍より以下は則魚なり。而して其の上下體分界の處と臍より両脇下の處に至るとに當て、而して半規の大小珠を生ず。各十枚大珠小珠を擁して並列して相附著す。小珠色白く其の大さ各々私咄伊的児(ストイテル)の如し−按ずるに、小児玩弄する所の丸子其の大小未だ考えず。大珠の色各々小珠と同じ。其の大さ各々小珠に四倍。而して大小珠相ひ附着して而して其の状恰も纓絡の如し。鰭大小珠の下より生ずる。其状ち猶を摺疊扇を展開する若し。凡そ其の數十四片、毎片其の大さ一指横径、其の色黄にして淺蘭色の細理有り。或は六條或は七條又た鰭毎片其の末各々其の方に向ふて捲曲す。其の前に當て最も長き者は其の捲曲の長さ小指の中節と同じ。此れより左右漸く短く漸く小にして而して其の両季に在る者は約するに臍部横径と一指横径と相ひ併合することの長さに過ぎず。蓋し鰭の全状亞奈那私(アナナス)花の萼に似たり。而して其の物これを以て上下體の間隔を作す者の若し− 亞奈那私は本と草の名、圖説和蘭本草に詳。下體は鱗鰭倶に加児不爾(カルプル)魚−鮒鯉の類−の如くにして、而して其の鱗間隔を作すの鰭下に接近する者は、其の色青し。此より以下は尾前界埒を作すの處に至て、而して其の色白く青を帯ぶ。其の鱗二處倶に滑澤にして而して它魚と異なること無し。間隔鰭より尾端に至るまで其の長さ三十五拇指横径なり。又た下體上下二面倶に鬣有り。而して其の鬣上面二處、下面之れと相ひ當る處にも亦た二處、共に四處となす。各々長ふして並に列る。恰も格子の如し。大抵間隔鰭及び四鰭尾、此の三つ者の其の状ち皆相ひ似たり。又た下體の終り尾と相接する處一肉輪有て、而して三大珠其の上に生ず。其の色黄にして而して淡紅を帯。蓋し肉輪自ら下體と尾の間隔を作すに似たり。
ファレンティン著『新旧東インド誌』アンボイナ島の部分には、1712年にブル島の海中でzee wijf人魚が捕獲された、とある。飼育場を作って海水が通じる水辺で飼ったが、問いかけても答えることはなく、声も発しなかった。食物を与えても食べなかった。何を好むかもわからず、いろいろ試みたがうまく行かなかった。4日と7時間後に死んでしまった。人魚の体長は147.5cm、5フィートであった。人魚が捕獲されたことを聞いたアンボイナ島商館長の部下サミュエル・ファロアーズ(Samuel Fallours)は、生存中に写生し、死後は薬品に浸け保存した。日の経過と共にやや収縮した。ファロワーズは商館長ファン・デル・ステル(Adriaen Van der Stel)に献上したが、商館長は一瞥して返還した。人魚はそれほど珍しいものではなかったのだろうか。ファロアーズが描いた図を見てみよう。頭、顔、目耳鼻口、胸、腹、乳房、肩、腕は婦人とまったく同じである。肌の色は白くて、やや青っぽい。目が淡い青色なのが唯一変わっている点だ。髪は後に垂れ、灰色に青みを帯びている。上半身、臍から首までの長さは35cm、下半身は魚体である。上体と下半身を分ける辺り、臍から脇腹の周囲に半円形の大小の珠がある。大きな珠は10個あって小さな珠が附着していて帯のようになっている。小さな珠は白くて、大きさはおはじき程である。大きな珠の色は小さな珠と同じで、大きさは4倍である。大小の珠はそれぞれ附着していて、装身具のようである。鰭が珠の下から生じている。その形は扇子を開いたようである。鰭の数は14片、1片の大きさは2.5cm(?)、黄色で、薄い青の線がある。線は6〜7本で、鰭の先端は曲がっている。曲がっている部分の最長はは小指の真ん中の関節ほどの長さがある。鰭は左右に分かれて曲がっているが、段々短く小さくなり、(その最も端にある鰭はウェストに2.5cm加えた長さしかない−−この部分、私には正しく解釈できない。)腰回りの鰭の全体の形はアナナスの花に似ている。これで上下の部分を分けているように見える。下半身は鱗、鰭、ともに鯉のようである。鱗の色は上部は青く、下部と尾の前の部分は白くて青色を帯ている。鱗は青の部分も白の部分も滑らかで蛇のようである。腰の鰭から尾の端までの長さは87.5cmである。魚体の部分は上下に鬣のような鰭があり、上面に2鰭、下面にも2鰭、同じような位置にあって、合計4つの鰭である。それぞれ長くて、上下並行して、格子のようである。腰回りと魚体の4鰭の形は似通っている。下半身が尾と連なる部分は盛り上がっていて、3つの大きな珠がある。色は黄色で淡い紅色を帯びている。この肉輪も下半身と尾と分けるもののようだ。
六物新志の記述は人魚捕獲とその後の経緯、人魚の形態説明という二つの部分から成っている。この人魚についてはルイ・ルナール『モルッカ諸島産極彩色魚類、エビ・蟹類図譜』(Louis Renard:Poissons, Ecrevisses et Crabes de Diverses Couleurs et Figures Extraordinaires, que l'on Trouve Autour des Isles Moluques、et sur les Cotes des Terres Australes、1719、1754、1782)の巻末に載る「人魚のような怪物」(Monstre semblable a une Sirenne)が有名である。ルナールはファロアーズの絵を元にして刊行したので、六物新志の形態記述を追認することができる。現在ではネット上に何点もあるが、1990年代初期には荒俣宏『ファンタスティックダズン第9巻 極楽の魚たち』(リブロポート、1991.5.20)pp.116〜117で見ることができた。図に付けられた説明には、「アンボイナ州のボルネあるいはボエレン島の海岸で捕獲された人魚に似た怪物。長さ59インチで、全体はウナギのようである。陸上の桶の中で4日と7時間生きていた。時々、ネズミのような鳴き声を立てた。小魚、貝、カニ、ザリガニなどを与えたが、食べなかった。死後に、ネコがするような糞が桶の中に見つかった」とある。六物新志とほぼ同じ内容である。ルナールの人魚図は尾が右方向に向かっているが、ファレンティンの図は反転した左方向に伸びる尾をしていてノコギリザメなどの魚類と描かれている(ルナールのものは、触角が真っ直ぐのびたゴシキエビと並べられている)。人魚の腰にアナナスのような腰簑が描かれ、葉の根元には周縁に小珠7〜9を持つ10枚の半円形の房が描かれている。この腰簑を持つ人魚は時に目にするが、私は今まではアラベスク模様のような植物と動物が結びついた装飾の名残だろうと思い、人魚の重要な特徴だとは考えていなかった。また、神社姫に描かれる宝珠は稲荷の狐にもあるような日本的信仰の現れだと思っていた。だが、六物新志で人魚の珠を特筆していることに気づき、西洋伝来の図の影響も考慮する必要があるかも知れないと思い始めている。だが、ファレンティンの原著を見ていないので、珠の記述が訳述なのか、図を見て(その場合は彩色したものであるが)大槻玄沢が説明しているのか断定できないので、玄沢が珠にこだわっているのかが今はわからない。
フランソワ・ファレンティン(1666〜1727)はオランダ改革派教会に属し、1685年、19歳で東インド会社によりアンボイナに牧師として派遣された。10年後にオランダへ戻るが、1705年、妻と子と共にアンボイナへ行く。従軍牧師として東ジャワへの遠征にも加わるが、健康を害した。オランダへの帰国を願うが、なかなか許されず、帰国が叶ったのは1714年であった。5巻9冊の『新旧東インド誌』を完成させ、1724〜26年に刊行した。アンボイナの自然誌記述はルンプ(George Eberhard Rumpf、ラテン名ルンフィウスRumphius、1627〜1702)に多くを依っている。ルンプはドイツ生まれで、オランダ東インド会社に雇われた博物学者。アンボイナで多くの新種を発見した(ルンプについては西村三郎「〈インドのプリニウス〉−ゲオルク・エーベハルト・ルンフィウス」[西村三郎『未知の生物を求めて−探険博物学に輝く三つの星』、平凡社、1987.3.18、pp.26〜79]に詳しい)。
ファレンティンの人魚記述は、エマソン・テネント卿(J. Emerson Tennent、1804〜1869)の著『セイロン島自然誌』で窺うことができる。ファレンティンは東インド誌魚類の章の最初に「Zee-Menschen, Zee-Wyven」人魚を持ってきている。ファレンティンはジュゴンを知っていて、伝承の人魚と似ていることを認めつつ、古代から知識人が目撃し伝えた人魚とはジュゴンの見間違えではないと主張している。1653年には、アンボイナ沿岸行軍中のオランダ兵の集団が間近に泳ぐ男の人魚を見たとファレンティンは言う。人魚は髪が長く、灰色と緑の中間の色をしていた。その目撃から6週間後にも、同じ地点で白日の下、50以上の人が人魚を再び見た。これほど確実なことはないとファレンティンは主張する。1661年4月29日には、タクアン寺院の近くの水域で、午前中に男の人魚、午後には女の人魚が目撃されたとアルバート・ハーポート(Albert Herport)が伝えている。また、六物新志が訳述する1714年、ブロ(ブル)島の人魚こそファレンティンが人魚を確実視できる確かな証拠であった。ファレンティンは人魚の実在に関する多くの例を挙げ、他の実在する魚類に関する報告と合わせて記述している
アンボイナの人魚は有名になり、オランダ駐在のイギリス公使は、ロシアのピョートル大帝をアムステルダムで迎えたとき、大帝が生きたままのアンボイナの人魚を実見したいと述べたと、ファレンティンの手紙の中で披露している(1716年12月28日)。人魚の存在証明の最後に、ファレンティンは自国オランダで1404年に見つかった、いわゆるエダムの人魚を語っている。嵐のため、エダムの堤防を越えて、生きたまま発見された人魚は、プルメル湖からハールレム市に運ばれ、オランダの婦人から糸を紡ぐことを教えられ、数年の後、カトリック教徒として死んだ、というものである。ファレンティンは熱心なカンヴァン教徒であったが、事実の前では、カトリックだとしても否定はできなかった。
ファレンティンが伝える歴史上の人魚記述者は、プリニウス(23?〜79)、ガザのテオドール(Theodore Gaza、c1398〜c1478)、トレビゾンドのグレゴリウス(George of Trebisond、15世紀)、アレサンドロ・アレサンドリ(Alexander ab Alexandro=Alessandro Alessandri、1461〜1523、ナポリの法律家)などであるが、プリニウス以外はその人となり、人魚記述について私は知るところは今のところ皆無に近い。ファレンティンは以上の記録、実見体験から、「海牛」「海馬」「海狗」「海樹」「海花」などがあるので、人魚の実在は間違いないと主張した。
ファレンティンの教会活動を手伝ってもいたサミュエル・ファロアーズ(1706年9月から1712年5月まで、副牧師補の任にあった)は兵士として東インド会社に雇われたが、魚類図を描く画家として働くようになった。実物の魚類も描いたが、既にあった他の画家の手による図、また自身が一度描いた図も複製して、需要に応えてもいた。その原図を元に魚類図譜を出版したのがルイ・ルナールである。ルナールはフランスのユグノーであるが、1685年、ナントの勅令廃止家族と共にオランダへ亡命し、1703年、アムステルダムで書店、出版業を開始(〜1720年頃)。1717年にはイギリス国王ジョージ1世(1660〜1727、国王在位1714〜1727)のエージェントとなり、廃位となったスチュアート朝の復位運動をオランダで監視、阻止の活動をしている。次王ジョージ2世(1783〜1760、国王在位1727〜1760)にも仕え、生涯イギリスのために働いている。ルナールについてはワシントン大学教授シオドア・W・ピーチ(Theodore W. Pietsch)の論文(‘Louis Renard' Fanciful Fishes:A collection of grossly inaccurate scientific illustrations has some merit after all’−Natural History, 93(1),1984.1,pp.58〜67)、図譜複刻がある。
ファレンティンは1715年8月28日のルナール宛の書簡で、アンボイナの魚類の驚くべき色彩を実際のものと保証し、ファロアーズが実物を見て描き彩色したと伝えている。それほどルナールの魚類図譜は美しく、誇張されていると出版当時から考えられていたのである。ピーチは、the work is clouded by embellishment, exaggeration, and outright falsification−so much so that the book has been ignored by virtually all nineteenth- and twentieth-century biologists. と述べている。ルナールの図版100葉には460種の生物が描かれている。内訳は魚類416(415)、甲殻類40(41)、直翅目昆虫2、ジュゴン1,人魚1である。ピーチは416の魚類について、211は種レベルで同定でき、83が属、56が科を同定することが可能としている。ライデンの自然誌博物館のホルツイス(L. B. Holthuis)は40の甲殻類で24を種、6を属、4を科で同定した。結論としてピーチは16%が全くの空想の産物であると言っている。荒俣宏は「ファロワズの図には、不正確さや誤りを吹きとばすほどの迫力と陶酔とが備わっており、それが見る者を圧倒する事実を、われわれは認めねばならない。これはむしろ、標本に忠実であろうとするあまり、かえって幻想にとらわれた〈巧まざる結果としての空想画〉なのだ。実物をしっかりみつめていながら−それでもなお生じてしまった空想がなのだ」と言っている。なお、ピーチにはファロアーズの人魚図についての論考(Samuel Fallours and his “Sirenne” from the province of Ambon)があるが、未見である。
ヨーレンのマーマン昔話集を少し覗いてみよう。この本はプロローグとエピローグの他に9つの章に分かれている。北ヨーロッパ、ロシア・スラブ世界、英国、南ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカ、太平洋地域、南北アメリカの9章それぞれで、人魚・水の精を紹介しつつ昔話の再話を載せている。他の地域では直接分からない点もあるので、日本を見てみよう。アジアは日本から始まっている。日本の水の精/神では、龍王Sagaraから始まり、金比羅、河童、田螺、「池の精」、鮑、寄り神、夷三郎、鮫人が紹介されている。河童の好む移動手段は「空飛ぶキュウリ」flying cucumberとはやや奇異に聞こえるが、河童の他の記述は良しとしておこう。Sagaraとは、あまり聞き慣れないが、神功皇后の三韓征伐の時に力を貸した海神のことで、潮干、潮満の珠を授けたオオワタツミノミコト、トヨタマヒコノミコトはその異名だとヨーレンらは記述している。「娑(沙)伽羅」龍王のことである。まあ、そこそこに正しいのだろう。知らない地域の記述では気にならないが、日本のことだと少し正確ではない点が目に付く。それは、自分自身にも返ってくることで、大して知りもしない外国の例を書き連ねている時は後ろめたい気持ちに駆られる。ゼロよりは、まあいいだろうと思って、書いているのだが、不正確な点、不明瞭な点、明らかな間違い、寛大に見守っていただき、ご指摘下されば幸いである。
ヨーレンはアメリカのアンデルセン、現代のイソップなどと紹介されることもあるが、昔話の再話集、絵本、ヤングアダルト作品、詩など200以上の作品がある。最近では、恐竜絵本(『きょうりゅうたちのおやすみなさい』『きょうりゅたちがかぜひいた』小峰書店)が有名である。1939年、ニューヨーク生まれ、スミス・カレッジ卒業後、編輯助手を務め、1965年から専業作家となる。日本語に訳されているのは、全作品の1割にも満たない。ハヤカワ文庫FTの5点も現在は品切れであろう。人魚への興味を強く持っていることは指摘した通りで、ハヤカワ文庫の『水晶の涙』『三つの魔法』『夢織り女』、絵本『グレイリング』の他、未紹介の『ネプチューン・ライジング』『シー・マン』『魚の王子』『海の王』などの作品がある。もっとも、人魚の関心は、更に大きい昔話への愛好の一部ということもできる。10冊以上の昔話再話集があり、中でも『世界昔話選集』(Favorite
Folktales from around the World、1988)は有名である。「彼女がもっともよく知られているのは、現代のテーマを例証するのに古い物語の要素を用いて書く民話や童話である」という評もある。なお、マーマン昔話集『魚の王子』の巻末には海神語彙集が添えられていて、世界中から66の神名が集められている。日本の海神としては、金比羅、オオワタツミ、龍神、水天宮、スサノオが立項されている。また、『ネプチューン・ライジング』に収録されている作品は、「ネプチューン・ライジング」「乙女とマーマン」「リア老王」「ウンディーネ」「グレイリング」「白いアザラシ娘のバラッド」「スケリィ岩礁」「セルキーの真夜中の歌」「アザラシと共にいる老人」「デイヴィ・ジョーンズの海の棺桶」「漁師の妻」「人魚に乾杯」「河の娘」「海の回廊」「骨董店のマーマン」「マレイシアの人魚」「変身」の19編である。詩や昔話、短篇が散りばめられている。
ヨーレンの『シー・マン』はオランダを舞台にしていて、そこからオランダ東インド会社の牧師ファレンティンなどに話を繋げたが、オランダの都市には市旗に人魚をあしらったものを使っているので、最後にその謂われを紹介しておこう。
ゼーランド州ショウエン−ドゥイヴェランドの市旗は向かい合う男女の人魚と黄・青・白・黒の4色が使われている。西ショウエンの漁師たちの網にマーメイドがかかり、マーマンが放してくれるよう涙を流して懇願した。漁師は嘲笑って、その要求を拒絶した。すると、マーマンは呪いの言葉した。西ショウエンは呪いの通り、何度か海水に浸かり多数の人命が失われたという。
ファレンティンも触れているエダムの人魚に関係深いプルメルの治水組合で昔使われた旗は緑・黄・緑の横線に錘を持った裸体の乙女と桶を担いだ二人の乳搾り女が描かれていた。裸体の乙女が人魚を表している。17世紀以降干拓地となったプルメルの地は、1403年には人魚が迷い込んだ湖であった。人魚は激しい嵐でザイデルゼー(オランダ西部の湾状の海、現在のエイセル湖)に流され、堤防に空いた穴と通ってプルメル湖に打ち寄せられた。岸から岸へさまよっていたが、海に帰ることはできなかった。人魚の姿は衣類を付けず、からだは海藻と苔に覆われていた。湖の周辺のエダムや他の村の女たちは、牛の乳搾りのため船で湖を渡っていた。その途中で人魚に気付いたのである。人魚を水から船に上げ、エダムに連れて行った。人魚の言葉は誰も理解できなかったし、人魚も人々の言うことは分からなかったが、人魚のからだをきれいにし服を着せ、食事を与えた。人魚はしばらくは水に逃げようとしていた。ハールレムの人々が人魚を求めたので、エダムでは人魚を贈ることに決めた。ハールレムで人魚は糸紡ぎを覚え、長いこと生きていた。生前、十字を切る仕草をしていたので、教会墓地に埋蔵されたという。エダムのプルメル門には記念の人魚像が立っていたという。
フローニンゲン州エエズモンドの市旗は緑・黄・青の横線に人魚が描かれている。この地域の海岸にアザラシが多いことから人魚が使われたという。
今回は絵本を10冊ほど紹介しようと書き始めたが、思わぬ方向に進み、オランダ関連の人魚記事が主になってしまった。漫筆たる所以である。
海の修道士が出現したとされる時代は三十年戦争末期で、プロテスタントのデンマーク王とカトリックの神聖ローマ皇帝への和解の徴の意味があったかも知れず、「海の修道士」とは極めて政治的存在で、実在の生物を想定することは意味がないことかもしれない。このような怪物出現の意味についてはダストン/パーク『驚異と自然の秩序 1150−1750』(Lorraine Daston, Katharine Park, “Wonders and the Order of Nature”, 1998)に詳しい。なお、同書p.150の図版4.3.1.「健康の書」(1491年)では修道士魚とセイレーンを見ることができる。
菅家史朗(aka. MORO)
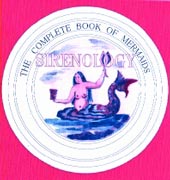
手許に「フォア文庫 2007年解説目録」がある。400冊ほど収録された中で、人魚に関連したタイトルを拾うと、『ふたごの魔法つかい 人魚のうた』(川北亮司)、『赤いろうそくと人魚』(小川未明)、『ジエーラひめのぼうけん 海の王冠』(村山早紀)、『妖界ナビ・ルナ2 人魚のすむ町』(池田美代子)、『魔女探偵団 千年のラブストーリー』(藤 真知子)、『星の牧場』(庄野英二)となろうか。1%にしかならない。
国会図書館で「人魚」のタイトルで書籍検索をすると、587件ヒットする。年代を区切って見てみると次のようになる。
| 明治時代(〜1912) | 3件 |
| 大正時代(1913〜1926) | 12件 |
| 昭和戦前(1927〜1945) | 19件 |
| 1945〜1949 | 11件 |
| 1950〜1959 | 47件 |
| 1960〜1969 | 37件 |
| 1970〜1979 | 59件 |
| 1980〜1989 | 80件 |
| 1990〜1999 | 161件 |
| 2000〜2006 | 158件 |
明治時代の3件は、巌谷小波が2件と南新二「一夜漬人魚甘鹽」である。大正の12件には谷崎潤一郎「人魚の嘆き」、小川未明「赤い蝋燭と人魚」が含まれ、昭和戦前期にはアンデルセンの各種翻訳が入っている。1945年まで合算しても34件で、1950年代の47件に及ばない。もちろん、すべての書籍が網羅されているわけでもなく、定期刊行物掲載作は除かれるが、大体の傾向を窺うことはできる。戦後はそれ以前に比べ「人魚」本は増加し、増加のペースは1970年代以降、加速度的になっている。人魚姫の様々なヴァージョンが含まれているとはいえ、ファンタジー、漫画、やおい系、ゲーム関連と人魚が生息する本は増え続けている。これは日本のみならず、アマゾンでmermaidを検索すると、3、4年前は300から400であったものが、現在では1000を越えている。これらすべてを追いかけることは出来ないが、近年目を通した児童書を中心に、棚卸しをしてみよう。
人魚の知識絵本で最も興味を引いたのはナレル・オリヴァー作/絵『人魚、何と驚くべきもの』(2005年)である。オリヴァーは1960年生まれの絵本作家で、オーストラリア、ブリスベイン在住。環境問題に関心を持ち、オ−ストラリア固有の動物が生息環境にいかに適応しているかを描いた作品で知られている。この人魚の本はオーストラリアでは2001年に出版されている。絵本の常套全32ページで、本文は4つのパートに分かれている。
最初は「実在、非在、それともアザラシの見誤り?」として、コラージュのように世界中の人魚伝承を絵と短い解説で伝えている。バビロンの神格オアンネス、ポリネシアの神ヴァテア、ヒンドゥーのヴィシュヌ、北アメリカ原住民シャワノの人々をアジアからアメリカに先導した魚尾の神、スコットランドの吸血人魚、フィリピンの人魚になった子供、セルキー、ウクライナの人魚、ニュージーランドのマラキハウ、日本の人魚根付け、メキシコの砂漠の人魚、英国中世の羽を持つ人魚、ガーナの人魚タービイン、メロウ、アボリジニーの人魚ヨークヨーク、ヨーロッパの人魚の子孫、ドイツのニクス、15世紀の二又人魚を見ることできる。作者のフィールドであるオセアニア、ポリネシアの人魚伝承は興味を掻き立てられる。また、ヘブリデス諸島のハイイロアザラシのメスは個体変異で体色がピンクになるものがいて、岩に寄り添う姿が人魚と見誤られたこともあったかも知れないと解説している。
次いで、実際人々が目にした人魚の例を挙げる部分である。六物新志にも描かれたアンボイナの人魚、これも江戸時代には情報が伝わっていたオランダ、エダムに漂着した人魚、1881年、ニュー・オーリンズで捕獲された人魚はかぎ爪があった、パウサニアスが伝えているタナグラのトリトン、ナイル川で592年に目撃された雌雄の人魚(これも六物新志にある)、1830年、ヘブリデスでは少年の投げた小石にあたり人魚の少女が死んでいる。1833年にはスコットランドの漁師の網に猿のような顔の人魚が掛かっている。南方熊楠も「人魚の話」で伝えている1560年、当時のセイロンで捕獲された7匹の人魚たち。今まで記録に残された最大の人魚は、887年スコットランドに漂着した。その長さ195フィート(59.4m余り)。
不思議な人魚に魅せられた人々は、フェイクを作ったり、人魚を演じたりするようになった。模造人魚を手に入れるために船を売ってしまったイーディス船長はロンドンで見料1シリングの見世物興行を行った。最も有名な人魚興行はバーナムのフィジー人魚である。また、14世紀のアフリカのベニン王国の王チェンは身体が不自由になったが、廃位を恐れ、下肢が魚尾になって海の神オロクンに変じつつあると言って王位を保った。岩に腰掛けて歌う人魚を装った英国の聖職者もいた。1826年のことである。孤島から救助された海難者を桶に入れて人魚として見世物にしたこともあった。今日でも、コマーシャル、映画、演劇、ショーで人魚を演じる女性たちがいる。
ナレル・オリヴァーの絵本の最後の部分は人魚の伝説・昔話である。「ヨークヨーク:夢の人魚」「コース湾の男性人魚」「人魚とアプサラ」「トフンガ」「魂の籠」の5話が紹介されている。北アメリカの人魚と結婚した娘の話である「コース湾の男性人魚」とメロウが溺死人の魂を籠に入れて海底にとどめている昔話は日本でも何度か紹介されている。ヨークヨークはアボリジニー、トフンガはマオリの話で、この本で初めて知った。
ヨークヨークと記述したがYawkyawkを何と発音するか分からない。ヨークヨークは 北オーストラリアのアーネムランドの人々が信じている水の精である。オボリジニーがしばしば言及する虹蛇ボルングと同一視されることもある精霊である。川から現れ、川の近くに多くの小さな池を作った。善良な要素を呑みこみ、あらゆる水の関連する生物を創造した。魚類、水生昆虫、爬虫類、水鳥などである。近年アボリジニーの芸術家たちはヨークヨークの彫像・画像を多く造っている。環境、フェミニズムへの関心が女性の精霊であるヨークヨークを創作する背景にある。レナ・ヤリンクラ、イエニー・ヌガリンバ、サムエル・ナムンジャ、オーウェン・ヤランヂャらがヨークヨークを創作しているが、それぞれ形が異なっている。女性で魚尾があるという基本はあるが、ヤリンクラは染色した植物繊維で編んだ造形、ヌガリンバ、ナムンジャ、ヤランジャは伝統的な樹皮画である。総じて細長い身体で割れた尾を持つヨークヨークは、髪は長く、川筋やその近くの池は体の一部だと考えられている。ヨークヨークの神話を明確に語る準備はまだできていないが、紹介されることがなかったので記してみた。
マオリのトフンガは呪術師という意味である。ワカタネ村のトフンガは偉大な力を持っていて人々に恐れられていたが、死後その魂は海に入り、マリキハウという精霊、神格になった。オリヴァーは、人々が海で災害に遭うときにはマラキハウが救助してくれると述べているが、長い舌を持つマラキハウはカヌーに乗った人間をのみ込むこともできたらいい。ニュージランド北島の北部と東部で顕著な海の神格(怪物)で、典型的なカウリマツの木像は頭部、身体は人間の様であるが魚尾を備えている。このマラキハウについても詳細は不明であるが、『オセアニア神話』(ロズリン・ポイニャント、豊田由貴夫訳、青土社、1993.6.30)p.15に、管状の長い舌を垂らして魚を捕らえる魚尾を持ったマラキハウの壁板の写真が掲載されている。キャプションには「ニュージーランド北島、トコマル湾にあるマオリ族の集会所(テ・ホノ・キ・ラロトンガ)にある彫刻がほどこされた壁板で、1920年代に建てられた。管状の舌を持った「マラキハウ」という神話上の海の生き物を表している」とある。マラキハウの管のように伸びた舌の先端はカップ状になっていて、魚やカヌーはそこから吸い込まれる。古くは腹部や頭部に三角の鱗がある姿であったが、体の鱗は消え、頭部の鱗は二本の角に変わり、間もなく、角も鱗もないが魚尾を持つ姿となった。この姿の変容は19世紀末、20世紀初頭に起こったとされる。『オセアニア神話』に掲載されたマラキハウは古形を留めた姿のものである。
「人魚とアプサラ」の出典はドナルド・A・マッケンジー『中国、日本の神話』(1922年)であるが、インドの昔話である。難破して、一人不思議な島にたどり着いた若者が井戸の底の王国の女王である人魚と結ばれる。たった一つの条件は、決してアプサラ像に触れないということであった。昔話の約束通り、若者が像の足に触れると、足がのび、ものすごい力で蹴り上げられ、故郷に無一文で帰ったという話である。浦島にも似た話柄だ。
ナレル・オリヴァーは「イーデス船長」と人魚の「乾物」について紹介しているが、その部分で、19世紀初頭の英米では人魚標本の展示はそれほど珍しいことではなく、オラウータンの上半身とサケの身体から作ったまがい物は、日本の漁師の製作品はみごとな出来であった述べている。
これはいわゆる「フィジー人魚」を念頭に置いた記述であるが、フィジー人魚−いわゆる人魚のミイラには多くの問題がある。これらの人魚は本当に複数の生物を繋ぎ合わせたフェイクなのか、という根本的な疑問がある。哺乳類、或いは陸上生物と魚類の交錯点として人魚は意識されたであろうが、その考えに現代の私たちも捕らわれすぎていたかもしれない。今まで紹介した人魚を廻る生物学者たちも、複数の生物から作られたと考えてきた。
内田恵太郎「人魚考」(「自然」1960.8、pp.45〜46)
日本でもよく見世物に出る人魚は、私も数回見たが、上半身は哺乳動物でサル類が多く、下半身は魚で、コイ・ニベ類・オオウナギと思われるものであった。両者は胴で巧みにつなぎ合わせてあるが、魚の鰭の棘には獣骨や獣角と思われるものの削ったのが刺してあった。ミイラのような乾いたもので、長さ1m内外、数回見たが、みな種類が違っていた。むろん作りもので、南シナ広東周辺にはこういう偽物を作って売る者があるそうである。私の見たところでは、上半身の獣も下半身の魚も熱帯亜熱帯産のもののようであった。日本の見世物の人魚は、日本で作られたものではなく、海外から持って来たものに違いない。そしてこれらはシナの説話にもとづいて作られたものと思われる。
日野巌『動物妖怪譚』(上巻、中公文庫、2006.12.20、p.205)
一八二五年頃、日本のある野師が鮭の胴に猿の頭をつぎ足して、人魚をつくりあげた。それをあるオランダ人が買い取って本国へ持ちかえって、同地の学会の大問題となったが、やがてその本体が暴露して学者たちもあいた口がふさがらなかったそうである。
本間義治「妙智寺(鯨波)所蔵の人魚をめぐって」(「蒲原」第78号、1990.5.30、p.5)
妙智寺の人魚はすでに紹介したように、種は不明なもののサルの一種(ホンドサルか?)の頭胸骨に、脂鰭をもつサケ型魚類の一種(多分サケ=シロザケ)の胴体を巧みについだもので醜怪な容貌をしている。
J.R.ノイマン『魚の博物學』(黒沼勝造訳、大日本出版株式会社、1943.7.8、p.551)
半人半魚の人魚は中々消えない傳説で、無智の人々の間では今でも語られてゐる。時には、人間の様な頭に魚の様な體をしてゐる、ヂュゴンやアシカが人魚と思われた事もあるが、その話が中々消えないのは東洋を旅行した人が實際に持歸つた乾燥標本があるからである。然し、これを良く調べてみると、猿の頭と肩とが針金で魚(ナイルパーチが多い)の尾部に巧に結び付けてあるもので、エジプトや支那にこの人魚を慥へて瞞されやすい旅人に賣る者がゐるのである。そして、實際に海で捕へた人の署名のある證明書を附けてゐる。嘗て大リンネはある高官の所有してゐた人魚の標本の眞偽を尋ねる爲にオランダの町を離れようとした事があると云はれてゐる。
皆が上半身はサルであると言う。生物だとすると、人間とは言えないので、サル類にするのであろうが、最近は上半身が生物ではなく作り物だと言う記述も見られるようになった。国立科学博物館「化け物の文化誌」展でX線調査した「人魚ミイラ」は、「身体の内部に頭蓋骨や脊椎骨などの骨要素が全く無い」ので、「完全なつくりもの」であるとしている(「下半身は魚を流用」)。頭部は「張り子(紙塑など)」で作られ「口を開けた部分に魚の口をはめ込んである」と推測している。ミルウォーキー公立博物館所蔵の「ジャパニーズ・マーメイド」は「魚類とパピエ・マシェ(紙張子)の組み合わせ」だと報告されている。同形のハーヴァード大学ピーボディ博物館の「ジャワ人魚」も、以前はサルの頭部と魚尾を結合したものと考えられていたが、1990年の調査で、パピエ・マシェとコイやタイ(porgy)の顎や歯、棘条、鰭を適当にアレンジしたものと発表されている。なお、ピーボディ博物館には、もう一体、1928年にキャリー・ラムによって寄贈された「シャパニーズ」人魚がある。実際、最近作られているギャフ(gaffs)の「フィジー人魚」は完全な製作品である。
日本が人魚の輸出国だとされていることも、幕末の外国人による報告、明治の新聞などで記述されているが、「フィジー人魚」がどこで作られたか確証はないようだ。また、現在日本に残されている「人魚ミイラ」の多くが日本国産であるとも、言えないような気にもなっている。本当に日本は人魚ミイラの大生産地だったのであろうか。そうかもしれないが、上半身サル説のように、無批判に受け入れることにためらいを覚える。
それでは、「フィジー人魚」とは、そもそも、どのような歴史をもった人魚だったかをもう一度みてみよう。幸い、研究書にはジャン(ヤン)・ボンデソン『フィジー人魚、その他の自然、および不自然誌に関する論集』(1999年)があり、ネット上には一次、二次の多くの資料がある。
現在「フィジー人魚」Feejee(Fegee) Mermaid=Fiji Memmaidと呼ばれる「人魚のミイラ」は、興行師のバーナムが「フィジー諸島沖で捕獲した」人魚という由来を説いたことによるもので、東洋からイギリスへもたらされた時には、その名は無かった。最初に英国へ携えてきた人物はナレル・オリヴァーの絵本にも紹介されていた「イーデス船長」サミュエル・バレット・イーデス(Samuel
Barrett Eades)であった。
イーデスは経験を積んだ貨物船ピカリング号の船長であるが、船主ではなかった。7/8の所有者はスティーヴン・エレリィで、イーデスは1/8の権利を持っていたに過ぎない。東インド、つまりインドネシア近海を航行中イーデスは、沈没しそうなオランダ軍艦の船員を救助した。オランダ東インド政府から報償を得ようと、イーデスはバタビアに寄港した。ここで出会ったのが、人魚の乾物(ミイラ)である。オランダ人商人は、日本の漁師から買い取った博物上の驚異を5000スペインドル=1200ポンドという値段を付けた。探検家、驚異の発見者として、世界の中心地ロンドン、故国の中心地ニュー・ヨークに凱旋することを夢見たイーデスは1822年1月、ピカリング号を6000ドルで荷もろとも売り払い、人魚をついに手に入れた(オランダ政府からの報奨金は得られなかった)。イーデスには船を売却する権利はなかったのであるが。
イーデスは人魚を持って、他船(アメリカ船、ライオン号)の乗客となり、ロンドンを目指した。途中、ケープ・タウンで人魚を披露して旅費を稼いだ。また、人魚の話題は宣教師の通信としてロンドンへもたらされた(1822年7月31日発行「博愛通信」。M.フィリップによる。この記事では、人魚は3フィート、ヒヒに似て、6つの鰭と尾を持ち、中国北部で捕獲され、バタビアにもたらされたととしている)。前宣伝である。人々はヒヒに似た恐怖に歪んだような顔の人魚を本物と信じた。
人魚は数週間、税関に留め置かれ、検疫、関税をどうするか問題となるが、イーデスの手許に返された。
税関倉庫に保管されていた人魚を、解剖学者エヴェラード・ホーム(王立外科医大学総長、1756〜1831)の助手ウィリアム・クリフト(ハンテリアン博物館館長)がイーデスの求めによって調査した。イーデスはホームに学術誌に報告する独占権を与えていた。クリフトは、長さ2フィート10インチの人魚が、メスのオラウータンの頭部と胴を加工し、サケ科の魚に繋いだまがい物だと結論付けた。しかし、イーデスは人魚は本物だと思い続けた。
人魚はついに、セント・ジェームズ街59番地「ターフ・コーヒーハウス」(ワトソン氏所有)で、日曜を除く毎日、午前10時から午後5時まで、見料1シリングで公開された。広告はジョージ・クルックシャンク(1792〜1878)が描いた。人魚は尾の部分を曲げた立ち姿でガラスケースに収められた。イーデスらは大忙しで見学者に人魚の説明をした。毎日300から400人が、科学上の驚異を見ようと押しかけた。1822年の秋のロンドンは「人魚」の話題で持ちきりであった。
船主のスティーヴン・エレリィは人魚公開会場を訪れ、イーデスに賠償するように叱責したが、イーデスは金を返さず、エレリィが訴訟に持ち込めば、人魚と共に国外へ逃亡するとまで言った。勿論、人魚公開による利益も分け与えなかった。
エレリイの弁護士は、大法官エルドン卿にイーデスの不当を述べ、イーデスが人魚を移動することも、売ることもできないように訴えた。そのため、大法官の許可無く、人魚は処分できなくなった。
イーデスは、エヴェラード・ホームが人魚は本物だと認めたと、各種新聞、広告に発表してしまった。怒ったホームはクリフトにモーニング・ヘラルド紙などに人魚非難記事を発表させた。
J.マレーも、ジェントルマンズ・マガジンに人魚とイーデスを非難する記事を載せ、人魚が本物だと言っていた知識人を嘲笑した。マレーは人魚をテナガザルとガンジス川産のサケ科近似の魚との結合物と考えた。旅行経験が豊富なマレーの友人モリソン博士も、東洋人は人魚作りが巧みで、ヨーロッパ人を騙すことがあると披露した。
人魚パンフレット「サイレンまたはマーメードと呼ばれる海の動物が実在することに関する歴史的研究論文」が出版されるが、人魚人気は凋落する。
大法官を揶揄する戯画(エルドン卿がイーデスの人魚をあやしている図)をクルックシャンクが描くが公表には至らなかった。同時期に、ストランド街で、別の人魚と「賢い」学者ブタの見世物があった。
ターフ・コーヒーハウスでの人魚公開は寂しく終了する。以後、人魚は翌1824年、あるいは25年まで、地方回りをすることとなった。
エドワード・ドノヴァンが「ナチュラリスト・リポジトリィ」誌に、実見した人魚の報告を掲載した。ドノヴァンは、人魚と言われるものは、サケとオランウータンの合体物で、マラッカ諸島の現地民が、ヴィジュヌ神の変身に似たものとして崇拝の対象としていたものが、オランダ人によってバタビアに運ばれたと推測している。
この間、イーデスの人魚、その他の人魚の情報は散見するが、確証はない。
イーデス船長は、使い込んだピカリング号の売却代金を返済するようにとの判決をうけ、船乗り生活に戻った。イーデスは1840年代初頭に亡くなり、人魚は息子の手に渡る。ボストン博物館モーゼズ・キンボール(1809〜1895)が人魚購入を申し入れ、手に入れた。キンボールは、「1817年に、ボストンの船長がカルカッタ寄港中に、日本の船員から6000ドルで人魚を購入し、部下に船を任せ、自分はロンドンへ向かった」と聞いていた。
ジョージ・ジョンンストンが「自然誌年鑑」に、以前観察したオランダにある日本産と伝えられていた人魚の報告を行い、作り物と断定している。
ヘブリディーズ諸島のベンベキューラで、小型人魚が少年の投げた小石にあたり死亡、埋葬された。
収益金の分配をめぐって裁判沙汰になった。
モーゼズ・キンボール、友人の興行師フィニアス・テイラー・バーナム(1810〜1891)に、人魚による一儲けを相談した。バーナムはキンボールから1週間当たり12ドル50セントで人魚を借り受け、人魚のプロモート計画を練った。バーナムはロンドンの自然史講堂のグリフィン博士がフィジー諸島沖で捕獲され、中国にあった人魚を携えてアメリカにやって来るという話を作り上げ、複数の新聞社に伝えた。バーナムの助手で弁護士でもあるレヴィ・ライマンが「グリフィン博士」としてフィラデルフィアのホテルに投宿し、少人数に「フィジー人魚」を披露し、その後ニューヨークへ出発した。フィラデルフィアの新聞が人魚のことを伝えたので、ニューヨークでは記者たちがグリフィン博士の到着を待ちかまえていた。バーナムは3つの新聞社に人魚図(魅力的な女性人魚)の掲載を、それぞれ独占的取材と言って掲載させた(7月17日)。グリフィン博士は人魚を公開することを拒んでいたが、ついに1週間という期限付きで、ブロードウェイのコンサート・ホールで博士の講演付きで披露することとなった。髪を梳かす3人の美女人魚を描いた宣伝幕が掲げられたという。期日は、8月8日(月)から13日(土)か。バーナムはパンフレットを1万枚配り、「人と魚のミッシング・リンク」である人魚をあおり立てた(アザラシと鴨をつなぐカモノハシ、鳥と魚はトビウオ、爬虫類と魚の中間点はパドル・テイル・スネイクなどとうたい、入場料は25セントであった)。バーナム編集の冊子「人魚小史」はイーデス船長が出したものの剽窃であった。
1週間の盛況後には、バーナムは自分のアメリカン・ミュージアムに人魚を移した。ラライバルのベネッツ・ミュージアムでは急遽、ニュー・ヨークの剥製師に人魚を作らせ、展示した。利益配分の不満から、グリフィン博士ことライマンはバーナムから離れた。
ニュー・ヨークでの人気が下火になったので、バーナムは南部の諸州で人魚を巡回させることとした。ライマンに代わって、バーナムのおじ、アランソン・テイラーが説明役を努めた。1月、サウス・カロライナ州チャールストンでは人魚擁護(チャールストン・キューリアー紙)、非難(チャールストン・マーキュリー紙)の2新聞が中傷合戦を始め、人魚の破壊を危惧したバーナムは急いでフィジー人魚をニュー・ヨークに戻した。
数年間アメリカン・ミュージアムで展示されたフィジー人魚は、その後キンボールのボストン博物館へ戻された。
ウィリアム・マクギガン(フィラデルフィアの剥製師、一時ピールのフィラデルフィア博物館の館長となる)がフィージー人魚のライヴァルを作製する。日本産と宣伝した。
ロンドン、スピタルフィールズ、ヴァインコートのホワイト・ハートというパーラーで、人魚が公開された。フランシス・T・バックランドがオーウェンの依頼で観察した。バックランドは最初から人魚の実在を否定していたが、その報告によると、長さは3〜4フィート、上半身はサル、下半身はタラ科の魚のようだったという。バックランドはリーゼント・ストリートでも25インチの人魚を見ている。
噂によると、ロンドンの鳥剥製師が数年前にマーマン、マーメイドのペアを作製し、ホワイト・ハートのものはマーマン、バーカーフォート・マーケットの骨董屋にはマーメイドを置いていたという。
バーナムは人魚を携えてロンドンへ渡り、講演を行い、盛況を収めた。6月、人魚は再び、キンボールの元に戻され、長い間展示された。
バーナム、水族館をニュー・ヨークに開設。
バーナムのアメリカン・ミュージアムが焼失した。
カミング船長が、横浜から英国へ人魚をもたらした。
ベルギーのオステンドで、乾燥人魚公開される。
バーナムは、人魚巡回を再開したが、今回のフィジー人魚は新しく日本から取り寄せたものであった。この頃、キンボールの博物館は火災に見舞われたが、人魚は救出されたと伝えられている。
ニュー・オーリンズで人魚公開(アスピンウォール湾で捕獲)。
英国のブライトン水族館で「生きた」人魚公開。
バーナム死去による競売で、ニュー・ヨークの建築家スタンフォード・ホワイトが「フィジー人魚」を落札した。ホワイトの死後、1906年、聖ボナヴェントゥラ大学(ニュー・ヨーク州、カトリック・フランシスコ派の私立大学)に寄贈された。
キンボールの息子の相続人から、人魚はハーヴァード大学ピーボディ博物館へ寄贈された。現在残っているピーボディの人魚は、バーナム/キンボールの「フィジー人魚」とは異なった形をしている(本来のフィジー人魚は手がムンクの「叫び」にような形になっているが、ジャバ、ジャパニーズ人魚と呼ばれるものはスフィンクス型の前に突き出した手をしている)。
ブルムズベリーで、西アフリカ産乾燥人魚(16インチ)が公開された。
イーデスのフィジー人魚が日本製かインドネシア製か、あるいはその他の地の作であるか、決定できる資料はないと思われる。また、バーナムのフィジー人魚が一つの人魚を指すのではなく複数のものが存在した可能性もあり、大学や博物館に現在残っている人魚資料も決め手に欠くと言った方がよいだろう。バーナム以降、多くのショーマンが、それぞれに「フィジー人魚」を公開し、見世物に欠かせない展示物となった。いかがわしさと歴史を背景に持つフィジー人魚は、サイドショーへの郷愁、リスペクトを伴って、新しいアーチストによって製作され続けている。
その一人に、ブルックリン在住の山田武司氏(1960〜)がいる。2006年10月2日から2007年12月31日まで、遊園地とサイドショーで有名なコニーアイランドにある公立図書館で「山田武司の世界の驚異博物館:コニーアイランド・サーカス・サイドショー」と題した個展(作品数500)を開いている。ブクックリン公立図書館コニーアイランド分館の番地は、その名もマーメイド・アヴェニュー1901番地である。山田は大阪出身で、23歳で渡米留学、芸術活動を行いながら西海岸からニューヨーク、ブルックリンへやって来た。山田のフィジー人魚は4フィートのものと6フィートのものがあるが、顔の表情は女性的で、直線的で魚尾の部分が長く、腕、上半身部分も鱗に覆われている。ミイラ風ではあるが、写実的な女性人魚を思わせる作で、フィジー人魚にまとわりついた、いかがわしさや滑稽さを払拭した、江本創(1970〜)の作る精妙な幻獣たちと似た作品となっている。山田の作るサーフ・マーマンは江本の魚人(『幻獣標本博物記』、パロル舎、2004.2.4、p.57)と極めて似ている。江本は作品の素材を「紙、モデリングペースト、竹籤」などと言っている。山田の作にはフェイクの古典的作を再現した毛鱒、チュパカブラ、乾し首といった立体の他に、一連の幻獣、実在の奇妙な生物らの「コニーアイランド印」珍奇缶詰のラベル(角ウサギ、人魚の爪、巨大タランチュラなど76種。話題のクマムシは英名water bearそのままに8本足のクロクマを描いている。)や、独創的なカブトカニの甲羅にペイントした作品群がある。山田はカブトガニの楯をもって、コニーアイランドの夏の恒例行事マーメイド・パレードにも参加した。
マーメイド・パレードは1983年に始められた行事で、間もなく25周年の紀念すべき年を迎える。毎年、夏至後の最初の土曜日(6月の第4土曜日)にコニーアイランドで行われ、参加者が人魚に扮して楽しむものである。コニーアイランドは海岸行楽地として19世紀初頭からホテルが建設され始め、世紀末の火災によって歓楽街が焼失すると、ニュー・ヨークの労働者家族の娯楽地として巨大遊園地が出現した。1895年のシー・ライオン・パークは1903年にルナ・パークとなり、1897年開園のスティープルチェイス・パーク、1904年のドリームランド・パークといった3大遊園地があった。ローラー・コースターや観覧車といった古典的な遊園地の原形が出来上がった。1920年には地下鉄が開通している。コニーアイランドはたびたび火災に見舞われ、開園時には最先端の乗り物や出し物も古びて行き、主要プロムナードであるバワリー通りに並んだ見世物、フリークショーが名物となった。そのノスタルジアを芸術にしたのが山田の作品群である。山田の人魚への思い入れは深く、フィジー人魚の他に人魚を主題としたタブロー作品もあり、人魚の歴史のエッセイもネット上に掲げている。その山田がフィジー人魚製作の先駆者として尊敬しているのがマーク・フリアソン、ホーマー・テイト、ドゥーグ・ヒグリィである。
マーク・フリアソンは1964年、フロリダ州生まれのサイドショー(見世物)のバナー(垂れ幕)、ギャフ(ネタ、展示物)作者である。バナーの作者は現在全米で3人となったが、フリアソンはその最年少である。海中を泳ぐフィジー人魚のバナーも描いているし、ニュー・オーリンズのヴードゥー・ミュージアムにあるフィジー人魚(ラバー製)も製作した。ニュー・オーリンズの人魚は水掻きのある両手をもち、髪が長く、首を正面に向けているスフィンクス型のものである。それとは別の、顔が小猿で、尾を右に曲げた、イーデス船長の人魚に似た作品も作っている。ロブ・ゾンビー監督「マーダー・ライド・ショー」(House of 1000 Corpses)で、フリアソンの作品を見ることができる(フィジー人魚はアクアリーナという名)。
ホーマー・テイトは1884年に生まれ、1975年に亡くなっている。その活躍期は1940〜50年代であった。そのフィジー人魚、フィッシュ・ガールは粘土で作ったような感じ(素材は新聞紙、トイレットペーパー、膠、砂漠に落ちている動物の骨などという)で、長い赤髪をしているスフィンクス型のもので、一見稚拙にも見える。テートの製作品には、ワニ少年、悪魔の子供、双頭のミイラ、乾し首などがある。
ドゥーグ・ヒグリーは1950年代にニューヨークで子供時代を過ごし、タイムズ・スクェアーのダイム・ミュージアムやコニーアイランドのサイドショーを見て過ごした。その作品は人魚の他、アトミック・フィッシュ、エリー湖のワォーター・ドッグなどがあり、素材は布を使うのが好きだと言っているが、ポリマー粘土と水彩絵の具も用いている。ヒグリーの人魚はかなり奇怪な表情をしている。一時期、タホ湖近くに「真の驚異、昔ながらの博物館」を開設していた。そこには自身の作品や、テイト、フリアソンの作品もあった。現在はギャフは製作していないと言うが、作品同様、複雑な性格のヒグリーはギャフ、サイドショーの歴史の研究者でもある。
フィジー人魚の製作者にはその他サリーナ・ブルーワー、ファン・カバナ、ケヴィン・T・ジェローンなどがいる。サリーナ・ブルーワーはミネアポリス美術大学で学び、現在は剥製師免許も取得した女性作者である。その作品は動物遺体も使っているようで、極めて精妙なものである。フィジー人魚は12インチから24インチまでの大きさで、600ドルから1400ドルのもの(横型)と、バーナムのフィジー人魚(縦型)、800〜1000ドルのものがある。双頭のヒヨコ・ネズミ、ジェニーハニヴァー、ユニコーン、グリフィン、チュパカブラなどの作品がある。ファン・カバナは掌サイズから等身大(6フィート)まで様々な人魚を作っている。6フィートで6000ドルと、最も高価なフィジー人魚である。カバナのサイトには30センチほどの日本製アンティーク小型人魚が掲げられている。マサチューセッツ州出身のフランクリン・ブレイク(1837〜1871)の遺品で、江戸湾の北東海域で漁師捕獲され、保存状態にされたものと伝えられている。ブレイクは最初、横浜に居住したが、最終的には神戸に落ち着いた。
フィジー人魚に触発された芸術作品を作るアーチストも他にいるが、フィジー人魚を持ってサイドショーを現在も主催しているショーマンも当然いる。その一人に、ドクター・ウィルソンがいる。バナーはボッティチェリ「ヴィーナス誕生」の下半身を魚尾にしたものである。人魚の謂われとして、ロバート・モズレィがバーナムの遺品を含む多くのサーカス、サイドショー関連の品を手に入れ、フロリダ州サラソータに博物館を開いた。博物館は1957年に閉館したが、その遺品は息子のジョンに残らず受け継がれた。そのジョンも2002年に死亡し、噂を聞いたドクター・ウィルソンが駆けつけ、フィラデルフィア博物館と書かれた箱を開けると件の人魚があったというわけである。メディシン・ショーの口上なので、どこまでが真実か分からないが、その人魚を譲り受けて、一座は興行を行っている。「ウィルソンとダークの巡回驚異のカーニヴァル劇場」という名の一座である。
キンボールやバーナムの博物館はダイム・ミュージアムと呼ばれ、見世物兼科学知識とエンターテイメントを同時に楽しめる施設であった。ボストン、トレモント通りにあったキンボールのボストン博物館は50万の展示品を誇り、蝋人形による歴史情景、事件の再現、動物剥製(ゾウ、オランウータン、ノコギリザメなど)、エジプトのミイラにフィジー人魚、毎夜のミンストレル・ショーや喜劇芝居など盛りだくさんの内容で、入場料25セントであった。ヒグリーのタホ湖畔の施設もそのダイム・ミュージアムの再現であったが、その名も「アメリカン・ダイム・ミュージアム」という博物館が1999年から2003年秋まで、4年間ボルチモアにあった。サイドショーの研究家・収集家で、研究誌「驚異と娯楽」を主催しているジェームズ・テイラー(同名のシンガー・ソングライターとは違う人物)が共同所有者であった(テイラーは、2006年7月、ワシントンD. C. にショーバーと収集品を集めた「驚異の宮殿」を開いた)。ダイム・ミュージアムはスミソニアンの本格的科学博物館に代わられる存在だが、科学としての生物学が確立された現在でも、クリプトゾゥオロジー(神秘動物学)が存続できるように、郷愁といかがわしさ、そしてアートの中に存在の場を見つけている。山田武司の個展もそうであるが、ビッグ・フットの研究家ローレン・コールマンはメイン州ポートランドで「インターナショナル・クリプトゾゥオロジー・ミュージアム=国際神秘動物博物館」を2003年8月に開設した。8フィートのビッグフットのモデル、雪男イェティの足跡、角ウサギ、フィジー人魚、モスマンなどを見ることができる。
今回はナレル・オリヴァーの人魚絵本からフィジー人魚について論を進めたが、人魚ミイラについて常識と思われていたことは確定された事実ではないことに気付かされた。サルと魚という生物を素材にしていると説明されてきたが、上半身は細工物である場合もあった。また、イーデスの人魚が日本製であった確たる証拠もないようだ。イーデスに人魚を売りつけたオランダ人は「日本の漁師から買い取った」と言ったようだが、人魚を本物らしく装う話とも受け取れる。ジャワや周辺の地域の製作物である可能性もあると思える。ジャワには海の女神「ニヤイ・ロロ・キドゥル」の伝承やヒンドゥー文化の影響もあり、人魚を製作する土壌はあった。また、当時の博物学が「生物の連鎖」を想定して人魚の存在を肯定的にとらえていたとする物語も検証を要する。少なくとも、多くの専門家は、目の前の乾物を拵え物と見抜くことは簡単であった。今日の神秘動物学的傾向を指向する博物愛好家もいたが、むしろショーマンの宣伝自体がミッシングリンクの物語を利用し増幅させたと思える。カモノハシのような新種は驚きを持って迎えられたが、人魚の存在の可能性を直ちに実際の乾物に置き換えることはできない。珍奇なものを歓迎する人間の心性をフィジー人魚は突いたのである。飽きやすさ、下等なものを敢えて喜ぶ気紛れさもまた人間の心である。現在の興行師、アーチストが作り続けるフィジー人魚の物語は、実際の検証された歴史ではなく、もう一つの物語としての歴史に大きく依存している。ダイム・ミュージアムでなく、現在の学術的博物館は、フェイクの歴史、フェイクの保存の観点からフィジー人魚を時に取り上げるが、歴史と物語の交差を点でなく線にすることは始まったばかりである。また、学問とは別に石黒達昌(1961〜)がハネネズミ、エンジェルマウス、カミラ蜂を記述したようなやり方で人魚の物語を書いてくれる人の出現も期待している。
by高安太陽(aka.MORO)