�����l�`��y�����������Ȗ��M

INDEX��32P
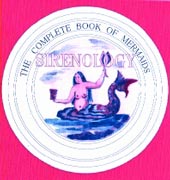
�@��苐�l���s�Ղ̗��蕨�����f���Ƃ����l���ߋ���u��������效�v�Ɏ��߂Ă��邱�Ƃ͕ςł���B���N���J���ꂽ���{�����V���}��
�فu�l�������Ƀf�[�^�x�[�X�v�ł͎O�̎l���s�Րl���A�l�����A�����l���A�����l����A���q�l���A�V�������q�N���l�����ʐF�t���Ō��邱�Ƃ��ł���B
�@�l���s�Ղɂ��ẮA�������̒���w�s�s��̖����w�|�l���s�Ղ̗��j�Ɩ����x(��c���@�A2006.6)���o�ł��ꂽ�B�{�̂̔w�\���ɂ͐l���̗��蕨�A�\���E���\���ɂ͌~�D�A���s�����A�x�m�̊���A�R�ԂȂǂ��`����Ă���B�����̎l���s�Ղ̐l�C�o�����A������R�ԁA�~�D�s���ɂ͂܂Ƃ܂����_�l�����߂��Ă��邪�A�l���ƁA������Ƃ�܂����s�����̗��蕨�Ɋւ��Ă͗]��G����Ă��Ȃ��̂��c�O�ł���B���s�����́A�u�ɐ��l���s�z�K���_����X�t���v�Ƃ����G�掑��(���q�{�̐���N��Ɋւ������́u�]�ˎ���Ŗ�������قږ��������̐���ƍl���Ă悳�����ł���vp.72�Əq�ׂĂ���)�ɕ`����Ă��āA��O�܂Ŗk�̏o�����ł������B�l���s�Ղ́u���É��^�R�ԁv(���É��𒆐S�ɂ������C�n���Ɍ�����A���炭��l�`�t���̎R��)�̓o��ŏo�������ω��������A�u�������v�́u�x�m�̊���v�A�~�D�A������ƂƂ��ɕω����Ȃ��������蕨�ɕ��ނł���B�u�������v�ɂ��ē����́u�l�`�⋛�̍�蕨�ɐl�������āA���[�����X�ɓ����Ȃ�������Ă����Ƃ������Z�ł������v(p.105)�Əq�ׂĂ���B�����́u�l�`�v���u�l���v�Ɠǂݑւ��Ă��A�����ԈႦ�ł͂Ȃ����낤�B���q�{������Ɓu�k�����v���������Ŕ̌�ɉ͓A��A���A�I�A�ɐ��ڂȂǂ̋���̔�蕨����l���S����12�̗��蕨���m�F�ł���B���̒����ɂ́A�l�Ԃ̊�����Ď��O�ɑg��ł���u�l���v�Ǝv���镨���`����Ă���B�I�ƈɐ��ڂ̌�ɂ́u���m���v�̑�����R��(�u�S����v���������m�F�ł���)���T���Ă���B���݂̎l���s�Ղł͑�����R�Ԃ́u���[����������ۑ���v�ɂ���ĊǗ��^�c����Ă���B
�@�G�掑���Ō������A�l���͘r��O�ɑg��ł��邪�A��ȉ��͋��̂ł���B���a�ɂȂ��Ă���̐l���R�Ԃ͋��������l�ԂŁA���̂͑̂̔����Ƃ������m�^�l���ɂȂ��Ă���B�����Ƃ��A�g��Ɣw�h�̑O�ɂ͕�삪����A����������Ƃł������ׂ������I�ŁA�]�ˎ���̐l���̎���c���Ă���B���`���Ă���̂́A�l���s�̖��ÏāA���䓩�y��̋����̗��Ɂu�l���s�܂�l���v�Ə����ꂽ����(�͔����F�ŁA�ꕔ�����͋��F)�A���N�F�Ƌ��ōʐF���ꂽ�A���������y��̓y��u�l����v�A�y��Ɠ����F���̓��y��u�������v�ł���B�\��͋���ł͂��ꂼ��ʎ��I�ňقȂ������̂ƂȂ��Ă��邪�A���ۂ̕��͑f�p�ȕ\�������Ȃ��B����͊G�ɂ��ꂼ������̐��@�������L���Ă���B�������̊G�ɂ́A�u���a�\��N�V���v�Ɗ������t������Ă���B
�@��苐��̌l���u�l���v�ɂ��āA�ȑO�͖����ŕ��ł��Ȃ������B�����ŁA���̖ڎ����Љ�Ă������B
�@�����͂P�`�U���܂ł��u�l���v�A�V�����u�ɂ�v�ł���B��P���̍ŏ��̋L���u�ɂ�v�͑n���̎��Ƃ���������̂ł���B
���܂���ɐl���Ɖ]�ӂ���Ȕ����趎��̗l�Ȃ��̂�n�ւČ��܂������@�͐l���Ɖ]�ӎ��������̏N�߂ċ���܂��l�`�ƑP�����ċ���܂��̂ŁA���ď��g�������̖{�̏����ɂ���Ȏ��������ꂽ�l�ɋL�����ċ���܂��A�����ׂĐl���̙B���Ȃǂ��������������ɂ͓��ꍟ�S���̏\�Z�ł��Ă�������Ȃ����ɂȂ�܂��A(����)
���܂���ɏo�҂�趎��̎��ł����獡�㖈���o�����u���ɂȂ��疔���N�Ɉ�x�A��N�Ɉ�x�A���͑n���j�̏I���j�ɂȂ��瑴粂�笕����ڒ��ɂ�ę҂�܂��A���̂�l�`��̃v���p�K���_�Ƃ��ĊF�l�ɏE�Ē����l�ւł������܂��B����ş��܂���Ɉ�s�ł���椂݂��������܂���Ύ��̎�ӂ��ʂ�桂ł������܂��B
�@�n�����͂��̌��t�ʂ�ߋ�E�l�`�����ɏI�n���Ă���B�Q���ɂȂ�ƁA�u�l����萂�������́T�N�W�v�Ƒ肵�A�l���Ɋ֘A�������̂��L���W�߂邱�Ƃɂ����Ƃ̐錾������B�O�c���}��(�ё��A1876�`1960)�ɐl���̊G�𐿂�����A�F�l����l���̐�����������肵�āA�u������ǁX�Ɗe��̂��̂��N�߂��邾���N�߂Č������ł������܂��v�ƌ����Ă���B���}������́A�������̐l���A������l���̃~�C���������āA�u��������l�����̖{���Ƃ��Ēp��������ʒ��i�A�����w���t�ɗ���ŏɎq�������A�H��d��~�����Ĕ[�߂܂����v�Ƃ��L���Ă���B���̎��̍�u�[���������ɐl���̉�����Ƃ炵����v�B�R������́u�l��趘b�v�Ƃ��Đl���Ɋւ��鎑�����Љ�āA�U���܂ő������B�V���͎������u�ɂ�v�ƕς��A�u����́A�l�`��ߋ��萂������������Ə����Ēu�������Ǝv�Ђ܂��v�ƌ�L�ɏ����Ă���B�l���֘A�̎��́u�s���ɂ��ʂ̍��q�ɂ��Ēu�������Ǝv�Ђ܂��v�Ƃ����邪�A��p���Ɋւ��Ă͉���m�邱�Ƃ͂Ȃ��B������肩�A�W���ȍ~�u�ɂ�v�����������ǂ�����������Ȃ��B�Ȃ��A�u�l���v�̔��s�����͑�T���́u�R���S铁v�Ƃ����L������T�S���Ǝv����B�i�ŁA���m�F�Ɉ��A����ɔz�z���Ă����悤�ł���B�K�v�Ƃ���҂ɂ͊��ŕ����Ă������A�u���Ȃǂ����⍇���̕�������܂����A����ȕ��ɂ͂��Ԏ������グ�܂���v�Ƃ������Ă���B
�@�u�l��趘b�v�����Ă݂悤�B��R���ł́A�u㉖{��܂Ɣ䎖�v���̔�����u�������l����ߊl���đł������l�v�́u�ސl���v(���̋L���́u�Í������W�v������������)�A�u�ዷ��̔��S��u��v(���g����ɉ��N���Ɣ��S��u������e�̑��t���˗�����)�A���V���Q�ԗx��̐l���ߏ�(�吳12�N�t)��`���Ă���B
�@��S���͖ؔōʐF���u�z��̐l���v(�u���症铂̒j�q����ɛ���̂₤�Ȃ��̂������A���_�ɏ悶�ĊC���Y�����v)�A�i�n�]���u���V��杁v(�u���V���L�v)�A�u�������X�쌱�L�v(���{��O�Y�쐶�l�`��㉖{�u�O�\��ԁ@�ߍ]�ω����@�l���v)�A�u�������l�k�v�A�u���ٌÍ����k�v�A�u�l���̔��v(�R���ŋ��`�����Q�ԗx��̋����̎��������ꂽ)�A�u�l���̍��v�A�u�R�����̐l���v�A�����l�`�u�����v����Ă���B�u���ٌÍ����k�v�͎ʖ{�ŁA���̓��e�͂����ł���B�ԂɊ|�������l�����C�ɋA�������A�m�̐��@�ɂ��ƁA���i�̍����q��艜�B�ɗ����ꂽ�⏼�^�̎�N���d�E����A���̎���߂����ꂪ�C�ɐg�𓊂��l���ɕϐ��������̂��Ƃ����B�l���̏o���͋g���ŁA���̔N�͋ߔN�ɂȂ��務�ɕl�͓�������B�u�l���̍��v�͓�m�Y�̊C�b�̘]���ŁA��ނƂ��ċ���������́B�����炭�W���S���̍��ł��낤�B�u�R�����̐l���v�͉u�a���s���ɓĎu�Ƃ��ōs�����ꖇ���A�u���ӂ蘪�����鏗�������O�ɏo���A�����͋�铂ɂĔ��̐悫�ɎO�{�̙��Ƌ��Ɉ�{�̙��Ƃ���A����ٗl�̎p�Ȃ�v�Əq�ׂĂ���B�_�ЕP�ł��낤�B�S���ł͑��̏ꏊ�ɕ����l�`�ƈƔn�̓y�Ă̐l���ɂ��Ă����Ă���B�����l�`�́A�u�傳�͉��������A�����l���v�u���ɂ͒Z������{�̊p�Ƌ��ɂ͋��F�̛��삪�O�����̎肪�����ĕh�ɂȂĂ�܂��A�����O�c�҂ɂȂĂ�ċ����̔@���A��͐F�����Ղ�̐�����l�ɏo�҂ł�܂��A�̕����͔��n�F��A���l�F�ɒ��F���ċ������ӂĂ���܂��v�Ɛ������Ă���B
�@��T���ł́A�\���́w��̙B���x(�吳�Q�N�U���A�����X)����z��́u�l���ˁv�̈����A�u�b�q��b�v�A�u��a�{���v�A�u�R�C���Y�����v�̐l���֘A���������Ă���B��U���́u�Í���k�Ђ������v�A�u�������M�v�Ȃǂ��甪�S��u��֘A�L���A�u���捜���G���v�̒|���v��̋L�����p���s���Ă���B
�@�N�W�̎�͊ߋ�ŁA�l���͕��Y���ł��邪�A�m�F�Ɂu�l�`�A��㉁A�|�X�^�[�A���c�e���A�����A�G�t���A�ӕ[�A���ЁA�O��趎��A��`�v���̉������˗����Ă���B�i�̂���������́u�l�����v�Ƒ肵�ăX�N���b�v�ɂ��A�u�l���̓W����ɂ͏N�W�̐l���Ɛl�������Y�����c�ƓW�J���čD���ƂɌ��Ē�������v�Ɨ\�����Ă���(�R���Ap.33)�B�܂��A�吳����̐l������Ƃ��āA�u�ߔN�l���Ƃ������̂����ɑ�������Ę҂܂����A���ꂪ���̏N�߂Ă��ɔ��ɕ֗����o�ւĂ���܂��A�����s�͎��Ƃ��Ă͓s���悭�ȂĘ҂������Ɵc��ŋ���܂��v�Əq�ׂĂ��āA�R�����j�́u���X�Ɛl���F�吳�̃V���{���v�𗠕t����،��ƂȂ��Ă���B
�@����́u�l���v����Ŏ����̊��s���̐�`���s���Ă���̂ŁA��������Ƌ��ɂo�q���Ƃ��Ă̑��ʂ��������B�w���M�@�������┠�x(�y���ߋ�����Ƃ�����S�}�̖ؔʼn�A��A�l�c�،^��㉁A�Еz�`���A�吳13�N)�A�w��������㉏W�x(��c��c㉁A�����T���Ɖ���A�P�`20�W�A�吳�W�N����)�A�u���y�̌��v(�吳15�N�W���`���a�R�N�T���A�S20�W�A�e�W�͖ؔ�10�����10���ڎ��P���A���ܓ���)�Ȃǂ���`����Ă���B�u�l���v�͌l���ł��邩��A�]��A�{�q�̗v���A�X�^�[���Ƃ����b�ȂNj��g�̏����Ȃǂ��L����Ă���B
�@����͊ߋ�ʼn�W��u�l���v�̊O�ɁA���̒�����s���ɂ���e���ċ��y�ߋ�A�������ۂȂǂ���Ă���B�{�R�j��(1888�`1974)�́u�y�̗�v�ɂ́u�ےÏZ�g�̂�������v(��P�S�A�吳�X�N�U��15��)�A�u�䕍�ߎq��S�v(��X�S�A�吳10�N10���P��)�u�j�R�̎���^�_���̂�����Ձv(��Q�S�A�吳�X�N�W���P��)�A�u���̎������v(��T�S�A�吳10�N�Q���P��)�A�u�O��̃l�U���o�v(��W�S�A�吳10�N�W���P��)�A�u���̓��w�v(��10�S�A�吳10�N12���P��)�A�u���݂���̉œ���v(��11�S�A�吳11�N�Q���P��)�A�u���s���n����㉔n�^��㏫�R�n����㉔n�^��㐣�˕��̑��蕨�ƒn���Ձv(��12�S�A�吳11�N�S���P��)�A�u���n���~�̗x��v(��13�S�A�吳11�N�U���P��)�A�u�Օ��w��v(��15�S�A�吳11�N10���P��)�A�u�Z�g�u�ӂƂ܂���v�v(��17�S�A�吳12�N�Q���P��)�A�u��̂Ђ邠���̂�v(��18�S�A�吳12�N�S���P��)�A�u�����̂��߁^��エ�ł����̂��߁v(��19�S�A�吳12�N�U���P��)�̋����e��������B��Q�S�A��T�S�ɂ͋���M�̑}�G�����߂��Ă���B
�@�{�R�j��͑���c��w���A�u�y�̗�v���s���͒��菤�Ɖ�c���Ζ��ł������B�u�y�̗�v�͉�����̎G��(�ŏ�����50�K�A��13�S����P�J�N10�~)�ŁA���������s(����͕S�����炸)�A����F��(1867�`1941)�A���X�؊�P(1886�`1933)�̓��e������B�j��͑吳12�N�ɏ㋞�A���a�R�N�Q������͎G���u���������v���E�łŊ��s����(�u�]�āu�y�̗�v�̔��Ɏ������Ēu���������Ȏ�́A����Q���������ēy�n���삦���n������ɑ����Ȃ�܂����B�����Ŏ��͍��̋@���Ɍ��ԁu���������v���Ɂu���������p���v�̓��ڎ����̎苖���犧�s���邱�Ƃɂ����̂ł���܂��v�|�u�����������s�̌��t�v[�u���������v���S]���)�B�u���������v�͉���݂̂̔z�z�ŁA�l�Z��50�ŁA���ꃖ��25�K�ł������B�A���u���������p���v(����������25�K)�ƕ������킹�z�{�ł������B�j��ɂ��Ă͏���݂��q�u�{�R�j��|���̐��U�Ə����v(�u�s���s����j�����ٔN��v��15���A1998.3.20)���ڂ����B
�@�E�ł̎G���ŋ���e���Ă�����̂ɉ���ԏ�(�ƏG)�u�c�Ɂv������B�n���͏��a�X�N�P��10���B�Z�g�y��������(���s�Z�g���R�����l���ڎO�܁@����ƏG��)�����s���ƂȂ��Ă���B�n�����̕ҏS��L�ɂ́u�{���͏����̓��y�{�ł���������g�D�ɂ����������D�̊F�l�ɂ��̂�����ړI�Ő��܂ꂽ�̂ł��v�u�{���͔N����ᢍs�̗\��ŕS�������x�Ƃ��܂��v(��12���̉��t�ɂ́u���\������Łv�Ƃ���)�Ƃ���B�uᢍs�̂��Ƃv�͎��̒ʂ�ł���B
�@�ŋߋ��y�M�̗����ɂ�ċ��y�W�̊��s�����������ĎQ��܂����B���y�����݂ɏЉ��Ƃ��ӎ��͐��Ɋ��������ł��B�B�����q�K�������������Љ�łэs����Ƃ�����X���Ŏ炵���͂��Ƃ��鋽�y�ߋ�����삷�邱�ƂȂǂ��c�R�s�Ȃ͂�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B���Ӗ��ɉ��Ď��Ȑ�{��˂����Ȃ݂��G�z�ɂ����������F�l�̑O�ɂ����肵�܂��B���e�̓_�ɂ����Ă͑S������̎���ł��B���{����������N�����y����ᢘI����n��Ȃ鎑�������ď����A�˂���w�͂Ă����U����Ύ��̉ߏd�̌��Ăł��B��������ਂɌ�ᔻ�A�䏕�͂����͂���B
�@�n����(�S44��)�͉����l�Ŏ��M�������A�Q���ȍ~��e���ڂ���悤�ɂȂ����B��R��(���a�X�N�R��15��)�͐�苐��u��̓y�l�`�v����n�܂��Ă���S78�ł́u�����j�v�ł���B����́u�y��̗��s�v(��U���A���a�X�N�V���P��)�A�u�p��ߋ�v(��W���A���a�X�N�X��20��)�A�u�����̂����āv�u�\���̐����v(��11�j�u���H���N�I�O�j�v�A���a10�N�R��15��) ����e���Ă���B��11���́A����̖ؔłŕ\�����u�R��l�`�̒��v�A���G�́u�N��菬�@�t�v�ł���A�����̕��͂��V�c�l�Y��u�o�b�N���[���m�ƃX�^�[�����m�����Ӂv�ł���B�u�c�Ɂv�̊�e�҂ɂ͋���A�V�c(1899�`1971)�̊O�ɒ��s���O(1887�`1942)�A�{���c��(�݂�Ȃ��@�܂�����A1893�`1964)�A���R���Y(1876�`1947)�A�G��原�Y(1884�`1964)�A���c�\�Y(1881�`1952)�Ȃǂ�����B�u�c�Ɂv�͂��܂ő������̂ł��낤�B�q�c��(1916�`)�́w���{��������n�@��S���@�ߋE�x(�p�쏑�X�A1975.5.20)�̉���Łu�Z�g�y��������̉���ƏG���u���Ȃ��v���n�������̂���N�ꌎ�ŁA���̎G���͗��N�܂ł������ď\����������Ă��邪�A���W�́w�ĎR�q�l�x�ɂ͒��w���������M�҂��̖K�L�^�𑗂����v���o������v(p.478)�Əq�ׂĂ���B�u�c�Ɂv��S�������Ɂu�u�ĎR�q�v��萂��錴�e��W�v(�u�f�ڂ̕��ɂ͔��Ӓ��v�Ƃ���)���ڂ�A��T���̕ҏS��L�ɂ́u�ĎR�q�̌��e�͌���ŁA���c����B�����ύX���ĒP�s�{�Ƃ��ēZ�܂����̂��o���ς�ł���B��������̕i�́A�S�\�ԏo�łŁA����ڍׂ͒ǂ�ᢕ\����v�Ƃ���B��10����L�ł́u�ĎR�q�j�͐F�X�̎x��ɂ�薾�N�ɏo���܂��B���e�͈�����ɉ�ċ���܂����A�ߓ��̕����Ђ�ਂɐ��������őS���F�l�ɂ͐\桂��Ȃ��A�ȊO�̉����A�������b����P����Ђ܂��v�Əq�ׂĂ���B�u�ĎR�q�l�v�͉���ҏS�A�Z�g�y�������s�̍E��150���Ƃ��āA���a10�N�R���ɔ��s���ꂽ�B
�@����̊�e��͂��̑��u����v(������y������^�n���Д��s)�A�u�ϑԐS���v(���{���_��w��)�A�u���ƙB���v(�O����)�Ȃǂ�����B���̓��u���ƙB���v�ł͏��a�X�N�Ɂu�l�������M�v�S10���A�ڂ��Ă���B���̖��M��U��(���a�X�N�U���P��)�Ɂu�l���v�Ƃ������ڂ����邱�Ƃ͕ςł���B �u���ƙB���v�ő��̋���̕��͂��E���ƁA�u�Q�ؓy�����k�v(���a�S�N�S��)�A�u㔘Q�ؓy�����k�v(���a�T�N�R��)�A�u�r�̊ߋ�v(���a�U�N�P��)�A�u���̊ߋ�Ɖ��N���v(���a�V�N�P��)�A�u郙B�@���C���ߋ�ē��v�̓��u�Č�郂�����郁v(���a�V�N11��)�A�u���l�`�Ƌ��y�ߋ�̎�l�`�v(���a�V�N12��)�A�u���̏t�̂�������v(���a�W�N12��)�A�u����ɂ̊ߋ�ꑩ�v(���a10�N�W��)������B�u����v�ł́u��㋽�y�ߋ�v(���a�U�N�P��)�A�u��̉��k�v(���a�W�N�X��)�A�u���ߋ�̝̑J�v(���a10�N�R��)�A�u���s���̐_�Ђ�萂���y���M�Ɖ��N�������v(���a10�N�V��)�A�u�A�T�q�r�[���Ə�́v(���a10�N10��)�A�u�q���V�т̈����v(���a11�N�S��)�A�u�Z�\�R��ׂ̒Ґ�v(���a13�N�Q��)�Ȃǂ�����B
�@�u���y���i�v���a�W�N�P�����ɂ́u�����}���̑��������l�`�v���ڂ��Ă���B30�ȏ�̕����l�`�������ĒZ�������t���Ă���B�u�L�T�l�`�ƗL�T�D�v�́u�L�T���c��l���J����́A���D�Ɏ����ӂ̎��̂������Ƃč���D�ł���v�Ƃ�����ł���B�������u�l���v�����グ�Ă���B���p���Ă݂悤�B
�u�l���v���o�҂Ă��A�����ܔN�����Ƀg���R���Ɖ]�ӌ�h�a�̔@�����̂����s���Ď��ҏ\�O���P�J�i���݂̂��߂��ł����A�����Ɏs������Ƃ���ŁA�l����㉂̈�������o�҂āA�ǂȂǂɓ\����āA��������Ă����͓̂��a�ɜ��ʂƉ]�ЙB�ւ����̂ł����A�����ɍ�㉂���Ƃ��ĕ����Ăō�����̂ŁA�����吼�̉ƂəB�͂Ă�č�����������B
�u���y���i�v�����ɂ͐l���q�u�ߋ�̈��D�҂ɂ͈��l�͂Ȃ��v������B�u�䚠���S铂̉ƒ�Ɋߋ�I���Ă���ē��邱������D���Ă�ւ���A�ߍ��̔@���v�z���ŃC���C���������鎖���Ȃ��炤�ƁA���͂����]�ӎ����l�ւČ����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B
�@���ߋ�̌��p����������Ƃ��U�����Ƃ͌����Ȃ����A���̍��u�l�`�v(�l�`�ЁA���a10�N�P���n���H)�A�u�l�`�ߋ�]�_�v(�l�`�ߋ�]�_�ЁA���a14�N�X���n��)�Ƒ肵���G�������s����Ă����B�u�l�`�v���a10�N�Q�����̊����̕��͂͏��얢���u�Y�p�Ƃ��Ă̐l�`�v�ł���B�����́u�ŋ߂ł́A���y�Y�p���A���̒n����萂���{�p�I��������A�������́A�y����̌��͂�ł���Ƃ����Ӗ�����A�Ƃ�͂��s��l�ɂƂāA�V�����F�����������₤�ɂȂ�܂����B���ꂪ���߁A�ƁX�A�f�p�[�g�Ȃǂ֓W�����Â������̂ł���܂��v�Əq�ׂ����A�f�b�T���E�F�ʂ����������H���̐���i��Җ]���Ă���B���̎���Z������ƂƂ��ɁA��荂���|�p�������߂�v�����������B�u�l�`�ߋ�]�_�v�ɂ́u���ېl�`�W�����W���������āv(���V�J��)�A�u���{�l�`��l��W���V��v(���䎇�_)�A�u���{�l�`�Y�p��Ƌ������W�v(���g��)�ȂǂƂ����L����������B���u��������㉁v�������Ă���Ƃ���A���V�J��(���{��ƁA1889�`1965)�́u�l�`�ߋ�㉁v�Ə������l���ł���B�J���͌����B
�@���͂��̒��ɉ��Ď��Ȃ̐M�O�������̋��𖡂ЂT�A�l�`�ߋ�㉂̊����ɂƐS���X���č������Ɛi��Ř҂��B��Ɏ��Ƃ��Ă̖����͍ŋ߂ɉ�����l�`�ߋ�㉂̒��ڂł���A�ꗬ�`�l���i��ł����`�ނƂ��Ė��Z�����̍ޗ��̏��ᢊ����T���邱�Ƃł���B�������āu�I���`���v�ȂnjĂ��j������ꂽ���̕��ʂ����V�@�����͑S���������āA�p���`�ނ���������ə傳���Ȃ炴�閘�ɁAᢓW���҂����Ƃ̝̉��ɂ́A�S�����납����Ȃ��̂ł���B(���V�J���u�l�`�ߋ�㉁v�|�u�l�`�ߋ�]�_�v���a14�N�X��)
�@��������������{��Ƃł���B���̎t�͒���F��(�P���Y�A1841�`1899)�ł���B�F��͒����F�~(�̐욠�F��l)�ɓ��債�����G���w�сA�ŋ��G�ŔA�o�D����G�A�V���}�G�Ȃǂ�`�����B����13�N�ȍ~�A�����ς�w�l�������̌��{���F���`���B�ߔN�������i��ł�����̋ъG�V���ւ̏����́u���ؖF��v�ł���B����33����̋I�O�ɖ�l�������ł��鋐��̎�Łw�F���`�W�x(���a�U�N)���o�ł���Ă���B����́u����㉎u�v(���a�U�N�W��)�Ɂu����F��搶�_�B�v���ڂ��Ă���B����͖{�����g�A����10�N�U���Q���A��s�_������V�m�O�ŁA��茹���̎O�j�Ƃ��Đ��܂�A�F��ւ̓���͖���25�N�ł���B����30�N���肨�������������A�u��������㉁v����A�ߋ�̔w�i�̌����A�����̊��s�A�W���ɐ�����B���a17�N�X��15���A�����B65�B
�@�l���s�Ղ̌������w�s�s��̖����w�x����A��苐��̐l���G�A�l���u�l���v�𒆐S�Ɂu�I�����܂݁v�Ƃ��ďq�ׂĂ݂��B
�@����M�u�l���̛��D�v��Y���Ă����܂��̂ŁA�悢�����������������B
by���_�@��(aka.MORO)�@
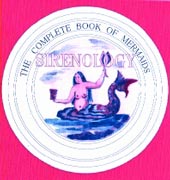
�@2006�N�������Ƃ����Ԃɉ߂����낤�Ƃ��Ă���B�I�⏰�ɂ͎����ƚ������܂�A�܂Ƃ܂������ł����ɁA�܂��܂����E�����Ȃ��Ȃ����ł���B�ڂɂ������́A�L���Ɏc���Ă�����̂̒I���������݂Ă݂悤�B
�@�������x�������Ă���b�������A����40(1907)�N�R��20���`�V��31���܂ŏ��ŊJ�Â��ꂽ�������Ɣ���������ɐ݂���ꂽ���琅���ق́u�l���v�W���ɂ��Ă܂����������������Ƃ�����B�u�����V��v��2582��(����40�N�U���W��)��Q�ʂɁu�����Ɣ����𐅑��ڂ֏o�i�v�Ƃ����G�������B
���d�R�S���\���߂ɉ��Ĕ����[�����P�̊C�n��ߊl�������Ȃđ��ٙZ(�����O���P)�Ƌ��ɖh����(�}�}�A��)�𒍎˂��Ėډ��J�𒆂̓������Ɣ����𐅑��ڂ֏o�i�����邪��߂��V�q�̌ĕ�����ׂ��ƒA����ق��`�ē�������菜�������
�u�C�n�v�Ƃ̓W���S���̂��Ƃł���B3m���̃��X��91cm�̐��ʕs���َ̑����h���������{����ēW�����ꂽ�̂ł���B�W���J�n�̎����͏��Ȃ��Ƃ���������ł͂Ȃ��悤�ł���B�u�����V��v�͂S���Q������u�����������͔@���Ȃ�i�����v�Ƒ肷��L����f���I�Ɍf�ڂ��Ă������A���̂T���(�̖��L�͂���Ă��Ȃ�)�Ǝv����S��17���ɂ͐����ق����グ���Ă���B�������A�C�n���l���ɂ��ĉ���G����Ă��炸�A�����Ԃ������U���W���ɏo�i�̎G�ڂ����B���̊ԁA�T���́u���{���N�v(��Q����T���A�T���P��)�A�u���w�E�v(��S����11���A�T���T��)�A�U���̏�싳�甎���ي��w���{�����}���x�ɂ͐l���W���֘A�̋L�����݂���̂ŁA�U���W���ł͒x������Ƃ��l�����A�J�n�����͍��̂Ƃ���s���Ƃ��邵���Ȃ��B
�@���琅���ق̗l�q���u�����V��v�̋L������M���ƁA�C�b�ނ̐��̎��炪�s���Ă����悤�ł���(�u�����V��v����40�N�S��17���A�Q��)�B
���̖ʐϊK���S��\�A�K��l�\�ܒA�����̝ɕ����Ďl�\�����苛���O�S�A��ޘZ�S�ɒB���K��̎��͈�ؔV�������̐��Y���i���ɏ[�Ĕ����̒�����Ñ�̐����Ȃǂ���ق̒����Ȃ�C�b�r�͎�����\�Z�ڂ��荟�̒��ɊC醁A�K���`�A��l����������Ă���l���̕ǂɂ͖�㉂ɂĈӏ����Â�����C�̛݂��i��`�����Ă���
�C���͎O�Y�����̏��։������ȋ��܂őD�ʼn^�сA���ɖ���150���������ƌ����B
�Ȃ����̖���40�N�H�ɂ͒��茧�Łu������{���A�����Y���i��v���J�Â���A���ꂩ���800�_�̏o�i���\�肳��A���̒��ɂ́u�C�n���Z�v���܂܂�Ă���(�u�����V��v����40�N�S��19���A�Q��)�B
�@���Ɣ�����ɂ͓����̖ڋʂƂ��ăn�[�Q���x�b�N������(�J�[���E�n�[�Q���x�b�N�����1873�N����1914�N�ɁA150���̃L�������w�������|�x���g���g�E���E�t�@�[�w�L�����`���l�x)���A���Y�̃L�����A�̃I�i�K�U���A�n�Q���V�R�H�A�C���R�ނS�H�A�u�����ށv�Q���Ȃǂ��w������(�u�����V��v����40�N�R��24���A�R��)�B���̎��Y�̃L����(�Ƃ��ɂS��)�����{���n���炵���A�ΐ��㏼(�鎺�����ٓV�Y����)���ӔC�҂ł������B�L�����l�C�͂����܂����A�����ȍw����(8000�~�A�^���G���)�������̓��ꗿ�����ʼn���ł����悤�ł��邪�A�ɐB�����҂���Ȃ���A�~�̊������炩�A���N�n�߂ɂ͂Ƃ��Ɏ���ł��܂����B�Ȃ��A���̖���40�N�Q���ɂ��i�ٔ���������Ђ��ݗ�����Ă���(�u�����h�Ƃ��Ắu�i�كr�[���v�̓W���p���E�u�������[�ɂ�薾��21[1888]�N���琻������Ă���)�B
�@���ƌ����A�����Ȋw�����ق�10��17������11��12���܂ŊJ�Â���Ă����u�������̕������@�������ɒ����ꂽ�Ȋw�̖ځv�W�ɂ͐l���W�̓W���i�ő����o����Ă����B�u�l���̃~�C���v�Q�́A���̓��̈�̔��˔˓암�Ƌ����̐l���͑o��(����q)�ł��蒿�����v�����B�w���B�e�ɂ��A�㔼�g�͍�蕨�A�����g�́u�R�C�̒��ԁv�̗�h�����p����A�u�V�����v���p�����Ă���B���˓암�Ƃɂ̓~�C���Ƃ͕ʂɁA�l���́u�܁v�u����v�u���v�u��v�u�S�q���v�u�q�v���`�����Ă����B�Ȋw�����ق̍b�\�����E�R�c�i�ɂ��ƁA�S�{�́u�܁v�̂����Q�̓n�N�W���ł���I�L�S���h�E�̎��ŁA�u��v�̓c�`�N�W���̎��Ɛ�������Ă���B�����̐l���W���W�i�͔��˔�(�암�����˂̎x�ˁA�Q����)�̍Ō�̔ˎ�X��암�M��(�̂Ԃ䂫�A1813�`1872�A�ˎ�E�m�ˎ�1842�`1871)�ɂ����̂ƍl�����Ă���B�M���͓��Ïd��(���܂Á@�����ЂŁA1745�`1833)�̎q�Ł@�Z�ɉ�������(1781�`1855�A�d�����j�A���Ôˎ�)�A���c����(���낾�@�Ȃ��Ђ�A1811�`1887�A�d���X�j�A�����ˎ�)�炪����B
�@�喼�Ɛl���̊֘A�ł́A���ƌ����Ă��L���Ȃ̂́u�b�q��b�v�������Y�ÎR(1760�`1841�A���˔ˎ�)�B��b�ɂ͊��V���u���C�ɂĐl�������鎖�v�Ƃ��������ꂪ����(1744�`1748)�̎n�߂ɖڌ������L���̊O�ɁA���ъ��V���\�Z�u�w��L�x�V��v�Ɂu�l���v�̕���������B2004�N�A���s�s���~���[�W�A���ōs��ꂽ�u���{�̌��b�|���m�F�����o���^�v�W�̐l���̃~�C���́u�����\��N�@��(?)�H�����@��B��O���@���l�@�Ďq�r�Z�g�Δ��v�ƁA1815�N�ɑ���~���̗�Ɍ~�g��������D�≮�ɑ���ꂽ�Ƃ�������ꂪ�������B�Ďq�͕��˔˗̂ł���B
�@�������̕������W�ł́u�������D�}���v�́u���l���v(�ȑO�Љ�����Ƃ�����)�A�u���蕷���^�v�́u�C���v�u�C�l�v�A�u�a���O�ː}��v�u�l���v�A�u�����E(���{�˂̝�)���v�Ƃ��ẴZ���U���R�E�A�d���G���́u�l���v�A2005�N�P�����˓��C�ō̏W���ꂽ�����E�O�E�m�c�J�C�W�{�A�L�N���A�u�Z���V�u�v�Ȃǂ����������A�������Ƃɋ������o�����̂͏ڍוs���́u�]�ˎ���̉������j���[�X�v�L�ڂ́u�L�N���v�ł������B��O���˂ɏo�������l���b���_�̎g���ŁA�V�N�̑�L��ƁA���̌�̗��s�a��\�����A�p�̎ʂ�������҂͕a��قꕟ�M���b�ނƐl�X�ɓ`�����ƌ����B�H�͐��A�̒��T�ڂƐ������ɂ���B�����u�A�}�r�G�v�ł���B
�@�ŋߔ������ꂽ�t�B�M���A���������S�����NO.3�u�A�}�r�G�v�́u�������̂���l���̂悤�ȉ����v�Ƒ��㌒�i���������Ă���悤�ɁA�����Ȕ��h�����`����Ă��邪�A���́u�������j���[�X�v�̐}�͐l�ʒ��ł���B���l�̗\�����ɂ͏���ˎm�����ˎR�̌������^�u���z�ٖ��M�v��91�̖����ɍڂ����Ă��钹�}������B2003�N�S��19������U���P���ɒ���s�������قŊJ�Â��ꂽ��48����ʓW�u���̐��E�d���|�M�B�يE���؋��|�v�}�^p.46�Ō��邱�Ƃ��ł���B���{�̋L�q�͐}�^����͓ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ����A�}�^�������ɂ́u�V��10�N(1839)�V���ɔ�O������(���茧)�ֈٍ���肫���ْ��ŁA�u���͐_�̎g���ł���A����u�a�����s��A�l�͂V���ʂ莀�ʂ��낤�B���̎p���ڂ��Γ�ꕟ���~���ɂȂ�v�ƋL����Ă���v�Ƃ���B��͐l�ʂƌ������t�N���E�̂悤�ł���B
�@�A�}�r�G�͍O���R(1846)�N�S�����{�A���Ɍ���Ă���B����ȑO�̎p�̕��˂̖L�N���͒����̂��́A�I�E�����㊯���Ƃ������ٍ��̐l���b�����̌������Ƃ��̌���|���N���̂悤�ɑz���͓����B�O��10�N���߂̃I�E���E�L���E�J���`���E�̋L�^����쒼�G�w���{�������N�\�x�ɋ��߂�ƁA�V�ۂT(1834)�N�T��13���̓��t�Łu���É���{�R��O�ō���(���}�A���V)�̌������n�܂�B�V�ێO�N�n���̌̂��B���ɐ`�g��(�L���E�J���`���E)���_��(�I�E��)��������v������B�V��10�N�̋L���͂Ȃ��B����ł��A�A�}�́u�C�v�A�r�G�́u�I�����_��papegaaai�p�y�K�[�C��parrot���I�E���v�ȂǂƗ^����f�������Ȃ邪�A�u�A�}�r�G�v���u�A�}�r�R�v���ɂ͋y�Ȃ����낤(���{����w���{���b�}���x�A�͏o���[�V�ЁA2005.7.30�App.65�`97�u�\�����錶�b�v)�B
�@�Ȃ��u���z�ٖ��M�v��48�ɂ́A����13(?)�N�V���A�z��ؘ@���ŊJ�����ꂽ�l���̋L�q�Ɛ}������B�u�}�O���@���S���Y�Y�v�Łu�^��ڂȂ炸�v�ƋL���Ă���B��̏�ɍڂ���ꂽ�l���́A���m�l�j���̂悤�Ȋ痧���ŕ`����Ă���B
�@2006�N�̓W���ŋC�t�����l���֘A�̂��̂ɂ́A���s�����فE���ʓW�u��]�˓����}���|�q�E�N�E�Ёc�\��x����l���E�͓��܂Ł|�v(9/22�`11/5)���������B���s�������́u�l���~�C���v�A�����Q�N�Ɋ��Łu�l���}�@�ꖼ�C���v�A���ˁE��Ό���́u�Z���V�u�v�A�u�P���R�C�^�v�Ȃǂ��W�����ꂽ�B�}�^�����ɂ͓��R����u�ۂ������A�����o���A�l���������I�|�]�˂̕s�v�c��������|�v(pp.131�`136)�Ƃ����_�l���ڂ��Ă���B�����ʍW�w�������G�u�x�A���C�f�������ق̂R�̂̐l���~�C��(�o�����ْ��u�����z�t�̎��W�i)�A�w�~�������x�Ȃǂ��Љ�u��������V�۔N�ԍ��ɂ͍]�˂���E���É��̎s���ɐl�����o�v���邱�Ƃ����X�������̂ł���v�ƌ����Ă���B�܂��A�u���ł͂��̐l����R�їނɑ�����[�C�������E�O�E�m�c�J�C�ɔے肷������L�͎�����Ă���v�Ƃ��w�E���Ă���B�Ȃ��A�}�^����119�u�l���̃~�C���v�̐������ɂ́u�l���̃~�C���̑����͒����암�ł���ꂽ�Ƃ����v�Ƃ���Ap.101Column17�u�͓��Ɛl���v�ɂ́u�Â��̓I�I�T���V���E�E�I�A�܂��̓A�U���V��A�V�J�̂悤�ȊC�b��l���Ƃ݂Ȃ��Ă����悤�����v�Ƃ��L���Ă���B
�@�]�ˎ���́u�s�v�c�v�ɒ��ڂ������W�͐����s�␣���ɂł��J�Â��ꂽ(�u�s�v�c�͊y�����`�]�ˎ��㒿�k��k�`�v�A4/8�`6/18)�B�}�^p.10�͐l���֘A�R���������邱�Ƃ��ł���B�u���L�\�ŕi���}�l�v(�Éi�Q[1849]�N�ŁA�ۉ����A�����t����)�́u�l���v���i�u�ߐ������ɐl����Ď��n�鍜�n�ł�������Ɍ����荟���̐����H�l��N�̎����������Ƃ��ւ�v�j�A����ᩎR�ҁw�ȕ���M�x�����u�P���}�v�A�u����W�v(���X[1759]�N�A�z���������ɏo���l��)�B�ȕ���́u���s�̔���������v�ŁA���̋L�^���w�ȕ���M�x(�����U[1823]�N)�ł���B�u�P���v�́w��߁x�L�ڂ́u�_�ЕP�v�Ɠ����A���������̃R���������G�}�ł��邪�A�S���W���ɔ�O���˂Ɍ��ꂽ���_�̎g�҂Łu�����莵�N�Ԃ́A�����ɃR�����Ɖ]��܂Ђ͂��l���������v���A�u��`���Ɩ�ɂ͂肨��@��܂Ђ��̂���q���͂₤�Ȃ�v�ƍ������Ƃ����B���̐g�͂P��T�A�U��(4.5�`4.8m)�B�L��̗\���͓`�����Ă��Ȃ��B
�@���̖L�N�Ƃ��̌�̉u�a���s�\���͉A�z���̗L�T�E���T�̍l�������W���Ă���悤�Ɏv����B�L�T�Ƃ͂V�N�����g��̔N���A���T�͂��̋t�̂T�N���������N���̎��ł���B�u�L�T�ɓ���v�ƁA���蕨(�L�T�G)�A�l�`�A�َq�Ȃǂ�����ꂽ�Ƃ����B�����ɂ́u�Ӂv�̎��s�����̂��̂��V�W�߂�ꂽ(�x�m�A�D�A�M�A�����A�����A�J�A�܂Ȃ�)�B���{�����V���}���فu�l�������Ƀf�[�^�x�[�X�v�ŁA��苐��u�ߋ�v�����́u�����L�T�l�`�v�����邱�Ƃ��ł���B�S�̂��x�m�R�̌`�ŁA�Y�̕v�w��̊Ԃɓ�������A�D�ɂ͕����E�����E�܁E�M���ς܂�Ă���B�g���̔N���A���ɒʂ�����蕨�ƁA�_�ЕP�E�A�}�r�G�ɋ��ʂ��镶��������悤�Ɏv����B
�@�_�ЕP�͗��_�̎g�҂ł��������A���{�̊C�̐_�X�ɏœ_�Ă����ʓW�͋�B���������فu�C�̐_�X�|������ꂽ�|�v(10/8�`11/26)�ł������B���ڐl���Ɍ��т��W���͂Ȃ��B�������A���Q�����p�قŊJ�Â���Ă����̂́u���̂������W�|�݂�A�ނ�A�A�F��A�V�ԁ|�v(10/12�`11/26)�ł���B���Y�w�n��}�ďW�x(�吳15�N)�ɂ́u�l���v�̐}�Ă��������B�̐l���}�Ă̓A�h�E�~���[�W�A�������@���ʊ��u�吳���_�j�Y���ƍL���W�v(8/1�`9/23)�ł����邱�Ƃ��ł���(�w��ʜ�p�}�ďW�x�A�吳10�N�A������)�B
�@�吳����Ɛl���̌��т��ɂ��Ă͎R�����j���w�E���Ă���B�u���X�Ɛl���F�吳�̃V���{���v(�u�n�挤���W���[�i���v��12���A���R��w�����������A2002.3.1�App.110�`121)�B����͏��R��w���w���ƍ����؏��吳���}���ً�����Â̍u����̋L�^�ł���B�����؏��吳���}���ق̑�30��ٓ���݃e�[�}�W�������́u���X�Ɛl���W�`�吳�̃V���{���`�v(2001�N�R�`�U��)�������̂ŁA���̓W���֘A�̍Î��ł��������̂Ǝv����B�R���̐l���ւ̊S�Ƃ��������A�W���ɑ����Ęb��i�߁A���B�W���A���̒��S�ɂ͂Ȃ������u�ǂ��炩�Ƃ����ƒʑ��I�v�ȁu�l���v�Ɂu���a���Ă���悤�Ȃ��̂��������グ��v�R��������݂̎������_���y�����q�ׂ����̂ł���B�u�Z���V���V�v����Δk(1801�`1878)�̒��ɂȂ��Ă�����A�h�{���U�[�N�̃I�y���u���T�[���J�v�̃X�g�[���[���������ς������肷��̂͂����h���B�w�E���Ă�����̂��L����ƁA�Z�C���[��(�V���[�k)�A���[�x���X�A�{�b�X�A�����[�A�����b�N�A�o�[���E�W���[���Y�A�E�H�[�^�[�n�E�X�A�t�H�[�Q���[�A�����W�[�k�A�h�{���U�[�N�A�C���h�l�V�A�̖ؒ��A�u�Z���V�u�v�A�u�a���O�ː}��v�A�����ܗt�A�J�菁��Y�A�������ەz�A�L�ؐ����A�u���̑D�v�A���Y�A�|������A�����؏��A���J�����ł���B�J��ȉ����u�吳�v�Ɍq����l���ł���B�Ƃ肽�ĂĒ������z�w�ł��Ȃ����A���ꂼ����ڍׂɏЉ���l���{���Ȃ��̂ŁA���O�ɂ͋����[��������������Ȃ��B
�@�Z�C���[���ɂ��Ă͒m���Ă���悤�ŁA���{��ł܂Ƃ܂�����������߂ɂ͂Ȃ�����ł���B�p�ꌗ�ɋ��߂�ƁA���N�̐��ʂɂ́w�T�C�����̉��y�x(�����_�E�t�B���X�E�I�[�X�^�[���A�C���i�E�i���f�B�c�J�����ҁA�C���f�B�A�i��w�o�ŋǁA2006)������B12�҂̘_�l�ƃC���g���_�N�V���������߂��Ă���B�u�Ñ㒆���̃Z�C���[���v�A�u���V�A�̃��T�[���J�ƃi�V���i���Y���v�A�u�T�C�����̃Z���i�[�h�F�}�~�E���^�A���̑��̃A�t���J�̐��̐��v�����ɋ����[�������B
�@�Z�C���[���͍]�ˎ���ɊC�O�m���Ƃ��ē`����Ă������A�z�����X�u�I�f���Z�C�A�v��e�͂�͂薾���ȍ~�̂��ƂƂȂ�B�Ԏi���ԁE�Γc�t���ҁw�I�a�b�Z�[�T�@�������(�Y��)�x(���`�����ЁA����37�N�P���Q��)�́A���̏����̏Љ�ƌ����邾�낤�B�Ԏi�E�Γc���҂ɂ́w�k���_�b�@���́x(���`���A����35�N�W��15��)�A�w�C���A�b�h�[�T�@�|�̋��x(���`���A����37�N�P��10��)�A�w�_�b�[�T�@�V�n�x(���艮���X�A����35�N�S��20��)�A�w�_�b�[�T�@�Ӓ��V�|���x(���艮���X�A����35�N)������B�w������Ёxpp.34�`36�����p���Ă݂悤�B
���_�`���P���ޓ��̏oᢂ��������V�����X�l�̊C�݂��A���Ȃ��ʉ߂��ׂ��p��������������A���̃V�����X�Ƃ́A�C�̗���(�j���t)�ɂ��āA�ޓ��̉̂ӂ�A�������́A���S��ɐS�����A�s�K�̍q�C�҂́A���炸�A�����A���A����Y��A���ɊC��̐����ƂȂ�Ɏ���Ƃ��ӁB
�`���P�A�T���A�E���Z�X�ɋ��ւāA���v���̎����A�X���Ăӂ����A�ȂāA�V�����X�̖��������炵�߁A�܂��E���Z�X�́A����A�g���ɔ����A���̖��ɏ]���āA���v�����߁A���ċ��܂��ނ�܂�ƍ����ʁB
�E���Z�X�́A�`���P�̋��ɏ]�ЁA�X���ȂāA���v�̎����ǂ��A����g���ɔ����A�������ăV�����X�̓��ɋ߂�����ɁA�C��A�Âɂ��āA�����N�炸�A�ޕ��̓����́A�D�ɖ��ւȂ���߂�����B���S��g�A���̂��悬�ɂ�āA���̖ʂ��킽�藈�钲�ׂ��߁A���͋߂��A�{���̉��F�A���C�̉C�A����D�ЁA�S���������ꂵ�ނ�ɁA�E���Z�X�́A���ӂ�ǂ�������A�E�ׂǂ��E�т��ĂɁA����E���A�߂�����ɍs���ނƋ��сA���Ȃ��Ɍ��Ђđ����ƍ������A��������ނƂ��ւǂ��A�����Ђ��鐅�v�ǂ��́A�ȑO�̖����ł����āA�u���ق��ނ��A���̍q�H�i�݂ɐi�߂A�₤�₤�A����ꡂ��ɗ���āA�����̋���������Ȃ�ʁB
���R�Ɏ���āA�E���Z�X�́A�����X����苎��A�����āA�܂��A�Ȃ������������߁A�����݂ɖ����Ȃ肵����яj���ʁB
������ɁA�V�����X�̈�l�Ȃ�p���e�m�y�́A�E���Z�X�̓قꋎ�肵�����āA����͂̋y�����߂݁A�C�ɓ����Ď����ʁB
�ޏ��̎r�A���ꗬ��āA�ȑ����̊C�݁A�����A���̃l�[�v���X�̒n�ɕY�В����ʁA���̒n�A���ăV�����̖��ɂ��ČĂ�ɂ��ƂȂތ��B�ӂ�B
�i�|��(�l�A�|���X)���Z�C���[���u�p���e�m�y�[�v�Ɉ��s�s�ł��邱�Ƃ́A�}�m�G���E�I�����F���ēu�i���̌�炢�v�ł�����Ă������A��������Ɋ��ɓ`�����Ă������ƂɁA���߂ċ��������B�Ԏi�E�Γc�̓u���t�B���`�w�`���̎���x�A�Q�C���C�w�p���w�̌ÓT�_�b�x(1900)�Ɉˋ����A�z�����X�̎��͎�Ƀ|�[�v�̖���Q�l�ɂ����B�p�������V�[�Y���u�E���Z�X�v�A�T�C�������u�V�����v�ƕ\�L���Ă���B�Ȃ��Γc�t���͖{�����G(1877�`1943)�ŁA�o�l�E�����w�ҁB�Ԏi���Ԃ͔ɑ��Y(1872�`1965)�ŁA�L���X�g�҂ł���A�q���ɗY���ɂ��w���R����̉^���|�Ԏi�ɑ��Y�̐��U�Ƃ��̎��Ӂx�ɏڂ����B��l�Ƃ��o�œ������É��ݏZ�ŁA���É��ꒆ�ŋ����Ă����Ǝv����B�w������Ёxp.35�ɂ͔����ɂR�H�̃Z�C���[�����~�܂��Ă���I�f���Z�E�X��̑D(������͂U�l)���`����Ă���B
�@�Ԏi�ɑ��Y�͂��̌��i���≺�ɂ��������j���@�[�T���X�g����t���A�����p�ꏗ�w�Z�̍Z���߂����A���t�ɂ͐��c���](1882�`1936)�A�X�c����(1881�`1949)�A�����(�k�����J���S�l�A1865�`1940)�炪�����B���̐����p�ꏗ�w�Z�ł͕��˂炢�Ă�(1886�`1971)���w��ł���B���c���]�ɂ��w�I�f�B�b�V�C�x(���E�����p�����ҁA���������X�A�吳11�N�V��25��)�̖�����Bpp.299�`300���Y�������ł���B
�u�����č��`�Ă̍����̎��͏I��������Ȃ�B�T�����͉䂪���ɍ����鎞��ɒ����B�����Đ_���玞�ɗՂ݂ē��ɂ�����v�ЋN�����ׂ��B�T�C�������ɂ܂Ő�Ó��͓���ށB�ޏ����͔ޏ����ɓ���Ƃ�����`�Ă̐l�X��f�͂��Ȃ�B���炸���ނɋ߂Â��A�T�C���������߂̋����Ƃ���̎҂͉��l�ɂĂ���A�ނ͂Ђɟd�����Ĕނ̖T�ɗ��Ă�Ȃ����Z�����邱�ƂȂ���ׂ��B���͔ޓ��͂Ђɔނ̟d�����}�ւĉx�т��Ȃ����ƂȂ���ׂ��B�T�C�������͑��̖�ɍ����āA���炩�Ȃ�ޓ��̉̂����Ĕނ�U�Иf�͂��Ȃ�B�����Ă��ׂĂ��̂܂͂�ɂ́A�l�X�̍��̑�Ȃ�R����Č͂�A���̂܂͂�ɂ͔炠��ċ������ꂽ��B����Ǔ��͓��̑D�����čs���߂���B�����Ė��X��s�˂āA��������ē������ԓ��̎���h�荞�߂�B�k��Ȃ鉽�҂������̉̂����ƂȂ����ਂ߂ɁB����Ǔ�����ɂ��ĕ����ނ��Ƃ�~�ӂɎ���A�ޓ������ē��̎葫�𑬂��D�̒��ɔ��߁A�����̙|�ɒ����ɐ����A���������Ĕ����Ɍ��Ђ����߂�B����Ήx�т����ē��̓T�C���������߂����ƂށB�����ĎႵ�������̒��ԓ��ɐ��Ћ��߁A�ޓ������ē����ׂ��������߂ނ��Ƃ��˂��͂ނɂ́A����Δޓ������čX�ɂ�茘�����߂��߂�B����Ǔ��̗F�������̑D�����č����̂��̂��s���߂����鎞�́A��͉���̓r�����̌���̂��̂ɂĂ���ׂ������A�\���ɓ��ɍ�������ׂ��B���͓����炻����v������B
�@���a�ɂȂ�Ɛ�O���ɂQ��́u�I�f���b�Z�C�A�v�������ƂɂȂ�B�P�͓c���G���E���Y�È�w�I�f���X�Z�B�A�[�x(�O�������X�A�㊪���a14�N�S��14���A�������a14�N�T��17��)�B�����P�͓y��ыg(�Ӑ�)�w�I�a���b�Z�[�A�x(�y�R�[�A���a18�N�Q��20��)�ł���B
����̍�茘�łȂ�D�́A�v���ɁA�Z�B���[�����̓��ɗ����B(����)
�u����ǁA���͉s���Ȃ陘���āA���X�Ȃ���ׂ��荏�݁A�킪痂����_����āA�����s�˂�A���X�͂킪��Ȃ�ؗ͂ƁA�V��q�̌N�Ȃ���ւ̐_(�G�[�G���I�X)�̌����̂��߂ɁA�v���ɉ���ʁB���́A���������ׂĂɁA��l��l�̎��ɁA�����h�肽��A�ޓ��́A�����A�D�̒��́A���̍��������Ɏ�̑������X�ɔ���A��̐�[����ɂ����ƌ��єޓ����g�͍����낵�A�ޓ��̟D���āA�D�F�̊C����@���ʁB(����)
�u�ޏ����́A���Ɩ��Ȃ��߂𑗂�āA���₤�Ɍ��ЂʁB���̎��A�킪�S�͎��X����Ɨ~���A�������ɔ����Ђ��߂č������Ȃ��A���������Ɩ�������ǁA�ޓ��͟D�������Ɖ����āA�����i�݂ʁB���A�����Ƀy�����[�f�[�X�ƃG�D�������R�X�Ƃ͗���������āA�����u�X�����������߂ʁB����ǁA�ޓ����A�Z�B���[�����̂�����𑆂������A�ő��A�ޏ������߂��̂��������������ɁA�������́A�����ɁA��ꂪ�ޓ��̎��ɓh�肵���X����苎��A�����ڂ������ʁB(�w�I�f���X�Z�B�A�[�@��xpp.359�`362)�Z�[���[�l�X�ɂ܂Ð�ɓ��s���ׂ��A��藈��
�l��������U���f�킷�����̌Q��
���l�ɂ܂�m�炸���ā@�Z�[���[�l�X�ɋߊ���
�����߉�����ҁB�@�ނ͌̋��ɟd��s���A
�}�ւĚ��ލȂƎq�̊�Ԋ�ߓ����A
�Z�[���[�l�X�͐X�̖�ɍ����A�̂�
�N�X�ƋႶ�Ĕނ�f�͂��ށA�݂̂ւ��ɗ݁X��
���l�̍��͂��Â������A�畆�͏k�݂ĔV�ɂ��B
���̂��Γ𑆂�������B�������đO�ɏ]�҂��
���ɖ��X�s�˂ē���A���̊O�̒N�ɂ���
�d�����߂����߂ȁA�����畷���܂��A
�O�ɖ����Ĕ����̋��ɓ��点��A
�������ɗ��Ă�g�̎葫�����ƒ��ɂ����点��B
�������ē���тăZ�[���[�l�X���ߕ����ށB
��������ׂ��]�ғ��ɓ��̖�����͂A
�ނ�́A����挵�d�ɓ�ɓ���ׂ��B
�����ď]�҂獟���ޔg���킯�Đi�ނׂ��B(�w�I�a���b�Z�[�A�xp.382)
�@�c���G��(�ЂłȂ��A1886�`1974)�͋��勳���A���m�ÓT�w�����n�ݎҁB���Y�È�(1891�`1967)�͓��勳���A�p���w�ҁA���c���]�Ɠ������Ėڟ��Ζ剺�B�y��Ӑ�(1871�`1952)�͎��l�E�p���w�ҁB�w�I�f���X�Z�B�A�[�@��x�ɂ́u�I�f���X�Z�D�X���Z�B���[���ɗU�f����隤�v(p.360)�Ɓu��(����O�ܐ��I�̊��c�r�)�v(p.361)�����߂��A�u�I�a���b�Z�[�A�v�ɂ́u�Z�[���[�l�X�v�̒��Ƃ��āu�����d���T�C�����Ȃ�A�z�[�}�A�ɂ͑��ɓ�A�㐢�̎���ɂ͎O�A�������ă|���L�X�̑����Ə̂��v�ƋL����Ă���B
�@���̌�͊�g���Ɍ��Έ�(1897�`1977)��w�I�f���Z�C�A�[�x�㉺(1971/72�N)�A��������H(1915�`)��w�I�f���b�Z�C�A�x�㉺(1994�N)�����邱�Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B
�@���[�}�c��e�B�x���E�X(�O42�`��37�A��Q��c��)���u�����w�ҁv(�����g�V����ɂ��B�p���Y�́u�M���V�A���w�̋����v�Ɩ�)�ɁA�u�V���l�X�͂����ǂ�ȉ̂��������Ă������v�Ǝ��₵�����Ƃ̓X�G�g�j�E�X(ca.70�`130�A�w���[�}�c��`�x)���`���Ă��邪�A�ߑ�̍�ȉƂ��Z�C���[���̉��y���Č����ĕ������Ă���Ă���(�Ⴆ�A���C���S���g�E�O���G�[��[1875�`1956]�̌������u�T�C���[��(���̐�)�v��L���ȃh�r���V�[[1862�`1918]�̖�z�ȑ�R�ȁu�V���[�k�v)�B�z�����X�I�ȃZ�C���[���̃C���[�W�Ƃ͈قȂ�V��̉��y�Ɋ֘A����Z�C���[����`���Ă���̂̓v���g���́u���Ɓv�ł���B�n������芪�����A���z�A�����A�����A�ΐ��A�ؐ��A�y���A�P���́u�ЂƂЂƂ̗ւ̏�ɂ̓Z�C����������Ă��āA������ɂ߂���^��Ȃ���A��̐��A��̍����̐����Ă����B�S���Ŕ��̂����̐��́A�݂��ɋ��a�������āA�P��̉��K���\�����Ă���v(����ߕv��w���Ɓx�����A��g���ɁA1979.6.18�Ap.363~364)�B�o���f���o�[�m(ca.1500�`1557)�u�Z�C���[���̎��̏W�v�́A���̃s���^�S���X�^�v���g���I�ȃZ�C���[���̉��y�ł���B
�@�z�����X���ŌÂ̋L�^�Ȃ�A�����E�G�W�v�g����̉e��(�A�b�V���A�̃A�V���[����G�W�v�g�̃o�[)�����Z�C���[���̑��`�́A�M���V�A�ł͋I���O�V���I�̏������璤���A�r�^��G�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�v�����X�g����w���p�ق�2003�N10��11������2004�N�P��18���܂ōs��ꂽ�u�P���^�E���X�̔��݁v�W�̃R�[�q�[�E�e�[�u���E�u�b�N���̐}�^�ɂ̓Z�C���[���֘A�̂��̂��W�_���߂��Ă���B���l���`�͏����ł͐��ʕs���ł�������A�j�������������A�I���O�T���I�����畁�y����悤�ɂȂ�ƁA�������A�l�ԉ��̌X���������ɂȂ����Ƃ����B����Ɠ����ɁA�揊�Ƃ̊֘A�̊함������������悤�ɂȂ����B�v�����X�g���̐}�^78�́u�Z�C���[���^�����r�v(�Z���~�b�N�A���M���V�A�A�I���O�U���I�j��2004�N�V��17������X���T���̊��ԁA�Ñ�I���G���g������(�r��)�ōs��ꂽ�u�Ñヂ���X�^�[���[���h�ւ悤�����@��z�����E�_�X�̐��E�W�v�œW�����ꂽ�u�Z�C���[��(������)�v�Ɠ��^�̂��̂ł���B�I���G���g�����ق̂��͍̂���13.5cm�u���̃Z�C���[���͒���ɂȂ��Ă��āA���̕������獁���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł��܂��v�Ɛ}�^�̐����ɂ���B�v�����X�g���W���̂��͍̂���13.1cm�A����19.7cm�A�Ƃ��Ɏ����ɍד����ʂ����̕t������������B�v�����X�g���̃Z�C���[���͍ŌÂ̂��̂��I���O750�`700�N�A�V�������̂ŋI���O440�`430�N�ł��邪�A���オ�V�����Ȃ�ɏ]�������ȑ��`�A�f�U�C�����ɕx���̂ɂȂ��Ă���B
�@�Z�C���[���͕��ʁA���͉͐_�A�P���[�I�X(�����̃M���V�A�ő�̐�̐_�i)�A�܂��͊C�̐_�i�|���L���X�ŁA��̓��[�T�̈�l(�����|���l�[�A�e���v�V�R���[)���Ƃ���A�M���V�A�{�y�ł̓e���N�V�G�y�C�A�[�A�A�O���I�y�[�A�y�C�V�m�G�A��C�^���A�ł̓p���e�m�y�[�A���Q�C�A�[�A���E�R�V�A�[�̑g�ݍ��킹�Ō���Ă����B�|���L���X�̖��ɂ́A�S���S�[���A�O���C�A�C�A�X�L�����������B
�@���l���狛�l�ւ̃Z�C���[���̕ω��ɂ��Ă͕ʍe�ŏq�ׂ邱�ƂƂ��邪�A�I���G���g���瓌�Q�������l�ɂ��Ắu���{�̔��p�v��481��(�������A2006.6.15)[�l�ʂ������|�ޗ˕p���̐��E�^���،���Y]���V�����B�������_�u�Ñ�n���C���E�ɂ�����l�ʒ��ƗL���l���v(pp.90�`98�ł̓Z�C���[��������Ă���B
�@2006�N�̓W���W�ł͐�t�������������فu���ق̐[�C�����|���m�̐[���E��������v(7/1�`9/3)�́u�����E�O�E�m�c�J�C�v�A���{�����V���}���فA�l�������Ƀf�[�^�x�[�X�q�C�L�O�u���ꂪ�g��������G�h���I�`����ߋ�Ɍ���吳�E���a�����̋��y�ߋ�`�v(10/10�`10/26)�A�ڍ�����p�فu�R�����v�ƌF�c���ؓW�v�u�F�c�����W�v(6/24�`9/3)�A���s�s���~���[�W�A���uNIPPON�@����m�V���Ɠ��{�H�[[1931-45]�v(7/8�`9/3)�A���c�s�������فu���ӂ��̐��E�|�x���i�[���E�t�����N�R���N�V�����v(9/12�`10/22)�A�p���̍������R�j�����فu�h���S���|�Ȋw�̃t�B�N�V�����̊ԁv�W(4/5�`11/6)��������������ꂽ�B
�@����͐�苐����Ăю��グ�Ă݂����B�i���c�̌Ï��X�W���o�[�E�H�b�N�ɋ���́u��������效�v���{�Q�A�T�A�V�A�W�A�X�A10�W������܂��B�V�A10�W�ɂ͐l���ߋ�����߂��Ă��܂��B�j
 |
 |
 |
 |
 |
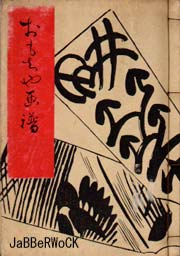 |
by�\������(aka.MORO)