東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>31P
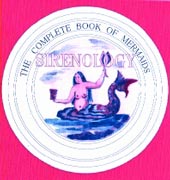
人魚博士こと平坂恭介(1887〜1965)については既に述べた。今回とりあげる神谷敏郎はクジラ博士と呼ばれた小川鼎三(1901〜1982)の研究室にいた。平坂は動物学者であるが小川は解剖学者、つまり医学者である。二人の博士にまつわるエピソードから始めよう。
1935年3月8日、石垣島猪野田浜沖で小型のクジラが捕獲され、平坂は写真、骨格からコマッコウと同定した。平坂はマッコウクジラ科の小型種Kogia brevicepsとKogia simusは同一種の個体異変と見なしていたが、それに異を唱えたのが小川鼎三であった。複数の頭骨の比較から小川はbrevicepsとsimusは別種との結論を発表した。simusは今日では小川の名を冠した和名オガワコマッコウと呼ばれている(命名者は黒田長禮)。このエピソードを報じている平坂の弟子本間義治は「平坂先生は本邦産コマッコウ属鯨類の分類に、先駆的な研究を果たされ、しかもその論文が他の研究者によって取り上げられ、議論の対象にされたことは、その後の引用度が低いとしても、まずは良しとせねばなるまい」(本間義治『日本海のクジラたち』、考古堂書店、2003.9.1、p.61)と総括している。
平坂に反論した当時、小川は東北大学医学部解剖学教室助教授であったが、後に東京大学医学部に転じ教授となった。神谷敏郎は青山学院大学文学部教育学科卒業後、東京大学大学院に学び、1956年、医学部助手となり、1964年医学博士号取得、1971年、医学部解剖学教室の講師となった。解剖学の教授は小川(教授在任1944〜62)、細川宏(教授在任1962〜67)であった。この小川・細川時代で有名な話がヒマラヤの雪男研究である。先年「トリビアの泉」でも取り上げられた。
1950年代、ヒマラヤ登山隊が雪中の大きな足跡を発見し、全世界的にヒマラヤ雪男の存在がニュースとなった。これに反応して日本でも雪男存否の議論が起こり、東大医学部解剖教室内に「日本雪男研究グループ」が結成された。代表は小川鼎三教授、幹事細川宏助教授・神谷敏郎助手。毎日新聞社などの資金援助と、文部省・日本山岳会の後援で学術探検隊が組織され、ネパールでの海外調査が1959年12月から翌2月まで実施された。隊長は小川教授、副隊長林寿郎(元上野動物園園長、1912〜1986、帰国後『雪男 ヒマラヤ動物記』[毎日新聞社、1961.6.1]の著がある)、隊員は山崎英雄(比較動物学、後に札幌大学教授)、大塚博美(登山家、当時日本教育テレビ社員、1924〜)、依田孝喜(毎日新聞写真記者、〜1998)、尾崎陽一郎(毎日放送カメラマン)であった。ラマ教寺院に保存されていた「雪男の頭皮」の一部を日本に持ち帰ったが、動物名を特定するには至らなかった。神谷は「これらの調査は四〇年以上前のものであるから、毛については顕微鏡下の比較解剖学的研究が限界であった。現在であれば、毛一本についてのDNA分析からもち主の鑑定は容易であり、決定的な結論がでるだろう。しかし、ヒマラヤの僧院で信仰の一翼を担っている謎の「雪男」の正体は、神秘性を秘めたままいつまでも人々のあいだに生きていくべきなのかもしれない」(神谷敏郎『川に生きるイルカたち』、東京大学出版会、2004.4.16、p.13)と述べている。
東大の雪男研究は真摯なものだったろうが、今では何かトンデモ話のように思われてしまう。未知の生物発見はオカピやシーラカンスを先例としてcryptozoology(未知動物学、日本ではUMAと称される)の存在理由に挙げられるが、想像力の探求と思って楽しんでおこう。crypto-の付かないzoologyの分野での「Lost World」発見で最近(2006年2月)話題になったのは、インドネシア領ニューギニアで25の新種と希少動物の再確認があったことだ。日本の新聞社も各紙、写真付きで報じていた。新聞社は「未知の生物」が好きなのか、21世紀になっても朝日新聞は雪男イエティ探索隊の後援をしていた。近年、雪男の解明に精力的に取り組んでいる登山家の根深誠は、雪男の正体はチベットヒグマであると結論付けている。東大の雪男探検隊にも参加した大塚博美(第20代日本山岳会会長)が、1970年、エベレスト登山隊長として遠征したときにイエティの足を日本に持ち帰り小川に鑑定を依頼した結果、ヒグマのものだったというエピソードから導かれたものである。根深の調査について神谷は「彼は一〇年来雪男探索の旅を重ねているが、その正体はヒグマであると主張している」と述べ、大塚の弁として神谷が引用するのは「イエティは我々にとって唯一解けない謎だ。面白半分に受け止めないよう、実証的、科学的に調査を進めてほしい」という朝日新聞後援の高橋好輝(登山家、イエティ・プロジェクト・ジャパン代表)隊へのコメントである。雪男にかんする神谷のスタンスは、当事者として意義が損なわれないよう決定的なことは言わないようにするというものであった。神谷にとって1959〜60年のヒマラヤ遠征の意義は、雪男調査不成功の場合の第二案であったガンジスカワイルカの学術調査にある。
雪男学術調査で確証を得られなかった小川隊は1960年3月、ガンジスカワイルカの調査を行うこととなった。小川鼎三は人間の脳の解剖学者であったが、比較解剖学を展開し、陸水生の哺乳類の脳を自ら採集し研究した。始めは鰭脚類の脳を求め樺太海豹島、色丹、択捉島でアザラシ、オットセイ、トドの脳を採集した。さらに鯨類の脳へと進み、日本各地で研究資料を収集した。その中にコマッコウも複数あったのである。鯨類の標本をもとめ、小川の研究室から南氷洋捕鯨母船に研究者が派遣されていた。小川から教授職を継いだ細井宏は戦後再開された南氷洋捕鯨(1947〜48年漁期)に第一日進丸の船医として乗船している。神谷敏郎は1961〜62年の漁期に水産庁監督官として参加し、「鯨類の胆路についての比較解剖学的考察」と小型シロナガスクジラについて研究している。カワイルカは鯨類進化の研究に欠かせぬ位置を占めている。絶滅したムカシクジラ亜目から現世のヒゲクジラ・ハクジラ亜目は進化したと考えられているが、脳サイズの小さいカワイルカ類は古い形をとどめていると見なされている。
カワイルカ類はバイジー(Baiji)と呼ばれるヨウスコウカワイルカ、スースー(Susu)ことガンジスカワイルカ、ブーラン(Buhlaan)ことインダスカワイルカ、ボートー(Boto)ことアマゾンカワイルカ、フランシスカーナ(franciscana)ことラプラタカワイルカが現存種である。これら5つのカワイルカを種、科、上科でどう分類するかは研究者により様々な見解がある。日本語で比較的容易く参照できる文献には、粕谷俊雄編著『カワイルカの話 その過去・現在・未来』(鳥海書房、1997.1.31)と神谷敏郎『川に生きるイルカたち』(東京大学出版会、2004.4.16)があるので、詳しくはこれら二著をご覧いただきたい。ここでは主として神谷の著からの紹介となっている。
カワイルカは吻が長く、胸鰭が大きな淡水(ラプラタカワイルカは海の沿岸部に棲む)生活の小型イルカである。脳のサイズがマイルカ類より小さく、保育期間も短期で、社会構造も未発達であると考えられている。その生息数は少なく、絶滅の危機にあり、種の保存が課題となっている。東京大学は最初解剖学教室、細川教授の死後は海洋研究所の西脇昌治教授(1914〜1984)の指導のもと、何度かの海外調査を行ない、三冊の学術調査報告を出している。医学部の神谷、海洋研究所の粕谷は研究参加者であり、その後もカワイルカの研究・保護・啓蒙に従事してきた。
揚子江にはバイジーの他にスナメリも棲息している。スナメリは日本では海洋性であるが、海洋性のイルカが河川に住む例としてはカワゴンドウが有名である。形姿はシロイルカ=ベルーガに似ている。イラワジ、メコン、ガンジス、ブラマプトラ川に棲息し、英名をIrrawaddy dolphinという。川に住むからといってカワイルカの類ではなく、分類上はマイルカの類である。樋口英夫(1948〜)著『アンコール・ワット 旅の雑学ノート』(ダイヤモンド社、2001.4.20)にはコラム「人魚プサオの伝説」(pp.208〜209)がある。カンボジア、トンレ・サップ湖畔の村に伝えられている話は、蛇婿に呑み込まれた花嫁がプサオ=人魚に変身したというものである。蛇の腹中から助け出された娘は河畔で銀の小鉢(プテル)に水を汲み、髪に付いた粘液を洗い流していたが、小鉢を被るようにして川に身を投げてしまう。それ以後、この村ではプサオを見かけるようになったという。小鉢を載せたような丸い頭を持ち、背しか見せないカワゴンドウがプサオである。村の子供たちは大人から、プテルを被って遊んではいけない、プサオになってしまうと、注意される。
カワゴンドウは沿岸海域にも分布しオーストラリア北部海域にも分布している。アンソニー・マーティン編著、粕谷俊雄監訳『クジラ・イルカ大図鑑』(平凡社、1991.12.6)p.107には「カワゴンドウは泳ぎが遅く目立たない。生息範囲の一部を共有するジュゴンとのみ見誤る可能性があるが、背びれの有無によって区別することができる」と記述されている。また、同書はカンボジア・ベトナムの漁民がカワゴンドウを神聖視するとともに、魚を網に追い込むのにこのイルカを利用していると報じている。
東南アジアの人魚はヒンズー=インド文化の影響下にあると思われるが、まとまった研究を読んだことはなく、断片的な情報を持っているだけで報告するのも躊躇われるが、二、三書き付けておこう。安藤浩(1921〜)『切手に見るタイ』(文芸社、2001.3.15)には叙事詩「ラーマキヤン」に出てくる夜叉王と魚の娘スパンナマッチャー(スワンナマッチャー)が紹介されている。父夜叉王の命によりラーマ王子を妨害していたが、ハヌマーンの妻となった後は協力者となる人魚である(p.177)。タイの詩人スントーン・プー(1786〜1856)の長編物語「プラ・アパイマニー」(1870年、没後刊。2万4500行のタイ古典文学史上最大作)の一部分を絵本に表現した『スサコーン』(アンティ・アウル再話、ナリン・シャウピブーンキット絵、渡辺祥子訳、財団法人おはなしきゃらばんセンター、2005.5.30)には、王子アパイマニーと人魚の間に生まれたスサコーンが竜馬に乗って父親探しの旅に出るというものである。猿の武将ハヌマーンが人魚に恋するという「ラーマーヤナ」のエピソードはクメール(カンボジア)舞踊では有名なものらしい。踊り手は衣裳に魚尾を付ける。
平凡社東洋文庫『黄色い葉の精霊 インドシナ山岳民族誌』(フーゴー・アードルフ・ベルナツィーク、大林太良訳、1968.2.10)には、マライ半島西岸に住んでいたモーケン族の民話「人魚の起源」(p.49)が収められている。両親に反抗的な態度を示していたモーケン族の娘が精霊たちによって海に引きづり込まれ、ドゥユグンという生き物に変えられた。ドゥユングとは、半魚半女で、「身長三ないし四フィート、豊かな髪と魚のような尾と胸、性器そして女の声をもっていた」。この人魚を捕らえたいと思ったら、静かに歩かねばならないと言い、捕獲人に気付くと話しかけて逃げ去るとのことである。杉田秀明は「「ドゥユグン」とはすなわち「ジュゴン」(儒艮)の言語に相当するのだろう」としている。ジュゴンとなマレー語からの転用である。ベルナツィーク(Hugo Adolf Bernatzik、1897〜1953、オーストリアの民族学者)は続けて、ドィユグン=人魚が鮫に変じて、捕獲者を逆にむさぼり食ってしまう話を紹介している。
ヤン・ドゥ・フリース編、斎藤正雄訳、関敬吾監修『インドネシアの民話』(法政大学出版局、1984.9.5)にも人魚の話が収録されている。二人の姉に虐待されていた男が人魚を釣り上げる。ここでの人魚もジュゴンである。助命の願いを聞き入れた男に、人魚は用があればいつでも助けになると約束し、背に乗せて海の向こうの国に渡す。男が森で手折ったジャスミンの蕾が美女に変わり一緒に暮らし始める。美女に恋慕したこの国の君主は男に難題を課す。その一つに、濁流の中から澄んだ水を取ってくるという課題があったが、人魚の助力でこれも達成する。怒った君主は男を焼き殺すが、海水を灰に注ぐと、以前にも増して美しい姿で蘇った。それを見た君主とその妻は、自らの身を焼いたが、決して蘇らず、人魚を助けた若者が君主の座を継ぐこととなった。ハルマヘラ島北部のトベロ族の話である。
訳者の斎藤正雄は興味をそそられる人物である。明治28(1895)年東京生れ、早稲田大学英文科卒業後、報知新聞に入社。同人誌に参加し文学に志す。大正10(1921)年ジャワに渡り、翌年「ジャワ日報」社長となり、比較言語学、民俗学に興味を進める。昭和12(1937)年「東印度日報」社長となり、戦後の1946年帰国。以後も日本とインドネシアの文化交流に携わる。著書には詩集『未知の花』(文教書院、1922年)、『東印度の文化』(寶雲舎、1940)、『南海諸島の神話と伝説』(寶雲舎、1941)などがある。「ジャワ日報」は加藤朝鳥が創刊主筆を務めたバタビアの新聞で、朝鳥が妻の発病で帰国後、斎藤は主筆を務めた。
朝鳥は明治19年生れなので、9歳年少の早稲田英文科の後輩が斎藤である。
「SFマガジン」2006年2月号にジェイン・ヨーレン「マレーシアの人魚」(中村融訳、イラスト加藤龍勇。pp.228〜235)という短篇が載っていた。Jane Yoren, “Neptune Rising−Songs & Tales of the Undersea Folk”(1982)の最後から2番目に収められた(pp.137〜148)短篇(The Malaysian Mer)である。英国グリニッジの裏通りの店で骨董探しの名人スタンブリー夫人が見つけたものは「マレーシアの人魚」であった。「マレーシアの人魚」とは聞き慣れない言葉だが、我々には十分馴染みのある人魚のミイラのことである。ヨーレンはこう説明している。
もちろん、本物の人魚ではない。じつは、マレーシアの原住民が猿と魚からこしらえたまがいものだ。マレーシア人は猿を殺し、臍のところで上半身を切断すると、魚の尾に縫いつけたのだ。ミイラ化した遺骸は、そのあとヴィクトリア時代の無邪気な英国人水夫たちに売りつけられた。原住民はミイラを人魚と呼び、それを信じた若い船乗りたちは、人魚を故郷へ持ち帰り、愛する者たちにあたえたのである。(中村融訳)
値段は三百ポンド。6万円前後。スタンブリー夫人の夢想か、老店主の魔法か、夫人めがけて人魚が襲ってくる。骨董の目利きを自認する夫人と一癖或る店主との人魚をめぐる駆け引きの物語とも読めそうだが、中国や日本以外に、東南アジアも人魚ミイラの生産地と欧米では考えられている一端が窺えられて興味深かった。
『インドネシアの民話』には西イリアン、ヌフォル族の「海豚の婿入り(海豚の皮を着た若者)」という話も収められている(pp.234〜239)。前半は姉弟が母親と別れる話、後半は、成長した弟が領主の娘に求婚する話、と二部分に分かれた構成になっている。海豚の皮を着て化身した弟が求婚すると、領主の二人の姉娘は拒むが、末娘が応諾する。海豚が美しい青年だとわかると姉たちは婿を横取りしようとするが、今度は若者の拒否に合う。
恨んだ姉たちは若者を殺そうとするが、末娘の機転で助かる。夫婦はは新天地を求め舟で出発する、という内容である。
『インドネシアの民話』には190話が収録されているが、その中には「一つの手、一つの耳、一つの目、一つの足しかない」片側人間が8本の角を持つ牛を見つけ出してくる「片身人間の冒険」という興味深い話もある。
イルカとフォークロアの結びつきについては粕谷俊雄がアマゾンカワイルカに関して報告している。
アマゾンカワイルカが魅力的な男や女に姿をかえて、人間の異性を誘惑して河の中に誘い込むという民話がある。また、未婚の女性が妊娠してもカワイルカの子供だと称して社会に受け入れられるという習慣が流域にあるらしい。本種の油が喘息の薬に使われたり、目と生殖器の干物が異性を誘惑するためのお守りとされたりする例があると言われる。(『カワイルカの話』、p.48)
粕谷はまたペルーではアマゾンカワイルカは恐ろしい存在で、イルカの死体に触れると不幸な出来事が起こると信じられているとも報告している(p.66)。
毎日新聞の論説委員を務めた詩人緒方昇(1907〜)は釣りが趣味で釣号を釣禅堂魚仏と称したが、「魚仏のロッキング・チェア」という連載エッセイ中の第38話「人魚の声」に「人魚A」「人魚B」と題する詩を載せている。両詩の初出は「歴程」第137号(1970.2.1)で、以前にも紹介したことがあったが、「人魚B」には「このごろ、南米アマゾン産の川イルカを/人魚と称して/見世物の商売にする物がおる」との詩句がある。アマゾンカワイルカは鴨川シーワールドで16年間飼育されたことがあるので、そのことを言ったものだろうか。緒方の父は熊本県水産組合長をしていて、ジュゴンの塩漬け肉を家に持ち帰り、カレーライスにして食べたことがあったとも「人魚B」では詠っている。
東大のカワイルカ研究は当初、雪男学術研究から引き継いだ医学部解剖学教室が担っていた。神谷は予備調査で1966年3月、上野動物園長林寿郎の世話によりインドへ向かった。ガンジス川を2週間に渡り旅し、ガンジスカワイルカの全身骨格をパトナ大学から譲渡された。研究代表者は細川宏教授の死後、東大海洋研究所の西脇昌治教授に引き継がれ、1969年(東パキスタン=バングラデシュ・ネパール。ガンジズカワイルカ)、1972年(南米。ラプラタ・アマゾンカワイルカ)、1974年(パキスタン。インダスカワイルカ)、1981年(中国。ヨウスコウカワイルカ)と四次の海外学術調査が行われた。カワイルカの詳細については神谷、粕谷の書に当たられたい。
神谷はカワイルカ研究に従事していた時期の1980年、筑波大学医療技術短期大学部教授になった。カワイルカ研究代表の西脇昌治は東大定年後、琉球大学の教授となった(1975〜1980年)が、そこでカワイルカと同じく文部省の科学研究費による海外学術調査「海牛類の生活生態の把握と適応形態の対比に関する研究調査」の代表者になっている。神谷は1978年、オーストラリア東北部でジュゴン調査にあたった。海牛研究グループでは1980、81年、セネガル・ガーナ・ナイジェリアなどでアフリカマナティーの調査をしている。1970年代以降、日本では海牛類の研究、飼育、化石発掘など話題が豊富である。南氷洋の母船型捕鯨が動物保護から困難となると時期を同じくして、水生哺乳類の保護を前提にした研究が主流となっていった。戦前の台湾・パラオのジュゴン研究が途絶えた後、海牛類研究は再び進みはじめた。担い手は水族館で飼育に従事する人々と、西脇・神谷らの研究者、それと古生物学者である。
1960年代からのカイギュウ関連の国内の動きを見て行こう。
1960年12月6日
奄美大島笠利村喜瀬でジュゴン捕獲
1965年10月25日
伊良部島でジュゴン捕獲(それ以前、戦後は5頭のジュゴン捕獲があったという)
1965年8月
長野県戸隠村でダイカイギュウの肋骨化石発見。
1967年
北海道初山別村明里で、化石発見。1990年に、体内に胎児化石をもつカイギュウの全身骨格と判明。ショサンベツカイギュウ(メタクシテリウム、1200万年前、3.6m。胎児は1.5m)
1968年11月18日
南米スリナム産アメリカマナティー(オス2頭。タロー・ジロー)、よみうりランド海水水族館に搬入、飼育始まる(ジロー、1978年11月29日死亡)。
1968年12月17日
大分マリンパレスで、オーストラリア産ジュゴン(メス、125cm)、17日間飼育。
1969年4月12日
熱川バナナ・ワニ園でアマゾンマナティー1頭(オス)の飼育始まる。
1969年7月11日
アマゾンマナティー2頭(チビオス・チビメス)、よみうりランド海水水族館に搬入。チビメスは後マミーと命名、2002年10月6日の死亡時まで33年7ヶ月間飼育。
1970年7月
沖縄本島浦添貝塚からジュゴンの上腕骨出土。
1975年7〜9月
「西南太平洋島嶼部の漁撈民学術調査」隊(隊長藪内芳彦関西大学教授)、トレス海峡諸島で研究調査(ジュゴン漁)。
1975年9〜10月
沖縄海洋博記念公園水族館で、ジュゴンメス2頭(インドネシア、スラウェシ島で捕獲)、9月29日から22、23日間飼育。
1976年9月
下関水族館、パラオでシュゴンの捕獲を試みるが、不成功。
1976年
北海道本別町、本別川支流クンタルシプイ沢で、カイギュウの肋骨化石発見。
1977年5月20日
鳥羽水族館、フィリピン・ルソン島産ジュゴンメス1頭の飼育始める(じゅんこ。1985年6月17日、死亡。飼育8年1ヶ月。推定年齢9才)
1977年9月
鳥羽水族館、ジュゴンオス、17日間飼育。
1977年
「海牛 類の生活生態の把握と適応形態の対比に関する研究調査」研究班(研究代表者、西脇昌治琉球大学教授)発足。(1977年〜78年、第一次学術調査)
1978年4月30日
北海道北桧山町小川の中新統層よりジュゴン亜科の臼歯化石発見。
1978年5月1日
メキシコ政府より寄贈されたアメリカマナティーつがい(ユカタン、ユメコ)、沖縄海洋博記念水族館で飼育始まる。
1978年5月
神谷敏郎、オーストラリアで30日間ジュゴンを現地調査。同時期、鳥羽水族館でもオーストラリア・ジュゴン調査があり、共同で調査に当たった。
1978年8月上旬
小学生二人によりカイギュウの化石、最上川(山形県西村山郡大江町)で発見。ヤマガタダイカイギュウ(Dusisiren dewana。3.8m)。
1979年1月18日
沖縄県名護市で、165cmのメス幼獣ジュゴンが漁網にかかり保護される(沖縄海中公園で33日間飼育の後、死亡)。
1979年9月11日
鳥羽水族館、オスジュゴン(じゅんいち)の飼育始める。
1980年4月
鳥羽水族館、新設プールにオス、メスのジュゴンを同居させる。
1980年6月
北海道広島町からカイギュウの上腕骨、下顎骨、肋骨化石発掘。ステラーカイギュウ北広島標本。
1980年8月10日
北海道滝川市、空知川中洲で大型動物の化石骨発見。タキガワカイギュウ(Hydrodamalis spissus、500万年前、7m)
1980年11月
福島県耶麻郡高郷村(現、喜多方市)からカイギュウ目の肩甲骨化石発見。
1980年・1981年
文部省科学研究費によるアフリカマナティーの海外調査。
1982年8〜9月
北九州市若松区有毛の海岸で海牛類(ジュゴン科)の尾椎2個発見。
1982年9月5日
滝川市空知川河床の下部鮮新統層よりカイギュウ類(幼体)の肋骨発見。
1982年
福島県高郷村から、カイギュウのほぼ完全な頭骨化石発見。アイヅタカサトカイギュウ(Dusisiren takasatensis、3.7m、800万年前)。
1983年7月
北海道今金町で、カイギュウの体の前部1/3化石発見(翌年発掘)。ピリカカイギュウ(120万年前、推定8m)。
1984年
鳥羽水族館、雌雄のジュゴンを分離させる。
1986年10月
鳥羽水族館、150cmのメスジュゴン保護、飼育開始(セレナ)。
1987年4月5日
沖縄海洋博記念水族館で、アメリカマナティー双生仔誕生(父ユカタン、母メヒコ)。それぞれ5月8日、5月11日に死亡。
1987年5月23日
宮城県黒川郡富谷町明石でカイギュウの臼歯化石発見。
1987年9月
北海道沼田町、幌新太刀別川中流の河床からカイギュウ化石発見(この個体の一部の化石は1977年8月に採集されていた)。ヌマタカイギュウ、Dusisiren sp.。
1988年1月4日
沖縄県佐敷町の海岸にジュゴン死体漂着。
1988年7月12日
よみうりランド海水水族館に北京動物園より、北京生まれ(1982年3月1日)のオスのアメリカマナティーが贈られる。名は京生(ジンセン)。
1988年8月
北海道沼田町の幌新太刀別川河床からタキカワカイギュウ左側中位肋骨化石発見。
1990年4月26日
沖縄海洋博記念水族館でメスのアメリカマナティー誕生(ユメコ)。
1990年9月26日
宮城県黒川郡大和町でカイギュウの臼歯化石発見。
1991年4〜5月
群馬県安中市下秋間の秋間川で、海牛の肩甲骨、肋骨、椎骨化石発見。シモアキマカイギュウ。
1992年2月29日
屋島水族館、アメリカマナティー、オス(ベルグ、1989年12月15日、ドイツ、ニュルンベルグ動物園生れ)飼育開始。
1993年
北海道黒松内町熱郛でカイギュウの肋骨化石発見。
1994年6月30日
屋島水族館、アメリカマナティー、メス(ニール、1992年8月8日、ドイツ、ニュルンベルグ動物園生れ)飼育開始。
1994年
千葉県市原市の砂利採取所からステラーカイギュウの肋骨化石発見。
1995年
山形県戸沢村の鮭川の川べり地層で、海牛の肋骨化石発見。トザワカイギュウ。
1996年6月
鳥羽水族館、アフリカマナティーつがい(カナタ、ハルカ)飼育開始。
1999年4月1日
沖縄県東村字宮城にオスのジュゴン死体漂着。
1999年10〜11月/2000年8〜9月
静岡県掛川市上西郷で、海牛目の肋骨片産出。
2002年10月9日
熊本県牛深市茂串の砂浜にシュゴン死体(オス、2.6m)漂着(4日、牛深市魚貫町沖で定置網にかかり放された個体と思われる)。
2003年8月
札幌市南区の豊平川からダイカイギュウの肋骨4本、胸椎2個発見。サッポロカイギュウ(850万〜790万年前)。
1960年代末から70年代にカイギュウの飼育が各地の水族館で始められるようになるとともに、70年代後半からはカイギュウ化石が主に北日本で発見されるようになった。生態的、古生物学的研究が蓄積され、1989年末の神谷『人魚の博物誌 海獣学事始』で一般にもカイギュウ学の成果が知られるようになったのである。
神谷の著は5章に分かれ記述されているが、大きくは3つの部分から成っていると言えるだろう。最初は、想像上の人魚から生物としてのカイギュウ類へと進んだ東西の歴史。続いて、近代に絶滅したステラーカイギュウと日本の化石ダイカイギュウの説明。最期は専攻分野の解剖学からみたジュゴンの特徴と神谷のジュゴン研究の回顧と展望である。
人魚の興味から神谷の書を手に取った者には最初の部分「人魚学事始」こそが中心部分と言えよう。近代生物学で海牛類がどう認定されていったか、世界、日本について記述しつつ、それ以前の人魚についても一応触れているからである。人文的な研究である人魚の歴史は神谷の専門外であるので、新知識や興味ある記述は期待できない。日本の人魚に限って記述を追って行くと、「日本書紀」「古今著聞集」「和漢三才図会」「六物新志」を紹介し、明治以降は田中芳男訳のブロムメ『動物學 哺乳類』、岡田信利『日本動物総目録』、南方熊楠「人魚の話」、飯島魁『動物学提要』を取り上げる。正統な、骨格標本のような布陣である。文学やフォークロア、単行本ではない定期刊行物にはあまり興味を示してはいない。篤実な解剖学者としての節度をわきまえた選択をしている。
ブロムメ『動物学』については、同書にジュゴンのことを「ジュヨン」とあることを指摘し、「ジュゴンという語が広く本邦で親しまれるようになったのは、この《ジュヨン》に始じまり、ブロムメの『動物書』を通して海牛類についての理解が進んだことによる」と重要視している。ブロンメの書は1982年に恒和出版「江戸科学古典叢書」34として複刻されている。複刻本にはブロムメと同時期(明治7年)に刊行されたスロイス『斯魯斯氏講義動物学初篇』も収録されている。スロイスには「此等ノ次等草食ノ物ハ「シレ子ン」ナリ是皮膚ニ僅少ノ毛ヲ生シ臼歯ハ扁平冠ヲ有ス海濱ニ住シ「ウヰール」海草ノ類ヲ食ス之ニ属スル「ヂュトンフ」は印度海ニ住シ海牛ハ亜墨利加ノ海門ニ住ス」とある。スロイスは元オランダ陸軍一等軍医で、明治4年3月、金沢藩医学館に着任、多くの教科を教えつつ診療にも当り、雇用期間満了後の明治7年9月帰国している。医学館での講義を太田美濃里が筆記したのが「動物学初篇」である。これら二つの哺乳類についての教科書が、どの程度ジュゴンについて人々を啓蒙したかについては疑問が残る。
『日本動物総目録 有脊椎部』(金港堂本店、明治24年7月22日)の著者岡田信利(1857〜1932)について神谷は、「旧徳島藩士で、箕作麟祥について蘭学を学ぶ。東京大学動物学教室に籍をおいて研究活動を行なった明治時代の動物学者である」と述べている。岡田について触れている文章は、神谷の他は目にしたことがない。神谷は他の場所でも岡田の書について、「日本人の手になる最初の系統的な動物分類学書である。底本は大英博物館刊行の動物目録で、円口類から哺乳類までの脊椎動物全般にわたっての、本邦産脊椎動物の学名、和名および分布域が記載されている」と紹介している(神谷敏郎「海の哺乳類19−コロンブスの人魚」[「海洋と生物」第65号、1989.12.15、pp.4.72〜473])。ナメクジウヲからサルまで収録している全125頁のうち魚類が64p、両生類3p、爬虫類5p、鳥類42p、哺乳類11p、という構成になっている。CLASS MAMMALIA(哺乳類)はpp.115〜125で、ORDER SIRENIA(海牛目)、Family Manatidae(マナティー科)に Halicore(ジュゴン属)にdugongが記載されている。和名は「ザンオイヲ(沖縄方言)」、分布は「大島(薩摩) 沖縄諸島」と哺乳類の最初に位置している。次いでセミグジラなど12種のクジラ目が続いている。
カイギュウ目の現在の分類は西脇昌治(西脇昌治・神谷敏郎「海牛類について」[『世界の動物 分類と飼育〔奇蹄目・ハイラックス目・管歯目・海牛目〕』、東京動物園協会、1984.2.15、pp.114〜121])によると、プロラストミ科、原海牛科、ジュゴン科、マナティー科の4科があり、「大部分は絶滅」したとする。ジュゴン科は4亜科に分かれるが、ジュゴン亜科ジュゴン属のジュゴンのみが現生。マナティー科マナティー属にはアメリカマナティー、アマゾンマナティー、アフリカマナティーがいる。ジュゴン科ダイカイギュウ属のステラーカイギュウは1741年に発見されたが、その27年後の1768年に絶滅してしまった。
岡田『日本動物総目録』が刊行されたころは、水産学者が沖縄のジュゴンに注目していくつかの報告を行っていたことは、かつて触れたことがある。(例えば、「大日本水産會報」第162号[明治28年12月15日]p.73「儒艮の漁場」では西表島北岸、東岸が漁場として挙げられている。石垣島ではジュゴンの乾物が1斤、11、2銭で売られているとも伝えている。)その後明治40年の上野教育水族館での展示についても何度か書いてきた。明治40年になっても「ジュゴン」という言葉は生物学者以外にはあまり使われず、「人魚」「ザン」「海馬」などと沖縄での呼び名が用いられていたようである。
秋山蓮三編『哺乳動物』(嵩山房、明治36年10月1日)第廿七章は「海牛(マナタス)類」である。3行の総説と「儒艮」「海牛」(海牛とはマナティーのこと)の各説が述べられ、ジュゴン、マナティーの図が他書から転用されている。「儒艮」部分を引用しよう。
(九二)儒艮(琉球方言ザンノイヲ)(Halicore dugong)ハ英語ニDugongト称ス、其形魚ノ如ク、頭ハ圓ククシテ稍左右ヨリ抑壓セラレタルガ如キ状ヲナス、口邊ニ剛毛アリテ唇厚ク、鼻孔ハ鼻ノ前端ニアリテ瓣ヲ有シ、其目ハ最モ小サク、體ニハ短毛アレドモ殆ンド裸出セリ、牡ニアル門歯二枚ハ牙状ニ突出シ、牝ハ腋下ニ二個ノ乳房ヲ有ス、其幼児ニ哺乳スル際ハ、其児ヲ前肢ニ抱キ、児ノ頭ヲ自分ノ頭ト共ニ水上ニ出ス性質アリ、此獣ハ身長ケ八尺以上ニ達シ、後肢ナケレドモ、前肢ハ橈状ノ鰭トナル、常ニ群居シ海藻ヲ食ス、本邦ニテハ沖縄及ビ薩摩ノ大島近海ニ出没スレドモ、又紅海、印度洋、フリツピン近海、亜弗利加ノ東海岸、及ビ豪太利亜大陸ノ北海岸ニ産ス、其肉ハ食スベシ
神谷が紹介している飯島魁『動物學提要』は大正7年3月8日の発行である(大日本図書)。第十四門脊椎動物乙亜門有羊膜脊椎動物第六綱哺乳綱乙亜綱眞哺乳類乙部胎盤哺乳類第四目が海牛目Sireniaである(pp.926〜927)。第千八十五圖にBlainville氏圖 Halicore australis(現在の学名とは異なるオーストラリア産のジュゴン)の骨格が示されている。前半に骨格の説明があり、続いて「脳ハ比較的小ニ、表面ノ皺襞複雑ナラズ。睾丸ハ腹腔内ニ留マリ、乳嘴ハ一対胸ニ在り。子宮ハ雙角状胎盤ハ環帯状、非脱落性ナリ。」とあるが、それ以外の内臓についての記述はない。「本目ノ現世ニ在ルハ後記三属アルノミ」とし、「海牛 Manatus」「儒艮Halicore」「大海牛 Rhitina stelleri Retz」をあげ、「此ノ目ニ属スル化石種類ハ欧洲及ビ北米洲ノ第三紀地層ヨリシラレタル者尠ナカラズ」と化石にまで言及している。さらに「人魚ノ伝説或ハ此ノ類ト関係シテ起チタルカラン乎」とも述べている。
「儒艮」という言葉は飯島「動物學提要」刊行前後にはかなり普及していたと思われる。例えば、大正6年10月5日(第10巻第12号)発行『少女の友』(實業之日本社)pp.16〜18「海の中に棲む獣 〔附〕鯱と人魚の話」でも「儒艮」が語られている。
この他海獣に儒艮といふのがあります。属に人魚と云ふものですが、世間ではいふやうに半分人間の形をしてゐるわけではありません。唯、こゝに掲げた圖を見てもわかるとほり、頭が圓く、頬の肉はふくれて、顔の中央に鼻もあり、小さい口は可愛らしくて、その上肩が人間らしいので、泳いでゐる處を遠くから眺めると、十七八の少女のやうに見えるのであります。
10.東京日日新聞「人魚の養殖」
大正7年11月16日から25日に渡って「東京日日新聞」に連載された「人魚の養殖」(全9回)については一度紹介したことがあるが。「龍落子」(タツノオトシゴ?)の署名記事は以下のような見出しであった。
|
大正7年11月16日 |
5面 | 人魚の養殖(一)▽傳説の人魚(上) |
| 大正7年11月17日 | 5面 | 人魚の養殖(二)▽傳説の人魚(下) |
| 大正7年11月18日 | 3面 | 人魚の養殖(三)▽人魚の本體 |
| 大正7年11月19日 | 5面 | 人魚の養殖(四)▽人魚の種類 |
| 大正7年11月20日 | 5面 | 人魚の養殖(五)▽人魚の経済的價格(上) |
| 大正7年11月21日 | 5面 | 人魚の養殖(五)▽人魚の経済的價格(下) |
| 大正7年11月22日 | 5面 | 人魚の養殖(七)▽人魚は養殖し得るか |
| 大正7年11月23日 | 5面 | 人魚の養殖(九)▽日本の人魚(上) |
| 大正7年11月25日 | 3面 | 人魚の養殖(九)▽日本の人魚(下) |
回数の数字に錯誤があるが、紙面にあるままを記した。
1、2回目の「傳説の人魚」では、主に「和漢三才図会」と『廣文庫』より「廣大和本草別録」の記事を引用している。西洋のものとしてはヨハン・シュミットがニューファウンドランドの海岸で目撃した人魚の絵を指摘している。「顔といひ、手といひ、また尻尾といひ、「三才圖繪」の人魚の繪乃至は清心丹のビラ繪と非常によく似たものである」と「清心丹」を引き合いに出しているところが注目される。
「人魚の本體」では、人魚とは不思議の存在ではなく、動物学上は海牛類であると断定している。海牛類については、「體の形が細長くて大體魚のようになつては居るが、併し其處には背鰭も腹鰭もなく、尾鰭はある場合には海豚のやうにその先が二又に別れて居り、また或る場合には團扇のやうに圓くなつて居る。一對ある胸鰭は吾々人間などの手に當るものだ。鼻の穴は、鯨などとは異つて頭の前方に開き、一對の乳房が胸にある」と説明している。ジュゴンとマナティーの尾の違いを指摘している(団扇型がマナティー)が、乳房が胸にあるという部分は不正確である。乳は前肢(胸鰭)の付け根にある。更に説明は、海牛類が草食性で、陸に上がることはなく水中生活者であることを伝えている。
「人魚の種類」は海牛類分類に及ぶ部分であるが、かなり専門的な記述を含んでいる。「現今此地球上に生活して居る人魚の種類は、學問上唯下の二屬しかない」と言い、「マナツス」(マナテイー)「ハリコーレ」(ヂユゴン)について説明している。マナティーについては現在の和名(アメリカ、アマゾン、アフリカマナティー)を使わず、マナツス・ラテイロストリス、マナツス・イヌングイス、マナツス・セネガレンシスと当時の学名で呼んでいる。ジュゴンは2種としてオーストラリア沿岸に生息するものをハリコーレ・アウストラリス、それ以外の海域のものをハリコーレ・ヂユゴンとしている(現在では世界中のジュゴンは1種、Dugong dugonとされている)。後半では1768年に絶滅した「ステレルの海牛」について報じている。飯島魁『動物學提要』では、
◎大海牛 Rhitina stelleri Retz. ハ體長二丈餘ニ達シ無毛ナリ。此ノ巨大ナル奇獣ハ十八世紀中ハホべーりんぐ海ニ棲息シタル者ナルガ其ノ後ハ亡滅セリ。
と簡単に触れられているが、「龍落子」は発見の経緯と滅亡の原因を簡潔にまとめている。
前に現存の人魚の種類が唯二屬であることを云つたが、其外に今一つ、比較的近年(一七六八年頃)に至つて絶滅種となつた「リチナ」(Rhittina)といふ屬がある此人魚は前掲の二屬の者よりは形が餘程大きく、體長廿乃至廿五呎(フィート)に及び、ベーリング海のベーリング島やコツパー島附近に棲んで居たもので、西暦千七百四十一年の冬、かの有名な露國海軍の探検家ベーリングが、獨逸の博物学者ステレルと共に、北米アラスカ沿岸の帰路、逆風に遭ひ遂に難破漂着した折發見されたものである。漂着した船員達は、殆ど十箇月も此「リチナ」の肉を食つて生活して居た。
ステレルは詳細に此人魚を記載して學界へ紹介したそれ故此人魚は俗に「ステレルの海牛 」(“Stelleris sea-Cow”)と呼ばれて居る今欧州の博物館にある「リチナ」の標本は何れも部分的なもので、完全なものはない。又「リチナ」は、前にも云つたやうに、ステレルの發見後程なく(今から百五十年ばかり前に)絶滅して、地球の表面から消え失せたから、ステレルの前記の報告は、學問上大變に大切なものとなつて居る。
尚此人魚は、ベーリング等がコツパー島地方へ漂着した折は、其附近の海に海草などを食つて、無數に群をなして生活して居たが、其澤山ある肉が非常に美味であつたのみならず、脂肪も皮も皆役に立ち、その上性質が餘り敏捷であく、且人に怖れなかつたから、漂流船員の永い間の食糧となつた外に、又スレレルの報告を聞いて、其後その地方へ押しかけて行つた無數の強慾な鯨猟師に忽ち狩り盡されて、遂に全く絶滅されるやうな運命に立ち至つたのである。
ステラーカイギュウはドードーとともに絶滅生物の中でも有名な種であるが、大正時代の紹介記事は珍しいので長く引用した。
この新聞連載記事の題名「人魚の養殖」の意味するところは、当時アメリカで主唱されていたマナティーの繁殖保護と養殖から発想されたものである。アメリカのフロリダでの保護活動は、資源利用のためではないが、「龍落子」は食糧、皮革利用なども視野に入れて論を進めている。そこで海牛類の経済価値として美味な肉と共に皮膚、脂肪層を指摘している。皮膚は紅海沿岸では屋根葺きに用い、カムチャツカではステラーカイギュウの皮で舟を造ったという。脂は肝油の代用としての薬用と燈火用に供された。アメリカマナティーの食草は優秀な牧草になると書いているが、それではマナティーの保護とは言えないだろう。フロリダでは1907年5月に制定した法律でマナティーを捕獲した者は500ドルの罰金が科されるようになったと伝えているのだから、人間のための養殖を意図しているわけではなかろう。養殖の実例として、ハイチのサント・ドミンゴの湖水で一匹のマナティーが26年間飼育されたことがあると書いている。野菜は勿論、パンでも食べると記している。大正時代に不確かなものとしても飼育について言及していることにも注目される。
連載の最期の二回は沖縄地方のジュゴン=ザンを明治時代の文献(松原新之助、黒岩恒)を引用して紹介している。ジュゴンの現状についての情報は手元になかった思われ、「若し讀者諸君の中に、琉球地方の「儒艮」の現状に就て正確な知識をお持ちになつて居られる方があつてそれを筆者の許までお知らせ下さるならば、甚だ仕合せに存じます」の一文が最後に添えられている。「龍落子」も結局は「今に於て何等か適當の方法を講じないならば、日本の「儒艮」も、かのベーリング海の「リチナ」同様、早晩絶滅の運命を免れぬであらう」と自然保護を訴えている。
さて「龍落子」とは誰であろう。自然保護と同時に資源としての意識を持っている、正確な生物の知識を身に付けている、松原新之助を多く引用している、これらの点から水産学者ではないかと見当を付けてみた。そこで思い出すのは農商務省水産局の能澤鱗である。能澤は「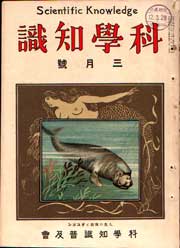 科學知識」大正12年3月号に「人魚の傳説と其正體」(pp.70〜76)を発表している。決め手はないのだが、『廣文庫』記載の人魚文献の利用、清心丹への言及、紅海の儒艮の皮の利用の指摘など重なる部分が目につく。紹介資料が重複しない部分もあり、能澤の文には保護・飼育という視点がないなど大きな相違もある。また能澤はジュゴンを三種に分類しているという齟齬もある。紅海に棲むジュゴンを別種としているのである。分類の問題は依拠する文献の違いと言っても良いだろう。他に思い当たる人物がいないので、候補者として能澤鱗を指摘しておく。
科學知識」大正12年3月号に「人魚の傳説と其正體」(pp.70〜76)を発表している。決め手はないのだが、『廣文庫』記載の人魚文献の利用、清心丹への言及、紅海の儒艮の皮の利用の指摘など重なる部分が目につく。紹介資料が重複しない部分もあり、能澤の文には保護・飼育という視点がないなど大きな相違もある。また能澤はジュゴンを三種に分類しているという齟齬もある。紅海に棲むジュゴンを別種としているのである。分類の問題は依拠する文献の違いと言っても良いだろう。他に思い当たる人物がいないので、候補者として能澤鱗を指摘しておく。
能澤鱗についても断片的なことしか知るところがない。能澤鱗は筆名、本名は能澤捨次。著書に『生物ローマンス(海の巻)』(新光社、大正13年6月20日)、『ろばにおわれたくま』(宝雲舎、昭和23年)があり、初期の雑誌「新青年」(第1巻第7号、第3巻第9号)にも執筆している。『生物ローマンス』は「故有島武郎先生に捧ぐ」と献辞があり、生前に送られた有島の書簡が序文に代えて掲げられている。能澤は明治40年の春、水産学専攻の目的で札幌農学校に赴いた。札幌農学校はその年の9月、創設された東北帝国大学の農科大学となった(その後、大正7年4月には北海道帝国大学となる)。有島武郎は札幌農学校出身で、能澤の入学時(有島は明治40年12月赴任)、英語と実践道徳を受け持つとともに、同窓会誌「文武會會報」の編輯部長を務めていた。能澤は練習船忍路丸での実習航海の日記を「文武會會報」上に発表していたという。現在北海道大学附属図書館には大正2年夏の能澤の水産学漁撈部第3年級生徒引率記録「オコツク海漁撈實習記念」と題された手稿が残されている。能澤は母校の教師となっていたものと思われる。
能澤と同時期、札幌農学校で学び、有島と交わっていた者に科学ジャーナリスト原田三夫(1890〜1977)がいる。原田は愛知一中(小酒井不木と同級)卒業後、札幌農学校に入学(明治40年=能澤と同級と思われる)したが中退。八高を経て東京帝国大学理学部植物学科を卒業し、東京府立一中、北海道帝国大学水産学専門部の教師となっている。原田は大正6年「子供と科学」、大正12年「科学画報」、大正13年「子供の科学」と、科学雑誌を創刊するが、科學知識普及會(京橋区木挽町4ノ9)の雑誌「科學知識」の創刊にも関係している。能澤が「人魚の傳説と其正體」を掲載した雑誌である。もっとも創刊後の内紛で原田は「科學知識」を去り、新光社から「科学画報」を出すこととなった。その新光社が『生物ローマンス』の版元であり、「科学画報」子供版とも言うべき「子供と科学」は誠文堂が発行所であった。昭和10年、誠文堂は新光社を吸収合併して、現在の誠文堂新光社となっている。能澤鱗と原田三夫は重ねる部分が多くあるように思える。
『生物ローマンス』は新光社(四谷区左門町55)の「趣味の科学叢書」の一冊で、全355頁、定価2円30銭。箱入り、恩地孝四郎装幀。「海の哺乳動物」「海の鳥」「海の爬蟲類」「海の魚類」「海の甲殻類」「海の軟体動物」「海の棘皮動物」「海の腔腸動物」「海綿動物」「海草」の部分からなっている。最初の「海の哺乳動物」は「鯨の髭」「人魚の傳説」「人魚の正體」の3つが収められている。雑誌掲載の「人魚の傳説と其正體」が二つに分かたれているが、文章は順序の入れ替えはあるが、ほぼ同じである。雑誌には岩に手をつく人魚の挿絵が添えられているが、単行本には「傳説の人魚」と題された谷崎「人魚の嘆き」風の挿絵とジュゴン、オットセイの群れの写真が挟まれている。
新光社は明治末期から出版を始めた模様だが、大正になると「西洋講談」「支那哲学叢書」「心霊問題叢書」などを刊行し、大泉黒石「老子」(大正11)、加藤朝鳥「爪哇の旅」(大正11)「十字軍」(大正12)などの版元となっている。「趣味の科學叢書」には他に原田三夫『山の科學』『海の科學』『星の科學』『地震の科學』、石井重美『世界の終り』、古川龍城『星のローマンス』『月の科學』(古川は東京天文台の技師。もと僧侶。)、村林仁八『遺傳の科學』、渡邊十千郎『風景の科學』、小熊虎之助『心霊現象の科學』などがあった。新光社については原田三夫が『思い出の七十年』(誠文堂新光社、昭和41年3月25日)で触れている。
そのころ(大正11年−引用者注)麹町の半蔵門近くに、新光社という出版社があった。満州で新聞をかっていた立川雷平という豪放な男が資本を出し、仲摩照久という作家崩れが専務をやっていた。仲摩はその前に京橋区の桜橋あたりで「美人画報」や「飛行少年」をやっていた。新光社では「世界少年」を出し、大泉黒石の「老子」、友松円諦の釈迦の戯曲、椎尾弁匡の宗教書など、仏教、思想関係のものも出版していたが、科学物に目をつけて私に書かせようとした。(p.232)
昭和になると新光社は『日本地理風俗大系』(全19巻、昭和4〜7年)『世界地理風俗大系』(全26巻、昭和3〜7年)『世界文化史大系』『万有科学大系』(正続全30巻、昭和6〜8年)などを継続的に出版していたが、昭和10年、小川菊松の誠文堂に吸収合併された。現在に続く誠文堂新光社である。小川について原田三夫は、
東京の本郷に古くから至誠堂という大書店があって、出版も小売もやっていたが、そこの小僧の一人は目から鼻へぬけるような利巧もので、勤勉でもあり顔付もかんじがよかったので、皆に可愛がられたが、誠の一字をもらい誠文堂として独立し、神田錦町の小さな店で専ら出版を始めた。かれは女遊びが好きであったが、非常な精力家であった。数点の書で手ならしができたところで、早稲田の文科を出た加藤美侖と相談して、加藤が執筆、命名した「是丈は心得おくべし」という叢書二十五巻を出版したが、これが物すごく当った。その小僧上りが、のちの誠文堂新光社の社長、会長であった小川菊松である。(原田『思い出の七十年』、pp.176〜177)
能澤のもう一つの著作は、いろは科学童話集『ろばにおわれたくま』(寶雲舎、昭和23年10月15日)である。『生物ローマンス』から随分年月がたっているが、能澤自身の「本書の創作について」を読むと、23、4年前にまとまっていたが、適当な挿絵画家が得られなかっため手元に置かれていたことが分かる。その時序文を石川千代松(1861〜1935)から得ていたが、日暮里で戦災に遭い失ってしまったという。そこで今回の「序」は石川の女婿寺尾新(1887〜、理学博士、生物学者、水産講習所教授)が書いている。寺尾は、「能澤さんは水産の専門家であり、また或る工業会社の工場長でもある。官吏としての経験もあれば、油にまみれて機械と取組む経験も積んでおられる」と書き出している。寺尾の言から、能澤には「さかなのおくら」という著作もあることがわかった。
『ろばにおわれたくま』は、「いろは」47文字を頭文字とする生物を主人公とする物語に絵を添えて、文字と科学知識を楽しく覚えさせようとの意図のもと試みられたものである。能澤の幼い娘への愛からの企画でもあったが、出版された時には、娘は小学校の教員となっていた。「いろは」順の物語の題名は次の通りである。
| いすかのはしいかのくちばし | pp.1〜3 |
| ろばにおわれたくまのはなし | pp.3〜6 |
| はりねずみとねずみ | pp.6〜9 |
| にわとりのやくそく | pp.9〜11 |
| ほたるのしんごう | pp.11〜13 |
| へいけがに | pp.13〜14 |
| とびうお | pp.14〜17 |
| ちどりとあほうどり | pp.17〜19 |
| りすとふくろう | pp.19〜21 |
| ぬえたいじ | pp.22〜25 |
| るりのとり | pp.25〜28 |
| おしどりとつる | pp.28〜31 |
| わさびとしょうが | pp.31〜32 |
| かにのあし | pp.32〜34 |
| よしのあなから天のぞく | pp.34〜36 |
| たかとすゞめ | pp.36〜39 |
| れんこん | pp.39〜41 |
| そらまめとらっかせい | pp.41〜44 |
| つばめのす | pp.44〜47 |
| ねむの木 | pp.47〜48 |
| ながにしのあさん | pp.49〜51 |
| らくだと馬 | pp.52〜54 |
| むささびのひこう | pp.54〜59 |
| うぐいすとうさぎ | pp.59〜61 |
| いのしゝとぶた | pp.62〜64 |
| のこぎりざめとつちくじら | pp.64〜66 |
| おたまじゃくしのしゅっせ | pp.67〜70 |
| くしゃくのじまん | pp.70〜72 |
| やつめうなぎ | pp.72〜73 |
| まつとしたくさ | pp.74〜76 |
| けしつぶ | pp.76〜79 |
| ふきのはなし | pp.79〜83 |
| こい | pp.83〜85 |
| えびのなかま | pp.85〜88 |
| てながざる | pp.88〜91 |
| あさがおとお日さま | pp.91〜94 |
| さるの木のぼりきょうそう | pp.94〜99 |
| きじとあおだいしょう | pp.99〜101 |
| ゆずりはとだいだい | pp.101〜104 |
| めだかのてがら | pp.105〜107 |
| みつばちとちょうちょ | pp.108〜110 |
| ししのおやこ | pp.110〜112 |
| えんどうのつる | pp.112〜114 |
| ひばりうた | pp.114〜117 |
| もずのにえさし | pp.117〜119 |
| せみとり | pp.119〜123 |
| すすめはおどる | pp.123〜125 |
pp.127〜147は「引用動植物の解説−父兄母姉の方々に−」と題して生物学的説明が話柄事になされている。題名となった「ろばにおわれたくま」という話は、熊に襲われた子供の驢馬が大声で親に助けを求め、親は大勢の仲間に助力を請い、多勢に無勢で熊は逃げだし、最後は「ろばはよわいものですから、いつも大ぜいでゐ一しょにあつまっていることにきめました」と結ばれている。表紙は赤地で木に隠れている熊(洋服を着ている)が描かれている。著者名はひらがなで「のざわ・りん」。裏表紙には草をはむ驢馬の絵がある。画家は古山弘(1907〜1977)で、定価は80円であった。
「のこぎりざめとつちくじら」は大工道具や楽器の名に関連した海の生物が多数登場する話である。
のこぎりざめはかわった魚で、頭の前の方に、大きな長い鋸をつき出して、海の中をおよぎまわっているものです。
ある日、のこぎりざめがつちくぢらに出あいました。つじくぢらはまた、頭が才槌のような恰好をしているのでそういうのです。二ひきは鋸と才槌を持っているので、海の中の大工さん仲間です。
のこぎりざめが、私達はこの海の中の大工だから、一つ石持さんに石をだしてもらって、石垣鯛さんにたのんで石垣をきずき、簾貝だの錐貝だの、いろいろの大工や建具の仲間をあつめて、りっぱな家を建てようじゃありませんかといいました。
つちくぢらは、「それはいゝ考えだ。この海の中に大きなお家をたてゝ、みんながあつまるとおもしろいぞ」と話しているところへ、神楽鮫がやって来ました。二ひきは神楽鮫にもこの話をすると、「海の大工さん仲間で、うんとりっぱな家をたてゝ下さい。みんなよろこびますよ。そのお祝いには、私の仲間が大神楽を上げましょう。そして笛吹鯛さんや三味線貝、喇叭海膽などにも来てもらって、にぎやかにお祝いしようぢゃありませんか」といって大さんせいです。
さて、海の中にどんなお家がたちましょう。
それこそ昔話の龍宮のようなきれいな御殿がたちましょう。
『ろばにおわれたくま』の出版元は寶雲舎(中央区銀座4ノ2)であった。発行者は小池又一郎。寶雲舎は戦前、小野賢一郎の出版社として知られていた。小野賢一郎の名は今日では蘭郁二郎の義父(小野は蘭の母の再婚相手)として言及されるのみであるが、著名なジャーナリスト、俳人、陶器愛好家であった。小野は明治21(1888)年7月2日、福岡県生まれ。小学校教員を経て、新聞記者となり、大正13年9月、東京日日新聞社会部長兼事業部長に就任している。編集顧問を経て(昭和7年12月、東京日日新聞退社)、昭和9年には日本放送協会参事兼業務局文芸部長になる。大正初年から東京日日新聞に小説や署名記事を発表していて、当時台頭してきた「新しい女」(文学・演劇上の主人公から女優・作家などの現実の存在へと変化したフェミニズム運動の発現)とも接触を持っていた。昭和期には俳誌(「虎杖」→「鶏頭陣」)や陶器趣味の雑誌(「茶わん」→「古美術」)を創刊するなど通人として知られていた。雑誌「茶わん」(昭和6年3月創刊)の発行元が寶雲舎であり、蘭郁二郎(遠藤敏夫)は昭和7年5月号から編集発行人になっている(後、小池又一郎に交替)。蘭郁二郎の研究家会津新吾は蘭が昭和19年い亡くなったときの肩書きは「寶雲舎常務取締役兼編集長」で、社葬が行われたと述べている。小野は寶雲舎から『陶器大辞典』など陶器関係のものや随筆などを出版し、昭和18(1943)年2月1日、55歳でなくなっている。『陶器大辞典』や『陶器全集』の出版費用は自己の所持品を処分するなどして捻出し、妥協を許さぬ仕事振りであった。小野、蘭亡き後の寶雲舎は小池又一郎が受け継ぎ、戦後も盛んに出版活動をしていたが、「茶わん」昭和25年11月号以降、活動の跡は窺うことができない。また、能澤鱗のその後も不明である。
神谷敏郎『人魚の博物誌』第一章「人魚学事始」の記述から明治、大正のジュゴン研究を辿り、神谷が触れていない新聞記事、能澤鱗の業績を補足してみた。神谷第二章は「大海牛」である。1768年以降絶滅したと考えられているステラーカイギュウ、1960年代後半以降、日本各地で発見されたカイギュウ化石を中心に語られている。ステラーカイギュウについては「龍落子」による東京日日新聞紙上の記事を引用したので、発見と絶滅の大まかな経過はお分かりいただいたことであろう。
ステラーカイギュウは発見と絶滅の経緯が劇的であることと、その巨大さで今でもドードー同様多くの人の興味を繋いでいる。児童書の分野でも、ページを開けば、ステラーカイギュウの姿に再会できる。
『ドードーを知っていますか−わすれられた動物たち−』、ショーン・ライス絵、ポール・ライス/ピーター・メアリー作、斉藤たける訳、福武書店、1982.10.10、pp.7〜8「ステラーカイギュウ・メガネウ」
『巨大生物図鑑』、デイビッド・ピーターズ作、小畠郁生監修、偕成社、1987、pp.70〜71「ステラ海牛」
『帰ってこない動物たち 人間が絶滅させた動物たちの記録』、黒川光広作、今泉忠明監修、ポプラ社、1994.4、pp.6〜7「ステラー海牛 」、pp.20〜21「殺されるままだったステラー海牛」
『世界の絶滅動物 人類が滅ぼした動物たち』、黒川光広、童心社、1995.7.20、pp.6〜7/pp.38〜39「ステラー海牛 」
『ドードー であえたはずのどうぶつたち』、倉科昌高、ピエ・ブックス、2005.12.25、「ステラーカイギュウ」
漫画では星野之宣「罪の島」で、現代に人為的に再生させたステラーカイギュウを扱っているが、1960年代にステラーカイギュウが生存しているのではないかというニュースが流れたことがあった。例えば、東京動物園協会発行の「どうぶつと動物園」第17巻第7号(1965.7.1)p.12「海外だより」には「オオカイギュウの再発見」として「1962年になって、ソ連の捕鯨家が、ケープナヴァリンふきんで、6頭のオオカイギュウを発見したのです。6頭以上いるかもしれないが、数がふえて昔のようになるかどうかは、なお疑問だとされています」とある。翌年10月の同誌には西脇昌治「北太平洋にいる珍しい海牛類」(「動物だんわ室〔22〕」、p.2)と題したコラムが載った。
1962年7月にソ連の捕鯨船Buran号に乗って海洋観測をしていた科学者達が、ベーリング海のナワリン岬付近で約6頭の見たこともない不思議な動物の群を発見したのです。これはステラー大海牛 (Rhytina stelleri)だと思われるというのです。(中略)ソ連の科学者達は、この大海牛が冬も結氷しないナワリン岬付近のどこかで生き残っていた可能性は充分あるといっているのです。しかしこのことは目撃の報告だけで、証拠となる写真とか標本とかがないので、真疑のほどはまだ不明といわねばなりますまい。もしこのことが事実だとすればなんと喜ばしいニュースではありませんか。
西脇1968年2月の「どうぶつと動物園」では、「最近、私の所にきたソ連の哺乳動物学者ソコロフ博士の言によると、ソ連においても、この報告は、恐らく何かの間違いであったのではないかと考えられているそうです」とトーンダウンしている。それでもやはり「どこかで細々と繁殖しており、それが見つかったするならば誠に喜ばしいことではありませんか」と希望をもって文を終えている(p.15)。西脇はステラーカイギュウ生存の可能性に継続的に興味を示し、絶筆とも言える「ジュゴンの話」(『全集日本動物誌30』、講談社、1984.10.10、pp.3〜52)の最後でもステラーカイギュウに言及している。1962年に目撃した科学者はベルツイン博士であったこと、1974年、モスクワで開催された第一回国際哺乳動物学会議で会ったベルツイン博士は大海牛生存の可能性を強調していたこと、1979年に再会した博士は生存説を捨てていたことを報告している。「再発見と思われた年以来十七年を経過しており、そのときベルツイン博士ははじめて残念そうに、ステラー海牛は絶滅したものと考えるに至ったと結論しました」。
西脇の近くにいた神谷敏郎も「近年(1962)になって、ベーリング海で操業中のソ連の捕鯨船によって大海牛 が再発見されたという報告があったが、その後これは誤報であったことが、ソ連の海洋学者によってたしかめられている」(神谷「人魚の正体−ジュゴンの生物学−」[「自然」第35巻第6号、1980.6、pp.45〜53]p.48)と述べている。
現在、地球上に棲息するカイギュウ類はジュゴン科のジュゴン、マナティー科の3種のマナティーのみである。マナティーは大西洋と、そこに注ぐ淡水域、ジュゴンはインド洋・西部太平洋と、棲み分けがきっちりできているが、新生代全体を見渡せば多くの化石種がいたことがわかっている。2006年2月23日の各新聞はニホンウナギの産卵場がついに突き止められたことを報じたが、前日および同日には、札幌で発見されていたカイギュウ化石がヒドロダマリス属の最古のものであることがわかったことを新聞は伝えている。河北新報は「市博物館活動センターの古沢仁学芸員によると、海牛類には21の属があるが、ヒドロダマリス属としては世界最古という」と述べている。ヒドロダマリスとはステラーカイギュウがぞくするダイカイギュウ属をいう。札幌の化石はおよそ820万年前(790万年前から850万年前)という測定結果が出た。それでは他の属、およびカイギュウの分類はどうなっているかというと、残念であるが正確な知識を持ち合わせているわけではない。日本のカイギュウ化石については近年、古沢仁が中心となって研究が進められ、各採集地点の調査報告書も出されるなど活況を呈しているようである。カイギュウによる町おこし、観光の中心にもなっている。
ヒドロダマリスHydrodamalisはカイギュウ目Sireniaジュゴン科DugongidaeのHydrodamalinae亜科の属名で、有名なステラーカイギュウはHydrodamalis gigas(かつてはRhytina gigasも用いられた)の学名を持つ。800万年前は新生代第三紀中新世(2500万年前〜500万年前)の末期で、カイギュウの進化では比較的新しい属である。『絶滅哺乳類図鑑』(冨田幸光・伊藤丙雄・岡本泰子、丸善、2002.3.20)p.127には「カイギュウ類の系統図」があり参考になる。図示されている種にはミオシーレン(ジュゴン科ミオシーレン亜科、中新世。群馬県立自然史博物館でその骨格を見ることができる)、ステラーカイギュウ(更新世〜現世)がある。同図鑑の「カイギュウ類」の説明では最古の化石は始新世中期で、現世種にかなり近い形態をしているとあるが、2001年10月に、四つ足をもつカイギュウ類の化石がジャマイカで発見されたとナショナル・ジオグラフィック・ニュースは報じている(Pezosiren portelli Domning)。5000万年前というから始新世(5500万年前〜3800万年前)初期のものである。新生代は6500万年前から始まるので、1000万年ほどの間に海牛類の祖先は海に回帰したようである。始新世ではプロラストムス、プロトシーレン、エオテロイデス、プロトテリウムという属が、次の漸新世(3800万年前〜2500万年前)ではハリテリウム、カリボシーレン、アノモテリウム、リティオドゥスという属が存在した。中新世(2500万年前〜500万年前)はカイギュウ類が最も繁栄した時代である。漸新世から続くハリテリウム、カリボシーレン、アノモテリウム、リティオドゥスの他に、メタクシテリウム、ヘスペロシーレン、タラトシーレン、プロハリコア、ミオシーレン、シレノテリウム、、ポタモシーレンという属が加わったが、鮮新世(500万年前〜200万年前)になるとメタクシテリウム、リボドン、ヒドロダマリスの3属になってしまう。第四紀ではリボドン、ヒドロダマリス、ジュゴン、マナティーの属があり。現在はジュゴンとマナティーのみが生存している。『絶滅哺乳類図鑑』は、「進化史上あまり繁栄しなかったことは、アマモ類の分布と盛衰に深く関係していたからである」とのべているが、ヒドロダマリスはコンブなどの海草を餌として北の海に生息地を求めていた。
カイギュウ目が4科に分類されることを西脇昌治が記述しているとは先に述べた。その4科とはプロラストムス科(Prorastomidae)、プロトシーレン科(Protosirenidae、西脇は原海牛科と訳している)、ジュゴン科(dugongidae)、マナティー科(Trichechidae)である。プロラストムス科には最古の四つ足カイギュウ、ペゾシーレン(Pezosiren)も含まれる。ジュゴン科はジュゴン亜科(Dugonginae)、ヒドロダマリス(ダイカイギュウ)亜科(Hydorodamalinae)、ハリテリウム亜科(Halitheriinae)、メタクシテリウム亜科(Metaxytheriinae)の4亜科に分類される。分類は学者によって異なる場合があり、ジュゴン科を9亜科に分けることもあるようだ。ジュゴン科の属はエオテロイデス、プロトテリウム、ハリテリウム、エオシーレン、カリボシーレン、メタクシテリウム(以上ハリテリウム亜科)、クレナトシーレン、ジュゴン、ディオプロテリウム、ゼノシーレン、コリストシーレン、リティオドゥス、バーラティシーレン(以上ジュゴン亜科)、ドゥシシーレン、ヒドロダマリス(以上ヒドロダマリス亜科)、アノモテリウム、リティオドゥス、、ヘスペロシーレン、タラトシーレン、プロハリコア、ミオシーレン、がある。マナティー科にはマナティー、シレノテリウム、ポタモシーレン、リボドンの属がある。ただし、ミオシーレンをマナティー科に分類する学者もいる。種としては現在、50種が記載されている。
日本の化石カイギュウの多くはヒドロダマリス亜科である。ヒドロダマリス亜科はヒドロダマリス属とドゥシシーレン属に別れる。サッポロカイギュウがヒドロダマリス属では世界最古と考えられているが、ヤマガタダイカイギュウ(Dusisiren dewana)、アイヅタカサトカイギュウ(Dusisiren takasatensis) 、サッポロカイギュウ、タキカワカイギュウ(Hydorodamalis spissa)、ピリカカイギュウ、ステラーカイギュウの時代順になるようである。これは日本を中心とした西太平洋のダイカイギュウであるが、カリフォルニアを中心とした東太平洋でも、ドゥシシーレンからヒドロダマリスへという化石カイギュウが発見されている。進化の正確な記述は古沢仁「北太平洋海牛類(ヒドロダマリス亜科:Hydorodamalinae)の進化と古環境」(「化石」第77号、2005.3.25、pp.29〜33)を参照されたい。また、カイギュウ化石を含む特別展図録、「大海牛 ・大鯨展−海で進化する哺乳類−」(山形県立博物館、2000.9.22)や「クビナガリュウからステラーカイギュウ−化石にみる世界の海」(北海道開拓記念館、1997.7.11)も参考になる。勿論、調査報告書は重要である。「シモアキマカイギュウ発掘調査報告書」(群馬県安中市教育委員会、1993.3.31)、「美利河産海牛化石発掘調査報告書」(美利河海牛 化石調査研究委員会/北海道今金町教育委員会、1992.3..31)、「タキカワカイギュウ調査研究報告書」(タキカワカイギュウ関連地質調査団/滝川市教育委員会、1984.3)、「ヤマガタダイカイギュウ発掘調査報告書」(山形県立博物館、1983.3)、「山形県戸沢村産海牛 化石調査報告書」(山形県立博物館、1998.3)。タキカワカイギュウには「タキカワカイギュウの研究」(古沢仁、滝川市美術自然史館、1989.3)、ピリカカイギュウには「太古からの使者ピリカカイギュウ」(今金町教育委員会、1998.7)もある。
ステラーカイギュウは歯と指骨が退化し認められないが、ドゥシシーレンは歯を保有し指骨も認められる。体長はドゥシシーレンは4〜5mであるが、ヒドロダマリスはより大型になり7〜10mになった。ヒドロダマリスの出現はサッポロカイギュウの発見、測定でかなり時間を遡ることとなったが、カイギュウ目の分岐進化はまだ明らかにはなっていない。現世種のジュゴンとマナティーの進化も明らかになっていないようだ。日本のヒドロダマリスの進化だけでも手近で見られる本があればありがたい。古沢仁が「月刊たくさんのふしぎ」1999年7月号で発表した「時をながれる川」のような形で見ることができればと思っている。「時をながれる川」は北海道沼田町を流れる幌新太刀別(ほろにたちべつ)川のことで、下流から上流へ遡るほど古い化石があらわれる。タキカワカイギュウ、ヌマタカイギュウも紹介されている。「たくさんのふしぎ」シリーズで北のカイギュウを見てみたい。
ステラーカイギュウを報告したドイツ人博物学者シュテラー(1709〜1746、Georg Wilhelm Steller)は『カムチャツカからアメリカへの旅』(Reise von Kamtschatka nach Amerika mit dem Commandeur Capitan Bering、邦訳、『世界探検全集4』、加藤九祚訳、河出書房新社、1978.11.10)という日誌を残している。カイギュウの記述を拾うと、以下の通りである。
私は岸に近い水の中にマナティをたくさんみた。私はこの動物をこれまで見たことがなく、今でも、いつも半分水の中にいるので十分に見ることができなかった。しかし、この動物はカムチャツカのどこでも見かけないと私のコサックが断言したことや、高木や灌木がどこにも見られないことから、私はここがカミチャツカであることを疑いはじめた。(1741.11.8)[訳書pp.100〜101]
私は同時に、ここで見た未知の海獣、マナティのことや、反対側に当たる南方の雲の性質についても話した。(1741.11.10)[p.105]
ロシア式にこの粉をアザラシの脂肪か鯨油、終わりごろにはマナティの脂肪で揚げて小さなケーキをつくり、皆に一つずつ配った。(1941.11.15)[p.118]
近くでマナティを獲って、隊員の食糧補給を容易にした。それによって舟の建造に時間と人手を余分にまわせるようになり、靴と衣類がすでにかなり欠乏している隊員たちが、山越えのきつい道をでかけないですむこになった。マナティ狩りはわれわれにとって大きな利益をもたらすものであったが、これについてはベーリング島に関する記述の中で詳しく述べた。(1942.5.5)[p.129]
われわれの食料はライ麦粉二五プード、塩漬けのマナティの肉五樽、えんどう二プード、塩漬けの牛肉一樽などであった。この牛肉は皆がほしいものではあったが、帰りの航海のために取っておかれたものだった。この他に、バター四ポンドが各人に渡された。節約してやってきたほとんどの隊員は自分の蓄えを使って航海用に半プードほどのビスケットを焼くことができた。しかし、それができないものは、自分でマナティの乾燥肉を用意した。(1742.8.8)[p.131]
シュテラーらが当時地図上になかったベーリング島に上陸、越冬し発見した海獣が「マナティー」と呼ばれていることに違和を感じる向きもあろう。だが、未知の動物には名はなかった。これに関して、ベーリングの航海の研究者レフ・セミョノヴィチ・ベルグは「ステルレルは彼特有の驚くべき洞察力を以て、この動物は、スペイン人によつてその前肢が手に似ていることからmanati(マナティ)とよばれる南アメリカ産のものと同種類であると咄嗟の間に認定した。彼はさらにベーリング島の海牛は南アメリカ産と全く同一のものであるとさえ考へた」(『カムチャッカ発見とベーリング探険』、小場有米訳、原書房、1982.7.31、pp.320〜321)と述べている。
マナティーという呼び名はカリブ海地域でmanattouiと称していたことによる。ベーリング探検隊の副司令ワクセルの手記『ベーリングの大探険』(平林広人訳、石崎書店、1955.6.25)でもステラーカイギュウの言及があるが、訳者は「海牛」としているものの、わざわざ「デンマーク訳には海牛であろうとなっているが海豹(あざらし)のこと(と)思う」と注を入れている。カイギュウの巨大さと数の多さで、シュテラーら生き残った隊員達がこの動物を盛んに利用していたように思われていたが、実際に捕獲したのは数頭であったようだ。座礁した11月から翌年の春まで主な捕獲食料はライチョウ、ラッコ、アザラシ、トド、オットセイ、座礁鯨であり、カイギュウ狩りは5月になってからのことであった。他の海獣が近くで見つからなくなり、遠出をしていては船の建造に差し支えたからである。ワクセル中尉が中心となって狩りの方法を考えたようである。
わたしくは、ついにこれをつかまえるため魚を釣る鉤の形をした大きな鉄の鉤をつくることにした。目方がおよそ十五−十八ポンドくらいもあって、四インチくらいの厚みにつくった鋭利な鉤を、陸上の綱につないで、力の強い五、六人の壮年が舟で持って行って、力任せに近づいてくる海牛の体を目がけて打ちこむのである。それと同時に、陸上には四十人もの人々が綱を曳いて引き寄せる仕組みにした。ところが、海牛の力はすこぶる大きくて、綱を引いている大勢のものが、波打ちぎわまでも引きずりこまれかけることが少なくなかった。陸上で綱を引くだけでなく、その間に舟の壮年たちは海牛の力を弱らせるために、力まかせに切りつけるので、血潮は噴水のように噴き出して赤く染めるのであった。しまいには、それらの苦闘をやめて、満潮時にすっかり海牛の体に鉤をうちこんで、四インチの太い綱でつないでおいて、干潮時に、海水に置き去りにするまで待って、次の潮の満ちて来るまでに生捕って、遠く陸上に引き上げることにした。(ワクセル『ベーリングの大探険』、pp.181〜182)
ステラーカイギュウは全長7〜8m、体重4〜5tといわれているが、ワクセルは「一度総がかりで一頭の海牛を捕らえると、全員が十四日間は食糧については何の心配もなくなった」と述べているので、海牛だけでこの期間凌いだとすると8月13日の離島まで7頭で賄えたことになる。解体作業中にシュテラーは観察し記録を残した。死後出版された「海獣について」(De bestiis marinis 1751)と『海獣の記録』(Ausfuhliche Beschreibung von sonderbaren Meerthieren , mit Erlanterrungen und nothigen Kupfern versehe 1753)である。この唯一の生態・解剖記録については神谷敏郎が内容の一部を報告している。その中で『海獣の記録』の共同研究者の一人にドイツの解剖学者ヨーハン・アダム・クルムス(Johann Adam Kulmus、1689〜1745)がいて、クルムスは有名な『解体新書』の原著者だという興味深い事実を指摘している。また、蘭学者に大きな影響力を持ったシーボルトの「日本動物誌」(1844年。海獣類項はライデン博物館のシュレーゲルによる)には「ステラーカイギュウRhitina stelleriが日本近海では、その分布が確認できなかった」とあるとも神谷は述べている。これに関しての神谷のコメントは「Rhytinaが狩り尽されたとされる1768年から80年後に刊行された「日本動物誌」において、Rhytina探索がなおも取りあげられていることは興味深い史実である」というものである。
専門の解剖学からステラーカイギュウの特徴を神谷は次のように説明している。「タキカワカイギュウとステラーカイギュウの両種は歯をもたない。(中略)そこで海牛類特有の角質の咀嚼版が、ちょうどマウスピースをはめ込んだ状態で発達している」(『人魚の博物誌』p.85)。「ステラーカイギュウの前肢の骨格をみてみると、自由前肢の骨格は手首から先の骨がまったく欠けている。(中略)自由前肢(胸びれ)の芯をなしている手の骨が完全に欠如していたとすると、ステラーカイギュウの胸びれの形態は杓子状ではなくて、棒状に近い特異な形状ではなかったかと想像させられる」(同pp.86〜88)。また脳のついては「ステラーカイギュウの頭蓋腔容積については、米国の研究者によって一七五七立方センチと算出され、脳容積の小さいことが指摘されている。これらの数値からステラーカイギュウの脳重を推算してみると、一五〇〇グラムどまりとなる。(中略)ヒトの脳重は体重の約二・三%を占めているが、大海牛では〇・〇二五にすぎない」(同p.90)と述べている。神谷はイルカ・クジラと比較し現生カイギュウ類の脳が主さだけでなく、構造も単純であることを何度も指摘しているが、ダイカイギュウも同様であった。
ステラーカイギュウの内臓に関する神谷の記述をまとめると、胃は単胃(反芻動物の複胃ではない)、腸の長さは体長の20.5倍の152m(ジュゴンは体長の23倍)、胆嚢は欠き、腎臓は高度に分葉している(ジュゴン、マナティは胆嚢を持ち、腎臓の分葉は見られない)、などの特徴があった、と言っている。ステラーカイギュウの現行学名はHydrodamalis gigas(巨大な水の若牛)であるが、かつてはRhytina stelleri(シュテラーの樹皮状の皮膚をもった海獣)またはRhytina gigasが使われていた。この樹皮状の皮膚に甲殻類のダイカイギュウシラミ(Cyamus rhytinae)が寄生していたことも神谷は伝えている。この生物もダイカイギュウと共に絶滅した。ベーリング島で絶滅した生物は他にベーリングシマウ(メガネウ、Phalacrocorax urile)がいることを指摘するのは新妻昭夫である。新妻は1994年夏季に日露共同の海獣類調査隊の一員としてベーリング島を訪れている。ベーリングシマウの絶滅は1850年前後のことである(新妻「海牛とステラーの島 コマンドルスキー紀行」[「科学朝日」第55巻第9号、1995.8.1、pp.8〜13])。古沢仁も1992年7月19日から8月1日、ベーリング島に渡りステラーカイギュウの形態的研究を行った(古沢「カムチャッカ州ベーリング島のステラーカイギュウ」[「化石」第58号、1995 6.30、pp.1〜9])。古沢は海岸に漂着、露出していた標本を採取している。
ベーリングの第2次探険隊は、ステラーカイギュウに出会ったアメリカ遠征の本隊と別に日本へ遠征した隊があった。1738年6月中旬オコツクを出帆し、ボルシェレツクで越冬、翌39年5月再出発した。シュパンベルグ船長のミカエル号は仙台藩網地島、ウィリアム・ワルトル船長の希望号は更に南下して房州天津に停泊、上陸までしている。北方の異国ロシアを幕府は意識しなければならなくなった。仙台藩出身の若年寄堀田正敦(1755〜1832、若年寄の任は40年以上[1790〜1832])が北方防備の中心人物(正敦は文化4[1807]年、蝦夷地視察を行っている)であり、かつ国家的規模の博物誌の編纂者であることに注目したのは鈴木道男(鈴木道男編、堀田正敦著『江戸鳥類大図鑑 よみがえる江戸鳥学の精華『観文禽譜』』、平凡社、2006.3.16)であるが、正敦の下に集まった外国語ができた俊英馬場佐十郎(貞由、1787〜1822)、大槻玄沢(1757〜1827)は江戸後期の人魚情報の発信者でもあった。玄沢の「六物新志」は有名であるが、佐十郎には玄沢との共用とでも言うべき人魚情報「海人(人魚)訳説」がある。ロシアとの関係では玄沢の「環海異聞」、佐十郎は高橋景保(1785〜1829、シーボルト事件に関連して獄死)との共訳「遭厄日本記事」(ゴローヴニン「日本幽閉記」のオランダ語からの重訳)、ロシア経由の北方牛痘術書「遁花秘訣」(小川鼎三・酒井シズ校注のテキストが岩波書店『日本思想体系65 洋学下』に収録されている)がある。佐十郎、玄沢の幕府での大翻訳事業にはショメール(1633〜1712、リヨンの司祭)の家政百科事典のオランダ訳書からの翻訳「厚生新編」(文化8[1811]〜弘化2[1845]年)がある。堀田正敦はこれらの外国情報に目を通していた。ステラーカイギュウの発見が日本の外国人魚情報の蓄積に関連していることに言及してみた。
堀田正敦は松平定信(1758〜1829)と盟友関係にあったが、定信に取り立てられた洋風画家亜欧堂田善(1748〜1822)が銅版印刷で製作した世界図に「新訂万国全図」がある。2006年春に府中市美術館で開催された「亜欧堂田善の時代」で見ることができた。レザノフ(1764〜1807、1804年に長崎に来日)がもたらしたアロースミスの世界地図をもとに間宮林蔵(1775〜1844、1808年、樺太が島であることを松田伝十郎[1769〜?]とともに明らかにした)の見聞も加味した北アメリカ北極部分以外は明らかになった世界最新の地図である。ベーリングの探険成果は「ベリンゴウ海峡」「アレウツキヤ諸島」「ベリングス島」などと表示されている。その他、「チブカ諸島所謂千島」「ヲホツカ海」の文字が見える。この地図の日本周辺で興味深い点は日本近海の太平洋が「大日本海」とされ、今日普通日本海と呼ぶ所には記名がなく、朝鮮半島東に「朝鮮海」とあることだ。戦前南洋庁が置かれジュゴンも棲息したパラオ諸島については「新訂万国地図」には「ペレウ諸島」の名の下に「エミユング、エミデケ、コローラ、アンテガル、ペレウ、ヨイール」などの名が附されている。この極めて正確な地図は、天文方高橋景保が中心となり、間重富(1756〜1816)、馬場佐十郎らが協力し編纂された。文化7(1810)年に基本形ができたらしい。銅版製作は文化13(1816)年頃と言われている。鈴木道男は「蝦夷地および千島、カラフトは、19世紀初頭に至っても両極を除いた地図上の唯一の空白域とされており、その状況は地理的発見の時代と博物学の時代が同時に進行していたかのような様相を呈していた」(鈴木道男「若年寄の蝦夷地視察−堀田正敦の『観文禽譜』(六)、「東北大学大学院 国際文化研究科論集」第8号、2000.12.20、pp13〜29、引用部はp.14)と述べているが、「新訂万国地図」は南極部分が正確に把握され、日本北方も明らかになっている最新版であった。
シュテラーはダイカイギュウをマナティーと最初呼んでいたが、コロンブスも目撃したと思われるアメリカマナティーに学名を付けたのはリンネ(1707〜1778)である。神谷は当該部分のリンネ『自然の体系』第10版(1758年)第1巻p.34を『人魚の博物誌』の最初(p.2)に掲げている。Trichechus manatusの属名トリケクスとは「毛のあるもの」の意で、口のまわりに生えている毛を指しているという。アコスタ『新大陸自然文化誌』第15章「魚の種類と、インディオが魚をとる方法について」にマナティの記述がある。
エスパニョーラ、クーバ、プエルト・リコ、ハマイカ等の、いわゆるバルロベント諸島には海牛 (マナティ)という奇妙な種類の魚がいる。魚とはいっても、この動物は子供を生きたまま生み、乳頭をもち、乳で子を育て、野の草をたべる。しかし実際は、ふつう水の中に住むので、魚として食用に供されるのである。とはいうものの、私はかつてサント・ドミンゴで、金曜日にその肉を食べ、ちょっと心配にすらなったことがある。別に右に述べた事情からでなく、その魚の肉切れが、色といい味といい、子牛のもも肉にそっくりだったからだ。この魚は牛のように大きい。(増田義郎訳『アコスタ 新大陸自然文化史 上』、岩波書店、1966.1.12、p.265)
アコスタ(1540〜1600)はスペインのイエズス会士で、ペルーに渡り、アンデス布教を指導した。1600年代にはローマ法王がマナティーは魚であるという教令を出し、カトリック教徒は金曜日に魚としてのマナティーの肉を食べることができた。ジュゴンの学名はリンネの死後、『自然の体系』第13版(1788年)でグリメン(1748〜1804)によって付けられた。
1799年から1804年にかけて南アメリカを探険したアレクサンダー・フォン・フンボルト(1769〜1859)はインディオたちがアプシアあるいはアビアと呼ぶマナティーについて報告している。鰭の縁は完全に滑らかで爪の痕跡は見当たらなかったが、皮膚を除去すると指の第三関節に爪の原基が見えること、唇が周囲の事物の認識に関連していること、胃はいくつかの小胞に分かれていること、背中を開くと巨大は浮き袋のような二つの肺があることなどの解剖所見や、グアモ族とオトマコ族は好んで食べるが、一般にはあまり食用にされることはないことを述べている。聖職者たちはマナティーを魚と見なし、四旬節では珍重され、脂肪は教会の紹明にも使用され、皮は綱や鞭に利用されているとも記している(大野英二郎・荒木善太訳『新大陸赤道地方紀行 中』[17・18世紀大旅行記叢書【第2期】10]、岩波書店、2002.12.19、pp.228〜230、第6部第18章)。
フンボルトはまた、「レベス」というコバンザメ属の魚を使って海亀を捕らえる漁法を
伝えている。前回、コバンザメでマナティー、ウミガメを捕獲することは紹介したが、この奇妙な漁についてフンボルトは次のように記述している。
ゴマラや、皇帝カール五世の顧問をしていた学者ピエトロ・マルティーレ・ダンキエラがこの話をコロンの旅の同行者の口から聞き出してヨーロッパに紹介した時、人々はこれ尾を「旅行者の物語」にすぎないものと考えたようだ。確かに次のような言葉で始まるアンギエラの物語にはどこか現実離れしたところがある。「我々ガ平原デ犬ヲ使ッテ兎ヲ狩ルヨウニ、きゅーば島ノ住人ハ魚ヲ餌トシテ他ノ魚ヲトッテイタ」。ロジャーズ船長やダンビア、コメルソンらの証言によって、我々は今日、「ハルディニリョス」で行われているのと同じ漁法が、アフリカ東岸のナタール岬付近やモザンビーク、マダガスカル島などでも見られることを知っている。(『新大陸赤道地方紀行 下』、pp.420〜421)
コバンザメ漁についてはオビエード(1478〜1557)『インディアスの征服史ならびに博物誌』第13巻第10章が詳しい。コバンザメは「ペヘ・レベルソ」(サカサウオ)と呼ばれている。染田秀藤・篠原愛人訳『カリブ海植民者の眼差し』(アンソロジー新世界の挑戦4、岩波書店、1994.9.9)pp.293〜301。
神谷の海生哺乳類の研究は、カワイルカが『川に生きるイルカたち』(東京大学出版会、2004.4.16)、鯨は『鯨の自然誌』(中公新書、1992.4.25)、海牛類は『人魚の博物誌』(思索社、1989.12.20)にまとめられたが、その原形は雑誌「海洋と生物」誌上の連載「海の哺乳類」(1986.12.15〜1992.12.15、全37回)にある。37掲載分の内容をつまみ食いしてみよう。
1.「南極海調査捕鯨」、「海洋と生物」第47号、1986.12.15、p.447
南極海捕鯨船団の最後の出漁は1986〜87年漁期であった。2.「淡水イルカの保護」、48号、1987.2.15、pp.56〜57
神谷の最後の単行本は『川のイルカたち』であり、その保護に尽力していた。3.「海獣の顔付き」、49号、1987.4.15、pp.130〜131
海獣とは鰭脚目、海牛 目、鯨目に属する水生哺乳類である。神谷はジュゴンの半円盤状の上唇部から口裂の縁にかけて生えている剛毛が血洞毛(知覚神経と繋がっている一種の感覚装置。例えばネコのひげ)であることを何度も強調している。カイギュウ目の上唇の洞毛は餌の探索と選別のためのものである。4.「脳くらべ」、50号、1987.6.15、pp.206〜207
カイギュウ目の骨質は緻密で重い。頭骨も厚く堅牢である。脳を摘出することはなかなか大変な作業となる。その脳重は300g(体重のおよそ1/1000)、上から見ると「ヒョウタンのように中央で大きくくびれている」。表面は平滑であるが、小脳は大きい。5.「海牛余聞」、51号、1987.8.15、pp.266〜267
4月5日、沖縄海洋博記念水族館でアメリカマナティーの双生仔が誕生したが、1ヶ月余りで死亡したことを伝えている。また、リンネが最初に学名を付けた海牛類はアメリカンマナティー(1758年)であると指摘している。6.「海獣の骨格標本」、52号、1987.10.15、pp.348〜349
宮崎信之により『国立科学博物館海棲哺乳類標本目録』(1986.3)がまとめられたこと、そのなかには神谷の恩師、小川鼎三のコレクション、鯨研で西脇昌治が中心となって収集した標本が含まれていることを伝えている。西脇と神谷はイチョウハクジラ(Mesoplodon ginkgodens)を新種として命名、研究した(1958年)。7.「鎖国時代の海獣学」、53号、1987.12.15、pp.420〜421
シーボルト『日本動物誌』(1844)には海獣類としてはアザラシ類1種とクジラ類8種が記載されている。また大槻玄沢『六物新志』には一角と人魚が取り上げられている。人魚の項にはオランダの宣教師「ファレンタイン」の著から図が模写されている。神谷は「彼(ファレンタイン)がいかなる推察でこの人魚像を描いたのであろうか。対象調査域であった島じまには今日でも多数のジュゴンが生息しており、ファレンタイン自身も恐らくジュゴンを観察していたと考えられるからである。多くの人たちが人魚のモデルはジュゴンと答える根拠のルーツと、なんらかの関連を連想させるからである」と述べている。8.「大海牛の解剖」、54号、1988.2.15、pp.18〜19
シュテラーは1742年7月12日に行われたメスの大海牛(体長752cm)の解体記録を残している。神谷はメスジュゴン(254cm)との計測値比較表を掲げている。体長は3倍であるが、腹部の体周は4倍以上(620/145cm)となっていて、「腹部が蛙のように大きく膨れて」というシュテラーの記述が肯定できる。ちなみに乳頭の長さは10cmと2cmと5倍である。アメリカ国立自然史博物館のスティネゲールによる大海牛復元図(1887年)も掲載されている。陸に上げられ、仰向けにされ解体されようとする図である。同様の構図で描かれた捕獲図は雑誌「ニュートン」2001年9月号(p.71)でよりリアルに見ることができる。「ニュートン」pp.68〜69には見開きで海中のステラーカイギュウが描かれている。前肢の特徴がよく分かる迫力の図である。9.「消化管の比較」、55号、1988.4.15、pp.100〜101
海獣を食性から大雑把に分けると魚類食(鰭脚類・歯鯨類)、甲殻類食(ひげ鯨・少数の鰭脚類)、海草食(海牛類)の3つに分けることができる。海獣類全体に味覚の発達は悪いらしい。味より量。鯨類の舌には味蕾が見当たらないという。海牛類の胃は「非常に厚い筋層を備えた球状を呈する単胃である。ただ、胃底部に指サック状に突出した腺塊をもっていて、組織学的には胃液分泌細胞層が厚く覆っている」。ジュゴンの腸管は「若い個体では、小腸と大腸との長さがほぼ同じであるが、成長するにしたがって大腸の割合が長くなり、成体の大腸は小腸の2倍、腸全体の67%を占めるまでになる」という。10.「消化腺の特徴」、56号、1988.6.15、pp.184〜185
海牛類は唾液腺の発達が良い。シュテラーは大海牛には胆嚢が欠如していると指摘し、胆管と膵管が合流して1本の管として十二指腸に開口するとも述べている。胆嚢を欠く動物としてはウマ、シカ、ゾウがいるが、近縁関係にある種間でも、胆嚢の有無が異なる場合があり、神谷は「哺乳類にとって胆嚢は、どのような働きをもっているのか、その普遍性の整理は一筋縄には行かない」と述べている。11.「呼吸運動器官の特徴」、57号、1988.8.15、pp.274〜275
海牛類の肺は「長円盤状」で、「体長240cmのジュゴンの肺の長さは90cmもあ」り、「ダイバーが背中にアクアラングを背負った形で胸腔に収まっている」。したがって海牛類の横隔膜は「頭側から尾側に水平に張っていて、体幹を背腹にほぼ二分している」。12.「淡水イルカ研究会」、58号、1988.10.15、pp.360〜361
この時点での淡水イルカ研究会は顧問養老孟司、責任者神谷、幹事吉田穣の3人だけであった。絶滅の危機にあるアジアのカワイルカへの理解を広げようと神谷が行動を起こした。13.「クジラ目の新分類」、59号、1988.12.15、pp.434〜435
国際自然保護連盟鯨類専門委員会で検討決定された分類表の紹介である。14.「Mesoplodonの昭和史」、60号、1989.2.15、pp.20〜21
1989年、昭和は終わった。Mesoplodonとはアカボウクジラ科オオギハクジラ属このとである。下顎に2本だけの歯をもつオオギハクジラ属は12種(タイヘイヨウアカボウモドキ、ニュージーランドオオギハクジラ、アカボウモドキ、ヒガシアメリカオオギハクジラ、イチョウハクジラ、ミナミオオギハクジラ、オオギハクジラ、ハッブスオオギハクジラ、タイヘイヨウオオギハクジラ、ヒモハクジラ、ヨーロッパオオギハクジラ、コブハクジラ)。20世紀に確認された種が5種。昭和元年(大正15年、1926年)に新種報告されたのがタイヘイヨウアカボウモドキ。昭和33年に西脇・神谷により報告されたのがイチョウハクジラである。最も新しい記載は1963年のハッブスオオギハクジラである。15.「Perrin博士からの書館」、61号、1989.4.15、pp.118〜119
国際自然保護連盟鯨類専門部会議長のペリン博士より新分類表の転載許可が得られたので、p.119に載せてある。あわせて、ヨウスコウカワイルカの保護活動について述べている。16.「人魚巷談」、62号、1989.6.15、pp.208〜209
古沢仁のタキカワカイギュウの学術報告を読んだこと、人魚の海牛類モデル説、海牛 類の日本での飼育について述べている。神谷の人魚=海牛類をめぐる文章の型を踏襲している。海牛類の記載の歴史、化石カイギュウと現生カイギュウ類の紹介、日本での研究、飼育の報告、それに人魚本来の歴史を少々。これらの集大成が『人魚の博物誌』であった。神谷や西脇の立場は「人魚の伝説が先にあって、ジュゴンやマナティーは後からあてがわれた」というものである。「今日知られているジュゴンに関する学術報告で最も古い文献は、16世紀に入ってから紅海のジュゴンについての報告」であるとしている。17.「日本で発見された大海牛」、63号、1989.8.15、pp.282〜283
日本の大海牛 化石第1号は、長野県戸隠村で1966年8月に発掘された標本である。鹿間時夫博士とD. P. Domning博士により1970年に報告されている。その後1978年8月ヤマガタダイカイギュウ、1980年6月北海道広島町、同8月タキカワガイギュウの発見があった。ヤマガタダイカイギュウはDusisiren dewana、タキカワカイギュウはHydrodamalis spissaと属が異なる。ヤマガタダイカイギュウは計12本の臼歯が確認されたが、タキカワカイギュウは歯を持たない。18.「夏の海獣小話」、64号、1989.10.15、pp.380〜381
勇魚会の機関誌「勇魚」第10号が紹介されている。神谷は「勇魚」第12号(1990.5.27)に「淡水イルカをもとめて25年」を第18号(1993.6.25)には「神谷敏郎先生のお話を聞く会」を載せている。また「勇魚」第24号(1996.6.25)は「特集 海牛類」であった。計8本の論考が掲載されているが、その最後はJ. E レイノルズ、J. K. オデール「ステラーカイギュウ:人間が犯した罪の物語」である。近年では第39号(2003.12.25)に明田佳奈「海牛類の消化管をかいぼうする」「海牛類の摂餌特性と消化機構に関する研究」の報告がある。19.「コロンブスの人魚」、65号、1989.12.15、pp.472〜473
コロンブスの航海日誌1493年1月9日に「3匹の人魚」を見たことが書かれているのは有名な話だ。マナティーはオビエド(1478〜1557、スペインの植民地官吏。『インディアスの征服史ならびに博物誌』を著す)によってヨーロッパに伝えられた。ジュゴンという名称を動物学的に採用したのはビュフォン(1707〜1788、フランスの博物学者。主著『博物誌』全44巻)『博物誌』第13巻(1765)が最初らしい。20.「海獣のポスター」、66号、1990.2.15、pp.24〜25
ザトウクジラ、アザラシ目、カイギュウ目のポスターが紹介されている。カイギュウ目ポスターはマナティー3種、ジュゴンとともにステラーカイギュウが1/10の縮尺度で描かれている。アマゾンマナティー<アフリカマナティ<ジュゴン<アメリカマナティ<ステラーカイギュウとなるようだ。21.「シロナガスクジラ」、67号、1990.4.15、pp.108〜109
シロナガスクジラは史上最大の動物で、最大の個体は体長31mとも言われているが、「平均体長は雄25m、雌26.2m」である。亜種に雄の平均体長が「21.6〜21.9m」のピグミーシロナガスクジラがいる。小型シロナガス研究に最初に取り組んだのは市原忠義(1930〜1981)であった。神谷は1961〜62年漁期に水産庁監督官として南氷洋捕鯨に参加した。当時シロナガスは21.3m以下の捕獲は禁止されていたが、捕獲されたほとんどが20m前後で、ピグミーシロナガスクジラと思われた。22.「コククジラ」、68号、1990.6.15、pp.190〜191
コククジラは北大西洋では18世紀初頭に絶滅してしまい、太平洋のアジア側とアメリカ側に生息している。一時絶滅を心配されたアメリカ側のコククジラは増えたが、数が多かったアジアのコククジラは激減している。23.「セイウチの頭蓋」、69号、1990.8.15、pp.282〜283
東京水産大学(現在は東京海洋大学)資料館所蔵のセイウチ頭蓋骨の牙は58cmもある。(同資料館にはジュゴンの剥製もあるという。)セイウチは1科1属1種で、19世紀前半にはTrichechus(毛のあるもの)という属名が使用されていたが、トリケクスは現在ではマナティーの属名となっている。マナティーの旧属名はManatus、セイウチの現学名はOdobenus rosmarusで、属名は「歯を使い前進するもの」の意である。24.「スナメリ」、70号、1990.10.15、pp.404〜405
日本近海の鯨類最小種はスナメリであるが、シーボルト『日本動物誌』にもNamino-uo(ナミノウオ)と紹介されている。揚子江にもカワイルカとともにスナメリが生息していることを神谷は何度も伝えている。スナメリは日本各地で江戸時代以降様々な名称で呼ばれてきた。長門のオショウウオ、周防のボウズウオ、安芸のゼゴンドウ、備前・備中・和歌山のナメウオ、常陸・江戸のスナメリなどがる。瀬戸内海では「スナメリ網代」という漁法がある。スナメリに追われたイカナゴが海中に潜り、餌のイカナゴ目がけてやって来たタイやスズキを漁師が釣り上げる。立春から八十八夜にかけ、スナメリの群れの回りを釣り船もまわる。スナメリが海鳥アビに替われば「鳥付網代」(アビ→イカナゴ→タイ→漁師)となる。キム・ファン文、藤井広野絵の絵本『のんたとスンメリの海』(素人社、2002.5.25。巻末の解説は粕谷俊雄「スナメリの生物学」)は「スナメリ網代」を主題としている。25.「鯨類の痕跡後肢と奇形」、71号、1990.12.15、pp.482〜483
「現生の鯨類や海牛類の後肢は特殊化し、一対の骨盤骨として肛門の前外側の筋肉中にうずもれている」が、ムカシクジラ類のバジロサウルス(4000万年前)化石には60cmの下肢骨が存在していた。また、先祖返りとも言える下肢をもった奇形クジラが捕獲されることもある。26.「雄の生殖器」、72号、1991.2.15、pp.38〜39
「海獣類の陰茎は平時は体内に収納されている。流線型に近い体型を保持するために、突起物は極力体内に取り込まれている」。「海牛類のマナティーやジュゴンの陰茎には亀頭があり、その形態や尿道突起には、固有の特徴が認められる」。27.「湾岸戦争とジュゴン」、73号、1991.4.15、pp.118〜119
1991年の湾岸戦争ではペルシア湾で原油の流出があり、ジュゴンも犠牲になった。28.「鯨目の新種」、74号、1991.6.15、pp.200〜201
アカボウクジラ科Mesoplodon属13番目の種Mesoplodon peruvianus(ペルーオウギハクジラ)をミード博士らが報告した。29.「腎臓の特徴」、75号、1991.8.15、pp.278〜279
神谷の鯨類関連の第一論文は小腎の分葉度についてであった(1958年)。鯨類の腎臓は小さな組織塊が集合して形成されている。マナティー、ステラーカイギュウは分葉腎であるが、ジュゴンは平滑な腎臓をしている。30.「鯨類の小腎柱」、76号、1991.10.15、pp.338〜339
餌と共に大量の塩分を摂取している鯨類の体液や血液中の塩分は陸生哺乳類と差がない。塩分は小腎の尿細管で調整されているのではないか、というのが尾坂知江の研究である。31.「海獣の郵便切手」、77号、1991.12.15、pp.428〜429
日本復帰以前の琉球切手にジュゴンの図柄の3セント切手があることはよく知られている。神谷は白木靖美(切手収集家)と共著で切手ミュージアム2『クジラ・イルカと海獣たち』(未来文化社、1995.6.25)を出している。同書pp.12〜13には「シュゴンやマナティーのなかま」の原色図版があり、人魚切手も見ることができる。解説で神谷はジュゴンの脳、カイギュウ類の種類、人魚のモデル問題について言及している。32.「シカゴ海生哺乳類学術集会」、78号、1992.2.15、pp.16〜17
神谷は形態解剖学が専門であるが、近年発展著しいのは分子生物学手法を用いた研究である。ミトコンドリアDNAの解析から鯨類の先祖はラクダだという説が出された。33.「わが国で発見されたカワイルカの化石」、79号、1992.4.15、pp.106〜107
1992年1月、平泉で発掘されたラプラタカワイルカ近縁種の化石(400万年前)についての報告が岩手県立博物館からあった。神谷『川に生きるイルカたち』には、仙台市西北部から産出したヨウスコウカワイルカ科に属すると思われる化石(1996年発見)、三重県のインドカワイルカに繋がる鯨類化石(1998年発掘、1700万年前の地層)の記述がある。34.「デスモスチルス(束柱類)」、80号、1992.6.15、pp.198〜199
デスモスチルスはカイギュウ類に近縁の動物として名高い化石である。1950年10月に岐阜県土岐市で発見された化石はデスモスチルス目の新属パレオパラドキシアに分類された。パレオパラドキシアの頭蓋腔複製標本の形態学的研究を受け持ったのが神谷である。
脳重はカイギュウ類とほぼ同じ(392g)、嗅神経はよく発達し(鯨類では嗅神経は退化しているので、半陸生動物の可能性が強い)、三叉神経根の形態はジュゴンによく似ていた。35.「日中バイジー交流11周年」、81号、1992.8..15、pp.284〜285
1981年3月のヨウスコウカワイルカ日中共同考察団(西脇昌治、片岡照男、神谷)から11周年。36.「雌の生殖器」、82号、1992.10.15、pp.346〜347
「後肢を欠く海獣類にみられる大きな特徴は、骨盤が存在しない点である」。「海牛類の卵巣は卵巣嚢によって包まれていて、このふくろの内側端は漏斗状となり、次第に細くなって卵管に移行する」。37.「三人の恩師」、83号、1992.12.15、pp.434〜435
連載の最後に、小川鼎三(1901〜1984)、細川宏(1922〜1967)、ポール・ピルロ(Paul Pirlot、1920〜1990。モントリオール大学生物科教授、コウモリの研究家)の三人を恩師として挙げている。
「海の哺乳類」連載以外で、管見に入った神谷の海牛関連文は以下の通りである。
神谷敏郎・内田詮三・鳥羽山照夫・吉田征紀「ジュゴンの観察(1)(2)」(「鯨研通信」第325号・第326号、1979.5/1979.6、pp.25〜34/pp.35〜42)
神谷敏郎「人魚学ことはじめ」(「海洋と生物」第1巻第4号、生物研究社、1979.10.15、pp.30〜31)
神谷敏郎「人魚の正体−ジュゴンの生物学−」(「自然」第35巻第6号、中央公論社、1980.6、pp.45〜53)
西脇昌治・神谷敏郎「海牛類について」(『世界の動物 分類と飼育〔奇蹄目・ハイラックス目・管歯目・海牛目〕』、東京動物園協会、1984.2.15、pp.114〜121)
神谷敏郎「人魚の博物巷談」(「UP」第263号、東京大学出版会、1994.9.5、pp.1〜7)
神谷敏郎の先輩の鯨・海牛研究者西脇昌治(1915〜1984)には絶筆「ジュゴンの話」(『全集日本動物誌30』、講談社、1984.10.10、pp.3〜52)がある。宝塚で轟夕起子の「ローレライ」を聴いたことや昭和初期に人魚の見世物を何度か見たことから書き始めている。見世物は乾物、娘が作り物の魚の胴体に入っているもの、脚を縛られたタイワンザルがコイかレンギョのくり抜いた部分に押し込められているものなどがあったという。「ジュゴンの先祖」「染色体数」「宮古島のジュゴン」「人魚のイメージと伝説」「ジュゴンと泳ぐ」「ジュゴンの形態」「歯の機構とジュゴンの寿命」「ジュゴンの皮と毛」「脳の話」「ポンプをもっている腸」「ジュゴンの分布」「ジュゴンの味」「ジュゴンを飼う」「ジュゴンの交尾」「附録・ステラー海牛の悲劇」という構成である。今まで述べてきたことと重なる内容が多いので紹介は省略する。
2006年2月に刊行された遠藤秀紀(1965〜)『解剖男』(講談社現代新書)には(動物)遺体解剖に取り組んでいた著者、山際大志郎、彼等の先生である神谷敏郎の姿が描写されている。「大学は成果が出にくい遺体研究を、無関心や嫌悪感の下に遠ざけるようになっている。(中略)その逆風の中で、神谷先生と山際さんと私は、笑えるほど小さな車で、学者が誰も見向きもしない門外不出の遺体たちを日々運んでは、謎解きに奔走していたのである」(p.158)。神谷は鬼籍に入り、山際は政治家になり、一人解剖男遠藤は「遺体を嘲笑っているいまの学会の価値観がいずれ崩壊する日」まで、謎解きに邁進している。
神谷敏郎は2004年7月13日に亡くなった。なお、神谷には東大所蔵のエジプトミイラについての著『あるミイラの履歴書 エジプト・パリ・東京の三千年』(中公新書、2000.4.25)もあるが、海牛に関連していないので内容紹介は省いた。
by海老名厚(aka. MORO)