�����l�`��y�����������Ȗ��M

INDEX��30P
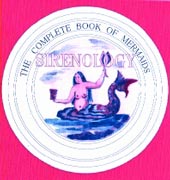
�@�O��́u�l�����m�v���ƁA��k�鍑��w�������⋱��(1887�`1965)�𒆐S�ɐ�O�̃W���S�������ɂ��ĕ����B����̒��S�l���͑哇����(1884�`1965)�ł���B�哇�͕���̓����鍑��w�����w�Ȃ̐�y�ŁA������������A��w���ƂƓ����ɑ�p���{�����������Z�t�Ƃ��đ�p�ɓn���Ă���B�哇�̑�p����͖���44�N����吳13�N�܂łŁA���̊ԁA�č��X�^���t�H�[�h��w�ŋ��ފw�̌��ЃW���[�_�����m(David Starr Jordan�A1851�`1931)�Ɏt�����āA��p�Y���ނ̓��茤�����s���Ă���B
�@�哇�̌����̈�͑�p����̃V���A���A���ތ����A���n�ɖ߂��Ă���͍������ނ̌����A�펞���̑哌�����h���̓Ŏ����ƁA�����E���ށE��ނ̍L��ɓn���Ă���B�܂��A�q�������Ȋw�[�֏��̕���ł��������c���Ă���B����ɁA���e���D�y�_�w�Z�̑������̃L���X�g��(�哇�����A1859�`1938)�ł��������Ƃ���A�D�y�A�N���[�N���m�Ɋւ��镶�͂��c���Ă���B�����̒��j�͑����������A���k�n���̒����j���U�������������]���ꂽ���j�w�҂ł�����(�哇�����A1909�`1944)�B���̎O��̊w�Ґe�q�𒆐S�ɍ���͐i�߂�B
�@�哇�����̐l���֘A���͂͂R����(����ȊO�ɂ����邩������Ȃ�)�B
�u�l�ʋ�铂̉����v(�w��������x�A����{�Y�����u�k�ЁA���a�W�N�S��10���App.80�`85)
�u�l���̐�铂������v(�u�Ȋw���v��24����11���A�������V���ЁA���a10�N11���P���App.80�`83)
�u�l���̐��́v(�u�����V���v���a28�N12��20���[���Q�ʁA�u����������H�������̂̐_��S�v)
�@�哇�͐l���̐��̂͊C���ނł���ƌ������Ă���B���̈�r�����哇�̐^�����ł���B��łȂ̂ł͂Ȃ��B����F�߂�ΑO����������邱�Ƃ��S�O���Ȃ��������i�ł���B�u�l�ʋ�铂̉����v��ǂ�ł݂悤�B
�@�u�l�ʋ�铂̉����v�͂S�̕�������Ȃ�B�u�C�ɐ��ސl���v�u�l���ƍl����ꂽ�C���v�u�ƃ}�i�e�B�[�v�u�C���Ƒ��v�B�����o���̓X�^���t�H�[�h��w�����w�����ɂ���u�l�ʋ�铂̉��W�{�v�ł���B�l���~�C������肵���u���̉��t�W�����_�����m�v�́A���Ȃ�����������B
������ɂ�铂ɉ��̏㔼�g���Ƃ�������̂ł��邪�A�������떂�����̂��܂��x�ߐl�̍삾�����āA�Ȃ��Ȃ����܂��o���Ă��B�̂��猾�ЙB�ւ��Ă��l���Ƃ͂��̂₤�Ȃ��̂��炤�Ƒz�����āA����Ȃ��̂����o�����Ƃ���ɖʔ��������邩��A�W�{�Ƃ��Ă��Ƃ߂ė����̂��B
�l���~�C���Ɍ��y���邱�Ƃ͐l���ɂ��Ă̕��͂̏퓅�ł���B�l���ɂ��đ哇�͒����ł́u�m�_�^�v�u�h�ًL�v�A���{�ł͐���27�N�̋L���A�u�a���O�ː}��v���Љ��B���́u�a���O�ː}��v��ǂ哇�́u����͊C���̗ނ��ȂƎ��͂����ɋC�t���܂����v�Əq�ׂĂ���B�C���̌�����́u���ށv�ł��邪�A�ߎ��ɐ�ł����X�e���[�C���́u铒����V���[�g�����O�ɒB�����v�Ɠ`���Ă���B�́u�O��ށv��F�߂Ă���B�W���S���ƃ}�i�e�B�[�̈Ⴂ�͉�̗L���A���̌`��̈Ⴂ(�}�i�e�B�[�͉~�`�A�V���S���ł͒������ꍞ��ł���)���Ƃ��Ă���B�W���S���̕����Â�����m���Ă���̂ŁA�u�����͐l���̖{铂ł���Ƃ��Ă悢�̂ł���܂��v�ƒf�����Ă���B�}�i�e�B�[�����B�ɒm��ꂽ�̂͐���1500�N�A�X�e���[�C�� ����ł����̂�1772�N�A���ƋL���Ă���B�����܂ł̋L�q�͂��̎��_�܂ł̐l�����C���ޏЉ�̏퓅����o�Ă��Ȃ����A�Ō�ɊC���ނ̐i���ɂ��ďq�ׂĂ��镔���͓����Ƃ��Ă͖ڐV�����Ǝv����B�C���̐�c�Ƃ��ăG�W�v�g���甭�@���ꂽ���G�I�Z���C�f�X�������Ă���B�G�I�Z���C�f�X�͌㎈������Ă����B�C���ނ͌~�Ƌ߉��Ƃ���̂͌��ŁA�ۂƈ�ԋ߂��A���ʂ̐�c���番���ꂽ�Ɛ������A�����̏ہE�C���ƌÑ�̏ہE�C���̓����̐}��Y���Ă���B�哇�́w��������x�͖L�x�Ȏʐ^�A�}�G�������ƂȂ��Ă���B�l�����������͂ł͏ہE�C���̔�r�}�̑��Ɂu�吼�m�ɂ����ꂽ��l���u�v�v(�ʐ^�͕ߊl����t���ɒ݂��ꂽ�V���S���ł��邪�A�吼�m�ɂ̓W���S���͐������Ȃ��̂ŁA�����m���邢�̓C���h�m�̊ԈႢ�ł��낤)�A�u�A�t���J���݂ŕߊl���ꂽ�u�v�v�A�u�t�����_�̃}�i�e�B�[�v�̎ʐ^�E�}�����߂��Ă���B�W���S���ƃ}�i�e�B�[�̐i���ɂ��ẮA
����(���ƂȂČ���ė���C����)�̑������̌`�����Ă��Ƃ��������ƁA�͂��̐̂��Ȃ�A���n����ɕ��z���Ă���̂ł��āA���̎�ނ��������ł��낤�Ƒz������܂��B
�@����Ɋr�ׂČ���ƃ}�i�e�B�[�̉��͂����ď����A���̔��B�̂��Ƃׂ邱�Ƃ͐��鍢��ł���܂��B�����}�i�e�B�[������ł��n��������̉����V�R�Ɍ���ė��܂��B�}�i�e�B�[�������Ɠ������̂��A�ǂ����ă}�i�e�B�[�Ƃ�����b�����̂��A���̊W�͍��Ȃٖ��炩�ɂȂĂ�Ȃ��̂ł���܂��B
�Əq�ׂĂ���B�哇�̊C���ސi���̂܂Ƃ߂͍����ł�������������̂ƂȂ��Ă���B���{�ł�1970�N��ȍ~�A�C���މ���35�ȏ㌩�����Ă��邪�A����͑哇�̎���̂��Ƃł���B�Ȃ��A�哇�ɂ͐��w�����Ȑi���w�ҕ���x(���`�o�ŎЁA���a24�N12���P��)�Ƃ����q�������ɐi��������{������B���̏��̊����ɖ��`�o�ŎЂ���V�łŊ��s���ꂽ�w��������@�O�сx�̍L��������B������Љ�Ă������B
�V�Ł@��������@�`�T�Ł@�㐻���{�@160�Ł@�艿�S���\��
�C�ɏZ�ސl���̘b�A�钆�ɘr�Ɋ����t�������q�����E�ŗL���ȓŎփR�u���A�����v���Ƃ����Ēނ������[�C���A㯂����ݎE�����E�܂����A�C�k�l�A���͈�x�̖��тɖ��Ђ傤�ǂ����A�C�ɗ��ɐ��E�̒���ȓ����A���ނ̏K���Ȃǂ܂��܂��F����̒m��ʂ��̂��Љ�������X��@�ǂ�ŋ�����ᶂ����A�����Ēm�����g�ɕt����D�̉ۊO�Ǖ�
�ʐ^�S�]������́A�f���������ǖ{�ł��B
���`�o�ŎЂ͕����揬������Q��26�A���s�l�͊|�쒇�O�Y�B�V�Łw��������x�̌�т͗����a25�N�̏o�łł���B�u�k�Дł́w��������x�͏��a�W�N�S���̏��łŁA���a11�N�S��38�ŁA���a13�N�ɂ�52�ł𐔂��A�����̓ǎ҂Ɍ}����ꂽ���̂Ǝv����B
�@�哇�ɂ����̐l���֘A�����́u�Ȋw���v���a10�N11�����ɍڂ����u�l���̐�铂������v�ł���B�������X�����^�C�g���̉��ɂ͓��ɂQ�{�̊p�����C�̈����̐}��������Ă���B���̘r�ɕh�������A�Z���M���������Ă���C�̉����̊G�͍����ł͂���ӂꂽ���̂ƂȂ��Ă���B�Q�X�i�[(1516�`1565)���甭���A�A���h�����@���f�B(1522�`1605)�A�p��(1510�`1590)���o�āA�ߔN�ł͔��i�ДŁw��������S�ȁx(�W�����E�A�V���g��[1834�`]���A�����鏟��A1992.6.20)�̕\���G�ɂ��g���Ă���u�C�̈����v�ł���B�p���w�����Ƌ��قɂ��āx�ɂ��ƁA�Q�X�i�[�̓A���g���[�v�Ŏ��ۂɂ��̉�����������Ƃ���G����肵���Ƃ����B�Q�{�̊p�A������������c�E�ȓ����A�r�͐l�ԂƓ��l�ł��邪�̂͋��̉����̓C�������A�C(�A�h���A�C�H)�ŕߊl���ꂽ�B�݂ɂ��ǂ�オ��A�߂��ɂ���������߂炦�悤�Ƃ������A�t�ɑD���B�ɒǐՂ���A������ꂽ�ɓ����萅�ۂŗ��������B(���l�̎p�ŁA��≷�a�ȕ\��̊C�̉�����1523�N11���R���Ƀ��[�}�ł��ڌ�����Ă���B�傫���͂T�A�U�Ύ�)���̉����ɂ��Ă̑哇�̐����͂Ȃ��B�}���f�����Ă��邾���ł���B
�@�哇�͂܂��u�a���O�ː}��v�̐����������A�u�A�����J�E�C���f�B�A���v�Ԃɂ�����قǐ��E�I�ɕ��Ղł���l������̖{�̂͑����̉���(�I�b�g�Z�C�A�����̋���)������Ă������A�u�ț{�̐i���Ƌ��ɁA�Â��z�[�}�[�̕���Ɍ��͂�Ă��l���̖{铂͍g�C���ʂɐ������Ă��C���̈��ł���Ƃ��ӂ��Ƃ������ɂ����₤�ɂȂ��v�Ǝ咣����B�����ĊC���̐������s���Ă��邪�A�u�}�i�e�B�[���T���h�~���S�ɐ������邱�Ƃ����߂Ĕ��������̂̓s�G�g���A�}���e�B�[���A�A���M�G���ŁA���͈�܂O�O�N�̂��Ƃł����v�Ƃ����L�q�͒��ڂ����B��́u�l�ʋ�铂̉����v�ł́u�����ܕS�N�̐̂ɁA���C���h�����Ƀ}�i�e�B�[����邱�Ƃ����B�ɒm���Ă��܂��v�Əq�ׂ��ɂƂǂ߂Ă������A�����ł͕҂̖��������Ă���B�C���̑c�於�́u�G�E�Z���C�f�X�v����u�G�I�Z���A���v�ƂȂ��Ă���(�G�W�v�g�Ŕ������ꂽ�n�V���ɐ������A���ՓI�Ȍ㎈���Ƃǂ߂Ă���G�I�e���C�f�X��Eotheroides�̂��Ƃł���)�B��̕��͂ɂ͂Ȃ������C���ނ̓������ł̎���Ɋւ����������Ă���B����ɂ��Ɠ������ւ̎��e�̍ŏ��́u������Z�\�N�O�Ƀ����h���������v�ōs��ꂽ�B����Ȍ�r�₦�Ă������A�ŋ߂܂������h���������Ƀg���j�_�[�h���ŕߊl���ꂽ���Y�̃A�����J�E�}�i�e�B�[���o�ꂵ�l�C���Ă���Ƃ����B�a�͊C���ł͂Ȃ����^�X��^���Ă����B
�@�哇�͂��̔N(���a10�N)�̉āA�Ί_����K��Ċ��쎢(1869�`1937�A�Ί_��������)����̊������ꂽ�B���͐Ί_���ŕߊl���ꂽ�V���S���̎ʐ^�������Ă������A��������ɕ����Ă��炢�A�Ȋw���ɍڂ��Ă���B��p�암�̃W���S�������{����V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ��t�������Ă���B���ꂩ�牝�Â̐V�铇�ł̃W���S�����̗l�q�ƁA�����́u�C�V���E�k�E�I���v(�U���̋{�E���̋{�B�W���S���̓����߂Đ_�̂Ƃ��A���͂��W���S���̍��ЂƐő������_���߂��炷�j�ɂ��ďq�ׂ�B����ɁA����P(1858�`1930�A���ꌧ���_�w�Z�Z��)���U���̋{�ŕW�{���W�߂��Ƃ���ē��҂ɐ����ꂽ�G�s�\�[�h������Ă���B�哇�͊�肩�瑗��ꂽ�s�V�����̖���̔�͎���H���邱�ƂȂ��A�u�l���̛�铂̈ꕔ�������W�{�Ƃ��Ē�����������v���Ƃ̌��ӂ����A���̕��͂��I���Ă���B�u�C�̈����v�A�Ί_���ŕߊl���ꂽ�W���S���̑��ɓY����ꂽ�ʐ^�͂S�t�B�}�i�e�B�[�̉���A�����̗��ʁA�W���S���̓������i�ƈ�̉�ł���B
�@���āA�哇�����[���b�p���E�ւ̃}�i�e�B�[�̑��҂Ƃ��ċ����Ă���u�s�G�g���A�}���e�B�[���A�A���M�G���v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȑl���Ȃ̂��낤�B�u�s�G�g���A�}���e�B�[���A�A���M�G���v��Pietro Martire d'Anguiera����d'Anghiera(���e����Petri Martyris Angli�A�X�y�C����Pedro Martir de Angleria)�̂��ƂƎv����B1456(57)�N�A�k�C�^���A�A�A���[�i�̐��܂�B���[�}�Ŋw�сA�X�y�C�������Ɏd���A1501�N�ɂ̓C�U�x�������̗�q���t���i�ՂƂȂ�B�J�����X�P���ɂ��1518�N�C���f�B�A�X����@(�V�嗤�A���n�^�c�̂��߂̑g�D)�̈ψ��ɔC�����ꂽ���A����ȑO����L�^�҂Ƃ��ĊW���Ă����B�s�G�g���E�}���e�B�[���͐V�嗤�Ɏ���s�������Ƃ͂Ȃ����A�R�������n�߂Ƃ���q�C�҂炩��̏������Ȃ̌`�ł܂Ƃ߂��w�V�嗤�ɂ��Ă̏\���̏��x(De Orbe Novo Decades)�����B��̏���10���ō\������A�ŏI�̑�W����1530�N�ɏo�ł��ꂽ�B��R���܂ł͒��҂̓��ӂȂ��ł͂��邪1516�N�Ɋ��s����Ă���B���̂R���܂ł̏��������j��w�V���E�ƃE�}�j�X�^�x(�u�A���\���W�[�V���E�̒���Q�v�A��g���X�A1993.3.15)�ł���B
�@����pp.204�`206�Ƀ}�i�e�B�[�̋L�q������B�u�O�㖢���̋����ׂ��C�̋��v�u���Z���������}�i�e�B�[�Ƃ�ԋ��勛�v�́u�T�̂悤�Ɏl�{���Ȃ̂����A�ƂĂ��Ȃ��ł���ɍb���Ȃ�ʗ����Ă���B���������ċ|�������邱�Ƃ��Ȃ��A�����̓ˋN�Őg�����B�w���͕���ŁA�����͂܂�ŋ��̂��ꂾ�B���̋��͐��������ł��ƂȂ����A�̂�т艮���B�v�}�i�e�B�[�̎q����Ԃŕߊl�������n�́u��́v�́A�����Ԏ���ň�Ă���A�߂��̌ɕ������B�������ČĂԂƏo�Ă��āA�傫����������Ɛl��w�ɏ悹�Č������݂ɓn�����Ƃ܂ł���悤�ɂȂ����B25�N�ԁA�l�ԂƐe����ł������A�n���P�[���ɂ���^���ŊC�ɗ�����Ă��܂����B�y�h���E�}���e�B���́u���̃}�i�e�B�[��̋����͔������������ŁA������̊C�ɂ�������v�Əq�ׂĂ���(��O������)�B�G�X�p�j���[����(�n�C�`��)�̃o�C�m�[�A�n���ɂ��ĕ��������ɍڂ��Ă���B
�@�b�͑哇���痣��邪�A�}�i�e�B�[�ɂ��Ă̏������J���ƁA�H�p�̑��ɑ��̕��ʂ̗��p�@��t�H�[�N���A���Љ��Ă��ċ����[���B�p�g���V�A�E�R���K���́u�}�i�e�B�[�͎��Ȑ���ŁA�������鎞�ɂ͊Q���Ȃ��悤���ʂ̂܂��Ȃ��̌��t���K�v���v�u��A�����J�̂��镔���̓}�i�e�B�[�͖��@��������ꂽ�l�ԂŁA��̒�̒��ɏZ��ł���v�Əq�ׂĂ���(Patricia Corrigan,�gManatee Magic for Kids�h, 1996)�B
�@�V�����@�[�X�^�C���́u��A�����J�̐鋳�t���̓}�i�e�B�[�̎��ɗp�����B�X�y�C���l��́A�}�i�e�B�[�̎����ɂ͖��@�̗͂�����A�ӂ��ĕ���ɂ��ĕ��p����ƒɂ݂����܂�A�w�ɂ�a�炰����A�J���~�点�邱�Ƃ��ł���A�ƐM���Ă����B����Ăł͍����ł��������Ƃ��Ď�����g�ɕt���Ă���v�ƕ��Ă���(Alvin, Virginia, and Robert Siverstein and Laura Silverstein Nunn, �gThe Manatee�h, 1995)�B
�@16���I�̃K�X�p�[���E�f�E�J���o�n���_���́u�}�i�e�B�[�̔琻�̏|�Őg�����Α�|�̖���˒ʂ��Ȃ��v�Ɠ`���Ă���B�܂��A�u��̓J�k�[�ɂ͂��A���͍d���ďd���̂Ş��_��Ȃɉ��H���ꂽ�B�����̕��͈��p�̑��ɈݒɁA���Ă��A�l�ɂ̎��z�܂Ƃ��Ďg���A���[���b�p�l�͏ۉ�̑�p�Ƃ��đ����p�ɗp�����v�Əq�ׂĂ���̂̓N���@�E�v���C�X�|�O���t�ł���(Claire Price-Groff, �gThe Manatee�h, 1999)�B�v���C�X�|�O���t�́u1643�N�ɃI�����_�̉�Ђ̓M�A�i����}�i�e�B�[�̓����J���u�C��̍��l�z��p�̐H�ƂƂ��ĉ^�����n�߂��B1660�N�܂łɁA�N��20�ǂ̃I�����_�D���}�i�e�B�̓����^��ł���v�ƋL���Ă���B�}�i�e�B�[�̓����}�i�e�B�[�̎��ŗg�����H�ו���mixira�ƌĂ�Ă����B ���A�t���J�A�J�����[���̋��t�̓}�i�e�B�[�͐�̓��A�ɐ��݁A�l���Ɉ�������ēM��������ƐM���Ă����B���������A�t���J�̂��镔���̓}�i�e�B�[��l�̐��܂�ς�������̂ƌ��Ȃ��A�}�i�e�B�[���E�����j�͂R���ԉƂɂ�����A���̊ԏ������͖閾����������܂ʼn̂��̂��A�������}�i�e�B�[�̗���Ԃ߁A���̌�A�}�i�e�B�[�̓��͐�c�̗�ƕ����̊e�ƒ��ɕ��z���ꂽ�Ƃ����B�j�J���O�A�̃��[�}���̓}�i�e�B�[���̌�ŁA�}�i�e�B�[�̌���S�g�ɗ��сA���̌㍜���E�����ꏊ�ɖ߂��A���̎��̐��ʂ�O�����Ƃ����B
�@�W���S���̍����}�i�e�B�[���l�̌��\�����҂���A�]�ˎ���̓��{�ł��p����ꂽ�B�܂��A�W���S���̗܂��W�߂ěZ��Ƃ��ėp�����̂̓}���[�V�A�ł������B�W���S���̎���������M�����A�X�������J�ł͐ԗ��ɁA�}�_�K�X�J���ł͔畆�a�ɗp����ꂽ�B
�@�W�F�C���Y�E�p�E�G���͊C���ނ̃t�H�[�N���A�ɂ��āA�u�C���̐�����ł́A�l�X�͏����A�Đ��Y�A�����A�H�ƁA�D�P�A�q���Ɋ֘A����_�b�╨��ɊC�������т��Ă���v�Əq�ׂĂ���(James Powell, �gManatees�FNatural History & Conservation�h, 2002)�B
�@�Ȃ��A�J���u�C�����̃}�i�e�B�[���ŋ����[���������Ƃ́A���{�̉L�A�����̃J���E�\���g�������@�̂悤�ɁA�R�o���U�������炵�āA���̋z�Ղ̗͂Ń}�i�e�B�[��C�T�A��^���ނ�ߊl���Ă����Ƃ����b�ł���B�I�r�G�[�h(1478�`1557)�����̒��w�C���f�B�A�X�̔������Ȃ�тɐ����j�x�̑�13���œ`���Ă���B�I�r�G�[�h�͎������̑��a�Ɍ����Ƃ��`���Ă���B
�@�C���ނ̃t�H�[�N���@�ɏڂ����̂��W�F�t�E���v�����A�h�D�[�O�E�y�����ʐ^�w���E�̃}�i�e�B�[�ƃW���S���x(Jeff Ripple, Doug Perrine, �gManatees and Dugongs of the World�h, 1999)�ŁA���̑�S�͂́u�_�b�A�����̊C���v(pp.87�`105)�ł���B�}�i�e�B�[�A�W���S���֘A�̎��ۂ̑O�ɒZ���l���`���ɐG��Ă���B�n���C�����n���̐_�i�Ɏ����ŌÂ��L�q�̈�Ƃ��ă��K�X�e�l�[�X�������Ă���B�I���O300�N���A�V���A�E�Z���E�R�X������C���h�E�}�E�������̃`�����h���O�v�^�̋{��ɔh������A�A����u�C���h���v�����M���V�A�l�ł���B���v���̓��K�X�e�l�[�X���X�������J�̃^�v���o�l�[���ŏo����������̋L�q�Ƃ��āu�����̂悤�ȊO�ς����A���̑��̑���ɞ��������Ă���v�Ƃ����`�ʂ�`���A�W���S���̂��Ƃł��낤�Ƃ��Ă���B���K�X�e�l�[�X���l���L�q�Ɋ֘A���Ă��邱�Ƃ�19���I�̃C�M���X�̐A���n�s�����G�}�[�X���E�e�l���g(1804�`1869)�̒��w�Z�C���������R���x(J. Emerson Tennent, �gSketches of the Natural History of Ceylon�h, 1861)�ł��q�ׂ��Ă���B�X�������J�ɎY����M���ނ̋L�q���ɃW���S���̍�������A�����ł̓��K�X�e�l�[�X���C���̉������ŏ��ɕ��A�A�b���A�m�X(�A���A�k�X�A95?�`175?�A�Ñネ�[�}�̐����ƁA�u�A���N�T���h���X�����L�v�u�C���h���v�Ȃǂ̒��q������)�����P�����ƋL���Ă���B�e�l���g��1560�N�ɃS�A�ʼn�U���ꂽ�u�l���v��t�@�����e�B��(�I�����_�鋳�t�A1666�`1727�A�w�V�����C���h���x[1724-26]�̒�������)�̃A���{�C�i�́u�l���v�ɂ��G��Ă���B���̂�����̋L�q�͓���F��(1867�`1941)�́u�l���̘b�v(1910)�̏�ł��낤�B
�@�}�i�e�B�[���o�N�Ɗ֘A�Â��Ē���Ăł͔F������Ă��邱�Ƃ����v���͓`���Ă���B
�����E�m���̐��b�ł͕v��S�������o���͈ꏏ�ɕ�炵�Ă��������_���₦�Ȃ������B������A���q��A��ĐX�ɍs�����o�����̂̂���ƁA�e�q�͍ŏ��̃o�N�ƂȂ�A�̂̂���������͐��ɏZ�ނ͂߂ɂȂ��āA�����̂Ȃ��̎q�Ƃ��ǂ��ŏ��̃}�i�e�B�[�ɂȂ����Ƃ����B�j�J���O�A�̃��[�}���̐��b���}�i�e�B�[�ƃo�N�̊֘A���番�͂����̂͐l�ފw�҃t�����N�����E���������h�ł���ƁA���v���͏q�ׂĂ���(Franklin O. Loveland, �eTapirs and Manatees�FCosmological Categories and Social Process Among the Rama Indians�f1976)�B���������h�ɂ��ƁA���[�}���͐�A�͌��A�J���u�C�ɗאڂ����X�тɋ��Z���Ă��邪�A�ޓ��̓}�i�e�B�[�������A�D�ꂽ���o�̎����傾�ƌ��Ȃ��Ă���B���[�}�̐l�X�̓}�i�e�B�[�̐����ꏊ����ɂ��Ă̘b���ނ�ł���B�}�i�e�B�[�������Ă��āA���̗��������̂�����邩��ł���B���̂悤�ɁA�}�i�e�B�[�͐Î��Љ�K�́A�����̂܂Ƃ܂�Ƃ��������I�ʂ̏ے��Ƒ������Ă���ƃ��������h�͍l�����B���������h�������������̂�1969�A1970�N�Ȃ̂ō\���l�ފw�̉e�����ɂ���ƂȂ��Ă���悤���B�����Ɨ���ΑΔ䂳���͎̂��R�A�쐶�ł���B������ے�����̂��o�N�ł���B�}�i�e�B�[���ɂ͑����̃^�u�[�����邪�A�o�N���ɂ͐����V���͕K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��B�}�i�e�B�[�̎E�Q�A��́A���z�ɂ͍אS�̒��ӂ������A�����̂̏d�v���ł���B�}�i�e�B�[���E�������ӂɂ͍����߂���A���͏Ă���A���₩�ɐH����˂Ȃ�Ȃ��B���[�}�̐l�X�͂܂��A�}�i�e�B�[�����͋���Ȉꓪ�̌~�̕ی쉺�ɂ���A�Q������͈̂�݂̂ɂ����ƐM���Ă���B���͕����ő��h����邪�A�}�i�e�B�[�̓��͌��ɂ��Ȃ�(���U�ōŏ��Ɏd���߂��}�i�e�B�[�̐S�����߂̓��͗�O�I�ɗ^������)�B�ʏ�͎�����Ɛ�I�ɗ^������B�����̊l���������@�m���Ȃ����߂̂܂��Ȃ��Ƃ��āB
�@�����Ɋւ��ă��v�����`���Ă���͈̂ȉ��̎���ł���B���J�^���ł͖��@�����̎A�j�J���O�A�̃~�X�L�[�g���ł͕s�^������邽�߁A�p�i�}�A�O�@�e�}���ł͐w�ɂ�a�炰�邽�߁A�����̃C�M���X�l�A���́A�ӂ��đ��₩�ɋ�݂̈ɓۂݍ��߂��l�ɁA�ԗ��̓�����A���F�l�Y�G���ł͎q���̉����⎕�ɂ̗\�h�A�����E�m���ł͎Ꮬ���ɏ��N�͎��́A�����͗Y�̃}�i�e�B�[�̎�����g�ɕt����A����ɒ����ł̓W���S���̎��������͐t�������ꂢ�ɂ���ƍl�����Ă����B
�@䥂ł��}�i�e�B�[�̔���������ɍ����Ĉ��p����ƚb��������A�D��ɂ��ėp����Ή����\�h�̌��ʂ�����Ƃ����B���̓J���u�n��ł͊I�̑��H�ɂ������s�ǂ̖�A���F�l�Y�G���ł͔~�łɌ����ƍl�����Ă����B
�@�C���ނ����͐l�Ԃł������Ƃ̐��b�������̒n��Ō���Ă����B�}�i�e�B�[��J���C���J���I���m�R��Ɉ��������ꂽ�l�ԂŁA���̉ƂŐH����H�ׂ����ʕϐg����̂��ƐM�����Ă����B�ϐg�����l�Ԃ��}�i��(manari)�ƌĂԂƃ��v���͋L���Ă���B�g���u���A���h�����̃W���S����������t�����ꖺ���ϐg�����p�ŁA�W���S�����ɂ͍������g�����S�����A�ߊl��͂��̍����ŕ@�E�������������������Ƃ����B�p�v�A�ł͔D�w���W���S�����Y�݁A�C�t�����v���W���S����˂��h�����Ƃ���ƁA�u�Q�T�ԍȂƂ̓����T���˂A���͏o���Ȃ��v�ƃW���S���Ɍ���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B
�@�哇�����̐l���L�q���炾���ԗ���Ă��܂����B�哇�̎O�Ԗڂ̕��͂͒����V���[���́u����������H�@�������̂̐_��v���ŁA�ǎ҂̎���u�l���̐��̂����m�点�������v�ɓ��������̂ł���(���a28�N12��20���A�[����Q��)�B�哇�����ƃ��[�W���E�o�[���Y�̏���������A�}�i�e�B�[�̐}���Y�����Ă���B�u�C���Ƃ����C�b�͎q���𗼎�ł������ď㔼�g���C��ɓ˂��o���A�g�̂܂ɂ܂ɕ�����ł��邱�Ƃ�����܂��B���̎p����������Ȃ��߂�ƁA�����ɂ��l�ʋ��̂̉����Ɍ����܂��B���ꂪ���l�����Ƃ��Č��`����ꂽ�̂ł��v�ƒf�����Ă���B�����ł͎q���������p�͔ے肳��Ă���B�͊C�� �ɃW���S���ƃ}�i�e�B�[�̓�킪����A����̃W���S���u�U���m�C�I�v�͗������ɕs�V�����̗��Ƃ��Č��コ�ꂽ���ƁA�����ł͐l���l���������Ă��邱�Ƃ��q�ׂĂ���B���܂ł̑哇�̐l���L�q�̚��O�̏��͂Ȃ��B���̓��̂��̑��̎���́A�E�T�M�̖ڂ͂Ȃ��Ԃ����A�Y�����̍��̗Y�̐�[���Ȃ����Ă��錴����q�˂Ă���B
�@�}�i�e�B�[�ɒE�����āA�哇�����̉ƌn�ɂ��Ă͐G��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�e�����߂Ă�����B
by�C�V����(aka. MORO)
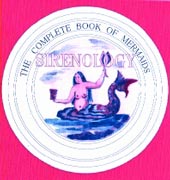
�@���⋱��u�l�����m�v�ƌĂ�Ă������ƂɌ��y�����̂͏����a�ł������B�u���Y�t�H�v���a15�N�W����(��18����11��)�A�����a�u�l���̖��v(pp.310�`314)�ɂ́A�u�l�����m�Ɖ]�͂�镽�⋱�������A�l���𛉍ۂɖڌ��������Ƃ��r���H�B���̓��𖡂ӂɎ��ẮA�w��ǐ�]�Ƃ��ցA�c�Ă����ł͂Ȃ����v�Ƃ�������������B���M���A�����a(���ɂ����̂��A1873�`1947)�͖����}�ږ�B���ꏄ�V���ɐΊ_���̗����ŃW���S���̓���H�ׂ����Ƃ������Ă���B������u�l�����m�v�ƌĂԂ̂́A��k�鍑��w��������ɃW���S���̌��������Ă������Ƃɂ��B�W���S���͌��݁A�������ی�@�̍��w��V�R�L�O���ł��邪(1972�N�w��)�A��O�̏��a�T(1930)�N�ɂ��j�Ֆ����V�R�L�O���ۑ��@�ɂ�荑�w��V�R�L�O���ƂȂ��Ă����B����A��p�̃W���S���͕ߊl�A������̝����͋֎~����Ă����̂ł���B����ł��A�����̋q�����ɃW���S���͐U�镑��ꂽ�̂ł���B��l���͍ŏ��A���̐��̂𖾂��������ǂ���畏������悤�����A�u����͐l���ł���v�Ɠ`�����B�����͖��ł��~�ł��Ȃ��A����Ƃēł��Ȃ����Ɍ˘f�������A���ɓ���A�u�ʂɕs���Ƃ��Ӓ��ł��Ȃ����A����Ƃđ�w�Ȕ����Ƃ��S���Ȃ������v�Ɗ��z���L���Ă���B
�@�����a�͖����U(1873)�N���쌧���܂�B����27�N�A�D�y�_�w�Z���ƌ�A�k�C���J��ɏ]���B���̌㓌�������V���Ђɓ��ЁB����44�N12���A986�ł̑咘�w���˓��C�_�x(�����X)�����s�B������45�N�A�O�c�@�c���ɏ����I�A���̌�V��̓��I���ʂ����B���̊ԁA���������@�̐���ɐs�͂����B���ۑS�╶�����ی��͐����Ă����������W���S�������ɂ��鎖�ɂȂ��Ă��܂����̂́A���������s�{�ӂł͂������낤���A�u�l���̖��v�̕����ɂ́A
�l���̕ی�A�אB��ׂ��A�ߊl�̋֎~��O��I�ə��s����݂̂Ȃ炸�A���̐���������V�R�̂܁T�A�i�v�ɕۑ����ׂ��A�Ќł���𝘘������߂���₤�v�]���Ď~�܂ʂ��̂ł���B
�Əq�ׂĂ���B
�@�l���̓��������ꂽ���Ƃ���ی�̗v�]�܂ł̊ԂɁA�����͐l�����W���S���ɂ��Ēm�蓾�������J���A����̊����܂Ŕ�I���Ă���B���r�����Ƃ͒������̂ŁA���p���Ă݂悤�B
��l�f�B�@���Ŕ���B
�Ȏ����c�Z�B�@����T�M���B
����݉��F�B�@�V���ٖ��ɁB
�������p铁B�@�H��ᢈ��߁B
�������s�^�B�@������C���B
�@�������`����W���S�����́A����ł̗l�E���p���@(���͋ߔN�̖��̑�p�Ƃ��Ďg�p)����n�܂�A����t��������l���A�P�[�v�^�E���̔����ق̐a�m�Ɏ������l���A��m�ł̃W���S���̗��p�@�A�W���S���̌`�ԂȂǂɋy��ł���B�P�[�v�^�E���̐l���Ƃ́A�����p���ɂ��āA�X�q�A�m���𒅂��Đa�m�Ɏd���ďグ���A�����̌��t�����p����u�l�Ԃ̎p�ɝ̌`�����l�����{�c�g�v�̂��Ƃł���B���łɓ���ނ��w�����d��杁x(1926.11)�Ő}�������ďЉ�Ă�����̂Ɠ����ł���B����́u���S�\��N�ɃA�t���J�̃P�[�v�^�E���ŕ߂炦�����͊炪�l�Ԃɂ悭���Ă��̂ŔV���C�̘V���ƌĂB���̋��ɖX�q�����Ԃ��m���𒅂��t�������͂�������Ɨ��h�Ȑa�m�̎p�ɂȂ��B���͂ǂ����̔����قɟk�Ă��v�ƋL���Ă���B���̐l���̌��͓���͋��ނƂ��Ă��邪�A�W���S���̉\�������낤�B
�@�������`�����m�ł̃W���S�����p�ŋ����[�������́A�W���S���̔S�t�������ƂȂ�Ƃ����Ƃ���ł���B�Z���x�X���암�̃}���[�n�C�m���u�M�X�́A�W���S���̔畆���番�傳���S�t���̂��āA�g���E�R�[�q�[�ɍ��������Ĉ��܂���ƁA���l�ɂ��邱�Ƃ��ł���ƐM���Ă���B���̕��K�ɑ��鏬���̉��߂͋ɂ߂č����I�Ȃ̂��̂ł���B�u�S���I�ɁA�܂����M�I�ɁA���܂��������K���������āA������ɛ����A�M���㫂߂Đڋ߂��A�v�����邽�߂ɁA��������A����g���������邱�ƂɂȂ�̂ł��낤�v�Ɛ������Ă���B
�@�������ی�̓_�ł́A����{���E�����ߊC�̃W���S���́u�w��ǐ�łɋ߂��v�Ƃ��A���\���ʂɁu�����̏o��������v���x���Ƃ��Ă���B��p�ł͏��a�V(1932)�N�A���Y�B�P�t���̊C�݂ŕ߂炦��ꂽ�R���̗Y�̂��ŏ��̐����ƂȂ��Ă����i���⋱��ɂ���������j�B�����́u�����ɓK����n���I���������������A��p�ɂ������ɕ��z�̋��悪������̂ƍl������v�Ƃ��Ă���B���E�I�Ɍ��ăW���S���́u�l���̔��B�v�A�u�l�̊�@�v�ɂ��u�����ׂ����ȂāA�Q���̈�r��H���āv����ƕ��͂��A�����J���ی��i���Ă���B�����̓W���S���ی�̐��҂̈�l�ł������B�����A�ی�̑Ώۂł���W���S�����̂��̂̌����͕���Ȃǂɂ��[�����J���ꂽ����ł������B
�@���⋱��(�Ђ炳�����傤����)�͖���20(1887)�N12���Q���A��������B����44�N�A�����鍑��w���ȑ�w�����w�ȑ��ƁB�����攪�����w�Z�����A��p���{�����_�ъw�Z�������o�āA���a�R�N�A�V�݂��ꂽ��k�鍑��w���_�w�����㋳���ƂȂ�B��̓����ɏڂ����A�C�m�����w�S�ʂɍL���m���������A�n�������w�A�����w�j���u�����B���͏��a24�N�A�V���V����w���w�������ƂȂ�A���w�������ՊC�������̏��㏊�������߂��B���a34�N�A�V����w�ސE�B���a40�N�T���V�������B���w���m�B
�@����ɂ��Ă͐V����w����̒�q�ł���A����̗ՊC���������߂��{�ԋ`���������̕��͂������Ă���B���̒��ŎQ�Ƃł������̂́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�u���⋱��搶�Ɛіژ^�v�A�u�V�����������猤����v��R���A1966.6.5�App.92�`97
�u�̕��⋱��搶�̊C���M���ނɊւ���Ɛт��߂����āv�A�u�V�����������猤����v��31���A1996.3.28�App.53�`59
�u���⋱��搶�̊C���M���ތ����v�A�u���{�C�Z�g���W�[�����v��12���A2002.4.30�App.35�`40
�u���⋱��搶�̊C���M���ތ����|�W���S���v�A�w���{�C�̃N�W�������x�A2003.9.1�App.59�`62
�@�{�Ԃ͕���̊C���M���ނɊւ���Ɛт����̌����҂̘_���Ɉ��p����邱�Ƃ����Ȃ����Ƃɕs���������A��L�̘_�������ɂ����B���ɃW���S���A�R�}�b�R�E�ɂ��Ă͕���̌�������s���Ă���̂ɁA�w�ǖ�������Ă����悤�ȏ��c�O�Ɏv���Ă����B�����ł́A�{�Ԃ̘_���Ɉˋ����A����̃W���S�������ɂ��ĒH���Ă݂悤�B
�@���a�U(1931)�N�P��18���ߑO10�����A��p�̓�[���A���Y�B�P�t�S�P�t������[�̉��݂ŁA�����̋��t���C�ݐ��t�߂ňꓪ�̊C�b�����j�E�����B�牺�̎��b�͌����A���͏㓙�̓ؓ��̂悤�Ŕ����B����ȊC�b�̓��͋��ƎҁA���ݏ�����ɕ��z���ďܖ������B����ɂ��̊C�b�ߊl�̂��Ƃ�m�����P�t�S���Y�W�͂��ݎ̂ďꂩ�瓪���A���{�A�̘]�����������k�鍑��w�����̕��⋱��̌��֑����Ă����B����͊C�b���W���S���i�����̊w���ŁAHalicore dugong(ERXLEBEN)�j�ƒf�肵�A�p���̕������M����(�eThe occurrence of dugong in Formosa�f, 1932)�B����͂��̎������W����{�����w�E���ōu�����A�v�|�́u�����w�G���v��45����532/533��(1933.3.15)�Ɂu�i�s�Ɏ�(Halicore dugong(ERXLEBEN))�̎Y���鎖�ɏA���āv�Ƒ肵�Čf�ڂ���Ă���(pp.106�`107)�B���Ƃ��ĉ�̏���ꂽ��Ȃ̂Ō`�Ԃɂ��Ă͋��t�̋L������Č����ꂽ���̂ł��邪�A����͎��̂悤�ɕ��Ă���B
�O�`�͔��h�A���h��L�����̔@���œ��[�͓Ɏ��āA���[����ɂ��ĕ@�E�͏�ʂɕ����ċ����B�ׂ���Ə��Ȃ鎨�������B�O���͂��̌`ꈍb�T�̎��Ɏ��Ē܂Ȃ��A�O�ڈʂ����B���͕��ʂɍ�����Ȃ����E����[�̊Ԋu�͓�ڈʁB�畆�͐����Ɏ�����F��悵�A�\�ʈ�l�A�e�ɍ��т��ċ����B���̌����͖�ꐡ�ʁB铒��͋�ڈʁA�����Z�ځA������������ړ�O���A铏d�͎l�S���P�ł����B
�@铂̕��ʂɂĊώ@���ꂽ���̂͋����ɓ���ꛔ�A�����ɜl�ʂ��`�A�����O��������ڈʂ̉A�s�����肻�̌������傪�����B
�@�̒�2.7m�A�̏d240kg�̗Y�̌̂ł������B���ꂪ��p�ɂ��W���S�����������Ă��邱�Ƃ������ŏ��̎���ł������B�]���A�t�B���s���A����ɃW���S�����������邱�Ƃ͒m���Ă����̂ŁA���̊Ԃ̋�ł����p�ł̊m�F�͂��Ȃ�x���Ȃ����B����́u���̌㒲�������|�ɂ��ƕK�������{���ɎY����H�L�Ȃ��̂Ƃ͉]���܂��v�Əq�ׁA���߂ɂ͂Ȃ��Q���قǐ������Ă���͗l�ł��邵�A��p���C�݂ɂ������̉\��������Ƃ��Ă���B�܂��A���a�U�N�S���ƂU���ɂ��P�t�S�ŕߊl���ꂽ�Ƃ����B��p�̃W���S���Ɋւ��ĕ���͌�Ɂu�v������i�s�ł͎�l���Ƃ͖��_�]�͂Ȃ����A����܂����������l���v(�u�����i�s�v�A1942.10)�Əq�ׂĂ��邪�A���a�W�N�̕ł́u�אl�̒��ɍ��̓������w���ɔ�Ɛ�����������̙B��������l�ł���v�ƋL���Ă���B
�@����͂܂��A�W���S���̖k���ɂ��ẮA�����哇�Ȗk�Ƃ��āA���v���畷�����b�Ƃ��ċ{�茧���Õ��߂̃V�r��d�Ԃɓ����Đ_�˂Ő��S���Ŕ���ꂽ��ƁA���a�W�N�T���̐V�����璩�N�S���k���S�R���ÌS�R���߂ŕߊl���ꂽ���Ƃ���Ă���B�������A���̐^�U�͍���̒�����K�v�Ƃ��邱�Ƃ�t�������Ă���B
�@��p�̃W���S���͉���E�����ɑ���������Ƃ��Ē��ڂ���A�V�R�L�O���̎w����A����ɂ��w�V�R�I�O�������@��P�S�@�x(�i�s�`�{�����ǁA���a�W�N)�����s���ꂽ(��p���{���s�́w�V�R�I�O�������x�͑�R�S���f�ؓ���[1882�`1970]���u�i�s�̒��ނɏA���āv�A��S�S�A�����M��E���c���u��r�ΊC�����сv�A��T�S�A�^�V���E�����L�i�u�i�s���n�Y���|����܂��܂��v�A��U�S�A�ؕ���Y�E���ΐV�g�u����E���Ӂv�ł���B�Ð����w�ґ����Y���u�D�ΎR�v�u�L���Αw�v�u�C�I�Ζ�v�����M���Ă��邪�A����炪��Q�S�ł��낤��)�B�����Ɠ����e�̂��̂́A�u��p���Y�G���v(��234/235���A���a�X�N)�Ɂu�A���u�l���v�ɏA���āv�Ƒ肵���\���ꂽ���A�c�O�Ȃ��疢���ł���B�{�Ԃ́u�W���S���ւ��铮���w�I���߁A�ߎ���Ƃ̌n���މ��A�e�n�̋��l�@�A���p�A�`�����ڏq�A�Ō�ɓV�R�L�O���w��Ɏ������ۑ��̗��R�V���ڂɂ��ĕ��Ă���v�Ƃ��̓��e��`���Ă���(�u���⋱��搶�̊C���M���ތ����v�A2002�Ap.36)�B�u��p���Y�G���v��286��(���a13�N)�ɂ�����́u�j���l���v���f�ڂ��Ă���B
�@�����a14�N�A����́u�Ȋw��m�v(��Q����Q���A���a14�N11��25��)�Ɂu�p���I�̎v(pp.11�`18)���ڂ��Ă���B���a12�N�Q��26�������A�p���I�{�����݃A�����m�O�C���߂ʼn���̋��v�̖Ԃɖ������ݒ����������̂��A���c���������߁A�M�ѐ����������Ŕ�ƍ������A�������������A�D�ւő�k�鍑��w�ɑ���A���i�W�{���w�����ɔ����邱�ƂƂȂ����o�܂��悸�q�ׂ��Ă���B���c��(1908�`1995)�͓����p���I�M�ѐ�����������(1935�N6���`1937�N6���A1938�N8�`11��)�Ńv�����N�g���w��(�w�C�ƃv�����N�g���x1944�N�A�w�����m�C�m�����̑��B�x1973�N�Ȃǂ̒���������)�A��ɖk�C����w�A���C��w�����ƂȂ�B
�@����u�p���I�̎v�̍\���́u��A����v�u��A�O�`�v�u�O�A���i(���@��ł̘b)�v�̎O��������Ȃ�A���}�Ƃ��Č��c�̎B�e�����S�̋y�ѕ����ʐ^�T�t�A�S�g���i�A�����̎ʐ^�A�W���S����ŌM�͂�����ɂ͂߂��p���I�̒j���̎ʐ^�Ȃǂ��Y�����Ă���B����l�͌��c�������炵����(254cm�̗Y)�Ɛ�쒷�Y�ɂ��Q�́A�ؕ���Y�ɂ��t�B���s���Y�̎��A�g�D�f�N�X���[�̃I�[�X�g�����A���C�ݎY�̎��Y�Q�̂̌v�U��̑̒��A���ʁA�ő���A�����A�����A���W�ˋN�A�A�A�O�����A�����A�@�E���A�@�E��蕫�A�@�E����A���莨�E�A�����O���A�������̐��l���f�����Ă���B
�@�O�`�Ɋւ��Ă͕��A���ӂɓ���������̂ŏڂ����A���c�ɂ��X�P�b�`���S�t������Ă���B���̐����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�ۂ̕@(proboscis)���c��|�́A�@�E����O�W�v��O���ɐ����ɂȂĂ�(�}�})�w��ǔn���`���Ȃ��A�A����(snout; Schnauze)�ł���B����ɂ��V�R�畆��ᰂ�����e�т�A���т��e���ɎU�����ċ���B��������Ɨ������ɑ��ӂČ����Ȑ[���a������B���E�̍a�̊O���ɂ͓��ɑ������т��p�����ċ���B���̗������Ȃ������͉������ʂɐi�݂ɏ]�Ĉ�w�悭ᢒB���ĕ����A���Ȃ�A�L������L���邱�ƐO�Ɏ��Ă��邩�炱��𑤐O�Ɖ]�ӁB����͗����Ɍ������āA���ĉ����āA�H�����W�ߌ��ɉ^�ԍ�p������B���ƍ��̕����͕��G�Ȃ�ؓ��ƁA�P�T�̂���畆�A�牺�@�ۑw��萬���X�Ȃ�`������鎖�����R�ł���A���̓����̑��e�ɑ��l�Ȃ�̉����o�ւ�B
���Ƒ��O�̉��ɂ͗Y���b�݂̂ɂRcm���̖厕����{���E�ɂ���A����́u�����ɗp����ʂƂ��]�ւʁv�ƌ����Ă���B
�@���ފw�I�ɂ́u�C�� �ڂ͊O�`�͌~�ڂɋ߂�����U�w�I�ɂ́A���@�ڂɋ߂��Ƃ���Ă��B����͍������d���Ō~�̔@�����j�ɓK����悤�䉻���ċ��Ȃ��B�i�����j���ɂ͈�����x�̒�������L�������̂�����A���ɋ߂��\���̕@�[����ւċ����Ƒz�������̂ł���B�v�Əq�ׂĂ���B�܂��A�C�� �ނ͎����I�ɗ���ɏオ�邱�Ƃ͂Ȃ��A�O���͗���Őg�̂��x���邱�Ƃ��ł����A�����Őg�̂���]�����鎞�A�H���������W�߂鎞�̗p�ɂ����Ȃ��A�Ǝw�E���Ă���B�]���āA�����ł̉^���̎�͔͂����S���Ă���ƋL����Ă���B
�@���i�ɂ��Ă͎ʐ^���f���邾���łƂ��ɒ��߂͂Ȃ��B�p���I�̐l�X�������ł����ɘΗp���Ă��邱�Ƃ͗L���ł��邪�A����ɂ��ăA���e���[�v���̑D���w�����B�E�E�B���\����18���I���̋L�q�����p���Ă���B�}�J�I���o�������A���e���[�v���̓p���I�̊O�ʂɏ��グ��j�����B�E�B���\���̓R���[���̑�U���ɉ������đ��̕����𐧈����A�퓬�̌��ɂ��A��U������ō��͂ł���W���S���̍���������ꂽ�B
�@���₪����l���r�������A�̘_�������Ă������B
�@��쒷�Y�́u�A���y�����v��U����U���ƂV��(���a13�N�U���A�V��)�Ɂu�p���I�̎ɏA�āv(pp.37�`41�App.49�`58)�\���Ă���B���\���͓�m�����Y������ɋ߂Ă����B���͓��{�ϔC�������́u��m�Q���v�ł́A�W���S���̓p���I�����݂̂ɕ��z���݂���Əq�ׂĂ���B�p���I�����́u��m�Q���v�̐�����Ɉʒu���A���̐����̓|���l�V�A�A�p�v�A�A�t�B���s���̏��v�f��������ȕ��z�������Ă���B�W���S���͎�Ƀp���I�{���A�y���������̃T���S�ʓ��ɐ������Ă���B�����̃p���I�x���ɂ��V�R�I�O���ی�̉��A�ߊl���֎~����Ă������A����ȑO�ł͖��N�ꓪ�͕ߊl����Ă����悤�ł���B���a12�N�ɂ͂S���̕ߊl���m�F����Ă���B�ꓪ�͌��c������ɉ������đ������́B�����łV��16�������A�p���I�{�����݃A�C�~���[�L�̏ʌ���œ�������ő̒�2.48m�̎��A�X��27�������A�����n�_��1.19m�̗Y�̗c�b����͂���ŕߊl���ꂽ�B���݂̃J�C�V�����̏ʌ���ł��ߊl���������B
�@��ł���r�ւ鉝�Â���̃W���S�����ɂ��Đ��͕��Ă���B�U������W���S�����̖�������ƁA�N��ɂ��敪�ł��鏭�N�E���N�E�V�N�̑g���̓��̈�͑��̏W���ɉ������߂��A�����番������A�H���A�����̋����ɒu�����B���ɂ͒���60�`80m�A��4m�A�Ԗ�30cm�̞��q�̎��̑@�ۂō�����u�r�e�v�N�g���v�Ƃ������h�Ԃ��p�����A�g�����͑�^�̐퓬�J�k�[�Q�ǁA���ʂ̃J�k�[�U�ǂɏ�荞�ݖ�ԂɌ��s�����B�U�ǂ̃J�k�[����s���A�W���S���̔�����A�ޘH���Ւf����B����̐퓬�J�k�[�ɂ͖Ԃ��ς�ł���B�Ԓ��ɃW���S����߂炦��ƁA�j�B�͊C�ɔ�э��݁A�퓬�J�k�[�Ɋl���������グ��B�W���S�����m�ۂ����ƁA���ɏ]�������S�����C���ɐZ��g��G�炷�B�W���S����ςD���͟F�P����������f���A�@���L��炵�A�҂���B���Ɏc�����l�X���~�ɋ��̐������F��A�l�Ɍ}�����l�X���g���C���ɔG�炷�B
�@�W���S�����œ����l���̈ꓪ�͏U���̂��̂ƂȂ�A���̑��͔��p�����B�p���I�̉ݕ����̓��{�~�Ɋ��Z���A���͂T�炩��X��~�Ƃ��������Ȑ����������Ă���B���ɂƂ��Ă͐푈�ɂ��C�G����A���̂悤�ȃW���S�����͖������N���炢�܂ő����Ă����Ƃ����B���̌�̓_�C�i�}�C�g�ɂ�鋙�A��ɂ�鋙�Ɉڍs�����B�W���S�����p����͓��{�l�b�艮�����삵���̂Łu�J�a���T���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�W���S���́u�J�a���T���v(����223cm�̕��ɁA�S������126cm�E�a�Pcm�����A50�`70m�̍j���t��������)���g�p�����l�A�T����l�A�J�k�[��ǂŕ߂炦�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@���͓̃W���S���̑���l����Ă��邪�A�̒�248cm�̎��̌̂̏����ǂ̑S����34m�A�̒���14�{����A�A�W���i�H���j�ŏ[������A�ݒ��ɂ͉�30���قNJ��Ă����B�W���S���̗c���͕�e�ƍs�������ɂ��A���[�ɂ����݂����܂܊ɂ₩�ɟ��j����Ƃ��q�ׂĂ���B���̏�ŁA�u�����Ɍ�����@���A���h�Őg铂��x�ցA�ǂ��|�ŏ㔼�g���C�ʏ�ɏo���āA�M�����Ă�����i���������̂͂Ȃ��B���T�邱�Ƃ��]�͂��l�ɂȂ��̂͋��炭�������l�������[�l�I�ɍl�ւ��ׂł͂���܂����v�Ǝ咣���Ă���B
�@�p���I�ł̓W���S���͕�e�̌����������Ȃ����������ϐg�������̂ƐM�����Ă����B���̓`�����N�����������ł̓W���S����߂炦�邱�Ƃ��A����H�ׂ邱�Ƃ��ւ����Ă���B�p���I�ł̃W���S���̖��̂́u���Z�L�EMesekiu�v�ł��邪�A���̈Ӗ�����Ƃ���ɂ��Đ��́A
���Z�L�E�Ƃ��Ӗ��̂͑O�q�̙B����萶�܂ꂽ����Mes�͌���Ƃ��ӈӖ�������AKiu�Ƃ��ӂ̂͐l�����������Ɍ�ē���ł��t�������A���������Ƃ��ӐS���̎��Aᢂ����ł���Ƃ��ӁB��������́u���̗l�Ȏp�ɂȂĕ�̉]�Еt�������Ȃ����߂��A���Ă�鎄�����ĉ������v�Ƃ��ӈӖ������͂��Ă��̂��Ɖ]�͂��B
�Əq�ׂĂ���B�C�ɓ����������A��ɂ̓P�A���̎����Ɋ��������̂����Ɋ܂ݖj��c��܂����Ƃ����A���̐��ł̓^���C���̉Ԃ��܂Ɠ`�����Ă���B���̈Ⴂ�ɂ���ă��Z�L�E�����ɕ�����A�P�A���̎��̂悤�ɉ��{���ۂ��c��Ă���W���S�����u���Q�G�����P�A��Burengeherrakeam�A��̌�����������ɂȂ��Ă���W���S�����N�~�[�� Kmier�A�܂��̓I�E�e���E�A�e���K�qOutelauatelngai�ƌĂ�ł���B
�@�p���I�̓������ɂ��Ă͍]���O(1899�`1957�A�����w)�A����q�Y(���Y�w)�̕�����B�u�Ȋw��m�v��P����R��(1939.3.20)�Ƒ�Q����P��(1939.6.15)�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�p���I�Q���̓�����(��)�v(pp.20�`29)�A�u�p���I�Q���̓�����(��)�v(pp.9�`15)�ł���B��쒷�Y�A������������͂��Ă��邪�A�]��̏��a11�A13�N�A����̏��a13�N�̃p���I�؍ݒ��ɒ��ړ�������̎悵�����̂����S�ɂȂ��Ă���B�M���ނ̕M���Ɏ�(�w���͌��s��Dugong dugon�ŕ\�L����Ă���)mesekiu���������A���̚M�������ł͔n�A�~�A�R�r�A���A�A�L�A���A���A���啁A���啁A�l�ɑ���p���I�ď̂�������Ă���B�]��̐��̍����͑��̈ȉ�32�킪���グ���A����bangikoi�̑��̂����邱�Ƃ�������B�G���u��m�Ȋw�v�͓��{�w�p�U����Ɠ���ɂ���Đݗ����ꂽ�p���I�M�ѐ����������ɂ�銧�s�ł������B
�@���ɂ��p���I�̕ł���P��ł̘r�ւ͐G����Ă���B�r�ւ̓I���E��Oreur�Ə̂���A�j�q�̌��J�͂ɗp�����A�U���݂̂�����������錠����L���Ă����B����r�ɂ͂߂邽�߂ɂ͎w�����Ō��сA��ɖ�(�J���}���̖̔�Ɨt�𐅂ɓ��Ꝙ�a���Ăł����S�t)��h�芊�炩�ɂ��A�߂������Ēʂ��B�����ɛƂ߂邽�߂Ɏw��畆�����邱�Ƃ��������B���������Ŕ������Ƃ̂ł��Ȃ����_�̒��ł������B�p���I�����ł��A�����̃A���K�E�����ƃJ�����K�����̏Z���́A�{���A�R���[�����A�y���������̐l�X����̎�����A�r�ւ𒅂��邱�Ƃ�F�߂��Ă��Ȃ������B�{���ł������ɂ�葕���ƁA�����_�O�ɋ����邾���Ƃ����悤�Ɉ��������قȂ��Ă����B���̕��_�ő������Ă����p���I�l�͏U������15�l�Ɍ����Ă����B���͘r�ւ̊��K���C���h�l�V�A����(�X���_�����E�e�j�o������)����`�������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
�@�Ō�ɐ��̓W���S���̕ۑ��ɂ��ĕ��⋱��̎咣�����p���āA�~�N���l�V�A�B��̕��z�n�ł���p���I�ł̕ی��i���Ă���B����̎咣�Ƃ͈ȉ��̂V�_�ł���B
�P�D�͉ߋ��ɉ��ĕ��z���A���A��ނ��������̂ł��邪�A�����ɉ��Ă͎�ނ��������A���z���ɂ߂Đ�������āA�Q��ǂ��ďk�������T����B
�Q�D���̏K���͉��a�Œ�Z�I�ł��邩��A�e�Ղɕߊl��ᶂ����B
�R�D�X�e���[���C�� �̔@���A�܂���l�̋L���ɐV���ł���ߎS�ȖŖS�̗Ⴊ����B
�S�D�{�M�̗B��̎Y�n�ł����������A�����ł͍r�p�ɋA����Ƃ��Ă��B
�T�D�i�s�ɉ��ẮA�����n�߂đ��̑��݂����炩�ɂȂ�A���������z����Ƃ̋^�Ђ�����B
�U�D�������C���Ēu�����́A���̗�Ɍ��邪�@���A�߂����ɐ�ł����T���ꂪ����B
�V�D�{��ォ�猩��ƁA�����ł͔M�т̖��J�̒n�ɋ͂ɋ͏��̎�ނ���������݂̂ŁA��ʂ̐l�ɂ͖ܘ_�A�{�p�I�ɂ����钿�d���ׂ����̂ł���B
�@���₪�S�z������p�̃W���S���͍����ł͐�ł����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B�K���A����{�����ӂ̃W���S���͍��Ȃ��ڌ�����Ă��邪�A���̉^�����S�ׂ����̂�����B�p���I�̃W���S�����]����ۂ��Ă���悤�ł��邪�A�ǂ��Ȃ�ł��낤���B
�@�Ȃ��A���̓p���I����A�����A���a18�N���_�ł͐_�ސ쐅�Y������ɋΖ����Ă������Ƃ��A������㏼(1907�`1967�A���ފw��)�Ƃ̘A���̘_���u�X�~�_��Antimora microlepis BEAN�̖n�`�X�ɏA����(����)�v(�u���{�C�m�{�����v��Q����Q���A1943.3.5�App.11�`15)�ɂ��m�邱�Ƃ��ł����B
�@�̘_�����Љ��O�ɁA�p���I�ɂ�������m���̍��ꋳ�ȏ��ҏW���L�Ƃ��ď��a16�N�V�����痂17�N�R���܂ŋΖ����Ă���������(1909�`1942)�ɂ��Ăӂ�Ă������B�����̏��a16�N�X��12���t���A���j�����̗t���ɂ͒��������̂�H�ׂ��Ə�����Ă���B�u�C�ɂ��ނ��̂łˁA�N�̂��Ă���A���f���Z���̂��b�ɏo�Ă�����̂���v�Ƃ���̂ŃW���S�����낤�Ƒz�������(�쑺���ҁw�����ց@������q�ւ̓�m�����x�A�W�p�ЁA2002.11.10�App.104�`105)�B�����́u��m杁v�̈�ҁu�K���v�ɂ́u��(�I�������K�����̑�꒷�V)�͖����C�T�̎���ΏĂ̎e��l���َ̑����啂̎e�̏��ĂȂǂ̔��H�ɂ����Ă���̂ŁA�ނ̕��͎����ěs�ݓ̔@���ɂӂ����ł���v�Ƃ����ꕶ������B�����͓y���v��(1900�`1977�A���a�S�N����17�N�܂ŁA�ꎞ�A���������������邪10�N�ԁu��m�v�ŕ�炵���B���a14�N�ɂ͓�m�����Y�̏����ƂȂ�)�ƃp���I�Őe����������Ă���(�u������o�����s�ɂł�B���x�͓y������ƈꏏ������y�����v���a17�N�P��17���A�Ȃւ̎莆)���A�y���Ƀp���I�̐l���ɂ܂��̘b�̏Љ���邱�Ƃ͊��q�̒ʂ�ł���(�w�p���I�̐_�b�`���x���u�l���̘b�v)�B
�@���a12�N�R��25���A�t�B���s���k���A�J�~�M�������ŕߊl���ꂽ�W���S���͗Ⓚ�ۑ�����A���A��k�鍑��w�ؕ���Y�����̓����w����(��r�`�Ԋw�E�M�������w)�̒ቷ���ɔ[�܂����̂��U�����ł������B�͕��⋱��̓��������ŚM���ފw�����A��Ɋ�����ȑ�w�̏���w���߂��B�p���I�̃W���S���������ŕ���ɑ���ꂽ�̂ɑ��A�t�B���s���̌̂͗①����Ă����̂ŁA������ؓ����ǍD�ȏ�Ԃɕۂ���A���͓����w�ғ��ɂ���Ď��H���ꂽ�B��U�͐؋����̗��ΐV�g�A�c�����A�Ô��k�Y�̑��A���⋳���̌��c�\�g�E����l�Y��A��p�����ق̖ʁX�A��k�s�������A���t�͂��������������A�����U���Ԃɓn���čs��ꂽ�B��U�̂͑̒�238cm�̎��ŁA77cm�̎��َ̑���g�Ă����Ă����B�O���ώ@�ł́u�������Ƌ����ɛ����鋫�ڂ͔��R�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ���_�́A���́u�����Ɠ����Ƃ̊Ԃɂ͕s���ĂȂ����Ə̂��ׂ����̂��F�߂�ꂽ�v�Ƃ����L�q�ƈقȂ��Ă���B�����ώ@�ł͐�A�݁A�����A�咰�A�̑��A�t���A�����A�S���A�x�A�b��B�ɂ��ĕ��Ă���B��́u�Ⓚ����ᢒB�̎��Ƃ��ĉ䂪���ł͎n�߂ẮA�O���l�̂���̂ɔ�ׂĂ��J��ċ���Ǝv�͂�鍟�̊��S�ȉ�铂̏����̈�[��ᢕ\���鎖�͑傢�ɈӋ`���鎖�ł���v�Ǝ��M�ɖ����ĕ��Ă���B�u�̉�铏����v(�}���R�C���łW)�́u�ț{���i�s�v��U����T��(���a13�N11��20���A�i�s�����ً���)�ɔ��\���ꂽ�B���̍��́u�����j�v�Ƒ肳��A�\���ɂ̓W���S���̍��i�A���\���ɂ̓g���X�C���̃W���S�����������ꂽ�^��L�̎ʐ^����������Ă���B
�@����͋��֏�v�ҏS�̎G���u�����i�s�v��16��(��Q��10�����A���a17�N10��5��)�ɐ��M���́u�l���G�L�v(pp.6�`7)�\���Ă���B���̒��ŁA�ؓ��Ɖ�U�����َ������������W���S����U�̌o������u�l���̙B���̗��R�Ƃ��Ĉ�ʂɉ]�͂����A�e��O���ŕ����グ�ĚM������Ɖ]�Ӑ��͂��̓���̈ʒu���炷��Ǝ��ɑ���ʑ����ł���v�ƌ������Ă���B�܂��A���{�̐l���Ƃ��ĕ��₪�q���̍��悭�������̂Ƃ��Đ��S�O�E���w���̏��W�ƂȂ��Ă����u�P��������Ȃ��A�k����̗l�Ȕ���U�蘪�������́v�������Ă���B����ɑ��鐼�m�̐l���Ƃ��āA1927�N�t�Ɏ��g�ŖK�ꂽ�o�[�[���Ō����x�b�N�����́u�g�̋Y��v(���傤�ǃx�b�N�����a���S�N�L�O�W����Â���Ă���)��R�y���n�[�Q���̐l�������v���o���Ă���B�Ō�Ɂu�i�s�ł͎�l���Ƃ͖��_�]�͂Ȃ����A����܂����������l���B�������A�p���I�ł͂��낢��̙B��������v�ƌ����āA�u�{��椎ҏ��N�̓��ɁA�l�����͎Ɋւ���x�ߖ����i�s�̌���A�B�����䏳�m�̕�������A�������肢�x�����̂ł���v�ƌ���ł���B
�@�u�l�����m�v�Ƃ́A���⋱��ɂ��ď����a���`���Ă��ď̂ł��邪�A��k���̓������͖{�ԋ`���ɂ��ƕ���̂��Ƃ��u�w������(Halicological Institute)�����v�ƌĂԂ��Ƃ��������炵���B����̃W���S�������ł͒��S�ƂȂ镶���w�V�R�I�O��������P�S�x�����̂܂܂̏Љ�ł��������A��O�̐A���n�A�ϔC�����n�ł����p�A�p���I�̃W���S��������𒆐S�Ɏ茳�̎����łȂ����Ă݂��B
�@�Ȃ��A�p���I�̃V���S���ɂ��ẮA���{�ɂ�鐳���ȈϔC�������F�߂���ȑO�̐�̊��ԂɊ��ɒ����g�\�Y�̒Z��u�p���I�̐l���v(�u���Y�������v��15����1���A1920.1.1�Ap.12)������B���������������̂́u铒����ڌv��̖����[��������������́v�ł���A�u�y��}�X�L���E�v�ƕĂ���B�����͂܂��A
�@���̓����͗����n���ɂċ��l�����T��(Dugong)�Ɠ����̂��̂Ȃ��ۂ�͍�篂ɒf�肵����A���̌`�ԓ���萄���ăn���R�[��(Halicore)�ɛ�������̂Ȃ�ׂ��䂪����n���̎��⌸�ł���Ƃ��鎞���c��V�ɂ��̎���ƙB���ɕx�߂钿��Ȃ铮���̎Y�n�Ƃ��ăp���I������͒��ڂəJ���ׂ��B
�Əq�ׂĂ���B�p���I�̐l���`���ɂ��ẮA���A�y���̖����l���ɕϐg�����Ƃ������̂ɑ��A��҂��W��ł̋c�_�Ɍ������C�ɐg�𓊂��u�}�X�L���E�v�ɂȂ����Ƃ����b��`���Ă���B�����́u���Y�������v��15����U��(1920.6.1)�ɂ́u�p���I���Y������v(pp.17�`24)���f�ڂ��Ă���B
�@�p���I�̃W���S���������A�ی�A�ɐB�̂��߂ɓ��{�̐����قŎ��炵�悤�ƌv�悳�ꂽ���Ƃ�����B�̊C200�C������ɓ˓����悤�Ƃ�������ŁA�p���I�̐��Y�����J���ɓ��{�����͂���Ƃ����w�i���������B���֎s�����ق͈ȑO����W���S��������v�悵�Ă������A1976�N�W���̗\�������A��77�N�X���ɂ͒����E�ߊl���p���I�Ŏ��݂��B���R�ی�̊ϓ_����l�X�Ȏs��������������A�����ߊl�̎w���ɓ�����������@(1910�`1987�A���Y�w�ҁA�E�i�M�̌����Œm����)�͏\���Ȑ��Ԍ����̏�ł̎���A�ɐB���v�悵�Ă������A�ߊl�ɂ͎���Ȃ������B���䂪�W���S���ɋ������������̂́A��p�̑��{�����ق̃W���S���W�{���w������Ɍ������ƂƁA���a13�N�ɐ��Y�u�K�����K�D����ۂŃp���I�Ɋ�e�������ƂȂǂ��_�@�ƂȂ��Ă����B�����̃p���I�ł̗l�q�͌Ð�O(1925~�A���؏܍��)���`���Ă���(�u�J�b�p�܂�����v��P����R���A1976.11/12�App.292�`310�u�l���͖����̖�ɋ����v)�B���̌�A�����̃W���S�����������͍��ی�����ȂǂŔ��\����Ă���(1977.9��1979.12)�B
�@�W���S���̓��{�����ł̎���͑啪���Ԑ����قƉ���C�m���Ŏ��݂�ꂽ�B1975�N�̊C�m���ł́A�C���h�l�V�A�Y�Q���̃W���S�����^�ꂽ���A���̕�W���Ɉꃖ���Ŏ��S���Ă��܂����B���̌�A���H�����ق�1977�N�T���A�t�B���s���Y�̎��W���S���̎�����n�߂��B����C�m���I�O���������ق̃W���S������ɂ��Ă͓��c�F�O�E���H�R�ƕv�E�g�c���I��̂R������B��́u�W���S���̎����v(�u�����������َG���v��20����P���A1979.1.31�App.11�`17)�B����́u�W���S���̐����l�v(�u�����������َG���v��21����R���A1980.9.30�App.49�`53)�Ɓu�W���S���̊O�^�v���l�ƖU�������v(�u�����������َG���v��21����R���App.54�`61)�ł���B���H�����ق̃W���S���ɂ��Ă��u�����������َG���v�ɕ�����(�u�W���S���̎���ɂ��āv�A��20����S���A1979.12.29�App.78�`85)�B
�@�����̊w�p�_���̑��ɁA�����̏T�������W���S������ɂ��ĕĂ���B�u�`���̐l���u�W���S���v�����Ȃ��܂܂ɂ��̐��䂫�v(�u�T���f�[�����v�A1975.11.9)�A�u��̊C���璿�b�W���S���������I�v(�u�����v�A1977.6.19)�A�u�J�������l�������ƂP�N�R�������������R�l�̐N�́u������L�v�v(�u�v���C�{�[�C�v�A1978.9.19)�A�A�u�~���s���̂���߃W���S���ɗc�ȍȁv(�u�����Z�u���v�A1987.5.7)�A�u�W���S���̃W�����C�`���ȁA�Ȃ�ƃJ����M���v(�u�T�������v�A1986.2.20)�Ȃǂ̋L���ł���B
�@���H�����قł̓W���S���̎��炪�n�܂��ĂP�N���1978�N�A�����̂��߃g���X�C���̖ؗj�����ɁA���l�Y�A�Óc�����A�_�J�q�Y��h�����Ă���B���݁A�������ق̒�����s���uTOBA SUPER AQUARIUM�v�ɐ��l�Y���u�l���̐��ފC�v��A�ڂ��Ă��邪�A���̍ŐV��(2005 �~ NO.48)�ł́A�g���X�C���ł̃W���S���ɂ��ĕĂ���B�N��300�����ߊl����A�P��������P���Ԃقǂŏ�������A�����S���тɕ��z����Ă���Ƃ����B�g���X�C���ł̃W���S�����ɂ��ẮA���{���K�����ڂ����L�q���Ă���(�u�g���X�C�������̋�������(������)�|�}�u�B�A�O(Mabuiag)���𒆐S�Ɂ|�v�B�u�����w�����v��41����S���A1977.3�App.368�`389)�B���͖ؗj���ł́u�����܂ł��L���ɗ��p���Ă��܂��v�Əq�ׂĂ��邪�A���{�́u�J���ɂ���W���S���ɂ���A�_�̂��Ǝ��o�����Ƃ̍���Ȕ]�������A�_�炩�ȕ����͌���������܂߂��ׂĐH���ɂȂ肤��B�������A�����ł͎�v�ȓ��̂ق��A�����ł͏����̈ꕔ�Ɣx�ȊO�قƂ�ǎ̂Ă���v�Ƃ��A�u�q�������̒��ɂ̓W���S����J���̗����������ƐH�����������Ƃ����������v�ƕ��Ă���B
�@�W���S���̗��p�͉���ł͓ꕶ���������猩����B�k����K�́u�l�ފw�G���v��84����Q��(1976.6.30)�Ɂu����{���Y�Y�L�ˏo�y�̃W���S��(Dugong dugon)�̏�r���̓���Ɖ�U�w�I�Ȃ�тɐl�ޛ{�I�l�@�v(pp.139�`146)�\���Ă���B�قڌ��^�ʂ�ŏo�y������{�̏�r���͐H�p�ɋ����ꂽ�̂��V��ɊW���Ă���̂��͒f�肳��Ă��Ȃ��B�k���͏�L�_���̈��p�����ɕ��⋱��̂R�_���A�ؓ��u�W���S���̉�̏����v�A���u�p���I�̎ɏA�āv�ȂǁA����Љ����O�̃W���S���������������܂߂Ă���B
�@����͕��⋱��𒆐S�Ƃ�����O�̑�p�A�p���I�Ȃǂ̃W���S�����������グ���B
��k�鍑��w�ɂ͐X���p(1890�`1967�A�X���O���j�A��U�w��)�A���֏�v(1897�`1983�A�l�ފw�ҁE��U�w��)�A�f�ؓ���(1882�`1970�A�����w��)�A�����Y(1891�`1977�A�Ð����w��)�A�O���M��(1903�`1983�A�A���r�A�w)�A�n������(1909�`1988�A�Љ�l�ފw)�ȂLjِF�̊w�҂��W���A���̎��ӂɂ͎��쒉�Y(1906�`1945?�A�n���w��)�A��������(1908�`2005�A�l�ފw�E�l�Êw��)�Ȃǂ������B�����̐l���A�w��͋����[�����ł��邪�A�M�҂̗͂ł͕`������Ȃ��̈�ł���B
�@����́A2004�N�V��13���ɖS���Ȃ�����U�w�Ґ_�J�q�Y�̃W���S���A�l���������Љ�Ă݂悤�B�_�J�ɂ́w�l���̔������@�C�b�w���n�x(�v���ЁA1989.12.20)�Ƃ������̑��ɁA���グ��ׂ��_�������҂�����B
by����[(aka.MORO)