東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>3P


The Saturday Book とは何か。ロンドン,ハッチンソン出版のクリスマスギフト用書籍で、1941年以来、毎年更新されている。(現在も健在であるかは不明)。世界大戦の最中に送り出されてから18年、1959年の19号が手元にある。土曜、週末のスノッブたちが興味を持ちそうな話題満載の箱入りの本である。イタリア旅行、ワイン、銀食器、自然。ちょっとした洒落た会話に利用できそうな、映画、マグリットの絵画、60年代の回顧(ただし、1860年代)、入浴の哲学についての記事。どうしたわけか、リチャード・カリントンの「人魚の博物誌」(Richard Carrigton,The Natural Histry of Mermaid,pp.293-300)が掲載され、箱絵(贈答用外箱)と表紙もW.マクラーレンの人魚入浴の図である。英語圏の人魚知識の基本が那辺にあるか押さえるのに便利であるので紹介してみよう。

カリントンと言えば、『人魚とマストドン』(1957)の著者である。日本では『失われた動物』の題名で訳された。サタディ・ブックで、彼は、「人魚は神話・民俗学上、最も魅力的、詩的な存在であろう」と書き出している。人類の想像世界に残る人魚の足跡を、自然科学、心理、信仰に渡って跡付けることを目指すものである、と謳っている。
人々が人魚の実在を、比較的最近まで信じていたことの証左として、「タイムズ」1809年投稿欄に、マンロウというスコットランドの教区小学校校長の人魚実見記が掲載されたことを述べている。19世紀がいかに人魚に魅せられていたかを語り、ビクトリア時代の人々が、ベックリンの絵とテニスンの詩の中の人魚を好み、80年代のミュージックホールでは、ロイドの「人魚と結婚して」を愛唱していたと続ける。
次に、近代の人魚記述に進む。ファレンチンの「アンボイナ自然史」、ハドソンの航海記。1560年、ゴアに運ばれ解剖された男女の人魚。これらルネッサンス以降の人魚記述の根底には、原始宗教から続く人類の人魚への思いがあると言う。それらは、オアンネス・ダゴン・アタルガティスから、ギリシャ神話のセイレーン・トリトンへと繋がる。神話から科学へと発展したのもギリシャ・ローマ時代で、人々は口承や航海記よりも、実証の科学的記述に就き、アリストテレスの博物学などでは、懐疑的になるも、プリニウスなどは人魚の存在を擁護している。プリニウスの17世紀のイギリス人翻訳者、フィレモン・ホランドも人魚を確信していた。
人魚の実在説は中世、ルネッサンスを通じて支持され、19世紀には、剥製人魚が現れ、一層興味をかきたてた。専門家は否定したが、人々は人魚を信じていたのである。この核心に止めを刺したのは、動物学であった。ジュゴン・マナティーの種の記述がされ、海牛や鰭脚類が誤視の原因とされるようになった。
以上が、カリントン「人魚の博物誌」の骨子であるが、カリントンは生物学的実証がすべてと言っているわけではなく、人類の想像力にも重きを置いている。この短いエッセイを基調に、「シ」から「ソ」へと変調させていってみよう。
(by 八谷鏡人)


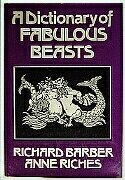 最近出版された本の中から、人魚の記述を拾ってみよう。
最近出版された本の中から、人魚の記述を拾ってみよう。
★“Fantastic Beasts&Where to Find Them by Newt Scamander”,J.K.Rowling.2001
『川伯井守氏著 幻獣とその生息地』,J.K.ローリング,2001年
ハリー・ポッターが、魔法学校1学年で、使用した教科書の体裁を取る本書には、「人魚一族 MERPEOPLE」pp.28-29が記載されている。
魔法省認定危険度4(危険、特別知識必要、熟練魔法使いのみ扱い可能。5段階評価の上から2番目。ケンタウルスや一角獣も同評価)。
世界中に分布、形態は様々で、人魚語を習得した魔法使いによると、高度に発達した人魚社会もあるという。最古の記録はギリシヤのセイレーン。一般人間が文学、絵画にしばしば描く人魚は暖水域に生息。スコットランドのセルキー(海豹人間)やアイルランドのメロウは醜い。人魚一族の共通点は音楽を嗜好することにある。
ACROMANTURA(人語毒蜘蛛)からYETI(チベット雪男)まで、アルファベット順の75種幻獣事典には、龍やマンティコラなど定番種もあるが、ローリングの創作と思われるものも含まれている。もっとも、龍の記述には、代表種10種別の解説があったりと、ハリー・ポッター本編(第4作『炎の盃』参照)に関連したオリジナルな説が楽しめる。水の精は、人魚の他、9生物が認められ、日本の河童も立項されている。(Richard Barber/Anne Riches.“A Dictionary Fabulous Beast”,1971.にもKappaは掲載。撃退方が、お辞儀をして皿の水を落としてしまうことも同じ。)ネッシーが世界最大のケルピー(水馬)だとするのはご愛嬌。アメリカでは、書評家に不評であった第4作と異なり、好意的に、このホーグワーツ魔法学校認定教科書は受け入れられているようだ。
★Ann Beattie, “Perfect Recall”,2001
アン・ビーティー(1947〜)は、ニューヨーカー派の短編を得意とする作家。最新短編集の第2作品目がMermaids(pp.101-131)。キーウェスト(フロリダ)のヒルトンホテルでクリスマスを過ごす中年夫婦。男友達と伯母も一緒だが、男二人は釣りに出かけ、女一人プールで過ごす。面識のない伯母が加わり、夫のかつての結婚生活などが語られる。停滞した雰囲気の中、警笛(サイレン=セイレーン)が何度も聞こえる。夫を迎えに桟橋まで来てみると、男たちは、人魚のように着飾った女たちと下船してくる。mermaidは誘惑する存在なのか、未来(嵐)を予知する者なのか。気怠さと、噛み合わない会話に暗示される人間関係を味わう作品なのだろうか。幻獣としての人魚とは直接関係ない作品であった。
★『歴史読本』2001年5月号は、「秘宝・名宝の日本史」を特集。そのpp.196−197に、不老不死伝説ゆかりの珍宝として、八百比丘尼「人魚の絵」(福井県小浜空印寺)が紹介されているが、もはや珍宝ならず、陳腐であろう。
このあたりで「最近」の項を終わり、「south」の「さ」へ移りたいのだが、その前に、最近知りえた安土桃山時代の人魚記述を一つ紹介したい。中世日本の人魚認識の一端は、『時代別国語大辞典 室町時代編』でもうかがえるが、今回のは図も添付されている。松平家忠(1555−1600。徳川家康家臣の武将。伏見城番として関ケ原の戦い前哨戦で戦死。)の日記『家忠日記』(『増補 続資料大成』19巻)、天正9年(1581)4月の余白に、
正月廿日二かんてんちへあかり候、安土ニ而食人をくい候、聲ハとのこほしと鳴候、せいハ六尺二分、名ハ人魚云、
(by 八谷鏡人)