東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>29P
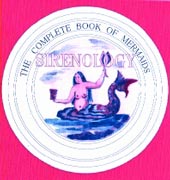
『原色日本海魚類図鑑』(桂書房、1990.6.30)の著者(図と文)津田武美(つだたけよし)は富山県新湊市出身。公立の小中学校校長を務め、退職後は新湊市文化財審議委員、富山県理科研究会会長に就いた。理科教育の実践者であり、魚の研究者でもある。富山湾に生息する魚類を中心に、いわゆる紐帯類と人魚の関係、魚類から両生類に進化する過程を展示した「富山のさかなと人魚展」は2002年7月4日から9月1日まで新湊市博物館で開催され、津田は記念講演「富山湾の人魚」を行っている。
津田の人魚観は『原色日本海魚類図鑑』中のコラム「人魚考-〈サンカルチー〉」(p.113)、「人魚考-〈振袖花魁〉」(p.114)、「人魚考-〈竜宮の魚たち〉」(p.117)、「人魚考〈童話と記録〉」(p.118)に窺うことができる。アカマンボウ目フリソデウオ亜目=紐帯類、サケガシラ・テンガイハタ・フリソデウオ・ユキフリソデウオ・リュウグウノツカイ・アカナマダ・テングノタチの説明ページに添えられている。「サンカルチー」の語があるように、津田も内田恵太郎「人魚考」の論旨を受け入れて、人魚論を展開している。
津田が紐帯類=人魚論に寄与した点は、富山県では、これらの魚を「おいらん」と呼んでいるのを知らしめたことだろう。西村三郎は「富山湾沿岸では、冬になるとこれらの魚が稀ならず定置網に入るが、漁師たちはかれらを「おいらん」と呼んでいる。「花魁」-海の荒くれ男どもは、それらの艶やかな魚たちの姿の上に、白い肌に熱く白粉をぬり、鮮やかに口紅をさし、あるいは真紅の肌襦袢をまとったあの美女たちのおもかげを重ねあわせていたのでもあろうか」(「人魚とリュウグウノツカイ-伝説と動物学のはざま」、『物のイメージ・本草学と博物学への招待』p.61)と述べている。また、本間義治も「ribbon fish、oar-fish、Riemenfischなどの改米名(ママ)もよくその姿態を現しているが、新潟県柏崎の方言“しらたぎ”ことに富山湾の方言゛花魁〝は妙である」(「新人魚考」pp.59~60)と「花魁」に言及している。津田はその魚類図鑑で、和名、学名、英名、中国名の他に地方名を取り上げている。サケガシラの地方名は「サケガシラ(寺泊) オイランタッチョ(新湊)」という具合である。リュウグウノツカイの地方名は「オイランタッチョの親(新湊)」、アカナマダ「オイランタッチョ(富山湾新湊)」とある。「人魚考-〈サンカルチー〉」では、「富山県放生津浦(新湊市)の漁師は゛おいらん〝と呼ぶ。市は、おいらんを天然記念物に指定した」と津田は述べている。
サケガシラは富山湾では年に数十尾も獲れ、津田は百尾を測定し最小、最大、平均値を体長・背鰭条・胸鰭条で求めている。最大の物は177.0cm、最小は110.0cmであった。フリソデウオ、ユキフリソデウオは独立した種ではなく、幼魚ではないかという説があるが、津田は「ユキフリソデウオ→サケガシラ、フリソデウオ→テンガイハタ」という方向を示しつつも「今後の課題」としている。この点に関しては、本間はユキフリソデウオ、サケガシラ、フリソデウオの原記載、内外の研究論文、標本などを比較し、専門の組織学事実を加味することで「ユキフリソデウオ(80~100cm未満)→サケガシラ(100~150cm)の順に成長していくものであろう」(「組織像より推定した中部日本海における漂泳漂着動物の生活」[「動物と自然」第8巻第1号、1978.1])と推定している。テンガイハタに関しては「松原(喜代松)は背鰭条数や斑紋の類似からフリソデウオをテンガイハタの幼魚ではないかと推察した。しかし、同大の両者を比べても著しい形態上の差異があり、同意できない。むしろ、ユキフリソデウオのさらに小さい段階のものを求むべきであり、その観点からフリソデウオとの関係も吟味する必要があろう」と本間は同文で述べている。東海大学出版会『日本産魚類大図鑑』には「サケガシラとテンガイハタの分類的差異は不明瞭である」という記述もあり、フリソデウオ科の種についてはまだまだ解明されていない部分が多い。
津田は『廣文庫』にある人魚文献に江戸時代のかわら版(越中國富山領放生津四方浜に文化2(1805)年5月に現れた3丈5尺(10.5m)の人魚。背薄赤、腹火の如し)などの記述を加え、日本の人魚の共通する特徴を3つ挙げている。
そして、結論としてリュウグウノツカイ、サケガシラ、富山湾で「おいらん」と呼ぶ魚類を日本の人魚の正体としている。津田が人魚を語る時は、立山の白比丘尼、黒部の玉椿姫という八百比丘尼の類話、隣県出身の未明「赤い蝋燭と人魚」へと思いは広がる。そして、最後はサケガシラを食べたときの経験が披露される。「その赤い鰭を切りとる。身肉は、白い。煮ても焼いても、ろうのようにとけてしまった。刺身にしても、くにゃくにゃして気味が悪く、不味くて、とても食えた代物ではなかった」。
紐帯類の食味について、本間は自著『新潟県 海の魚類図鑑』でリュウグウノツカイ「肉は白身であるが、やわらかくて、うまくない」、サケガシラ「肉は白身で軟らかく、うまくない」と述べている。また、1963年1月30日・2月16日と66年3月30日の3回伊豆大島東岸で一本釣り操業中に水深250~350m前後で釣獲されたサケガシラの報告文には次のようにある(広瀬泉・坪川慎二・倉田洋二「伊豆諸島の海産生物2.稀魚 サケガシラ」、「採集と飼育」第32号第2号、1970.2、pp.50~51)。
素焼きにしたが脂肪は全くなく肉の歯ざわりはなくあたかもマシュマロをかむに似て歯ごたえは全くなく、たいへん不味で二度とはしをとる気がしなかった。私たちは他の紐帯類を試食したが(リュウグウノツカイRegalecus russelliiアカマナダLophotus capellei)、サケガシラは味覚からいうと最下等で全く食品価値はないと考える。
また、同文中には波浮港市場ではサケガシラを「ギンナガシ」と仮称していることが述べられている。駿河湾では「ギンダチ」とも言うらしい。
ともに漂着物の研究家である。
中西弘樹は1947年生れ。広島大学理学研究科博士課程修了。理学博士。植物生態学が専門なので動物学者ではない。その著『海流の贈り物 漂着物の生態学』(平凡社、1990.7.16)では魚類の漂着としてハリセンボン・リュウグウノツカイ・サケガシラを取り上げている。リュウグウノツカイは1986年1月6日対馬の西泊で捕獲され10日に長崎水族館に持ち込まれた個体を観察している。このリュウグウノツカイは尾が損傷していて体長3.25m、体高は頭部付近で32cm、体重26.2kgであった。その様子は「顔つきは他の魚とまったく異なり、角ばった頭の先端に大きな突き出た口があり、目も大き」く、特徴的な背鰭、腹鰭は既に退色していた。中西は30程のリュウグウノツカイの捕獲例を月別、体長別にグラフ化している。月別では2月と6月にピークがあるが、体長では0.8~5.5mまで同じように捕獲されているのが分かる。pp.129~130は「人魚の正体」と見出しが付けられ、内田恵太郎の説と、そこで使われた『甲子夜話』『六物新志』の赤髪、白肌の特徴がよく現れている部分を引用し、「そのような特徴はリュウグウノツカイの形態に一致する点が多い」と述べている。そして、結論として「リュウグウノツカイは、その特異な形態と稀にしか姿を見せないことから、想像上の動物に発展していったのであろう」としている。サケガシラについては記述は6行と短いが、捕獲のピークは2、3月だと指摘している。
以上の説明は中西の別著『漂流物学入門 黒潮のメッセージを読む』(平凡社新書、1999.11.17)でも確認できるが、新書ではリュウグウノツカイ=日本の人魚への言及はない。だが、新書には「トラザメ科の卵殻」が加わり、古代ギリシアの小銭入れに似ているところから「人魚の財布」と欧米では呼ばれ、日本の海岸にも漂着していることを述べている。なお、ハリセンボンの漂着現象については西村三郎の「日本海洋学会誌」上の研究(「日本列島対馬暖流域におけるハリセンボンの“寄り”現象について」、1958)が詳しい。西村は漂着生物を海岸で拾う行為を「いそこじき」と呼び、本間は「うろつき回る」とだけ表現していたが、中西らは「ビーチコーミングBeachcombing」の用語を使用している。
漂着物の収集では石井忠が第一人者であろう。石井は1937年、福岡県生れ。國學院大学文学部史学科卒業後、中学・高校の教諭を務めた。石井も動物学者ではない。30数年前から玄界灘に面した砂浜で漂着物(生物だけではない、人間の作った製品も含む)を集め、その数8千点以上。整理し考察を加え、1977年の『漂着物の博物誌』(西日本新聞社)以来、10冊余りの著書にまとめて発信している。その間、コレクションは企画展などで何度か公開されている。石井の漂着物研究の集大成が『新編 漂着物事典 海からのメッセージ』(海鳥社、1999.4.25)である。そのpp.263~265が「「人魚」考」である。まずはジュゴンを取り上げて、日本の古記録の紹介に進む。「日本書紀」「古今著聞集」「甲子夜話」は見なれた布陣であるが、次は奥村玉蘭『筑前名所図会』で、博多区龍宮寺の伝承を取り上げている。さらに名越左源太『南島雑話』を引用する所は史学出身を感じさせる。最後に、内田恵太郎の「人魚考」に及び、「古今著聞集」「甲子夜話」の記述は「どうもリュウグウノツカイではないかと思うのだが」と、ささやかな賛意を表明している。なお、『漂着物事典』には「八百比丘尼」(pp.271~272)、「サケガシラ」(p.326)の記述もある。サケガシラについては「この魚はデンマークやスウェーデンでは「海の乙女」と呼ばれ、人魚の正体とする説もあるという」と述べ、明記はしていないが内田の論考から得た知識を伝えている。
リュウグウノツカイについての科学論文では、しばしば宇井縫蔵『紀州魚譜』(紀元社、大正14年1月11日)を引用文献に挙げている。例えば、本間義治も「宇井によれば、リュウグウノツカイでも幼時ないし小形のものには、体側に成魚にはみられない暗色斑が存在するという」(「組織像より推定した中部日本海における漂泳漂着動物の生活」)と宇井を参照している。宇井縫蔵は奥付を見ると、「和歌山縣西牟婁郡田邊町大字下屋敷町」とある。田辺と言えば南方熊楠である。宇井は南方周辺の人物として知られている。魚譜の他に『紀州植物誌』も著している。魚譜にはマンダイ科マンダイ(アカマンボウ)(pp.87~88)、クサアジ科クサアジ(p.120)、フリソデウヲ科フリソデウヲ(p.275)、リウグウノツカヒ科リウグウノツカヒ(pp.275~276)のアカマンボウ目の魚類が収録されている。その内、クサアジ、フリソデウオには写真も載せられている。リュウグウノツカイの部分を見てみよう。
リウグウノツカヒ科 Regalecidae
リウグウノツカヒ 龍宮ノ使 Regalecus Russellii(Shaw.)
〔方言〕水族志にリウグウノマモリガタナ・マダチヲ・ヒモタチヲなどゝある。
體形タチウヲに似て、大に側扁派し平紐状を呈する。背鰭は全背を覆ひ、前端の數個軟條は長く延び、腹鰭は少數の軟條より成つてゐる。尾鰭は歪形で上方のもの延長する。全體銀白色で、幼時體側に數個の大なる暗色斑點を有するやうである。體長二尺に達する。稀。
『紀州魚譜』は表紙に人魚の版画が配されている。人魚の装幀画がある書籍とは魅力的な課題であるが、今は準備不足である。
南方熊楠には牟婁新報に載り発禁処分となった有名な「人魚の話」という論考があるが、女婿である岡本清造(1903~1979)にも、水産講習所勤務時代に「洪水★人魚★女神」(「水産公論」第25巻第2号、1937.2.1、pp.43~48)と題する文章がある。昭和12年は広田弘毅内閣(2.26事件後の昭和11年3月9日成立)が1月23日に陸相と政党出身閣僚が対立して総辞職、最初宇垣一成に組閣命令が下るが陸軍の反対で辞退、陸相後任問題で難航するも、何とか林銑十郎内閣が2月2日成立。ただし四ヶ月しかもたずに6月4日には第一次近衛内閣に替わっている。その時代の転換期を岡本は「大洪水直前の状態」と表現した。
大洪水の後に何が殘存し、又それが人間の發展に何を齎らしたか。世界各國に傳承せれてゐる大洪水物語は、この質問に對して、魚を主題とした傳説と造形藝術とを傳へてゐる。七面倒な政治論や經濟論を試みて、お互に神經を焦立たせるよりも、火鉢でも圍んで氣樂にこんな昔語りでも復習して、番茶でも喫つてゐる方が、餘程時代的な味があらう。ナチス獨逸でさへ、トホウもない紅天夢の如き映畫を作製してゐる今の世の中だ。
人魚はワルシャワの対ドイツ抵抗運動の象徴だったが、洪水後に生き残るノアのイメージを人魚伝承に探る岡本の論考はユニークなものとなっている。岡本は西ノ谷村(現、田辺市)出身で、京都帝大大学院卒。専門は水産(漁業)経済学。水産講習所教授を経て、日本大学経済学部教授。昭和22年、南方熊楠の長女文枝と結婚。熊楠顕彰に尽くした。
魚体に象徴されたノアは各地で様々な名称で尊敬された、というのが岡本の論の主題である。バビロンのオアンネス、メキシコのコクスコクス、ダゴン、インドのヴィシュヌなどがノア及びノアの箱船に関連して語られる。魚体と人間の結びつきは様々な段階があり、魚の頭の上に人間の頭が載っていたり、魚体から人間が飛び出していたりで、所謂人魚の形は人間の想像力がかなり発達した時点のものだを推測している。原始社会の段階的発展により文化は進歩し、それを現代人は理論化できるという立場の論である。魚の多産性、豊饒性に着目すれば、ノアの妻は新世界の産みの母となり、人魚像は女性へと変化する。その例として岡本はシリアのアテルガティスを取り上げる。魚身に人間の腕が加えられた初期の形態から漸次変化し、半人半魚の、いわゆる人魚形へと洗練されて行く。さらに、魚を完全に脱ぎ捨て美の極致ヴィーナスへと昇華される。すると、半身魚體の神格は随神へと移行する。それがギリシアのトリトンである。経済学者らしい解釈で語られた人魚の変遷史は何を伝えるための物語だったのかというと、岡本の結論は次のようなものであった。
轉換の後に何が殘り、それが如何に發展するか。果して、我が國民にとつて而して我が水産界にとつて、ノアが生存らへて人間生命の大發展に有益な役割を演じるのであらうか、又人魚的形像から純人間的形像の眞美の極致に迄形態的發展が齎されるであらうか。
キーワードは「発展」である。新世界に真美のユートピアを建設する発展モデルとして、人魚が使われた。私たちは洪水以後の世界に生き、人魚を消費している。もしかしたら、八百比丘尼の道を辿っているのかもしれない。
この師弟の魚類学者もリュウグウノツカイに強い興味を抱いていた。
先に紹介した萩の田中市郎がリュウグウノツカイを入手したとき田中茂穂は写生図を画家に複写させ、蒲原稔治は写真を得ている。
田中茂穂(たなかしげほ)は明治11年、高知県生れ。寺田寅彦と中学では同年であった。明治37年、東京帝国大学理科大学動物学科卒業。「動物学雑誌」の編集委員となり、明治43年、帝国大学講師となる。明治44年から昭和5年まで『日本産魚類図説』48巻を刊行(287種)、大正2年にはスタンフォード大学のジョーダン、スナイダーとの連名で“A catalogue of the fishes of Japan”(「東京帝国大学理科大学紀要」第33巻第1号)を発表している(1235種)。理学博士。昭和13年、東京帝国大学教授。昭和49年、96歳で亡くなっている。魚類学確立に努め、多くの標本を残した。(『近代生物学者小伝』[平河出版社、1988.12.5]pp.325~331、富永義昭「田中茂穂 日本魚類学を確立」参照)
田中茂穂『奇魚珍魚』(興學會出版部、1934.7.15)には、第11図としてリュウグウノツカイ(p.46)が掲げられている。田中は、40年前に新潟沖で捕獲されたリュウグウノツカイ2尾を大学が20円で購入したことを伝えている。「當時の金額としては頗る大金であるが、當時では頗る珍らしいためであった」と述べている。ちなみに、1960年佐渡海峡でとれたリュウグウノツカイは市場で百円とも三百円とも伝えられているが、当時としても決して大金ではない金額で引き取られている。また、種は違うが、今年(2005年)6月、登別沖の定置網にかかったサケガシラ(2m、4.7kg)は、室蘭魚市場でキロ30円、141円の値しか付かなかった。田中はその後、千葉、山口、鹿児島でリュウグウノツカイが捕獲されたことを加え、「學界から見て目出度いことである」と述べている。この文章は第2章「形の奇な魚」(pp.15~49)にあるが、リュウグウノツカイ自体については「タチウオに似たもので、頗る長いのがあって、七メエトルに達するから驚かざるを得ない」と記している。田中は「頗る」という語をよく用いたらしい。
『奇魚珍魚』第八章は「傳説と怪魚」(pp.189~196)である。そのp.194に人魚にふれた部分がある。
人魚とは何であらう。海驢又は琉球の沿岸に居るザンノイオなどのことであらうと學者は云ふ。然かし畫に載せられた人魚はどうも左様なものでなく、顔は處女で、體は魚である。稀に吾々の見る人魚(乾かしたもので古金襴へ大事に包んだもの)は顔は猿で、體はスゞキであって、尾鰭も此魚のものである。これが外国へ多少輸出せられるやうであると聞いては一種の灌漑を惹き起こさゞるを得ない。
田中茂穂は人魚=ジュゴン説に与していないが、リュウグウノツカイと結びつけてもいない。日本の人魚の古記録を見れば魚類学者であればリュウグウノツカイを思い浮かべるとは言われるが、それは内田恵太郎が提唱した後のことである。田中市郎の得たリュウグウノツカイに興味を持った3人の魚類学者の内(市郎は田中茂穂を「東大の魚学の最高権威」、蒲原を「現今の魚学の新鋭」、内田を「魚族研究では本邦屈指の権威」と形容している)で、一人内田がリュウグウノツカイに人魚の姿を見た。それはそれで、画期的なことであったのだ。
蒲原稔治(かもはらとしじ)は明治34年高知県生れ。大正15年、東京帝国大理学部動物学科を卒業、高知高等学校教授を経て、戦後は高知大学文理学部教授。昭和47年死去。魚類分類学が専門。田中茂穂に師事。著書は『原色日本魚類図鑑』(保育社)などがあるが、昭和24年4月15日、日本出版社刊『深海の魚族』pp.150~151に「リュウグウノツカイ」が載っている。
英語でoar-fishというのは「腹鰭が各々1鰭條から成っていて、それが長く延び、その先端が拡がつてボートのオールのようであるからである」と解説している。全長10mに達するものがあり、「太平洋岸では九十九里濱から鹿児島、日本海岸では越後、丹後、山口等で採集せられている」とある。同書にはリュウグウノツカイの図版はないが、テンガイハタ、テングノタチの図を見ることができる。アカナマダについては「面白いことには體の内部に大きな墨汁嚢を具えている。この墨汁は恐らくイカ等のように、敵に出遭つた場合に自分の姿を消す防衛作用を有するものではないかと見られている。それはこの魚が胃にとり入れた食物に墨汁が着いていない點から、之を食物を捕らえるために使用するとは考えられないからである」(p.148)と述べている。
アカナマダ(赤波馬駄)は体内に墨汁嚢をもつ唯一の魚として有名であるが、一時期、口から墨を出すと解説されていたことがあった。本間義治は1980年に津村と共に発表した論文で、墨は尻(総排泄腔)から出されるという見解を打ち出した。本間は翌1981年にも水沢六郎との連名で「糸魚川海岸へ漂着したアカナマダ(真骨魚類・紐帯類)-墨の吐出をめぐって」(「新潟県生物教育研究会誌」第16号、1981.3.28、pp.21~26)を発表して自説を補強している。解剖所見によれば、「精巣の半ばくらいの位置の背方には、頭方が目盲管状の1本の墨汁嚢が存在する。後方に至るほど細くなり、腸管に密接したまま総排泄腔に達し、開口している」とある。墨汁嚢の長さは75cm。墨汁嚢の背面にかけてウキブクロが変形した円筒状盲管=スポイトがあり、末端は墨汁嚢背面に密着した小嚢に連絡している。スポイトから発射されたガスは小嚢を膨らませ、墨汁嚢を圧迫、結果として墨は総排泄腔から出される。墨が防御のためなのか、補食のためなのかについては本間らは明言を避け、「今後の研究をまちたい」と言うにとどめている。
アカナマダの墨汁嚢については戦前に岩手県水産学校の富永盛治朗が報告している(「墨吐く魚」。「水産研究誌」第33巻第11号、1938.11.5、pp.518~520)。その中で富永は「スポイトを壓縮し之れより吐出する瓦斯は導管を通じて墨汁嚢内に入り更に墨汁を壓縮して體外に吐出するものと思はれる。(中略)墨汁は柔魚の如く防衛作用なるや、補食作用なるや不明なり」と述べている。本間らは、直接ガスが墨汁嚢内に入ることには疑問を呈している。富永は同文で「食用としては相當の味あり、此種の如き棲息帯の魚類中油脂尠き方なり」と記しているが、脂が多い魚を好む近年の食事情では「相当の味」とは言えないかもしれない。
現今ではアカナマダの墨は総排泄腔から噴出すことが定説となっているようだ。東海大学『日本産魚類大図鑑』でもJoseph S. Nelson“Fishes of the World”(3rd edition)でも、‘ink sac present, which discharges into cloaca’と記述されている。 ‘cloaca’とは総排泄腔である。
人魚の登場作品なら多数挙げることができるが、魚類のリュウグウノツカイを登場させている作品はなかなか思い付かない。注意して集めてこなかったからかもしれない。立原えりか『小さな魚物語』(じゃこめてい出版、1978.8)pp.29~36「竜宮使 忠実なしもべリュウグウノツカイ」は乙姫から浦島に戻ってくるようにとの手紙を託されたリュウグウノツカイが長い旅の果てに今は水族館にいるというショート・ショート。「竜宮の使い」という命名が実は本当の使いだったという内容。『小さな魚物語』には、魚の捕れなくなった漁師町の沖の岩場に人魚と誤認されたジュゴンが迷い住み、漁師たちによって大海に放たれるという「儒艮 ジュゴンはもどらない」(pp.123~135)も収録されている。
長野まゆみ「リュウグウノツカイ」(「文芸」第43巻第1号、2004.2.1、pp.176~189)は魚類のリュウグウノツカイを扱ったものではなく、亀の報恩とタイムマシンとしての竜宮を背景にした物語。最近文庫化された川上弘美『龍宮』(文春文庫、2005.9.10)にも「龍宮」「海馬」という興味深い作品が収録されているが、魚類リュウグウノツカイは登場していない。
タイムマシンの竜宮と言えば、松永豊和『龍宮殿』があるが、雑誌掲載時の第27話は「リュウグウノツカイ」と題されていたが、これも直接には魚種と関係していない。諸星大二郎「深海人魚姫」(「別冊モーニング」第1号、2004.4.14、pp.235~296)には魚のリュウグウノツカイが描かれている。諸星はリュウグウノツカイに似た「夜の魚」を描いたこともある(『栞と紙魚子と夜の魚』、朝日ソノラマ、2001.8.30、pp.174~234)。
また、小説でも漫画でもないが、新日本動物植物絵本14『ふかい海のさかな』(武田正倫ぶん・渡辺可久え、新日本出版社、1982.8.30)の表紙絵は渡辺による描き込まれたリュウグノツカイの姿である。表に上半身、浦に下半身が、西村三郎が推測したように斜め立ち泳ぎの姿勢で描かれている。一見の価値がある。児童文学では、あさのあつこ昨・佐藤真紀子絵『いえでででんしゃ』(新日本出版社、2000.9.25)がある。家出した子供たちが乗る電車には人間の女の子のほか、ホバリングがうまくできなくて父親にしかられたチョウゲンボウ(ハヤブサの一種)や、ぼんやり考えるのが好きなのに、それを母親からたしなめられたリュウグウノツカイが乗車する。
チョウゲンボウとリュウグウノツカイと言えば、明石散人『鳥玄坊 時間の裏側』(講談社NOVELS、1998.12.5)がある。時空を超越する鳥玄坊一族は、三百年以上も年を経たリュウグウノツカイの表皮から「竜鶏丹」を作る。作中には「江ノ島の人魚」(pp.59~92)という章もある。そこでは、建保4(1216)年正月16日に片瀬の海に15尋(27m)ものリュウグウノツカイが漂着したことになっている(p.85)。ちなみに、地球史上最大だと言われている魚類は1億5500万年前のLeedsichthys problematicusで全長22m(72フィート )と推測されている。リュウグウノツカイは現生硬骨魚類では最長で、10m前後に達するとされているが、40フィート(12m)、50フィート(15m)にまでなると想像している人もいる。日本での最長個体は5.5mらしい。『鳥玄坊』は宇宙の誕生と消滅を背景に、時間を超越する存在が登場し、日本の浦島伝説などもからめて物語は進む。巻末の参考文献には西村三郎の「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」、『物のイメージ・本草と博物学への招待』も挙げられている。明石散人の『鳥玄坊』は三部作で、「時間の裏側」は第2作にあたる。
時空を大宇宙ではなく、小宇宙、人間の精神世界に求め、そこから出現するリュウグウノツカイを描くのが水落晴美『夢界異邦人 竜宮の使い』(メディアワークス電撃文庫、2001.4.25)である。イラストは椋本夏夜が担当、表紙絵にリュウグウノツカイが見える。諸星の「夜の魚」のように、飛翔するリュウグウノツカイは異界の魚である。水落の「竜宮の使い」はシリーズの第2作目。異形のリュウグウノツカイは小中千昭「深淵を歩く物」(『深淵を歩くもの』、徳間デュアル文庫、2001.4.30、pp.211~238)にも登場する。同文庫には「人魚」(pp.159~164)「ダゴン」(pp.203~207)という題名の掌編も収録されている。
物語のリュウグノツカイは時空を超え、身をくねらせて出現する異形の魚として描かれやすく、実際より更に巨大になっている。その中で、のんびり屋の家出リュウグウノツカイが親しみやすい存在となってる。佐藤真紀子の絵も楽しい。
近年、ネット上で地方のニュースが検索でき、リュウグウノツカイを始めとする紐帯類の捕獲、漂着の情報を多く目にすることができるようになった。サケガシラなど2005年の2月には氷見で定置網に百匹以上かかっていることが分かった。それでも、成長過程、分類など多くの課題が未解決である。その中で、リュウグウノツカイが日本の人魚の正体(モデル)であるとする内田恵太郎以来の仮説が魚類研究者の間では周知の事実のように取り扱われるようになっている。内田の着眼と資料収集には敬意を表するが、それを無批判に受け入れることにはためらいがある。その疑問をリュウグウノツカイのように長々と綴ってきた訳であるが、漂着死体のように尾が欠損して、結論とてない様をさらけ出している。内田は主に日本の人魚をリュウグウノツカイで説こうとしたが、北欧以外でリュウグウノツカイを人魚として見てきたかどうかさえ、今のところ当方には資料の持ち合わせはない。やはり、紐帯類は今後の課題だ。
by釜野啓(aka. MORO-Z)
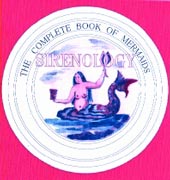
本間義治は新潟大学名誉教授である。1930年4月1日、新潟市生れ。1950年新潟大学教育学部卒。新潟大学理学部教授、同大学理学部附属佐渡臨海実験所長を務めた。専門は魚形動物の神経・内分泌系・造血系諸器官の組織学的研究。農学博士。顕微鏡下の研究の一方、新潟県の漂着動物の調査報告でも多くの業績があり、論文は500編以上、30冊余りの著書がある。単著には『新潟県 海の魚類図鑑』(新潟日報事業社、1992.6.25)、『日本海のクジラたち』(考古堂書店、2003.9.1)がある。近年は新潟大学大学院医歯学総合研究科顕微解剖学分野で組織学の研究を続ける一方、日本海セトロジー研究会で活発な活動を展開している。Cetologyとは鯨学の謂である。漂着動物の研究でも業績を重ね、2005年7月30日発行の「ちりぼたん」(日本貝類学界)第36巻第2号に、青柳彰、箕輪一博、中村幸弘と連名で「2004~2005年冬季に新潟県沿岸へアミダコが次々と漂着」を載せている。
本間が人魚に関心を抱き、発表するようになったのは、直接には松森胤保の「両羽博物図譜」を磯野直秀らと研究する機会を持ったことによる。松森がその図譜に人魚を真物として取り上げていたことから発している。勿論、それ以前から漂着動物の調査で、リュウグウノツカイ、サケガシラなどアカマンボウ属魚類についての報告もあった。本間は同じ魚類学者の内田恵太郎の人魚についての論考を評価し、日本の人魚=リュウグウノツカイ説を受け入れ、ことある毎にその説を普及させることに努めた。現今のリュウグウノツカイ人魚説の中心人物と言っても良いだろう。本間の人魚論には次のようなものがある。
その他、「リュウグウノツカイとサケガシラ」(「蒲原」第33号、1973、pp.43~52、未見)、「日本の人魚-正体を探る」(『新潟の生物誌-海から山まで』、1992、pp.73~84、未見)、特別展(柏崎の海・珍希生物展)図録『珍希生物』(柏崎市立博物館、1994.7.23、pp.37~38、「魚類」)、Comparative Anatomy and Histology of the Visceral Organs of an Oarfish, Regalecus russelli, and a Razorback scabbardfish, Assurger anzac, caught off the Coast of Fukui Prefecture, Sea of Japan(「紐状型魚類2種の内蔵諸器官に関する比較解剖学的ならびに組織学的研究」、「柏崎市立博物館館報」第16号、2002、pp.71~86、牛木辰男・武田政衛・石橋敏章と連名)なども関連ある論文であろう。
松森胤保(1825~1892)は江戸末期から明治にかけての博物学者。庄内藩の支藩松山藩の付家老を幕末に勤め、明治維新後も地方政治にかかわった。晩年は奥羽人類学界を興し、東京の「東京人類学界雑誌」に寄稿している。その傍ら、獣類、禽類、爬虫、魚類、貝螺、飛虫、植物の図譜など多くの著作を残している。その図譜は『両羽博物図譜』と称され、磯野直秀らにより研究紹介されている。
『両羽博物図譜』は戦前は江崎悌三の研究があり、戦後は中村清二『幕末明治の隠れ足る科学者 松森胤保』の著があるが、より一般に知られるようになったのは1980年以降のことだろう。月刊グラフ山形デラックス『みちのくの美しき城下町松山と日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ松森胤保』(東北出版企画、1980)、洲之内徹『人魚を見た人』(新潮社、1985)、『幕末明治の科学者 松森胤保の世界』(致道博物館、1987)、博物図譜ライブラリー2『鳥獣虫魚譜 松森胤保[両羽博物図譜の世界]』(八坂書房、1988)、志田正市『郷土の偉才松森胤保』(1989)、『彩色江戸博物学集成』(平凡社、1994)、松本健一『幕末畸人伝』(文藝春秋、1996)、などの著作の他、磯野直秀の「慶応義塾大学日吉紀要・自然科学」誌上の諸論文、本間の「ミクロスコピア」「新潟県生物教育研究会誌」上の諸論文など生物学者の研究論文も発表されている。
磯野直秀は八坂書房版『鳥獣虫魚譜』の「あとがき」で次のように述べている。
『両羽博物図譜』に私が初めて対面したのは、昭和六十一年(一九八六)の三月三十一日であった。松森胤保翁の進化論についての記述を調べる目的で酒田市の光丘文庫を訪れた折りのことであった。一見して、図のすばらしさと資料的価値の高さに驚き、また図譜の背後に潜む胤保の枚挙の精神と体系化への意欲に圧倒された私は、以来『両羽博物図譜』を主軸に、松森胤保翁の足跡を追いはじめたのである。
そして、図の同定にあたり、爬虫類・両生類・魚類・軟体動物に関して本間義治の協力を仰いだ。
本間は佐渡奉行所の絵師石井文海が描いた海亀と海獣の絵を考証した論文中で松森『両羽博物図譜』にアカウミガメ幼体の図があることを指摘し、松森に興味を抱いていた。1987年富山大学で催された動物学会で磯野と出会い、協力関係が生まれた。その年の夏、鶴岡市致道博物館では「幕末明治の科学者 松森胤保の世界」という企画展も開催されている。本間「明治前半の偉大なナチュラリスト松森胤保の〈両羽博物図譜〉-その1 海の魚」(「ミクロスコピア」第5巻第3号、1988.8.15、pp.36~42)には、「人魚の実在を信ず」の部分があり、松森の人魚種の図も添えられている。「人魚 干燥物ノ写真」(写真とは正確に写した絵図のこと)は各部分16項目の測定値が記載されているが、これは安政3(1856)年に写生し、明治16(1883)年に複写したものである。本間は「サル類の頭骨と胸部骨格の後方に、スズキ型魚類の一種の骨格を継いだものらしい」とその素性を推測し、「人魚の実在を信じた松森の旧態依然とした態度と供に解せないのは、「人魚変類」として、「シンジョ種」と「油子種」を挿入していることである」と疑問を呈している。シンジョはアイナメ、油子はクジメの山形での呼び名である。松森の分類大系では魚類は海魚部と川魚部に二分され、部は属、類、種と下位に分類されている。人魚は海魚部人魚属人魚類人魚種となる。人魚属は人魚類の他に人魚変類があり、変類にシンジョ種、油子類が分類されている。正確な観察眼を持っている松森が人魚の存在を容認していたことに対する疑問が本間の興味を人魚に向かわせた。
「ミクロスコピア」の次号第5巻第4号に本間は「日本の人魚-リュウグウノツカイ」を載せている。論題が示しているように、最初から本間は結論を述べている。「日本古来のマーメイドは、決してジュゴンでもなければ、西欧でいうある種の海獣やイルカでもない。かつて内田恵太郎先生(故人)が説いておられたように、リュウグウノツカイという魚なのである」。リュウグウノツカイを彷彿とさせる文献としては、やはり「諸国里人談」「甲子夜話」の文を引き(内田が引用で誤記した「諸国里人談」中の「寛永年中」[←宝永が正しい]までも踏襲してしまっている)、その他「六物新志」の指摘などで、新しい文献としては、「北方文学」第2号掲載の「人魚塚」が取り上げられている。本間は溝井秀雄『飛ぶか海風号』から該当部分を引用している。今、「北方文學」第1年第2号(明治45年6月1日)pp.123~124のRH生「人魚塚(越後)」に帰って、引いてみると次のようになる。
たヾ一つ不思議なのは女の死骸が、磯明神の傍の砂の上に、波に打ち上げられて居た。死體の下腹には人魚のやうに、細かな美しい赤と銀の鱗が生えて居て、美はしい顔はうらめし氣に眞珠の歯を食ひしばつて、長き緑の髪は藻のやうに亂れみだれて居た。
本間によれば「緑色の髪を除けば、これもリュウグウノツカイを思い起こさせる描写である」となる。「緑の髪」とは決して「緑色の髪」ではなく、黒髪の形容であるが、漂着死体であるという以外は、リュウグウノツカイとも思えない。「細かな美しい赤と銀の鱗」などはリュウグウノツカイと一致しない、「人魚」の文学的描写と捉えて構わない。この佐渡情話の一バージョンである「人魚塚」に関する説話は扱いが難しい。島から本土に夜夜渡ってくる女の悲話は、初島、琵琶湖などにも見られるが、死体が必ず人魚と結びつける必要はないようである。男女の秘話で良いし、人魚となった女が裏切った男を海に引き入れるという話に発展させてもよいと、極めて扱いにくい話柄である。今は深く立ち入る必要はないが、本間の郷土愛と受け止めておこう。それは、臨界研究所が置かれた佐渡の八百比丘尼伝説に言及することにも窺える。佐渡の八百比丘尼は高津家の娘と語られていて、その高津家は家宝として「九穴の貝」を伝えている。本間はそれがオウムガイであると報告している。長寿の原因には人魚の他に「九穴の貝」としているものも全国的に見られる。それが実は漂着したオウムガイかもしれないのである。ここは本間本来の業績が反映している部分であろう。本間は最後に同じ魚類学者の末広恭雄(1904~1988)が内田と同じ文献を引き(二人とも単に「廣文庫」を利用したに過ぎないのだろうが)つつ「人魚」を論じていて、ジュゴンばかりに言及していることに苦言を呈している。曰く、「リュウグウノツカイには一言も触れておらず、底が浅い」。だが、果たしてそうであろうか。
本間が批評の対象としている末広の文章は『魚と伝説』(新潮社、1964.11.30)所収の「人魚の実相」pp.227~230という文章である。書き出しは「私は一昨年アラブ連合共和国に半年ほど滞在し、その間紅海の沿岸にある海洋研究所にしばらく足をとどめたが、そのおり私の注意をひいたもののうちに紅海のジュゴンがある」とあり、最初からジュゴンが中心であることを断っている。しかも、「世界におけるジュゴンの分布は、主として熱帯地方であるため、日本ではジュゴンの姿は殆ど見ることが出来ないし、まれに見る可能性があるとしてもその地域は九州の最南端よりもっと南の方である」として、日本の多くの人魚伝承がジュゴンで説明できるとは言っていない。「日本の人魚はジュゴンではなくてほかの水棲動物ではないかと考えられる」とする一方、「日本の人魚の記事はまゆ唾ものかもしれないし、好意的にみれば、すばらしい空想に発した文芸作品なのかもしれない」と結んでいる。「他の水棲動物」としてリュウグウノツカイを魚類学者の末広が指摘しなかったことに、むしろ興味を覚える。「廣文庫」に挙げられた記述から末広はリュウグウノツカイに結びつくものを見いださなかった。朝鮮でリュウグウノツカイやサケガシラに結びつくサンカルチーを知っていた内田の経験が、白い肌・赤い髪という文字にリュウグウノツカイを見てしまったのである。海の異形が赤い髪を持つという修辞は中国では普通の表現であった。強いてリュウグウノツカイを持ち出さなくてもよいように思えて仕方がない。むろん、ジュゴンに結びつけることにも違和感を持つ。
末広の人魚記述に戻るが、単行本に収録された文章の他に、末広には「人魚について」(「科学読売」第17巻第9号、1965.9.1、pp.78~83)という文章がある。前半は「人魚の実相」と同じく文献に現れた日本の人魚の紹介、つまり『廣文庫』を引くことである。内田同様「甲子夜話」の記述に注目しているが、内田がリュウグウノツカイとはあまり結びつかないものと思ったのか、紹介をしていない人魚の恩返しと言える「広大和本草」の人魚記述にも注目している。また、「日本における人魚の文献はまことに多いが、それをいちいちあげることは、余りにもわずらわしいので、人魚なるものを解説する上に必要だと思われる、いま一つの古事について話しておきたいと思う」として空印寺の八百比丘尼についても一応報告している。動物学者の人魚記述の約束事とでも言うようなミイラについては、おもしろい話を紹介している。
1825年ころだといわれているが、日本のあるきわもの師が、サケの胴にサルの頭を継ぎ足して人魚をつくりあげた。ところがそれをあるオランダ人が買い求めて国に帰り、学界に発表したところ、大問題となったが、偽物とわかって、その学者はたいへんな恥をかいたということが文献にしるされている。
「あるオランダ人」とはシーボルトのことかもしれないが、手元に確証がないので不明としておこう。これと同様のことを本間も「妙智寺(鯨波)所蔵の人魚をめぐって」(1990)で伝えている。「ことに、この人魚を新種であろうとオランダへ持参した学者(誰かは特定できない)が大恥をかいたというエピソードが伝えられているくらいである」と本間は記している。
末広「人魚について」の後半はジュゴンについての概説となっている。末広は「どんな動物が人魚と見誤られたかということを検討してみる必要がある」と言って、イルカやジュゴンを挙げ、「現在動物学者の間で一番強く推されている動物はジュゴンである」と記す。ただ日本各地で目撃談としてつたえられている人魚についてはジュゴンである公算は少ないとも認めている。そして、それ以上の詮索を放棄してジュゴンの形態・生態について概説することに止めている。拠り所としている文献はドイツのリュッペル(1833年)、エジプトのゴーハル(1957年)、平坂恭介、阿部襄のものである。阿部のものは原文の引用もかなり長く行っている。平坂恭介(1887~1965)は戦前は台北帝国大学、戦後は新潟大学で教授を務め、本間義治が初代所員として勤務した新潟大学理学部附属臨海実験所の所長を勤めた動物学者である。本間には平坂の業績を論じた文章が数編ある。近いうちに平坂の人魚関連の文章を紹介しようと思っているので、詳細はその場に譲ることとしよう。
日本の戦前のジュゴン研究は平坂の台湾と南洋庁(1922年4月~1945)が置かれたパラオ諸島が中心であった。そのパラオのコロール島アラバケツに1934年に開設されたのが「パラオ熱帯生物研究所」である。阿部襄(あべ のぼる、1907~1980)もこの熱帯生物研究所でサンゴを研究した。阿部襄は阿部次郎(1883~1959、哲学・美学者)の甥(長兄一郎の長男)で、1931年東北帝国大学理学部卒業。浅虫臨海研究所で貝の研究の後、パラオに渡り、その後、満洲吉林の師道大学教授となった。戦後は山形大学農学部の教授を務めた。子供向けの科学書も多く執筆している(「貝の科学」「サケの一生」「パラオの海とサンゴ礁」など)。広島大学教授、向島臨海実験所長であった動物学者阿部余四男(あべ・よしお、1891~1960)も叔父である。阿部襄は松森胤保が付け家老となった山形県松山の出身である。
末広が引用している阿部の文章は「人魚」(平岩米吉編『動物とともに』、筑摩書房、1956、pp.121~123)と題する短文である。書き出しは「人魚の話は世界のあちこちで話されているが、起りは東洋だということである。日本の人魚の話は、どうも北の荒海に多いようである」。その後『古今奇談 莠句冊』を引くところなどは、通常の動物学者に見られない文学素養を感じさせる趣向である。『莠句冊(ひつじぐさ)』の人魚も「肉白く髪赤く長し。紅鰭の間に手あり」と表現されているので、内田や本間が見たらリュウグウノツカイだと、断言するであろう。『莠句冊』にはまた、人魚を一字の漢字で表す{魚+役}、{魚+人}という見なれない文字も使われているそうである。これらの漢字については加納喜光が「漢字動物苑(5)人魚」(「月刊しにか」、1995.8)で解説している。脱線になるが、加納は同文の文頭で、小学生時代に、奄美大島に打ち上げられたジュゴンと思われる死体を見て、末広恭雄(雑誌に海の怪物について述べていたことを加納少年は覚えていた)に手紙を出し、返事(詳細を報告するようにとの内容)を得たことを書いている。
さて、阿部襄に戻るが、阿部はパラオでジュゴンを何度か目撃している。
島の向こうにふと人魚があらわれた。胸から上を水面に出して、少し前かがみになっている。その白い肌。母親の人魚が、珊瑚に腰かけて赤ん坊にお乳を飲ませているらしい。
ここで言う「人魚」とはジュゴンのことである。近年はジュゴンの立姿での授乳は否定されているのであるが、阿部はそれを目撃しているのである。末広が阿部とともに引くゴハール博士の紅海での観察例でも、「私はかつて、母親のジュゴンが浅瀬に出て、ヒレを手のようにつかって、幼児を抱きかかえて授乳している姿を幾度か見たが、それはいかにも人魚の仕草によく似ていた」とある。末広はこれら文献の記述を踏まえ、エジプトの研究機関で実際に見たジュゴンの標本の前で、「これならいわゆる人魚を頭に浮かべてもしかたないだろうという感じを受けたのである」と思った。率直な感想なので、「底が浅い」とも言えない。リュウグウノツカイを実際に見たら人魚だ思うように、ジュゴンも人魚なのである。ただ、それでは学者の批評眼ではないと言えば、そうであろう。末広は日本の人魚のモデル探しを放棄してしまったのだから。だが、モデルはいない、という立場なら話は別であるが。末広は「人魚について」の最後に、東京大学に留学しているセイロン(現スリランカ)人男性から得た結婚式のジュゴン料理の話を紹介している。
1匹が平均15万円くらいだが、プレゼントする際には、腹をさいて丸焼きにし、その中にはキャベツとコメをつめて、そのままのカタチデテーブルにのせ、皆してそれを食するということだ。なお、同氏の語るところによれば、肉の色は紅色で、その味は、ごく上等の牛肉のようだということだ。
末広「人魚について」には補足としてか西脇昌治「「人魚について」を読んで」(「科学読売」、pp.82~83)が添えられている。西脇(1915~1984)は当時東大教授、鯨・鰭脚類・海牛類の専門家である。西脇は日本の人魚伝説はジュゴンの代役としてスナメリが寄与しているのではないかと述べている。スナメリはシュゴンより広い生息域を持ち、「日本海では九州はもちろん、太平洋岸では金華山島付近まで、日本海では能登半島付近まで知られており、化石または半化石は北海道周辺から出る」と、日本の人魚を考える上で重要な動物であると指摘している。また、自身で生体を観察したフロリダのマナティーについても報告している。
末広がリュウグウノツカイに言及している文章に、「地震に対する魚類の異常生態」(「京急油壺マリンパーク水族館年報」第1号、1968、pp.4~11)がある。末広は1934年に三陸沖の海底大地震の際に深海魚シギウナギが小田原海岸で採集されたことに刺激を受け、地震と魚類の敏感性に注目して研究を続けていた。そこには初代地震研究所長であった父末広恭二(1877~1932、工学博士、東京帝国大学工科大学教授、造船学。明治の小説家、政治家末広鉄腸[重恭、1848~1896]の次男)の影響があるのかもしれない。末広恭雄の有名な研究に地震予知へのナマズの脳は利用がある。恭雄は昭和4年東京帝国大学農学部水産学科卒。農林省水産試験場技師を経て、東大農学部教授。その後京急油壺マリンパーク水族館長を勤め、ユニークな展示方法を実践した。魚類学の啓蒙随筆を多数執筆し、著書は120を超える。
「地震に対する魚類の異常生態」には調査結果として、伊豆新島地震(1963.11.14)の2日前にリュウグウノツカイが波打ち際で捕獲、新潟地震(1964.6.16)の2日後に柏崎市海岸波打ち際でリュウグウノツカイ捕獲、宇和島湾地震(1968.8.6)の3ヶ月前に宇和島市小池の浅瀬でリュウグウノツカイ捕獲などを報じている。これらが何を意味しているのか、あるいは意味していないのかの評価を下すことは出来ないが、本間は「リュウグウノツカイの浮上と地震を短絡的に結びつけている」と「新人魚考」で批判している。次に本間「新人魚考」とは、どのようなものなのか見て行こう。
本間義治の「新潟県生物教育研究会誌」第24号(1989.3.28)pp.55~62に掲載された論考である。先に発表した「ミクロスコピア」誌上の2論文を一つにまとめた体裁である。前半は松森胤保の人魚、後半は日本の人魚について述べている。書き出しは「人魚について、我が国で最もよく実例を挙げ、実証に努め、科学的に考究したのは、内田の論説であろう」と内田恵太郎の業績へ最大級の賛辞を呈している。これに対し非難の対象になるのが末広恭雄である。「一方、末広は、その著『魚と伝説』の中に上記と同様の古文書を紹介して、人魚を解説しているが、ジュゴンの分布などにこだわり、リュウグウノツカイと見抜けず、内田を読んだ節がなく、全く物足りない」。何度も言うようだが、「最もよく実例を挙げ」た内田も「同様の古文書を紹介した」末広も、内田と本間が参照した日野巌も、大本は『廣文庫』に収録された人魚文献に大きく依存しているに過ぎない。それが今までの日本の人魚記述の基本であり、それに何をプラスするかで論者の興味のありようを測ることができるというものだ。内田はリュウグウノツカイを持ってきた。末広はジュゴン、日野は『廣文庫』以外の若干の日本の文献と外国書からの情報、本間は松森胤保の人魚と地元新潟の人魚伝説である。
「新人魚考」には『両羽博物図譜』から人魚に関する「松森の記述の全文」を引用してくれている。人魚図とそれに添えられた測定値は『鳥獣虫魚譜 松森胤保[両羽博物図譜の世界]』(八坂書房)のカラー図版で見ることが出来るが、全文はなかなか確認できない。松本健一『幕末畸人伝』p.137、pp.138~139、pp.140~141にも片仮名を平仮名書きに変えた松森の記述が引用されているが、所々判読不明字があったり、最後が省略されているなど全文ではない。また、本間が引く磯野直秀からの教示による、松森『生類微事』からの人魚に関する記述も重要である。それらの情報によると、松森が写した人魚は、鶴岡の商人のもとにあり、丈は二尺ほど。魚の部分は松森には「シンジョ」、つまりアイナメに似ていた。上半は人に似ていたが、むしろ「獣畜ノ相」に見えた。人間そのものでなく、「獣畜」に似ていたことが、松森にそれが真物ではないかと思わせたらしい。松森は「獣相ヲ備ヘ天造ノ妙 人工ノ及ハサル所ヲ有ス」と述べ、さらには橘南渓『西遊記』から日向の山女の記述中に「人間ニ異ナラスト雖 獣相アリ」と「獣相」の文字がある故に真実だと確信する、とまで言っている。美しい顔の人魚でない故に、自然物と信ずるとは独自の見解である。松森は人魚を人間と魚の中間物として、その存在を措定し、人間では無いのだから獣の類、獣相を持つはずだと考えたのである。美しい人魚は空想や修飾の産物として、常々「擬物」としてその存在を否定していたのである。磯野直秀は『鳥獣虫魚譜』の解説で、「人魚や海産哺乳類が登場するのは、胤保の古さを示すものであるが、彼の「万物一系理」からすれば、人と魚、哺乳類と魚類をつなぐ存在が重要だったということを理解する必要があろう」(p.119)と述べている。
松森もこの人魚に不自然な部分があることには気付いている。「又云自然ノ物ニシテハ独不都合ナルモノアリ人ノ胸尽タランニハ魚ノ腹之ニ属スヘキノ理ノ如シ 然ルニ否セス人胸尽テ魚胸次ク理果シテ如何ントス」。胸部が人間と魚、二つ存在することへの疑問である。この自問に対する答えは述べられておらず、疑問のままである。松森の記述で興味深い点は他に、「郵便報知新聞」の明治16年7月26日の記事を引いていることがある。この日付は正確であり、当該記事を見つけることができる。「郵便報知新聞」第3116号、第2面の「府下雑報」記事中に以下のような文章がある。(郵便報知新聞は明治5年6月10日創刊。明治14年矢野龍渓に経営が移ると、改進党の機関紙として民権派の急進論を載せるようになった。)
○怪魚 神奈川縣下久良木郡根岸本牧村の漁夫田沼九十郎が三四日跡金澤沖に於て漁業の際網にかけて引揚げた魚ハ体の長さ二尺五寸にて頭ハ猿の如く顔面の摸様人に彷彿として全身に黒き短毛を生し尾ハ畳針を十二本列び種ゑたる如くにて蹼にも四本の大針ある異形の魚なれバ怪しとて其趣を戸長役場へ届け出しといふ
松森は明治17年7月1日、山形県飽海郡酒田の戸長になっているが、それ以前には県議会議員にも当選し、政治、世相に関心を抱いていたことがわかる。東京の郵便報知新聞にも目を通していたのであろう。それはともかく、この記事にたいする松森の興味は次のように要約されている。
胤保案スルニ亦之人魚ノ一ナルヘシ 頭ハ猿の如く顔面ノ模様人ニ彷彿トシテト有ルハ尤要所ナリ人面ニシテ蓋シ獣相ナルモノナルヘシ
「怪魚」は「人魚」に分類され、その重要な点は「獣相」にあった。実に都合の良い記事があったものである。人魚のミイラを目の前にしているような書きぶりである。人魚を信じたい松森の気持ちが通じたような新聞記事である。
本間はUTAN第7巻第7号(1988.7)の記事から、明治時代に神奈川県の漁師が外国人向けに人魚のミイラを製作したと伝えている。明治時代の人魚製作については竹内久一(帝室技芸員・東京美術学校教授)が「贋物に就て」(「書画骨董雑誌」第75号、大正3年9月1日、pp.27~32)と題する文章中で述べている。「余の人魚の研究」との見出しの下に以下のような興味深いことが語られている。
其の時件の商人は斯んなことを語つた。
斯様な事は善くある事で、昔或金満家が人魚を食ふと不老不死だと云ふので、多額の金を投じて或商人から一匹の人魚を購ふた。而して愈々食せんものと腹を切開して見ると中から鉋屑が出たとのことだ。云々。
乃で私は此人魚と云ふ物に急に興味を起し、之を研究して見る氣になつた。一體人魚と云ふ物は古来傳説にはあるが未だ其の活物を見た者はない。偶々人魚だと云ふ物を見るとそれは乾物である。斯くて段々其の研究を積んで居ると不圖人魚を造る人に出會した。それで其の人に就て人魚の作法を尋ねると、人魚と云ふ物は全く想像的の動物で、猿の子の干物を以て頭と手を作り、胴體は魚の剥製で造るのである。其の魚は鯉でなし、鱸でなし一見何魚か解せられなかったが、聞けば鯔に限るとのことだ。而して猿の頭と鯔の次ぎ目は猿の毛で隠し、更には五色の糸などで下の臺に結び付け以て人を欺いた。今の人は斯様なものに欺かれぬが昔の人は善く欺かれた。人魚の作者は淺草蔵前の大萬と云ふ人であつた。
江戸時代にも浅草奥山に宇禰次という人魚制作者がいたが、見世物の中心地浅草には製作技術が伝承していたのかもしれない。その他、中京にも製作地があったことを新聞は伝えており、複数の製作中心地があったことが推測される。その人魚を江戸時代にオランダへ持ち帰った学者を本間はこの「新人魚論」では「シーボルト?」と推測していたが、後の文章では「誰かは特定できない」と訂正している。この部分のエピソードは末広の文章でも見られたことは既に報告している通りである。
新潟県下では人魚のミイラは柏崎市鯨波の妙智寺にある。その報告は本間「妙智寺(鯨波)所蔵の人魚をめぐって」(「蒲原」第78号、pp.3~10)に詳しい。人魚を収める箱裏の文章(人魚所有之事暦)も全文掲げられている。本間は人魚の正体を「種は不明なもののサル類の一種(ホンドザルか?)の頭胸骨に、脂鰭をもつサケ型魚類の一種(多分サケ=シロザケ)の胴尾を巧みについだもの」と記している。また、有名な学文路の人魚についても写真を見て「胴尾はやはりサケである」と見なしている。次いで東京大学理学部動物教室に残る『梅園魚譜』写本の人魚についても報告する。この人魚についても本間は「サルの胸郭(梅園の添書きでは鳩尾)に、脂鰭をもつサケの胴尾をついだ跡がはっきり分る」と述べている。『梅園魚譜』の人魚は今や国立国会図書館のサイトで見ることができる。毛利梅園(1798~1851)は人魚の来歴について「塩辺大工町辻川氏所蔵スルヲ白山下指舎町赤塚伊勢屋ヨリ塾医神谷玄雄借来リシヲ余ニ真写セヨトアトウテ時天保八丁酉九月廿日頓写一覧ノ上相返ス」と記している。松森が最初に写した安政3(1856)年から19年前のことであった。商家、大名家などにはかなりの人魚があったことが窺える。本間は妙智寺の人魚を報ずる文章の最後で、「ヴィクトリア朝の絵画」展に出品されたウォーターハウスのマーメイド、シャガール展の「エンジェル湾」の人魚にふれている。好奇心と探求心の深さが感じられる論考である。
さて「新人魚考」の後半は小川未明「赤い蝋燭と人魚」に反映していると上笙一郎が指摘した大潟町の「人魚塚」にまつわる話、日本の伝説や実見譚、八百比丘尼伝承など既出の「日本の人魚-リュウグウノツカイ」で述べられたことと重なるので紹介は省略する。結論部分を引いてみよう。
めったに見ることのない奇態な魚を人魚と見做すことは無理のないところであろう。生時は幻想的な美しさをもつリュウグウノツカイも、水分過多のため、一度乾からびたら、一挙に醜悪な老婆に化してしまうのである。これをあわれみ、埋葬してやった海辺の人達の心根はゆかしい。このことと人魚の吉凶ことに大時化と結びつけて考えれば、人魚伝説や実見談も相当な程度に氷解するのである。
この部分は自身の漂着リュウグウノツカイを観察した経験が強く感じられ、それを過去に反映してるようでならない。「人魚」という言葉は中国からの移入語彙である。それについて記述してきた人々は知識人であった。「海辺の人々」が奇妙な生き物を見て、「人魚」という語を思い付くことが出来るようになったのは江戸時代末、あるいは明治になってからかもしれない。少なくとも江戸初期までの海辺の人々には「人魚」という概念は無かったように思われて仕方がない。記述された知識を共有する人々は時代とともに広がりを見せるであろうが、知識の担い方は民衆の経験が先行するとも限らない。「人魚」という外来の概念があり、そこに多種の経験が付随し蓄積、記述される。その一部にリュウグウノツカイの漂着が無かったとは言えないが、それが一番の原因とも思えない。江戸時代以降の博物学知識の普及と考証随筆の隆盛の中で、人魚と異魚リュウグウノツカイとの結びつきを直接示唆するものが乏しすぎる。内田以降の魚類学者が引用する文献は他力本願(『廣文庫』の利用を指す)で発展性が少ない。一段の意欲的な文献発掘がなければ、日本の人魚=リュウグウノツカイ説は脆弱な仮説に留まるだろう。内田が着想したリュウグウノツカイ説を大事に守るだけでなく、より豊かな事例で補強することが大切である。それがない、或いは出来ない時は大声でリュウグウノツカイ説を広めてはならない。それはリュウグノツカイ説を示唆している魚類学者の責任であり、それに組みしない者をそのことだけで非難することは酷ではなかろうか。
その意味でも今回取り上げる本間の最後の論考「博多龍宮寺の人魚をめぐって」は興味深い。龍宮寺の人魚骨はリュウグウノツカイのものでないことは明らかである。それに本間らは取り組み、日本の人魚伝承の広がりを確認できたのだから。
福岡市博多区冷泉町4-21の浄土宗冷泉山龍宮寺には「人魚の骨」が収められている。人魚骨、人魚を描いた掛け軸、境内の人魚塚についてはサイトがある。こちらは『益軒全集』巻之四(益軒全集刊行部、明治43年12月15日)p.95「筑前國續風土記巻之四」の「龍宮寺 浄土宗鎮西派」を引いてみよう。
冷泉山視現院と号す。開山谷阿上人と云。開基の年号詳ならず。此僧四條院仁治二年に遷化す。寺家に云伝ふるには、此寺初は意浮御堂といふ。寺号を龍宮寺と改し事は、貞応元年四月十四日博多のうみより人魚を捕得たり。此由朝廷へ奏聞しければ、勅使として冷泉何某下向ありて、暫く此寺に居住せらる。其時安倍大富といへるうらかたの博士、人魚出現の事を占ひ、国家長久の瑞兆なりと申ける。やがて人魚をば此寺中にうづみぬ。其後改めて龍宮寺と号す。此魚人に似て、海中より出たれば、龍宮より来れる物といへる意也。又冷泉院と号せしは、冷泉何某此所に逗留せられしによりてなり。
人魚出現を陰陽博士に占わせるなどは鎌倉初期の様相を呈しているが、貞応元年は1222年である。鎌倉時代の著名な人魚漂着は宝治元(1247)年、津軽に漂着したものであるが、その時は「先規不快」という悪い徴ととらえた。博多の人魚は全長33間と60m余りの長大な物であったと伝えられている。本間等は人魚の骨と伝えられているものは、「鯨類の手羽すなわち胸鰭を構成する諸骨を主体としているように見受けられ」と推測した。鯨だとすれば本間等が推奨する日本の人魚=リュウグウノツカイ説の埒外になり、文末には「リュウグウノツカイにあらざる人魚伝説が、内陸のカワウソ以外にも海生動物に基づくものがあったことに、少々の動揺を覚えながら纏めてみた」とある。どうやら、この論文以前に本間らはカワウソも人魚に関連するのではと推測していたらしい。それに関する論考は残念であるが、目を通していない。また、龍宮寺の調査は1997年夏、上越市立水族博物館で開催された「人魚展」準備の資料収集の過程で行われたことが論中に明記されている。この「人魚展」も見る機会を逸している。これまた残念であった。
本間は1996年7月、スウェーデンで開催された国際シンポジウムに参加した帰途、コペンハーゲンの人魚姫像を見ている。好奇と実地主義の発揚である。その点は脱帽に値する。本間、およびその周辺の人々がリュウグウノツカイ説の更なる精密化を図られることを切に希望して、やや無礼であったかもしれない今回の紹介を終えよう。
by釜野啓(aka. MORO-Z)