東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>28P
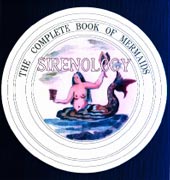
内田恵太郎は古代ギリシアのセイレーン伝説についてメイグルというニベ科の魚が鳴らすウキブクロの音ではないかと述べたことがある。荒俣宏『世界大博物図鑑2魚類』(平凡社、1989.5.30)は「ニベ・グチ」項において、その音は「オルガンの低音部のような、鐘のような、カエルの合唱のような、巨大なハープを奏でるような音」「はじめは太鼓を打ち鳴らすように聞こえ、やがて湯が沸きたつような音になる」「雷のような声」と諸書を引いて説明している。人魚のうたが打楽器にたとえられるようではさびしい気もするが、そんな説を考えた魚類学者もいた。
セイレーンとオデュッセウスの船を表紙に画いた雑誌が明治末年に発行された。明治45年3月11日印刷、3月15日発行の「シレエネ」である。シレエ子編輯所は小石川区雑司ヶ谷町八七、シレエ子発行所は大阪市南区天王寺北河堀町2449。東京一手販売所は文好堂書店(牛込区通寺町)、大阪一手販売所は登美屋書肆(東区相合橋一丁東)。定価は一冊25銭、郵税2銭であった。セイレーンを画いた表紙絵は宇野浩二、裏絵は青木精一郎。青木は渡瀬淳子と共に挿画も描いている。全149頁の内容は次の通りである。
| 悲しき日のために | 齋藤青羽 | 1〜6 | 詩 |
| 苦悶と自嘲 | 堀口朔 | 7〜28 | 感想 |
| 薤露歌 | 三上白夜 | 29〜54 | 小説 |
| ペレアスとメリサンド | 出隆訳 | 55〜70 | メーテルリンク戯曲 |
| 暁の歌 | 宇野浩二 | 71〜84 | 戯曲 |
| LAMPの蔭より | 今井白楊 | 85〜87 | 感想 |
| 愛の言葉 | 春日野篤訳 | 88〜95 | モーパッサン小説 |
| IPSE DIXIT | 白夜子 | 96〜101 | 感想 |
| ゼ、ルネツサンスの序 | ウォルタア・ペァタァ | 102〜108 | NH生訳評論 |
| 宗右衛門町の小品 | 浩二 | 109〜121 | 小さい清二郎の記憶 |
| シモンズの詩 | 青羽生訳 | 122〜125 | 訳詩4篇 |
| 雨の夜の一時間 | 田村華陽 | 126〜135 | 小説 |
| 創作批評 | 堀江朔 | 136〜144 | 二月の小説批評 |
| 雨の夜 | 同人 | 145〜148 | 編集後記 |
| 大阪にて | 同人 | 148〜149 | 編集後記 |
「シレエネ」の編輯をした宇野浩二は『文學の三十年』で当時のことを次のように回想している。
井汲を知った年の翌年の春、私と齋藤と三上が合議して「シレエネ」といふ雑誌をだした。シレエネといふのは、英語のSirenで、ギリシャ神話のシレン(岩の多い島に住み船員たちをその音楽に依って誘惑したと言ひ伝へられる女または半女半鳥の妖魔)である。又、シレエネは英語のサイレンのギリシア語といふのは嘘か誠か。いづれにしても、慥これは三上が云つたので、この題も三上が附けたやうに思ふ。さうして、これは、いかにも三上好みの題であるから、間違ひではないと思ふ。この雑誌は、いはゆる同人雑誌でなく、費用は、私の中学の同窓、青木宏峰(今の大乗)が出した。
セイレーンを「シレエネ」と表記することは今日では普通ではないが、与謝野晶子も詩「涼風」(初出、「明星」大正13年9月)の一節「風の中の美くしい女怪」の「女怪」に「シレエネ」というルビをふっている。
「シレエネ」に集った若者たちは主に早稲田の学生たちであった。宇野浩二(1891〜1961)は後の小説家。三上於菟吉(1891〜1944)は大衆小説家。齋藤青羽(寛)は後に外国語学校の仏語科を卒業し郵船会社の重役となった。堀口朔(1891〜1939)は評論家。出隆(1892〜1980)は齋藤の中学の同窓で、東大哲学科卒、専門はギリシア哲学。今井白楊(1889〜1917)は詩人。モーパッサン「愛の言葉」の訳者春日野篤は増田篤夫(1891〜1936)か、増田は評論家。青木精一郎(1891〜1979)は後に大乗と名のって日本画家。田村華陽については紅野敏郎も「その後のありようは、いまのところわからない」「大阪組の一人であったに違いない」としていて、不詳。
実は表紙のついた「シレエネ」を見たことはない。表紙の欠けたものを読んだだけである。表紙については紅野敏郎が「国文学 解釈と教材の研究」の連載「逍遙・文学誌」(13)で「宇野浩二・三上於菟吉らの「しれえね」」について表紙写真付きで紹介している論考に全面的に依拠している。紅野は表紙絵についてこう語っている。
古代の奇妙な形をした舟、櫓をこぐ六人の人びと、中央の太い帆柱、しかし帆をたかだかとかかげているというわけではない。全体が大きな甕のなかに収まっていて、その甕の外に羽根をひろげた鳥が左右に二羽。鳥ではあるが、人に羽根が生えたかのような雰囲気も漂っている。ギリシア神話のシレン、舟人を音楽で誘惑したと伝えられている「半女半鳥の妖魔」である。宇野文学のキーワードともいうべき「夢」で織りなされた意匠、といってよかろう。その下に配した朱の「志れえね」の文字も人の心を強くひきつける。
先に目次で示した「雨の夜」「大阪にて」はいわば編集後記で、当時の慣例として6号活字で組まれている。その中で「格のかいた表紙の絵は鳥渡うまいね。字は於菟がしるしたのだが、評判によると王義之以上ださうな」とある。「格」とは宇野浩二の本名格次郎の「格」、「於菟」はもちろん三上於菟吉である。「帆をたかだかとかかげているわけではない」船とは、帆柱にオデュッセウスを縛っているところを際だたせるために表現されたもので、よく目にする大英博物館蔵の「赤絵のスタムノス」(アッティカ式、紀元前490年頃)のものに近似している。墜落するセイレーンが省かれているのは、これからの発展を願って創刊した雑誌の失墜のようで憚られたものか。実際の「シレエネ」も於菟吉の「薤露歌」により発禁となり、続かなかったのである。
セイレーンというとホメーロスの伝えるオデュッセウスの物語があまりにも有名であるが、意外なことに、図像的にはオデュッセウスとともに描かれるセイレーンは紀元前6世紀に始まり、現在知られているものは多くない。コリントの工房が最初でアテネが追随したらしい。帆に縛り付けられたオデュッセウスと漕ぎ手、岩上で歌う二羽のセイレーンを描いたコリント式のアリュバロス(球形の胴部を持つ香油入れ)は紀元前6世紀の第二四半期のものだという。白地に黒絵のレキュトス(細長い胴部の香油入れ)には柱に縛られた英雄と楽器を奏でる左右二羽のセイレーンが描かれているが、船は描写されず、跳ねるイルカで海上であることを表している。先の有名な赤絵は実は赤絵で描かれた唯一の例らしい。
「シレエネ」の失墜を招いた三上於菟吉「薤露歌」を読んでみよう。
全編、誌名に用いた「シレエネ」をモチーフにしたような作品の書き出し部分は、旅先のホテルで知り合った若い既婚女性へのわかれを綴る手紙の一節である。そこには「底知れぬ青みもて妖しの歌うたう瞳よ」とあって、女性が主人公の青年にとってセイレーンのようなファム・ファタルであったことを暗示している。もちろん、ファム・ファタルなどと言うことは男側の一方的な幻想で、女性側からすれば違う見方にはなるが、今は於菟吉、或いは「薤露歌」の主人公の青年の視点で見て行くことにする。
「幻想と惑乱とに充たされた長い間の都の生活は、薄手の玻璃の杯を挙ぐるものさえ倦くなるほど、若い心身を傷けそこで遂に彼はこの山の湯に旅客となつた」。主人公の青年の携えてきた本と言えば、「パメグラ子ツトの詩人が美しく悲しい物語」「ブルヂエ」である。「パメグラ子ツトの詩人」とはオスカー・ワイルドであろうか。ワイルドには「ざくろの家」A House of Pomegranatesという童話集がある。「ざくろの家」には4作品が収められているが、その一編は「漁師とその魂」、人魚(=シレーヌ)を扱った作品である。ワイルドは明治末年から本格的に日本へ紹介され始め、大正初期には「サロメ」が盛んに上演され、「漁師とその魂」も「帝国文学」(大正4年)「国民文学」(大正6年)などに邦訳が載っている。大正5年には春陽堂から「幸福な王子」所収の5作も含めたワイルドの童話作品全て(9作)の訳書『ワイルド童話集 柘榴の家』が本間久雄(1886〜1981)により出されている。「ブルジエ」はポール・ブールジェ(1853〜1935)であろう。フランスの批評家・小説家で、翻訳は昭和に入ってから本格化する。
その「ブルジエ」を借りたいと言ってきたのが一人で宿泊していた「若い奥様」であった。作品は「ブルウ、ダッチエス」、英訳本である。女性は父親が公使で、10代の頃はパリにいた。「悪の華」や「エルナニ」の感想を青年と語ることができた。「ヘリオトロオプ」の香を部屋に漂わせ、「キユラソオ」を嗜む。当時流行の「新しい女」なのである。夫も外交官で今は海外に赴任中である。青年にとって「彼の女の肉体はすべて誘惑であつた」。夫人の部屋を訪れると、「窓から流れこむ月が善いことよ。灯○○○○○○。」十日余りの間「夫人の肉体は彼を引きつけて一刻も離さなかつた。ローマの貴族に抱へられた美しい奴隷のやうな生活は、だんだん彼の心を腐らし身体を傷けはじめた」。都会に置いてきたはずの生活が旅先で復活してしまった。逃れる先は、また都会である。下宿に帰り身を休めて見る夢は「マーメイド」=シレーヌである。
閉じた眼は闇の中に輝く銀色の糸を見た。それがやがて集まって波頭のやうに空をうねりまはる。ふとその波頭に人の姿が浮いた。マーメイドである。人魚の顔は誰やら覚えのある面影であつた。そして熱い誘惑の眼付を投げながら、やる瀬なげに一声彼の名を呼んで沈んでしまつた。
夢から目覚め、見に行った芝居の結末は、「薄倖な恋のために、親を捨て主に背いた美しい男女は、岩の上から波に飛んでその姿を消した」というものであった。芝居がはねて、向かう先は、久々ではあったが馴染みの遊女の元である。ここでも青年の心は落ち着きを得られない。夢から夢へ移るように、翌日の夕には大河のほとりにたたずんでいた。絶えず「生の充足と心霊の威力」を思っていた彼は、河音が死へ誘う歌に聞こえてきた。抽象的な歌ではない。ある「ウインナの詩人」の作品の一節「暗き憂愁の琴に高まる甘くして神秘なる楽の音となれる死」。川面の渦の下には静かな里がある。「来ないか。来ないか」「妖姿の眼は彼に斯う語つた」。ついに「シレエヌ」の歌に身を委ねたのである。「夕闇はやうやう河面に迫つて来た。冷たい風に鳴る岸の葦が、するかせぬかの瀬の音と悲しい調和をなして、死せるものゝのために薤露の歌を奏でた」。
薤露とは夏目漱石「薤露行」でも使われているが、古楽府の「人生は薤上の露の如く晞き易し」から、ニラの上の露のように消えやすい人生のはかなさ、高貴な人々の葬儀で歌われた歌の意味である。既婚婦人、しかも外交官の夫人との関係を扱ったので、発禁処分となったようであるが、今日では問題視するような内容ではない。於菟吉の読書経験、生活が反映された、デカダンスと精神的なものに憧れる当時の青年の姿を素直に、或いはやや通俗的に描いた作品である。
文末に「(完−四五・二・一一夜)」とある。「シレエネ」創刊号は宇野浩二の編輯で、(一月)「二十一日の夜」に作業が終わったと思われる。その夜、宇野、三上、斎藤がいた下宿に堀江もやって来たことが編集後記「雨の夜」(21日は雨が降っていた)にある。「一月の末から三月上旬迄の休息です。そしてヤツとこんなものが出来ました」と宇野は最後に書き記している。しかし、「薤露歌」は二月の完成。堀江朔「二月の小説批評」も2月11日の稿。編集がごたごたしたことは窺われる。だが、次号の構想も、宇野の「大自慢のドラマ」、堀江の「大努力の結果になった研究」、斎藤の「アナクレオンを芝居に仕組んだもの」、三上の「仏蘭西文学の研究発表」など準備が進み、2号は4月5日、3号は5月1日に出すと宇野は弁明している。しかし、創刊号は発禁処分に合う。発行人青木精一郎(米穀商の父が雑誌の出資者)は40円の罰金を科され、以後の出資の道は立たれた。「シレエネ」の失墜である。三上於菟吉はどう受け止めたのであろうか。「雨の夜」では同人中で一番「せんちめんたりすと」と書かれた「於菟」、「西洋福の神」(ビリケン)に似ているという噂があった「於菟」。三上於菟吉は「薤露歌」のような数年を以後過ごすことになる。
早稲田大学文科予科を中退し、埼玉県北葛飾郡桜井村大字木崎(現、春日部市)の「四面皆梅楼」と称した自宅で読書と執筆の蟄居生活を3年続けた、と庄和町の『三上於菟吉と長谷川時雨』(1999.12.15)にはある。だが、講談社版『日本近代文学大事典』で菅原宏一は、於菟吉は神楽坂の芸妓と馴染み、連れ出して雑司ヶ谷に隠れ住み、抱え主と悶着を起こし、父親に連れ戻されたと記している。女との別れ方に自己嫌悪に陥り海で投身しようと乗船する。その船中で、姦通事件を起こしこちらも自殺を志した北原白秋に出会うという、それこそ小説のような話を菅原は伝えている。その蟄居生活の成果が自費出版『春光の下に』(大正4年)であった。今度は朝鮮独立運動を作中で触れていたため発禁処分。ただし、良いこともあった。『春光の下に』の献本先の一人に劇作家長谷川時雨(1879〜1941)がいた。最初に時雨が手紙を出すと、於菟吉は毎日のように手紙を書く。二人は一緒に暮らすようになっていった(大正6年)。於菟吉は大正5年以降、通俗小説を書くようになり、大正13年の新聞小説「百鬼」(大阪時事新報、大正13年8月16日〜大正14年4月5日、156回)が評判となり、流行作家と成って行く。
於菟吉は大正12年には直木三十五(1891〜1934)を助けて、元泉社という出版社を起こす。直木は以前から出版業に身を置き、鷲尾雨工(1892〜1951)の冬夏社(現在もある春秋社と一時近い関係にあり、「ユーゴー全集」「ダニンチオ全集」「マーテリンク全集」などの全集類やハヴェロック・エリスの翻訳書を出版、資金難のため大震災後の大正12年破綻)にいたこともあった。。元泉社からは於菟吉訳のゾラ『歓楽』、カーテイス・ヨーク『嘆ける曙』、木村荘太訳、ロマン・ロラン『天才』、木村幹訳、マルセル・プレヴォー『情熱時代』などが刊行されていたが、9月の関東大震災の影響で十ヶ月で倒産。同じ年、時雨も友人岡田八千代(1883〜1962)と「女人芸術」という雑誌を創刊(発行元は元泉社)したが、こちらも震災により2号で休刊となっている。同名の雑誌「女人芸術」は、昭和3年、流行作家となっていた於菟吉の資金援助で創刊され、48冊を刊行し、多くの女性作家を世に送り出した。於菟吉は昭和10年、サイレン社を起こす。「シレエネ」ならぬサイレンである。世に警報を発する気持ちを込めたものであろうか。
サイレン社で発行された書物で、現在岩波文庫に入っているものに、真山青果『随筆滝沢馬琴』、長谷川時雨『近代美人伝』がある。サイレン社刊の時雨作品には他に『草魚』があり、於菟吉作品には『幽霊城』『随筆わが漂泊』『青空無限城』『燃える処女林』『艶説隠れ蓑』がある。大衆作家の作には長谷川伸『藁人形の婿』、下母沢寛『霧の白菊』、松村梢風『駿河富士』などがある。その一方で、サイレン社はどちらかというと硬い内容の書籍も出版した。魯迅『支那小説史』、松村武雄『神話伝説の支那』、清水幾太郎『日本文化形態論』、中山太郎『愛慾三千年史』、式場隆三郎『心理解剖室』、安田徳太郎『社会診察録』などのラインである。翻訳書はスタンダール『パルムの僧院』、モンテスキュー『ペルシア人の手紙』などもあるが、当時流行していた外国探偵小説の路線が特徴的である。クヰイン『希臘柩の秘密』、マイヤース『トレント殺害事件』、キング『白魔の一夜』、シメノン『倫敦から来た男』などである。
『近代美人伝』についてはネット上にも松岡正剛氏の論考(「千夜千冊」第千五十一夜「長谷川時雨『近代美人伝』上・下」)があるので、そちらをご覧いただくことにして、『草魚』について報告しておこう。
『草魚』は昭和10年7月12日、サイレン社(神田区一ツ橋二丁目九番地 教育会館内)発行。発行者は鹽谷晴如。237頁、定価1円40銭。女性画家7人による絵が収められている。ブブノワ「山」、有馬さとえ「花」、甲斐仁代「猫」、長谷川春子「娘」、橋本はな子「鯨」、佐伯米子「街」、遠山陽子「女」である。内容は雑誌、新聞に掲載した短文を収録した、いわゆる随筆集である。表題になった「草魚」は、時雨が薬研堀の装身具店で見かけた碧玉の魚から、於菟吉と一緒に旅した中国の河、そこに住む「サフヒー」という魚、最後は食用に愛知県でも養殖が始まった草魚へ続く。青い小魚を思い浮かべていたら、大魚の川魚と知った驚きを、中国旅行とからめて語った「東京朝日新聞」昭和10年6月26日の掲載作品である。時雨という名を使っているからには長谷川ヤスは雨が好きなのだろう。「落葉を拾つて」という作品は、こんな書き出しである。
ほどよく降る雨はとてもよいものである。雨を好んで名にする私は、いつの雨でも好きなのだが、秋からふゆにかかるころのしぐれが、その時、その折りの情景を織り込んで、サツと過ぎてゆくのを、夕立のつぎに好んだ。
銀杏の落葉を本にはさもうとして、活字を追うと「虚耗」のことが書いてあった。虚耗とは「人の物を盗み戯れとし、人の喜を耗すを楽しむ」小鬼で、玄宗皇帝の病夢に現れ、鍾馗に退治されてしまった存在である。時雨は、このいたずら者が好きだった。「人間よりもよつぽど正直で、おもしろい奴だから好きだった」。そこから時代時代に伝えられる、一見嘘のような話の中にある真実を語り始め、「嘘の嘘、虚耗とはくらべものにならない話」として、「若狭の白尼」、八百比丘尼を取り上げる。「八百比丘尼」とは一人の八百歳の尼のことではなく、沢山の尼がいることを表したものに過ぎないのだという合理的解釈に賛意を表している。
元の記は、若狭守護代年数旧記といふものに載せられてあるのであろうが、試に「言葉の泉」の八百比丘尼とあるのをひいてみると、
八百比丘尼、若狭の小濱に比丘尼が多いことをいふ語。
と明瞭である。もしその小濱に道徳的に出家したものが多かつたのか、または、ある種の職業名の比丘尼が多かつたのか、どちらか知らないが、比丘尼とよばれる売女が多かつたのだろうと思われなくもない。
「東京堂月報」昭和8年11月掲載である。
「草魚」巻末のサイレン社新刊・近刊広告を見ておこう。
新刊は三上於菟吉の二著。『随筆わが漂泊』(内容、出来栄えともに誇るに足る随想集)と『青空無限城』(面白くて、廉くて、而も一家中で楽しめる幕末もの)である。『随筆わが漂泊』は於菟吉の自装本で、生家にあった梅の木が描かれている。近刊には魯迅『支那小説史』、於菟吉『燃える処女林』、石坂洋次郎『金魚』、中山太郎『愛慾三千年史』、スタンダール『パルムの僧院』、中村亮平『世界美術要鑑』の6冊が告知されている。
サイレン社は新刊月報「サイレン」を出していた。「シレエネ」とは性格が異なるが、於菟吉のセイレーンに対する思い入れが「サイレン」に蘇ったとも思われる小冊子である。「サイレン」第4号は、昭和10年9月5日印刷、9月10日発行。発行者は鹽谷晴如、印刷者君島潔(共に『草魚』の奥付と同じ)。ノンブルは打ってないが、内容は以下のようである。
時雨は美人伝について、幼いときから漠然と「女性はいつもいかなる位置に居たか」と思ってきたが、「ものを美しく見たがる性格」から「古来から美しい女人を記憶するように、なるべくうるはしい方面のみ物色」していた、と告白する。その内に、「心の目が開かれて」きて、「女性はどんな風にあつかはれて来た」ということに関心が移った、ともいう。時雨が『近代美人傳』を出版するまでに書きつづってきた女性の素描には、『日本美人傳』(明治44年11月刊)『臙脂傳』(明治45年6月)『明婦傳』(大正8年5月)『麗人傳』『美人傳』(「婦人画報」大正3年1月〜大正12年7月まで掲載)がある。
雑誌『サイレン』發刊御挨拶は、以下の通り。
謹啓
時下残暑の候貴下益々御清適大慶のことと存じ上げます。
陳者、豫てより時代の要求として、ヂャーナリスト中心の文化雑誌は計画され待望されながらも、遂に今日までその生誕を見ませんでしたが、此の度漸く機運熟し、九月創刊にて月刊雑誌「サイレン」を發刊することとなりました。同人としては新聞社及び雑誌社の同感の士の結合したものでありますが、将来は、一般ヂャーナリストの御援助を得て、この挙を益々意義あらしめたいと念じてをります。国家多端の秋、ヂャーナリストの使命愈々重きを痛感する際、幸ひ貴下の御賛助と御支持を賜ることは、獨り小社の喜びのみではないと信じます。御挨拶旁々爰に改めて御後援をお願ひいたす次第でございます。敬具
昭和十年八月 月刊雑誌「サイレン」編輯同人一同
これを読むと、目の前にある「サイレン」4号とは異なる性格の雑誌を発行する目的があったらしい。「編輯室便り」には「九十中旬一流ヂャーナリストを同人として月刊文化誌「サイレン」を創刊する。文化の前衛に活躍するニュース・センスが、本誌を通して如何に閃光を放つかは、全国読者の要望するところであらうと思ふ」とあるので、秋の創刊を目指していたらしい。
4号の近刊書目には、中村亮平『世界美術要鑑』、サント・ブウヴ著・石川湧訳『わが毒舌』、藤澤桓夫『大阪の話』、トオマス・マン著・土方定一訳『文学論』、安田徳太郎『研究評論集』、栗原昇訳著『ナチス国家論』、フランツ・ウアヘル著・大江壽一訳『ムサ・ダグの四十日』が掲げられている。
「サイレン」第7号は昭和11年1月19日発行、やはり新刊月報である。巻頭の於菟吉「新春を迎えて」は、サイレン社が生誕十ヶ月で、16種の既刊を持ち、期待以上の売れ行きで同業者の羨望を買っていると報告している。
「サイレン」第9号は昭和11年2月19日発行。今月の新刊として時雨『近代美人傳』、清水幾太郎『日本文化形態論』の2点、近刊予告には12点が上がっている。謹告として、地方の読者にサイレン社の本が行き渡らないと言う声に対し、3月から地方に販売網を広げると準備ををしていると言っている。編集室便りにも「色々新飛躍の計画があるが、追々に發表してゆく。着實に倦まず撓まず、所期に向かつて愛讀者の各位と共に進んで行きたい」とある。なにやら大変な様が予想されるが、この昭和11年7月、於菟吉は脳血栓で倒れ、以後右半身麻痺になる。讀賣新聞連載中の於菟吉「日蓮」(昭和10年6月18日〜昭和11年12月28日、353回)は時雨が書き継いだ(同時期、「時事新報」にも於菟吉は「江戸末代男」を連載していた。昭和11年6月12日〜12月24日、161回。こちらはどうしたのだろうか)。サイレン社の出版も昭和12年のものは見られない。
時雨は以後も輝ク会を結成、機関誌「輝ク」を発行するなど奔走するが、昭和16年8月、白血球顆粒細胞減少症にて死去、享年61歳。於菟吉は生家近くに疎開していたが、昭和19年2月、病の悪化のため永眠、享年53歳であった。於菟吉は盛期には菊池寛に次ぐ流行作家であり、大衆向けの作風でありながら、外国文学の造形深く、一目置かれる存在であった。両者ともに、自己の作家活動の他に、出版、社会活動に関心をもって、精力的に場を広げた。現在では一部で高く評価されているものの、一般には昔の活躍を思えば、忘れられつつある作家の部類に入ってしまっていると言ってよいだろう。於菟吉の「シレエネ」「サイレン社」にセイレーン=人魚の声を聞き、取り上げてみた。最後に、サイレン社の出版物にある「人魚」を見ておこう。
岡本綺堂『支那怪奇小説集』は昭和10年11月20日の発行である。定価2円。中国の六朝から清の時代の小説筆記の類から220種の怪奇談を収めている。小石川吉利支丹坂にある青蛙堂に9月の末に集まった風流の文人たち十人余りが順に語った怪奇談の速記録を綺堂が訂正を施し纏めたという、百物語のような体裁になっている。清の「子不語」からその名も「人魚」という話が取られている。「子不語」の著者の甥が四川の某村を通りかかった時に耳にした話である。一夜で妻の下半身が魚に変わってしまったという奇譚であった。顔や髪、肌の色は元の通りであったが、痒くて仕方がなかった下半身は乳から下に鱗が生じ、両足が自然に癒着し魚体になってしまったのだという。甥は供の者に実否を見届けさせたが、事実であった。甥は旅を急いでいたので、夫が妻をその後どう取り扱ったかは見届けていないという。宋の「稽神録」(よく本草書に人魚関連の記事を引かれている)からは「海神」「海人」が語られている。海が荒れているので船の荷を海神に捧げたが、まだ波風が治まらない。その内、絶世の美女と、「朱い髪を散らして、豕のような牙」をむき出した4人の従卒を乗せた船が寄ってきた。女は「いい髢」を要求し、従者たちには乾肉を所望した。要求が叶えられたので船は無事に目的地に到達した。以上が「海神」の内容である。「海人」は網に黒い、体中に毛が生えた人間がかかった。漁師が、これは海人という不吉の者だから殺してしまおうと言うのを、豊漁を約束すれば助けてやろうと指揮者が言って放した。翌日からは大漁になった、というものである。
他には、海中の大魚「鰌魚」の鱗や背鰭が紅い旗のように見えるという「夷堅志」(宋)からの「海中の紅旗」。やはり「子不語」から水死した人間が水鬼となって、自分の身代わりを水中に引くという「水鬼の箒」、年を経た黒魚の精が人間を食って、その人になりすますという「帰安の魚怪」、海に住む全身毛に覆われて猿のようで、頭の天辺だけが禿げている小さな人間についての「海和尚、山和尚」などがある。
サイレン社昭和11年11月14日発行の、松村武雄『神話傳説の支那』(定価1円50銭)も水界の説話を扱っている。綺堂が「夷堅志」から引いた「海中の紅旗」も「海の怪魚」として語られている。「紅い旗のように見えたのは、其奴の鱗や鬣でさ」と舟人が言っているところなど、紅い鬣=リュウグウノツカイ=人魚と論を進める魚類学者が注目してもおかしくない部分である。松村はまた、河伯の使者は「朱の鬣をした白馬に乗り、白衣元冠、十二の童子を従えて水の上を走る」、と「神異経」の説を伝えている。これなどもリュウグウノツカイ論者が利用してもよい。河伯(河の神)は「酉陽雑俎」によると、人面にして魚身という信仰があるという。猿形の水神は「無支祈(むしき)」というらしい。「鼻が縮まつて、額が高くて、体は青い色をして、首が白くて、目が金色で、牙は雪のやうに白くて、頚を伸ばすこと百尺、その力は、九匹の象に勝ってゐた。そして身が軽くて、忽ち奔り忽ち飛び、現れたかと思ふと、忽然として見えなくなる」という。江水の女神が魚簗にかかり、漁師に陵辱されたので、その仕返しをしたことは「洽聞記」に書いてある。このような「河海の神に関する説話」が15節に分かれて紹介されている。また別章には「田螺乙女物語」も語られている。
なお、三上於菟吉の出版事業については、小田光雄が「古本屋散策7 三上於菟吉の出版事業」(「日本古書通信」第67巻第10号、2002.10.15、p.24)で触れている。小田は於菟吉の翻訳に注目し、特にゾラ作品の英語からの紹介を重視している。於菟吉が大正11年に紹介したゾラ『貴女の楽園』は長い間全訳がなかったが、2002年10月に『ボヌール・デ・ダム百貨店』(伊藤桂子訳)として翻訳がなることを伝えている。
「シレエネ」についても「日本古書通信」に関連記事がある。1962年3月15日号、pp.4〜6、長尾桃郎「宇野浩二氏と発禁誌『しれえね』創刊号」である。宇野浩二は前年の11月に亡くなっている。その『宇野浩二全集』第1巻(普及版、中央公論社、昭和47年4月20日)の月報1は「シレエネ」の発行人であった青木大乗(精一郎)の「『しれえね』前後」で構成されている。宇野の表紙絵、青木の裏絵がともに掲げられている。青木と供に挿絵を描いた渡瀬淳子が宇野の小説『恋愛合戦』のモデルで、後に沢田正二郎(1892〜1929、新国劇創立者。三上、宇野と早稲田の同期)の妻になった女性であること、裏絵には青木が当時長髪であった宇野の顔をスケッチしたものを載せたことを伝えている。さらに、青木は、「『しれえね』第一号は不備な点はあったがかなり立派な雑誌で、意外な反響があって、いろいろの批評や激励文が沢山舞い込んで、次号を大いに期待されたのであった。」の述べ、突然の裁判所からの出頭命令が自分に来たことと、その後の経過を記している。雑誌については、「『しれえね』はこの世に只一度だけ顔を見せたきりで、昇天してしまったのか、海の底に沈んでしまったのか、その姿は見えなくなった」と結んでいる。宇野や青木の「シレエネ」は消えてしまったが、三上のサイレンは23年後に出版社名として復活した。その年は三上の全集が平凡社から発行され始めた年でもあった。だが、セイレーンはやはり不吉の物だったのか、順調と思われた出版事業も於菟吉の病に潰えてしまった。セイレーンの歌は死を招いたのだろうか、於菟吉はオデュッセウスやオルフェウスにはなれない通俗作家でしかなかったのだろうか。時代は三上於菟吉を忘れようとしている。
by宇多垣こゑる(aka. MORO-G)
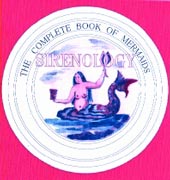
手元に内田恵太郎(1896〜1982)の人魚に関するテキストが4つある。
(4)は(2)(3)をうけて構成を変えてまとめたものである。順に見て行きたいが、その前に内田恵太郎の経歴に触れておこう。
内田恵太郎は明治29(1896)年12月27日、東京神田小川町駿河台下に生まれた。6歳の時に母と死別。小学校2年の時に病弱のため神奈川県岬町尋常小学校城ヶ島分校に転校。大正11年東京帝国大学農学部水産学科卒業、大学院に進む。昭和2(1927)年朝鮮総督府水産試験場技師(養殖部主任)となる。昭和17(1942)年九州帝国大学教授となり、新制となった後も昭和35(1960)年まで勤め、その間昭和22(1947)年に朝鮮魚類誌で農学博士号
を得る。専門は魚類の生態生活史、水産増殖学。著書に上記の『さかな』『私の魚博物誌』の他、岩波新書『稚魚を求めて』(1964)、『さかな異名抄』(朝日新聞社、1966。後朝日文庫、1987)、『流れ藻』(西日本新聞社、1972、1983)などがある。昭和58(1982)年3月3日没。没後の1983年『流れ藻』は歌文集。そのあとがきで妻は内田が本当は国文科へ行きたかったと言っていたことを伝えている。人魚について思いをめぐらす素地はあったのかもしれない。また、生前はRKBラジオで「十分間の生物学」という番組を持っていたように、科学啓蒙にも力を尽くした。
まずは『さかな』所収のテキストである。「人魚」は「民俗文芸と魚」の項に収められている。「人魚はむろん想像上の動物だが、世界じゅう至るところにその説話がある。それらを比較してみると、形や性質など、各地同じではない」とし、「近年、人魚の起源は熱帯太平洋に棲む一種の海獣ジュゴンであるという説が広まっているが、これは西洋流の考え、あるいは現地住民の俗信がそのまま輸入されたものと思われる。日本古来の人魚は決してジュゴンに似ていない」と、日本の人魚=ジュゴン説に反論しようとしている。「日本古来の人魚」の実見例として内田が挙げる文献は、「古今著聞集」「諸国里人談」「甲子夜話」「武道伝来記」「六物新志」の5点である。「武道伝来記」は西鶴の創作であるがその文頭に引く「宝治元年」に大浦に流れ着いた人魚記録は他書にも見られるので取り上げたのであろう。内田の論を踏襲した西村三郎は「宝治元年」の記録を「吾妻鏡」に置き換えて、他のものはすべて「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」で利用していることは前稿で述べた。内田が使用した資料が何であるかは明記がないのでわからないが、利用できうるものとしては、『廣文庫』第15冊(1916年)、日野巌『動物妖怪譚』(1926)、金井紫雲『東洋花鳥圖攷』(1943)などが考えられる。『廣文庫』には「古今著聞集」「諸国里人談」「甲子夜話」「六物新志」の4文献が「にんぎよ」項で見ることができる。ただし、内田が引く「六物新志」の該当部分は掲載されていない。日野は『廣文庫』を利用していると思われるので、当然4文献は引用済み(「六物新志」は『廣文庫』通りなので、内田が引く部分はない)である。さらに「武道伝来記」も日野は取り上げているが、内田の利用部分とは異なる。金井紫雲は「武道伝来記」「古今著聞集」「六物新志」(内田利用部分を含む)「甲子夜話」「諸国里人談」(但し、金井は菊岡沾凉の書を「諸國異人説」と伝えている)と、内田の引用した部分全てを網羅している。
さらに内田は「本草綱目」の「蜃」に注目して「その特徴が日本の人魚に似ていて、多分同じものであろうと思われる」と言っている。それでは、内田が文献から摘出した日本の人魚の共通点とはどのようなものであろうか。
頭部に鶏冠のような長い赤髪があり、顔は白く、体は魚の形で長い。顔は遠くから眺めると美しい女のようだが、捕らえてはっきり見ている記事には、サルに似ているとある。肌が白くて、すこしぽつぽつがあったというところまで観察してある。
これらの特徴を備えている水棲生物として内田が思い浮かべるのがリュウグウノツカイという魚である。鶏冠のような赤髪は背鰭の条、白い顔とは体色、リュウグウノツカイの顔を内田は「普通の魚と違って口がとがらず、人の顔のような感じがないでもない」と表現している。また無鱗の皮膚については「小さな疣のようなぽつぽつがある」と述べている。実際の魚の游泳状態については「ときどき海面に身をうねらせて游いでいることがあり、頭上の赤い鰭条を鶏冠のように立てる」と伝えている。第63図として「水上に顔を出したリュウグウノツカイ」の挿絵がp.200にある。日本の人魚の出現文献の多くが日本海沿岸にあることと、この時点でのリュウグウノツカイの捕獲・漂着例も日本海側に集中していることも考慮すると、結論として「私は、この魚が古来伝えられている日本の人魚の正体だと考えているのである」と提示する。
最後に朝鮮のサンカルチーに言及する。内田は昭和2年に東京帝国大学農学部講師から朝鮮総督府水産試験場技師へ転出し、昭和17年に九州帝国大学教授になった後も兼務していた。技師時代には朝鮮各地を調査し、博士号も「朝鮮魚類誌」によって受けている。朝鮮の魚類の第一人者といって良いだろう。朝鮮の言い伝えではサンカルチーは空を飛んでいるが、水を飲もうと海岸に降りてきたときに捕らえられる。その肉はハンセン病の妙薬として高価であるという。内田がサンカルチーとする魚はリュウグウノツカイとサケガシラである。ともにアカマンボウ目の魚である。内田はサケガシラを食べてみたと言う。ゼラチン質が多く不味かったと伝えている。サンカルチーについて言及できるのは内田の強みである。中国、朝鮮、日本。東アジアの人魚伝説で、今一つ弱い部分は朝鮮の伝承であろう。サンカルチーは一つの足がかりである。
なお内田はこの「人魚」論の初めでいわゆる「人魚のミイラ」にも触れて、「両方(上半身の獣類部分と下半身の魚類部分のこと−引用者)とも種類はいろいろあって、適当の大きさのものを何でも用いたようだが、ただ人の見なれた獣類は使っていない」と実見の感想を述べている。第62図は「見世物の人魚のミイラ」である。
中国の蜃、朝鮮のサンカルチー、日本の近世までの人魚記録を使って、日本の人魚の正体は、ジュゴンではなく、魚類のリュウグウノツカイであると結論を下す内田の人魚論は以後の論考でも一貫した姿勢である。また、人魚とリュウグウノツカイを結びつけたのは、おそらく内田恵太郎が初めてではなかったかと思われる。赤い鬣、白い顔、これに直接結びつくのは六物新志、甲子夜話(甲子夜話の著者は六物新志を読んでいるので、その影響下にあると考えると、六物新志一作とも言えるであろう)の人魚記述である。それ以前の文献は実見記録と言い切れない伝承部分を含んでいる。ジュゴン説がなじみにくいように、リュウグウノツカイ説も、そうかもしれないし、違うかもしれない。見方、思いこみの強さによって、人それぞれであろう。『さかな』は昭和31年の単行本であるが、内田の人魚論考が最初他の媒体で発表されていたかについては分からない。朝鮮時代から内田はリュウグウノツカイやサケガシラに興味を持ち、萩の田中市郎が昭和16年にリュウグウノツカイの完全標本を得たときには内田は写真、測定値を手に入れようと田中に要請している。人魚について内田が再度筆を執るのは昭和35年のことである。
中央公論社発行の雑誌「自然」に掲載された「人魚考」は世界の人魚伝説に充分目配りし、最後に「日本の人魚」としてリュウグウノツカイ説を展開している。挿絵、写真も12葉を添えてあり、力が入っている。全体の構成は、
の四部となっている。
書き出しは難しい。「人魚の起源」と大上段の章名があるが、「未知と未理解」から「想像」によって「実在しない奇妙な怪物を考え出し、それを実在するものと信じた結果いろいろな説話を伝えた」ことにより「世界各地の神話説話」に人魚は現れている、という説明である。その上で「人魚の形態や性質は各地決して同じではなく、それぞれの地方で異なる実在の動物のモデルがあるようである」としている。「想像」はモデルがなくとも働くのかもしれないが、心理や哲学ではなく、魚類学者としては実際の生物、世界中に人魚伝説があるのなら、分布を考え、多種の生物にモデルを求めることになるだろう。もちろん魚類だけでなく、水棲脊椎動物が候補となりうる。ここにおいて、軟体動物のイカやタコの類は省かれたことになる。次には、どのような説話があり、それに相応しい動物は何かという展開になる。
人魚を表す言葉はヨーロッパ諸国語がよく知られている。ただし、言語学者ではないので正確な発音を表記することは無理である。内田が取り上げたのは、北西ヨーロッパのイギリス・スコットランド、アイルランド、ウェールズ、デンマーク、アイスランド、ドイツの言語である。カタカナで発音を表し、アルファベット文字も添えてある。同じ諸国の言語を引く日野巌がカタカナだけなので、内田は外国語の人魚文献によったものと思われる。内田はロシアの水の精にも及ぶ。「ヴォディアニー」(Vodyany)と「ルサルカ」(Rusalka)である。普通ルサルカはともかく、普通は「ヴォディアニー」とは言わない。ヴォジャノイと単数で表す。説話の例としてはアザラシ人間とも言えるセルキーを取り上げている(セルキーという言葉は使用していないが)。それは、人魚=半人半魚となる歴史を想定し、「最初は半人半魚でなく、ある能力を持った水棲の動物がある時、例えば月夜などに陸地へ来て人間の姿に変わってある時間を過し、また動物の形に返って水の世界に帰ってゆくというのである」と、第一段階の例として取り上げたのである。次いで「水に住むある動物と人間とが時間的に変換すると考えられたのが、のちに両者の特徴を同時に一身に兼ね具えた半人半魚の体になったのであろう」と想像している。人魚が陸上では人間と変わらない姿になるとする話は、「両者変換の原型の残りではあるまいか」とも言っている。人魚の進化はともかくも、北欧の人魚は海獣、特にアザラシの影響を受けていると内田は指摘する。
北欧の次は南欧、地中海沿岸地域である。そこではギリシア神話のセイレーンに起源を持つシレーヌ、シレーナという言葉で人魚を表している。もちろんセイレーンは半女半鳥の怪物である。「それがいつのまにか下半身魚の人魚になってしまったのである。いつの時代にどうして鳥が魚になったか私は知らない。その道の専門の人にききたいと思っているが、まだ果たさない」。この文章は、19年後の昭和54年刊の『私の魚博物誌』に「人魚考」が収められるときにもまだ残っている。内田には自分なりの説明があったのである。古代ギリシアの人魚に関連する神格トリトン、ネーレイスを取り上げつつ、地中海ではイルカが人魚と結びつきやすかったと語り、「サイレンの鳥の下半身が魚に変わったのは、このネレイスと混同されたのであろう」と言っているのである。さらに、内田は面白い仮説を開陳する。「サイレンあるいはネレイスが美しい声で歌うということは、私は魚のなき声から来ているのではないかと思う」。その魚とはニベ科の「メイグル」maigreという、1〜2mになる大型食用魚のことである。ニベ科の魚はウキブクロを鳴らすことで知られているが、その音が船乗りに聞こえセイレーン伝説になった、とまで言っている。魚類学者は神話を魚類で解釈することに巧みである。このセイレーン=ニベ説はヨーロッパでも言われていることなのだろうか。それとも内田のオリジナルなのであろうか。
「各国の人魚」の後半はアジア、北米を廻る。バビロニアのエア、インドのガンガ、北米原住民がアジアからアメリカへ移住したときに導いた神格に触れ、インド洋太平洋の熱帯地域ではジュゴンが語られる。内田はこの地域に関しては人魚のモデルがジュゴンであるという説は否定していない。沖縄のザン、パラオの「マスキウ」。これらの言葉はジュゴンであるとともに人魚を意味する。ただし、それを全世界的に広げることには反対し、地域ごとにモデルがあるいう立場である。日本に一番近い中国については二つのタイプに分けて説明する。一つは山海経でいう人魚、「ナマズに似て四つ足で、人間の赤子のような声で啼」き、脂で灯をともす。オオサンショウウオである。「本草綱目」が引くより人間に近い「女性の形をして、肘のうしろに赤いたてがみのようなものがある」人魚。また、「泣くとその涙が落ちて珠」となる鮫人。鮫人に関しても魚類学者らしい説明がある。「サメ類(エイ類を含めて)にはざらざらした堅い鱗があり、鱗のやや大きな種類では鱗のある皮を磨くと、鱗が白い珠をちりばめたようになる。これを装飾に使う。サメザヤ・サメヅカなどはこれである。鮫人の涙が落ちて珠になるとはこのことからきたのであろう」。
中国の人魚を語るこの部分ではまだ蜃については触れず、見世物の乾燥人魚に筆は及ぶ。内田が見た感じでは下半身は「コイ・ニベ類・オオウナギ」と思われるものであった。数回見たが、みな種類が違っていたいたと言う。広東周辺には偽物を作って売る者がいるらしいと伝え、「日本の見世物の人魚は、日本で作られたものではなく、海外から持ってきたものに違いない」と以前も述べた主張を繰り返す。
最後が「日本の人魚」である。内田は「古代の神話に人魚らしいものがないのはかえって不思議である」と言いつつ、トヨタマヒメや推古天皇27年の異物に言及し、「そのころには人魚という名が日本にはまだなかったのだ」とする。実見談としては、やはり「古今著聞集」「諸国里人談」「甲子夜話」「六物新志」を引く。西鶴の「武道伝来記」は省かれている。内田は「諸国里人談」に載る「人魚」を「寛永(17世紀前半)」と先の『さかな』所収の論考でも書いているが、著者菊岡沾涼は「宝永年中」の事としている。宝永を正字で書けば寶永なので「寛永」と誤ったのかもしれない。内田の論を受けた西村三郎「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」でも「諸国里人談」による記録は「17世紀前半(寛永年間)」となっている。宝永年間は1704〜1711年、寛永年間は1624〜1644年なので60年以上の開きが生じた。内田は中国の人魚を述べる文中で「このほかシナの古書には人魚の記事がいろいろあるが、私はまだ十分に比較して調べていない。動物妖怪譚(日野巌.1926)にはシナ・日本その他の国の人魚に関する記事が多く引用してあるので参考されたい」と日野『動物妖怪譚』を参照したことを伝えている。蜃についても『動物妖怪譚』は述べているので、内田が重要視するリュウグウノツカイ→蜃→日本の人魚という流れも日野の著から発想したのではなかろうか。蛤型の蜃とは別の蛟の一種の蜃は「体はヘビのように長くて大きく、頭に赤いタテガミがあって、腹の下には逆の鱗があり、脂肪はロウに交ぜてロウソウを作る」という生き物である。この論考中には朝鮮のサンカルチーには触れていないが、内田はリュウグウノツカイの形状、生態を説明し
このリュウグウノツカイの特徴が、本草綱目の蜃、日本沿岸で実見された人魚によく合うので、わたしはこれが日本の人魚の正体であろうと考えているのである。とにかく日本の人魚はジュゴンではない。
と結論を下す。言葉尻を捉えるようであるが、沖縄も日本である。この論考が発表された時点ではアメリカから返還されてはいなかったが、日本であることには変わりはない。内田も沖縄のザンに触れていた。日本の人魚は日本海周辺においてはリュウグウノツカイ、沖縄周辺ではジュゴンと言ってもよかったのであろうが、人魚=ジュゴン説に対する反証としてリュウグウノツカイ説を立ち上げるためには、あえて無視したものと思われる。
ただし、沖縄の人魚はジュゴンとは別物であると信じている人もいた。喜舎場川石(永ジュン{王+旬}、1895〜1972)「琉球八重山島に於ける人魚の話」(「旅と伝説」第2年第5号、昭和4年5月、pp.37〜41)には、「儒艮は鯨類に近い動物であつて人魚とは全く異なるものである」とある。それでは、八重山の人魚とはどのようなものかと言うと「想像上の動物ではなく現住せるどうぶつであって、よく預言者のやうに又は神憑でもした人のやうに人の知らない古い事までも話して聞く人をして一種の霊感を起こさしめまして、海人の子と思われて居ります。俗に「人魚の魚」(ニンギヤウヌイズ)といつてゐます」という存在である。喜舎場は8年前に「黒髪を垂れた上体は女のようで下体は魚類のような」人魚が岩に座っているのを見ていた漁師のことを伝えている。また、明和8(1771)年3月の大津波を予言した人魚の事にも触れている。普通知られているところでは、捕らえた人魚を助けたので大災害から一村が助かったという話であるが、喜舎場の話は異なっている。白保村では3軒を村から追放した。この3軒の者は野原という村から離れた淋しいところに住まねばならなくなった。ある時3軒の者が漁をしていて人魚を捕らえた。人々は喜んで、半分は塩漬け、半分は鍋で煮た。それぞれの半身が語り出した事は、津波が来て人が死ぬという内容であった。人々は人魚の身を海に返し、3月10日を迎えた。津波は彼等を追放した白保村を滅ぼし、野原の人々だけが助かった、と言う。その他喜舎場は、釣りの邪魔をする不思議な動物を釣り上げると、近隣の人々は皆人魚であることを認め、人魚は釣り上げた男の先祖の家譜を淀みなく話し海に帰っていったという話を50年前の石垣島大川村で起こったこととして伝えている。結論部分では、
要するに八重山に於ける人魚は如上のやうに預言をしたり悪戯をした者は天罰を蒙るなどゝ神化された想像上の動物ではなくて現住する不可思議な動物視されて居るのであります。
と言っている。人魚は儒艮(ザン)ではなく、物言う動物だとしている。
「人魚考」に戻るが、最後に内田は世界各地の人魚の正体と思われる動物の一覧表を掲げている。「人魚」を水棲脊椎動物として理解すると以下のようになる。
| 軟骨魚類 | サメ | 中国 | 海産 |
| 硬骨魚類 | リュウグウノツカイ | 日本 | 海産 |
| 各種の大魚 | − | 海産・淡水産 | |
| 両生類 | オオサンショウウオ | 中国 | 淡水産 |
| 爬虫類 | ヘビ | インド・その他 | 淡水産 |
| ウミガメ | 日本・中国 | 海産(海坊主) | |
| 哺乳類 | ジュゴン | 熱帯インド洋・太平洋 | 海産 |
| マナティ | 熱帯大西洋 | 海産・淡水産 | |
| イルカ | 地中海 | 海産 | |
| アザラシ他 | 大西洋・太平洋の北部 | 海産 |
『さかな』発刊時から「人魚考」発表までの間に森為三によるリュウグウノツカイの測定値の報告があり、「人魚考」から「続人魚考」の間には西村三郎の測定値報告、游泳方法の仮説発表があった。
「続人魚考」には本論前に次のような文章がある。
幼い日の思い出につながるメルヘンをはじめ、神話伝説のたぐいから、文芸美術作品の中に現われる“人魚”のイメージは、世界各地で各様の姿をとる。今回は日本人の記録に残る人魚の実像にさぐりを入れよう。
内田の文なのか、編集者が入れたものなのかは分からない。本論は6つの部分に分かれる。
図は10葉添えられている。
「リュウグウノツカイという魚」の部分では、いわゆる「紐体類」のリュウグウノツカイ科、フリソデウオ科、アカナマダ科について述べられている。1931年に朝鮮巨斉島の大敷網で捕獲された2.75mのリュウグウノツカイ、1941年の釜山で捕獲された1.28mのサケガシラ、山口県萩沖の1.38mのテングノタチの写真が掲げられている。リュウグウノツカイ、サケガシラが朝鮮産であるところが内田らしい。テングノタチはアカナマダ科テングノタチ属Eumethichthysの魚で内田の説明によると、「テングノタチははなはだ奇妙な魚である。体がタチウオのように長く、頭の前頭部が天狗の鼻のように長く突出しているので、京都大学の松原喜代松教授がこの和名を与えたのである。これはきわめて珍しい魚で、最初南アフリカ沿岸でとれてE.fiski(Gunther)と命名されたが、日本近海でその後わずか数回、高知沖、山口県萩沖などでとれているばかりである。説話の種にでもなりそうな魚だが、あまり稀にしかとれないので漁業者も知らず、話の種にもならないらしい」とある。
次いでリュウグウノツカイに関する世界の伝説を紹介している。
北ヨーロッパではリュウグウノツカイはニシンの群れを率いている王と思われ、殺傷すればニシンが不漁になるとされた。同様に北米ではフリソデウオ科の魚がサケの王と信じられていた。サケガシラの名もその伝承に由来する。フリソデウオ科は北欧では「海の乙女」を意味する名が与えられている。
リュウグウノツカイに関連する伝説で最も有名なものは巨大海蛇伝承であろう。その姿は鬣のある首をもたげ、白く光った体をうねらせるというものである。内田は「魚類学者がこの話をきけば、まず思い浮かべるのはリュウグウノツカイである」と言い、1808年にオークニー諸島に打ち上げられた56フィート(17m)あった海蛇はリュウグウノツカイだろうと伝えている。
中国の蜃については前の「人魚考」でも触れていたが、より詳しい報告をしている。「本草綱目」「剪燈新話」「伽婢子」「和漢三才図会」「大和本草」を引き、蜃気楼を吐く、蛤ではないミズチの類の蜃をリュウグウノツカイではないかとしている。平凡社東洋文庫版「和漢三才図会」(第7巻、1987.7.10、pp.11〜12、「蜃」)には次のように記述されている。
『本草綱目』に、「蜃は蛟の属である。状は蛇ににているが大きく、角があって竜の状のようである。鬣は紅色で腰以下の鱗はことごとく逆になっている。燕子を食べ、よく気を吐いて、楼台城郭の状を画き出す。雨が降りそうな天気のときにそれがあらわれ出る。これを蜃楼という。また海市ともいう。蜃の脂は蝋にまぜて燭をつくる。香はおよそ百歩四方に漂う。この炯の中にも楼閣の形がみえる」とある。
その他、蛇と雉が交わると蜃が生まれるとか、雉が大水に入ると蜃になるという話も「和漢三才図会」は伝えている。小野蘭山『本草綱目啓蒙』では「蜃 竜類ニシテ和産詳ナラズ」としている。
内田は蜃に角があるという記述がリュウグウノツカイの形態に合わないことに対しては、「この角は、蜃を竜の一族だとしたことから逆に観念的につけ加えられたものではあるまいか、角のない竜を蛟というのだという説もシナにはあるのである」と言っている。蛟は角がないとするのは説文による。
朝鮮のサンカルチーについても再説している。サンカルチーとは「サンは山、カルチーはタチウオで、山に住むタチウオに似た動物という意味である」と語意を説明している。「朝鮮に在住した日本人は、これをヤマダチと呼んでいた。有名なもので、しばしば話題になるので名だけはみなよく知っている」とも書いている。最初は内田もサンカルチーが何であるか見当がつかなかったが、話を聞く内にリュウグウノツカイではないかと思い当たり、実物だとして持って来られたものを見て推測が当たっていたことを確信した。但し、リュウグウノツカイだけでなくサケガシラもサンカルチーと称せられていて、ともに標本収集に役立てている。
日本の人魚について、食べると不老長寿になると信じられていることに対しては、「シナから伝わった俗信だろうと思うが、シナの方のことがはっきりしない」と明言を避けている。内田がサケガシラを朝鮮で食べたことについては『さかな』でも述べていたが、ここでも記して、「寿命がいつまでつづくかは今後の問題である」と人魚を食べたことにして興味をつないでいる。内田はこの論の20年後、85歳で亡くなったので、サケガシラの効能もそれなりにあったのかもしれない。
内田自身がリュウグウノツカイの伝承についてまとめているので引いておこう。
最後は魚類学者に戻り、「リュウグウノツカイの生物学」で締めくくる。そこでは前年に発表された西村三郎の研究「リュウグウノツカイの游泳方法をめぐって」に着目し、「私もだいたいにおいて賛成である」と言っている。「だいたい」とは、急に動くときは体をうねらせることがあると考えているからである。それは、朝鮮の漁師への質問で得られた情報、形態が似ている他種の魚類の泳法から推測して下した結論である。
立風書房版『私の魚博物誌』第5章である。「自然」掲載の「人魚考」「続人魚考」の文章をほぼそのまま踏襲している。「自然」では中国のことを「シナ」と記述していたが、ここでは中国に改めている。また、蜃については「続人魚考」に詳しかったので、その部分を旧「人魚考」の「日本の人魚」の部分に付け足し、日本の人魚=リュウグウノツカイという主張をより際だたせる構成としている。また、旧「人魚考」の最後にあった人魚と思われる動物一覧表を論の最後尾に持ってきている。「リュウグウノツカイの生物学」の部分もそのままで、新しい研究を取り込んではいない。見出しを列挙すると、「人魚の起源」「各国の人魚1(本来はローマ数字)」「各国の人魚2(本来はローマ数字)」「日本の人魚」「リュウグウノツカイという魚」「北欧・北米のリュウグウノツカイ説話」「中国の竜の蜃」「朝鮮のサンカルチー」「日本の俗信」「リュウグウノツカイの生物学」となって、一部前稿を改変している。また、「人魚考」「続人魚考」には冒頭のベックリン画「波の戯れ」など全部で22の図、写真(その他に、人魚のカットが1つある)が添えられていたが、立風書房版ではすべて省かれている。
内田恵太郎は朝鮮総督府水産試験場技師時代からリュウグウノツカイ、サケガシラなどいわゆる紐体類の調査研究をしていて、また、河童(『私の魚博物学』第四章は「河童の生物学」である)、人魚などの伝説にも興味を抱いていた。ラジオ番組など科学啓蒙にも努めていた内田は60歳前後から、「日本の人魚の正体はリュウグウノツカイである」という説を書籍、雑誌に発表するようになった。その根拠として、古書の人魚実見談に、「赤い髪、白い顔」などとあり、その特徴がリュウグウノツカイに合致するということを挙げている。また、日本の人魚伝承に影響を与えたと思われる中国の蜃、朝鮮のサンカルチーなど、どちらもリュウグウノツカイ的特徴を持った伝説の動物の存在も関連している。内田は世界各地の人魚伝承は、それぞれの地域ごとにモデルとなった動物が異なり、全てをジュゴンに結びつけることには反対した。昭和30年以降、リュウグウノツカイの科学的測定、研究が発表され始め、科学と文化誌の融合、ある意味で余裕の産物として内田の「日本の人魚=リュウグウノツカイ」説は世に出た。それはすぐに西村三郎に受け継がれ、魚類、水産学者に広まり、一部では既定の事実となった観がある。だが、内田の根拠は究極的には「六物新志」の記述のみにある。「六物新志」の時代には既に、博物学者間にはリュウグウノツカイは異魚として認識されており、その検証文にも「人魚」とは書かれていない。日本人がリュウグウノツカイを人魚だとしたことは明確な根拠をもつ説ではなく、そうかもしれないという仮説である。もちろん、ジュゴンが人魚のモデルだということにも大きな疑問は残っている。神話伝説には何らかの合理的背景があるはずだとは19世紀の発想であろう。ただし、そう考えた人々がいて、ある程度受け入れられたというのは歴史である。歴史は否定できない。人魚も思考の歴史である。あらゆる視点に触れぬ訳にはいかないのである。その一点への興味が、以後も続く。
by釜野啓(aka. MORO-Z)