東京人形倶楽部あかさたな漫筆

INDEX>27P
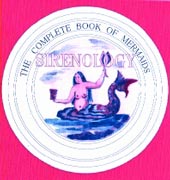
東京堂版『魚の事典』(1989.1.30)「リュウグウノツカイ」P.429には「魚体の大きさ、形、体色が非常に特徴的であるため、人魚伝説や地震と結びつけられたりして特に有名なのであろう」(沖山宗雄)とある。リュウグウノツカイの目撃が日本の人魚のモデルとなったとする仮説は、人魚=シュゴン説と同様今日においては暗黙の基本知識となっているようだ。吉岡郁夫『人魚の動物民俗誌』(新書館、1998.10.5)でも、「人魚のモデル」として、オオサンショウウオ、鰭脚類、ジュゴンなどとともに「リュウグウノツカイ」(pp.52~54)が取り上げられている。「魚類の研究者によって説かれている有力な説の一つは、リュウグウノツカイをモデルとするものである。この説は内田恵太郎と西村三郎によって唱えられている」。内田、西村ともに、リュウグウノツカイを実見し、論文あるいは啓蒙的文章を発表しているが、この二氏に同じく魚類学者の本間義治を加えれば、主な人魚=リュウグウノツカイ説の主張者は網羅できるであろう。今回は西村三郎(1930~2001)の主張を中心に見てみよう。だが、その前にリュウグウノツカイについて最近のトピックを拾ってみよう。
ネットが普及してからは、リュウグウノツカイの漂着、生体の目撃報告などがかなり頻繁に知ることことが出来るようになっている。南日本新聞は2005年5月19日夕に南大隅町の大浜漁港でリュウグウノツカイと思われる3m程の魚が立ち泳ぎをしている様を漁師たちが目撃したことを伝えている。
一転して江戸時代のリュウグウノツカイ他の珍獣異獣奇魚の記録を報告しているのは磯野直秀である(「珍獣異獣奇魚の古記録」、「慶應義塾大学日吉紀要 自然科学」第37号、2005、pp.33~59)。磯野によるとリュウグウノツカイは寛政12年(1800)、文政7(1824)年、天保2(1831)年に全5例の記録があるという。ほぼ19世紀になってからの報告である。それ以前が人魚認識時代と言ってよいのだろうか。ちなみに、磯野氏が公開講演を予定している国立国会図書館での特別展示「描かれた動物・植物-江戸時代の博物誌-」が10月中旬から行われ、「珍獣異獣奇魚」のコーナーでは『異魚図賛』のリュウグウノツカイとアカナマダが見られるらしい。
『写生物類品図』には6尾のリュウグウノツカイの図があるが、寛政12(1800)年夏に出雲の日御﨑灘での例では、先ず小野蘭山が鯊(サメ)の類、あるいはヤガラの類かと考証するが、栗本丹洲はヤガラ説には同意せず、自身の鯊魚類纂の巻中に入れるために堀田候より図を借りたと記している(文化14[1817]年)。丹洲は文化14年4月19日の医学館薬品会に模写したリュウグウノツカイの大図を出品し衆人に見せた。図に添えられた計測値は長さ1丈2尺余り(360cm余り)、同径5寸、背鰭の高さ1寸5分、上下の長い鬣状の鰭の長さは3尺余りで、骨は上は7本、下は2本で、骨の間は薄紙で貼ったようになっていると記録している。
また同じく寛政12年5月28日には肥前唐澤姉子ノ灘でもリュウグウノツカイは捕獲されている。長さは5尺2寸(157cm余)、幅2寸、厚さ3分程。丹洲は天保2年に萬香亭主人より図を借り、先の出雲の異魚と年月は同じ、産出地、寸法が異なっているとし、同一物かあるいは別々のものかは分からないが、後日の考証のために写しておくと書いてある。長い鰭は下顎は2本であるが、上部のものは根元では5本であるが先になると7,8本になっているようで、図が稚拙であるので分からないとも書いている。
三図目は天保2(1831)年正月18日、志摩郡西浦で漁師が水面に漂っているリュウグウノツカイを網で捕獲したもの。長さ3尺余、全身が白色銀で美しく、撫でると銀粉が手に附着すると記してある。西村三郎によるとリュウグウノツカイは「体全体がグアニン銀白でべったり覆われていて、銀白色に輝いている」。志摩郡の魚は尾が切れていた。そこで、鮫に食いちぎられたが、その傷跡は既に癒えたかとも、また漁師が言うように、尾が切断されたので漂着したのだろう、とも考察している。リュウグウノツカイの尾は欠損しやすく、日御﨑のものは尾が描かれてなく、姉子ノ灘のものは二本の線が描かれている。ここでも魚の名は誰も知らなかった。
四図目は二匹のリュウグウノツカイが描かれ、雌雄だとされている。雄魚とされているものは、長さ1丈4尺4寸(436cm余)、頭から1.8mの所で幅31.8cm、3.6mのところで幅21cm。腹の皮膚は「鮫肌アラアラトアリ」と、ざらついている様を記している。雌とされるものは、長さ1丈8尺4寸(557cm余)。この2尾も尾が欠損している。この2匹のリュウグウノツカイは栗本丹洲の『栗氏魚譜』にも描かれており、そこには天保2年7月6日土佐幡多郡小戈(才)濱に先ず雄が次いで雌が上がり、城下から40里の場所だったので3つに切り分け塩蔵で城下に送り、珍魚故に8月23日江戸に到着したと記されている。丹洲の絵では銀色の体色で、上部には白点、半分より下は鮫肌を表すために荒い白・黒点で表現されている。頭部の赤鰭は繋がって1本のように、下顎の赤鰭は2本描かれている。
最後の6体目は丹後の宮津、与佐(謝)浦で捕らえられたもの。長さ1間半許(2.7m)、慶応元(1865)年閏5月9日、高橋作之助が写し、さらに同月11日に靄山が写してコレクションに加えている。この魚も尾が欠けている。
19世紀初頭から半ばにかけてリュウグウノツカイの捕獲、漂着は、異魚・珍魚として博物学仲間に伝えられ、図が模写されもしたが、魚の名は明らかになっていなかった。荒俣宏は『世界大博物図鑑2魚類』(1989.5.30、平凡社)p.215「リュウグウノツカイ」の項で「《水族志》では、龍宮のタチガシラと名づけている」と、畔田翠山著『水族志』(1827年成立)で名が明らかになっていることを指摘している。明治17(1884)年9月28日に田中芳男によって出版された『水族志』p.115にはタチヲの仲間として「オキダチヲ」一名龍宮ノ守リ刀が記載されている。馬ダチヲ、ヒモダチヲともいう太刀魚の同類として述べられている。
形状帯魚ニ同ジ身ニ銀箔アルコト亦同ジ背腹鬣尾ニ連端通ジテ紅色頭短ク觜不尖眼頂ニヨリ馬頭ニ似タリ腹下の鬣圓ク長七八寸淡紅ニシテ透明紐ノ如シ
リュウグウノツカイの特徴に合致する記述である。
明治時代のリュウグウノツカイについては未調査で、報告することはできないが、大正になると、先に取り上げた谷津直秀『動物分類表』(大正3年10月28日)p.153に紐體類としてリュウグウノツカヒとフリソデウヲが記載されている。説明文はない。大正9年の増補改訂版になると、リュウグウノツカヒにkinng of the herring、フリソデウヲにking og the salmonの名が加わる。昭和13年の全訂改版ではフリソデウヲdealfishに(死骸が板の如き故)が加えられている。
大正15年4月20日発行の中村正雄著『新潟縣天産誌』p.401にはフリソデウオ科の一種が紹介されている。図はリュウグウノツカイにも似ているが、サケガシラなのであろうか。説明文には、
本種ハ大正八年二月鉢崎濱ニ打上ケヲレタル珍ラシキギョルイニシテ全長九尺五寸幅五寸乃至六寸體色銀白色ニシテ鱗ニ犬牙状ノ突起アリシト其全部ヲ見ルコトヲ得サリシハ遺憾ナリシ肉ハ食スルニ堪ヘサリシト云フ、田中茂穂氏(東京大學)曰ク本種ハTrachipterus sp.ナルベシ學界ノ珍種ナリト後日ノ考定ヲ待ツ
とある。
博文館『幼年世界』第7巻第7号(大正6年7月1日)pp.12~13には「不思議ナオサカナ」と題してリュウグウノツカイの絵が掲載されている。説明文には「コノオサカナハ「オーアヒツシユ」ト云ヒマス長サガ一丈二尺モアルサウデス」とある。体を波打たせて前進する頭部の長鰭が9本、下顎には2本の長鰭のあるリュウグウノツカイが描かれている。Oarfishと英語名で紹介されているので、一般にはリュウグウノツカイという名は普及していなかったと思われる。この幼年世界に紹介された図と同じ原図が時代が下った昭和9年2月25日「サンデー毎日」p.8にもある。記事は水魔列傳「迷信がそれをつくり 科學がそれの正體を發く」でサイレン、河童、海蛇、人魚、海坊主などの正体と思われる動物(サイレン=セイレーンには正体動物は明示されていない)を提示した啓蒙記事である。リュウグウノツカイ図のキャプションは「ひもうを-海蛇といはれた奇魚です-」とある。本文には「ひもうを(リボン・フイッシュ)には二、三十フィートの長さのものがるが、これはよく海蛇の噂を生む。殊に地中海からの海蛇はこれだ」と書かれている。ここでもリュウグウノツカイという和名は使われていない。
ついでにサンデー毎日の同記事中の人魚記述を見ておくことにしよう。筆者M. Y. S. S. は「人魚ほど人間の猟奇線に触れたものはなかろう」と言って、人魚の本質を「波の運動と、海洋の不思議と、そして「女の神秘」とを混ぜ合わせてつくりあげた」ものとしている。古代の神格としての人魚は太陽の出没を表象すると指摘する。「上身の人間は太陽が陸上で一日を送り、下身の魚体は一夜を波の下で暮すのに象つたのである」と自然学派の神話解釈を開陳している。ただ、日本の人魚は殆ど中国の伝説の焼き直しに過ぎないと断定している。さて、人魚のモデルとしては海女の誤認、サンショウウオも指摘するが、やはりマナティー、ジュゴンの海牛類を取り上げている。最後は人魚の見世物にも筆は及ぶ。
人魚の見世物はいつの世でも人気を博すものである。ドイツ人も海豹を人魚として見せたこともあった。徳川時代にわが国の香具師で子猿と鮭の半身を巧に継ぎ合せて人魚だと囃したてゝゐたのを、オランダ人が買ひ取り、欧州に持ち帰り一時学界を賑はした。かうした人魚の骨が、今なほモナコの水族館に飾られてゐる。
モナコの水族館と言えば、先に取り上げた谷津直秀が研究した機関である。
サンデー毎日は昭和9年であったが、その一年半ほど前、昭和7年8月の科学知識普及協会発行の雑誌「科學知識」の表紙には杉浦非水による「深海模様」と題して、リュウグウノツカイに近い種であるテンガイハタが描かれていた。
昭和初期にリュウグウノツカイに興味を持ち地方新聞、雑誌に紹介した人物に田中市郎(1877~1946)がいる。旧制萩中学の博物学教諭で私設の博物館を開設した。死後に纏められた著『珎魚之譽』(萩文化協會発行、昭和25年12月15日)の表紙は河村松溪の筆でリュウグウノツカイ、テンガイハタとリュウグウノヒメが描かれている。田中の自慢の業績を顕彰するものである。全62頁のこの著には田中の88編の文章が収められている。その11から13番目の文章で田中はリュウグウノツカイを扱っている。まず昭和8年9月に萩市場で田中はリュウグウノツカイを初めて見つけた。数日前に引き網にかかった個体である。長さ1m余り、尾は欠落している。写真に撮り、実物大に写生し、彩色を施し、ホルマリン漬けにした。その図を田中茂穂(1878~1974、理学博士、魚類学、東京帝国大学教授)は写し取り、標本の代わりにしたという。次いで昭和14年12月、大敷網で捕獲された個体は長さ75cm余、やはり尾は欠落していた。さらに昭和16年に捕獲された個体は待望の完全な標本となったもので、長さ136cm余り。内田恵太郎(当時は朝鮮総督府水産技師)が写真、測定記録を懇望したことを田中は述べている。内田は同種を朝鮮近海で入手したが、完全標本は得難い旨を伝えている。
田中はリュウグウノツカイの他に近縁のテンガイハタを昭和16年に、昭和13年7月にはサケガシラ、ユキフリソデウオを入手している。サケガシラの学名「トラキプテルスイシカワヱ」Trachipterus ishikawae Jordan et Snyder が石川千代松(1860~1935、東京帝国大学農学部教授)を記念する名であること、ユキフリソデウオの異名Trachipterus iijimaeが飯島魁(1861~1921、東京帝国大学教授)の記念名であることを田中は伝えている。田中市郎については荒俣宏の紹介記事があり、また2005年10月1日から群馬県立自然史博物館で始まった企画展「ニッポン・ヴンダーカマー 荒俣宏の驚異宝物館」でもコレクターとして紹介され、萩博物館(田中の私設博物館から発展)所蔵のリュウグウノツカイの剥製標本が展示されているという。
このような前史を持つリュウグウノツカイであるが、今回取り上げるのは西村三郎の論である。西村は1930年弘前生まれ、京都大学理学部卒業、水産庁日本海区水産研究所に勤務の後、京都大学教養部教授となる。理学博士。海洋生物、地球生物地理の研究から、近代西欧の探険博物学者の研究に進み、日本と西欧の博物学史を俯瞰する『文明のなかの博物学』上下(紀伊國屋書店、1999.8.31)をまとめる。死後出版された著に『毛皮と人間の歴史』(紀伊國屋書店、2003.2.17)がある。2001年11月30日死去。他の著書に、『原色検索日本海岸動物図鑑』1、2(保育社)、『日本海の成立』(築地書館)、『未知の生物を求めて』(平凡社)、『リンネとその使徒たち』(人文書院、後朝日新聞社)などがある。
西村のリュウグウノツカイ関連の文章で最も一般に読むことができるのは、山田慶兒編『物のイメージ・本草と博物学への招待』(朝日新聞社、1994.4.5)所収の「人魚とリュウグウノツカイ-伝説と動物学とのはざま」(pp.43~64)であろう。エピグラムは「人間の熱烈な想像力によって確立された詩的実存-人魚」という上野益三『日本博物学史』からの言葉である。その想像力は、自然界に実在する「<人魚>と思わせるような」生物から喚起されたとするのが西村の主張である。しかも、海牛類モデル説を退けて、内田恵太郎の説を受けて、リュウグウノツカイを有力な候補に上げている。西村は日本における海牛説の最初の紹介者として南方熊楠をあげ、それが明治43の「牟婁新報」掲載「人魚の話」としているが、これは不正確であろう。明治17(1884)年1月出版の『百科全書 上巻』(丸善商店発行)p.488には「メルメイドニ關シ、世上ニ流傳セル力數多ノ小説アリ、蓋其源因ハマナチデーノ一種ニ由ルナラン、如何トナレハ、此獣ハ、唯頭部ノミヲ水上ニ露ハシタル時ハ、其容貌眞ニ人類ノ顔色タルヲ想像セシムレハナり」とあるからである。「マナチデー」とはManatidae、つまりマナティーのことである。『百科全書』は例言によればチャンブルの「インフォルメーション、フォル、ゼ、ピープル」の翻訳である。
西村はまずリュウグウノツカイの生物学的特徴を説明し、次に「リュウグウノツカイ=人魚説をめぐって」として、内田がかつての日本の人魚記録の一部にはリュウグウノツカイの目撃例と推定できるものがあると主張する、人魚の特徴を4点に分けて列記している。
それらに合致するものとして、『六物新志』、『甲子夜話』の原文を提示する。
ちなみに『甲子夜話』の該当部分を平凡社東洋文庫本(『甲子夜話2』、1977.9.26、pp.12~13)から引用すると、次のようである。
人魚のこと、大槻玄沢が『六物新志』に詳なり。且附考の中、吾国所見を載す。予が所聞は、延享の始め伯父母二君〔本覚院、光照夫人〕平戸より江都に赴給ひ、船玄海を渡るとき天気晴朗なりければ、従行の者ども船櫨に上りて眺臨せしに、舳の方十余間の海中に者出たり。全く人体にして腹下は見へざれども、女容にして色青白く、髪は薄赤色にて長かりしとぞ。人々怪みて、かゝる洋中に蜑の出没すること有べからず杯云ふ中に、船を望み微笑して海に没す。尋で魚身現れ、又没して魚尾出たり。此時人始て人魚ならんと云へり。今『新志』に載る形状を照すに能合ふ。漢蛮共に東海に有と云へば、吾国内にては東西二方も見ること有る歟。(巻二十)
松浦静山は大槻玄沢『六物新志』を読んでいるので、それに合わせた文章になったのかもしれないが、延享年間(1744~1748)のリュウグウノツカイの記録として読もうとすれば、できなくもない。西村は「二例をリュウグウノツカイの目撃記録とするのはさほど無謀ではあるまい」と控えめに言っている。
人魚との関連部分は以上の二例が中心で、論文の後半は西村が1960年代前半に発表したリュウグウノツカイの生態、遊泳法を述べた業績の要約となっている。リュウグウノツカイが一般に考えられている程は稀なものでなく、生息域も真の深海ではなく暖流中深層(日本海では25~200m)で、蛇行泳法ではなく立ち泳ぎをしているという。この泳法を推測し、実地で確認されたことが西村のリュウグウノツカイ研究での最大の功績である。それを誇る余りか、最後には「古来日本近海に出没した人魚のなかに大型硬骨魚類リュウグウノツカイが含まれていることは、もはや疑問の余地がないといってよかろう」「人魚の正体を無批判に海牛類のジュゴンやマナティとする考えは、このさい改められねばならないことは確かである」と主張し、『長崎聞見録』の挿絵人魚を「尾びれに向かって細長く伸びた体、長い頭髪、細い腕など、リュウグウノツカイの特徴と一致する点が多い」と説明する。西村のこの論文を紹介した吉岡郁夫は西村が「自信満々」であるとまで言っている。リュウグウノツカイを知った目で見れば、人魚との関連を指摘したくなるが、18世紀までに捕獲、目撃された日本のリュウグウノツカイは本当に人魚として人々に認識されたかは、証明の難しい推測仮説に留まるとした方が無難であろう。筆者の興味はそのような仮説を提供してきた人々がいたという事実にあり、それの検証の任にはない。
それでは、遡って西村の1960年代の論考を見て行こう。
1960年2月24日の昼頃、佐渡海峡で底曳網漁を行っていた小型漁船が見慣れぬ魚を捕獲した。翌朝、新潟魚市場に水揚げされた巨大なタチウオのような魚は人々の興味を引いたが、商品となるかは分からないので入札する者がなく、一人の鮮魚商に百円とも三百円とも言われるが、当時としても非常な安価で引き取られた。新潟日報の記者が取材し、日本海区水産研究所の所員だった西村三郎に珍魚のことを伝えたので、西村は魚春に急行し、まだ完全には切断されていなかった個体を手に入れることが出来た。後の回想によれば、「さっそくタクシーを呼び、いやがる運転手を説き伏せて研究所に魚を持ち帰った」とある。西村は青森県弘前の出身。子供の頃、浅虫にあった東北大学臨海研究所の水族館でリュウグウノツカイの絵葉書を入手し、この珍魚に興味を抱き続けていたと言う。
この個体は長さ3225+Xmm。尾と尾鰭の部分が失われていたが、この時点で記録された日本海で捕獲されたリュウグウノツカイ(測定記録がないものも含めて20例近く)の計測値では最大のものであった。それ以前では1~2mの個体が記録されていたのである。西村はまず「採集と飼育」第22巻第8号(1960.8)pp.231~233に「深海魚リュウグウノツカイ-佐渡海峡で捕獲-」と題し短報を発表した。「深海魚」としたのは当時の常識に従ったものか、或いは学術誌ではないので厳密に用語を適用しようとする意識が働かなかったのか、編集サイドの提案でもあったものか、分からないが、のちの西村のリュウグウノツカイは「中層漂泳性フォーナ」であるという認識とはずれがある。4葉の写真とともに、測定値、記載が述べられ、日本海での捕獲事例の紹介、リュウグウノツカイが日本海の所生的な群集ではなく、むしろ多生的なものである可能性が高いことを指摘している。新潟県下での1960年の捕獲は西村の知見では「20数年ぶりのこと」で過去には数例しか確認できない。ただし、島根県水産試験場には1948年以降10頭近くの個体が持ち込まれているので、「少くとも日本海岸に関する限り、この魚種はひじょうに稀というほどのこともなさそうである」と文中で述べている。
西村は前号の「採集と飼育」にも「1959-60年の冬、新潟県の海岸に漂着した珍動物6題」pp.213~216を報告している。6題とは、ソデイカ、ヤリマンボウ、アザラシ、大イカ、サケガシラ、オサガメである。リュウグウノツカイと同じアカマンボウ目のサケガシラは6日前の1960年2月18日の朝、新潟市青山海岸に生きて漂着した。味は「水分多く、脂肪少く、マンボウの肉に似て不味だった」と伝えている。日本近海からは13例(新潟県では未記録)しか知られていないとここでは述べられているが、現在では報告は稀ではなく、普通の種になりつつある(東京堂出版『魚の事典』、「サケガシラ」の項では、沖山宗雄が「日本沿岸に分布する普通種」と記述している)。「採集と飼育」第22巻[1960年]前半には、他に「日本近海におけるオサガメ捕獲の記録」[3月]、「海水浴客を悩ましたウキヅノガイ」[3月]、「新潟県沿海に出現する外洋性大イカ:ソデイカ」[6月]と題した西村の報告があり、p.74には「日本海区水産研究所玄関前の西村氏」という白衣姿で坐っている当時30歳の西村の写真が掲載されている。
その後西村はその年の「日本海区水産研究所研究年報」(第6号、1960.12.28、pp.58~68)に計測記録、所見、体色、摂取食物などのより詳細な報告を英文で載せた(A Record of Regalecus russellii(SHAW) from the Sado Straits in the Japan Sea「佐渡海峡で捕獲されたリュウグウノツカイの1標本」)。佐渡の個体は未成熟な雌で、特徴的な背鰭は条数が6/322+X(一部欠損)であった。鮮紅色の鬣のように長い頭部の背鰭は基部では膜で繋がっているが6本の条が確認された。同じく長い腹鰭は一本の鰭状から形成されている(1-1)。尾末から1305mmの所での切断面写真も添えられている(この論文には5つの添付写真がある)。胃にはほとんど残留物は見られず、腸には暗赤色の粘液が観察されるだけで、餌となる生物の残留は認めることができなかった。
リュウグウノツカイの筋肉の観察が、西村にこの魚の定説となっていた泳法への疑問へと研究を進めさせることとなる。翌1961年12月30日発行「日本海洋学会誌」第17巻第4号pp.215~221に発表された論文「リュウグウノツカイの游泳方法をめぐって」がそれである。西村は最初英文で論文をまとめたが、和文に直し、かつ平易な記述にして「日本海洋学会誌」に発表したのである。
その中で西村は「リュウグウノツカイの海中での生活様式、とくに游泳方法については、さまざまな想像がめぐらされてきた」と指摘、実見観察されたことがないので「空想」と言った方がよいとまで総括する。リュウグウノツカイの游泳方法に関しては1911年にシュレジンガーが体を蛇行させながら前進するとの見解を発表し、多くの魚類学者の支持を得てきた。中にはデュボワ-レイモンのように、形態から蛇行游泳の不可能性を指摘し、背鰭を細かく動かすことで前進すると想像した者もいた。西村は「この魚は外部形態や骨骼系のみならず、筋肉系もいちじるしく変わっている」とし、「主として背びれをたえまなく波打たせることによって推進力をえているのではないか」と想像する。ただし、生体の目撃例から「体幹を左右に大きく蛇行させて泳ぐという運動が不可能ではない」ともしている。背鰭の前端の長い軟条と一対のこれまた長い腹鰭は、懸垂状態での体のバランスを取るのに適していると考えている。リュウグウノツカイはウキブクロを欠き、発達した脂肪組織も持たないため、「なんらかの方法を講じないかぎり、その体は海の中を沈降してとどまることがないであろう」とする。ただし、西村が想定するリュウグウノツカイの生息域である躍層下の水域では海水の比重が大きく、ウキブクロを欠いていても骨質化が悪く、無鱗、体側筋の発達も悪いので、予想以上に比重は低く、「静止状態にあって沈降するとしても、それは、おそらく、ごくゆるやかであろう」と推定している。ここでも長い鰭は摩擦抵抗を高めるのに役立っている。また、欠損しがちな尾鰭も斜上方に曲がっていて、沈降姿勢に適応したものと想像している。
「背びれの軟条を支える神経間棘はきわめてよく発達しており、かつ、独特の形態を備えてい」て、「前後の神経間棘の細長い柄部の間にできたひろい腔所には、すこぶるよく発達した背びれ軟条の挙筋と、それほど発達はよくないが、屈筋が収容されている」。しかも、その挙筋は長時間疲労することのない赤色筋からなっているのである。したがって、「たえまない背びれ挙筋の仕事をとおして、斜上方への推進力を得」、尾鰭は体が左右に振れるのを防ぐ役割をになっていると結論する。体を左右に蛇行させるのに必要な体側筋は白色筋で、波浪との格闘では容易に疲労してしまい、寄せ波に運ばれ海岸に漂着することとなる。以上の西村の仮説は、後に海中での生魚の観察で確かめられ、西村本人もうれしく思ったことであろう。
リュウグウノツカイについて次いで発表された論文は「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」(「横須賀市博物館研究紀要 自然科学」第7号、1962.3、pp.11~22)である。ここで初めてリュウグウノツカイと人魚との関連への言及が行われた。ヨーロッパでは大海蛇伝説のモデルの一つと考えられていることに寄せて、「最近では、日本伝来の“人魚”の正体はこの魚であろうという説さえおこなわれている(内田 1956 & 1960)」の一文がある。(内田 1956 & 1960)は論文末の文献目録における内田恵太郎の業績を指す。 1956年の文献は『さかな-日常生活と魚類-』(慶応通信、1956.2.10、pp.196~200「人魚」)で、1960年のものは「人魚考」(「自然」、第15巻第8号、1960.8、pp.42~47)である。内田恵太郎の人魚論考については次回触れる予定であるので、内容紹介は控えておく。西村がリュウグウノツカイの標本を得た年に内田はその「人魚考」を発表していた。その続考とも言える「続人魚考-リュウグウノツカイ-」(「自然」第17巻第9号、1962.9、pp.52~57)を発表したのが西村の「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」の半年後であった。このように内田と西村はそれぞれの論考を同じ年に発表しているのが分かる。西村も指摘しているように、日本の人魚の正体がリュウグウウノツカイであろうとする説は内田が唱え始めたものと考えてよいだろう。
西村「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」は6つの部分と文献から成っているが、一番興味を引く部分は「2.日本近海における捕獲記録」と「表1.日本近海におけるリュウグウノツカイ出現の記録」である。表には1247年から1960年までの31例が掲げられているが、1900年以降の23例はリュウグウノツカイであろうが、それ以前の古書の記述をリュウグウノツカイとしたことはどうであろうか。それこそが日本の人魚=リュウグウノツカイ説の核心なのだが、ややリュウグウノツカイ→人魚という目で見過ぎているようにも思えてしまう。一つ一つ見てみよう。
(1)1247年4月24日(西村による陰暦から現行暦への換算が施されている)
陸奥国津軽(漂着)、『吾妻鏡』による。
『吾妻鏡』宝治元年5月29日には「三浦五郎左衛門の尉左親衛の御方に参る。申して曰云く、去る十一日陸奥の国津軽の海辺に大魚流れ寄る。その形偏に死人の如し。先日由比の海水赤色の事、もしこの魚の死せるが故か。随つて同比、奥州の海浦の波濤赤くして紅の如しと。この事則ち古老に尋ねらるる處、先規不快の由これを申す。所謂文治五年夏この魚有り。同秋泰衡誅戮す。建仁三年夏また流れ来る。同秋左金吾御事有り。健保元年四月出現す。同五月義盛大軍。殆ど世の御大事たりと。」
(2)不明(5月頃)
常陸国東西ノ浜(漂着)、「古今著聞集」
(3)不明
伊勢国別保(網に入る)、「古今著聞集」
『古今著聞集』巻第二十魚虫禽獣「伊勢国別保の浦人、人魚を獲て、前刑部少輔忠盛に献上の事」による。以前にも紹介したので、該当部分の引用は省略。
(4)17世紀前半(寛永年間)
若狭国乙見村(目撃)、「諸国里人談」
人魚の文献として極めて有名。『日本随筆大成』第二期第24巻(吉川弘文館、1975.1.10)p.427に該当部分はある。
○人魚
若狭国大飯郡御浅嶽は魔所にて、山八分より上に登らず。御浅明神の使者は人魚なりといひつたへたり。宝永年中乙見村の猟師、漁に出けるに、岩のうへに臥たる体にして居るものを見れば、頭は人間にして襟に鶏冠のごとくひらひらと赤きものをまとひ、それより下は魚なり。何心なく持たる櫂を以打ければ則死せり。海へ投入て帰りけるに、それより大風起つて海鳴事一七日止ず。三十日ばかり過て大地震し、御浅嶽の麓より海辺まで地裂て、乙見村一郷堕入たり。是明神の祟といへり。
(5)1677年10月
肥前唐津海上、「遠碧軒記」、「嘉良喜随筆」
「遠碧軒記」は『日本随筆大成』第一期第10巻(吉川弘文館、1975.9.15)p.117、「嘉良喜随筆」は同第一期第21巻(1976.5.20)p.150。「嘉良喜随筆」は「遠碧軒記」の引用である。
延宝五年十月に、肥前の唐津の海上にて人魚をとれり、又両頭亀とれり。執権威を争へば両頭亀出ると古文にあり。又元亀二年霊陽院義昭公の、信長公にをしこめられしとき、両頭の亀出づ、先は不吉の例なり。
(6)18世紀中頃(宝暦年間)8-9月
陸奥湾(目撃)、「六物新志」
西村三郎「人魚とリュウグウノツカイ」p.53~54の読み下し文による該当部分は以下の通りである。
宝暦年中八月上旬、嘉(右衛門)小船ニ乗リテ魚ヲ野内ノ海ニ釣ル。舟ヲ操スル者一人従フ。時方ニ日グレ、将ニ船ヲ進メ徙ラントシテ嘉首ヲ回ラシテ望ムニ適々牝人魚ノ髪ヲ被リテ水面ニ現ズルヲ見ル。其ノ顔色瑩白、返照シ相映ジ皚皚トシテ光暉有リ。肌膚モ亦白ウシテ少シク甲錯ノ如キノ意有リ。髪赤クシテ黯色ヲ帯ブ。両乳両手倶ニ人ト異ナラズ。但腰ニ簑ノ如キ者ヲ帯ブルニ似タリ。而シテ以下ハ則チ見ヘザレバ得テ知ルベカラザル也。嘉怪訝之間急ギ従者ニ告グ。従者之ヲ見テ驚イテ銛ヲ水ニ墜ス。人魚モ亦駛キ懼レテ輙チ即チ没ス。而シテ復タ見ズ。
恒和出版、江戸科学古典叢書32『六物新志・稿/一角纂考・稿』(1980.10.6)pp.142~143も参照。
『六物新志』のこの部分は幕臣毛利梅園作「梅園魚譜」の「人魚」(所謂人魚ミイラの図の説明)でも引用されている。
(7)19世紀前半
玄界灘(目撃)、「甲子夜話」
先に引用済み。
(8)不明
丹後、出典古書不明(黒田長礼「駿河静浦附近産魚類目録追加」(第8)による)。
確かに『六物新志』の目撃記述などを読むとリュウグウノツカイかと思うが、江戸時代の博物書では1800年以降は異魚として、名は分からぬものの魚類の一種としていて、人魚とは認識していないので、それ以前の西村が指摘している例だけでは日本の人魚=リュウグウノツカイという構図は基盤が弱いように思われる。御浅明神の使者の人魚にしても
「岩のうへに臥たる体」に重きを置いて読めば海獣類とも考えられよう。もっとも、諸国里人談の記述が事実を伝えているという確証もない。すべてが虚構かもしれないのである。頭の鶏冠のような赤いひらひらしたものとの記述がリュウグウノツカイと想像させる根拠となっているのであろうが、「本草綱目啓蒙」などの本草書が引く「華夷考」の文「皮肉白如玉、無鱗有細毛、五色軽軟、長一二寸、髪如馬尾、長五六尺」などの影響、または前にも述べた西鶴「命とらるゝ人魚の海」の文「かしら、くれなひの鶏冠ありて」が反映しているとも考えられ、菊岡冶凉の文飾かもしれない。中世、古代にリュウグウノツカイが漂着したことはあったであろうが、それが人魚と認識されたと証明することはできない。リュウグウノツカイ→珍魚・異魚→人魚の構図は想像しやすいのであるが、「珍魚・異魚」を抜かして、左と右を直接にリュウグウノツカイ→人魚或いは人魚→リュウグウノツカイとするには資料が少なすぎる。可能性はあるかもしれないが、検証なしに、最近ではリュウグウノツカイ=人魚説が頻繁に語られるようである。その一端は西村三郎の業績にあると思われるが、西村が根拠とする文献は「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」で上げられた以上の8点に過ぎない。しかも、網羅的に取り上げただけで個々の検証はされていないのである。もちろん、生物としてのリュウグウノツカイの測定、游泳法の推定などは立派な業績であるが、文化史的な部分、つまり人魚については記述が不充分で、内田の説を受け入れ、後にそれを広めるのに努めたという位置づけが妥当だろう。
リュウグウノツカイは一部の魚類学者の強い興味を引き、科学者の部分ではなく、想像力の領域で人魚と結びつき、今日ではジュゴン=人魚説に拮抗する日本の人魚=リュウグウノツカイという仮説を根付かせるに至った。早急な結論になってしまったが、そう思えてしかたがない。そもそも、想像の生物に、何らかのモデルがある、という考え方に違和感を持っているので、逆の意味で偏見をもって読んでいるのかもしれない。本来は、論の由来を語るのが、この場の意味であり、人魚にまつわるすべてが興味の対象なのであるが、あまりにリュウグウノツカイ=人魚説が無批判に語られるので、筆が滑った。次回は、この説の提唱者であるとおもわれる内田恵太郎の論を見て行くことにしよう。
とは言ったものの、リュウグウノツカイを既知のものとして今まで述べてきたが、そんな魚知らない、という方もいたかもしれないので西村の記述を中心に一般的な説明を付け加えておこう。「捕獲状況から考察したリュウグウノツカイの生態」の「はしがき」に分類学的な説明がある。
リュウグウノツカイ科Regalecidaeはアカマンボウ目Lampridiformes、フリソデウオ亜目Trachipteroideiに属する硬骨魚類の一群である。2属:Agrostichthys PHILLIPPSとRegalecus BRUNNICHとを含み、前者はニュウジーランドから1種A. Parkeri(BENHAM & DUNBAR)が知られ、後者すなわちリュウグウノツカイ属は大西洋・太平洋・インド洋の広範な海域から多数の種類が記載されたが、その多くは現在ではシノニムとされており、この属に何種を含ませるベキかについてはいまだに定見がない。インド洋および日本近海に産するリュウグウノツカイはふつうR. russellii(SHAW)なる学名が与えられているが、これがはたして東太平洋・北大西洋などに産するものと別種か否かという問題も完全に解決された訳ではない。
ジョセフ・S・ネルソン(Joseph S. Nelson)の『世界の魚類』第3版(1994)ではアカマンボウ目は7科12 属19種とされている。7科とはVELIFERIDAE(クサアジ科)、LAMPRIDIDAE(アカマンボウ科)、STYLEPHORIDAE(ステュレポルス科)、LOPHOTIDAE(アカナマダ科)、RADICEPHALIDAE(ラディイケパルス科)、TRACHIPTERIDAE(フリソデウオ科)、REGALECIDAE(リュウグウノツカイ科)である。東海大学出版『日本産魚類大図鑑』第2版(1988.11.30)にはアカマンボウ科(アカマンボウ)、クサアジ科(クサアジ・ヒメクサアジ)、アカナマダ科(アカマナダ・テングノタチ)、フリソデウオ科(ユキフリソデウオ・サケガシラ・テンガイハタ・フリソデウオ・オキフリソデウオ)、リュウグウノツカイ科(リュウグウノツカイ)が記載されている。その内アカナマダ科、フリソデウオ科、リュウグウノツカイ科がフリソデウオ亜目に含まれる。
リュウグウノツカイが江戸時代の図譜に異魚として取り上げられていることについては既に述べたが、フリソデウオ、アカナマダ、サケガシラ、アカマンボウ、クサアジも江戸時代に捕獲されたことがあった。シーボルト『日本動物誌Fauna Japonica』(1833~1850)にはアカナマダ、クサアジが既に紹介されている。磯野直秀は享和2(1802)年、「和歌山南方の小浦で得たフリソデウオの件が、『桃洞遺筆』巻四に記されている」(『日本博物誌年表』p.422)と指摘している。江戸科学古典叢書28『桃洞遺筆』(恒和出版、1980.5.30)pp.262~264の記述がそれに当たる。享和2年の春小野蘭山が熊野で採薬の命を受け、『桃洞遺筆』の筆者小原良貴(桃洞、1746~1825)も従った。日高郡三尾の荘小浦で小異魚を得たが、その土地の人々も名を知らなかった。大きさ5寸(15cm余)、尾は糸のようで赤色(長さ9cm)、鰭は長く柔らかく燃えるような赤色、胸の下に赤色の巨毛一條(長さ12cm)があり、体色は淡紫で小黒点があった。「総体麗しき魚なり」と言っている。この浦で時々釣りにかかる。添えられている図をみると、フリソデウオの幼魚のようである。解説の上野益三は「二十二丁に図示する小異魚は何種かよくわからない。日高郡三尾の荘、小浦で得たものだという」と述べているが。栗本丹洲「異魚図纂」(奥倉辰行画)にある魚も同じものだと思われる。説明には「紀伊黄門公ヨリ享和二壬戌ノ秋御國許リヨリ此圖ヲ以テ鑒訂スヘキヨシヲ云贈ラル余未見サル処其名モ不知ヨシヲ答フ」とある。丹洲にも分からなかったらしい。丹洲はマンボウに関心を持ち「翻車考」と題するマンボウに関する著があるが、アカマンボウ=マンダイ、錦ダイ、萬寶ダイ、萬年鯛についても魚譜で記述している。磯野直秀『日本博物誌年表』には正保4(1647)年4月、享保17(1732)年5月、寛政3(1791)年6月にアカマンボウの記述がある。同じく磯野直秀「珍禽異獣奇魚の古記録」には寛延元年(1748)年10月に三浦半島の小坪浜でサケガシラが、宝暦13年夏、仙台の奈武里浜でアカナマダが捕獲されたことを挙げている。
リュグウノツカイの測定値の科学的報告では1960年の西村以前では兵庫農科大学の森為三が行っている。「兵庫農科大学研究報告 自然科学篇」第2巻第2号(1956.12.25)pp.33~36「南日本海で獲られた稀魚 Regalecus russellii(SHAW)リュウグウノツカイに就いて」で、森は「従来本書の我が国に於ける記載は簡単且つ抽象的で完全な測定値など載っているのは見当たらない」と述べている。森は「日本でも本魚の採集された場所は10数カ所に過ぎず」と指摘し、後部欠損の兵庫農大の標本と他所三ヶ所の完全標本との測定値を表に表している。特徴的な背鰭条数は6/349、6/365、6/345、6/157+X 、と全て6本の長い第一背鰭条を確認している。その上で大西洋産のR.glesneとインド洋・北太平洋のR.russelliiがシノニムだとすることに異を唱えている。russelliiが4-6の第一背鰭条があるのに対し、glesneは8-15の条数がある。その他、鰓膜条の数、腹鰭の尖端・関節骨の形態に違いがあることを挙げている。西村は北大西洋産のR. glesneでは尾鰭が欠落しているといわれていると「リュウグウノツカイの游泳方法をめぐって」中で述べている。ネルソンの『世界の魚類』p.217に載るリュウグウノツカイ科の図を見ると鰭条数は9、尾鰭はなく尾の先が尖っている。説明文には次のようにある。
リュウグウノツカイ科-オールフィッシュ(oarfishes) 海産 全海洋に分布
無鱗;しり鰭なし;腹鰭は長く延びて、細く、鰭条は1本;背鰭は非常に長く、口吻先の後ろから明瞭に生じ、条数は260から412、尖端の数本の鰭条は長く延び鮮赤色;目は小さく;歯はない;ウキブクロを欠く;脊椎は143から170。Regalecus glesne(オールフィッシュあるいはニシンの王)は40から58の鰓耙がある;Agrostichthys parkeri(ストリーマーフィッシュ)の鰓耙は8から10。この魚群はおそらく多くの大海蛇伝説の原因であろう。最大全長はR. glesneで8m以上に達する。RegalecusとAgrostichthysの2単型属。
「eye small]とは森の「眼は普通大で」という記述や一般的イメージと矛盾するように感じる。兵庫農大の個体は西村が解剖した個体と異なり、「食道、胃などの内容物を見ると小形甲殻類の央ば消化されたもの」があった。小形甲殻類とはアミ類である。
森は第27回日本動物学界大会でリュウグウノツカイについて報告し、その要旨が「動物学雑誌」第66巻第2・3号(1957.3.15)p.104に掲載されている(「稀魚Regalecus
russellii(SHAW)リュウグウノツカイに就て」)。
西村が1960年に得た個体は2月24日に捕獲されたものであるが、同じ年7月4日に山口県萩沖の大敷網に体長2.77m、体重3.975kgの個体がかかった(上田常一「山陰地方の海岸に不時回遊し、または漂着した珍しい動物」、「山陰文化研究紀要」第2号、1962.3.30、pp.1~35)。
西村はリュウグウノツカイの捕獲時期に関して「冬から春にかけてと初夏の頃とのふたつのピークを区別しうるのではないかと思われる」と指摘しているが、1960年はまさにこのパターンに当てはまる。また、捕獲・目撃が極前線(暖流系水と寒流系水との間の不連続線)以南であることから、その分布が暖流系水の分布・消長に関連を持っていることにも言及している。さらに、温度・塩分関係の数値からリュウグウノツカイを中央水塊中に棲息すると推測した。西村の業績はリュウグウノツカイに関しては游泳法と棲息域の仮説にある。人魚モデル説に関しては内田恵太郎の論を継いだという立場にある。
なお、西村が測定したリュウグウノツカイの脳髄の構造については島村初太郎が報告を行っている(「日本海区水産研究所研究報告」第10号、1962.3、pp.59~74、「リュウグウノツカイ(Regalecus russellii SHAW)の脳髄の形態とこれから推察される行動についての研究」)。西村は同号pp.51~58に「Recent Increase in the Occurrence of the Deal-Fish in Alacent Waters to Japan(近年のサケガシラの捕獲状況について)」を発表している。サケガシラについては続報を第13号(1964.3.30)pp.127~129に掲載している(「Additional Information on the Biology of the Dealfish, Trachipterus ishikawai JPRDAN & SNYDER」)。
また、リュウグウノツカイ研究の前にはハリセンボンの日本海での冬期の漂着に着目し「日本列島対馬暖流域におけるハリセンボンの“寄り”現象について」を「日本海洋学会誌」第14巻第2号(1958.6.25)pp.53~63、第14巻第3号(1958.10.25)pp.103~107・pp.109~116に西村は発表している。海流と暖海性生物の漂着については、他に「熱帯・亜熱帯性動物-とくに魚類-の日本海への流入ならびにその内部における移動に関する一考察」(「日本海区水産研究所研究年報」第4号[1958.12.25]pp.113~119、「“佐渡年代記”にあらわれた流れ鯨の記録(1)」(「採集と飼育」第23巻第12号[1961.12.8]pp.371~373・p.375)、「日本近海におけるオサガメの記録」(「生理生体」第12巻第1・2号[1964.9.30]pp.286~290)などの研究がある。
水産研究所での11年間の研究の後、西村は母校京都大学瀬戸臨界実験所に移り、同大学教養学部教授となり、実際の生物から博物学史の研究へと進んだ。その最大の成果は先に言及した『文明のなかの博物学』上下である。
by釜野啓(aka. MORO-Z)
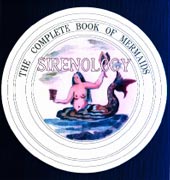
ソーダ・ポップがはじけるようなイントロで始まるガール・グループのオールディズ「ポプシィクルズ アンド アイシィクルズ Popsiclles and Icicles」。歌うはマーメイズ。ああ、人魚が歌っている、と思っていたら、THE MURMAIDSだった。なんでEじゃなくてUなの。1963年、全米トップ・テンに入った、耳に心地よいポップ・チューンは後にブレッドを結成するディヴィッド・ゲイツの作であった。マーメイズは3人組、セイレーンも3人(二人、四人説もあり)、ついでに言えば「ぴちぴちピッチ」の歌う人魚も3人であった。「人魚の歌」のことを考えていた時にラジオから聞こえてきた。
「人魚の歌」と言えば、こちらも気になるのが、メイ・サートンの『ミセス・スティーヴンズは人魚の歌を聞く』(May Sarton,“Mrs.Stevens Hears the Mermaids Singing”、大社淑子訳、みすず書房、1993.9.30)である。F.ヒラリー・スティーヴンズは70歳近い詩人・小説家。ニューイングランドの海に面した別荘で一人暮らしをしている。同性愛者の若者に詩を書くように勧め、作の中心部分では自身の詩人としての経歴、女性が文学者であること、母娘関係についてインタヴューという形で開陳している。作の初めの部分で若者に言う言葉、「彼には人魚の歌が聞こえないけど、あなたには聞こえるってことよ」(訳書p.27。He doesn't hear the mermaids singing, and you do.)。この部分に関して訳者大社淑子は「訳者あとがき」で、次のように解説している。
まず、本書の題名『ミセス・スティーヴンズ』の「人魚の歌」とは何か、という問題がある。この言葉はヒラリーが、マーと化学の教師との同性愛についての告白を聞いたとき、マーに向かって「彼(ルーファス)には人魚の歌がきこえないけれど、あなたには聞こえるっえことよ」と語るところに一度述べられているだけである。文脈から判断すると、この「人魚の歌」とは、感受性の鋭さであり、そうした感受性から成り立っている人間性であり、その結果としての芸術を創造する資質をさしていると思う。さらには、ミューズに出会うことのできる特質とも言える。詩は情熱を原動力として、ゆたかすぎる感情をみごとな形と秩序のなかに統御することによって生まれてくる。このような情熱に殉じることのできる人が人魚の歌を聞くことができる、と解釈してもいいだろう。
作中でスティーヴンズは「わたしは、自分の〝天才〟になんの幻想も抱いていないということを、いますぐ言わせてちょうだい」「限度まで開発した、ささやかで、正確な才能よ」と言っている。また、プラトン「パイドロス」ではソクラテスの言として、「ムゥサの神々から授けられる神がかりと狂気とがある。(中略)もしひとが、技巧だけで立派な詩人になれるものと信じて、ムゥサの神々の授ける狂気にあずかることなしに、詩作の門に至ならば、その人は、自分が不完全な詩人に終わるばかりでなく、正気のなせる彼の詩も、狂気の人々の詩の前には、光をうしなって消え去ってしまうのだ。」(『プラトン全集』第5巻、岩波書店、1974.10.4、p.176、藤沢令夫訳)と記している。
ムゥサとはミューズのことで、「文芸、音楽、舞踏、哲学、天文」など人間の知的活動を司る9人の女神である。セイレーンはムーサとの競技にに破れ海に身を投じたとも、ムーサの一人カリオペーは、アルゴ船の漕ぎ手達をその歌でセイレーンの魔力から守ったオルペウスの母とも言われ、人魚の音楽をめぐってはセイレーン、ムーサ、共に関連が深い。セイレーンの歌でさえ、決して魔の領域だけに限定されるわけではない。アルクマーンにおいては「ミューズの声が聞こえる。声あかるきセイレーネスよ!」と歌われ、「パイドロス」では「セイレンたちのそばを無事に船で通り抜けるように、彼らのそばにいながらそのうた声に魅惑されないでいるのを見るならば、きっと彼らは感心して、人間どもに与えるように神々から授かっている贈りものを、ぼくたちに与えてくれることだろう」(p.210)とある。「パイドロス」の「彼ら」とはソクラテスとパイドロスが話し合っている頭上で歌い、見守っている蝉をさしている。ソクラテスは蝉はムーサの神が生まれない前の時代に生きていた人間で、ムーサが誕生し、この世に歌が現れると、その楽しさに寝食を忘れて没頭し死んでしまった者たちの生まれ変わりだと言っている。蝉は食物を必要とせず歌い続け、死後はムーサの元へ行き、どの人間がムーサの神を敬っているか報告する役目を担っている。セイレーンはムーサと同様、音楽を代表し、ムーサの娘、冥界の女神となり、墓石に刻まれ、幸ある死者の島の音楽家と考えられるようになった。言語、文芸、音楽の洗練された形がムーサの領域であり、原始的な形がセイレーンに代表され、後には融合したと考えられようか。セイレーンの一人が海峡を渡りナポリを建国したとの言い伝えを、映画「永遠の語らい」(マノエル・オリヴェイラ監督)で聞いたことがある。また、文化神として海から現れたメソポタミアの神々を思い浮かべることも出来よう。
それはさておき、『ミセス・スティーヴンズは人魚の歌を聞く』にはまだ、人魚への言及がある。芸術家になれなかった母親との精神的格闘についてインタヴューでのスティーヴンズの発言、「八つにならないうちから、それが私をだめにしてしまった。あるいは、わたしを詩人にしたと言ったほうがいいかもしれない。アーノルドの『捨てられた雄の人魚』を読む声-〝子供たちよ、あれは昨日だったろうか?〟-を忘れることができるかしら?それから、〝マーガレット、マーガレット〟という叫び声の苦悶を。」(訳書p.244)の部分である。MERMAIDSも歌うが、MERMENも歌うのである。去っていった人間の妻「マーガレット」に。
マシュー・アーノルド(1822~1888)の作は森亮訳「そむかれたる雄の人魚」として「コギト」第87号(第8巻第8号、昭和14年8月1日)pp.45~53に見ることができる。海の王の妻となり、子供も何人か持った人間の女は、復活祭の教会の鐘の音を聞き「私は魂を失うてしまふ、人魚よ、此處にそなたとゐて」と嘆く。人魚は一時地上に戻ることを許すが女は海には戻らなかった。子らをつれて、共に名を叫ぶが声は届かない。女は子供達の姿を思い浮かべているようだが、教会にとらわれたように、海の底には帰らなかった。マーマンは歌う。「人の世の女來たり、/信なくて背きければ、/とこしへに獨り住まふ/わだつ海の王らは」「かしこに愛しき女住まふ、/さはれそはつれなくて、/永へに置き去りぬ/わだつ海の王らを侘しく」と。男の人魚の歌は誘惑でなく、恨み節である。神の言葉にはかなうはずもない。
海から帰ったマーガレットが教会で糸車を回している様は、有名な15世紀初頭のオランダの人魚を彷彿とさせる。山村昌永(才助、1770~1807)はその著「西洋雑記」(享和元年[1801]自序)で、西暦1403年にオランダの湾中から女人に異なるところのない異物を得たと記している(同書にはセイレーンの記述も含まれている。「セヰレデネンは海中に生ずる一種の怪物にして、その上体は婦人にして、下体は魚なり。よく魔魅妖術をなす。若し其の声を発して歌を唱ふが如くなる時には、風波大きに興りて海舟を覆没す。此の物、イタリア国の属島、シチリアの海辺にありといへり。然れども唯だ此の説をいひ伝へて、世に其の像を画きて崇飾を加ふる者ありといへども、たえて的実に此の者あるをきかず。けだしまた昔時の寓言ならん」)。この「水中の女」が教会の保護の下、織物も覚えたことは有名な話である。アーノルドによるマーガレットのイメージに共通するものがある。
陸に帰った妻を人魚が連れ戻そうとして、教会のために妨げられるというモチーフはデンマークのフォークロア「アグネーテと人魚」にも見られる。こちらは下宮忠雄が訳している(下宮忠雄「アグネーテと人魚」[「学習院大学言語共同研究所紀要」第6号、1984.3.1、pp.62~72])。アグネーテはホイエランの橋を渡っているときに、男の人魚に誘われ、海の底で8年間過ごし、7人の息子を得る。教会の鐘の音を聞いたアグネーテは、ブロンドの髪をなびかせないこと、教会の椅子に坐っている母親の所に行かないこと、牧師が神の名を呼んでもおじぎをしないこと、という3つの約束を夫の人魚として人間社会に一時もどった。アゲネーテは約束をことごとく破って、人魚が一人教会にやって来て、子供達が恋しがっていると言っても、冷たく「帰らない」と拒絶するのであった。
アンデルセンが「人魚姫」以前に、「アグネーテと人魚」という作品を発表していることは有名であるが、どのような話か読んだことはない。下宮によると、「人魚に恋した若い娘アグネーテが、婚約者を捨てて海の底に行き、男の人魚と7年間宮殿に暮らすが、人間世界に郷愁を感じ陸にもどってくると、そこでは7年でなく50年が経っていた。そして母親も昔の婚約者も死んでいた」という「戯曲詩」である。「アグネーテと人魚」については室井光広も言及している(「人魚の男-キルケゴールとアンデルセン(十四)」、「群像」第54巻第2号、1999.2.1、講談社、pp.448~460)。
ドイツ、スラブに淵源のある水の精と結婚し再び人間社会に戻ってきた女性のフォークロアを題材にアーノルドはマーマンの哀切な詩を作った。生真面目な人魚と当てにならない人間の心。水の精は、その住む水のように気紛れで変わりやすいものだとする考えを逆転し、人間こそが自分勝手で度し難いとして物語を展開することもあり得ることだ。19世紀の水の女性たちの物語は、この人間の変心を中心に展開している。子供の物語にもそんな話があった。「赤い蝋燭と人魚」以外に。
大正時代の子供雑誌「おとぎの世界」第4年第2号(大正11年2月1日)pp.30~38に掲載された島東吉「支那童話 人魚の歌」(挿絵 齋藤勇)がそれである。一人で舟に乗っていた少年が沖へ流され、人魚に岸に戻してもらうという前半。決して人魚について話してはならないという約束を少年が守らず、大人達が見世物にしようと人魚を捕獲したので、人魚は仲間を守るために人々を人魚に害を及ぼさない動物に換えてしまったという後半で話は構成されている。前半部の人魚の歌は、
お月様、お月様
まん丸いは笑ひ顔
笑ひ顔は明るいな、ハアオハアオ。
お月様、お月様、
細いつこいは泣いてる顔、
泣いてる顔は暗いな、アイヨーアイヨー。
と月を歌ったものである。また、「人魚は至って同情深い性質」であるから、「人間は極めて腹黒い生物」であることを承知の上で少年を助け、元気づけるために唱い踊る曲は、
踴れ踴れ、ロアンチーパーソアオ、
人魚の踴りを人間の子よ、カンイカン。
歌へ歌へ、メーカイエエンシイヤオ、
人魚の歌を人間の子よ、デヌイデス。
アイヨー、アイヨー。
であった。そして、忘恩の末に捕らえられた人魚の「呪文めいた暗い唸り」は、
お前は、嘴の赤い愚鈍な鴉になれ!
お前の親兄弟姉妹は、痩せつポチの驢馬になれ!
部落の者は、凡て人間を戀しがる蝗になれ!
というものである。人々がそれぞれの動物となって、人魚を捕らえることなどできなくなったので、人魚達は月光の下、また歌い出した。
人間心理の暗黒面を強調した作品が作者の創作なのか、原話があるものか分からないが、人魚と月の結びつきは各国の神話、昔話にしばしば見られることである。
「おとぎの世界」誌上にはもう一つ人魚を題材にした作品がある。第1年第7号(大正8年10月1日)pp.36~40、水野葉舟「人魚の娘」(初山滋・絵)である。15歳の誠子は妹と大学生の叔父とで鎌倉の別荘に来ている。誠子は物語を読むのが好きで、バーネットやアンデルセンを好んでいた。父は空想がちな誠子を心配して、旧約聖書物語やジャンヌ・ダルクなどの伝記的読み物を勧めていた。女学生である若い叔母は新橋を汽車で発つ時、アンデルセンを鎌倉に送ってくれると言っていた。「トイブツク風の、繪の美しい」本には「指姫」「月物語」「人魚娘」などが収められていた。誠子は海の近くに来ているということもあって人魚の話に惹かれた。「美しい聲を持つてゐる、それで唱ひながら、海の中をおどつて泳いでゐる」人魚のことを考えながら庭先から海に出ると、人魚の娘が自分を待っているような気がしてきた。と同時に、人魚が物語のように美しい者でなく「恐ろしい異様なもの」ではないかとも思われてきた。その時、背後に18位の女性が現れて「あなたにいゝところをみせてあげませうか?」と声をかけてきた。誠子は恐くなって女性を振り払って家のしおり戸まできて立ち止まると、「私は人魚の娘です」という声が聞こえたが、姿はなかった。
「おとぎの世界」という誌名から抱くイメージとは少し離れたホラーじみた話になっているが、水野葉舟(1883~1947)は大正前期には心霊現象に興味を抱いており、加藤朝鳥との共訳で雑誌「ARS」に「セザアル、ロムブロゾオ」の「死後の問題」などを発表している(第1巻第6、7号、大正4年9月、10月)。
人間に捕らえられた人魚が津波を呼び寄せたり、網に入った人魚を助けたので、その村の人々だけが大津波から助かったとする話は沖縄に多く見られ、チャイルド絵本館/日本の昔話4『にんぎょのはなし にんぎょのうた』(こわせたまみ文、夢田誠絵、1993.7.1)でも語られている。夜毎、海から娘の声らしい「ほそく、うつくしい、うたごえ」がきこえてきたが、その声の主は人魚で、海の秘密を人々に教えようと歌っていたのである。網にかかった人魚は大津波の襲来を人々に告げ、それを信じた村だけが生き延びたという伝説を元にしている。歌は海の予言を伝える前触れだったのである。他に沖縄の津波と人魚との関係を扱った絵本としては、民話のえほん『ニライからきた人魚<沖縄の民話>』(池田和文・井口文秀絵、小峰書店、1976.1.25)がある。
人魚の歌を聞きつけて、捕らえてみたものの、人魚の懇願により海に戻し、人間は見返りをもらうという話もイギリスに見られるが、次に紹介するのは松本苦味「フランス童話 人魚の歌」である。博文館「少年少女譚海」第3巻第8号(大正11年8月1日)pp.40~48。口絵「人魚の唄」は小笠原寛三による。余り豊かでない木靴職人の一家が「アヴァの森のなかのサン・カスの教区」に住んでいた。小さな息子が釣りをしていると、「えも云はれぬ美しい聲で、歌を唄うのが聞えた」。それは人魚であった。波間でうたた寝をしていた人魚を木靴職人は捕らえて家に持って帰る。焼いて食べてしまおうと妻が言うと、人魚は自分は仙女と同じ力を持っていて、食べたら最後、人間の命は亡くなるだろうと警告し、海に戻せば、望みの物を与えようと提案した。木靴職人が願ったのは、食物と衣類、借金を払うだけの金だった。水中で鰭を動かすと、金の玉や衣装箱が現れるのであった。一年後、財宝も少なくなった頃、もう一度人魚が唄うのを一家は聞きつけた。人魚は今回も財布一杯の金銀をくれたが、ここを去って暖かい国に行くと告げ去っていた。「それ以来、ふたゝびフリスネエの磯邊で彼女の美しい歌をきく人もなかつた」。
松本苦味、本名圭亮は明治23(1890)年生まれ、東京外国語学校でロシア語を学ぶ。大正12年に紅玉堂書店から『繪入世界童話選フランス童話集』を刊行している。第一輯『人魚の唄』(大正12年4月20日)。収録作品は人魚の唄、ある兵卒の話、失楽園、利口な泥坊、日曜日には働くな、笛の音の6編である。「人魚の唄」はPaul Sebillot著“Contes des Paysans et des Pecheurs”から採られた。第二輯『三獣士物語』(三獣士物語、おばけ馬、善心悪心、鶏のおかみさん、未来、二人の脊虫、ちびのヂョン)。第三輯『鬼をつかまえる話』(鬼をつかまえる話、プランポリオン、運命、地の娘、脊虫の王子)。童話関係ではデンマルク童話集『奇妙な箱』(冨山房、大正5年)、支那童話集『嘘の皮』(冨山房、大正5年)、世界童話集『たから舟』(大倉書店、大正9)、滑稽童話集『猫の市長さん』(実業之日本社、大正12)などの編著があり、専門のロシア文学関係では金桜堂パンテオン叢書にチヱーホフ『農夫 外五編』とゴオリキイ『どん底』(大正3)、文正堂書店刊、ツルゲーニエフ『春の水』(大正7)、リョフ・トルストイ、昇曙夢校閲、松本苦味編『露語讀本』(大倉書店、大正11年)があるが、関東大震災後は消息不明になったらしい。なお、パンテオン叢書については、紅野敏郎が日本古書通信の連載「大正期の文芸叢書」で取り上げている(「金桜堂の「パンテオン叢書」」、1997.2.15、pp.11~13)。松本苦味は同叢書の監修者であり、7冊出版されたらしい。
大正10年1月の實業之日本社「少女の友」(第14巻第1号)にも「人魚の歌」という作品が掲載されている。文、絵とも原田なみぢ。冬休み、南の国の海辺にある叔母の家に滞在していた光子は、ある日の夕方、海から楽しげな歌声が聞こえてくるのに気付いた。
まつかなお日様、お月様
海のお國は夢の國
さあさあ皆なで歌ひましよ
人魚の唄をうたひましよ。
顔の白い、黒髪の人魚たちが、長いラッパを吹きながら泳いでいるのが波間に見えた。光子が美しい海の国へ行ってみたいと思っていると、神様が望みの叶う指輪をくれた。決して指輪を他人に渡さないようにと言って。指輪の呪文で人魚に変身した光子は、友達になった人魚に指輪を渡してしまった。海の国に飽いて、人間世界に戻ろうと思っても帰ることは出来ない。汀で大声をあげて泣き出した光子は、自分の声に驚いて目を開けると、叔母の家の窓辺で寝込んでしまっていたことに気付くのであった。
同時期の博文館「女学世界」には「人魚と結婚した話」が載っている(第23巻第3号、大正11年3月1日、pp.90~98)。ジユル・ルメートル作、工藤ふた葉訳である。オデュッセウスとセイレーンの挿話を下敷きにしたコントである。ユリス(オデュッセウス)の船の水夫にウフオリオンという男がいた。ユリスが策を弄してまで聞きたいと思った人魚の声を、命を失ってもよいから自分も聞きたいと決意して、耳から蝋栓を剥ぎ落とした。海に落ちたウフオリオン一人残して船は去っていった。7人の人魚たちは唄をやめて、かれに襲いかかり洞窟の奥に引きずり込んで、肉を裂き血を啜ろうとした。一人の最も美しく見えた人魚に、本望であるから、あなたの手で殺されたいとウフオリオンが言うと、人魚ルユジアは愛を初めて感じ、二人で暮らすようになった。人魚は「この地上の秘密をばなべて知り居るわれ等ゆゑ」と歌っていたが、実のところは僅かな名詞と基本的な動詞を知っていたに過ぎなかった。「彼女等が唄つた言葉、今では夜毎に彼の聞くその言葉は、豊かな知識を述べてゐるのでは無く、朝の爽かさ、夕暮の壮麗さ、海の美感と廣大さや、又は単に気軽い疲れること無き身を持つことの歓びなのであった」。ウフオリオンは、ルユジアの無知と冷たい肌が厭わしくなり、かつての生活に戻りたくなっていった。そして人間生活がいかに美しいかを語り、人魚の好奇心を刺激して、一緒にアテンの都市に行くようにし向けるのであった。ウフオリオンは陸に上がると、一度は人魚を見すてようとしたが、人魚の目から涙が溢れ、「かわいそう」という言葉を初めて口にするのを聞き、ウフオリオンは人魚にと一緒にいたいと思うようになった。そこに女神テテイスが現れ、ルユジアから不死性を消す代わりに、人間の女となってウフオリオンと一緒に暮らせるようにしてあげるのであった。「テテイスには、彼等を果して幸福にしたかどうかが、あまり確かでは無かつたからである。実際、斯うして結婚した二人は、幸福になれたであらうか?」が最後の文章である。
この作品は「人魚」と題して井上勇訳が近代社版『世界短篇小説大系 仏蘭西篇』([下]、大正14年9月13日、pp.194~207)に収録されている。主人公はユウホリオンとリュウコシアとなっている。最後の一文は「彼女には果たして、二人のために幸福をさづけてやつたかどうかわからなかつたからである」となっている。連続猟奇殺人事件を扱ったヴァル・マクダーミドの「歌う人魚」でも、心理学者が殺人鬼を理解しようとし、愛まで口にして難を免れるが、人魚は人間に愛を求め、あからさまな拒絶には死を持ってするが、愛を感じたときには人魚自らが死ななければならないのが定めのようである。また、愛を得るためには、人魚姫の声のように、身を変える代償も多大である。
「女学世界」大正11年には9月号にも人魚の話題が載っている。宮良當壯(1893~1964)「貢物にされた 人魚の話」(第22巻第9号、pp.156~157)である。人魚の正体は儒艮、琉球でザンというものであると言い切っている。「私の幼い頃に漁師が儒艮をよく砂濱に仰向けさせてあつたのを見たことを覚えて居ります」と言って、「琉球ではその肉を食ふと肥満長壽を保つことが出来るといつて大いに食用に供しますのみならず、婦人が妊娠した場合には必らずその乾した物を剥いで煎じて汁を飲ませる風習もあります。(中略)又その脂肪からは脂を製します」と、この漫筆でも何度かふれた沖縄ジュゴンと食との関わり合いをここでも確認できる。また、ジュゴンが肉と脂に富んでいる所から「肥満した者をザンバンタリ(儒艮肥満)とかザンカミ(儒艮亀)などといひます。儒艮を亀の一種と思つてゐるのであります」と興味深い言葉の用法を教えてくれる。ジュゴンの食物はアマモであるが、宮良は「彼等の好物はわが國で生児の胎毒を下すに用ゐる海仁草といふ長さ一二寸ばかりの海藻ださうです」と言い、「人魚のザンであることは誰しも認むる所でありますが、ザンを儒艮と正解する人は甚だ多くないのであります。大抵海馬即り龍の落子といふのであります」とも伝えている。宮良の文の後半には、ジュゴンが浅瀬に寄ったことを歌う八重山のユンドク(讀言)と、ジュゴンの漁場であった新城島の恋歌集「變の花節」から、懐胎した儒艮を助けてやっていた乙女が、儒艮に救われるという物語の梗概を記している。
沖縄、八重山生まれの詩人伊波南哲(1902~1976)は昭和18年4月に興亜文化協会から『人魚のうた』という本をだしている。その中の「人魚のうた」(pp.129~134)は戦時色強い作である。弘は夏の月夜に人魚を釣り糸に掛けた。人魚は釣り針を取って海に放してくれたら、歌をうたってあげると言った。弘は歌が聞こえると、突然、「えりを正して、東の方に向ひ、はるか天子さまのおはす皇居を、ふしおがみました」。そのわけは、「この島のいひつたへに、戦争中、人魚をみたり、人魚のうたをきいたりすると、その國の大勝利うたがひなし。」ということを思い出したからだという。
沖縄ではないが、遠い南の島の人魚を扱っているのが物語詩「人魚の唄」である。前田芳雄著、千地養巣装幀並挿絵『(仏教童話宝玉集)人魚の唄』(興教書院、1932.5.5)pp.335~413に収められているジャータカのような趣の物語詩である。白椿の咲く南の島には美しいが寂しげな女人と今年15歳になる娘がたった二人で住んでいる。ある日娘は、湖に住む姫と一羽の鵠の鳥(コウノトリ)の「前世からはなれられない因縁」の夢を見た。鵠の鳥は姫に「人魚の唄」を思い出しはしないかと尋ねていた。南の島にいる鳥は孔雀と「コキラ鳥」である。コウノトリは海を飛びすぎて行くだけである。ある眠れぬ夜、コキラ鳥の鳴き声に誘われて娘は浜辺に出、月光の下、歌う人魚を見つける。娘は人魚に鵠の鳥と姫の話を知らないかと話しかける。人魚は「前世からはなれられない因縁」を物語った。
百羽の鵠の鳥が金の羽根を持つ長と副長に率いられてヒマラヤの峰々を毎年超え、旅していた。ある国の王がその鳥の飛ぶ様を見たいと思い、人造の美しい湖を作った。鵠の鳥の群れが立ち寄ったところ、番人が罠をしかけ、長がかかってしまった。副長以下は無事だったが、副長は自分も残り、群れの他を去らせた。罠にかかってもいないのに残っている副長に番人が訳を問うと、「わなよりもつときれにくい徳の綱」が教え導くと副長は答えた。感じ入った番人は二羽を放そうとするが、国王に罰せられるだろうからこのまま献上せよと鳥たちは言う。この一部始終を聞いた国王は自らを恥じて、鳥の綱をほどき、番人には褒美を与えた。その後は旅の途中に必ずこの国の湖を百羽の鵠の鳥が尋ね来るようになった。
これを伝え聞いた隣国の王は、さぞかし黄色の鵠の鳥は美味だろうと思い、罠を隠した湖を自国にも作った。この国の王が無慈悲なのを知っていた鵠の鳥の長は配下にその湖に下りることを禁じていた。しかし、旅に疲れた一羽の鵠の鳥は水面に降りて捕らえられてしまった。金の鳥でないことを怒った王は番人を鞭打とうとする。身ごもっていた妃は非道な振る舞いはやめて、鳥を放つよう懇願するが、国王の怒りは収まらなかった。鵠の鳥の背に妃を縛り付け、高塔の窓から投げ捨てしまったのである。鵠の鳥は弱っていたが、力を振り絞って西へ数百里、海を渡って椿の咲く島、白髭の老人が住む島目指して飛んで行く。翼の折れた鵠の鳥は海に沈んだが、白髭老人が船で妃を救い、泉の霊薬で元気になり姫が生まれた。老人はコキラ鳥になり、海に沈んだ鵠の鳥は人魚となった。
最後には仏の「智慧と慈悲」との救済を説き、
人魚の唄の愛しさは
月の光も 波音も
和み和んでしみじみと
奇しき縁に湧く涙
涙の光胸に秘め
やがてこの世を救ふべき
佛陀世尊のかゞやきを
待ちのぞむ唄 のぞむ唄
あゝその調べ、その調べ。
で作品を終えている。
著者前田芳雄は昭和初期に、京都本派本願寺執行所の「ともだち社」を発行所とする雑誌「ともだち文庫」の編輯兼発行人であった。「ともだち文庫」は第7巻第7号(昭和9年11月5日)しか見たことはないが、同号は全編「悲しき別れ」という関東大震災で両親と死別した三人兄弟が親切な学生の世話で生きて行く話である。震災後、上野公園に築地本願寺の出張所が出来、龍谷大学の学生が野外学校を始め、学生が京都に帰ってからは日曜学校の教師が教えるようになり、やがて、竜泉寺小学校の分校として正規の教師が授業を始めたと書いている。後期には、昭和9年9月21日に台風災害があり、数千人の人災があったと記している。「わが日曜学校では、早速義捐金を募集し、救援の資にあてると共に、西大谷へ遭難惨死学童教職員の墓碑を建てることにいたしました」とも書いてある。前田は興教社から他に『さんぶつ歌物語』(昭和5)、『聖者親鸞』(昭和16)を出版しているが、『聖者親鸞』は前田芳雄遺稿刊行会編となっている。なお、雑誌「ともだち文庫」は「ともだち」を改題したものである。浄土真宗本願寺派(西本願寺)の刊行物であった。
教訓話に人魚が登場することではキリスト教も伝統がある。博品社版『フィシオログス』(オットー・ゼール、梶田昭訳1994.6.25)の「セイレーンとケンタウロス」の項(pp.41~43)では、「セイレーンとケンタウロス、つまり分裂した生、不まじめな異教の似姿である。かれらは、セイレーンのように、まことしやかな言葉で、純朴な人びとの心を欺く。まことに、悪い交わりは良いならわしを台なしにするのである。」と言っている。この場合のセイレーンは鳥形であるが。ひのかずなり文・さし絵『うふふの動物たち』(福音館書店、2005.6.1)は名画に画かれた動物たちの楽しいおしゃべりを案内してくれる。コジモ「天使と馬と人魚(寓意)」(pp.6~7)は「あっちむいてホイ」をしているように見えるが、人魚は悪魔の化身で、馬を誘惑しているのである。誘惑者を気づかせてくれるのが、ここでは天使であるが、高崎能樹『童話集 鈴蘭』(宗教々育圖書刊行會、昭和3年12月10日)pp.45~51「人魚の誘ひ」では人魚の誘惑の歌を音楽家の「天國の歌」で撃退している。オルフェウスの故事をキリスト教的に描き直している。「偉い音楽家」とはキリストのことだと言っている。
「人魚のうた」をめぐって主に児童文学の作品を紹介してみた。誘惑者であったり、保護者、救済者、被害者であったりといつもながらの人魚の位置であったが、その歌声は少しは聞こえたであろうか。
by宇田垣こゑる(aka. MORO-G)
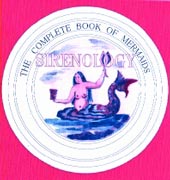
さまざまな立場から人魚について発言してきた人々がいる。神話学、フォークロア、文学、美術史、漫画、心理学、病理学、薬学、科学史、博物学、宗教、それこそあらゆるバックグラウンドを持った人々が人魚を話題にしてきた。そのなかで、動物学者(zoologist)の一群も人魚に興味を寄せてきた。ここで取り上げるzoologistとは普通の意味で動物を研究している学者のことで、いわゆるcryptozoology(未知動物学)ではない。当漫筆でもすでに水産関係の学者や高島春雄、動物学の教育も受けた歴史学者箕作元八などを取り上げているが、これから何人かの動物学者と人魚との関係を述べてみたい。そこで問題になるのは、
1.動物学における専門分野
2.発表媒体(学会誌/一般雑誌〔成人・子供〕/新聞)
3.人魚=儒艮説への言及
4.他分野への興味
などであろう。アト・ランダムに思い付く範囲で人魚論考のある動物学者を紹介して行こう。最初は谷津直秀(やつ なおひで 1877~1947)である。
谷津は明治10年9月8日、東京赤坂生まれ。明治33年、シャミセンガイの発生を研究して東京帝国大学理科大学動物学科を卒業。翌年、コロンビア大学に留学、無脊椎動物を対象とする実験発生学の研究に従事、その間、ナポリ臨海実験所でも研究を重ね、明治40年帰国、母校の講師となる。明治43年助教授、その後一時慶応大学医学部に移るが、大正11年、東京帝国大学教授となり、三崎臨界実験所長を兼務。退官は昭和13年、昭和22に70歳で死去。日本の動物学界に実験手法を導入したことが最大の功績である。主著は『動物分類表』。
以上は『近代日本生物学者小伝』(平河出版社、1988.12.5)pp.275~279、竹脇潔「谷津直秀」の項によった。他に磯野直秀「谷津直秀教授著作目録」(「慶應義塾大学日吉紀要 自然科学」第5号、1988.6.20、pp.37~54)、福井由里子「谷津直秀『動物分類表』(1914)について」(「生物学史研究」第68号、2001.12.20、pp.31~44)の論考もある。
磯野直秀「谷津直秀教授著作目録」は、1.著訳書・編書(24点)、2.欧文著作(36)、3.『動物学雑誌』掲載報文・雑録(717)、4.その他の雑誌に掲載された報文(104)の計881点が収められている。これから述べる人魚関連の文は、その中には含まれていない。
 実業之日本社刊「日本少年」(創刊明治39年1月、昭和13年10月終刊)は明治時代の博文館「少年世界」、昭和の講談社「少年倶楽部」と同様、大正時代に盛期を迎えた筆頭少年雑誌であった。小説とともに科学的記事も初期から掲載してきた。帰国し東京帝国大助教授となった谷津も少年向け啓蒙科学記事をいくつか載せている。その一つが第14巻第9号(大正8年8月1日)pp.50~53「人魚の話」である。谷津の肩書きは理学博士。鏡を左手で持ち右手の櫛で髪を梳かしている人魚の図が描かれている。乳房の下には胸鰭がある。見出しは3つあり、先ず「人魚の話は世界中にある」、次いで「私も二三度人魚を見た」、最後は「黒奴を烏賊だと思った人」である。書き出しは「昔は世界中どの人種でも、水中にも自分達と同じ様な人間が住んでゐると思つてゐた。最初は身體が全く人間と同じであると考へてゐたが、それでは水中にゐるのに不便であると云ふので、後世では、上半身は人間の女で、下半身は魚とし、鱗や鰭などがあるものとした。これが即ち人魚である。」となっている。当時よく説かれたオリエント神話からギリシア神話を経て伝説・説話の人魚へ繋げる具体的事例は報告していない。次いで伝説の人魚に説き及ぶ。その中では「瓶が好きで、それを投ずると出てくる」とか「頭に海藻を載せて浮いてきたのを、豚の鹽漬を餌にして、釣った」というような他ではあまり聞かれない話も紹介している。極めつけは自身で聞いた人魚伝説である。
実業之日本社刊「日本少年」(創刊明治39年1月、昭和13年10月終刊)は明治時代の博文館「少年世界」、昭和の講談社「少年倶楽部」と同様、大正時代に盛期を迎えた筆頭少年雑誌であった。小説とともに科学的記事も初期から掲載してきた。帰国し東京帝国大助教授となった谷津も少年向け啓蒙科学記事をいくつか載せている。その一つが第14巻第9号(大正8年8月1日)pp.50~53「人魚の話」である。谷津の肩書きは理学博士。鏡を左手で持ち右手の櫛で髪を梳かしている人魚の図が描かれている。乳房の下には胸鰭がある。見出しは3つあり、先ず「人魚の話は世界中にある」、次いで「私も二三度人魚を見た」、最後は「黒奴を烏賊だと思った人」である。書き出しは「昔は世界中どの人種でも、水中にも自分達と同じ様な人間が住んでゐると思つてゐた。最初は身體が全く人間と同じであると考へてゐたが、それでは水中にゐるのに不便であると云ふので、後世では、上半身は人間の女で、下半身は魚とし、鱗や鰭などがあるものとした。これが即ち人魚である。」となっている。当時よく説かれたオリエント神話からギリシア神話を経て伝説・説話の人魚へ繋げる具体的事例は報告していない。次いで伝説の人魚に説き及ぶ。その中では「瓶が好きで、それを投ずると出てくる」とか「頭に海藻を載せて浮いてきたのを、豚の鹽漬を餌にして、釣った」というような他ではあまり聞かれない話も紹介している。極めつけは自身で聞いた人魚伝説である。
私も先年キヤスコ湾と云ふ所へ行つた時、昔この灣で、人魚が丸木舟に手をかけたので、それを切り落とした處が、丁度人の手のやうであつたと云う話が、殘つてゐるのを聞いた。
また1670年にデンマークの島に現れた人魚は禁酒を人々に勧めたという。
「私も二三度人魚を見た」とは、いわゆる人魚ミイラ(標本)のことで、それに対しては「子供か猿の頭に魚の體を附けたもので、なかなか手際よく、素人には正體が見顯されない程巧妙で出來てゐた」と述べている。その前では、ロンドンで1755年と1822年に人魚の見世物があったこと、フランスの文豪アレクサンドル・デュマもハーグで見ていたこと、1825年には長崎に入港したオランダ船が人魚の標本を持ち帰ったことを伝えている。オランダ船の人魚については、「その標本の製造元は、多分支那であらう。それとも神戸か横濱かも知れない」と推測している。
人魚と誤認した生物としては、「オツトセイの類、サメの類、それから海牛儒艮である」としている。それに関しては、センテン湾の人魚から老人が「悪魔を退ける櫛」をもらったが、その保存されていたものはサメ歯であったこと、1817年と1863年にサフォークで捕れた人魚の首はシュゴンの骨格であったことを言い、「英国の解剖学者リチャード・オーウエンも人魚は儒艮であると云つてゐる」と述べている。恐竜の命名者オーウェンも人魚=ジュゴン説者であったことは忘れていた。
最後の部分「黒奴を烏賊だと思つた人」は見出しだけでは内容が想像できないだろうが、太平洋沿岸のアメリカ原住民が金ボタンが付いた洋服姿で日本へやって来た時に、それを人々は烏賊だと思ったという話から、異人種を異形の者、ひいては人魚だと勘違いしたのだろうと谷津は考えている。人間をイカと思い誤った奇話は知らなかったが、これは文化的断絶の有名な逸話なのだろうか。他動物の見誤りから、人間の相互理解の齟齬という心理的原因で人魚を語ることは、外国経験者である谷津ならではの観点であろう。だが、最後は動物学者としての言で締めくくっている。
前に述べた儒艮に就いて一寸説明して置かう。これは印度洋から南洋へかけて、琉球まで擴がつてゐる海牛の類の海獣で、魚の形をしてゐる。琉球ではサンノイヲ(犀の魚)と云ひ、海草を食つて生きてゐる。その母は鰭に變形した手で子供を抱いて、水面に半身を顯すことがある。
以上が谷津直秀の「人魚の話」である。小学生向きの啓蒙記事としてまとまっていると思われ、随所に興味を引く事例が並べられている。中心はやはり人魚=儒艮説である。大正8年の前半は第一次世界大戦後のパリ講和会議(1/18~6/28)が開かれた年である。その講和会議で赤道以北の旧ドイツ領諸島の委任統治権を日本は手にした(5/7)。これによりジュゴンが生息する地域に日本の権益が広がった。それと谷津の記事は直接関連は無いだろうが、当時の少年雑誌は冒険と武勇伝で増刊号が編まれるような傾向があったので、南洋は少年の夢を誘う言葉とも言えよう。
谷津が「日本少年」に掲載したその他の啓蒙記事は以下の通りである。
- ・「蛇や蛙を食べる人」(第8巻第7号、大正2年6月1日、pp.44~47)
- ・「面白い歯のいろいろ」(第8巻第14号、大正2年12月1日、pp.52~54)
- ・「人間の親類に當るツパイヤ」(第9巻第5号、大正3年4月1日、pp.70~71)
- ・「武器を持っている蟹」(第9巻第10号、大正3年9月1日、pp.48~50)
- ・「雁の實る木」(第10巻第5号、大正4年4月1日、pp.52~55)
- ・「平易く出来る水族館」(第11巻第2号、大正5年1月1日、pp.60~62)
- ・「怪鳥ドードー」(第11巻第14号、大正5年12月1日、pp.54~55)
- ・「蠅の話」(第12巻第7号、大正6年6月1日、pp.72~73)
- ・「人間並みに笑ふ動物」(第14巻第3号、大正8年3月1日、pp.48~49)
- ・「狼の話」(第14巻第14号、大正8年12月1日、pp.65~67)
「雁の實る木」はバーナクルbarnacleが甲殻類のエボシガイと鳥類のカオジロガンを意味することをめぐるヨーロッパの奇妙な伝説を紹介する者である。海を漂泊する木材からエボシガイが生まれ、成長するに従って羽毛が生じ雁に成るという。また、ある木の実が水中に落ちると鳥になるという説もある。スキタイの子羊、ワクワクの木などと同様植物から動物が生まれるという一連の説話の一つである。澁澤龍彦「スキタイの羊」のほか、博品社のシリーズ「博物学ドキュメント」にヘンリー・リー/ベルトルト・ラウファー『スキタイの子羊』(1996.4.25)があった。ちなみに、リー(1826~1888)には「人魚、海蛇、バーナクル、クラーケンなどを扱った」『海の怪物の正体』『海の伝説の解釈』の論考がある。博品社で紹介されることを願っていたが、叶わぬ事となった。
谷津は「ジラルドウス」「マンドヴィル」「ヂユ、ハルター」など12世紀から16、7世紀のバーナクル説を紹介し、挿絵には「アルドロバンヂ」「ジヨン、ゼラード」「セバスチヤン、ミユンスター」の諸書から雁のなる木を写している。その内、リーの“SEA FABLES EXPLAINED”(1883)の‘BARNACLE GEESE-GOOSE BARNACLES’にはアルドロヴァンディ、ジエラードの挿絵が収められている。「ヂユ、ハルター」というフランスの詩人の作(1578年)を谷津は次のように訳している。
北海の島島の木の葉は水に
落ち見る間に鳥となる
破船の腐片は化して雁と
なる、変化驚くべし
鬱蒼たる緑樹は変じて麗
しき船となり
又化して菌となり、今は
飛んで鴎となる。
実験動物学者が訳した詩とは興味深い。ちなみにリーの書では、Du Bartasの原詩をジョシュア・シルベスターが英訳したものとして、
So slow Boots underneath him sees,
In th'icy isles, those goslings hatched on trees,
Whose fruitful leaves, fallinf into the water,
Are turned, they say, to living fowls soon after;
So rotten sides of broken ships do change,
To barnacles, O, transformation strange!
'Twas first a green tree; then a gallant hull;
Lately a mushroom; then a flying gull.
が引用されている。同じものである。谷津はリーの書を参照したものと思われる。
バーナクルに関する谷津の結論は、「観察研究の不充分から来た事で、一種類の生物が、急に全く異つた別の種類に化けることは全然ありません」という科学者として真っ当なものである。
なお、リーの人魚論考についてはいずれ紹介したいと思っている。
「平易く出来る水族館」は「ロバート、ワントン」の「水族函」(アクアリウム)を作って水棲生物を研究することを勧めている。ワントンは金魚とセキショウモ、モノアラガイを同時に飼って、植物から出る酸素で動物が生き、動物からの炭素で植物が生きる、水の掃除をする生物も同居させ、平均を保ち、水を換えないでもよいことを実証した。
「此繪を見たまえ。随分格好の悪い鳥でせう。その上馬鹿で魯鈍で、弱蟲だと来てゐるので、とうとう一羽も殘らず叩きころされて仕舞つたのであるが、それに就て面白い話がある。」という書き出しで始まるのが「怪鳥ドードー」である。1638年にロンドンで生きたドードーの見世物があったことも伝えているが、末尾には「又このやうに全滅してしまつたのも、この鳥が安逸になれて、意気地なしになつてゐたからで、人間でもその通りである。」の一文がある。
また、ドードー同様、「今では日本内地に全く跡を断つてしまひました」という(日本)狼については、「此日本の狼は、俗間には狼と云つて居りますが、實は狼とは全くちがつたものであります」と言っているが、以後の説明は世界の狼の生態であって、ニホンオオカミがどのような動物であるかの結論を知ることはできない。
実験動物学を導入しようとするあまり軋轢が生じ、一時は慶応に移った谷津直秀に人魚という空想上の存在についての文章があったことは、驚きでもあり、また楽しいことでもあった。
竹脇潔は、「谷津先生を語るとき、今一つ忘れてならないことに先生の博覧強記がある。先生はいろいろなことに興味を持たれたばかりでなく、見たり聞いたりしたことをよく覚えておられ、折りにふれて何気ないお話にあらわれる百科辞典的な知識の広さには驚くほかはなかった。『動物分類表』の記事にも先生の博識がよくあらわれていて、先生にしてはじめて書けるものが少なくない。」と述べている。その『動物分類表』上でジュゴンがどう記述されているか見てみよう。
大正3年10月28日、丸善発行、p.211~213、「海牛類」
第六綱哺乳類第二亜綱眞獣類第二類単子宮類第一八目 海牛類 Sirenia
| *Halicore | ザンノイヲ(犀の魚の義)ジュゴン(儒艮)(dugong)Dugong |
| *Manatus | =Trichechusカイギウ(海牛 )(Manatee, sea-cow)Manati, Seekuh 頸椎の第二第三癒合して六となる |
| †Rhytina | R. stelleri=Hydrodamalis gigas STELLER'S sea-cow) 1741 BEHRJINGとSTELLERにより發見1768年頃死滅長さ三丈に達す |
大正9年9月6日、増補改訂再版、pp.255
「Dugong 三種あり」が説明に加わる。
昭和13年2月12日、全訂改版、p.427
| Halicore | H. dugongザンノイヲ(犀の魚の義)ジュゴン(儒艮)マスキュー(南洋で)dugong Dugong atlasを酋長の腕輪とす舌にtaste papillae, taste budsがない.3種あり.臺灣総督府天然紀念物調査報告第1輯 |
| Manatus | =Trichechus カイギュウ(海牛)manatee, sea-cow Manati, Seekuh 頸椎の第2,第3が癒合して6となる.M. inunguis オリノコ産,M. latirostris フロリダ,西印度産 |
| †Rhytina | R. stelleri=Hydrodamalis gigas STELLER's sea-cow 1741年にBEHRINGとSTELLERよつて發見1768年頃絶滅長さ9mに達す L. STEJNEGER:GEORG WILHELM STELLER, the pioneer of Alaskan natural history. Princeton University Press |
磯野直秀によると、丸善『動物分類表』には以上の他に、大正11年増補3版、昭和17年増訂5版、昭和18年6版、昭和27年、谷津の死後内田亨による補訂の7版がある。その後、1972年には中山書店から『谷津・内田 動物分類名辞典』が出版されている。
谷津は大正7年、實業之日本社から『趣味の動物』を出版している。「人魚の話」の掲載は大正8年8月であるから、当然のことであるが収録されていない。しかし、實業之日本社は「日本少年」の発行元であるから、以前に掲載した科学啓蒙記事の一部は収められている。目次を掲げると、
奇鳥ツーカン(一名オハシドリ)
奇獣オカピ
両手に武器を持つて居る蟹
赤坊を抱へて飛ぶ南洋の蝙蝠
装飾用の植物に似た動物
寒い所に棲む動物
雁の實る木
人間の親類に當るツパイヤ
骨になつて世界を潔める動物
紐育の大動物園
人と獣との相違
伊勢蝦
ミノムシ
蛇や蛙を食ふ人
河馬の話
各国の人形
恐るべき蠅
蠅と戦ふべし
鸚鵡と九官鳥
昆蟲の奇習
鴨
牛
海の光
蛾は何故に燈火に飛ぶ込むか
ルチエルンの氷河園
容易く出来る水族館
殘れるものと變れるもの
ヴエスーヴイオの大噴火
門と帽子
面白い歯のいろいろ
オーバーアンムガウの受難劇
北極發見
ハンモツクはルケーヤン人の記念
夏は自然研究の時期
『趣味の動物』という書名の科学啓蒙書は大正時代にもう一冊ある。飯塚啓(1868~1938、動物学者、理学博士、学習院教授)著、日進堂、大正10年2月1日発行のものである。68編が収められている。飯塚は谷津より3年前の明治30年に東京帝国大学の動物学科を卒業し、ゴカイ類の研究で知られ、主著に『海産動物学』(1907)『動物発生学』(1906)がある。「日本少年」には谷津よりも早く寄稿している。例えば、明治40年7月1日の第2巻第7号pp.25~30には飯塚の「鸚鵡と猿の戦争」が掲載されている。他に實業之日本社「日本少年」に科学記事を書いている人には、石川千代松(1860~1935、理学博士、動物学、帝国大学農科大学教授)、田中誠吉、田中義麿(1884~1972、遺伝学者、九州帝国大学農学部教授)、白井光太郎(1863~1932、植物学、東京帝国大学農科大学教授)、横山又次郎(1860~1942、地質学者)、丘淺次郎(1868~1944、東京師範学校教授)、三宅驥一(1876~1964、理学博士、植物学、東京帝国大学農学部教授)、岸上鎌吉(1867~1929、理学博士、魚類学、東京帝国大学農科大学教授)、宮島幹之助(1872~1944)、伊藤篤太郎(1865~1941、植物学、伊藤圭介孫)、山内繁雄(1876~1973、藻類学)、三宅恒方(1880~1921、理学博士、昆虫学)、大森房吉(1868~1923、理学博士、地震学)、松村松年(1872~1960、理学・農学博士、昆虫学、北海道帝国大学教授)などがいる。これらの人々は理学・農学・医学博士などであるが、初期の科学記事を書いている人に樋口二葉という人物がいる。
「日本少年」には確認した限りではあるが、明治40、41年の2、3巻に科学記事を載せている。
・「魚の體内に棲む魚」(第2号第5号、明治40年5月1日、pp.34~37)
・「蟻の捕虜」(第2巻第7号、明治40年7月1日、pp.40~43)
・「蝦の生涯」(第2巻第9号、明治40 年9月1日、pp.26~29)
・「動物を捕る海藻」(第2巻第10号、明治40年10月1日、pp.28~32)
・「鳥を丸呑みにする怪魚」(第2巻第12号、明治40年12月1日、pp.27~31)
・「世界で一番珍らしい猿」(第3巻第1号、明治41年1月1日、pp.67~71)
・「火星世界はどんな處か」(第3巻第2号、明治41年2月1日、pp.29~32)
・「世界一の醜い動物」(第3巻第6号、明治41年6月1日、pp.49~53)
二葉は「ふたば、によう」どちらで読むのだろうか。本名は新六、新聞記者の経歴があり、宮武外骨・西田長寿『明治新聞雑誌関係者略伝』(みすず書房『明治大正言論資料 20』、1987.11.15)p.210には、
樋口新六 明治一九年四月頃『東京絵入新聞』の記者。なお明治二○年一月六日同紙上には『絵入新聞』記者として、古川精一、仮名垣魯文、石原明倫、山内文三朗、樋口新六、落合幾次郎の六人の名が記されている。宮武外骨のメモでは、「画工樋口種貞トノ関係如何」とある。同一人であるかも知れぬ。
とある。国会図書館の資料では1863年生まれである。探偵小説、家庭小説の作があり、
日本書誌学大系35『浮世絵と板画の研究』(1983)の著者も樋口二葉であるので、外骨のメモの通り画工もしていた可能性もある。経歴、没年については現在知るところはまったくない。科学記事に関連して、樋口二葉名義の著に『理科新お伽』(晴光館、明治42年)、『少年理科博覧会』(日吉丸書房、明治43年)、『動物お伽噺』(博文館、明治45年)があることを記しておこう。
樋口二葉「火星世界はどんな處か」は「フラムマリオン氏」の説により、火星には陸と海があり、その割合は地球の反対で陸は海の2倍以上、圏気は水蒸気を多く含み、「動物でも植物でも、安全に生存し得べき筈である」としている。したがって、火星には人類が生息し、「體質知能共に地球の人類より勝つて居て、その官能の鋭敏な事は迚も我我の考へ及ぶ所でない。彼等は互に話をする事はなくとも、双方とも會ふと直に向ふの胸の中を見貫」くという。挿絵には星形の顔をした火星人が描かれている。当時の読者は素直に記事の内容を受け入れていたのだろうか。
樋口二葉は気になる存在であるが、今はこれ以上の追跡はやめておこう。「日本少年」の初期の記者を務めていたのかも知れない。「日本少年」の著名な記者には、星野水裏(久、1879~1923)、滝沢素水(永二、1884~?)、有本芳水(歓之助、1886~1976)、松山思水(二郎、1887~1957)、渋沢青花(寿三郎、1889~1983)などがいた。
有本芳水は大正4年に当時の「日本少年」の人気作家三津木春影(1881~1915)が亡くなったことを悼み、同年9月号(第10巻第10号)に「三津木春影君逝く」を載せている(pp.82~83)。春影は7月8日に亡くなったのだが、6日の午後、春影の妻から電話をもらい、雑司ヶ谷にあった春影宅に馳せつけた。芳水は「妻君」と書いているだけであるが、春影の妻は三津木貞子(1883~1945)といい、当時は歌人(窪田空穂に師事)、春影の死後の大正中期(「鍵」大正7年2月が処女作)から昭和初期にかけて、かなり精力的に小説を発表した文学者(徳田秋声に師事)である。6日に芳水も会った「義理の姉さん」は、貞子の姉、日本女子大学の家政科教授手塚かね(1880~1947)であろう(かね、貞子の弟は染織家石井徳次郎)。貞子は春水との結婚前には若山牧水との交友もあり、その小説作品ともども以前から注意してきた女性作家である。
三津木春影は信州伊那の出身、早稲田の英文科卒業。創作家となるべく柳川春葉(1877~1918)に師事し明治40年代には多くの雑誌に作を発表するようになるが、結核の病を持ち、文学を追究することに困難を覚え、少年、少女雑誌に探偵小説を盛んに発表するようになる。芳水とは雑誌「新聲」の誌友会が契機となり知り合うようになる(明治39年)。春影は實業之日本社の特別寄稿家になり、同社の「日本少年」「少女の友」のみに執筆するようになった。
明治44年頃から春影は「日本少年」に単発の小説を発表していたが、大正2年「密封の鉄函」(2月~5月)から連載小説を寄せるようになっている。「船室の時計」「空魔團」「地底の宝玉」「噴火魔島」「間諜團」と続いた春影の「日本少年」小説は、「間諜團」が8月号で中絶する。創刊当時から作を載せている江見水蔭が大正4年の一年間「半島の怪城廊」を掲載していたが、5年には春影遺作「少年船員」が1月から8月まで連載された。大正6年からは春影にかわり永代静雄が連載を担う。「怪頭號」「少年博士」「紐育の怪事件」「透視液」「小公爵」「地下宮殿」「宝珠の悩み」と大正8年まで永代の小説は続いている。大正10年には森下雨村「赤道を越えて」の連載があった。その大正10年の最後の号(第16巻第12号)には加藤朝鳥(1886~1938)が「南洋奇譚 獅子を殺す蟻」という科学知識絡みの創作を載せている。その末尾に、
加藤氏は爪哇日報主筆として一年間爪哇に居られ、爪哇地方研究をされて歸つて來られた方です。
来年の本誌には、南洋の事實奇談をかいて頂くつもりでゐます。南洋で活動してゐる日本少年の面白い話などもあるさうですが、諸君をして手に汗をにぎらせ、あつと云はせすに置かない、記事が出來ることゝ思ひます。どうかお待ち下さい。
とある。
朝鳥は早稲田英文科卒、新聞記者を経て、翻訳、文芸評論に筆を振るっていたが、大正9年9月、ジャワへ渡り、同地で「爪哇日報」の創刊に参加し主筆となったが、日本に遺してきた妻が病に倒れ、翌大正10年8月帰国。妻の作家加藤みどり(1888~1922)は大正11年5月死亡。朝鳥は後再婚し、大正大学教授に就任、英語を介してポーランド文学を翻訳、昭和初期には春秋社「世界大思想全集」にセネカ、カンパネルラ、ダ・ヴィンチ、ショウの翻訳を発表。雑誌『反響』を昭和7年1月から発行し始め、同誌は昭和13年8月、72号「加藤朝鳥追悼号」まで7年にわたり続いた。昭和13年5月17日、52歳で永眠。50冊以上の著作、翻訳を持ち、その中には『爪哇の旅』(新光社、大正11年5月28日)もある。大正5年には『シヤロツク・ホルムス』三冊を発表しているので、探偵小説史で言及されることがある。
なぜ、人魚に関連が薄い加藤朝鳥についてことさら言及したかというと、朝鳥も個人的に気になる文学者であるからに過ぎない。その後の朝鳥と「日本少年」との関係は実は調査が行き届いていない。今後の課題としたい。
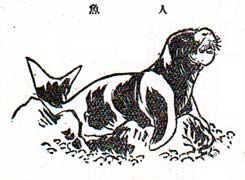 最後に「日本少年」の人魚関連記事をもう一つ紹介したい。既に何度かふれたことがあるが、明治40年3月20日から7月31日まで上野公園と不忍池畔で開催された東京勧業博覧会の教育水族館(水族館の写真とデザインされた魚類を配した記念絵葉書は別冊太陽『日本の博覧会 寺下 勍コレクション』[平凡社、2005.2.20]p.48で見ることができる)で展示されたジュゴンについてである。記者の石塚月亭(祐吉)が「少年博覧會」と題して「一番美しいもの」「一番大きなもの」など16のものを列記した最初に「一番珍しいもの」として「琉球から捕つて来た人魚。あじか。八つ目鰻。動物園の麒麟」をあげている(第2巻第5号、明治40年5月1日、p.73)。人魚、八目鰻の挿絵を添えている。本文の「人魚」には「じんぎょ」のルビがふってある。
最後に「日本少年」の人魚関連記事をもう一つ紹介したい。既に何度かふれたことがあるが、明治40年3月20日から7月31日まで上野公園と不忍池畔で開催された東京勧業博覧会の教育水族館(水族館の写真とデザインされた魚類を配した記念絵葉書は別冊太陽『日本の博覧会 寺下 勍コレクション』[平凡社、2005.2.20]p.48で見ることができる)で展示されたジュゴンについてである。記者の石塚月亭(祐吉)が「少年博覧會」と題して「一番美しいもの」「一番大きなもの」など16のものを列記した最初に「一番珍しいもの」として「琉球から捕つて来た人魚。あじか。八つ目鰻。動物園の麒麟」をあげている(第2巻第5号、明治40年5月1日、p.73)。人魚、八目鰻の挿絵を添えている。本文の「人魚」には「じんぎょ」のルビがふってある。
「日本少年」には「私の家には龍の骨があります」という読者の投書に石川千代松が「それは牛骨の化石でしょう」と答えている記事(第2巻第7号、明治40年7月1日、pp.30~33)、伊藤忠太の「翼のある馬」という東洋の天馬を多くの図と共に紹介している論考(第14巻第7号、大正8年7月1日、pp.62~64)など興味深い内容で、先の有本芳水の春影追悼記事の末尾に「余は二十萬の我愛読者諸君を代表して氏の冥福を祈つた」とあるように大正時代のトップ少年誌となっていった。そして、次代には「少年倶楽部」にその地位を譲ることとなり、昭和13年、遂に終刊を迎えた。
谷津直秀「人魚の話」を中心に、その掲載誌「日本少年」を紹介してみた。
by釜野啓(aka. MORO-Z)